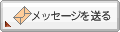2024年06月09日
ツキノワグマ捕獲名人。その2.
大谷石之丞:明治38年(1905)、津軽で最も僻地と思われる赤石村奥地の百姓の次男として生れました。小学校卒業後、家業に従事の傍ら、マタギのシカリ大谷吉左エ門さんから、マタギや川漁の手解きを受けました。
赤石村は藩政時代からマタギの村として知られ、昭和62年(1987)82才で亡くなるまで、60年以上も獲物を追い続け捕獲数は78頭、命懸けの人生でした。

当時は単発の村田銃で足を止め、槍で止を刺すやり方でした。
山の詳しさに於いては、右に出る者がいなく、山の読みが鋭い。より安全により効率的に目的を果たす為には、何と言っても山を知る事が最も重要な条件となります。
持ち前のこの特技を生かして、クマのいそうな所へ迫るのに妙を得ていました。
クマがどこを通るか、どこで待てば良いか、事の成行きに付いて判断は誠に適切で事実、その通りになる事が十中八九であり、誠に戦略に長けた人だったそうです。
吉野秀市:群馬で一般的な猟は、2人1組で数匹の猟犬を連れて穴熊を探し当てる物と、6~7人で行う巻狩りですが、彼はマタギ等の集団による巻狩りとは違って、群馬の藤原郷で殆ど単独で猟をして来ました。
積雪期に穴に籠っている熊を穴から熊を追い出し、銃で仕留める方法でした。

その捕獲数が桁外れ、1シーズンに最大32頭の捕獲実績を持ち、生涯では300頭もの月の輪熊を捕りました。「最後の熊捕り名人」として紹介されています。
恐らく彼が最多数捕獲者だったと思われます。原則単独猟の吉野さんは生涯で300頭を捕り、大きな怪我をする事もなく、その銃の腕は一度も撃ち損じた事は無いと言う程の物でした。
しかしその多数捕獲の原因は彼が単に射撃の名手だったからではありません。如何なる射撃の名手であったとしても、射撃の腕だけでそれだけの数の熊を 射止める事は決して出来ません。
それにはまず何よりも熊の棲息する山域の自然を吉野さんが熟知していた事と、そこで生活する熊の生態を知り尽くしていた事にこそあると言えました。
それはマタギを初め猟をする人々誰もが目指していた事であるにも拘らず、彼程それを成し遂げた人はいませんでした。
毎年冬の3月頃まで単独で山に入り熊を追うと言う事は、名人と言えども数々の危機を体験する事無しに、成得る物ではありません。万が一の事態に備える周到さが何時もあったと思われます。
恐らく誰も無し得なかった手法で、熊の冬眠穴を次から次へと発見して行ったと思われますが、凄い人がいた物だと感心します。
赤石村は藩政時代からマタギの村として知られ、昭和62年(1987)82才で亡くなるまで、60年以上も獲物を追い続け捕獲数は78頭、命懸けの人生でした。

当時は単発の村田銃で足を止め、槍で止を刺すやり方でした。
山の詳しさに於いては、右に出る者がいなく、山の読みが鋭い。より安全により効率的に目的を果たす為には、何と言っても山を知る事が最も重要な条件となります。
持ち前のこの特技を生かして、クマのいそうな所へ迫るのに妙を得ていました。
クマがどこを通るか、どこで待てば良いか、事の成行きに付いて判断は誠に適切で事実、その通りになる事が十中八九であり、誠に戦略に長けた人だったそうです。
吉野秀市:群馬で一般的な猟は、2人1組で数匹の猟犬を連れて穴熊を探し当てる物と、6~7人で行う巻狩りですが、彼はマタギ等の集団による巻狩りとは違って、群馬の藤原郷で殆ど単独で猟をして来ました。
積雪期に穴に籠っている熊を穴から熊を追い出し、銃で仕留める方法でした。

その捕獲数が桁外れ、1シーズンに最大32頭の捕獲実績を持ち、生涯では300頭もの月の輪熊を捕りました。「最後の熊捕り名人」として紹介されています。
恐らく彼が最多数捕獲者だったと思われます。原則単独猟の吉野さんは生涯で300頭を捕り、大きな怪我をする事もなく、その銃の腕は一度も撃ち損じた事は無いと言う程の物でした。
しかしその多数捕獲の原因は彼が単に射撃の名手だったからではありません。如何なる射撃の名手であったとしても、射撃の腕だけでそれだけの数の熊を 射止める事は決して出来ません。
それにはまず何よりも熊の棲息する山域の自然を吉野さんが熟知していた事と、そこで生活する熊の生態を知り尽くしていた事にこそあると言えました。
それはマタギを初め猟をする人々誰もが目指していた事であるにも拘らず、彼程それを成し遂げた人はいませんでした。
毎年冬の3月頃まで単独で山に入り熊を追うと言う事は、名人と言えども数々の危機を体験する事無しに、成得る物ではありません。万が一の事態に備える周到さが何時もあったと思われます。
恐らく誰も無し得なかった手法で、熊の冬眠穴を次から次へと発見して行ったと思われますが、凄い人がいた物だと感心します。
2024年06月09日
ツキノワグマ捕獲名人。その1。
志田 忠儀 (シダ タダノリ):1917年、山形県西川町大井沢生まれ。8歳から山に入り15歳で熊を撃ち、生涯で50頭以上の熊を仕留めた伝説の猟師でえした。

戦前から 山に入り、3度の召集の後、戦後も3月ウサギ撃ち、4~5月は熊撃ち、6月ゼンマイ採り、夏は釣り、秋は茸や山菜取り、その後はイタチ狩りや再びクマ狩り、そして厳しい冬、1年を通じて山と共に生きた伝説の山人として知られています。
80歳過ぎまで現役のマタギとして活躍しました。1959年、磐梯朝日国立公園朝日地区管理人になり、朝日連峰遭難救助隊を務め、1982年同管理人を退くまで地元のブナ林を守る環境活動にも携わりました。
地元猟友会会長等を歴任。それらの功労で1989年、勲六等単光旭日章を受章しました。
100歳で天命を全うした伝説の猟師の知恵山に生きて来た男でした。
「ラスト・マタギ」「伝説の猟師の知恵」等の著書があります。2016年5月23日没。
舘香菜子(たて かなこ 2022年現在27才):青森県東通村役場の農林畜産課に勤務。ハンターではありませんが、庁内で「熊捕り名人」として知れ渡っています。

50歳以上も年上のベテラン猟師達から、親しみと尊敬の念を込めて「親方」と呼ばれています。
獣害対策を担う先輩達をサポートして来ましたが、経験を重ね前向きな姿勢と 農家の顔を覚えた事等から本格的に任される様になりました。
ツキノワグマはブルーベリーなど果実を好みます。一方で畜産農家が保管の為に地中に埋めているトウモロコシも掘返して食べてしまいます。
民家近くに出没するクマは、ドラム缶で作ったワナで捕獲するのですが、設置場所の僅かな違いでも全く入ってくれません。
きっかけはベテラン猟師のボヤキでした。「どうしたら入ってくれるのか」。餌を求めクマが通る「獣道」は決まっており、すぐそばにワナを仕掛けなければ捕獲する事は難しいのです。
現場に出向くと倒伏した雑草があり、かすかにクマの残り香が漂っていました。
「根拠がある訳では ないけれど、ここを通る」と直感した場所にワナを移設すると、その日の夜に掛かり、同じパターンが何度か続きました。
抜群のセンスと猟師達に評価され、設置場所への相談が舞込む様になったそうです。
高関辰五郎:1890年マタギで有名な阿仁町に生まれ、18歳で白神山地の岩崎村大間越に住み、阿仁町でも岩崎村でも仙人と呼ばれた伝説的なクマ撃ち名人でした。
1人で撃ち取ったクマが105頭、仲間と獲ったクマなら300頭は下らないと言います。彼は獲物の多い白神山地に目を付け、津梅川のそばに小さな小屋を建てて住む、伝説の名人マタギでした。
上原武知:長野県上高井郡仁礼村字米子に住み、かなり以前の記録と思われますが、本件記録時には未だ45歳である彼はクマ撃ちを始めてから未だ僅かに7年間に44頭の月の輪熊を斃したそうです。
この地方の山村には、信州側にも越後側にも幾人もの熊撃ちがいますが、彼を一躍名人としたのは、彼の豪胆にして射撃が正確、そして健脚でした。
この名人が縄張りとしている山は、上州と越後と信州の三国が境する白砂山から始まり、西へ大高山、赤石山、横手山、渋峠、万座山、猫岳、四阿山、六里ヶ原等の深い渓谷と密林と懸崖でした。
彼は1度熊の痕跡を見付けるとそれを追いますが、彼の歩く速さは熊よりも速いとされています。
専ら筒の短い単発銃を使うのは、藪や険しい崖を這ったりする時に筒が長いと邪魔になり、2連銃の薄い銃身では銃口が潰れてしまうからです。
熊を引付けるだけ引付け、1~2mの熊の手が届く直前で撃つ、この距離なら外れる事は無く、これが最も正確で安全な方法であると言っています。
今まで幾度か危険な場合に遭遇した事もありますが、一度も怪我した事がありません。

戦前から 山に入り、3度の召集の後、戦後も3月ウサギ撃ち、4~5月は熊撃ち、6月ゼンマイ採り、夏は釣り、秋は茸や山菜取り、その後はイタチ狩りや再びクマ狩り、そして厳しい冬、1年を通じて山と共に生きた伝説の山人として知られています。
80歳過ぎまで現役のマタギとして活躍しました。1959年、磐梯朝日国立公園朝日地区管理人になり、朝日連峰遭難救助隊を務め、1982年同管理人を退くまで地元のブナ林を守る環境活動にも携わりました。
地元猟友会会長等を歴任。それらの功労で1989年、勲六等単光旭日章を受章しました。
100歳で天命を全うした伝説の猟師の知恵山に生きて来た男でした。
「ラスト・マタギ」「伝説の猟師の知恵」等の著書があります。2016年5月23日没。
舘香菜子(たて かなこ 2022年現在27才):青森県東通村役場の農林畜産課に勤務。ハンターではありませんが、庁内で「熊捕り名人」として知れ渡っています。

50歳以上も年上のベテラン猟師達から、親しみと尊敬の念を込めて「親方」と呼ばれています。
獣害対策を担う先輩達をサポートして来ましたが、経験を重ね前向きな姿勢と 農家の顔を覚えた事等から本格的に任される様になりました。
ツキノワグマはブルーベリーなど果実を好みます。一方で畜産農家が保管の為に地中に埋めているトウモロコシも掘返して食べてしまいます。
民家近くに出没するクマは、ドラム缶で作ったワナで捕獲するのですが、設置場所の僅かな違いでも全く入ってくれません。
きっかけはベテラン猟師のボヤキでした。「どうしたら入ってくれるのか」。餌を求めクマが通る「獣道」は決まっており、すぐそばにワナを仕掛けなければ捕獲する事は難しいのです。
現場に出向くと倒伏した雑草があり、かすかにクマの残り香が漂っていました。
「根拠がある訳では ないけれど、ここを通る」と直感した場所にワナを移設すると、その日の夜に掛かり、同じパターンが何度か続きました。
抜群のセンスと猟師達に評価され、設置場所への相談が舞込む様になったそうです。
高関辰五郎:1890年マタギで有名な阿仁町に生まれ、18歳で白神山地の岩崎村大間越に住み、阿仁町でも岩崎村でも仙人と呼ばれた伝説的なクマ撃ち名人でした。
1人で撃ち取ったクマが105頭、仲間と獲ったクマなら300頭は下らないと言います。彼は獲物の多い白神山地に目を付け、津梅川のそばに小さな小屋を建てて住む、伝説の名人マタギでした。
上原武知:長野県上高井郡仁礼村字米子に住み、かなり以前の記録と思われますが、本件記録時には未だ45歳である彼はクマ撃ちを始めてから未だ僅かに7年間に44頭の月の輪熊を斃したそうです。
この地方の山村には、信州側にも越後側にも幾人もの熊撃ちがいますが、彼を一躍名人としたのは、彼の豪胆にして射撃が正確、そして健脚でした。
この名人が縄張りとしている山は、上州と越後と信州の三国が境する白砂山から始まり、西へ大高山、赤石山、横手山、渋峠、万座山、猫岳、四阿山、六里ヶ原等の深い渓谷と密林と懸崖でした。
彼は1度熊の痕跡を見付けるとそれを追いますが、彼の歩く速さは熊よりも速いとされています。
専ら筒の短い単発銃を使うのは、藪や険しい崖を這ったりする時に筒が長いと邪魔になり、2連銃の薄い銃身では銃口が潰れてしまうからです。
熊を引付けるだけ引付け、1~2mの熊の手が届く直前で撃つ、この距離なら外れる事は無く、これが最も正確で安全な方法であると言っています。
今まで幾度か危険な場合に遭遇した事もありますが、一度も怪我した事がありません。
2024年06月06日
ヒグマ捕獲名人、その3.


原子一男:北海道旭川市在住、1955年生れ「クマ撃ち」歴49年(2024年現在)、
原子(弟)(名前は失念):北海道旭川市在住、1961年生れ「クマ撃ち」歴43年、(2024年現在)兄弟でハンティングの腕前は一流、特に兄の狩猟技術は2007年の後述の事故まで超1流でした 。
捕獲数はネットからは不明ながら、同じ旭川猟友会の同年代の2名に聞きましたが、2007年時点ですでに70頭以上、弟は兄に比べれば半分以下と言われていますが、それでも2019年現在で30頭位だそうで、その後3年間に毎年少なくとも1頭の追加があると思われます。
弟さんは普段は林業に従事され、ハラコゾンメルと言う地元ハンター達に愛用されている登坂に強い雪山用のスキーも制作されています。
そのゾンメルスキーに貼るアザラシ皮(シール)は根室漁協定置網に迷込み溺死した物であり、彼はそれを購入、ケンさんもその皮剥ぎを手伝った事があります。
以下はその「クマ撃ち」ベテラン猟師原子(弟)さんに話を聞いた話です。
原子(兄)さんは、は2007年ヒグマに襲われながらも仕留め、瀕死の重傷で意識不明の重体、両腕が折られ顎も半分取られ、意識朦朧ながら銃を持って車に乗り、20㎞位先の交番で保護されました。
当日朝猟に行って小さいクマを2頭獲った後、昼からまたその近くで足跡を見付けました。でもその熊は見付からず、山の方に背中を向けて歩いていたら、背後の笹からクマが襲い掛かって来ました。
一応命中させましたが、襲撃を阻止する事は出来ませんでした。
翌年の春にその場所から50m位の所に骨になったクマの死体が見付かったそうです。
ヒグマに脳のギリギリまでを齧られ、アゴも半分失い死に掛けましたが、病院で頭蓋骨を外し中を消毒、また頭蓋骨を戻したそうです。
写真は2007年、北海道猟友会の原子兄氏が害獣駆除で450㎏を捕獲した時の物です。
この年の秋に事故に会われました。体力抜群で事故当時52歳、ヒグマ捕獲 経験数も十分あり過ぎヒグマと言う物をやや嘗めていたのかも知れません。本事故以後、このスーパー能力は失われました。
彼曰く、「エゾ鹿なんぞ蚊を叩く様な物」であると、言う話を聞いた事があります。
体力抜群の彼は積雪期にエゾ鹿の新しい足跡を見付けると、ゾンメルスキーで追跡、鹿を深雪に追い込み、動けなくなった群れを丸ごと捕獲するそうです。
「究極の狩猟」国内最大の猛獣「ヒグマ」とはどんな動物なのか? そして「知られざる「ヒグマ撃ち」の世界とは? 原子兄さんは現在も現役ハンタ―、先頃もクマが出て、猟友会として 出動駆除しています。兄さんがそれでも「クマ撃ち」辞めない理由、弟さん」に聞いてみました。
昔(1970年代以前)、親父がやっていた様な時代は、「ヒグマ撃ち」がお金になったからだと 思いますが、今はお金にはなりません。
兄の事は分かりませんが、僕が狩猟が好きなのは、ただ撃ちたいからではなく、山を歩き獲物を獲る事が好きなんです。獲ったら必ずその肉を食べていましたから、まあ楽しんで食べる事でしょうか。
自分が獲った物を食べられると言う事は嬉しい事だと思います。
家族も獲物を取って戻ると、「美味いね」食べますから、楽しみにもしていると思います。
店に並んでいる市販肉とは内容が違い、狩猟で獲る熊とか鹿とか鴨とか、店に出ていない物
ばかりです。獲物がそんなにない時代には、ウサギとかスズメも獲り、狩猟が生活の一部でした。
僕が狩猟を始めたきっかけは、親がハンターで兄もやっており、自分も好きだったので始めました。
「銃を撃ってみたい」という気持ちもありましたし、山を歩くのも好きだったです。初めて狩りの現場に行ったのは、中学生で13~14歳位、その頃から「やってみたいな」と思っていました。
猟銃の所有許可が出るのは20歳からなので、その年齢を待って狩猟免許を取り、その冬から狩りに出ました。最初は鴨を撃っていました。
初めてクマを獲ったのは22歳でしょうか。1人で獲りました。その年齢でクマを獲った人は、まずいないと思います。僕の場合、小さい頃から親父や兄が獲っているのも見ており、凄腕の兄に一緒に付いて行って手伝ったりもしていました。
それで自分で猟をやる様になってからも、極く自然に山を歩いて見付けたから獲ったと言う感じでした。そもそもクマを獲る猟師はおっかないから余りいないです。
普段は林業で、狩猟期間の3~4カ月も、「ヒグマ撃ち」だけをやっている訳ではなく、エゾ鹿撃ちをしていて、ヒグマの足跡を見付け、獲れそうなら獲ると言う感じです。
何でも撃つ一般的なハンターと言えますが、「ヒグマ撃ち」は仕留め損ねると襲い掛かって来る事があり、特別だと思います。
一般的にヒグマに対しての恐怖感は大きくベテラン猟師でも 「おっかないからヒグマだけはやらない」と言う人も多いです。「ヒグマ撃ち」で今の所は危険な目にあった事はありません。
こちら側から危ないなと思えば逆から行ったり、笹が生い茂って視界がない様な所では、特に気を付けながら歩いています。
何時もどうやったら上手い具合に獲れるか考えながら、「襲われても撃てる倒せる」を考え、ヒグマ場合は頭脳戦です。
ヒグマは音にも敏感ですが、臭いにはもっと敏感です。山の中で風が廻っている様な所に人が入ると、その臭いで気付いて逃げられてしまいます。
頭も、耳も、鼻も良く。何かがおかしいと思ったら、立上がり鼻を空に向けて臭いをかいだりしてすぐに逃げてしまいます。「ヒグマ撃ち」は凄く難しいです。
今(2019年)まで仕留めたのは30頭駆除で獲る事はなく、殆どが狩猟なので、それ程多くはありません。昭和時代は害獣駆除として、クマが繁殖する春に「春クマ駆除」と言うのをやっていたんですが、クマの頭数自体も減り、平成の1990年になって廃止になりました。
最近はかなり生息数が増え、家畜を含めた農産物や人的被害があった時には駆除が行われています。
愛用のライフル銃はボルトアクションのサコーM85フィンライト、30-06口径のフィンランドの銃です。自動式を使っていた事もありましたが、ボルト式に換えました。
弾自体が結構高いので全部自分で作っています。ヒグマ撃ちの装備に特別な物はありません。
山に入る時はリュックサックに、ロープと大きいビニール袋とペットシートの60㎝×90㎝を10枚位持って歩いています。鹿を獲った後、解体して肉にして持って帰る時にこれに包むのです。
クマの肉の味は何と表現すればいいんでしょうかね……熊の味がします。
いわゆる市販の牛や豚肉とは全く味が違います。やっぱりちょっと獣の香りはします。
肉は赤身なんですが、秋口になると脂が載って来て中々旨いです。臭いんじゃないかと思われがちですけれど、上手に解体すれば臭みはありません。解体が下手な人がやると、クマの体の外側の体臭が肉に付いてしまい、血抜き不十分であれば臭みが出てしまいます。
肉はちょっと硬目です。特に大きいクマだと筋肉質で、そのまま焼いて食べる事はしません。圧力鍋で煮て一度柔らかくして、それからすき焼きみたいにして食べます。
ヒグマを見付けた時は「止まれ!」って思います。止まらなかったら走っていても撃ちますが、殆ど止まってくれるので、照準を予め合わせておき、こっちを見た瞬間に撃ちます。
鹿もそうですが、熊も殆ど頭しか撃ちません。頭が見える所で止まった瞬間に撃つ。
頭しか撃たないのは1発で殺さないと暴れるからです。近い時は10m位で撃つ事もあります。
そうすると殆ど一発で倒れます。
今年獲ったのは30m位の距離の1頭と、20m位の距離の1頭です。
クマは動きが速いので、その距離で撃ち損じたら大変です。
熊は主食ではありませんが、エゾ鹿を追掛け捕まえて食べています。速くないと捕まえる事が出来ず、熊は鹿より速いのです。僕の様な猟師はやたらに撃ちません。
自分が獲るのは自分達が食べる分だけ。1~2頭獲ったら、それ以上は何頭いても撃ちません。それ以上獲っても処理が大変なだけです。
世の中には動物を保護する視点しか持たない人も多くいます。
街中に出て来たり、農作物を食べてしまうクマの駆除に付いても、「かわいそう」と言う人もいる様ですが、北海道札幌市の住宅街にヒグマが出没し、住民を恐怖に陥れました。
もし自分の家の近くにクマが出て来たら……と想像して欲しいと思います。
真昼間に家の前までクマが来るのです。「黙ってじっとしていたら襲っては来ない」と思ってるかも知れませんけれど、そんな事は有り得ません。
これまで仕留めたクマで一番大きいのは400㎏超えです。大きさで言えば、軽自動車位です。凄く大きいです。
冬で穴に入っていたんですが、穴の近くにおり、もう1人頼んで出て来るのをしばらく待って出て来た所を2人で頭をドンと撃って、それで終わりです。
獲ったクマは翌朝3人で行って解体して、雪の上を引っ張るプラスチックのソリ、3台に乗せて持って帰りました。一日掛かりで戻ったら夕方の6時、真っ暗になっていました。
北海道でも今は冬眠しないヒグマも増えました。ハンターが減りエゾ鹿が凄く増えているから、それを餌にするクマも増えているのだと思います。
1年中食べ物に困らないので山奥にいるクマは大きくなるし、増えてしまうんです。
2024年06月04日
ヒグマ捕獲名人、その2.


池上治男:1949年、北海道上砂川市生れ、砂川猟友会支部長を30年以上務め、地区一のベテランハンターです。
砂川市は札幌から北東へ80km。12月中旬でも腰の高さまで雪が積もる程の豪雪地帯で、辺り一面が白で埋め尽くされていました。
池上さんは高校時代は美術や剣道、トランペットに打ち込みました。卒業後は「太平洋の真ん中でトランペットを吹いてみたい」と言う夢を胸に北海道大の水産学部へ進み、相手の手を掴んだだけで簡単に投げ飛ばす技を見て「剣道とは違う変わった武道だな」と興味を持ち少林寺拳法同好会に所属。
「何時かは道場を開いて子供達に少林寺拳法を教えたい」と言う目標も持っていました。
大学卒業後は、国内トップクラス水産会社の一つ、株式会社極洋の捕鯨部漁労科に配属されました。その後3年間、捕鯨母船の指令室で捕鯨船を指揮し、「太平洋の真ん中でトランペットを吹く」夢も 叶えましたが、捕鯨は世界中で反発運動が高まり、衰退の一途を辿っておりました。
池上さんは1975年に25歳で退職、砂川市に帰りました。「何時かは」と思い描いて来た、「子供達に少林寺拳法を教えたい」と言う気持ちが湧き上がりました。
しかし少林寺拳法の指導はボランティアであり、生活するには本業を別に持たなければなりません。
ある時池上さんは、市内に住む医者から「塾をやってもらえませんか?」と相談を受けました。
その頃の砂川市は、大手財閥が炭鉱会社や化学会社を営む等、市全体に経済力がありました。
一方で子供の平均学力は低下しており、医者の頼みは「医学部に行く様な子を増やしたい。
その為に子供達に勉強を教えて欲しい」と言う物でした。本職を探していた池上さんは早速、妻の実家のクリーニング屋の2階を借りて、学習塾「池上塾」を発足しました。
車で数分の場所に少林寺拳法の道場も開講。学習塾は生徒が次々と地元の偏差値トップ校へ進学した事で、口コミですぐに評判になり、市内の小中学生100人以上が池上塾で学んでいたそうです。
1978年には知人数人で市議会にも挑戦、16時頃まで市議会議員として働き、夜は塾や少林寺拳法の先生として、真面目で面倒見のよい池上さんは、あらゆる場所から引く手数多でした。
「ハンターの人手が足りない」1981年41歳の時、仕事の合間によく通っていた喫茶店のオーナー、当時猟友会事務局長・藤井録郎氏は池上さんにこう漏らしました。
「農家のカラス被害が酷いが、ハンターの人手が足りなくて困っている」。池上さんは資格を取ればハンターとして銃を持てると聞き、「農家の為なら」とやって見る事にしました。
「資格」とは第一種銃猟免許の事です。狩猟に使う銃には主に「ショットガン」と「ライフル」の2種類があり、この免許があればどちらも所持する事が出来ます。
ライフルはショットガンを10年以上所持して初めて所持許可を受ける事が出来ます。
池上さんは的に向かって何度も撃ちながら、ベストな”構え方”を研究しました。
ショットガンとは小さな粒弾が同時に何発も飛ぶ銃で、最大射程距離は約50m程度、鹿や鳥類を撃つ事に適しています。
ライフルは日本で所持が許可される銃の中で最も威力が強く、最大射程は300mに及び、到達距離は何と3㎞に及びます。その威力は「鉄筋すら破壊する」程で、ヒグマは主にライフルで撃ちます。
ヒグマを撃つ際は、弾の威力がまっすぐに行く様に基本「立射」ですが、雪や茂みの中に伏せて撃つ事もありますが、池上さんが「怖い」と感じた事は今まで1度も無いそうです。
「動じない精神を(少林寺拳法で)鍛えていたからね」と池上さんは笑います。
「銃の持ち方は少林寺拳法の「左中段構え」に似ているんですよ。
銃を中央に持ちきちんと頬付けをする。そうしないと銃が跳ねてしまうから、しっかりとした構えが必要なんだ」と理解したそうです。
銃免許を取得した池上さんはまず、事務局長から聞いた通り、カラスの有害駆除を始める事にしました。有害駆除とは、自治体から依頼を受け、農作物の被害などを防ぐ為に行います。
池上さんがヒグマを撃ったのは、それから10年以上後のライフル銃取得後でした。
山の食糧が豊富だった1980年代当時、ヒグマは人里に降りて来なかったのです。
初めて撃ったヒグマの記憶は薄れて来ましたが、1990年代以降、ライフルを使える様になった池上さんは、徐々に「箱罠」に掛ったヒグマの止刺しを依頼される様になりました。
箱罠とは鉄製の檻にエゾ鹿の死骸等を仕掛け、ヒグマが餌を食べようと中に入り、踏み板を踏むと扉が閉まる物です。「檻の外からではなく、檻のすき間から銃を差し込んで、一発でドンッと撃ちます。
普通はおっかなくて、銃を中にも入れられないよ。ヒグマにこう(手で振り払う仕草をしながら)やられてしまえば、銃自体が飛んで行くからです。
ところがね、頭を下げて「まいった」って」ヒグマって言うのは覚悟するのです。「ヒグマは頭が良く」箱罠の中で銃を向けられ、状況を理解するのだと言います。
撃つ場所は、脳天。体を傷付けず1発で苦しまずに倒れる様にする為です。
「可哀想だ」と言う気持ちは池上さんの中に常にあります。
元々池上さんはヒグマの絵を頻繁に描く程、ヒグマの事が大好きでした。池上さんはヒグマを撃った後、必ずその場で手を合わせ、般若心経を唱えます。
「生き物を殺すと言う事は、生命を断ち切る事。
命を頂きますと言う事である」と、絵を眺めながら話します。
彼の教えは、実戦では「必ず一発で仕留めろ」。理由は2つです。
1つはヒグマが苦しまずに済む様にする為です。
もう1つは1発で死なない「半矢」状態にならない様にする為です。
猟場で半矢になった場合、反撃してくる恐れが極めて高く、人に攻撃心を抱いたヒグマは、その後も人を襲う様になります。
その為池上さんはこれまで必ず、1発でヒグマを射止めて来ました。1度も外した事はありません。それがどれだけ凄い事なのか。ある時、池上さんが箱罠のヒグマを撃とうとした際、「ヒグマを撃った事がないので、代わりにやらせて欲しい」と別のハンターに頼まれました。
それならと任せた物の銃を構えた腕がブルブル震え、何時までも撃つ事が出来なかったと言います。殆どのハンターは、例え鹿や鳥類のベテランハンターだったとしても、巨大なヒグマを目の前にすると恐怖に圧倒されてしまうのです。
ヒグマを1発で仕留める為に池上さんが意識している事。それは「歩いている状態のヒグマを決して撃たない事」と、「20m以内の近距離から撃つ事」の2つです。
下手に遠距離から撃ったり、動いているヒグマを狙ったりすれば、半矢になる危険があります。
「撃つ」と言うのは非常に大きな責任が伴ないます。
「半矢となればそのヒグマを山中で探し出し、止めを刺さなければいけないと言う事です。
そして3つ目は、茂みの中に沈んでいるヒグマに狙いを定め、ヒグマが立ち上がり、目が合った瞬間に撃つ事です。撃つのは箱罠と時とは異なり、ヒグマが立ち上がっている為、喉元のやや下です。
「立ち上がった熊はこちらを見ます。その瞬間に撃たないとダーッと走って襲って来る。」そうです。
砂川猟友会にもヒグマを撃った経験のあるハンターは、池上さんを含め3人しかいないのです。
ここで、箱罠の時は「麻酔銃を使えば?」と言う、素人的な疑問も湧きます。
麻酔で眠らせたヒグマを山の中へ運び、そのまま置いて来る事は出来ないのでしょうか?
まず麻酔銃を扱うには獣医師等の専門資格が必要です。
加えて麻酔銃も銃ですから銃を扱う資格を持ち、その中でもヒグマを目前にして僅か数十mから発砲する度胸がある人はまずいません。
そもそも池上さん達ハンターは何故ヒグマを撃つのでしょうか?
池上さんが「我々は“熊撃ち”ではない」と言う様に、商売や趣味、そしてヒグマを撃つ事を生き甲斐にしている人達と、池上さんの様に「有害駆除」のみ行うハンターでは、目的が大きく異なります。
池上さん達の場合、「自治体」「地域の振興局」「警察」の三者が「駆除した方が良い」と判断して初めて、猟友会に依頼が来ます。
この時、特定のハンターが指名される事はありませんが、元々適任者は池上さんを含め、3名しかおらず、支部長である池上さんは自ら担当する事が多いそうです。
自治体毎の「目標頭数」と言うのも存在します。各自治体で目指す、ヒグマの駆除数の事です。
何故そんな物が定められているのかと言うと、ヒグマによる農作物被害は深刻で2019年にはその被害額が北海道だけで2億円以上に及んでいるからです。
「農業は農家さんの一生で、収獲出来る回数が本当に少ないのです。
1年に1回の収穫と考えると、30歳から60代までやったとしても、30数回しか収穫はなく、多大な費用と半年以上の努力の全てが無駄になり、死活問題と言う程度を遥かに超える大問題と言えます。
そんな池上さんは2018年、要請に従ってヒグマを駆除しました。現場には十分な高さの土手がありましたが、それを当局は危険場所の発砲とし、ライフル銃の許可を取消しました。
裁判でその安全性が認められ、ライフル銃の資格を取戻す事が出来ましたが、市街地のヒグマの駆除の在り方を根本的に考えさせられる事件となりました。
2019年以降砂川猟友会では、その理由だけではありませんが、ヒグマ駆除の要請を先頃から辞退を続けています。報酬金目的でヒグマハンターになる人はいません。
国や自治体からの報酬は有りますが、生活の糧に出来る程ではありませんから、誰もが本業を持っています。
ヒグマ駆除その出動は本業停止しての出動となります。
出動すれば若干の手当はありますが、周辺地区に比べそれは高校生のバイト並と余りにも低く、ハンターの特殊技能やヒグマ駆除のリスクが全く考慮されておりません。
住民を守るのが警察の役目ですから、ヒグマ駆除は本来警察の「狙撃部隊」が出動すべきです。
ヒグマ駆除に使えるライフル銃と射撃技術を持っています。
しかし実際のヒグマ戦で正しく機能する事は低率です。
ケンさんスクール事例では体重130㎏の無害と言える大物エゾ鹿に冷静に対処出来たのは100名中僅か2名だけでした。
池上さんが遭遇した最も大きいヒグマは実測体重275kg。射手より遥かに大きな猛獣ヒグマに対し、冷静な射撃が出来る事が条件ですが、対応出来る人は極めて僅かです。
猛獣の目前で日頃の訓練ぶりを発揮出来る人は実は100人に推定1人もいないのです。
ヒグマ駆除のベテランでも捕獲数の多くは箱罠の止め刺しに留まり、実戦ヒグマ撃ちも90%のヒグマは逃げるだけです。
反撃して来るヒグマと対戦した経験を持つハンターは極めて少なく、肝心の時に正しく機能出来る人は甚だ僅かであり、過去にもハンター多数が返り討ちに合っているのが現状です。
そんな池上さんの元には今も自治体から「プロファイリング」依頼が頻繁に舞込みます。
プロファイリングとは、ヒグマの足跡や目撃者等のデータから、ヒグマの移動ルートを探る事です。
約30年ヒグマと向き合い、今も毎朝ヒグマパトロールをし、山を熟知した池上さんだからこそ成せる業です。DNA鑑定等でプロファイリングをする鑑識の専門家とは違い、我々ハンターは現場で「動物と植物の動き」見て判断するんです。
山の変化は毎日見ないとわからない。
早朝に行くのは、ヒグマ達は何時も、夜明けと共に麓へ水を飲みに来るからです。
そんな池上さんをヒグマ達は影から見ているのでしょうか。ある牧場から「ヒグマがよく出て困っている」と言われ池上さんが訪れた所、現場に着くや否や、目の前に突然ヒグマが現れました。
所がヒグマは、池上さんを見るなり物凄い勢いで逃げて行ったそうです。
「ヒグマは怖い人間とそうでない人間を見分けているんです。
猟友会ではヒグマだけでなくエゾ鹿も駆除しており、エゾ鹿の残滓は地中に埋める事になっています。我々が鹿を解体する現場もヒグマは遠くから見ており、解体中に1〜2分その場を離れて戻ったら、忽然と鹿がなくなっていた事もありました、ヒグマが持って行くんです。
また以前埋めた残滓(死がいの事)を掘り起こして食べられている事もありました。
ヒグマが市街地へ来る様になった理由に付いて、池上さんは確信を持っています。「色々な見解がありますが、ヒグマは単にエゾ鹿を追って町に来ているだけだと考えている」そうです。
北海道内で その数を増やし続けているエゾ鹿。天敵だったエゾ狼の絶滅や、ハンターの減少が原因だと言われており、そのせいで増殖し過ぎ、エゾ鹿は山の食糧が不足し、人里に降りてくるのです。
ハンターが駆除したエゾ鹿も、残滓も施設でバイオ処理されます。池上さんは、「本来エゾ鹿残滓は「山に置いてくるべき」だと考えます。
元々ヒグマの主食はエゾ鹿ではありませんが、自らエゾ鹿を捕獲しており、残滓を山に置いてくれば、ヒグマは山の中でエゾ鹿を食べる事が出来、自然の摂理でエゾ鹿は増えず、農作物被害も減り、ヒグマを殺さなくて済む、と思っているそうです。
「ヒグマに出会ったら、とにかく息を殺し、動かない事。万が一気付かれたら、ヒグマの目を見ながら両手を大きく広げ、「俺は人間だ! 来るな!」と大声で威嚇するのが有効」だそうです。
池上さんは今、ハンターとしてヒグマのプロファイリングをする傍ら、池上塾の教え子達はやがて東大や早稲田、一ツ橋大、東北大、等の有名大学を卒業し、彼らが世の中を良くしてくれる事でしょう。
過去には「池上さんの様なハンターになりたい」と訪ねて来る若者もいましたが、池上さんは簡単にOKを出しません。
と言うのも生き物を銃で撃つと言う事は、「反発を受ける」事になるからです。池上さんの元にも抗議の電話が掛かり、酷い時には恐喝まがいの言葉を吐かれる事もあるそうです。
「撃つ事でその人の人生が変わる。家族がいる人に、安易に「行ってくれ」とは頼めません。
池上さんの心の根底にあるのは何時も「半分は自己の為に、半分は人の為に」と言う少林寺拳法の理念です。
自己を確立出来たら、その力を社会や人の為に役立て様、そうした意味が込められていると言います。池上さんは今日も猟友会の支部長として、自身のやるべき事をまっとうしています。
2024年06月02日
ヒグマ捕獲名人。
 山本兵吉
山本兵吉 ベルダン1870
ベルダン1870山本 兵吉(やまもと へいきち)、1858~1950年、日本の猟師。
獣害史最悪と言われた三毛別羆事件のヒグマを退治する等、生涯で捕ったヒグマは300頭と言われます。北海道留萌郡鬼鹿村温根の沢(現・小平町鬼鹿田代)の住人で、鬼鹿山など当時の天塩国の山を主な猟場としました。
山本兵吉の愛銃はロシア製ベルダン1870、黒色火薬11㎜口径単発、村田13年式と同程度のライフル銃です。

大川 春義(おおかわ はるよし)、1909∼1985年、猟師(マタギ)、1915年獣害史上惨劇と言われた三毛別羆事件の舞台となった北海道苫前郡苫前村三毛別(後の苫前町三渓)出身。数少ない目撃者の1人。
当時6歳だったが、同事件の犠牲者の仇を討つ為に猟師となり、生涯にヒグマを100頭以上仕留めてヒグマ狩猟の名人と呼ばれると共に、北海道内のヒグマによる獣害防止に貢献した。

赤石正男(あかいし まさお) 1952年生れ、北海道標津町出身、標津町在住。赤石が初めてヒグマを獲ったのは、成人して散弾銃を持てる様になってすぐの事でした。ハンター歴は約50年、現在も確約中、「野性の熊が最も恐れる男」と呼ばれます。ヒグマの生態を知り尽くし、単独猟歴は120頭を超え、ライフル遠射、罠や捕獲檻を使用しての動物捕獲のエキスパートである。
彼の射程距離は300~400mで、「遠射」の命中率は図抜け、この距離でも、クマより的が小さいエゾ鹿の頭を確実に撃ち抜く事も出来、最長記録は810m先のヒグマだそうです。
赤石氏は「いまだに3ヵ月に2回ペースで、90㎞離れた網走の射撃訓練場に通っている様です。


久保俊治(としはる):1947年、北海道小樽市生まれ。日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育つ。
20歳の時に狩猟免許を取得し、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始する。
1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後は現地プロハンティングガイドにもなるも、翌1976年帰国。
知床半島の根元の標津町で牧場を経営しながら、ドッグレスの単独で山に入りヒグマ猟を行っていました。日本で唯一単独猟のヒグマ猟師。
捕獲頭数は70頭以上と言われていますが、本人は公共せず定かではありません。狩猟方法から推定すれば、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちですからもっと少ない気もします。
2018年~狩猟を目指す人、自然が大好きな人のライフスタイルがより豊かな物になる事を願ってアーブスクールジャパンを開講しました。
2024.4.10.心不全の為76才で死去されました。
ヒグマに気付かれない様に、山に入る自分が自然の中で異質ではいけないと、餌を探す鹿と同じ速さで歩き、自らを自然に溶け込ませ、自然の一部と化して歩を進め5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃し、獲物を苦しめない、獲った命を無駄にしない事を信条としていました。
全ては1頭の為に狩猟技術の高みを目指すと著書等では書かれ、ケンさんも彼の狩猟に憧れた時期もありました。しかしその後ケンさんも色々を経験し技量が上がりました。
現在の推定ではヒグマの周辺を何時も歩き廻り、ヒグマから見てあの人間は「無害」であると思い込ませ、至近距離まで接近し撃ったと思っています。
困難だった時代のアメリカ留学と、その後の独自の子育て方法がマスコミに注目され、「大草原のみゆきちゃん」一気に有名になりました。
著書「羆撃ち」も売れましたが、ドッグレスハンターのケンさんに言わせると前半の主役は偶然に出会えた「天才犬フチ」の大活躍物語であり、後半は「フチ」を無くしてオロオロする単なる「名犬ロリコン」物語と言えました。
2024年05月25日
「ヒグマエースと言う称号」
戦闘機の機銃は飛行機に固定されており、高度な機動をする相手飛行機に先を読み、高難度の飛行機操縦を瞬時且つ精密に行い、機銃を相手の飛行機に向け、撃墜します。
ここ1番に「肝が座っていなければ」出来る技ではありません。
長年やっていれば1~2機はマグレ撃墜もあり得ますが、5機はマグレではない事の証明となり、それを称えるのがエースと言う称号です。
第2次大戦のアメリカでは数万人の戦闘機パイロットがいましたが、エースは僅か30人余です。
大物猟でも同様の事が言えます。ここ1番に足が地に着いた射撃が出来なければ、勝負に勝てないのは戦闘機と同じです。
一般的に鹿撃ちと言えば、本州鹿巻狩りになりますが、ケンさんは最初の1頭捕獲までに9年間出撃70余日を要しました。最初の10年間ではこの1頭だけでした。
1.ヒグマエース。
その後まもなくしてケンさんは本州鹿猟に開眼、その後の4年間の40日で20頭を捕獲、ここでエゾ鹿猟に転向、2回目の10年間では約100頭を捕獲、続く3回目の10年間では約1000頭を捕獲、「不可能に挑戦」のライフワークを続けて来ました。
3回目の1000頭中には「猛獣のヒグマ6頭」も含まれ、「ヒグマエース」も達成となりました。
ハンターは2024年現在約10万人弱、ヒグマ捕獲総数はシーズンに100頭程度、本州ハンターによる捕獲は極めて僅か、ケンさんは15m出会い頭のヒグマ、450㎏のヒグマにも「臆せずに対処出来た事」を誇りに思います。
6頭中の3頭のヒグマは走っており、「ランニング射撃もマグレで無い事を立証出来」ました。

2.日本大物クラブのエースバッジ。
且つて2002年頃と思われますが、日本大物クラブに会費を払っていた事があります。
エゾ鹿5日猟で10頭を捕獲した記事を狩猟雑誌「狩猟界」に載せた処、この小さな金バッジ2個(ダブルエース)を送って来ました。

時代はケンさんが「禅の心作戦」で本州鹿猟開眼後、本州鹿猟捕獲率を1桁上げた頃の話です。
日本大物クラブは会員数が約150名、多くの会員が5頭捕獲のエースを目指す処か、何時かは1頭目捕獲を目指す状態でした。
ケンさんも1頭目捕獲には随分苦労しましたが、本州鹿猟に「禅の心作戦」で開眼後は4年で本州鹿20頭を捕獲、しかし本州鹿猟に限界を感じ、これを卒業しました。
巷の本州鹿巻狩りでは1日平均0.05頭/日人、1頭捕獲には20日を要します。
当時の鹿猟は12月1日~1月31日までの2カ月、毎週土日を皆勤しても17日、正月休み分をプラスして、やっとシーズンに1頭程度でした。
従って60%出撃と仮定では、エース達成まで8年以上を要し、エースは価値ある称号と言えました。
本州鹿捕獲は非常に大変ですが、北海道のエゾ鹿猟ケンさんスクールでは生徒が1日に5回勝負し2頭を捕獲、エース誕生は3日猟で可能でした。3段角のオス成獣に限っても70%がそれですから、エースまで4日猟で楽勝でした。
ケンさんスクール開講直後でもあり、エゾ鹿猟は桁違いに捕獲出来る事、捕獲内容の素晴らしさを多くの人に伝えたいと思っていました。
ケンさんがやれば70%以上捕獲出来、1日に3~4頭捕獲出来ます。
しかし生徒が来た時に出会いが少ない様ではいけないと思い、かなり控目捕獲するのですが、それでも1日2頭は楽勝なのです。
本州鹿も有能なガイドが付けば、ケンさんスクール並に出会え、そして捕獲が可能な事をU生徒が立証しました。しかしこれをガイドするガイドは今の所は存在せず、本州鹿は巻狩り主体、これは当面変わりなさそうです。
3.ケンさんスクールエゾ鹿エース。
写真D生徒は丹沢通い10年でエースになりましたが、スクールでは5日猟で公表5頭を捕獲、実際はケンさんの代理射撃を行い、オス10頭+メス3頭を捕獲しました。


丹沢10年分を2日間で超え、しかもケンさんがヒグマを捕獲すると言うオマケもあり、そのヒグマの毛皮は彼が保管しています。
この頃はまだスクールの前期時代、すでに数年前の阿寒で巷のガイドの80%以上が全くの詐欺ガイドであった事を経験しましたので、平均値より遥かに上の実力である事は分かっていました。
しかし北海道には、ケンさんより遥かに凄いガイドが必ずいると思っていました。
その様なガイドは存在しない事が判ったのはスクール中期時代以後でした。
ケンさんスクールでは平均捕獲が1日2頭を超え、従って5頭エース達成は上手く行けば初回遠征の2~3日で十分となり、エースは価値の無い物になりました。
上写真右は角長70㎝超える大物です。普段の出会い率は1桁下がりますが、フィーバーの日にはズラズラ出て来ます。現実に2011年ケンさんはフィーバー3度で大物31頭が獲れてしまいました。

フィーバ-1日だけで射撃ミスが少なければ、大物ダブルエース達成、これではエースの価値がありません。
巷では出会う事だけからしても大物勝負は大変な事ですが、ケンさんスクールではフィーバー日でなくてもある程度の大物捕獲があり、平均値は1日に0.5頭でした。それで行けば大物エースまでは実戦10日、シーズン5日出猟で2年で達成出来てしまいました。
4.超大物エゾ鹿のエース。
次のクラスは角長80㎝を超える超大物、これは生息数が超大幅に減少し、射撃距離が遠く、照準時間は短く、「迫力負け」する事なく、ナミビアポイントを速やかに撃ち抜かなくてはなりません。高難度の4乗となります。
スクールに於いても超大物成功者は僅か5名しかおらず、1頭捕獲まで平均22日、シーズン5日の出撃では1頭捕獲まで4.4年を要します。
そのペースで超大物エースまでは22年を要する事になりますが、超大物の獲達成者5名中3名はマグレ捕獲、2頭目の捕獲が続きません。


真の達成者は2名だけでした。ケンさん自身も「迫力負け」に随分泣かされました。
これをイメージトレーニングで乗り越えても、当時Stdの心臓狙いでは未回収に成り易く、狙い目をショルダーのナミビアポイントに変更後、やっと捕獲が可能となりました。
この急所変更により超大物捕獲率は5倍に跳ね上がりました。また生徒に依る超大物捕獲も、ナミビアポイントを指導する様になってからでした。
大物までは生息数も多く、「迫力負け」も自然に5回失敗で克服出来ますが、超大物クラスになりますと、生息数が極端に少なくなり、5回失敗を積み上げるには超大物エース誕生と同程度に大変な事でした。
従って積極的に「迫力負け対策」のイメージトレーニングをする必要があります。超大物は出会う事も、捕獲成功する事も一気に超高難度となります。
因みにケンさんは735日を出撃し、超大物33頭を捕獲しています。
つまり超大物1頭の捕獲に22.3日を要し、それで行けば111日出撃すれば超大物エースが誕生となります。
超大物エース達成までにはシーズン5日の出猟では22.2年を要し、狩猟人生の全てを掛けなくてはならない事になります。ケンさんに取っても狩猟5年中30年までは試行錯誤の繰り返し、超大物戦は高難度でした。
ケンさんスクールに於いて超大物出会いは5%弱、平均的に言えば5日猟をすれば1回の勝負が得られ、70%成功確率なら超大物エースまで36日となり、シーズン5日出撃なら7年を要する事になります。
しかし、後述の様に敵は実戦から多くを学び、その対策であの手この手を運用する様になり、計算通りには行きません。要は普通の射撃だけでは全く手が出させない様になりました。
5.超大物鹿は高難度です。
2017年、U生徒の捕獲した88㎝はその1週間前、K生徒の前にも50mで出ました。
しかしこの怪物は銃を向けると5秒で動く事により、これまで生き延びて来ました。
K生徒は慎重を期し過ぎ5秒で撃てず、1生に1度のチャンスを逃しましたが、U生徒はやや遠い80ⅿチャンスを3秒で撃ち捕獲に成功しました。
怪物クラスは多くがこうした行動を取ります。
ケンさんが捕獲した88㎝怪物は車と並行して走り、突然に車の後方を突っ切ろうとしましたが、ケンさんには通用せず、ランニング射撃に捕えられました。
87㎝怪物は発見時150mをすでに走っていました。しかしこの先の丘のトップで立ち止まり振り返ると予測、そこへ先行し「待ってたホイ射撃」に賭けました。
結果は予定通り、200mで立ち止まって振り返り、「待ってたホイ射撃」で即倒しました。
超大物クラス勝負は通常朝夕の自己アピール会場での出会いでは200m以遠ですが、この距離でも銃を向けると5秒で動く個体が多く、「アバウト早撃ち」が必要です。
何故5秒なのか? それは通常照準が10秒だからです。
その通勤途上の鉢合わせでは先のU生徒の様に「スナップショット」が必要になります。
また出会った時にすでに走っている事も多く、「ランニングショット」や「待ってたホイ射撃」が多くなります。超大物はすでに過去何度も射撃を受けており、その対策を学習済なのです。
超大物はその技で現在まで生き延びて来れたのです。
単なる射撃距離が遠く、照準時間が短い、迫力負けせず、速やかにナミビアポイント射撃、そんな簡単な物ではなく、超大物戦は高度な特殊射撃のオンパレードなのです。
あの大変だった「迫力負け対策」すらが、超大物戦ではほんの入門だったのです。
何れも場合も射撃技術的に簡単ではありません。
そしてそれ以上に超大物エゾ鹿のそれら行動に対し、心の動揺があってはなりません。
エースは更なる新しい逃げ口に対しても、積み上げた技術の応用で対処出来なくてはなりません。
積上げた技術とはどんな大物にも「迫力負け」しない、猛獣ヒグマにも「恐怖負け」せず怯まない、心側の積み上げ技術。更に技術的には鹿が逃げる前に撃てる下記の数々の特殊な技術です。
まずは西部劇の早撃ち並ながら必ず命中する「スナップショット」が必要です。
近くの委託物を素速く利用して撃つ「半委託射撃」、十分な照準時間があれば150m「ワンホール射撃」、精密射撃に裏打ちされた150~200mながら3秒で撃つ「アバウト早撃ち」等々があります。
鹿がすでに走っている事も多く、鹿の習性や地形から立止まり振り返る位置を予測する「待ってたホイ射撃」、動的の古い「虚像」に惑わされない「スイング射撃」、体全体で 追尾する再肩付「スナップスイング射撃」の連射技術等々があります。
これらの技術を駆使し、極めて稀な一瞬のチャンスにも速やか且つ冷静に対処、ここから絶望的困難だった超大物捕獲成功が生まれます。
そしてそれが5回以上繰り返され、マグレで無い事が立証され、これがエースなのです。故に、エースと言う称号には大きな価値があります。
ここ1番に「肝が座っていなければ」出来る技ではありません。
長年やっていれば1~2機はマグレ撃墜もあり得ますが、5機はマグレではない事の証明となり、それを称えるのがエースと言う称号です。
第2次大戦のアメリカでは数万人の戦闘機パイロットがいましたが、エースは僅か30人余です。
大物猟でも同様の事が言えます。ここ1番に足が地に着いた射撃が出来なければ、勝負に勝てないのは戦闘機と同じです。
一般的に鹿撃ちと言えば、本州鹿巻狩りになりますが、ケンさんは最初の1頭捕獲までに9年間出撃70余日を要しました。最初の10年間ではこの1頭だけでした。
1.ヒグマエース。
その後まもなくしてケンさんは本州鹿猟に開眼、その後の4年間の40日で20頭を捕獲、ここでエゾ鹿猟に転向、2回目の10年間では約100頭を捕獲、続く3回目の10年間では約1000頭を捕獲、「不可能に挑戦」のライフワークを続けて来ました。
3回目の1000頭中には「猛獣のヒグマ6頭」も含まれ、「ヒグマエース」も達成となりました。
ハンターは2024年現在約10万人弱、ヒグマ捕獲総数はシーズンに100頭程度、本州ハンターによる捕獲は極めて僅か、ケンさんは15m出会い頭のヒグマ、450㎏のヒグマにも「臆せずに対処出来た事」を誇りに思います。
6頭中の3頭のヒグマは走っており、「ランニング射撃もマグレで無い事を立証出来」ました。

2.日本大物クラブのエースバッジ。
且つて2002年頃と思われますが、日本大物クラブに会費を払っていた事があります。
エゾ鹿5日猟で10頭を捕獲した記事を狩猟雑誌「狩猟界」に載せた処、この小さな金バッジ2個(ダブルエース)を送って来ました。
時代はケンさんが「禅の心作戦」で本州鹿猟開眼後、本州鹿猟捕獲率を1桁上げた頃の話です。
日本大物クラブは会員数が約150名、多くの会員が5頭捕獲のエースを目指す処か、何時かは1頭目捕獲を目指す状態でした。
ケンさんも1頭目捕獲には随分苦労しましたが、本州鹿猟に「禅の心作戦」で開眼後は4年で本州鹿20頭を捕獲、しかし本州鹿猟に限界を感じ、これを卒業しました。
巷の本州鹿巻狩りでは1日平均0.05頭/日人、1頭捕獲には20日を要します。
当時の鹿猟は12月1日~1月31日までの2カ月、毎週土日を皆勤しても17日、正月休み分をプラスして、やっとシーズンに1頭程度でした。
従って60%出撃と仮定では、エース達成まで8年以上を要し、エースは価値ある称号と言えました。
本州鹿捕獲は非常に大変ですが、北海道のエゾ鹿猟ケンさんスクールでは生徒が1日に5回勝負し2頭を捕獲、エース誕生は3日猟で可能でした。3段角のオス成獣に限っても70%がそれですから、エースまで4日猟で楽勝でした。
ケンさんスクール開講直後でもあり、エゾ鹿猟は桁違いに捕獲出来る事、捕獲内容の素晴らしさを多くの人に伝えたいと思っていました。
ケンさんがやれば70%以上捕獲出来、1日に3~4頭捕獲出来ます。
しかし生徒が来た時に出会いが少ない様ではいけないと思い、かなり控目捕獲するのですが、それでも1日2頭は楽勝なのです。
本州鹿も有能なガイドが付けば、ケンさんスクール並に出会え、そして捕獲が可能な事をU生徒が立証しました。しかしこれをガイドするガイドは今の所は存在せず、本州鹿は巻狩り主体、これは当面変わりなさそうです。
3.ケンさんスクールエゾ鹿エース。
写真D生徒は丹沢通い10年でエースになりましたが、スクールでは5日猟で公表5頭を捕獲、実際はケンさんの代理射撃を行い、オス10頭+メス3頭を捕獲しました。

丹沢10年分を2日間で超え、しかもケンさんがヒグマを捕獲すると言うオマケもあり、そのヒグマの毛皮は彼が保管しています。
この頃はまだスクールの前期時代、すでに数年前の阿寒で巷のガイドの80%以上が全くの詐欺ガイドであった事を経験しましたので、平均値より遥かに上の実力である事は分かっていました。
しかし北海道には、ケンさんより遥かに凄いガイドが必ずいると思っていました。
その様なガイドは存在しない事が判ったのはスクール中期時代以後でした。
ケンさんスクールでは平均捕獲が1日2頭を超え、従って5頭エース達成は上手く行けば初回遠征の2~3日で十分となり、エースは価値の無い物になりました。
上写真右は角長70㎝超える大物です。普段の出会い率は1桁下がりますが、フィーバーの日にはズラズラ出て来ます。現実に2011年ケンさんはフィーバー3度で大物31頭が獲れてしまいました。

フィーバ-1日だけで射撃ミスが少なければ、大物ダブルエース達成、これではエースの価値がありません。
巷では出会う事だけからしても大物勝負は大変な事ですが、ケンさんスクールではフィーバー日でなくてもある程度の大物捕獲があり、平均値は1日に0.5頭でした。それで行けば大物エースまでは実戦10日、シーズン5日出猟で2年で達成出来てしまいました。
4.超大物エゾ鹿のエース。
次のクラスは角長80㎝を超える超大物、これは生息数が超大幅に減少し、射撃距離が遠く、照準時間は短く、「迫力負け」する事なく、ナミビアポイントを速やかに撃ち抜かなくてはなりません。高難度の4乗となります。
スクールに於いても超大物成功者は僅か5名しかおらず、1頭捕獲まで平均22日、シーズン5日の出撃では1頭捕獲まで4.4年を要します。
そのペースで超大物エースまでは22年を要する事になりますが、超大物の獲達成者5名中3名はマグレ捕獲、2頭目の捕獲が続きません。

真の達成者は2名だけでした。ケンさん自身も「迫力負け」に随分泣かされました。
これをイメージトレーニングで乗り越えても、当時Stdの心臓狙いでは未回収に成り易く、狙い目をショルダーのナミビアポイントに変更後、やっと捕獲が可能となりました。
この急所変更により超大物捕獲率は5倍に跳ね上がりました。また生徒に依る超大物捕獲も、ナミビアポイントを指導する様になってからでした。
大物までは生息数も多く、「迫力負け」も自然に5回失敗で克服出来ますが、超大物クラスになりますと、生息数が極端に少なくなり、5回失敗を積み上げるには超大物エース誕生と同程度に大変な事でした。
従って積極的に「迫力負け対策」のイメージトレーニングをする必要があります。超大物は出会う事も、捕獲成功する事も一気に超高難度となります。
因みにケンさんは735日を出撃し、超大物33頭を捕獲しています。
つまり超大物1頭の捕獲に22.3日を要し、それで行けば111日出撃すれば超大物エースが誕生となります。
超大物エース達成までにはシーズン5日の出猟では22.2年を要し、狩猟人生の全てを掛けなくてはならない事になります。ケンさんに取っても狩猟5年中30年までは試行錯誤の繰り返し、超大物戦は高難度でした。
ケンさんスクールに於いて超大物出会いは5%弱、平均的に言えば5日猟をすれば1回の勝負が得られ、70%成功確率なら超大物エースまで36日となり、シーズン5日出撃なら7年を要する事になります。
しかし、後述の様に敵は実戦から多くを学び、その対策であの手この手を運用する様になり、計算通りには行きません。要は普通の射撃だけでは全く手が出させない様になりました。
5.超大物鹿は高難度です。
2017年、U生徒の捕獲した88㎝はその1週間前、K生徒の前にも50mで出ました。
しかしこの怪物は銃を向けると5秒で動く事により、これまで生き延びて来ました。
K生徒は慎重を期し過ぎ5秒で撃てず、1生に1度のチャンスを逃しましたが、U生徒はやや遠い80ⅿチャンスを3秒で撃ち捕獲に成功しました。
怪物クラスは多くがこうした行動を取ります。
ケンさんが捕獲した88㎝怪物は車と並行して走り、突然に車の後方を突っ切ろうとしましたが、ケンさんには通用せず、ランニング射撃に捕えられました。
87㎝怪物は発見時150mをすでに走っていました。しかしこの先の丘のトップで立ち止まり振り返ると予測、そこへ先行し「待ってたホイ射撃」に賭けました。
結果は予定通り、200mで立ち止まって振り返り、「待ってたホイ射撃」で即倒しました。
超大物クラス勝負は通常朝夕の自己アピール会場での出会いでは200m以遠ですが、この距離でも銃を向けると5秒で動く個体が多く、「アバウト早撃ち」が必要です。
何故5秒なのか? それは通常照準が10秒だからです。
その通勤途上の鉢合わせでは先のU生徒の様に「スナップショット」が必要になります。
また出会った時にすでに走っている事も多く、「ランニングショット」や「待ってたホイ射撃」が多くなります。超大物はすでに過去何度も射撃を受けており、その対策を学習済なのです。
超大物はその技で現在まで生き延びて来れたのです。
単なる射撃距離が遠く、照準時間が短い、迫力負けせず、速やかにナミビアポイント射撃、そんな簡単な物ではなく、超大物戦は高度な特殊射撃のオンパレードなのです。
あの大変だった「迫力負け対策」すらが、超大物戦ではほんの入門だったのです。
何れも場合も射撃技術的に簡単ではありません。
そしてそれ以上に超大物エゾ鹿のそれら行動に対し、心の動揺があってはなりません。
エースは更なる新しい逃げ口に対しても、積み上げた技術の応用で対処出来なくてはなりません。
積上げた技術とはどんな大物にも「迫力負け」しない、猛獣ヒグマにも「恐怖負け」せず怯まない、心側の積み上げ技術。更に技術的には鹿が逃げる前に撃てる下記の数々の特殊な技術です。
まずは西部劇の早撃ち並ながら必ず命中する「スナップショット」が必要です。
近くの委託物を素速く利用して撃つ「半委託射撃」、十分な照準時間があれば150m「ワンホール射撃」、精密射撃に裏打ちされた150~200mながら3秒で撃つ「アバウト早撃ち」等々があります。
鹿がすでに走っている事も多く、鹿の習性や地形から立止まり振り返る位置を予測する「待ってたホイ射撃」、動的の古い「虚像」に惑わされない「スイング射撃」、体全体で 追尾する再肩付「スナップスイング射撃」の連射技術等々があります。
これらの技術を駆使し、極めて稀な一瞬のチャンスにも速やか且つ冷静に対処、ここから絶望的困難だった超大物捕獲成功が生まれます。
そしてそれが5回以上繰り返され、マグレで無い事が立証され、これがエースなのです。故に、エースと言う称号には大きな価値があります。
2024年05月23日
久保俊治氏 死去。
久保俊治(としはる):1947年北海道小樽市生まれ。2024.4.10.心不全の為76才で死去されたそうです。
日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育ち、20歳の時に狩猟免許を取得、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始しました。
1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後現地プロ(アシスタント)ハンティングガイドになり、1976年帰国、標津町で牧場を経営しながら、単独で山に入りハンティングを行なっていました。
ヒグマに悟られない様に自然の一部と化して歩を進め、5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃す事を信条としていたハンターでした。

1.どの様にして五感能力が桁違いのヒグマに10mまで接近するのか?
永い間ケンさんにもその手法は分かりませんでした。
分からなかったからこそ、それを凄いと思い、また尊敬していました。
久保氏はプロハンターを目指し、若くして名犬フチと出会いました。フチは稀に見る天才犬と言えました。しかし以後は猟犬に頼り切った普通のダメハンターになってしまいました。
彼の著書「羆撃ち」は確かの素晴らしい物がありましたが、それは彼が主役ではなく、「名犬フチ」の物語でした。
しかし猟犬の寿命は短く、著書の後半は「愛犬ロリコン物語」でした。彼はヒグマ猟その物が分かっていた訳でもなく、猟犬の育て方が分かっていた訳でもありませんでした。
2代目以降の名犬を育て「名人芸」を持続させたなら、彼は名人と言えました。
フチの2代目誕生を試みましたが、全く上手く行かずそこで早々と完全に諦めてしまいました。
「フチは名犬」でしたが、「久保氏は名人では無かった」のです。

彼の愛銃は「サコ―フィンベア338ウインチェスターマグナム)でした。
このサコ―を入手した時期の久保氏は狩猟方法がまだ定まっていなかったと思われます。
彼の信条である10m射撃ではスコープ後付銃はスコープと眼の位置が定まらず、大幅不利になりました。スコープ専用銃ならスナップショットで急所を捉える事は可能ですが、そのスコープ専用銃は20年後の1990年頃にデビューしました。
ライフル銃は本来100m以遠を高精度で撃つ銃であり、彼もその目的でスコープ銃を選択したと思われます。ストックと銃の機関部や銃身のベディングと言う絶妙な取付け調整や、引金切れ味追及の為のシアチューニングをしていました。
これらは高精度射撃を目的でなければ、殆ど無意味と言える行為でした。
そもそも10mでヒグマを確実に仕留めるのであれば、スコープ付ライフル銃がベストではありません。
ヒグマ猟も意識し、それで338ウインマグと言う口径を選んだ様ですが、ライフルの鉛弾頭は近距離射撃やブッシュ越射撃が不得意と言うより、鉛弾頭には重大な欠陥がありました。
近距離射撃・僅かなブッシュ越・骨ヒットで鉛が飛散してしまい、以後威力を失う大欠陥がありました。鉛弾の欠陥を少なくするには下記の様に2つの方法がありました。
1つ目はA型セパレータ付の弾頭で先端部は全飛散しても後半部がそのまま残る弾頭であり、2つ目は重量弾頭で弾速を落とし、更にラウンドノーズで飛散率を低減させる方法です。
彼は近距離時の鉛弾の重大な欠陥には全く触れていませんから、それを知らなかったと思われます。10mのヒグマ対戦には無垢のブレネッキスラグ弾がベストであると思います。
弾速からこの弾頭は鉛の飛散が余り起こらず、確実にヒグマを倒してくれます。また薄いブッシュであれば通過可能です。また近距離ヒグマ勝負を行う場合は、咄嗟の場合に銃を速やかに構える能力が不可欠になる筈ですが、彼の銃はスコープ後付け銃であり、眼の位置がスコープに合わず、これには不向きでした。
これが1990年頃から普及したスコープ専用銃や、また2000年頃から法律で決められた銅弾頭であれば、話が全く変わります。
スコープ専用銃はケンさん考案の新しい銃で指向するスナップ射撃が可能となり、肩に着ける前に命中する発砲が可能となり、スナップショットは得意項目になりました。
また銅弾頭は鉛の飛散が全く怒らず、これを利用して積極的に「骨の急所を撃つ事が可能」となりました。
久保氏は猟犬を使った猟を諦め、ドッグレスで山を歩き廻る様になり、やがて至近距離からヒグマ 勝負を挑む様になりました。
銃の世界も1980年頃になりますと、スコープ専用銃が出始めていました。
銃のパフォーマンスを上げ様と日々の工夫があれば、新しい猟具や技術に興味が行く筈ですが、彼はそうなりませんでした。そう言う方面に関心が薄いのが猟犬を使うハンターの特徴と言えました。
彼より3歳若いケンさんはドッグレス猟であり、1985年頃にはショットガンもライフルも独自のスナップ ショットを完成し、スコープ専用銃「ルガー77ボルトライフル」もデビュー後の程なくして購入しました。
鹿猟犬を頼った猟をする久保氏は猟具に関心が薄く、狩猟の道具も1975年頃から、銃もナイフも全く進化せず、若い頃のスコープ後付銃のサコ―フィンベアをそのままの形でずっと使い続けました。
ナイフで申すなら炭素鋼のナイフから進化せずでした。ケンさんのナイフは炭素鋼→ステンレス鋼→ダマスカス鋼と進化し、画期的と言える程に進化しました。
炭素鋼では鹿1頭目の後半から切れ味が大幅低下しました。
ステンレス鋼になりますと、メス2頭目までは良いのですが、3頭目で切れ味が低下しました。
それがダマスカス鋼になりますと、メス20頭を研がずに解体出来ました。
久保氏が掴んだヒグマとの接触方法の極意は、多分結果オーライの形で得られたのではないかと思います。それは何時もヒグマのいる地域を歩き、ヒグマに無害の人間であると思わせたのです。
本州に住み、シーズン数十日のみの狩猟をしていたケンさんには真似の出来ない手法ですが、地元に住んでいて、特定エリア内の年間数頭以下のヒグマを捕獲するのであれば、可能な方法と言えました。50年狩猟をしていて新たに分かった事の追加です。
その延長で考えますと、ケンさんもヒグマ捕獲を目的に行動開始し、5年目の2006年に1頭目を捕獲、翌年に2頭目と3頭目を捕獲しました。そして箱罠に依るヒグマ駆除が始まりました。
それまで箱罠駆除は行われていなかったので、多くのヒグマがパタパタ掛かりまして、過半のヒグマが捕獲され、ケンさん猟場のヒグマ生息数は半分以下となりました。
そして7年目の2014年、ヒグマの生息数も回復し、4頭目と5頭目のヒグマを捕獲、エースとなりました。そして2015年6頭目のヒグマを捕獲しました。
これもヒグマ側からすれば、ケンさんの車を猟場でよく見掛ける様になり、逃げなくなったのではないかと思える部分もありました。唯ケンさんの場合は50m先を走るヒグマが多かったと言う違いはあります。
久保氏はテレビ取材時に、50mでノーマークのエゾ鹿を立ち木に半委託射撃で撃ちました。
流石に半矢で逃げ出す事は無かったのですが、驚いた事に即死ではない射撃でした。
獲物を苦しめない彼の信条からすれば、また5~10mでヒグマを確実に即死させている事からすれば、信じられない下手糞な射撃でした。
その時代ではアメリカ帰りが珍しかった事、更に独自の子育て「大草原のみゆきちゃん」の取材を通し、マスコミに有名になり、「羆撃ち}も売れました。
ヒグマ70頭を捕獲したと言う説もありますが、彼自身は捕獲数を公表しておらず、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちではそこまで行っていないと思われます。
ケンさんが若い頃には仙人の様な凄い人だと尊敬していましたが、唯の猟犬ロリコンダメハンターでした。
2.小山氏の銃のバランス。
別の話ですが、長い間ケンさんは小山氏が北海道でNO.1のガイドであると思って尊敬して来ました。それはケンさんが1頭も捕獲出来なかった90㎝以上を相当数捕獲していたからです。
その小山氏が昨今は動画を多数投稿される様になり、それで気が付いた点があります。300m遠射が多いとは言え殆どが即倒していないのです。どうしてなのかを考えてみました。
因みにケンさんの300mは殆どが即倒の即死です。

写真は小山氏の愛銃:レミントン700、カスタムバレル、口径レミントン7㎜マグナム、スコープ4~16倍ビデオ機能付、重装備です。
ハンティング動画撮影に拘りを持っておられ、ネットにも多数投稿されています。
射撃精度にもかなり拘っておられる様で、モア精度のハンドロードで7㎜レミントンマグをカスタムバレルから撃っておられ、300mなら過半が即倒だと思うのですが、即倒していないのです。
狙撃が心臓狙いもあってか、小山氏の投稿動画でも即倒が殆どありません。ケンさんが見た投稿動画10本余で、即倒は1回だけで、何時も半矢捜索で数十~数百mで死んでいました。
未回収動画を公開する事は無いと思われ、即倒率は更に低いと思われます。
そして角サイズに拘りを持っておられ、300m前後のビッグトロフィー級狙いの遠射が主体です。
小山氏とケンさんと何が違うかと言えば、口径と急所とスコープです。
ケンさんの愛銃はサコー75改バーミンターの308、スコープは安物の軽量型、使用弾は激安弾の140gr弾銅頭挿げ替え弾でした。
急所をナミビアポイントに変更してからのケンさんは、300m遠射を含む殆どを即倒に出来る様になりました。正しく急所ヒットすれば弾のパワーに関係なく、即倒します。
ケンさんのスコープに比べ小山氏のスコープシステムは重量が数倍あると思われます。全依託で手に持たないで撃つと銃が振動し、ケンさんの銃でも反動で跳ね多少弾着が上にズレます。
銃にはバランスがあり、これは静的でも動的でも大切な事だと思っています。
また後述説明の様に、スコープベースの取付け強度も心配です。
動画の安定性にも問題があり、小山氏の動画はこのスコープを通した物やヘッドカメラは良いのですが、歩いている時の映像は水平が定まっておらず、見ていると乗り物酔い症状になってしまいます。
また発射の反動で映像が消えてしまい、被弾の瞬間が写っていないのも非常に残念です。
海外の良い動画はスコープからの映像もありますが、歩いている時はジャイロ付ハンディーカメラ、捕獲時の映像は三脚に固定された別のカメラの撮影がメインです。
近年はカメラの性能が上がり、スロー再生ではライフル弾の飛行によって出来た、空間の歪が写っている事もある程になりました。
もう少し解像度とスロー再生能力が上がれば、ケンさんのスロー再生特殊能力で見えたヒットした部分の毛が立ち、それが水面の波の様に周りに向かって広がって行く過程が写ると思います。
あれは実際に見えた映像ですから、絶対に事実だと思っています。第2波や第3波が発生し、それが広がって直径30㎝で消えて行く、詳細な様子を確認したい物です。
小山氏のスコープを通した映像では、その瞬間が反動で消えてしまっており、見えません。
命中精度に関するケンさんの仮説ですが、このスコープ部分が重過ぎると全体の振動条件が大きく変わり、弾着が乱れると思います。
そのせいかどうかは分りませんが、小山氏の動画の射撃は殆ど即倒していません。狙う急所を即倒率の高いナミビアポイントに換えるべきだと思います。
肉を求めるミートハンターではなくビッグトロフィーを求めるハンターですから、前足軸線上の背骨を撃って背ロースが少しダメージを受けても関係なく、ナミビアポイントを撃つべきだと思います。
即倒は一種の芸術ですから、それが上手く獲れれば動画の価値も上がると思われます。
ケンさんもナミビアポイント実用化前は超大物多数を未回収にしてしましたが、ナミビアポイントを実用化後は殆どを即倒出来、捕獲率が5倍に急増しました。
ナミビアポイントは他の急所に比べ即倒エリアが広く、周辺ヒットでも即倒してくれます。
ケンさん自身もこのナミビアポイントで前記の様な大きな成果を上げましたが、ケンさんスクールでも急所をナミビアポイントに変更してから、生徒による超大物捕獲が可能になりました。
銃に色々を架装する事は銃の精度やスナップショットやスイング特製に変化を生じ、捕獲率の低下を招くと思っており、ケンさんはその方向になる架装をする気はありません。

 レミントンとサコー
レミントンとサコー
更にレミントンを始めとする世界中の多くの銃はスコープマウントベースが3㎜級ネジ2本で取付けられています。ケンさんも設計者の端クレですが、アレでは十分である筈が無いと思っています。

 ミロクとルガー
ミロクとルガー
サコーはレシーバーの作り付けマウントで、しかも緩みが来ない様に前が広いテーパとなっています。
ミロクでは中ネジ4本に強化されており、ルガーも絶対に緩まない様に嵌め込み式になっています。
従来版小ネジタイプの緩む率は不明ですが緩む可能性がある様です。それに対する対策が各メーカーで行われ、それが増えているのです。ケンさんは小ネジ部分タイプが緩んだ例は3件見ました。
レミントン、ウインチェスター、サベージサボットで各1件で、共に標準クラスのスコープでした。
標準負荷でも緩む可能性があるのに、その負荷を数倍にしたら緩まない筈がないと言う事になります。
小山氏が未だにマグナムに拘っている点も気になります。
彼の愛用は7㎜レミントンマグの様ですが、マグナム弾は即倒効果も遠射効果もゼロであり、アフリカの大型動物でもエゾ鹿仕様308のバーンズ140gr銅弾を遥々持参して試しましたが、500㎏クラスの大型動物でも十分と言えました。
3.銃はバーミンター、口径は308。
散弾銃では「ショットガン効果」と言うのがあり、「1粒のパワーには概ね無関係な3粒被弾で撃墜」出来ました。無関係とは言え皮下に達しなければ無効弾になります。
同様にライフルの場合も似た様な部分があり、「急所に正しくヒットすれば、パワーには概ね無関係に即倒」しました。勿論エゾ鹿でも概ね100%即倒ですから、パワーは十分と言えマグナムは不要です。
この場合も当然ですが、数十㎝深さの急所まで届く必要があります。
心臓ポイントは動脈出口付近の狭い範囲にヒットしない限り即倒しません。

ナミビアポイントは銅弾でしか適用出来ませんが、即倒エリアが広く、実用性は抜群です。
即倒に必要な最低必要パワーの幅は相当広く、十分獲れているのであれば、口径の選択をとやかく言うつもりはありませんが、精度的には7㎜マグより308の方が優れています。
7㎜レミントンマグでベンチレスト射撃大会にチャンレンジする人は皆無ですが、100mハンタークラスと300mハンタークラスに308はしばしば入賞しています。
ケンさん自身も300mは全依託射撃であれば、概ね殆どを即倒可能です。
ナミビアでは450㎏クドウを380mにて308銅弾の初弾で即倒させる事が出来ました。
弾速が速い事でマグナムは落差補正的にはやや有利で、同じ落差で308の300mが350mまで延長出来る事は事実です。
しかし遠射は基本的に弾道の安定性が決め手となり、高速弾の遠射が有利になる事も殆ど無いのです。ケンさん自身初弾命中ではありませんが、ボス決定戦の超大物を540mから2発連続で2頭とも即倒させられました。308の弾道の安定性はかなり良好と言えました。
アメリカの長距離スナイパーの300ウインマグも220grの重量弾頭を使用しており、50BMG弾(12.7×99㎜ NATO)でも650gr重量弾頭を使い、1㎞以遠の遠射で使っています。
軽量高速弾より重量弾頭の方が遠距離射撃時の弾道性能は良い様です。
また308同士でも高速な150gr弾よりも、180gr重量弾の方が300m以遠では弾速も精度も上廻ります。
またバーミンターモデルの方が射撃は安定しており、レミントン700やルガー77のハンターモデル時は弾のメーカーを変えると弾着が変わりました。
しかしサコーバーミンターは海外にも持ち出し、現地製の弾を何時も使用していますが、何処の弾も弾着は変わらず、スコープ調整は12年間1度もしていません。
願わくばですが、ケンさんの助言が届き、小山氏の射撃は何時も「即倒」となり、その瞬間が上手くビデオに記録される事を願っています。
また角長1m怪物級エゾ鹿と500㎏のヒグマが獲れるとイイなと思っています。
4.牛の様な巨大鹿&珍鹿。
余談ですが、2002年に滝上でムース級の怪物鹿に会いました。距離は800m、サイズは牛クラス、角はそれ程ではありませんが、太い2段角で角の開きが水平に近い真っ黒な個体でした。
化石の世界の大角鹿かユーラシアンムースの末裔だったかも知れません。

写真はヘラ角にならないユーラシアンムースの若鹿です。
当時は望遠カメラを持っておらず、ライフルスコープの観察で角の生えている方向はこんな感じでしたが、もっと遥かに凄い老練な個体でした。
残念ながら翌年にはいなくなりました。1998年根室別当賀地区の太平洋側でも、概ね同等の牛の様に見えるムースの様なデカい鹿を見ました。この鹿も翌年以降は寿命なのか見掛けなくなりました。


金色の鬣のキリンの様な頭の鹿を見たのは、苫小牧石油タンク基地の近く、2012年の事でした。あれから10数年が過ぎ、寿命を迎えた頃かもです。
次は2010の根室だったと思いますが、朝1番オスばかり6頭の群を300mで出会いました。
群れの1頭はかなりの大物、残りは中型に見えました。
そこで1番大きなのを撃とうとスコープに捉えましたが、片角でした。
それで隣の中型に見えるのを撃ち即倒、回収してビックリ81㎝130㎏でした。
ならばあの片角は軽く95㎝超、200㎏越だった?
片角でも撃つべきだったと思いましたが、時すでに遅しでした。
翌年その近くで、体格が群を抜いた直線計測88㎝を捕獲したと、風の便りに聞きました。直線88㎝は実角長105㎝前後となります。
紋別スクール2007年の事でした。
100%即倒急所であるナミビアポイントを2006年に開拓、生徒にも指導しました。
そして85㎝は絶対と言う大物に出会い、150m強からD生徒に撃たせましたが、ナミビアポイントの指導をコロリと忘れ心臓を撃って未回収、数日間周辺を探しましたが、見付けられずに終わりました。
D生徒はその前年も運に恵まれず(迫力負けで足が地に着かず)、90㎝近いのを未回収にしています。その数年前にもボス決定戦の4頭を全て心臓撃ちで未回収、実はそれがナミビアポイント開拓に発展しました。
彼のベスト記録は角先欠がなければ81㎝で超大物達成でしたが、欠けていた為79㎝に留まりました。D生徒は公式記録に依れば25日参加で50頭捕獲とスクールで第2位の記録ですが、残念ながら超大物は捕獲出来ずでした。
日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育ち、20歳の時に狩猟免許を取得、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始しました。
1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後現地プロ(アシスタント)ハンティングガイドになり、1976年帰国、標津町で牧場を経営しながら、単独で山に入りハンティングを行なっていました。
ヒグマに悟られない様に自然の一部と化して歩を進め、5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃す事を信条としていたハンターでした。

1.どの様にして五感能力が桁違いのヒグマに10mまで接近するのか?
永い間ケンさんにもその手法は分かりませんでした。
分からなかったからこそ、それを凄いと思い、また尊敬していました。
久保氏はプロハンターを目指し、若くして名犬フチと出会いました。フチは稀に見る天才犬と言えました。しかし以後は猟犬に頼り切った普通のダメハンターになってしまいました。
彼の著書「羆撃ち」は確かの素晴らしい物がありましたが、それは彼が主役ではなく、「名犬フチ」の物語でした。
しかし猟犬の寿命は短く、著書の後半は「愛犬ロリコン物語」でした。彼はヒグマ猟その物が分かっていた訳でもなく、猟犬の育て方が分かっていた訳でもありませんでした。
2代目以降の名犬を育て「名人芸」を持続させたなら、彼は名人と言えました。
フチの2代目誕生を試みましたが、全く上手く行かずそこで早々と完全に諦めてしまいました。
「フチは名犬」でしたが、「久保氏は名人では無かった」のです。

彼の愛銃は「サコ―フィンベア338ウインチェスターマグナム)でした。
このサコ―を入手した時期の久保氏は狩猟方法がまだ定まっていなかったと思われます。
彼の信条である10m射撃ではスコープ後付銃はスコープと眼の位置が定まらず、大幅不利になりました。スコープ専用銃ならスナップショットで急所を捉える事は可能ですが、そのスコープ専用銃は20年後の1990年頃にデビューしました。
ライフル銃は本来100m以遠を高精度で撃つ銃であり、彼もその目的でスコープ銃を選択したと思われます。ストックと銃の機関部や銃身のベディングと言う絶妙な取付け調整や、引金切れ味追及の為のシアチューニングをしていました。
これらは高精度射撃を目的でなければ、殆ど無意味と言える行為でした。
そもそも10mでヒグマを確実に仕留めるのであれば、スコープ付ライフル銃がベストではありません。
ヒグマ猟も意識し、それで338ウインマグと言う口径を選んだ様ですが、ライフルの鉛弾頭は近距離射撃やブッシュ越射撃が不得意と言うより、鉛弾頭には重大な欠陥がありました。
近距離射撃・僅かなブッシュ越・骨ヒットで鉛が飛散してしまい、以後威力を失う大欠陥がありました。鉛弾の欠陥を少なくするには下記の様に2つの方法がありました。
1つ目はA型セパレータ付の弾頭で先端部は全飛散しても後半部がそのまま残る弾頭であり、2つ目は重量弾頭で弾速を落とし、更にラウンドノーズで飛散率を低減させる方法です。
彼は近距離時の鉛弾の重大な欠陥には全く触れていませんから、それを知らなかったと思われます。10mのヒグマ対戦には無垢のブレネッキスラグ弾がベストであると思います。
弾速からこの弾頭は鉛の飛散が余り起こらず、確実にヒグマを倒してくれます。また薄いブッシュであれば通過可能です。また近距離ヒグマ勝負を行う場合は、咄嗟の場合に銃を速やかに構える能力が不可欠になる筈ですが、彼の銃はスコープ後付け銃であり、眼の位置がスコープに合わず、これには不向きでした。
これが1990年頃から普及したスコープ専用銃や、また2000年頃から法律で決められた銅弾頭であれば、話が全く変わります。
スコープ専用銃はケンさん考案の新しい銃で指向するスナップ射撃が可能となり、肩に着ける前に命中する発砲が可能となり、スナップショットは得意項目になりました。
また銅弾頭は鉛の飛散が全く怒らず、これを利用して積極的に「骨の急所を撃つ事が可能」となりました。
久保氏は猟犬を使った猟を諦め、ドッグレスで山を歩き廻る様になり、やがて至近距離からヒグマ 勝負を挑む様になりました。
銃の世界も1980年頃になりますと、スコープ専用銃が出始めていました。
銃のパフォーマンスを上げ様と日々の工夫があれば、新しい猟具や技術に興味が行く筈ですが、彼はそうなりませんでした。そう言う方面に関心が薄いのが猟犬を使うハンターの特徴と言えました。
彼より3歳若いケンさんはドッグレス猟であり、1985年頃にはショットガンもライフルも独自のスナップ ショットを完成し、スコープ専用銃「ルガー77ボルトライフル」もデビュー後の程なくして購入しました。
鹿猟犬を頼った猟をする久保氏は猟具に関心が薄く、狩猟の道具も1975年頃から、銃もナイフも全く進化せず、若い頃のスコープ後付銃のサコ―フィンベアをそのままの形でずっと使い続けました。
ナイフで申すなら炭素鋼のナイフから進化せずでした。ケンさんのナイフは炭素鋼→ステンレス鋼→ダマスカス鋼と進化し、画期的と言える程に進化しました。
炭素鋼では鹿1頭目の後半から切れ味が大幅低下しました。
ステンレス鋼になりますと、メス2頭目までは良いのですが、3頭目で切れ味が低下しました。
それがダマスカス鋼になりますと、メス20頭を研がずに解体出来ました。
久保氏が掴んだヒグマとの接触方法の極意は、多分結果オーライの形で得られたのではないかと思います。それは何時もヒグマのいる地域を歩き、ヒグマに無害の人間であると思わせたのです。
本州に住み、シーズン数十日のみの狩猟をしていたケンさんには真似の出来ない手法ですが、地元に住んでいて、特定エリア内の年間数頭以下のヒグマを捕獲するのであれば、可能な方法と言えました。50年狩猟をしていて新たに分かった事の追加です。
その延長で考えますと、ケンさんもヒグマ捕獲を目的に行動開始し、5年目の2006年に1頭目を捕獲、翌年に2頭目と3頭目を捕獲しました。そして箱罠に依るヒグマ駆除が始まりました。
それまで箱罠駆除は行われていなかったので、多くのヒグマがパタパタ掛かりまして、過半のヒグマが捕獲され、ケンさん猟場のヒグマ生息数は半分以下となりました。
そして7年目の2014年、ヒグマの生息数も回復し、4頭目と5頭目のヒグマを捕獲、エースとなりました。そして2015年6頭目のヒグマを捕獲しました。
これもヒグマ側からすれば、ケンさんの車を猟場でよく見掛ける様になり、逃げなくなったのではないかと思える部分もありました。唯ケンさんの場合は50m先を走るヒグマが多かったと言う違いはあります。
久保氏はテレビ取材時に、50mでノーマークのエゾ鹿を立ち木に半委託射撃で撃ちました。
流石に半矢で逃げ出す事は無かったのですが、驚いた事に即死ではない射撃でした。
獲物を苦しめない彼の信条からすれば、また5~10mでヒグマを確実に即死させている事からすれば、信じられない下手糞な射撃でした。
その時代ではアメリカ帰りが珍しかった事、更に独自の子育て「大草原のみゆきちゃん」の取材を通し、マスコミに有名になり、「羆撃ち}も売れました。
ヒグマ70頭を捕獲したと言う説もありますが、彼自身は捕獲数を公表しておらず、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちではそこまで行っていないと思われます。
ケンさんが若い頃には仙人の様な凄い人だと尊敬していましたが、唯の猟犬ロリコンダメハンターでした。
2.小山氏の銃のバランス。
別の話ですが、長い間ケンさんは小山氏が北海道でNO.1のガイドであると思って尊敬して来ました。それはケンさんが1頭も捕獲出来なかった90㎝以上を相当数捕獲していたからです。
その小山氏が昨今は動画を多数投稿される様になり、それで気が付いた点があります。300m遠射が多いとは言え殆どが即倒していないのです。どうしてなのかを考えてみました。
因みにケンさんの300mは殆どが即倒の即死です。

写真は小山氏の愛銃:レミントン700、カスタムバレル、口径レミントン7㎜マグナム、スコープ4~16倍ビデオ機能付、重装備です。
ハンティング動画撮影に拘りを持っておられ、ネットにも多数投稿されています。
射撃精度にもかなり拘っておられる様で、モア精度のハンドロードで7㎜レミントンマグをカスタムバレルから撃っておられ、300mなら過半が即倒だと思うのですが、即倒していないのです。
狙撃が心臓狙いもあってか、小山氏の投稿動画でも即倒が殆どありません。ケンさんが見た投稿動画10本余で、即倒は1回だけで、何時も半矢捜索で数十~数百mで死んでいました。
未回収動画を公開する事は無いと思われ、即倒率は更に低いと思われます。
そして角サイズに拘りを持っておられ、300m前後のビッグトロフィー級狙いの遠射が主体です。
小山氏とケンさんと何が違うかと言えば、口径と急所とスコープです。
ケンさんの愛銃はサコー75改バーミンターの308、スコープは安物の軽量型、使用弾は激安弾の140gr弾銅頭挿げ替え弾でした。
急所をナミビアポイントに変更してからのケンさんは、300m遠射を含む殆どを即倒に出来る様になりました。正しく急所ヒットすれば弾のパワーに関係なく、即倒します。
ケンさんのスコープに比べ小山氏のスコープシステムは重量が数倍あると思われます。全依託で手に持たないで撃つと銃が振動し、ケンさんの銃でも反動で跳ね多少弾着が上にズレます。
銃にはバランスがあり、これは静的でも動的でも大切な事だと思っています。
また後述説明の様に、スコープベースの取付け強度も心配です。
動画の安定性にも問題があり、小山氏の動画はこのスコープを通した物やヘッドカメラは良いのですが、歩いている時の映像は水平が定まっておらず、見ていると乗り物酔い症状になってしまいます。
また発射の反動で映像が消えてしまい、被弾の瞬間が写っていないのも非常に残念です。
海外の良い動画はスコープからの映像もありますが、歩いている時はジャイロ付ハンディーカメラ、捕獲時の映像は三脚に固定された別のカメラの撮影がメインです。
近年はカメラの性能が上がり、スロー再生ではライフル弾の飛行によって出来た、空間の歪が写っている事もある程になりました。
もう少し解像度とスロー再生能力が上がれば、ケンさんのスロー再生特殊能力で見えたヒットした部分の毛が立ち、それが水面の波の様に周りに向かって広がって行く過程が写ると思います。
あれは実際に見えた映像ですから、絶対に事実だと思っています。第2波や第3波が発生し、それが広がって直径30㎝で消えて行く、詳細な様子を確認したい物です。
小山氏のスコープを通した映像では、その瞬間が反動で消えてしまっており、見えません。
命中精度に関するケンさんの仮説ですが、このスコープ部分が重過ぎると全体の振動条件が大きく変わり、弾着が乱れると思います。
そのせいかどうかは分りませんが、小山氏の動画の射撃は殆ど即倒していません。狙う急所を即倒率の高いナミビアポイントに換えるべきだと思います。
肉を求めるミートハンターではなくビッグトロフィーを求めるハンターですから、前足軸線上の背骨を撃って背ロースが少しダメージを受けても関係なく、ナミビアポイントを撃つべきだと思います。
即倒は一種の芸術ですから、それが上手く獲れれば動画の価値も上がると思われます。
ケンさんもナミビアポイント実用化前は超大物多数を未回収にしてしましたが、ナミビアポイントを実用化後は殆どを即倒出来、捕獲率が5倍に急増しました。
ナミビアポイントは他の急所に比べ即倒エリアが広く、周辺ヒットでも即倒してくれます。
ケンさん自身もこのナミビアポイントで前記の様な大きな成果を上げましたが、ケンさんスクールでも急所をナミビアポイントに変更してから、生徒による超大物捕獲が可能になりました。
銃に色々を架装する事は銃の精度やスナップショットやスイング特製に変化を生じ、捕獲率の低下を招くと思っており、ケンさんはその方向になる架装をする気はありません。

 レミントンとサコー
レミントンとサコー更にレミントンを始めとする世界中の多くの銃はスコープマウントベースが3㎜級ネジ2本で取付けられています。ケンさんも設計者の端クレですが、アレでは十分である筈が無いと思っています。

 ミロクとルガー
ミロクとルガーサコーはレシーバーの作り付けマウントで、しかも緩みが来ない様に前が広いテーパとなっています。
ミロクでは中ネジ4本に強化されており、ルガーも絶対に緩まない様に嵌め込み式になっています。
従来版小ネジタイプの緩む率は不明ですが緩む可能性がある様です。それに対する対策が各メーカーで行われ、それが増えているのです。ケンさんは小ネジ部分タイプが緩んだ例は3件見ました。
レミントン、ウインチェスター、サベージサボットで各1件で、共に標準クラスのスコープでした。
標準負荷でも緩む可能性があるのに、その負荷を数倍にしたら緩まない筈がないと言う事になります。
小山氏が未だにマグナムに拘っている点も気になります。
彼の愛用は7㎜レミントンマグの様ですが、マグナム弾は即倒効果も遠射効果もゼロであり、アフリカの大型動物でもエゾ鹿仕様308のバーンズ140gr銅弾を遥々持参して試しましたが、500㎏クラスの大型動物でも十分と言えました。
3.銃はバーミンター、口径は308。
散弾銃では「ショットガン効果」と言うのがあり、「1粒のパワーには概ね無関係な3粒被弾で撃墜」出来ました。無関係とは言え皮下に達しなければ無効弾になります。
同様にライフルの場合も似た様な部分があり、「急所に正しくヒットすれば、パワーには概ね無関係に即倒」しました。勿論エゾ鹿でも概ね100%即倒ですから、パワーは十分と言えマグナムは不要です。
この場合も当然ですが、数十㎝深さの急所まで届く必要があります。
心臓ポイントは動脈出口付近の狭い範囲にヒットしない限り即倒しません。

ナミビアポイントは銅弾でしか適用出来ませんが、即倒エリアが広く、実用性は抜群です。
即倒に必要な最低必要パワーの幅は相当広く、十分獲れているのであれば、口径の選択をとやかく言うつもりはありませんが、精度的には7㎜マグより308の方が優れています。
7㎜レミントンマグでベンチレスト射撃大会にチャンレンジする人は皆無ですが、100mハンタークラスと300mハンタークラスに308はしばしば入賞しています。
ケンさん自身も300mは全依託射撃であれば、概ね殆どを即倒可能です。
ナミビアでは450㎏クドウを380mにて308銅弾の初弾で即倒させる事が出来ました。
弾速が速い事でマグナムは落差補正的にはやや有利で、同じ落差で308の300mが350mまで延長出来る事は事実です。
しかし遠射は基本的に弾道の安定性が決め手となり、高速弾の遠射が有利になる事も殆ど無いのです。ケンさん自身初弾命中ではありませんが、ボス決定戦の超大物を540mから2発連続で2頭とも即倒させられました。308の弾道の安定性はかなり良好と言えました。
アメリカの長距離スナイパーの300ウインマグも220grの重量弾頭を使用しており、50BMG弾(12.7×99㎜ NATO)でも650gr重量弾頭を使い、1㎞以遠の遠射で使っています。
軽量高速弾より重量弾頭の方が遠距離射撃時の弾道性能は良い様です。
また308同士でも高速な150gr弾よりも、180gr重量弾の方が300m以遠では弾速も精度も上廻ります。
またバーミンターモデルの方が射撃は安定しており、レミントン700やルガー77のハンターモデル時は弾のメーカーを変えると弾着が変わりました。
しかしサコーバーミンターは海外にも持ち出し、現地製の弾を何時も使用していますが、何処の弾も弾着は変わらず、スコープ調整は12年間1度もしていません。
願わくばですが、ケンさんの助言が届き、小山氏の射撃は何時も「即倒」となり、その瞬間が上手くビデオに記録される事を願っています。
また角長1m怪物級エゾ鹿と500㎏のヒグマが獲れるとイイなと思っています。
4.牛の様な巨大鹿&珍鹿。
余談ですが、2002年に滝上でムース級の怪物鹿に会いました。距離は800m、サイズは牛クラス、角はそれ程ではありませんが、太い2段角で角の開きが水平に近い真っ黒な個体でした。
化石の世界の大角鹿かユーラシアンムースの末裔だったかも知れません。

写真はヘラ角にならないユーラシアンムースの若鹿です。
当時は望遠カメラを持っておらず、ライフルスコープの観察で角の生えている方向はこんな感じでしたが、もっと遥かに凄い老練な個体でした。
残念ながら翌年にはいなくなりました。1998年根室別当賀地区の太平洋側でも、概ね同等の牛の様に見えるムースの様なデカい鹿を見ました。この鹿も翌年以降は寿命なのか見掛けなくなりました。
金色の鬣のキリンの様な頭の鹿を見たのは、苫小牧石油タンク基地の近く、2012年の事でした。あれから10数年が過ぎ、寿命を迎えた頃かもです。
次は2010の根室だったと思いますが、朝1番オスばかり6頭の群を300mで出会いました。
群れの1頭はかなりの大物、残りは中型に見えました。
そこで1番大きなのを撃とうとスコープに捉えましたが、片角でした。
それで隣の中型に見えるのを撃ち即倒、回収してビックリ81㎝130㎏でした。
ならばあの片角は軽く95㎝超、200㎏越だった?
片角でも撃つべきだったと思いましたが、時すでに遅しでした。
翌年その近くで、体格が群を抜いた直線計測88㎝を捕獲したと、風の便りに聞きました。直線88㎝は実角長105㎝前後となります。
紋別スクール2007年の事でした。
100%即倒急所であるナミビアポイントを2006年に開拓、生徒にも指導しました。
そして85㎝は絶対と言う大物に出会い、150m強からD生徒に撃たせましたが、ナミビアポイントの指導をコロリと忘れ心臓を撃って未回収、数日間周辺を探しましたが、見付けられずに終わりました。
D生徒はその前年も運に恵まれず(迫力負けで足が地に着かず)、90㎝近いのを未回収にしています。その数年前にもボス決定戦の4頭を全て心臓撃ちで未回収、実はそれがナミビアポイント開拓に発展しました。
彼のベスト記録は角先欠がなければ81㎝で超大物達成でしたが、欠けていた為79㎝に留まりました。D生徒は公式記録に依れば25日参加で50頭捕獲とスクールで第2位の記録ですが、残念ながら超大物は捕獲出来ずでした。
2024年05月20日
50年間で分かった事、その9:ドッグレス猟こそ究極の猟でした。
35.本州鹿巻狩りは射撃勝負ではなく、気配先取り勝負だった。
36.丸見えの場所で見張りを辞め、微動もしないで待つ「禅の心作戦」は有効だった。
37.本州鹿は季節的な移動をしないが、流し猟が可能だった。
連続敗戦70余日:ケンさんは出会いの多かったカモ猟では順調に腕を上げる事が出来ました。本州鹿巻狩りで9シーズン70余日の連続敗戦、出会いゼロでした。
カモ猟の経験から、野性鳥獣の五感は桁外れである事は知っているつもりでしたが、認識はそれでも甘く、ケンさんは「気配や殺気」を撒き散らしており、ケンさんの視界内に現れる鹿は9シーズン皆無でした。勿論その間に何もしなかった訳ではなく、試行錯誤を繰り返していました。
初捕獲当日は「改善案」がネタ切れ、「絶対に獲れる筈がない」と日当たりの良い場所で「フテ寝」をしておりました。その結果、「気配や殺気」が低下し、鹿はケンさんの存在に気が付かず、射程内までやって来ました。
そして今まで自分の気配の陰で、気が付かなかった鹿の気配にフト気が付き、目を開ければ鹿は間もなくケンさんの射程内でした。こうして初捕獲成功となりました。
禅の心作戦:後刻これを分析し「禅の心作戦」が出来上がり、本州鹿の巻狩りに開眼しました。
その結果、あれ程獲れなかった本州鹿ですが、3週連続で3段角の捕獲に成功、作戦は正しかった事が立証出来ました。
従来は「気配や殺気」を撒き散らしていました。
それは来たら「ブッ殺してくれましょう」としていましたし、速やかに撃てる様に「物陰から見張り」をしていました。考えた結果、「物陰からの見張りを辞めました。」
鹿の目は左右に付いており、両目で見ていませんから、動かなければ発見される事は絶対にありません。これは後刻2度試してみましたが、2mと5mまで引き寄せる事が出来ました。
1度逃げた本州鹿は勝手の分かった元の山に戻って来る習性があります。
そして獲物が1度遠ざかり1時間後位でこちらに向かい始めたと思われる頃から、正味30~60分だけ微動もせず、眼を閉じ丸見えの所で見張りをせずに待つと言う作戦でした。
鹿が近付けば、自分の気配が低下しており、鹿接近は自動的に分かりました。
今までは見張りをするから鹿に感付かれていたのでした。
本州鹿の流し猟:本州鹿も昨今の繁殖は著しく、流し猟も可能だろうと思っていましたが、山口のU生徒がこれを立証してくれました。
彼に依れば、出掛ければ出会いの無い日は殆ど無く、概ね1日当たり1~2頭の捕獲が可能と言う物でした。場所は山裾の耕作放棄地周辺、時間は朝夕と言う事でした。
距離は50m前後が多いそうですから、捕獲効率を上げるなら4号バックショット27粒弾の連射です。エゾ鹿猟の練習であればスコープ付ボルト銃です。
エゾ鹿猟の前半を予め「本州鹿の流し用」で体験しておけば、現地10回の基礎失敗の前半部を本州で体験出来、初回遠征猟の成功率を大幅に上げる事が可能となります。
38.エゾ鹿猟は世界的に桁違いの良環境だった。
39.ドッグレスは最高の猟であった。
エゾ鹿は本州鹿の2倍以上の最大150㎏を超える体重があり、最大90㎝に迫る大きな角があり、しかも肉が美味しいと言う3拍子が揃っています。
 ケンさん86㎝。
ケンさん86㎝。
 U生徒88㎝
U生徒88㎝
写真は角長86㎝、体重150㎏、2002年の紋別で捕獲しました。比較的新しい所ではU生徒が紋別スクールで2016年に85㎝、2017年に88㎝を捕獲しています。


ケンさんスクールでは1日5日の出会いと2頭の捕獲があり、0.5頭の大物が含まれていました。
狩猟先進国アメリカでは写真の「ホワイトテール鹿」と「ミュール鹿」がいますが、サイズはエゾ鹿クラスです。

ケンさんスクールでは2週間も猟をすれば、写真の様になりますが、アメリカでは狩猟期間は1ケ月・定数はシーズンで1頭・メスは禁猟です。
これを捕獲するガイド猟は1日1000㌦、1000ドル払っても捕獲の保証はありません。
それで飛行機代を払って物価の安いNZまで満州産の「シカディア」を捕獲する1式5000㌦のツアーがある程です。こちらは概ね100%の捕獲率です。
シカディアは日本鹿の事を言い、NZの鹿は概ね「満州産のエゾ鹿」です。
1000㌦は15万円ですが、日本のエゾ鹿はその半分以下の金額で狩猟が出来ます。
ケンさんスクールでは1日6万円でした。シーズンは3ケ月以上、定数は無く獲り放題、最高記録は5日猟で19頭、15頭越の記録はたくさんありました。同じ地球上で何と言う大きな差なのでしょう。
本州鹿巻狩りではそれに比べますと0.05頭/日人、比較になりませんが、アメリカの狩猟とは良い勝負と言えました。
その本州鹿も近年は流し猟が可能になって来ました。
ケンさんスクールでは16年間のエゾ鹿猟で捕獲ゼロはありませんが、捕獲までには10回の基礎失敗が必要でした。スクールでは4日日程で3日猟が可能、1日5回の出会いから2日で失敗10回を終了、3日目には例外は無く、初捕獲が達成されました。
この様な体制が出来る所は他にありません。
巷では通常4日日程で2日猟、出会いはケンさんスクールの半分前後しかなく、基礎10回を達成しない内に日程終了、捕獲は未達成で2年目以降に持ち越されます。
基礎失敗10回の内、前半は 本州鹿の流し猟でも体験出来ますから、違いの獲物の大きさと射程距離100mの2項目です。
週末に通える本州鹿の流し猟4日程度の経験と並行して100m5㎝の射撃技術取得の後に、北海道有料猟区に向かえば、恐らく全員が初遠征でエゾ鹿捕獲に成功すると思われます。
そんな風に本州猟 流し猟からエゾ鹿流し猟へのシステムを作る事が出来ればイイなと、ケンさんは思っております。
実戦では「5秒で鹿が逃げ出し」ますから、「スナップショット」の技術が不可欠となります。
また100mで5㎝の射撃技術も、単に射撃場通いをして射撃に慣れれば、得られる物ではありません。「銃だけに撃たせるトレーニング」が必要なのです。
更に銃の照準ブレを押さえる為には半委託射撃や全依託射撃が必要になります。
実戦射撃とは瞬時に周りの物を利用して射撃を安定させるテクニックが必要です。


左は主に150m射撃用の半委託射撃です。ケンさんはこれで最大380mのナミビアのクドゥを捕獲しました。右は主に300m遠射やワンホール射撃を狙う時に使う全依託射撃です。
300mは外れる気が起こらず、540mのエゾ鹿を2頭連続で即倒させた時もこの射撃を使いました。
ドッグレスは最高の猟だった:ケンさんが狩猟を始めたのは1970年。国内狩猟ブームの終わりが近くなった頃でした。
当時は洋犬の猟犬を連れて自動銃を持ち、頭にはハンチング帽、赤いウールのチェックのシャツを着て、革製 チョッキを着て、足には軽量地下足袋でキジ猟或いはヤマドリ猟を行う、そんな猟が主体でした。
当時は肩付けから始まるスナップショットの時代、銃はスキート射撃の様に下から肩に滑り込ませました。肩付けが安定して出来る様に厚着はダメ、皮のチョッキが不可欠でした。
狩猟が上手くなる為には「1に犬」、猟果は猟犬の能力次第でした。「2に足」、これは猟場を歩き廻り、獲物のいる所を知っていなければと言う意味でした。「3番目にやっと銃」が出て来ました。
 村田銃
村田銃
 SKBローヤル水平2連銃
SKBローヤル水平2連銃
銃は1960年頃まではボルト単発の村田銃、1970年頃までは水平2連銃、1970年を過ぎると自動銃が主流となりました。村田銃時代には装弾の販売は無く、全員が黒色火薬で手詰めの時代でした。
村田銃は1980年の村田13年式軍用銃が基本となりますが、民間製も同時に出廻り、町の銃砲店製も多数が出廻りました。
オリジナルは30番村田口径、76番(7.6㎜)・410~8番まで各種の新銃が製造されました。
明治後半には旧式となった村田軍用銃も猟銃に改造され払い下げ販売されました。
真鍮薬莢手詰め、火薬消費の少ない30番前後が好まれ、雷管も紙火薬で再生されていました。
やがて水平2連銃になりますと殆どが12番紙薬莢となり、装弾は1965年前後にはメーカー製装弾が製造される様になりましたが、紙薬莢や黒色火薬で手詰め愛好者もまだ残っておりました。
紙薬莢も最大10回ほど使えたと言う事で、すぐに張り付いて抜けなくなり真鍮薬莢より好評だったと聞きますが、20番紙薬莢はありましたが、他の口径は真鍮薬莢だけでした。
当時は洋猟犬を使ったキジ猟や山鳥猟が狩猟の主体でした。
猟犬を使う理由は野性鳥獣の圧倒的な五感と体力の差にありました。
猟犬は野性鳥獣に準じた能力を持っており、これを味方にすれば有能な部下になる事は十分に考えられます。それは良いのですが、全て猟犬頼みの狩猟をする様になり、本人が努力しなくなってしまうのが欠点と言えました。
ケンさんは不利を承知でドッグレスコースのカモ猟とエゾ鹿猟を選びました。その結果、野性鳥獣の習性をしっかり勉強すれば、猟犬を使った狩猟よりも遥かに桁違いの出会いが可能となりました。
今日の天気で今の時間なら何処に行けば獲物に会えるかが分かって来まして「ポイント猟」言う手法が可能となりました。
また出会いを有効に行かそうと、新しい各種射撃方法を開拓した結果、従来法に比べ、圧倒的に優れ且つ安全な手法を開拓出来、勿論それなりの猟果を上げる事が出来ました。
水面に落としたカモはどうするのか? カモを希望の方向に飛ばせ、回収が楽なエリアに撃墜、長靴不要でした。半矢追跡はどうするのか? 半矢にならない様に撃ちましたので追跡は殆どありません。
猟犬ハンターからすればその様な事が出来るのか? 彼らの「常識」からは「嘘もイイ加減にしなさい」となりますが、全て出来る様になった後には簡単な事でした。
散弾銃もライフル銃もフリンチングを克服して「究め」ますと非常に良く当たり、散弾銃は「3粒被弾撃墜のショットガン効果」を使うと従来のベテランより1桁撃墜率が向上しました。
害鳥駆除では多くの猟友会員が見ています。
エゾ鹿は群れでおり、1頭を即倒させれば残りは走って逃げます。
ライフルのランニング射撃は通常不可能とされています。ライフル銃で150mを撃つ時には止まっている鹿でも高難度と言えます。
それからすれば走っている鹿にマグレ以外当たる筈がないと言う事になりますが、スイング中のライフル銃はジャイロ効果で安定し想像以上によく当たりました。
 5発5中
5発5中
初弾で70%が即倒、5発で3頭以上が獲れました。
ケンさん自身まさかこれ程までとは思いませんでしたが、鹿肉大量注文とビッグフィーバーが重なり、1日に10頭捕獲が5日連続となり、5発5中もその間に3度達成し、もはや絶対にマグレで無い事の立証となりました。
結論的に言えば、ドッグレス猟だからこれ程の高い所まで上がれたのです。
ケンさん自身最初の10年は9年目の1頭だけでした。
それが末期には1日で10頭、しかもマグレではありません。ドッグ猟を続けている自称ベテランハンターからすれば2桁違いは絶対に信じられず、「嘘もイイ加減にしなさい」と言える程の大差が付いてしまったのです。
勿論言うまでも無く、本当の実績値です。
ケンさんの人生も仕事も不可能への挑戦でした。
ドッグレス猟も不可能への挑戦でした。
そう言う運命だったのか、偶然だったのかどうかは分かりませんが、相性は良く「ドッグレス猟こそ、最高の狩猟だった」と言えました。
ケンさんの不可能に挑戦する合理化努力は、当初自衛の為でありましたが、やがてそれが仕事にも使える事に気が付きました。ケンさんが担当すると特に悪戦苦闘する事も無く、全戦全勝で「不可能が可能」になりました。何時しか不可能を可能に変える「伝説の男」と言う事になってしまいました。
自前会社設立時も当初はどの様にして利益を得るのかと言う著しく不利な環境でした。
下請け的な仕事も大変だなと思いました。
しかし合理化を進めますと僅か半年で能率10倍が達成され、当初不利に思えた契約内容でもかなり大きな利益が上がる様になりました。
これも自らが作業するとなれば、たくさんの仕事をしても疲れない様にして、如何にして楽をするのが目的でしたが、パートのおばさんに教え込むとケンさんの能率の80%以上が再現出来ました。
やがて下請け的な仕事から手を引き、自前の仕事としました。
ランクルを改造申請する会社であり、小型トレーラーを製造販売する会社でした。こちらは支払いが非常に少ないのでもっと儲かりました。
それも従業員がやってくれる様になりまして、結局ケンさんは何もしないでも収入があると言う有難い環境となり、狩猟を堪能出来ました。
本州鹿猟では初めて本格的悪戦苦闘をしました。
9年目まで全く獲れず、「当初の10年間では9年目の1頭だけ」でした。
やがて「禅の心作戦」を考案、銃を向けるだけで命中する「新スナップショット」、 リード自動調整の「ショットガン版スイング射撃」を開拓、「バックショット専用銃」を考案しました。
捕獲率は10倍以上に向上、更にエゾ鹿猟メインに変更、天気や諸条件等を考えてそこに行けば鹿に出会える「ポイント猟」を開拓、「次の10年間には100頭」を捕獲出来ました。
更に2002年ワンホール射撃達成後間もなくの2006年、ライフル射撃に開眼、「ライフル版のスナップショット」「ライフル版のスイング射撃」によるランニング射撃にも開眼しました。
ベスト記録は「5日間に50頭」を捕獲、この中には「5発5中」が3度達成される等々、1度のチャンスから複数頭を捕獲出来る様になり、「3度目の10年間には海外猟を含め1000頭」を達成出来ました。
かなり苦労しましたが、狩猟に於いては「ポイント猟」の開拓で、獲物との出会いを圧倒的に多く出来、且つ超大物との出会率も圧倒的に高くなりました。
射撃に於きましては「スナップショット」で圧倒的に速く正確に構え発砲出来る様になり、「銃だけに撃たせる」事により、射撃精度も大幅に向上、150mワンホール射撃や300m以遠の遠射を可能とし、また「スイング射撃」により、従来は不可能とされていた走る鹿の連続ヒットも可能となりました。
結果的に「狩猟にも射撃にも大幅合理化は可能だった」と言えました。
36.丸見えの場所で見張りを辞め、微動もしないで待つ「禅の心作戦」は有効だった。
37.本州鹿は季節的な移動をしないが、流し猟が可能だった。
連続敗戦70余日:ケンさんは出会いの多かったカモ猟では順調に腕を上げる事が出来ました。本州鹿巻狩りで9シーズン70余日の連続敗戦、出会いゼロでした。
カモ猟の経験から、野性鳥獣の五感は桁外れである事は知っているつもりでしたが、認識はそれでも甘く、ケンさんは「気配や殺気」を撒き散らしており、ケンさんの視界内に現れる鹿は9シーズン皆無でした。勿論その間に何もしなかった訳ではなく、試行錯誤を繰り返していました。
初捕獲当日は「改善案」がネタ切れ、「絶対に獲れる筈がない」と日当たりの良い場所で「フテ寝」をしておりました。その結果、「気配や殺気」が低下し、鹿はケンさんの存在に気が付かず、射程内までやって来ました。
そして今まで自分の気配の陰で、気が付かなかった鹿の気配にフト気が付き、目を開ければ鹿は間もなくケンさんの射程内でした。こうして初捕獲成功となりました。
禅の心作戦:後刻これを分析し「禅の心作戦」が出来上がり、本州鹿の巻狩りに開眼しました。
その結果、あれ程獲れなかった本州鹿ですが、3週連続で3段角の捕獲に成功、作戦は正しかった事が立証出来ました。
従来は「気配や殺気」を撒き散らしていました。
それは来たら「ブッ殺してくれましょう」としていましたし、速やかに撃てる様に「物陰から見張り」をしていました。考えた結果、「物陰からの見張りを辞めました。」
鹿の目は左右に付いており、両目で見ていませんから、動かなければ発見される事は絶対にありません。これは後刻2度試してみましたが、2mと5mまで引き寄せる事が出来ました。
1度逃げた本州鹿は勝手の分かった元の山に戻って来る習性があります。
そして獲物が1度遠ざかり1時間後位でこちらに向かい始めたと思われる頃から、正味30~60分だけ微動もせず、眼を閉じ丸見えの所で見張りをせずに待つと言う作戦でした。
鹿が近付けば、自分の気配が低下しており、鹿接近は自動的に分かりました。
今までは見張りをするから鹿に感付かれていたのでした。
本州鹿の流し猟:本州鹿も昨今の繁殖は著しく、流し猟も可能だろうと思っていましたが、山口のU生徒がこれを立証してくれました。
彼に依れば、出掛ければ出会いの無い日は殆ど無く、概ね1日当たり1~2頭の捕獲が可能と言う物でした。場所は山裾の耕作放棄地周辺、時間は朝夕と言う事でした。
距離は50m前後が多いそうですから、捕獲効率を上げるなら4号バックショット27粒弾の連射です。エゾ鹿猟の練習であればスコープ付ボルト銃です。
エゾ鹿猟の前半を予め「本州鹿の流し用」で体験しておけば、現地10回の基礎失敗の前半部を本州で体験出来、初回遠征猟の成功率を大幅に上げる事が可能となります。
38.エゾ鹿猟は世界的に桁違いの良環境だった。
39.ドッグレスは最高の猟であった。
エゾ鹿は本州鹿の2倍以上の最大150㎏を超える体重があり、最大90㎝に迫る大きな角があり、しかも肉が美味しいと言う3拍子が揃っています。
 U生徒88㎝
U生徒88㎝写真は角長86㎝、体重150㎏、2002年の紋別で捕獲しました。比較的新しい所ではU生徒が紋別スクールで2016年に85㎝、2017年に88㎝を捕獲しています。


ケンさんスクールでは1日5日の出会いと2頭の捕獲があり、0.5頭の大物が含まれていました。
狩猟先進国アメリカでは写真の「ホワイトテール鹿」と「ミュール鹿」がいますが、サイズはエゾ鹿クラスです。

ケンさんスクールでは2週間も猟をすれば、写真の様になりますが、アメリカでは狩猟期間は1ケ月・定数はシーズンで1頭・メスは禁猟です。
これを捕獲するガイド猟は1日1000㌦、1000ドル払っても捕獲の保証はありません。
それで飛行機代を払って物価の安いNZまで満州産の「シカディア」を捕獲する1式5000㌦のツアーがある程です。こちらは概ね100%の捕獲率です。
シカディアは日本鹿の事を言い、NZの鹿は概ね「満州産のエゾ鹿」です。
1000㌦は15万円ですが、日本のエゾ鹿はその半分以下の金額で狩猟が出来ます。
ケンさんスクールでは1日6万円でした。シーズンは3ケ月以上、定数は無く獲り放題、最高記録は5日猟で19頭、15頭越の記録はたくさんありました。同じ地球上で何と言う大きな差なのでしょう。
本州鹿巻狩りではそれに比べますと0.05頭/日人、比較になりませんが、アメリカの狩猟とは良い勝負と言えました。
その本州鹿も近年は流し猟が可能になって来ました。
ケンさんスクールでは16年間のエゾ鹿猟で捕獲ゼロはありませんが、捕獲までには10回の基礎失敗が必要でした。スクールでは4日日程で3日猟が可能、1日5回の出会いから2日で失敗10回を終了、3日目には例外は無く、初捕獲が達成されました。
この様な体制が出来る所は他にありません。
巷では通常4日日程で2日猟、出会いはケンさんスクールの半分前後しかなく、基礎10回を達成しない内に日程終了、捕獲は未達成で2年目以降に持ち越されます。
基礎失敗10回の内、前半は 本州鹿の流し猟でも体験出来ますから、違いの獲物の大きさと射程距離100mの2項目です。
週末に通える本州鹿の流し猟4日程度の経験と並行して100m5㎝の射撃技術取得の後に、北海道有料猟区に向かえば、恐らく全員が初遠征でエゾ鹿捕獲に成功すると思われます。
そんな風に本州猟 流し猟からエゾ鹿流し猟へのシステムを作る事が出来ればイイなと、ケンさんは思っております。
実戦では「5秒で鹿が逃げ出し」ますから、「スナップショット」の技術が不可欠となります。
また100mで5㎝の射撃技術も、単に射撃場通いをして射撃に慣れれば、得られる物ではありません。「銃だけに撃たせるトレーニング」が必要なのです。
更に銃の照準ブレを押さえる為には半委託射撃や全依託射撃が必要になります。
実戦射撃とは瞬時に周りの物を利用して射撃を安定させるテクニックが必要です。


左は主に150m射撃用の半委託射撃です。ケンさんはこれで最大380mのナミビアのクドゥを捕獲しました。右は主に300m遠射やワンホール射撃を狙う時に使う全依託射撃です。
300mは外れる気が起こらず、540mのエゾ鹿を2頭連続で即倒させた時もこの射撃を使いました。
ドッグレスは最高の猟だった:ケンさんが狩猟を始めたのは1970年。国内狩猟ブームの終わりが近くなった頃でした。
当時は洋犬の猟犬を連れて自動銃を持ち、頭にはハンチング帽、赤いウールのチェックのシャツを着て、革製 チョッキを着て、足には軽量地下足袋でキジ猟或いはヤマドリ猟を行う、そんな猟が主体でした。
当時は肩付けから始まるスナップショットの時代、銃はスキート射撃の様に下から肩に滑り込ませました。肩付けが安定して出来る様に厚着はダメ、皮のチョッキが不可欠でした。
狩猟が上手くなる為には「1に犬」、猟果は猟犬の能力次第でした。「2に足」、これは猟場を歩き廻り、獲物のいる所を知っていなければと言う意味でした。「3番目にやっと銃」が出て来ました。
 村田銃
村田銃 SKBローヤル水平2連銃
SKBローヤル水平2連銃銃は1960年頃まではボルト単発の村田銃、1970年頃までは水平2連銃、1970年を過ぎると自動銃が主流となりました。村田銃時代には装弾の販売は無く、全員が黒色火薬で手詰めの時代でした。
村田銃は1980年の村田13年式軍用銃が基本となりますが、民間製も同時に出廻り、町の銃砲店製も多数が出廻りました。
オリジナルは30番村田口径、76番(7.6㎜)・410~8番まで各種の新銃が製造されました。
明治後半には旧式となった村田軍用銃も猟銃に改造され払い下げ販売されました。
真鍮薬莢手詰め、火薬消費の少ない30番前後が好まれ、雷管も紙火薬で再生されていました。
やがて水平2連銃になりますと殆どが12番紙薬莢となり、装弾は1965年前後にはメーカー製装弾が製造される様になりましたが、紙薬莢や黒色火薬で手詰め愛好者もまだ残っておりました。
紙薬莢も最大10回ほど使えたと言う事で、すぐに張り付いて抜けなくなり真鍮薬莢より好評だったと聞きますが、20番紙薬莢はありましたが、他の口径は真鍮薬莢だけでした。
当時は洋猟犬を使ったキジ猟や山鳥猟が狩猟の主体でした。
猟犬を使う理由は野性鳥獣の圧倒的な五感と体力の差にありました。
猟犬は野性鳥獣に準じた能力を持っており、これを味方にすれば有能な部下になる事は十分に考えられます。それは良いのですが、全て猟犬頼みの狩猟をする様になり、本人が努力しなくなってしまうのが欠点と言えました。
ケンさんは不利を承知でドッグレスコースのカモ猟とエゾ鹿猟を選びました。その結果、野性鳥獣の習性をしっかり勉強すれば、猟犬を使った狩猟よりも遥かに桁違いの出会いが可能となりました。
今日の天気で今の時間なら何処に行けば獲物に会えるかが分かって来まして「ポイント猟」言う手法が可能となりました。
また出会いを有効に行かそうと、新しい各種射撃方法を開拓した結果、従来法に比べ、圧倒的に優れ且つ安全な手法を開拓出来、勿論それなりの猟果を上げる事が出来ました。
水面に落としたカモはどうするのか? カモを希望の方向に飛ばせ、回収が楽なエリアに撃墜、長靴不要でした。半矢追跡はどうするのか? 半矢にならない様に撃ちましたので追跡は殆どありません。
猟犬ハンターからすればその様な事が出来るのか? 彼らの「常識」からは「嘘もイイ加減にしなさい」となりますが、全て出来る様になった後には簡単な事でした。
散弾銃もライフル銃もフリンチングを克服して「究め」ますと非常に良く当たり、散弾銃は「3粒被弾撃墜のショットガン効果」を使うと従来のベテランより1桁撃墜率が向上しました。
害鳥駆除では多くの猟友会員が見ています。
エゾ鹿は群れでおり、1頭を即倒させれば残りは走って逃げます。
ライフルのランニング射撃は通常不可能とされています。ライフル銃で150mを撃つ時には止まっている鹿でも高難度と言えます。
それからすれば走っている鹿にマグレ以外当たる筈がないと言う事になりますが、スイング中のライフル銃はジャイロ効果で安定し想像以上によく当たりました。
 5発5中
5発5中初弾で70%が即倒、5発で3頭以上が獲れました。
ケンさん自身まさかこれ程までとは思いませんでしたが、鹿肉大量注文とビッグフィーバーが重なり、1日に10頭捕獲が5日連続となり、5発5中もその間に3度達成し、もはや絶対にマグレで無い事の立証となりました。
結論的に言えば、ドッグレス猟だからこれ程の高い所まで上がれたのです。
ケンさん自身最初の10年は9年目の1頭だけでした。
それが末期には1日で10頭、しかもマグレではありません。ドッグ猟を続けている自称ベテランハンターからすれば2桁違いは絶対に信じられず、「嘘もイイ加減にしなさい」と言える程の大差が付いてしまったのです。
勿論言うまでも無く、本当の実績値です。
ケンさんの人生も仕事も不可能への挑戦でした。
ドッグレス猟も不可能への挑戦でした。
そう言う運命だったのか、偶然だったのかどうかは分かりませんが、相性は良く「ドッグレス猟こそ、最高の狩猟だった」と言えました。
ケンさんの不可能に挑戦する合理化努力は、当初自衛の為でありましたが、やがてそれが仕事にも使える事に気が付きました。ケンさんが担当すると特に悪戦苦闘する事も無く、全戦全勝で「不可能が可能」になりました。何時しか不可能を可能に変える「伝説の男」と言う事になってしまいました。
自前会社設立時も当初はどの様にして利益を得るのかと言う著しく不利な環境でした。
下請け的な仕事も大変だなと思いました。
しかし合理化を進めますと僅か半年で能率10倍が達成され、当初不利に思えた契約内容でもかなり大きな利益が上がる様になりました。
これも自らが作業するとなれば、たくさんの仕事をしても疲れない様にして、如何にして楽をするのが目的でしたが、パートのおばさんに教え込むとケンさんの能率の80%以上が再現出来ました。
やがて下請け的な仕事から手を引き、自前の仕事としました。
ランクルを改造申請する会社であり、小型トレーラーを製造販売する会社でした。こちらは支払いが非常に少ないのでもっと儲かりました。
それも従業員がやってくれる様になりまして、結局ケンさんは何もしないでも収入があると言う有難い環境となり、狩猟を堪能出来ました。
本州鹿猟では初めて本格的悪戦苦闘をしました。
9年目まで全く獲れず、「当初の10年間では9年目の1頭だけ」でした。
やがて「禅の心作戦」を考案、銃を向けるだけで命中する「新スナップショット」、 リード自動調整の「ショットガン版スイング射撃」を開拓、「バックショット専用銃」を考案しました。
捕獲率は10倍以上に向上、更にエゾ鹿猟メインに変更、天気や諸条件等を考えてそこに行けば鹿に出会える「ポイント猟」を開拓、「次の10年間には100頭」を捕獲出来ました。
更に2002年ワンホール射撃達成後間もなくの2006年、ライフル射撃に開眼、「ライフル版のスナップショット」「ライフル版のスイング射撃」によるランニング射撃にも開眼しました。
ベスト記録は「5日間に50頭」を捕獲、この中には「5発5中」が3度達成される等々、1度のチャンスから複数頭を捕獲出来る様になり、「3度目の10年間には海外猟を含め1000頭」を達成出来ました。
かなり苦労しましたが、狩猟に於いては「ポイント猟」の開拓で、獲物との出会いを圧倒的に多く出来、且つ超大物との出会率も圧倒的に高くなりました。
射撃に於きましては「スナップショット」で圧倒的に速く正確に構え発砲出来る様になり、「銃だけに撃たせる」事により、射撃精度も大幅に向上、150mワンホール射撃や300m以遠の遠射を可能とし、また「スイング射撃」により、従来は不可能とされていた走る鹿の連続ヒットも可能となりました。
結果的に「狩猟にも射撃にも大幅合理化は可能だった」と言えました。
2024年05月18日
50年間で分かった事、その8:世界的狩猟ブームもエゾ鹿猟ブームも業界に依って作られた物でした。
32.「狩猟ブーム」は銃業界がWW2後の不況対策で興し1955年頃日本に伝わった。
33.「マグナム銃」と「カスタム銃」も同様目的であったが、「銃業界の陰謀」だった。
34.1990年頃日本の銃販売業界が「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームを起こした。
起こされた狩猟ブーム:WW2終了で世界中の銃器業界は一気に暇(不景気)になりました。
そこで興されたのが、「アフリカ猟」を頂点とする世界的な「狩猟ブーム」でした。
そして同時に「アフリカンホットマグナム」を頂点に「マグナム銃」の普及が図られ、その後1964年には「カスタム銃」の神話的モデルにウインチェスター70が選ばれました。

アフリカンホットマグナム:アフリカ猟は主に貴族に依り1750年頃から行われていました。
当初は黒色火薬に依る先込め銃で火薬は先込め時代でした。
弾速が低かった事から象の正面から脳を破壊出来ず、即倒が難しい時代であり、1回撃つと馬で走り、安全距離を保って再装填、最大30回射撃した記録があったそうです。
1864年にボクサーカートリッジが発明されると元込めのブラックエクスプレス時代となりました。
口径は黒色火薬の8番水平2連銃と4番単発銃が使われ、ライフル付銃身から細長い弾丸型の弾を発射し、従来より即倒の可能性がかなり増えました。
1884年に無煙火薬が発明され弾速が2倍、黒色8番銃よりハイパワーな20番銃が1890年頃デビュー、600ニトロエクスプレスでした。
12番ベースは700ニトロエクスプレスでした。ニトロは無煙火薬を示します。
ライフル銃身から真鍮ソリッド弾を発射し、象や犀を正面から即倒させる事が可能となりました。
やがて無煙火薬弾も次の世代が誕生、古いながら今も生き残っている1912年の375H&Hです。1時期アフリカ猟ではミニマムカーリッジと言われていましたが、今ではStd308もかなり善戦出来る事が立証されています。
ケンさんはエゾ鹿用ロシア激安弾に売残りのバーンズ140grを挿げ替えた弾をアフリカに持参して試して来ました。
その結果少なくとも500㎏の獲物には絶対に大丈夫と言える事を確認しました。
北海道でも実際「推定体重450㎏の猛獣ヒグマも308の1発で御臨終でした。」
比較的新しいアフリカンでは1956年デビューの458ウインマグ(5400ft-lbf)があります。
7㎜レミントンマグや338ウインマグの兄弟です。
NZで700㎏の野牛撃ちの時、458ウインマグをガイドが用意して来ましたが、試射3発で頭痛、愛銃サコー75の308を使う事にしました。
結果は308で綺麗に即倒でした。「アフリカカンホットマグナムも多分業界の陰謀」であり、気休め程度だったと思われます。30-06を愛用する象駆除のプロハンターが且つていたそうです。
ウインチェスター70プレ64:銃の性能はライフル銃のバイブルでは、モアパワーやモア精度は捕獲成功に続ながるとされていました。しかしそれらは無意味であった事が立証されて来ました。
そんな作られたバイブルの伝説にもう1つ「ウインチェスター70のプレ64伝説」と言うのがあります。

ウインチェスターM70が名銃?:1964年以前、ウインチェスーM70は1936年にデビュー、その時代としては良く出来た銃と言えました。
ベトナム戦争1961~では海兵隊の狙撃銃となり、大きな成果を上げました。その結果、世界中のハンターの評判を呼び、ウィンチェスター社には膨大な数の注文が舞い込みました。アメリカの多くの銃メーカーがM70を下請け生産し、レミントンもその1社でした。
そこでウインチェスターはM70の製法を1964年に大幅リファイン、複雑な削りだし工程を簡素化する等、各部コストダウンを図りました。
その結果、実質的には製品の粗悪化を招いてしまい、軍隊にも民間市場にも、憤慨と共に拒絶される事になってしまいました。
入替わりに脚光を浴びたのが1962年発売のレミントン700でした。海兵隊狙撃銃にバーミンターモデルが採用されるや、世界中の公的スナイパーが本銃を採用し、ベストセラーになりました。
しかしケンさんも1年間運用しましたが、レミントン700はジャムが酷く使えない欠陥銃でした。
一方世界の銃販売店はこれ幸いとして、「ウインチェスター1964年以前の銃」を名銃とする「伝説」を作り上げ、プレ64と呼ばれる1964年以前製造のウインチェエスターの中古銃を集め、プレミアム価格で販売しました。
当時にカスタムメーカーもこの伝説に乗り、プレ64をベースにした、カスタムライフルを高額で販売すると共に、プレ64のクローンモデルを新作し、更なる高額で販売しました。

日本にもカスタム銃メーカー「キングクラフト」があり、勿論「プレ64名銃伝説」の上に成り立つクローンカスタム銃で、Stdライフルが20~40万円で購入出来た時代に、ゼロが1つ多い桁違いがスタート価格と言うとんでもない高額銃でした。
そしてWW2後、作られた狩猟ブームで、1964年以降に評価を受けたのがレミントン700です。
さて冷静に見ればウインチェスターM70に勝ったのが、使えない欠陥銃レミントン700だったのですから、その延長上で行けば、ウインチェスターM70プレ64の高性能ぶりも押して知るべしと言えます。
使えない欠陥銃レミントン700バーミンターは射撃精度面は優秀であり、市販銃で100mワンホールが出せる銃で一応当たる銃と言えましたが、これを名銃としたのはケンさんが立証したカスタム銃不要論等と同様、業界の陰謀と言えました。
勿論その銃の精度が仮に申し分ない物であっても、その運用者の技術レベルや心のレベルが低ければ、何の役にも立たないのですでにお話しした通りです。
「プレ64名銃伝説もレミントン700名銃説もカスタム業界によって作られた伝説」だったのです。
マグナム銃も「急所ヒットならパワー不問」であり、すでに無意味である事を説明しました。
しかし、今一つ急所その物をヒット出来ないハンターも非常に多く、マグナムなら捕獲率が大幅に広がると言うのが業界の「売り文句」でした。
しかしその様な効果は皆無、アフリカンホットマグナムを含め、それらは少しでも「高額銃を売付け様とした業界の陰謀」でした。命中させる為の最大障害は反動によるフリンチングと心の不安であり、反動の強いマグナムは究極を求める側から言えば、反対側の方向と言えました。
「エゾ鹿猟ブームとライフル銃ブーム」は1890年頃、日本の銃販売業界が興したブームでした。
第2次大戦後に銃販売業界が興した狩猟ブームは、日本にも1955年頃に伝わり、水平2連銃がバカ売れ、ハンターは10年で3倍に増え50万人に迫りました。
続く1965年頃から10年間ではハンター数は安定状態、今度は自動5連銃がバカ売れしました。ケンさんが自動銃を購入したのは1975年、当初数年は5連発でしたが、4連発数年を経由して3連発になり現在に至ります。
1985年頃になりますとすでに自動銃も行き渡り、期待の「クレー射撃ブーム」もそれ程は普及せず、一方で銃犯罪が増え、銃の新規取得者には茨の道となり、新規銃取得者は激減しました。
そこで新たに起こされたのが「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームでした。
ライフル銃は勿論業界に取って「利益が大きいマグナム銃ブーム」を同時に起こしました。
ライフル銃取得にはすでに経験10年が必要な時代になっていましたが、経験10年以上のハンターは多く、その点は余り心配無要でした。
エゾ鹿はかなり増殖し、捕獲対象はオスのみ、定数は1日1頭、猟期は12月1日~1月31日の2ケ月でした。
駆除もまだ殆ど行われず、少なくとも休猟区明けの解禁時の10分間だけはかなり豊猟が期待出来ました。と言ってもハンターはそれ以上に多く、成功率は幸運な20%程度でした。
メスは撃たれないので道端に多数おり、メスを求めて若オスも多数がウロ付いていました。大物は期待出来ず、狩猟雑誌「狩猟界」の成功レポートの様には行きませんが、多くの我と思わんハンターが北海道を目指し、その遠征者数は3000人に及びました。
我が地元猟友会からも数組が流し猟で遠征しましたが全滅でした。その原因は獲物に出会えない事が1番でした。メスは道端に立っている事も多数ありましたが、オスの出会いは余りにも稀と言えました。
ケンさんはもっぱら誰も走っていない林道を選びました。当時のエゾ鹿は道路を横断しようとする時、車が近付いてくると、それを見極め様としており、森の中50m位の木の陰でそれを見ていました。
それを発見するにはセンスが必要でしたが、非成功組はその狩猟センスが低かった事に尽きます。
全滅組の共通点は1度も真面な射撃チャンスが得られなかった事でした。若干見えた鹿は逃げる鹿だけでした。勿論それは特殊な射撃術を持っていない限り撃っても命中しません。
雑誌「狩猟界」の成功レポートは事実だと仮定しても 極稀に上手く行った事だけが書いてありました。1996年からケンさんは白糠で単独猟を行い、概ね1日1頭を捕獲していましたが、例外組でした。
同宿の他の6組は連日捕獲ゼロが続いていました。捕獲成功率は10%以下の様に見えました。
「狩猟界」は罪作りな記事を載せました。
せめて遠征失敗組にレポートも半数程度は載せるべきだったと言えました。
当時のエゾ鹿は右写真の様に見える事は甚だ稀、左写真の様に見えれば良い方なのですが、その半分程度しか見えていない鹿を探すのですからシロートには大変で、発見出来ない事が当然と言えました。発見すれば余り逃げず、且つ50mですから捕獲の可能性は十分ありました。


巻狩り組も捕獲に成功したと言う話は皆無でした。ケンさんも流し猟以前は白糠3シーズンで21日間の巻狩りを行いましたが、本命の巻狩りでは捕獲ゼロでした。
この頃は本州鹿巻狩りで「禅の心作戦」で「巻狩りに開眼」していたケンさんですが、それでも猟犬を使わないエゾ鹿の巻狩りでは「気配勝負に勝てず」獲れずにいました。



しかし車で猟場への往復途上や、また待ち場の配置に付く過程で鹿を踏み出し等で、毎シーズン1~2頭を捕獲していました。
踏み出しには当然スナップショットやランニングショット技術が必要でした。これら断片的なデータから流し猟の方が獲れそうだと考え、獲れない巻狩りを卒業した次第でした。結果は写真の様に概ね1日1頭を捕獲出来、数少ない生き残り側になれました。
マグナムライフル:「エゾ鹿猟とライフル銃」のブームは当然販売店側からすれば、高額マグナムライフルやカスタムライフルの売上げに結び付けたい陰謀がありました。
当時は「エゾ鹿猟に短薬莢の貧弱そうな308」を使う人は誰もおらず、Std口径も薬莢が12㎜長くパワーも5~10%強力な30-06が選ばれました。
本州鹿猟では急所を狙う習慣も無く、被弾しても未回収になる鹿は多く、Stdではややパワー不足とされ、当時に雑誌「狩猟界」の技術解説でもマグナムが奨励されていました。
当時はマグナムをモアパワーとモア精度でハンドロードする人が1番本格派に見えました。
マグナム弾は概ね1.4倍のパワーがあり、肉が血まみれになる範囲は2倍に及び、明らかな強力なパワーを感じました。
それに比例し即倒する確率や未回収減少等、少しでも効果があれば良かったのですが全く効果無し、つまり「マグナムは、銃も弾も高いだけで全くの無意味」でした。
ハンドロードに依るモアパワーは最大10~20%程度が可能でした。
モア精度の方は安売り市販弾程度であり、コスト的にも安売り弾よりやや安い程度で余り意味を成しませんが、ハンドローダーは本格的な感じがし、多くのライフルハンターはより本格派を目指し射撃場に通いました。
射撃精度の最大の敵は反動によるフリンチング、反動を伴う実射からの上達の可能性は極めて薄いのが本当でした。
エゾ鹿猟とマグナムライフルブームの企画は販売目的から言えば、一応成功と言えました。
3000人のハンターがライフル銃を手に北海道を訪れました。それ自体は大成功とは言えない程度 だったかも知れませんが、エゾ鹿猟とライフル銃ブームは北海道にも起こり、1万人以上がライフル銃を購入しました。
ブーム以前からエゾ鹿猟は北海道でも行われていましたが、普通の狩猟用散弾銃でスラグ弾を使用していました。
それがライフル銃ブームで北海道にもライフル銃が普及し、やがてエゾ鹿猟にはライフル銃が不可欠な時代に変わりました。
1995年以前のエゾ鹿猟のエゾ鹿は50~100mにいました。
これは50m超えを撃たなかったスラグ弾時代の影響がまだ残っていたからと言えました。
やがて年を重ねる毎にエゾ鹿はライフル銃の普及や2000年以降はサボットスラグ銃の普及に依り射程距離が長くなりまして、昨今では100~150mにいます。
これは普通の射撃場で練習した射手の精度が100m程度を限界としていた為であり、100mを超えると撃たれる可能性がかなり低下した からと言えました。
更にライフル銃ブームは本州にも及びました。従来からの散弾銃とノーマルスラグ弾は射程距離50mでしたが、それは射撃練習をかなり熟した後の成果でした。
それをしなければ射程距離は僅か20m未満、これに不満を持つ本州ハンターはたくさんいました。高精度な長射程のライフル銃ブームは 必ずしもライフル銃は必要としない本州猟ハンターにもかなり及んだのです。
更に当初はアフリカに行きたいからと国内制限の10㎜を超える超高額な大口径マグナムもOKになり、海外以外であってもヒグマ用マグナム、エゾ鹿用Stdライフル、本州用カービン銃とライフル銃3丁を所持する、自称本格派もチラホラいました。
これに比べればクレー射撃でトラップ用とスキート用の2丁と 言うのはありましたが、両射撃の愛好家は少なかった様です。
クレー射撃銃では技能講習実技で不合格になる人も実績不足を問われる人も甚だ僅かでした。
しかしライフル銃は魔法の銃ではなく、彼らは射撃練習を全くしなかったので、射程は20m不変のままでした。すでに説明しました様に、体が銃の反動を上手く受け様として硬くなる「フリンチング」と言う現象に依り、照準がズレてしまう事に問題がありました。
ライフル銃自体には200~300mの能力はあるのですが、練習を全くしなければ、どの銃を撃っても結果は大同小異の20m未満でした。
そして2012~2015の旧技能講習の実施以前は、銃の更新に実技試験は無く、平穏無事にライフル銃の所持許可の更新が続けられました。
旧技能講習はすでに説明しました様に、射撃練習をしていない本州のライフルハンターには絶望的な実技試験となりました。静止的とは言え、50mで14㎝命中がその合格条件でした。
正確には1点圏は16㎝、20発撃って40点以上が合格ですから、14㎝2点命中を平均的に繰り返せば、40点以上になり、合格出来る物でした。
結果は完全に2つのグループに分かれました。
ライフル射撃を趣味としていた人及びエゾ鹿猟複数捕獲実績組には7点以上に着弾、10発でも楽勝の40点ですが、そうでない人達はこの16㎝の的紙からハミ出してしまい、合格は絶望的でした。
半分位が合格すると良かったのですが、現実は受検 した70%以上が不合格、余りの難度に受検しなかった人も多く、結局本州ライフルの90%以上が所持許可の更新を出来ず、本州のライフルブームはこの時を以って終りました。
エゾ鹿猟ブームは「狩猟界」の成功レポートの様に上手く行った人は殆どおらず概ね全滅、最も成功率が高いと言われるガイド猟でも、肝心のガイドの90%が詐欺ガイドであり成功組は僅か、エゾ鹿猟ブームは10年程で消滅しました。
決してライフル銃やエゾ鹿猟自体に魅力が無くなったのではなく、今も愛好者はいますが、本州から北海道の狩猟登録する人は1000人程度になり、しかも多くが狩猟実績を作る為だけの出猟であり、実際のエゾ鹿猟は余り行なわれていない(獲れていない)様です。
散弾パターンでカバー出来るショットガンの射撃はクレーが放出機が15台、その設定表が9種類ですから飛行コースは135種で、毎回同じ様に飛ぶ事から、膨大な射撃場通いで上達する可能性があり、当時国体に出場なら年間3万発以上と言われていました。
クレー射撃は余りブームにならなかったと書きましたが、それは愛好者が10%を超えない程度だったからでした。
ケンさんの自宅から1時間尾範囲にクレー射撃場が4つあり、64発連続ヒットを出した時も田舎親善射撃大会では2位でしたから、そこそこの熱いブームはありました。
ケンさんはクレー射撃ブームには乗らず、年に数回の猟友会お付合い射撃に留めました。
クレー射撃から実戦が上手くなる事は無いと感じたからでした。
33.「マグナム銃」と「カスタム銃」も同様目的であったが、「銃業界の陰謀」だった。
34.1990年頃日本の銃販売業界が「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームを起こした。
起こされた狩猟ブーム:WW2終了で世界中の銃器業界は一気に暇(不景気)になりました。
そこで興されたのが、「アフリカ猟」を頂点とする世界的な「狩猟ブーム」でした。
そして同時に「アフリカンホットマグナム」を頂点に「マグナム銃」の普及が図られ、その後1964年には「カスタム銃」の神話的モデルにウインチェスター70が選ばれました。

アフリカンホットマグナム:アフリカ猟は主に貴族に依り1750年頃から行われていました。
当初は黒色火薬に依る先込め銃で火薬は先込め時代でした。
弾速が低かった事から象の正面から脳を破壊出来ず、即倒が難しい時代であり、1回撃つと馬で走り、安全距離を保って再装填、最大30回射撃した記録があったそうです。
1864年にボクサーカートリッジが発明されると元込めのブラックエクスプレス時代となりました。
口径は黒色火薬の8番水平2連銃と4番単発銃が使われ、ライフル付銃身から細長い弾丸型の弾を発射し、従来より即倒の可能性がかなり増えました。
1884年に無煙火薬が発明され弾速が2倍、黒色8番銃よりハイパワーな20番銃が1890年頃デビュー、600ニトロエクスプレスでした。
12番ベースは700ニトロエクスプレスでした。ニトロは無煙火薬を示します。
ライフル銃身から真鍮ソリッド弾を発射し、象や犀を正面から即倒させる事が可能となりました。
やがて無煙火薬弾も次の世代が誕生、古いながら今も生き残っている1912年の375H&Hです。1時期アフリカ猟ではミニマムカーリッジと言われていましたが、今ではStd308もかなり善戦出来る事が立証されています。
ケンさんはエゾ鹿用ロシア激安弾に売残りのバーンズ140grを挿げ替えた弾をアフリカに持参して試して来ました。
その結果少なくとも500㎏の獲物には絶対に大丈夫と言える事を確認しました。
北海道でも実際「推定体重450㎏の猛獣ヒグマも308の1発で御臨終でした。」
比較的新しいアフリカンでは1956年デビューの458ウインマグ(5400ft-lbf)があります。
7㎜レミントンマグや338ウインマグの兄弟です。
NZで700㎏の野牛撃ちの時、458ウインマグをガイドが用意して来ましたが、試射3発で頭痛、愛銃サコー75の308を使う事にしました。
結果は308で綺麗に即倒でした。「アフリカカンホットマグナムも多分業界の陰謀」であり、気休め程度だったと思われます。30-06を愛用する象駆除のプロハンターが且つていたそうです。
ウインチェスター70プレ64:銃の性能はライフル銃のバイブルでは、モアパワーやモア精度は捕獲成功に続ながるとされていました。しかしそれらは無意味であった事が立証されて来ました。
そんな作られたバイブルの伝説にもう1つ「ウインチェスター70のプレ64伝説」と言うのがあります。

ウインチェスターM70が名銃?:1964年以前、ウインチェスーM70は1936年にデビュー、その時代としては良く出来た銃と言えました。
ベトナム戦争1961~では海兵隊の狙撃銃となり、大きな成果を上げました。その結果、世界中のハンターの評判を呼び、ウィンチェスター社には膨大な数の注文が舞い込みました。アメリカの多くの銃メーカーがM70を下請け生産し、レミントンもその1社でした。
そこでウインチェスターはM70の製法を1964年に大幅リファイン、複雑な削りだし工程を簡素化する等、各部コストダウンを図りました。
その結果、実質的には製品の粗悪化を招いてしまい、軍隊にも民間市場にも、憤慨と共に拒絶される事になってしまいました。
入替わりに脚光を浴びたのが1962年発売のレミントン700でした。海兵隊狙撃銃にバーミンターモデルが採用されるや、世界中の公的スナイパーが本銃を採用し、ベストセラーになりました。
しかしケンさんも1年間運用しましたが、レミントン700はジャムが酷く使えない欠陥銃でした。
一方世界の銃販売店はこれ幸いとして、「ウインチェスター1964年以前の銃」を名銃とする「伝説」を作り上げ、プレ64と呼ばれる1964年以前製造のウインチェエスターの中古銃を集め、プレミアム価格で販売しました。
当時にカスタムメーカーもこの伝説に乗り、プレ64をベースにした、カスタムライフルを高額で販売すると共に、プレ64のクローンモデルを新作し、更なる高額で販売しました。

日本にもカスタム銃メーカー「キングクラフト」があり、勿論「プレ64名銃伝説」の上に成り立つクローンカスタム銃で、Stdライフルが20~40万円で購入出来た時代に、ゼロが1つ多い桁違いがスタート価格と言うとんでもない高額銃でした。
そしてWW2後、作られた狩猟ブームで、1964年以降に評価を受けたのがレミントン700です。
さて冷静に見ればウインチェスターM70に勝ったのが、使えない欠陥銃レミントン700だったのですから、その延長上で行けば、ウインチェスターM70プレ64の高性能ぶりも押して知るべしと言えます。
使えない欠陥銃レミントン700バーミンターは射撃精度面は優秀であり、市販銃で100mワンホールが出せる銃で一応当たる銃と言えましたが、これを名銃としたのはケンさんが立証したカスタム銃不要論等と同様、業界の陰謀と言えました。
勿論その銃の精度が仮に申し分ない物であっても、その運用者の技術レベルや心のレベルが低ければ、何の役にも立たないのですでにお話しした通りです。
「プレ64名銃伝説もレミントン700名銃説もカスタム業界によって作られた伝説」だったのです。
マグナム銃も「急所ヒットならパワー不問」であり、すでに無意味である事を説明しました。
しかし、今一つ急所その物をヒット出来ないハンターも非常に多く、マグナムなら捕獲率が大幅に広がると言うのが業界の「売り文句」でした。
しかしその様な効果は皆無、アフリカンホットマグナムを含め、それらは少しでも「高額銃を売付け様とした業界の陰謀」でした。命中させる為の最大障害は反動によるフリンチングと心の不安であり、反動の強いマグナムは究極を求める側から言えば、反対側の方向と言えました。
「エゾ鹿猟ブームとライフル銃ブーム」は1890年頃、日本の銃販売業界が興したブームでした。
第2次大戦後に銃販売業界が興した狩猟ブームは、日本にも1955年頃に伝わり、水平2連銃がバカ売れ、ハンターは10年で3倍に増え50万人に迫りました。
続く1965年頃から10年間ではハンター数は安定状態、今度は自動5連銃がバカ売れしました。ケンさんが自動銃を購入したのは1975年、当初数年は5連発でしたが、4連発数年を経由して3連発になり現在に至ります。
1985年頃になりますとすでに自動銃も行き渡り、期待の「クレー射撃ブーム」もそれ程は普及せず、一方で銃犯罪が増え、銃の新規取得者には茨の道となり、新規銃取得者は激減しました。
そこで新たに起こされたのが「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームでした。
ライフル銃は勿論業界に取って「利益が大きいマグナム銃ブーム」を同時に起こしました。
ライフル銃取得にはすでに経験10年が必要な時代になっていましたが、経験10年以上のハンターは多く、その点は余り心配無要でした。
エゾ鹿はかなり増殖し、捕獲対象はオスのみ、定数は1日1頭、猟期は12月1日~1月31日の2ケ月でした。
駆除もまだ殆ど行われず、少なくとも休猟区明けの解禁時の10分間だけはかなり豊猟が期待出来ました。と言ってもハンターはそれ以上に多く、成功率は幸運な20%程度でした。
メスは撃たれないので道端に多数おり、メスを求めて若オスも多数がウロ付いていました。大物は期待出来ず、狩猟雑誌「狩猟界」の成功レポートの様には行きませんが、多くの我と思わんハンターが北海道を目指し、その遠征者数は3000人に及びました。
我が地元猟友会からも数組が流し猟で遠征しましたが全滅でした。その原因は獲物に出会えない事が1番でした。メスは道端に立っている事も多数ありましたが、オスの出会いは余りにも稀と言えました。
ケンさんはもっぱら誰も走っていない林道を選びました。当時のエゾ鹿は道路を横断しようとする時、車が近付いてくると、それを見極め様としており、森の中50m位の木の陰でそれを見ていました。
それを発見するにはセンスが必要でしたが、非成功組はその狩猟センスが低かった事に尽きます。
全滅組の共通点は1度も真面な射撃チャンスが得られなかった事でした。若干見えた鹿は逃げる鹿だけでした。勿論それは特殊な射撃術を持っていない限り撃っても命中しません。
雑誌「狩猟界」の成功レポートは事実だと仮定しても 極稀に上手く行った事だけが書いてありました。1996年からケンさんは白糠で単独猟を行い、概ね1日1頭を捕獲していましたが、例外組でした。
同宿の他の6組は連日捕獲ゼロが続いていました。捕獲成功率は10%以下の様に見えました。
「狩猟界」は罪作りな記事を載せました。
せめて遠征失敗組にレポートも半数程度は載せるべきだったと言えました。
当時のエゾ鹿は右写真の様に見える事は甚だ稀、左写真の様に見えれば良い方なのですが、その半分程度しか見えていない鹿を探すのですからシロートには大変で、発見出来ない事が当然と言えました。発見すれば余り逃げず、且つ50mですから捕獲の可能性は十分ありました。


巻狩り組も捕獲に成功したと言う話は皆無でした。ケンさんも流し猟以前は白糠3シーズンで21日間の巻狩りを行いましたが、本命の巻狩りでは捕獲ゼロでした。
この頃は本州鹿巻狩りで「禅の心作戦」で「巻狩りに開眼」していたケンさんですが、それでも猟犬を使わないエゾ鹿の巻狩りでは「気配勝負に勝てず」獲れずにいました。


しかし車で猟場への往復途上や、また待ち場の配置に付く過程で鹿を踏み出し等で、毎シーズン1~2頭を捕獲していました。
踏み出しには当然スナップショットやランニングショット技術が必要でした。これら断片的なデータから流し猟の方が獲れそうだと考え、獲れない巻狩りを卒業した次第でした。結果は写真の様に概ね1日1頭を捕獲出来、数少ない生き残り側になれました。
マグナムライフル:「エゾ鹿猟とライフル銃」のブームは当然販売店側からすれば、高額マグナムライフルやカスタムライフルの売上げに結び付けたい陰謀がありました。
当時は「エゾ鹿猟に短薬莢の貧弱そうな308」を使う人は誰もおらず、Std口径も薬莢が12㎜長くパワーも5~10%強力な30-06が選ばれました。
本州鹿猟では急所を狙う習慣も無く、被弾しても未回収になる鹿は多く、Stdではややパワー不足とされ、当時に雑誌「狩猟界」の技術解説でもマグナムが奨励されていました。
当時はマグナムをモアパワーとモア精度でハンドロードする人が1番本格派に見えました。
マグナム弾は概ね1.4倍のパワーがあり、肉が血まみれになる範囲は2倍に及び、明らかな強力なパワーを感じました。
それに比例し即倒する確率や未回収減少等、少しでも効果があれば良かったのですが全く効果無し、つまり「マグナムは、銃も弾も高いだけで全くの無意味」でした。
ハンドロードに依るモアパワーは最大10~20%程度が可能でした。
モア精度の方は安売り市販弾程度であり、コスト的にも安売り弾よりやや安い程度で余り意味を成しませんが、ハンドローダーは本格的な感じがし、多くのライフルハンターはより本格派を目指し射撃場に通いました。
射撃精度の最大の敵は反動によるフリンチング、反動を伴う実射からの上達の可能性は極めて薄いのが本当でした。
エゾ鹿猟とマグナムライフルブームの企画は販売目的から言えば、一応成功と言えました。
3000人のハンターがライフル銃を手に北海道を訪れました。それ自体は大成功とは言えない程度 だったかも知れませんが、エゾ鹿猟とライフル銃ブームは北海道にも起こり、1万人以上がライフル銃を購入しました。
ブーム以前からエゾ鹿猟は北海道でも行われていましたが、普通の狩猟用散弾銃でスラグ弾を使用していました。
それがライフル銃ブームで北海道にもライフル銃が普及し、やがてエゾ鹿猟にはライフル銃が不可欠な時代に変わりました。
1995年以前のエゾ鹿猟のエゾ鹿は50~100mにいました。
これは50m超えを撃たなかったスラグ弾時代の影響がまだ残っていたからと言えました。
やがて年を重ねる毎にエゾ鹿はライフル銃の普及や2000年以降はサボットスラグ銃の普及に依り射程距離が長くなりまして、昨今では100~150mにいます。
これは普通の射撃場で練習した射手の精度が100m程度を限界としていた為であり、100mを超えると撃たれる可能性がかなり低下した からと言えました。
更にライフル銃ブームは本州にも及びました。従来からの散弾銃とノーマルスラグ弾は射程距離50mでしたが、それは射撃練習をかなり熟した後の成果でした。
それをしなければ射程距離は僅か20m未満、これに不満を持つ本州ハンターはたくさんいました。高精度な長射程のライフル銃ブームは 必ずしもライフル銃は必要としない本州猟ハンターにもかなり及んだのです。
更に当初はアフリカに行きたいからと国内制限の10㎜を超える超高額な大口径マグナムもOKになり、海外以外であってもヒグマ用マグナム、エゾ鹿用Stdライフル、本州用カービン銃とライフル銃3丁を所持する、自称本格派もチラホラいました。
これに比べればクレー射撃でトラップ用とスキート用の2丁と 言うのはありましたが、両射撃の愛好家は少なかった様です。
クレー射撃銃では技能講習実技で不合格になる人も実績不足を問われる人も甚だ僅かでした。
しかしライフル銃は魔法の銃ではなく、彼らは射撃練習を全くしなかったので、射程は20m不変のままでした。すでに説明しました様に、体が銃の反動を上手く受け様として硬くなる「フリンチング」と言う現象に依り、照準がズレてしまう事に問題がありました。
ライフル銃自体には200~300mの能力はあるのですが、練習を全くしなければ、どの銃を撃っても結果は大同小異の20m未満でした。
そして2012~2015の旧技能講習の実施以前は、銃の更新に実技試験は無く、平穏無事にライフル銃の所持許可の更新が続けられました。
旧技能講習はすでに説明しました様に、射撃練習をしていない本州のライフルハンターには絶望的な実技試験となりました。静止的とは言え、50mで14㎝命中がその合格条件でした。
正確には1点圏は16㎝、20発撃って40点以上が合格ですから、14㎝2点命中を平均的に繰り返せば、40点以上になり、合格出来る物でした。
結果は完全に2つのグループに分かれました。
ライフル射撃を趣味としていた人及びエゾ鹿猟複数捕獲実績組には7点以上に着弾、10発でも楽勝の40点ですが、そうでない人達はこの16㎝の的紙からハミ出してしまい、合格は絶望的でした。
半分位が合格すると良かったのですが、現実は受検 した70%以上が不合格、余りの難度に受検しなかった人も多く、結局本州ライフルの90%以上が所持許可の更新を出来ず、本州のライフルブームはこの時を以って終りました。
エゾ鹿猟ブームは「狩猟界」の成功レポートの様に上手く行った人は殆どおらず概ね全滅、最も成功率が高いと言われるガイド猟でも、肝心のガイドの90%が詐欺ガイドであり成功組は僅か、エゾ鹿猟ブームは10年程で消滅しました。
決してライフル銃やエゾ鹿猟自体に魅力が無くなったのではなく、今も愛好者はいますが、本州から北海道の狩猟登録する人は1000人程度になり、しかも多くが狩猟実績を作る為だけの出猟であり、実際のエゾ鹿猟は余り行なわれていない(獲れていない)様です。
散弾パターンでカバー出来るショットガンの射撃はクレーが放出機が15台、その設定表が9種類ですから飛行コースは135種で、毎回同じ様に飛ぶ事から、膨大な射撃場通いで上達する可能性があり、当時国体に出場なら年間3万発以上と言われていました。
クレー射撃は余りブームにならなかったと書きましたが、それは愛好者が10%を超えない程度だったからでした。
ケンさんの自宅から1時間尾範囲にクレー射撃場が4つあり、64発連続ヒットを出した時も田舎親善射撃大会では2位でしたから、そこそこの熱いブームはありました。
ケンさんはクレー射撃ブームには乗らず、年に数回の猟友会お付合い射撃に留めました。
クレー射撃から実戦が上手くなる事は無いと感じたからでした。
2024年05月10日
50年間で分かった事、その6:実射練習からは100mが限界。
17.実射練習からフリンチング対策は進まず、射撃が上達する事は無かった。
18.フリンチング対策をしなければ射程20m、射撃場通いは100m弱が限界だった。
19.失中の原因「迫力負け」等の心側の不安にあった。
射撃上達を阻害する原因は銃の反動にあり、反動を上手く受け様とする発射直前の体にチカラが入る生体反応に原因がありました。
これにより主に移動標的の散弾銃射撃では追尾していたスイングが止まってしまう「引止まり射撃」に陥り、銃のスイングが止まっている間のリードを追加する必要があり、リードは約3倍の高難度な射撃となり、通常ショットガン射撃は「近距離&低速限定となりました。」
また静止精密射撃のライフル銃射撃では照準がズレてしまい、「100m未満の射撃に陥り」ました。フリンチング対策の練習を全くしなければ急所を狙える射程は20m、壁は50mと100mにあり、「射撃場通いでは100mを超える事は不可能」と言えました。
2012~2015に設定された旧技能講習では受検した70%以上が50m先の15㎝の的に命中させられず不合格、高難度故に受験しないハンターも多く、全体の本州ライフルハンターの90%以上が所持許可を更新出来ずに終りました。
同じ試験を北海道ハンターは90%以上が合格した事から、射撃場通いすれば概ね全員が超えられる試験内容でしたが、射撃場通いをしない本州ライフルマンには絶望的高難度でした。
スラグ弾射撃の初期頃、ケンさんも50mで15㎝の的紙から時にはみ出し、50mで10㎝には概ね5年を要しました。
一方北海道では当時50~100mにいたエゾ鹿を捕獲する為のライフル銃でしたから、概ね全員が合格しました。
この事は射撃場通いをすれば概ね全員がこの程度にはなれますが、その後もエゾ鹿は100~150mにいた事を考えますと、100mを超えるエゾ鹿に射撃する人はおらず、150m射撃の能力を持った人は例外的な存在と言えました。
結論として「射撃場通いで50m能力は得られましたが、100m能力を持つ事は難しかった」事を意味しました。
またエゾ鹿猟では本州鹿にない新たなテーマもありました。本州鹿はハンターと同格で「迫力負け」は起こりませんが、エゾ鹿成獣オスは130㎏前後、日本人ハンターの2倍近い巨体でした。
巨大なエゾ鹿との対戦は対面した時、その大きさから来る「迫力に負け」で足が地に着かない射撃に なってしまいました。
身震いする様な大物エゾ鹿との勝負が最大の魅力なのですが、「迫力負け」が大きなテーマとなりました。「100mで5㎝の射撃精度が育ち、迫力負けに陥らなかった時、大物エゾ鹿の捕獲成功」に至りました。
20.休猟区明け解禁開けフィーバーは僅か10分間だった。
21.エゾ鹿はフィーバー日(概ね6日サイクルの悪天候明け)に一斉に行動する。
22.フィーバー日以外は鹿に出会えない3流ガイド。
23.繁殖期のエゾ鹿は広い場所で順番に自己の存在をアピールする。
24.紋別のエゾ鹿のベストシーズンは10月下旬からの4週間だった。
25.根室のエゾ鹿のベストシーズンは12月中旬からの4週間だった 。
エゾ鹿猟に限らず、狩猟で最も難しいのは獲物と射程距離内で出会う事です。1995年まで休猟区と言う制度があり、全体の10%で3年間狩猟を休ませるエリアがありました。
古くは1971年、ケンさんの家の近くが休猟区明けとなり、小雨の降る日にキジ猟に出撃しました。結果から申しますと、キジはウジャウジャいまして、25回のオスキジ射撃チャンスがあり、超未熟ながら2羽の捕獲となりました。
1992年まで白糠も休猟区でした。当時は駆除も無く、メス鹿も禁猟、道端には撃たれないメス鹿がウジャウジャ、そのメスとの出会いを狙った若いオス鹿もチラホラいて、これが狩猟のメインターゲットでした。
当初はガイド料不要の巻狩りを始めました。本州鹿巻狩りを極めていた事、巻狩りの方が鹿との出会いが多いと思っていた事等々がありましたが、これは大きな間違いでした。
白糠巻狩りは3シーズンで正味21日間行いましたが、本命の巻狩りではゼロ頭でした。
しかし猟場への往復の過程で数頭を捕獲しました。
それで4年目からは単独流し猟を行う様になり、概ね1日1頭の捕獲がありました。
ならば流し猟なら誰でも獲れるのか? 決してそうではなく、同宿の6組はどの組も捕獲はゼロ、ケンさん地元から出撃した流し猟数組も全滅、「狩猟界の記事はイカサマ」でした。
メス捕獲は更に高難度だった。:そのメス鹿が1994年1月15日から2週間特別解禁されました。あの頃のオスは撃たれるので中々姿を出しませんでしたが、メス鹿は撃たれないので本当に道端に幾らでも居ました。朝7時頃林道を走りますとカーブを10~20回程曲がるとメス鹿の群がいました。
その群の中には稀にピン角オスも稀に混じっており、群れを見掛けるとオスがいないかチェックです。オスがいなければ次の群れを探しに続行です。
またカーブを10~20回ほど曲がりますと次の群れがいます。こんな光景が毎日約1時間続きます。 夕方でもその半分位を見る事が出来ました。当時メス鹿ならばこれ程いたのでした。
メスも撃てるとあれば幾らでも獲れそうに思うのは全員だったと思います。
メス実験的解禁の年に元GUN誌編集長はかなり無理して15日間も休みを取って来ました。
メス鹿を毎日1頭獲れる予定でシカ肉注文もたくさん受けて張り切って北海道に遠征しましたが、実際の発砲は後述の様に初日に失中した50mの1回だけ、捕獲はゼロ頭でした。
メス解禁以前も猟期は12月1日から1月31日までの2ケ月ですが、捕獲の75%は何時も前半でした。今考えるとやはり繁殖期の雄が雌を追掛ける時期との関係が大きかったと思います。
又その時捕獲出来たのは3段角になったばかりの中小型鹿(オスとしての順位で№.3~4)が多かった事からも、やはり繁殖期が大いに関係していたと思います。
初のメス解禁の日には記録破りの驚く程の人出となりました。
実際に林道のメインストリ-トは100mに1台の車がウジャウジャおりました。
どの車にも2~3人が乗っております。あれ程たくさん居た鹿はすでに1頭も見えません。余りの車の量に鹿の動きが全く止まってしまった様でした。
これでは鹿に出会う事が難しいと思い、ケンさんはマイナー林道に入りました。
やがて解禁の時間になりますと、約10秒間銃声が鳴り続けました。
その音からも如何にたくさんのハンターがいるかを推定出来ました。
間もなくメス2頭群に出会い、足が地に着いていない編集長は失中、ケンさんはダブル捕獲、取り敢えずメデタシメデタシとなりました。
その後もう1頭を追加、解禁から10分は散発的な銃声が聞こえましたが、午前中の以後の出会いはなく、それで終わりました。
その日の夕方は1頭も見ず、2日目の朝も夕方も、更にその翌日もあれ程居たメス鹿は1頭も見る事がなくなりました。
4日目の朝少し遅めに1度だけ鹿が急に少し動き出しまして、1頭追加出来ましたが、夕方の出会いはゼロでした。
ケンさんはその翌日に帰りましたが、編集長はその後更に1週間の猟をしましたが、あれ程道端にたくさん居たメス鹿を、遂にその後1頭も見る事が出来なかったそうです。
毎日1頭を捕獲するつもりで肉の注文を確保してきた編集長はがっかりでした。
メインの林道の道端にはシカ捕獲の痕跡が約1㎞毎にありましたが、あの膨大な車の量からすれば獲れた組は僅か10%程度で、大多数は獲れなかったガッカリ組ではなかったかと思われます。
本州鹿メス全面解禁:2005年11月15日には我が愛知県もメス鹿が全面解禁になり、ケンさんが以前所属していた巻狩りグループもメス解禁に向け張り切っておりました。
メスなら幾らでも獲れる筈、誰もがそう思っていました。ケンさんは北海道白糠の経験があるので「最初の1~2頭は獲れると思うが、悪く見ればメス群れはオス以上に敏感、結局メスは殆ど獲れず、雄雌合計でもメス解禁以前と殆んど変わらないだろうと思いました。
結果はケンさんの予想よりも遥かに酷い物になりました。
メスは最初の数頭だけ獲れました。メスは撃たれないから以前は姿を見せたのですが、1度撃たれれば命が掛かっており、そう簡単には姿を出さなくなりました。
その後のオス捕獲は従前比で半減以下に大幅ダウン、雄雌合計しても数値は余り変わらず、鹿猟は従前より遥かに高難度となりました。
これがメス解禁の事実でした。
オスも猟期前半は繁殖期故にメスに惹かれて動きますので従来は多少姿を見る事が出来たのですが、メスが動かなくなったので、オスも動かなくなりオスの出会いも激減したのでした。
結局メス解禁で総捕獲数は2倍になる所か、雄雌合わせて半分となりました。
北海道のメス鹿の全面解禁時は行かなかったので知りませんが、スクール開講は2002からですが、その頃の定数はオス1とメス2でした。メス解禁で出会いは高難度となった様でした。
しかし北海道ではその時期に山から降りたオス鹿の繁殖期の縄張り争いからチャンスが多数生まれ、ケンさんスクールでは1日5回の出会いがあり、出会いの70%がオスの3段角成獣、20%が角長70㎝を超える大物を誇りますが、実を言うと用心深いメスには殆ど出会えなかったのです。
2003年頃からこの傾向が強くなり、2004年以降解禁の1ヶ月の出会い数はオスが90%、群れの№.2クラス(70㎝級)との出会いが全体の20%もあり、全体の70%が3段角のオスでした。
メスが姿を出し撃てる様になるのは雪が降ってからとなります。
結局、簡単に鹿が捕獲出来る方法は、休猟区開けの解禁直後の10分間を除けば無いのです。
1990年頃、雑誌「狩猟界」に成功レポートがたくさん掲載されていましたが、あれは休猟区明けの解禁後の10分間の物語だけでした。
そしてその頃はメスが撃たれなかったので、それに連られてウロ付くオスが獲れたのですが、そう言う時代も過ぎました。近年は鹿の被害が増え、その増殖に結付く休猟区設定も無くなり鹿の駆除も1段と増え、雄雌含めエゾ鹿に出会う事自体が高難度となりました。
エゾ鹿フィーバー:普段は出会う事自体が非常に高難度なエゾ鹿ですが、概ね6日サイクルの 悪天候明けの日には一斉に行動を起こします。
その日は大物ズラズラ、しかも何時もよりかなり距離も近く、鹿は周りのライバルオスに目を奪われ、照準時間も長らく貰えます。
超大物捕獲のチャンスはこの日を除けば非常に少なくなります。
地元3流ガイドでもこの日だけは鹿に出会える事でしょう。
その確率は1/6ですから17%、3流ガイドでは残る83%は出会いが得られません。
悪天候明けの鹿が一斉に動く日を「フィーバー日」と呼んでいます。
大物が多く、比較的距離も近く、照準時間も長目に貰え、ハンターに取っては1番良い日となります。毎シーズン1回、ビッグフィーバーになります。
超大物がズラズラです。ハンターであれば誰もがそんな日に出撃したいのですが、何時それが起こるのかは、その時にならないと分かりません。
エゾ鹿猟ベストシーズンとその場所:エゾ鹿は季節的な移動をします。狩猟解禁は10月1日ですがその頃は余り向いておりません。
鹿が行動を起こすのは10月下旬の高い山に冠雪があった時からとなります。
群は5~10頭の同族メスが中心となり、それを取巻くオス達から成り立ちます。
その時から約1か月間に悪天候明け毎に山から降りて来ます。
この時がエゾ鹿の繁殖期と重なり、ケンさんの紋別スクールでは山から直接降りて来る鹿を山に接する農地で狙います。
群れの近くにはボスがそれ程離れない位置に隠れています。
メス群とボスが引上げると群の№.2が その近くで「我ここにあり」と数分間アピールし引き揚げます。すると№.3がまたその近くで同様にアピール、次が№.4になります。
ボスは時間外の可能性が高いのですが、NO.2は境目付近、NO.3は合法時間である率が高くなります。夕方にはその近くで15時前後からその逆の順序でアピールが行われ、翌日以降は何となく一定ルールの基に下流に移動をして行きます。
山から降りるポイントは幾つかあるので、これらを追い掛けている内に、また次の悪天候明けとなり、新しい群れが降りて来ます。
概ね6日サイクルです。従って7日猟をすればフィーバーに会えます。
ケンさんのもう1つの猟場である根室の場合:鹿が山から降り始めるのは概ね同じ頃なのですが、山は阿寒摩周方面であり、山から降りたその1部が根室半島に向かいます。
根室の猟場は根室半島中場の別当賀周辺です。
鹿がそこに到着するのは12月中旬からの1か月間となります。
年末年始もその期間に含まれますが、ハンターが多くなり過ぎ、良い狩猟が出来ません。
良い猟場とは鹿が多い事と、ハンターが少ない事、どちらかと言えば後者の方が重要です。
根室半島は地図では小さな狭い半島ですが、全体が台地状になっており、モンゴルの大草原を思わせる地形です。
大型の鹿が多いのですが、射程距離が長いのと、照準時間をあまり長く貰えない事です。
すでにここに来るまでにあちこちですでに撃たれており、走っている鹿が多いのが特徴でした。
18.フリンチング対策をしなければ射程20m、射撃場通いは100m弱が限界だった。
19.失中の原因「迫力負け」等の心側の不安にあった。
射撃上達を阻害する原因は銃の反動にあり、反動を上手く受け様とする発射直前の体にチカラが入る生体反応に原因がありました。
これにより主に移動標的の散弾銃射撃では追尾していたスイングが止まってしまう「引止まり射撃」に陥り、銃のスイングが止まっている間のリードを追加する必要があり、リードは約3倍の高難度な射撃となり、通常ショットガン射撃は「近距離&低速限定となりました。」
また静止精密射撃のライフル銃射撃では照準がズレてしまい、「100m未満の射撃に陥り」ました。フリンチング対策の練習を全くしなければ急所を狙える射程は20m、壁は50mと100mにあり、「射撃場通いでは100mを超える事は不可能」と言えました。
2012~2015に設定された旧技能講習では受検した70%以上が50m先の15㎝の的に命中させられず不合格、高難度故に受験しないハンターも多く、全体の本州ライフルハンターの90%以上が所持許可を更新出来ずに終りました。
同じ試験を北海道ハンターは90%以上が合格した事から、射撃場通いすれば概ね全員が超えられる試験内容でしたが、射撃場通いをしない本州ライフルマンには絶望的高難度でした。
スラグ弾射撃の初期頃、ケンさんも50mで15㎝の的紙から時にはみ出し、50mで10㎝には概ね5年を要しました。
一方北海道では当時50~100mにいたエゾ鹿を捕獲する為のライフル銃でしたから、概ね全員が合格しました。
この事は射撃場通いをすれば概ね全員がこの程度にはなれますが、その後もエゾ鹿は100~150mにいた事を考えますと、100mを超えるエゾ鹿に射撃する人はおらず、150m射撃の能力を持った人は例外的な存在と言えました。
結論として「射撃場通いで50m能力は得られましたが、100m能力を持つ事は難しかった」事を意味しました。
またエゾ鹿猟では本州鹿にない新たなテーマもありました。本州鹿はハンターと同格で「迫力負け」は起こりませんが、エゾ鹿成獣オスは130㎏前後、日本人ハンターの2倍近い巨体でした。
巨大なエゾ鹿との対戦は対面した時、その大きさから来る「迫力に負け」で足が地に着かない射撃に なってしまいました。
身震いする様な大物エゾ鹿との勝負が最大の魅力なのですが、「迫力負け」が大きなテーマとなりました。「100mで5㎝の射撃精度が育ち、迫力負けに陥らなかった時、大物エゾ鹿の捕獲成功」に至りました。
20.休猟区明け解禁開けフィーバーは僅か10分間だった。
21.エゾ鹿はフィーバー日(概ね6日サイクルの悪天候明け)に一斉に行動する。
22.フィーバー日以外は鹿に出会えない3流ガイド。
23.繁殖期のエゾ鹿は広い場所で順番に自己の存在をアピールする。
24.紋別のエゾ鹿のベストシーズンは10月下旬からの4週間だった。
25.根室のエゾ鹿のベストシーズンは12月中旬からの4週間だった 。
エゾ鹿猟に限らず、狩猟で最も難しいのは獲物と射程距離内で出会う事です。1995年まで休猟区と言う制度があり、全体の10%で3年間狩猟を休ませるエリアがありました。
古くは1971年、ケンさんの家の近くが休猟区明けとなり、小雨の降る日にキジ猟に出撃しました。結果から申しますと、キジはウジャウジャいまして、25回のオスキジ射撃チャンスがあり、超未熟ながら2羽の捕獲となりました。
1992年まで白糠も休猟区でした。当時は駆除も無く、メス鹿も禁猟、道端には撃たれないメス鹿がウジャウジャ、そのメスとの出会いを狙った若いオス鹿もチラホラいて、これが狩猟のメインターゲットでした。
当初はガイド料不要の巻狩りを始めました。本州鹿巻狩りを極めていた事、巻狩りの方が鹿との出会いが多いと思っていた事等々がありましたが、これは大きな間違いでした。
白糠巻狩りは3シーズンで正味21日間行いましたが、本命の巻狩りではゼロ頭でした。
しかし猟場への往復の過程で数頭を捕獲しました。
それで4年目からは単独流し猟を行う様になり、概ね1日1頭の捕獲がありました。
ならば流し猟なら誰でも獲れるのか? 決してそうではなく、同宿の6組はどの組も捕獲はゼロ、ケンさん地元から出撃した流し猟数組も全滅、「狩猟界の記事はイカサマ」でした。
メス捕獲は更に高難度だった。:そのメス鹿が1994年1月15日から2週間特別解禁されました。あの頃のオスは撃たれるので中々姿を出しませんでしたが、メス鹿は撃たれないので本当に道端に幾らでも居ました。朝7時頃林道を走りますとカーブを10~20回程曲がるとメス鹿の群がいました。
その群の中には稀にピン角オスも稀に混じっており、群れを見掛けるとオスがいないかチェックです。オスがいなければ次の群れを探しに続行です。
またカーブを10~20回ほど曲がりますと次の群れがいます。こんな光景が毎日約1時間続きます。 夕方でもその半分位を見る事が出来ました。当時メス鹿ならばこれ程いたのでした。
メスも撃てるとあれば幾らでも獲れそうに思うのは全員だったと思います。
メス実験的解禁の年に元GUN誌編集長はかなり無理して15日間も休みを取って来ました。
メス鹿を毎日1頭獲れる予定でシカ肉注文もたくさん受けて張り切って北海道に遠征しましたが、実際の発砲は後述の様に初日に失中した50mの1回だけ、捕獲はゼロ頭でした。
メス解禁以前も猟期は12月1日から1月31日までの2ケ月ですが、捕獲の75%は何時も前半でした。今考えるとやはり繁殖期の雄が雌を追掛ける時期との関係が大きかったと思います。
又その時捕獲出来たのは3段角になったばかりの中小型鹿(オスとしての順位で№.3~4)が多かった事からも、やはり繁殖期が大いに関係していたと思います。
初のメス解禁の日には記録破りの驚く程の人出となりました。
実際に林道のメインストリ-トは100mに1台の車がウジャウジャおりました。
どの車にも2~3人が乗っております。あれ程たくさん居た鹿はすでに1頭も見えません。余りの車の量に鹿の動きが全く止まってしまった様でした。
これでは鹿に出会う事が難しいと思い、ケンさんはマイナー林道に入りました。
やがて解禁の時間になりますと、約10秒間銃声が鳴り続けました。
その音からも如何にたくさんのハンターがいるかを推定出来ました。
間もなくメス2頭群に出会い、足が地に着いていない編集長は失中、ケンさんはダブル捕獲、取り敢えずメデタシメデタシとなりました。
その後もう1頭を追加、解禁から10分は散発的な銃声が聞こえましたが、午前中の以後の出会いはなく、それで終わりました。
その日の夕方は1頭も見ず、2日目の朝も夕方も、更にその翌日もあれ程居たメス鹿は1頭も見る事がなくなりました。
4日目の朝少し遅めに1度だけ鹿が急に少し動き出しまして、1頭追加出来ましたが、夕方の出会いはゼロでした。
ケンさんはその翌日に帰りましたが、編集長はその後更に1週間の猟をしましたが、あれ程道端にたくさん居たメス鹿を、遂にその後1頭も見る事が出来なかったそうです。
毎日1頭を捕獲するつもりで肉の注文を確保してきた編集長はがっかりでした。
メインの林道の道端にはシカ捕獲の痕跡が約1㎞毎にありましたが、あの膨大な車の量からすれば獲れた組は僅か10%程度で、大多数は獲れなかったガッカリ組ではなかったかと思われます。
本州鹿メス全面解禁:2005年11月15日には我が愛知県もメス鹿が全面解禁になり、ケンさんが以前所属していた巻狩りグループもメス解禁に向け張り切っておりました。
メスなら幾らでも獲れる筈、誰もがそう思っていました。ケンさんは北海道白糠の経験があるので「最初の1~2頭は獲れると思うが、悪く見ればメス群れはオス以上に敏感、結局メスは殆ど獲れず、雄雌合計でもメス解禁以前と殆んど変わらないだろうと思いました。
結果はケンさんの予想よりも遥かに酷い物になりました。
メスは最初の数頭だけ獲れました。メスは撃たれないから以前は姿を見せたのですが、1度撃たれれば命が掛かっており、そう簡単には姿を出さなくなりました。
その後のオス捕獲は従前比で半減以下に大幅ダウン、雄雌合計しても数値は余り変わらず、鹿猟は従前より遥かに高難度となりました。
これがメス解禁の事実でした。
オスも猟期前半は繁殖期故にメスに惹かれて動きますので従来は多少姿を見る事が出来たのですが、メスが動かなくなったので、オスも動かなくなりオスの出会いも激減したのでした。
結局メス解禁で総捕獲数は2倍になる所か、雄雌合わせて半分となりました。
北海道のメス鹿の全面解禁時は行かなかったので知りませんが、スクール開講は2002からですが、その頃の定数はオス1とメス2でした。メス解禁で出会いは高難度となった様でした。
しかし北海道ではその時期に山から降りたオス鹿の繁殖期の縄張り争いからチャンスが多数生まれ、ケンさんスクールでは1日5回の出会いがあり、出会いの70%がオスの3段角成獣、20%が角長70㎝を超える大物を誇りますが、実を言うと用心深いメスには殆ど出会えなかったのです。
2003年頃からこの傾向が強くなり、2004年以降解禁の1ヶ月の出会い数はオスが90%、群れの№.2クラス(70㎝級)との出会いが全体の20%もあり、全体の70%が3段角のオスでした。
メスが姿を出し撃てる様になるのは雪が降ってからとなります。
結局、簡単に鹿が捕獲出来る方法は、休猟区開けの解禁直後の10分間を除けば無いのです。
1990年頃、雑誌「狩猟界」に成功レポートがたくさん掲載されていましたが、あれは休猟区明けの解禁後の10分間の物語だけでした。
そしてその頃はメスが撃たれなかったので、それに連られてウロ付くオスが獲れたのですが、そう言う時代も過ぎました。近年は鹿の被害が増え、その増殖に結付く休猟区設定も無くなり鹿の駆除も1段と増え、雄雌含めエゾ鹿に出会う事自体が高難度となりました。
エゾ鹿フィーバー:普段は出会う事自体が非常に高難度なエゾ鹿ですが、概ね6日サイクルの 悪天候明けの日には一斉に行動を起こします。
その日は大物ズラズラ、しかも何時もよりかなり距離も近く、鹿は周りのライバルオスに目を奪われ、照準時間も長らく貰えます。
超大物捕獲のチャンスはこの日を除けば非常に少なくなります。
地元3流ガイドでもこの日だけは鹿に出会える事でしょう。
その確率は1/6ですから17%、3流ガイドでは残る83%は出会いが得られません。
悪天候明けの鹿が一斉に動く日を「フィーバー日」と呼んでいます。
大物が多く、比較的距離も近く、照準時間も長目に貰え、ハンターに取っては1番良い日となります。毎シーズン1回、ビッグフィーバーになります。
超大物がズラズラです。ハンターであれば誰もがそんな日に出撃したいのですが、何時それが起こるのかは、その時にならないと分かりません。
エゾ鹿猟ベストシーズンとその場所:エゾ鹿は季節的な移動をします。狩猟解禁は10月1日ですがその頃は余り向いておりません。
鹿が行動を起こすのは10月下旬の高い山に冠雪があった時からとなります。
群は5~10頭の同族メスが中心となり、それを取巻くオス達から成り立ちます。
その時から約1か月間に悪天候明け毎に山から降りて来ます。
この時がエゾ鹿の繁殖期と重なり、ケンさんの紋別スクールでは山から直接降りて来る鹿を山に接する農地で狙います。
群れの近くにはボスがそれ程離れない位置に隠れています。
メス群とボスが引上げると群の№.2が その近くで「我ここにあり」と数分間アピールし引き揚げます。すると№.3がまたその近くで同様にアピール、次が№.4になります。
ボスは時間外の可能性が高いのですが、NO.2は境目付近、NO.3は合法時間である率が高くなります。夕方にはその近くで15時前後からその逆の順序でアピールが行われ、翌日以降は何となく一定ルールの基に下流に移動をして行きます。
山から降りるポイントは幾つかあるので、これらを追い掛けている内に、また次の悪天候明けとなり、新しい群れが降りて来ます。
概ね6日サイクルです。従って7日猟をすればフィーバーに会えます。
ケンさんのもう1つの猟場である根室の場合:鹿が山から降り始めるのは概ね同じ頃なのですが、山は阿寒摩周方面であり、山から降りたその1部が根室半島に向かいます。
根室の猟場は根室半島中場の別当賀周辺です。
鹿がそこに到着するのは12月中旬からの1か月間となります。
年末年始もその期間に含まれますが、ハンターが多くなり過ぎ、良い狩猟が出来ません。
良い猟場とは鹿が多い事と、ハンターが少ない事、どちらかと言えば後者の方が重要です。
根室半島は地図では小さな狭い半島ですが、全体が台地状になっており、モンゴルの大草原を思わせる地形です。
大型の鹿が多いのですが、射程距離が長いのと、照準時間をあまり長く貰えない事です。
すでにここに来るまでにあちこちですでに撃たれており、走っている鹿が多いのが特徴でした。
2024年05月07日
50年間で分かった事、その5:スコープ専用銃のスナップショットは画期的だった。
13.銃で指向する「スナップショット」は超画期的技術だった。
14.スコープ専用銃は超画期的な発明だった。
15.ストックの調整はチークピースの調整だけで完璧だった。
ショットガンには照準器がなく、現在の物は銃身にリブが付いていますが、従前の物は何も付いておりません。ではどの様に狙うのか?
まず散弾をバラ撒きますから、ライフル銃の様な精密な照準は不要です。
しかし一方で鳥の飛行速度は毎秒10m(36㎞/h)以上、一方射程は40~50mが最大ですから、あっと言う間に射程外まで飛び去られてしまいます。従って素速い動作が必要になります。
銃には反動があり、これを受けられるのはちょうど肩の鎖骨の少し下、肩の関節の少し内側にパッドプレートよりも少し広い所があり、そこだけが大きな反動を受ける事が出来ます。
数㎝ズレれば場合によっては重大な怪我を発生してしまいます。そこで銃は古くから正しく構えなければいけないとされて来ました。一方で瞬時に構えて発砲しなければ射程外に飛び去られてしまいます。
ペラッツィシステム:そこで考え出された手法が、銃を肩に正しく着けて構えると自動的に照準が出来る手法でした。
その為には体格が各自違うので、体格に合わせた銃床を作ると言う事になり、高級銃は全てそうなっていますが、その調整項目は10項目以上の多岐に渡ります。
ペラッツィはフルオーダーストックを昼食時間の内に作るシステムを考案しそれを「売り」にしています。現在は数年待ちの様ですが、順番が来ると本社に出向き、そこのフィッターがトライガンで体格に合わせた銃を設定してくれます。
ペラッツィのトライガンは実射出来るのが最大の特徴です。実射に依る修正も含め諸寸法が決まるとコンピューターが即座に自動で削り出し、オーナーが昼食中に、銃は半仕上がり状態ですが出来上がって来ます。付属のクレー射撃場で気の済むまで撃ちます。
その間も微調整には応じてくれ、納得が行ったら完全仕上げ工程に廻します。
その半仕上げ状態のまましばらく運用する為、持ち帰る事も出来ます。1か月後、完成した銃は自宅まで送られて来ます。
ハイテクストック。
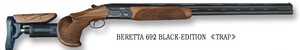

昨今では写真の様に射撃競技銃にフルアジャスト出来るタイプの物も現れました。
このタイプは反動を吸収するショックアブソーバも装着されています。
従来は既製品ストックを運用で慣れろと言う事でしたから著しい進歩と言えます。
サベージシステムストック:狩猟用の普及銃であっても多少の部品交換でアジャスト出来るタイプも出て来ました。写真の物はチークピースが4種、パッドプレートが3種交換出来る様になっています。
こうしたシステムストックのお陰で、普及銃もかなり満足の行く物になって来ました。



そうした良く出来たストックに於いても、旧来の射撃方法では銃を実際に構えた時に目標を正しく補足していなければ命中しません。それには㎜単位の正確な肩付けが前提になります。
それにはかなりの長期間トレーニングが必要になりますが、それでも完璧は期し難く、照準微調整の後の発砲となります。ケンさんもこの手法でトレ―ニングを繰り返し一応実用化出来ました。
ある時、フト感じたのは命中への必要要件は正しい肩付けではなく、正しく指向する事であると気が付きました。そこでそうする為にはを色々考え、次の様な新手法が完成しました。
発砲の決断と共に、体は最終発砲直前状態に移行します。
同時に銃身を眼の高さで目標を指差す様に突き出し指向します。
この段階ですでに目標を正しく捉えていますから、引き金を引けば命中しますが、反動で右手中指にトリガーガードが強く当たります。
銃はホッペをかすめ肩に向けて真直ぐ強く引き寄せます。
銃が肩に着くのを待つ必要は無く、引き金を引きますと弾が出た後に、銃が肩に着きます。
最近気が付いたのですが、これにより旨い事に1発目の反動を体が受けずに済み、同時に「反動が無いので、引止まりも起こさずに済みます。」
ストックはホッペの当たり具合と銃身の延長に目が正しく来る様にチークピースを調整しておけば、パッドは必然的に肩の正しい位置に納まります。
新手法は銃身で指向するだけですから簡単な短期トレーニングで身に付けられ、尚且つ照準微調整が不要ですから速く撃て、よく当たります。
「新スナップショットは西部劇並の早撃ちが可能」であり、それでいて確実に照準しておりますから「必ず命中」します。
「画期的な新射法」と言えます。銃を速やかに構える事でマイナスになる項目は1つも無く、「新スナップショットは全ての射撃の基本」と言えます。
動的への対応も極く自然です。まず最初に体を最終発砲状態に移行しますが、移動標的の場合は体のヘソで追尾を続けます。
銃を指向する時も当然目標を追尾しながらの指向になり、肩に引き寄せる時に体全体でスイングを加速し、追い越した時に引き金を引きます。
これが「スナップスイング射撃」です。追い越した時に 引き金を引く決断をしても発砲までは反応時間遅れにより時間を要します。
するとオーバースイングがリードとなり、これは非常に上手い事に、目標の速度と距離に自動比例してくれます。
「リード自動調整」は狭散布チョーク運用を可能とし、これに7.5号装弾との組合せは50m弱までショットガン効果の「3粒被弾撃墜」を生み、撃墜率大幅増加となります。これに対し一般的ハンターは引止まり射撃、リードが合わず撃墜率大幅低下、対策として散弾広散布チョークを使い、その結果 ショットガン効果の散弾密度に至らず、更なる撃墜率大幅低下、これを散弾パワー不足とし大粒散弾を運用、更にヒット率は低下し、撃墜率は更に更に大幅低下、「近距離&低速限定射撃に陥ります。」
新スナップショットの前提条件はチークピースの調整だけ、他の項目はアバウト、つまり市販ストックで「チークピースの調整」だけで済む事になります。その考えの基、システムストックが生まれました。
この考え方はスコープ取付け時のライフル銃にも応用出来ました。
旧来からのライフル銃には照星&照門が付いており、それは欠点の多い照準器でした。
ライフルスコープの発明は偉大でした。まず遠方の目標にも正確に照準出来ますが、イラストの様に微少上向き発射のお陰で実用照準距離が2倍になりました。

しかし視野が極端に狭いのがスコープの欠点で、素速い照準や走る目標には不向きでした。
この時、従来のスコープ銃はオープンサイトを併用する事も望んだ為、左写真の様にホッペの位置が定まらず、スコープとの位置決めは不可能となり、素速く眼がスコープを捉える事自体が不可能でした。これに対して右はケンさんとサコー75改スコープ専用銃です。


ホッペの位置がストックにより決まりますので、素速い照準が可能でした。
そしてそれは更に発展し、「スコープ専用銃はスナップショットやスナップスイングショットに依るランニング射撃」が得意項目と言える様になりました。
狩猟銃では急所が速やかに狙える事が使える条件としています。ボルトアクション銃はWW1前の1800年代末期にデビューした古い銃でしたが、ボルト銃は「スコープ専用銃で生まれ変わり、あらゆる距離のあらゆる場面で最強の狩猟銃」となりました。
1.落差無視で0~200mまで直撃が出来る。
2.遠射300mが可能である。
3.ワンホール射撃が150mで可能である。
4.アバウト早撃ち3秒が150mで可能である。
5.西部劇並の早撃ちが50m以内なら可能である。
6.未装填と安全解除を取入可能な最も安全な銃。
7.ランニングショット150mの5発5中が可能である。
前提条件にストックの調整がありますが、チークピースの調整だけで残りの項目は極めてアバウトで OKでした。
ライフルのスコープ専用銃は50m以内のショットガン効果を利用した散弾銃の連射以外、最強の銃である事が立証されました。
14.スコープ専用銃は超画期的な発明だった。
15.ストックの調整はチークピースの調整だけで完璧だった。
ショットガンには照準器がなく、現在の物は銃身にリブが付いていますが、従前の物は何も付いておりません。ではどの様に狙うのか?
まず散弾をバラ撒きますから、ライフル銃の様な精密な照準は不要です。
しかし一方で鳥の飛行速度は毎秒10m(36㎞/h)以上、一方射程は40~50mが最大ですから、あっと言う間に射程外まで飛び去られてしまいます。従って素速い動作が必要になります。
銃には反動があり、これを受けられるのはちょうど肩の鎖骨の少し下、肩の関節の少し内側にパッドプレートよりも少し広い所があり、そこだけが大きな反動を受ける事が出来ます。
数㎝ズレれば場合によっては重大な怪我を発生してしまいます。そこで銃は古くから正しく構えなければいけないとされて来ました。一方で瞬時に構えて発砲しなければ射程外に飛び去られてしまいます。
ペラッツィシステム:そこで考え出された手法が、銃を肩に正しく着けて構えると自動的に照準が出来る手法でした。
その為には体格が各自違うので、体格に合わせた銃床を作ると言う事になり、高級銃は全てそうなっていますが、その調整項目は10項目以上の多岐に渡ります。
ペラッツィはフルオーダーストックを昼食時間の内に作るシステムを考案しそれを「売り」にしています。現在は数年待ちの様ですが、順番が来ると本社に出向き、そこのフィッターがトライガンで体格に合わせた銃を設定してくれます。
ペラッツィのトライガンは実射出来るのが最大の特徴です。実射に依る修正も含め諸寸法が決まるとコンピューターが即座に自動で削り出し、オーナーが昼食中に、銃は半仕上がり状態ですが出来上がって来ます。付属のクレー射撃場で気の済むまで撃ちます。
その間も微調整には応じてくれ、納得が行ったら完全仕上げ工程に廻します。
その半仕上げ状態のまましばらく運用する為、持ち帰る事も出来ます。1か月後、完成した銃は自宅まで送られて来ます。
ハイテクストック。
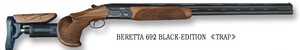

昨今では写真の様に射撃競技銃にフルアジャスト出来るタイプの物も現れました。
このタイプは反動を吸収するショックアブソーバも装着されています。
従来は既製品ストックを運用で慣れろと言う事でしたから著しい進歩と言えます。
サベージシステムストック:狩猟用の普及銃であっても多少の部品交換でアジャスト出来るタイプも出て来ました。写真の物はチークピースが4種、パッドプレートが3種交換出来る様になっています。
こうしたシステムストックのお陰で、普及銃もかなり満足の行く物になって来ました。



そうした良く出来たストックに於いても、旧来の射撃方法では銃を実際に構えた時に目標を正しく補足していなければ命中しません。それには㎜単位の正確な肩付けが前提になります。
それにはかなりの長期間トレーニングが必要になりますが、それでも完璧は期し難く、照準微調整の後の発砲となります。ケンさんもこの手法でトレ―ニングを繰り返し一応実用化出来ました。
ある時、フト感じたのは命中への必要要件は正しい肩付けではなく、正しく指向する事であると気が付きました。そこでそうする為にはを色々考え、次の様な新手法が完成しました。
発砲の決断と共に、体は最終発砲直前状態に移行します。
同時に銃身を眼の高さで目標を指差す様に突き出し指向します。
この段階ですでに目標を正しく捉えていますから、引き金を引けば命中しますが、反動で右手中指にトリガーガードが強く当たります。
銃はホッペをかすめ肩に向けて真直ぐ強く引き寄せます。
銃が肩に着くのを待つ必要は無く、引き金を引きますと弾が出た後に、銃が肩に着きます。
最近気が付いたのですが、これにより旨い事に1発目の反動を体が受けずに済み、同時に「反動が無いので、引止まりも起こさずに済みます。」
ストックはホッペの当たり具合と銃身の延長に目が正しく来る様にチークピースを調整しておけば、パッドは必然的に肩の正しい位置に納まります。
新手法は銃身で指向するだけですから簡単な短期トレーニングで身に付けられ、尚且つ照準微調整が不要ですから速く撃て、よく当たります。
「新スナップショットは西部劇並の早撃ちが可能」であり、それでいて確実に照準しておりますから「必ず命中」します。
「画期的な新射法」と言えます。銃を速やかに構える事でマイナスになる項目は1つも無く、「新スナップショットは全ての射撃の基本」と言えます。
動的への対応も極く自然です。まず最初に体を最終発砲状態に移行しますが、移動標的の場合は体のヘソで追尾を続けます。
銃を指向する時も当然目標を追尾しながらの指向になり、肩に引き寄せる時に体全体でスイングを加速し、追い越した時に引き金を引きます。
これが「スナップスイング射撃」です。追い越した時に 引き金を引く決断をしても発砲までは反応時間遅れにより時間を要します。
するとオーバースイングがリードとなり、これは非常に上手い事に、目標の速度と距離に自動比例してくれます。
「リード自動調整」は狭散布チョーク運用を可能とし、これに7.5号装弾との組合せは50m弱までショットガン効果の「3粒被弾撃墜」を生み、撃墜率大幅増加となります。これに対し一般的ハンターは引止まり射撃、リードが合わず撃墜率大幅低下、対策として散弾広散布チョークを使い、その結果 ショットガン効果の散弾密度に至らず、更なる撃墜率大幅低下、これを散弾パワー不足とし大粒散弾を運用、更にヒット率は低下し、撃墜率は更に更に大幅低下、「近距離&低速限定射撃に陥ります。」
新スナップショットの前提条件はチークピースの調整だけ、他の項目はアバウト、つまり市販ストックで「チークピースの調整」だけで済む事になります。その考えの基、システムストックが生まれました。
この考え方はスコープ取付け時のライフル銃にも応用出来ました。
旧来からのライフル銃には照星&照門が付いており、それは欠点の多い照準器でした。
ライフルスコープの発明は偉大でした。まず遠方の目標にも正確に照準出来ますが、イラストの様に微少上向き発射のお陰で実用照準距離が2倍になりました。

しかし視野が極端に狭いのがスコープの欠点で、素速い照準や走る目標には不向きでした。
この時、従来のスコープ銃はオープンサイトを併用する事も望んだ為、左写真の様にホッペの位置が定まらず、スコープとの位置決めは不可能となり、素速く眼がスコープを捉える事自体が不可能でした。これに対して右はケンさんとサコー75改スコープ専用銃です。


ホッペの位置がストックにより決まりますので、素速い照準が可能でした。
そしてそれは更に発展し、「スコープ専用銃はスナップショットやスナップスイングショットに依るランニング射撃」が得意項目と言える様になりました。
狩猟銃では急所が速やかに狙える事が使える条件としています。ボルトアクション銃はWW1前の1800年代末期にデビューした古い銃でしたが、ボルト銃は「スコープ専用銃で生まれ変わり、あらゆる距離のあらゆる場面で最強の狩猟銃」となりました。
1.落差無視で0~200mまで直撃が出来る。
2.遠射300mが可能である。
3.ワンホール射撃が150mで可能である。
4.アバウト早撃ち3秒が150mで可能である。
5.西部劇並の早撃ちが50m以内なら可能である。
6.未装填と安全解除を取入可能な最も安全な銃。
7.ランニングショット150mの5発5中が可能である。
前提条件にストックの調整がありますが、チークピースの調整だけで残りの項目は極めてアバウトで OKでした。
ライフルのスコープ専用銃は50m以内のショットガン効果を利用した散弾銃の連射以外、最強の銃である事が立証されました。
2024年05月05日
50年間で分かった事、その4:ショットガン効果。
12.ショットガン効果はパワー無関係の3粒被弾で撃墜。
散弾銃はバラ弾をバラ撒く銃ですが、これにも似た様な現象がありました。上半身に3粒被弾すると、1粒のパワーには概ね無関係に3粒被弾を満たすだけで、「ショットガン効果」で撃墜が可能な事を発見しました。
ショットガンは古く1850年頃からあった筈なのに、どうして1970年まで分からなかったのか?
実は近距離で撃つバックショットでは分かっており、駅馬車の護衛や保安官はショットガンを多用したのも「ショットガン効果」があったからでした。
ライフル弾は1884年の無煙火薬の発明で直ちに弾速が2倍以上に向上出来ましたが、鳥猟では散弾の構造に原因がありました。

永らくボール紙のピストンで散弾を押し出し、高圧になった火薬ガスは吹抜け易かった。
また弾速が上がると散弾粒は銃身壁に擦られ、溶けてしまいました。その為、無煙火薬によって弾速が上げられない構造にあり、初速は300m/sを下廻っておりました。
鳥猟で50mでショットガン効果により3粒被弾撃墜を満足させるには当然フルチョークの運用が前提です。
しかし旧構造散弾では初速が遅く、30m程度で弾速低下に依り無効弾となってしまい、故にやむなくもう少し大粒散弾を運用しなくてはならず、そうなるとショットガン効果成立の「3粒被弾撃墜には粒数不足」となり、鳥猟でショットガン効果を得る事は不可能だったのです。
3粒撃墜は急所である必要は無く、パワーには概ね無関係と申しましたが、ある程度は皮下まで弾粒が入らなければなりません。
それが旧構造では弾速途中低下で不可能だったのですが、右側1970年以降の新構造になりますと、ピストンは樹脂製で高圧ガスが吹抜け無くなり、散弾も樹脂製カップで、銃身壁で溶けなくなり、初速は400m/sを超える様になりました。その為、2.4㎜粒を50m弱まで無効弾にならず、3粒キープ密度で送り出す事が可能になりました。
その結果、マガモやカルガモでも50m弱で7.5号の3粒被弾撃墜が可能となりました。
急所でなくても3粒被弾で撃墜出来るのがショットガン効果の特徴でした。
鳥猟では2.4㎜粒が400個入った「7.5号 クレー射撃装弾」とフルチョークがベストパフォーマンスとなりました。
獣猟の場合は6.1㎜が27粒入った「4号バックショット」が最強装弾となり、射程は20m前後が多く適正チョークはスキート又はインプシリンダーとなります。
散弾新旧適合表
散弾重量 32 (g) 散弾サイズ㎜ 主な新用途 主な旧用途
スラグ 1 粒 18.0 使わない 熊・猪・鹿
OOO 6粒 9.14 ↑ ↑
OO 9粒 8.38 ↑ ↑
O 12粒 8.13 ↑ ↑
NO.1 16粒 7.62 ↑ 猪・鹿・中型獣
NO.3 20粒 6.35 ↑ ↑
NO.4 27粒 6.10 猪・鹿(獣猟最大効率) ↑
NO.5 38粒 5.50 中型獣 ↑
BB(号) 55粒 4.57 中型獣 沖鴨・中小型獣
1(号) 80粒 4.06 ↑ (キヨン) 遠鴨・小型獣
2(号) 95粒 3.81 使わない ↑
3(号) 123粒 3.56 ↑ ↑
4(号) 152粒 3.30 小型獣(キツネ等) ↑
5(号) 191粒 3.05 使わない 雉・山鳥
6(号) 253粒 2.79 ↑ ↑
7(号) 336粒 2.54 ↑ 雉鳩
7.5(号) 400粒 2.41 雉・山鳥・マカモ(最大効率) ↑
8(号) 461粒 2.29 ↑ ↑
9(号) 658粒 2.03 タシギ・小鳥類 ←
現在の散弾粒の序列は大きい方から、(スラグ18㎜)(OOO・9.1㎜・6粒)(OO・8.4㎜・9粒)(O・8.1㎜・12粒)と並び、次が1~5号のバックショット(7.6㎜・16粒)(6.4㎜・20粒)(6.1㎜・27粒)(5.5㎜・38粒)と続きますが、2号バックはありません。
この後にバードショット1~9号が続きますが、古い系列のBB号4.6㎜55粒だけが残っており、トラップ射撃用の7.5号2.4㎜400粒だけが少し系列外になります。
昔は7号もあり、小粒は12号まで、更に1~12号までの上にBシリーズ(BBB・4.75㎜・50粒、BB・4.50㎜・59粒、B・4.25㎜・84粒)がありました。
その上にAシリーズが(AAA・5.50㎜・32粒、AA・5.25㎜・ 37粒、A・5.00㎜・43粒)ありました。
更にその上がOシリーズ(OOO・9.1㎜・6粒)(OO・8.4㎜・9粒)(O・8.1㎜・12粒)でした。1~5号バックショットに換わり多少寸法違いですが、F・T・SG・SSG・SSSG等があり、様々な名称でした。

 ビロードキンクロとカナダガン
ビロードキンクロとカナダガン
旧用途よりもう少し昔の黒色火薬時代ではBシリーズが主に鴨用、Aシリーズは主に雁用、Oシリーズは中型獣用でした。
ケンさんが狩猟を始めた直後は旧用途時代で、黒色火薬と無煙火薬が両方使用されていましたが、市販弾は紙薬莢の無煙火薬、多くのハンターは黒色火薬の手詰めの時代でした。
市販弾の多くは銃砲店組立製でした。無煙・黒色の性能は概ね同じと言えました。
それ以前の時代では村田銃や空気銃も、かなりの数が町の銃砲店製であり、未登録銃が大手を振って横行していました。
1955年に「狩猟ブーム」が始まり、水平2連銃の時代となり、町の銃砲店製の銃は衰退して行きました。
ケンさんの狩猟を始めは1970年、この時代もカモにはBB号が多かった様に思います。
その頃はビロードキンクロと言うカルガモよりかなり大きな大型カモが20羽程の群で波状的に大量にやって来ました。
待受ける側は2m毎に1人、鴨の群が来る毎にBB号100発 前後が鳴り1~2羽が被弾し、飛行継続困難となり遠方に不時着、回収出来るのは10%も無いと言う酷いカモ撃ちでした。
誰の弾が当たったかは厚顔で手を挙げた人の物となりましたが、配慮で新人にも1羽持たせてくれました。弾数100発に対し1羽程度にしかならない低効率でした。
給料3万円時代に1発50円が100発はキツイ時代でした。これはケンさんの求めている狩猟ではなく、2度行っただけで終わりました。
2014年にケンさんがNZでカナダガン猟をした時は4号装弾を使いショットガン効果で撃墜、9発9中でした。
昔の雁撃ちはAシリーズの30~40粒クラスで撃ち、Bシリーズのカモ撃ちより散弾の粒数の比例で撃墜効率が低下し、捕獲効率は桁違いに悪かったと思われます。
この様に「ショットガン効果」の「3粒被弾撃墜」に比べ、撃墜効率は1/10を大きく下廻ったと思われます。その特殊効果を使わない場合は余程当たり場所が良くない限り撃墜回収に結び付きません。
鉛散弾の規制:すでにエゾ鹿猟では2000年から、2004年からヒグマ猟も禁止となり、2014年 からは所持その物が禁止されました。
2025年からは一般の散弾含む全てが対象となりますが、取り敢えずはモデル地区のみの実施となり、2030年を目途に全面禁止となる様です。
そうなると現在の時点ではスチール装弾5号までしか販売されておらず、「ショットガン効果」を利用した、「7.5号射撃装弾」+「フルチョーク」の組合せにより、「3粒被弾撃墜」の特殊効果が使えなくなってしまいます。
鉛の比重は11.36(鉛基準100%)、銅は8.93(78.6%)、鉄は7.87(69.3%)、錫は7.30(64.3%)、亜鉛は7.14(62.9%)、比重とコストで行けば鉄か銅と言う事になります。
ライフル弾やサボットスラグ弾では銅が使われており、散弾では主に鉄が使われています。現在市販されているのは主にスチール装弾で、同じ粒径で合計重量が同じであれば、1.44倍の粒数となります。
鉛7.5号トラップ装弾は32g時に400粒が入っています。
これで50m弱まで3粒被弾撃墜が可能です。
これと概ね同じ条件と言う事になりますと、鉄6号装弾があれば、散弾は364粒となり、鉛7.5号に比べ91%が保たれ45m前後まで3粒被弾撃墜が可能となります。
スチール弾の方がややチョークが強く作用し、もう少し善戦出来るかも知れません。
鉄6号装弾に10%以上飛行体重量を多くした、マグナム装弾があれば概ね対等と言えます。
しかし、現在は鉄5号275粒装弾までしか販売されておらず、鉛7.5号に比べ69%しか粒数が入っておらず、3粒被弾撃墜を35m弱までしか満足出来ません。
ショットガン効果の3粒被弾撃墜を満足出来なくなりますと、35mを超える射撃の撃墜は当たり場所が良かった場合に限られ、推定1桁撃墜率が下がります。
35m以下の射撃では下がらない為、総合撃墜率は推定で約半分程度になると思われます。
散弾銃はバラ弾をバラ撒く銃ですが、これにも似た様な現象がありました。上半身に3粒被弾すると、1粒のパワーには概ね無関係に3粒被弾を満たすだけで、「ショットガン効果」で撃墜が可能な事を発見しました。
ショットガンは古く1850年頃からあった筈なのに、どうして1970年まで分からなかったのか?
実は近距離で撃つバックショットでは分かっており、駅馬車の護衛や保安官はショットガンを多用したのも「ショットガン効果」があったからでした。
ライフル弾は1884年の無煙火薬の発明で直ちに弾速が2倍以上に向上出来ましたが、鳥猟では散弾の構造に原因がありました。

永らくボール紙のピストンで散弾を押し出し、高圧になった火薬ガスは吹抜け易かった。
また弾速が上がると散弾粒は銃身壁に擦られ、溶けてしまいました。その為、無煙火薬によって弾速が上げられない構造にあり、初速は300m/sを下廻っておりました。
鳥猟で50mでショットガン効果により3粒被弾撃墜を満足させるには当然フルチョークの運用が前提です。
しかし旧構造散弾では初速が遅く、30m程度で弾速低下に依り無効弾となってしまい、故にやむなくもう少し大粒散弾を運用しなくてはならず、そうなるとショットガン効果成立の「3粒被弾撃墜には粒数不足」となり、鳥猟でショットガン効果を得る事は不可能だったのです。
3粒撃墜は急所である必要は無く、パワーには概ね無関係と申しましたが、ある程度は皮下まで弾粒が入らなければなりません。
それが旧構造では弾速途中低下で不可能だったのですが、右側1970年以降の新構造になりますと、ピストンは樹脂製で高圧ガスが吹抜け無くなり、散弾も樹脂製カップで、銃身壁で溶けなくなり、初速は400m/sを超える様になりました。その為、2.4㎜粒を50m弱まで無効弾にならず、3粒キープ密度で送り出す事が可能になりました。
その結果、マガモやカルガモでも50m弱で7.5号の3粒被弾撃墜が可能となりました。
急所でなくても3粒被弾で撃墜出来るのがショットガン効果の特徴でした。
鳥猟では2.4㎜粒が400個入った「7.5号 クレー射撃装弾」とフルチョークがベストパフォーマンスとなりました。
獣猟の場合は6.1㎜が27粒入った「4号バックショット」が最強装弾となり、射程は20m前後が多く適正チョークはスキート又はインプシリンダーとなります。
散弾新旧適合表
散弾重量 32 (g) 散弾サイズ㎜ 主な新用途 主な旧用途
スラグ 1 粒 18.0 使わない 熊・猪・鹿
OOO 6粒 9.14 ↑ ↑
OO 9粒 8.38 ↑ ↑
O 12粒 8.13 ↑ ↑
NO.1 16粒 7.62 ↑ 猪・鹿・中型獣
NO.3 20粒 6.35 ↑ ↑
NO.4 27粒 6.10 猪・鹿(獣猟最大効率) ↑
NO.5 38粒 5.50 中型獣 ↑
BB(号) 55粒 4.57 中型獣 沖鴨・中小型獣
1(号) 80粒 4.06 ↑ (キヨン) 遠鴨・小型獣
2(号) 95粒 3.81 使わない ↑
3(号) 123粒 3.56 ↑ ↑
4(号) 152粒 3.30 小型獣(キツネ等) ↑
5(号) 191粒 3.05 使わない 雉・山鳥
6(号) 253粒 2.79 ↑ ↑
7(号) 336粒 2.54 ↑ 雉鳩
7.5(号) 400粒 2.41 雉・山鳥・マカモ(最大効率) ↑
8(号) 461粒 2.29 ↑ ↑
9(号) 658粒 2.03 タシギ・小鳥類 ←
現在の散弾粒の序列は大きい方から、(スラグ18㎜)(OOO・9.1㎜・6粒)(OO・8.4㎜・9粒)(O・8.1㎜・12粒)と並び、次が1~5号のバックショット(7.6㎜・16粒)(6.4㎜・20粒)(6.1㎜・27粒)(5.5㎜・38粒)と続きますが、2号バックはありません。
この後にバードショット1~9号が続きますが、古い系列のBB号4.6㎜55粒だけが残っており、トラップ射撃用の7.5号2.4㎜400粒だけが少し系列外になります。
昔は7号もあり、小粒は12号まで、更に1~12号までの上にBシリーズ(BBB・4.75㎜・50粒、BB・4.50㎜・59粒、B・4.25㎜・84粒)がありました。
その上にAシリーズが(AAA・5.50㎜・32粒、AA・5.25㎜・ 37粒、A・5.00㎜・43粒)ありました。
更にその上がOシリーズ(OOO・9.1㎜・6粒)(OO・8.4㎜・9粒)(O・8.1㎜・12粒)でした。1~5号バックショットに換わり多少寸法違いですが、F・T・SG・SSG・SSSG等があり、様々な名称でした。

 ビロードキンクロとカナダガン
ビロードキンクロとカナダガン旧用途よりもう少し昔の黒色火薬時代ではBシリーズが主に鴨用、Aシリーズは主に雁用、Oシリーズは中型獣用でした。
ケンさんが狩猟を始めた直後は旧用途時代で、黒色火薬と無煙火薬が両方使用されていましたが、市販弾は紙薬莢の無煙火薬、多くのハンターは黒色火薬の手詰めの時代でした。
市販弾の多くは銃砲店組立製でした。無煙・黒色の性能は概ね同じと言えました。
それ以前の時代では村田銃や空気銃も、かなりの数が町の銃砲店製であり、未登録銃が大手を振って横行していました。
1955年に「狩猟ブーム」が始まり、水平2連銃の時代となり、町の銃砲店製の銃は衰退して行きました。
ケンさんの狩猟を始めは1970年、この時代もカモにはBB号が多かった様に思います。
その頃はビロードキンクロと言うカルガモよりかなり大きな大型カモが20羽程の群で波状的に大量にやって来ました。
待受ける側は2m毎に1人、鴨の群が来る毎にBB号100発 前後が鳴り1~2羽が被弾し、飛行継続困難となり遠方に不時着、回収出来るのは10%も無いと言う酷いカモ撃ちでした。
誰の弾が当たったかは厚顔で手を挙げた人の物となりましたが、配慮で新人にも1羽持たせてくれました。弾数100発に対し1羽程度にしかならない低効率でした。
給料3万円時代に1発50円が100発はキツイ時代でした。これはケンさんの求めている狩猟ではなく、2度行っただけで終わりました。
2014年にケンさんがNZでカナダガン猟をした時は4号装弾を使いショットガン効果で撃墜、9発9中でした。
昔の雁撃ちはAシリーズの30~40粒クラスで撃ち、Bシリーズのカモ撃ちより散弾の粒数の比例で撃墜効率が低下し、捕獲効率は桁違いに悪かったと思われます。
この様に「ショットガン効果」の「3粒被弾撃墜」に比べ、撃墜効率は1/10を大きく下廻ったと思われます。その特殊効果を使わない場合は余程当たり場所が良くない限り撃墜回収に結び付きません。
鉛散弾の規制:すでにエゾ鹿猟では2000年から、2004年からヒグマ猟も禁止となり、2014年 からは所持その物が禁止されました。
2025年からは一般の散弾含む全てが対象となりますが、取り敢えずはモデル地区のみの実施となり、2030年を目途に全面禁止となる様です。
そうなると現在の時点ではスチール装弾5号までしか販売されておらず、「ショットガン効果」を利用した、「7.5号射撃装弾」+「フルチョーク」の組合せにより、「3粒被弾撃墜」の特殊効果が使えなくなってしまいます。
鉛の比重は11.36(鉛基準100%)、銅は8.93(78.6%)、鉄は7.87(69.3%)、錫は7.30(64.3%)、亜鉛は7.14(62.9%)、比重とコストで行けば鉄か銅と言う事になります。
ライフル弾やサボットスラグ弾では銅が使われており、散弾では主に鉄が使われています。現在市販されているのは主にスチール装弾で、同じ粒径で合計重量が同じであれば、1.44倍の粒数となります。
鉛7.5号トラップ装弾は32g時に400粒が入っています。
これで50m弱まで3粒被弾撃墜が可能です。
これと概ね同じ条件と言う事になりますと、鉄6号装弾があれば、散弾は364粒となり、鉛7.5号に比べ91%が保たれ45m前後まで3粒被弾撃墜が可能となります。
スチール弾の方がややチョークが強く作用し、もう少し善戦出来るかも知れません。
鉄6号装弾に10%以上飛行体重量を多くした、マグナム装弾があれば概ね対等と言えます。
しかし、現在は鉄5号275粒装弾までしか販売されておらず、鉛7.5号に比べ69%しか粒数が入っておらず、3粒被弾撃墜を35m弱までしか満足出来ません。
ショットガン効果の3粒被弾撃墜を満足出来なくなりますと、35mを超える射撃の撃墜は当たり場所が良かった場合に限られ、推定1桁撃墜率が下がります。
35m以下の射撃では下がらない為、総合撃墜率は推定で約半分程度になると思われます。
2024年05月02日
50年間で分かった事、その3、マグナム効果は皆無だった。
6.捕獲技術はお金で買う事は出来なかった。
 キングクラフトカスタム600万円~
キングクラフトカスタム600万円~
昔から高額なカスタム銃と言う世界がありました。上写真は国産のキングクラフトカスタム、300mで数㎝の着弾性能を立会試射で確認後の引渡しをしていました。
それ程に命中するなら、どんな獲物もバッタバッタなのか? 2000年頃、キングクラフトを持った歯科医を案内する機会がありました。100mもダメ、50mの鹿も怪しげでした。捕獲は50m以下で撃てたデメキン小物数頭だけでした。
高精度な銃はお金で買えますが、命中させる為には射撃技術と獲物に圧倒されない心が必要です。最も重要な「命中させる為の腕」と「捕獲する為の心はお金では買えない」のです。
つまり銃だけ抜群な物があっても全く役に立ちません。そして市販銃は全ての場面で捕獲に必用な精度とパワーを十分に持っています。「カスタム銃は業界の陰謀」だったのです。
7.即倒面でマグナム効果は無かった。
8.遠射面でもマグナム効果は無かった。
今や「全く無意味である事が証明されてしまったライフルのバイブル」ですが、それによれば、即倒する確率はパワーに比例すると言った感触が謳われていました。
スクール初期頃はそんな時代でしたからエゾ鹿用のライフル銃の過半は300ウインマグを筆頭としたマグナムライフルでした。
概ねStd308比で1.4倍のパワーでした。もし即倒率がパワー比例であれば、308で直径150㎜が即倒エリアであるとしたら、直径210㎜まで拡大しても即倒してくれる事になります。
これだけの差があれば目視で十分なパワー差による即倒率の違いを感じられる筈です。しかし実際のマグナムライフル射撃多数を見ましたが、「マグナムの即倒率効果は皆無」でした。
マグナムにはもう1つのメリットがあります。弾速が20%程速いのです。必ずしも20%弾速向上と40%のパワーアップは同時且つ完全には両立しませんが、弾速が速ければ落差が少なく、遠射にも有利な方向となります。一口に言えばStd308の300mと同じ落差で、350mまで行けます。
しかし実はライフル射撃の射程距離と言うのは次の様になります。
100m以遠の長距離射撃には特別な練習が必要でした。
殆ど練習しない場合は僅か20mに留まり、多少練習して50m、かなり練習しても100mを超えられず、地元猟友会がライフル銃で1年中行っている駆除でも150mは撃つ人は少なく、鹿は余り撃たれない150mにいます。
従って300mは夢のまた夢、銃と弾はすでに何度も申し上げている様にその性能を持っているのですが、それを発揮出来る射手は1%を大きく下廻る程度なのです。
つまり「300m遠射は概ね誰も出来ないのですから、弾速が速くても全く無意味」と言えました。そして射撃技術と落差補正さえ掴めば、「Std308でも300mの遠射は楽勝」でした。
エゾ鹿猟とライフル銃のブームは1990年頃、国内銃販売業者によって起こされました。
この時に国内銃販売業者は良く当たる筈のカスタムライフルと、良く倒れる筈のマグナムライフルが売り付け様としましたが、これらは全て「カスタムライフル&マグナムライフルは業界の陰謀その物でした。」
市販銃は十分な精度を持ち、マグナム効果は皆無であるにも拘らず、それらに依り捕獲率が大幅に上げると信じ込ませる、業界の陰謀だったのです。
9.銅弾は最高、良く命中し、良く倒れた。
10.即倒率100%の実用的な急所はあった。
11.急所ヒットすれば概ねパワーには無関係だった。
ライフル銃の弾頭は2000年頃から銅弾頭に変わり、初期の評判では「銅弾頭は従来鉛弾頭より命中精度が大幅に劣り」、「ヒットしても貫通するだけ倒れない」と言う風評でした。
ケンさんが実際に運用しても「なる程」と言う感触は多少ありましたが、やがてそれは従来鉛弾設定のまま銅弾頭にするから命中率が低下しますが、銅弾頭にも良い精度を出せる設定はあり、即倒も 急所に正しくヒットすれば普通に倒れ、正しく当てないので倒れなかったのです。

更に上写真の「ナミビアポイントを撃ちますと即倒率は100%」である事を発見しました。
この急所は鉛弾頭では使えなかった急所であり、「銅弾頭だから可能な急所」と言えました。
この「新開拓の急所は、即倒率100%」ですから、マグナム不要論にも完全に終止符を打つ事が出来ました。正しく急所ヒットすれば、308でも即倒即死となり、20番スラグ等の308比70%の弾頭でも、遜色なく即倒即死しました。
つまり正しく急所ヒットすれば、概ね「正しく急所ヒットすればパワーには無関係」だったのでした。
 キングクラフトカスタム600万円~
キングクラフトカスタム600万円~昔から高額なカスタム銃と言う世界がありました。上写真は国産のキングクラフトカスタム、300mで数㎝の着弾性能を立会試射で確認後の引渡しをしていました。
それ程に命中するなら、どんな獲物もバッタバッタなのか? 2000年頃、キングクラフトを持った歯科医を案内する機会がありました。100mもダメ、50mの鹿も怪しげでした。捕獲は50m以下で撃てたデメキン小物数頭だけでした。
高精度な銃はお金で買えますが、命中させる為には射撃技術と獲物に圧倒されない心が必要です。最も重要な「命中させる為の腕」と「捕獲する為の心はお金では買えない」のです。
つまり銃だけ抜群な物があっても全く役に立ちません。そして市販銃は全ての場面で捕獲に必用な精度とパワーを十分に持っています。「カスタム銃は業界の陰謀」だったのです。
7.即倒面でマグナム効果は無かった。
8.遠射面でもマグナム効果は無かった。
今や「全く無意味である事が証明されてしまったライフルのバイブル」ですが、それによれば、即倒する確率はパワーに比例すると言った感触が謳われていました。
スクール初期頃はそんな時代でしたからエゾ鹿用のライフル銃の過半は300ウインマグを筆頭としたマグナムライフルでした。
概ねStd308比で1.4倍のパワーでした。もし即倒率がパワー比例であれば、308で直径150㎜が即倒エリアであるとしたら、直径210㎜まで拡大しても即倒してくれる事になります。
これだけの差があれば目視で十分なパワー差による即倒率の違いを感じられる筈です。しかし実際のマグナムライフル射撃多数を見ましたが、「マグナムの即倒率効果は皆無」でした。
マグナムにはもう1つのメリットがあります。弾速が20%程速いのです。必ずしも20%弾速向上と40%のパワーアップは同時且つ完全には両立しませんが、弾速が速ければ落差が少なく、遠射にも有利な方向となります。一口に言えばStd308の300mと同じ落差で、350mまで行けます。
しかし実はライフル射撃の射程距離と言うのは次の様になります。
100m以遠の長距離射撃には特別な練習が必要でした。
殆ど練習しない場合は僅か20mに留まり、多少練習して50m、かなり練習しても100mを超えられず、地元猟友会がライフル銃で1年中行っている駆除でも150mは撃つ人は少なく、鹿は余り撃たれない150mにいます。
従って300mは夢のまた夢、銃と弾はすでに何度も申し上げている様にその性能を持っているのですが、それを発揮出来る射手は1%を大きく下廻る程度なのです。
つまり「300m遠射は概ね誰も出来ないのですから、弾速が速くても全く無意味」と言えました。そして射撃技術と落差補正さえ掴めば、「Std308でも300mの遠射は楽勝」でした。
エゾ鹿猟とライフル銃のブームは1990年頃、国内銃販売業者によって起こされました。
この時に国内銃販売業者は良く当たる筈のカスタムライフルと、良く倒れる筈のマグナムライフルが売り付け様としましたが、これらは全て「カスタムライフル&マグナムライフルは業界の陰謀その物でした。」
市販銃は十分な精度を持ち、マグナム効果は皆無であるにも拘らず、それらに依り捕獲率が大幅に上げると信じ込ませる、業界の陰謀だったのです。
9.銅弾は最高、良く命中し、良く倒れた。
10.即倒率100%の実用的な急所はあった。
11.急所ヒットすれば概ねパワーには無関係だった。
ライフル銃の弾頭は2000年頃から銅弾頭に変わり、初期の評判では「銅弾頭は従来鉛弾頭より命中精度が大幅に劣り」、「ヒットしても貫通するだけ倒れない」と言う風評でした。
ケンさんが実際に運用しても「なる程」と言う感触は多少ありましたが、やがてそれは従来鉛弾設定のまま銅弾頭にするから命中率が低下しますが、銅弾頭にも良い精度を出せる設定はあり、即倒も 急所に正しくヒットすれば普通に倒れ、正しく当てないので倒れなかったのです。

更に上写真の「ナミビアポイントを撃ちますと即倒率は100%」である事を発見しました。
この急所は鉛弾頭では使えなかった急所であり、「銅弾頭だから可能な急所」と言えました。
この「新開拓の急所は、即倒率100%」ですから、マグナム不要論にも完全に終止符を打つ事が出来ました。正しく急所ヒットすれば、308でも即倒即死となり、20番スラグ等の308比70%の弾頭でも、遜色なく即倒即死しました。
つまり正しく急所ヒットすれば、概ね「正しく急所ヒットすればパワーには無関係」だったのでした。
2024年04月22日
50年間で分かった事、その1。
ライフリングの発明は射程が数倍になりました。ライフルスコープも取付高を利用し微少上向き発射のお陰で、射程が2倍になり、2つの組合せはライフルの長射程の実用性を著しく向上させましたが、 スコープは「視野が狭くスナップショットは不得意」でした。所がスコープ専用銃のアイデアと銃を指向、肩に着く前に撃つと言う新射撃方法の組合せにより、「不得意項目は得意項目」に換わりました。
更にこの流れの延長は遠くを走る鹿さえもイージーターゲットとなり、これも「得意項目に換えました。」それらは過去の大発明に匹敵する素晴らしい発明と言えました。一方従来からその方面の常識と されていたライフル銃のバイブルがありました。「パワーと精度は狩猟成果に正比例、高額で強力な銃程、よく当たり、良く倒れる」と言う物でした。実際は以降の説明の様に「真っ赤な嘘」でした。
1.ライフル銃のバイブルは嘘だった。
銃身は真直ぐですが、ストックは肩に着ける為に下方に曲がっています。銃には反動があり、過渡的には反動で銃身が下に曲がり、それを戻そうとする為に銃身が振動を起こします。
振動は基本的に正弦波ですから、上下には安定期があり、この安定時期に弾が出れば、安定飛行すると言うのがライフル銃のバイブル的な考えでした。これ自体は間違ってはいないだろうと思います。
その為には2つの方法がありました。1つ目は火薬の量を微調整して弾速を変え、銃身の振動安定期に弾を通過させると言う物であり、これが王道とされていました。

自分の銃に合う弾を作る為に、火薬量を微調整した弾を多数作り、試射を繰り返し、モアパワーとモア精度を兼ねたベストポイントを求めると言う物でした。
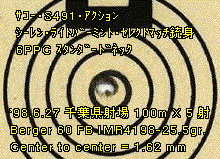
ベンチレスト射撃大会と言う物もあり、ベスト記録は100mで5発が1.08㎜であり、300mで9.82㎜射撃結果は、当然ワンホールの素晴らしい射撃となりました。
またパワー面では最大Stdカートリッジの20%増しに迫り、こう言うベストな弾を持ってエゾ鹿猟に行き、エゾ鹿の超大物を倒す事が彼らの目標と言えました。
2つ目は弾薬側の条件を固定しておき、銃身先端に反動軽減を兼ねたマズルブレーキを装着、その取付位置を微調整する事で、銃身振動定数を調整し、その安定期に弾を通過させると言う考え方でした。


ブローニング系とウインチェスター系の銃に1時期Bossシステムとして設定がありました。
理論は間違っていないとは言え、効果が無かった為か、比較的短期に立消えとなりました。
王道と言われた1つ目の火薬微調整手法も、同様に効果はかなり疑問でした。
ケンさんも試しにやって見ましたが、実験計測のプロであるケンさんがやっても安売り市販弾超えの精度の物が作れず、以後は市販弾をそのまま使いました。この時「ライフル銃のバイブル」に1回目の疑問を持ちました。
バイブルでは「市販銃と市販弾薬ではワンホール射撃は出せる可能性が無い」と言われておりました。確かのベンチレスト競技では凄いと言える結果が出ていますが、それはベンチレスト競技に特化した重装備の専用銃から出た結果でした。その特別な装備とは次の様な物でした。
 ストールパンダ6㎜PPC
ストールパンダ6㎜PPC
1.ベンチレスト専用銃+超極太銃身。
2.特別製の軽いトリガー。
3.高倍率50~80倍のスコープ。
4.銃の前後ともレストに載せた全依託射撃。
等々の実戦狩猟には決して使えない装備の数々でした。
ケンさんは1997年から根室でエゾ鹿猟をする様になりましたが、走る鹿が多く、これに命中させてやろうと思いました。弾の飛行精度は静止目標に向け発射した時と変わりない筈です。
照準合わせには至難が伴うであろうが、少なくとも比較的近くの50m、100m位までなら、何か手法があるだろうと思い、取り敢えず下記の手法に辿り着きました。

それでH&K SL7と言う高精度が謳い文句の自動銃を1998年に購入しました。そして3シーズンに 2000~3000発を走る鹿に向け発射、実用距離50mながら、5発強で1頭捕獲の「スイングショット」の入口に到達しました。当時はそれで「ランニングショット」を克服したつもりになっていました。
「高精度ワンホール射撃」も「ランニング射撃」も「遠射」も全て反動を恐れる「フリンチングが大きく絡んでいる」事にはすでに気が付いていました。
そんな時、交通事故に巻込れ、2年間弱実射が出来ませんでした。
そして1年強は弾を入れないドライファイアを繰り返しました。

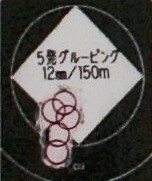
その結果、射撃には反動を伴わないと体を騙す事が出来、2002年射撃再開したその日に、150mテーブル撃ち5発が精度だけで言えば5発で9㎜が出ました。
的の中心寄りでも12㎜と言うワンホール射撃が達成されてしまいました。
銃はH&Kオート、もちろん市販ドノーマル銃、スコープは最も安売りのタスコ固定4倍、弾薬は比較的高精度の安売り市販弾と言われたラプア狩猟弾、射法は普通のテーブル撃ちでした。市販銃と市販弾でワンホール射撃が達成されたのは事実でした。
上位ベンチレストには至りませんが、「ライフル銃のバイブル」に2回目の疑問を持ちました。

その後300m遠射を達成する為に銃をサコー75改に換えました。



150m射撃は弾を安売り弾にグレードを下げた為、5発1ホールは出せず、ベスト18㎜のワンホール崩れでしたが、この時も3発なら10.0㎜、以後も3発なら13㎜・11㎜ワンホール直前が出ました。
この時「ライフル銃のバイブル」に3回目の疑問を持ちました。3回続くと言う事は最早動かし難い新しい事実が立証されたと言えました。
「ライフル銃のバイブルは全て嘘だった」だから「安売り弾の精度を超える弾を作れなかった」のであり、市販銃と市販弾で「ワンホール級射撃が可能」だったのです。
ランフル銃の最も中心的な考えが嘘だったのですから、以後も続々その立証が続きます。
更にこの流れの延長は遠くを走る鹿さえもイージーターゲットとなり、これも「得意項目に換えました。」それらは過去の大発明に匹敵する素晴らしい発明と言えました。一方従来からその方面の常識と されていたライフル銃のバイブルがありました。「パワーと精度は狩猟成果に正比例、高額で強力な銃程、よく当たり、良く倒れる」と言う物でした。実際は以降の説明の様に「真っ赤な嘘」でした。
1.ライフル銃のバイブルは嘘だった。
銃身は真直ぐですが、ストックは肩に着ける為に下方に曲がっています。銃には反動があり、過渡的には反動で銃身が下に曲がり、それを戻そうとする為に銃身が振動を起こします。
振動は基本的に正弦波ですから、上下には安定期があり、この安定時期に弾が出れば、安定飛行すると言うのがライフル銃のバイブル的な考えでした。これ自体は間違ってはいないだろうと思います。
その為には2つの方法がありました。1つ目は火薬の量を微調整して弾速を変え、銃身の振動安定期に弾を通過させると言う物であり、これが王道とされていました。

自分の銃に合う弾を作る為に、火薬量を微調整した弾を多数作り、試射を繰り返し、モアパワーとモア精度を兼ねたベストポイントを求めると言う物でした。
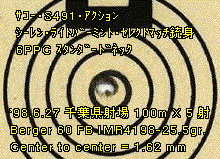
ベンチレスト射撃大会と言う物もあり、ベスト記録は100mで5発が1.08㎜であり、300mで9.82㎜射撃結果は、当然ワンホールの素晴らしい射撃となりました。
またパワー面では最大Stdカートリッジの20%増しに迫り、こう言うベストな弾を持ってエゾ鹿猟に行き、エゾ鹿の超大物を倒す事が彼らの目標と言えました。
2つ目は弾薬側の条件を固定しておき、銃身先端に反動軽減を兼ねたマズルブレーキを装着、その取付位置を微調整する事で、銃身振動定数を調整し、その安定期に弾を通過させると言う考え方でした。


ブローニング系とウインチェスター系の銃に1時期Bossシステムとして設定がありました。
理論は間違っていないとは言え、効果が無かった為か、比較的短期に立消えとなりました。
王道と言われた1つ目の火薬微調整手法も、同様に効果はかなり疑問でした。
ケンさんも試しにやって見ましたが、実験計測のプロであるケンさんがやっても安売り市販弾超えの精度の物が作れず、以後は市販弾をそのまま使いました。この時「ライフル銃のバイブル」に1回目の疑問を持ちました。
バイブルでは「市販銃と市販弾薬ではワンホール射撃は出せる可能性が無い」と言われておりました。確かのベンチレスト競技では凄いと言える結果が出ていますが、それはベンチレスト競技に特化した重装備の専用銃から出た結果でした。その特別な装備とは次の様な物でした。
 ストールパンダ6㎜PPC
ストールパンダ6㎜PPC1.ベンチレスト専用銃+超極太銃身。
2.特別製の軽いトリガー。
3.高倍率50~80倍のスコープ。
4.銃の前後ともレストに載せた全依託射撃。
等々の実戦狩猟には決して使えない装備の数々でした。
ケンさんは1997年から根室でエゾ鹿猟をする様になりましたが、走る鹿が多く、これに命中させてやろうと思いました。弾の飛行精度は静止目標に向け発射した時と変わりない筈です。
照準合わせには至難が伴うであろうが、少なくとも比較的近くの50m、100m位までなら、何か手法があるだろうと思い、取り敢えず下記の手法に辿り着きました。

それでH&K SL7と言う高精度が謳い文句の自動銃を1998年に購入しました。そして3シーズンに 2000~3000発を走る鹿に向け発射、実用距離50mながら、5発強で1頭捕獲の「スイングショット」の入口に到達しました。当時はそれで「ランニングショット」を克服したつもりになっていました。
「高精度ワンホール射撃」も「ランニング射撃」も「遠射」も全て反動を恐れる「フリンチングが大きく絡んでいる」事にはすでに気が付いていました。
そんな時、交通事故に巻込れ、2年間弱実射が出来ませんでした。
そして1年強は弾を入れないドライファイアを繰り返しました。

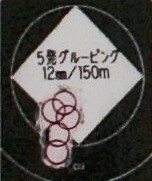
その結果、射撃には反動を伴わないと体を騙す事が出来、2002年射撃再開したその日に、150mテーブル撃ち5発が精度だけで言えば5発で9㎜が出ました。
的の中心寄りでも12㎜と言うワンホール射撃が達成されてしまいました。
銃はH&Kオート、もちろん市販ドノーマル銃、スコープは最も安売りのタスコ固定4倍、弾薬は比較的高精度の安売り市販弾と言われたラプア狩猟弾、射法は普通のテーブル撃ちでした。市販銃と市販弾でワンホール射撃が達成されたのは事実でした。
上位ベンチレストには至りませんが、「ライフル銃のバイブル」に2回目の疑問を持ちました。
その後300m遠射を達成する為に銃をサコー75改に換えました。

150m射撃は弾を安売り弾にグレードを下げた為、5発1ホールは出せず、ベスト18㎜のワンホール崩れでしたが、この時も3発なら10.0㎜、以後も3発なら13㎜・11㎜ワンホール直前が出ました。
この時「ライフル銃のバイブル」に3回目の疑問を持ちました。3回続くと言う事は最早動かし難い新しい事実が立証されたと言えました。
「ライフル銃のバイブルは全て嘘だった」だから「安売り弾の精度を超える弾を作れなかった」のであり、市販銃と市販弾で「ワンホール級射撃が可能」だったのです。
ランフル銃の最も中心的な考えが嘘だったのですから、以後も続々その立証が続きます。
2024年04月20日
50年間で分かった事。
1.ライフル銃のバイブルは嘘だった。
2.市販銃はワンホール射撃能力があった。
3.安物スコープは十分な実用性があった。
4.激安弾は十分な実用性能があった。
5.クリーニングは概ね不要だった。
6.捕獲技術はお金で買う事は出来なかった。
7.即倒面でマグナム効果は無かった。
8.遠射面でもマグナム効果は無かった。
9.銅弾は良く命中し、良く倒れた。
10.即倒率100%の実用的な急所はあった。
11.急所ヒットすれば概ねパワーには無関係で即倒した。
12.ショットガン効果はパワー無関係の3粒被弾で撃墜。
13.銃で指向する「スナップショット」は画期的技術だった。
14.スコープ専用銃は画期的な発明だった。
15.ストックの調整はチークピースの調整だけだった。
17.実射練習からフリンチング対策が出来、射撃が上達する事は無かった。
18.フリンチング対策をしなければ射程20m、射撃場通いで100m弱が限界だった。
19.失中の原因「迫力負け」等の心の不安にあった。
20.休猟区明け解禁開けフィーバーは僅か10分間だった。
21.エゾ鹿はフィーバー日(概ね6日サイクルの悪天候明け)に一斉に行動する。
22.フィーバー日以外は鹿に出会えない3流ガイド。
23.繁殖期のエゾ鹿は広い場所で順番に自己の存在をアピールする。
24.紋別のエゾ鹿のベストシーズンは10月下旬からの4週間だった。
25.根室のエゾ鹿のベストシーズンは12月中旬からの4週間だった
26.全依託射撃が出来れば300mは外れない。
27.ワンホールが出来ると150mアバウト早撃ちが出来る。
28.肉眼で見える「映像」は0.4秒程古い「虚像」であり、「実体は別の所」にあった。
30.リード自動調整の「スイングショット」は、散弾銃もライフル銃にも使えた。
31.散弾銃の引き止まり、ライフルの照準ブレ、原因は全て「フリンチング」だった。
32.「狩猟ブーム」は銃業界がWW2後不況対策で興し、日本に1955年頃伝わった。
33.「マグナム銃」と「カスタム銃」も同様目的であったが、「銃業界の陰謀」だった。
34.1990年頃日本の銃販売業界が「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームを起こした。
35.本州鹿巻狩りは射撃勝負ではなく、気配先取り勝負だった。
36.丸見えの場所で見張りを辞め、微動もしないで待つ「禅の心作戦」が有効だった。
37.本州鹿は季節的な移動をしないが、流し猟が可能だった。
38.エゾ鹿猟は桁違いの良い環境だった。
39.ドッグレスは最高の猟であった。
以下順番に次回から詳細説明に入ります。
2.市販銃はワンホール射撃能力があった。
3.安物スコープは十分な実用性があった。
4.激安弾は十分な実用性能があった。
5.クリーニングは概ね不要だった。
6.捕獲技術はお金で買う事は出来なかった。
7.即倒面でマグナム効果は無かった。
8.遠射面でもマグナム効果は無かった。
9.銅弾は良く命中し、良く倒れた。
10.即倒率100%の実用的な急所はあった。
11.急所ヒットすれば概ねパワーには無関係で即倒した。
12.ショットガン効果はパワー無関係の3粒被弾で撃墜。
13.銃で指向する「スナップショット」は画期的技術だった。
14.スコープ専用銃は画期的な発明だった。
15.ストックの調整はチークピースの調整だけだった。
17.実射練習からフリンチング対策が出来、射撃が上達する事は無かった。
18.フリンチング対策をしなければ射程20m、射撃場通いで100m弱が限界だった。
19.失中の原因「迫力負け」等の心の不安にあった。
20.休猟区明け解禁開けフィーバーは僅か10分間だった。
21.エゾ鹿はフィーバー日(概ね6日サイクルの悪天候明け)に一斉に行動する。
22.フィーバー日以外は鹿に出会えない3流ガイド。
23.繁殖期のエゾ鹿は広い場所で順番に自己の存在をアピールする。
24.紋別のエゾ鹿のベストシーズンは10月下旬からの4週間だった。
25.根室のエゾ鹿のベストシーズンは12月中旬からの4週間だった
26.全依託射撃が出来れば300mは外れない。
27.ワンホールが出来ると150mアバウト早撃ちが出来る。
28.肉眼で見える「映像」は0.4秒程古い「虚像」であり、「実体は別の所」にあった。
30.リード自動調整の「スイングショット」は、散弾銃もライフル銃にも使えた。
31.散弾銃の引き止まり、ライフルの照準ブレ、原因は全て「フリンチング」だった。
32.「狩猟ブーム」は銃業界がWW2後不況対策で興し、日本に1955年頃伝わった。
33.「マグナム銃」と「カスタム銃」も同様目的であったが、「銃業界の陰謀」だった。
34.1990年頃日本の銃販売業界が「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームを起こした。
35.本州鹿巻狩りは射撃勝負ではなく、気配先取り勝負だった。
36.丸見えの場所で見張りを辞め、微動もしないで待つ「禅の心作戦」が有効だった。
37.本州鹿は季節的な移動をしないが、流し猟が可能だった。
38.エゾ鹿猟は桁違いの良い環境だった。
39.ドッグレスは最高の猟であった。
以下順番に次回から詳細説明に入ります。
2024年04月14日
白糠のメス特別解禁。1994年。
メス鹿が特別解禁1994年1月16日~31日、
永らく禁猟であったメス鹿が特別解禁されました。解禁の前日までのメスは本当に道端にゴロゴロおり、メスなら幾らでも獲れると思った人も多いと思います。

メス解禁前は朝7時頃林道を走りますと、カーブを10~20回程曲がれば、撃たれないメス鹿の群れがいました。またカーブを10~20回ほど曲がりますと次の群れがいます。
こんな光景が毎日約一時間続きます。夕方でもその半分位を見る事が出来ました。元GUN誌のW編集長の狩猟能力は驚く程に酷いのですが、それでもメス解禁に白糠のメスなら「オレでも獲り放題」と、鹿肉の注文をたくさん集めて来ました。
当時メス鹿はこれ程いたので、メスが撃てるとあらば、獲り放題誰もがそう思いました。
初のメス解禁の日には記録破りの驚く程の人出となりました。実際に林道のメインストリ-トは100mに1台程の車がウジャウジャおりました。どの車にも2~3人が乗っております。あれ程たくさん居た筈のメス鹿はすでに1頭も見えません。
余りの車の量に鹿の動きが全く止まってしまった様でした。
ケンさんはこれでは鹿に出会う事が難しいと感じ、すぐさまマイナー林道に入りました。
やがて解禁の時間と共に、銃声が連続十数秒続きました。如何にハンターが多かったのか想像が付きます。
間もなくケンさん達もメス3頭の群れに50m強で出会いましたが、編集長は心が定まっておらず失中、ケンさんはダブル捕獲でした。その後ケンさんは更にもう1頭を捕獲しました。
午前中の出会いはそれで終わりましたが、その日の夕方も、2日目も朝夕、更にその翌日も、あれ程居たメス鹿は1頭も見る事がなくなりました。
4日目の少し遅目の朝に1度だけ鹿が急に動き出しまし、またそこで1頭を頂く事が出来、ケンさんはその翌日帰りました。
しかし編集長はその後更に1週間猟をしましたが、あれ程たくさん道端に居たメス鹿は、その後遂に1頭も見る事がなかったそうです。全く見事なメス鹿群れの豹変でした。
メインの林道の道端には鹿捕獲の痕跡が約1㎞毎にありましたが、あの100mに1台の膨大な車の量からすれば、獲れたのは10台に1台程度、獲れなかったガッカリ組が殆どではなかったかと思います。
オスも猟期前半はメスに惹かれて動きますので、従来はオスも多少姿を見る事が出来たのですが、メスがハンターに追われた以降は、オスの出会いも激減しました。
その翌年、ケンさんは白糠山奥で脱輪させ、回収は来春を覚悟しましたが、Hプロに助けられました。休猟明けから数年、特にメス特別解禁の後の白糠は、出会いが極端に少なくなりました。
それ故にHプロも来年から休猟明けとなる根室に移ろうと思っており、ガイドも出来るので良かったら来ないかとの誘いを受けました。車を助けてもらったお礼を兼ね、ガイド猟を試す事にしました。
白糠のエゾ鹿の単独流し猟。1996年。
花巻合同の白糠民宿巻狩りは何年やっても獲れないので解散、ケンさんは単独流し猟を計画しました。そこで北大駐在のボロパジェロを白糠まで回送してくれるように依頼しました。
日頃諸経費全てをこちら持ちで何年も無料運行しているのですから、それに応じて当然と言えました。また状況が変わり、車を引き上げる事になっても、言うべき言葉は「永らく無料で使わさせて頂き、ありがとうございました」になる筈です。
しかしW編集長の長男はグズグズ言って逃れ様とし、車をゴネ得しようとしました。何時の間にか原則を忘れ、人の褌でイイカッコするのが、当たり前になってしまったのでした。
それで頭に来まして、北大の寮まで取りに行きました。
勿論日時は事前に連絡してありますが、予想通り居留守でした。
車を預けておく方法は上手く行かない事が判りました。
駐車場で車を探し出し、寮の管理人に車を引き上げる旨の連絡を残し、持参のスペアキーで持ち帰りました。1996年からケンさんは白糠の単独流し猟を行い、概ね1日1頭を捕獲が可能となりました。


さてケンさんは概ね1日1頭が獲れた流し猟ですが、誰でも獲れるのか?
ケンさんの地元からも「狩猟界」流し猟成功記事に刺激された有志3組が、ガイドレス自前流し猟に挑戦しましたが、実戦1週間ずつ3年通っても、残念ながら全て撃沈でした。
また白糠同宿の流し猟6組も連日捕獲ゼロが続いていました。エゾ鹿猟は誰でも獲れる程甘くはないのです。多くのハンターは「銃業界」と「狩猟界」合同の陰謀により、無駄な出費と努力を強いられました。
永らく禁猟であったメス鹿が特別解禁されました。解禁の前日までのメスは本当に道端にゴロゴロおり、メスなら幾らでも獲れると思った人も多いと思います。
メス解禁前は朝7時頃林道を走りますと、カーブを10~20回程曲がれば、撃たれないメス鹿の群れがいました。またカーブを10~20回ほど曲がりますと次の群れがいます。
こんな光景が毎日約一時間続きます。夕方でもその半分位を見る事が出来ました。元GUN誌のW編集長の狩猟能力は驚く程に酷いのですが、それでもメス解禁に白糠のメスなら「オレでも獲り放題」と、鹿肉の注文をたくさん集めて来ました。
当時メス鹿はこれ程いたので、メスが撃てるとあらば、獲り放題誰もがそう思いました。
初のメス解禁の日には記録破りの驚く程の人出となりました。実際に林道のメインストリ-トは100mに1台程の車がウジャウジャおりました。どの車にも2~3人が乗っております。あれ程たくさん居た筈のメス鹿はすでに1頭も見えません。
余りの車の量に鹿の動きが全く止まってしまった様でした。
ケンさんはこれでは鹿に出会う事が難しいと感じ、すぐさまマイナー林道に入りました。
やがて解禁の時間と共に、銃声が連続十数秒続きました。如何にハンターが多かったのか想像が付きます。
間もなくケンさん達もメス3頭の群れに50m強で出会いましたが、編集長は心が定まっておらず失中、ケンさんはダブル捕獲でした。その後ケンさんは更にもう1頭を捕獲しました。
午前中の出会いはそれで終わりましたが、その日の夕方も、2日目も朝夕、更にその翌日も、あれ程居たメス鹿は1頭も見る事がなくなりました。
4日目の少し遅目の朝に1度だけ鹿が急に動き出しまし、またそこで1頭を頂く事が出来、ケンさんはその翌日帰りました。
しかし編集長はその後更に1週間猟をしましたが、あれ程たくさん道端に居たメス鹿は、その後遂に1頭も見る事がなかったそうです。全く見事なメス鹿群れの豹変でした。
メインの林道の道端には鹿捕獲の痕跡が約1㎞毎にありましたが、あの100mに1台の膨大な車の量からすれば、獲れたのは10台に1台程度、獲れなかったガッカリ組が殆どではなかったかと思います。
オスも猟期前半はメスに惹かれて動きますので、従来はオスも多少姿を見る事が出来たのですが、メスがハンターに追われた以降は、オスの出会いも激減しました。
その翌年、ケンさんは白糠山奥で脱輪させ、回収は来春を覚悟しましたが、Hプロに助けられました。休猟明けから数年、特にメス特別解禁の後の白糠は、出会いが極端に少なくなりました。
それ故にHプロも来年から休猟明けとなる根室に移ろうと思っており、ガイドも出来るので良かったら来ないかとの誘いを受けました。車を助けてもらったお礼を兼ね、ガイド猟を試す事にしました。
白糠のエゾ鹿の単独流し猟。1996年。
花巻合同の白糠民宿巻狩りは何年やっても獲れないので解散、ケンさんは単独流し猟を計画しました。そこで北大駐在のボロパジェロを白糠まで回送してくれるように依頼しました。
日頃諸経費全てをこちら持ちで何年も無料運行しているのですから、それに応じて当然と言えました。また状況が変わり、車を引き上げる事になっても、言うべき言葉は「永らく無料で使わさせて頂き、ありがとうございました」になる筈です。
しかしW編集長の長男はグズグズ言って逃れ様とし、車をゴネ得しようとしました。何時の間にか原則を忘れ、人の褌でイイカッコするのが、当たり前になってしまったのでした。
それで頭に来まして、北大の寮まで取りに行きました。
勿論日時は事前に連絡してありますが、予想通り居留守でした。
車を預けておく方法は上手く行かない事が判りました。
駐車場で車を探し出し、寮の管理人に車を引き上げる旨の連絡を残し、持参のスペアキーで持ち帰りました。1996年からケンさんは白糠の単独流し猟を行い、概ね1日1頭を捕獲が可能となりました。
さてケンさんは概ね1日1頭が獲れた流し猟ですが、誰でも獲れるのか?
ケンさんの地元からも「狩猟界」流し猟成功記事に刺激された有志3組が、ガイドレス自前流し猟に挑戦しましたが、実戦1週間ずつ3年通っても、残念ながら全て撃沈でした。
また白糠同宿の流し猟6組も連日捕獲ゼロが続いていました。エゾ鹿猟は誰でも獲れる程甘くはないのです。多くのハンターは「銃業界」と「狩猟界」合同の陰謀により、無駄な出費と努力を強いられました。
2024年03月28日
新射撃法のメリット。
5.「新スナップショット」と「スナップスイングショット」
1秒早く撃てる事は射程の短い散弾銃猟では発砲チャンスが大幅増、且つ濃い散弾に依り「撃墜率大幅向上」の効果がありました。
移動目標の場合は体全体で目標追尾しながら、指向スイング中の銃を肩に引き寄せながら、更にスイングを加速しながら、一定リズムで追い越した時点で、引き金を引きます。肩に銃が着くのを待つ必要は無く、この考え方はライフル射撃の200m以内にもそのまま使えます。
この時に引止まり射撃に陥らない事が最重要ですが、ショットガン射撃に通用する程度であれば、この追越して引き金を引く、イメージトレーニングと素振りのトレーニングで、確立出来ると思われます。
これが「スナップスイング射撃」と言う射撃方法になり、ショットガン猟で最も多用する、リード自動調整の高撃墜率の射撃方法となります。但しこの射撃方法を出来る人は巷には殆どいません。
6.スイングショット。
追い越す時に引き金を引く「スイング射撃」により、リードが何時も自動調整され、従来射法の「近距離&低速専用限定」は解除、本項単独で「撃墜率数倍向上」がありました。
一般射法ではリードは射撃距離や飛行速度により大きく変動しますが、これが自動調整される事は非常に有意義でした。
追い越した時に引き金を引く決断をしても、実際に弾の出るのは神経の反応遅れ等により、この間も加速したスイングは進行し、これがオーバースイングとなり、それがリードとなります。
一定リズムで追い越す様に心掛けますと、このオーバースイング量は目標の速度に正比例し、また 同時にそのスイング角度の開いた先は大きくなり、自動的に距離にも比例する事になります。
つまり弾速が一定とすれば、一定リズムで追い越す時に撃てば、リードの調整は完全に自動化され、高確率な自動命中が可能となります。
実質的に従来射法ではリード合わせが毎回違い、それを合わせる事は困難となり、「近距離&低速に限定」ですが、スイング射法であれば、その低い次元の限定から解放され、遠距離まで、そして高速まで、リードは広範囲で自動調整可となります。
しかし実際は小粒弾の弾速は途中低下が大きく、射撃距離により多少のリード追加側の調整を要しますが、その補正の難度は引止まり射撃のリード程の大規模高難度ではなく、容易です。
つまりスイング射撃をマスターすれば、散弾の命中率は最大1桁、格段に上がります。
これが散弾散布域の狭いフルチョーク運用を可能にし、濃い散弾密度を遠方までキープさせられます。そして7.5号の2.4㎜400粒の小粒弾運用と併せますと、50mまで4項の「3粒被弾撃墜」の「ショットガン効果」の運用を可能にし、劇的な撃墜率向上が可能となります。
7.高速3連射。
スイング射撃のマスターに依り、ショットガン射撃は従来の引止まり射撃より、遥か遠方の遥かに高速の獲物まで対応可能になりますが、追い風に乗った高速時の遠射までは及びません。
フルチョークの濃い弾幕を、秒速3発の高速連射で散弾パターンを横長弾幕で撃ち出せば、これに鳥を飛び込ませる事が可能となり、遠射高速時までカバー範囲が広がります。
またこの延長で群れに対しパターンを斜め袈裟掛け的に被せると、「複数瞬時撃墜」が可能になりました。
8.クレー射撃用7.5号小粒装弾。
7.5号装弾は狩猟用装弾の半額価格が魅力です。
小粒ですが弾粒数が多く、弾速途中低下分のリードを追加すれば50mまで無効化せず、フルチョーク時には、3粒被弾密度を50mまで送り込む事が可能となり、「ショットガン効果」の恩恵を十分に利用する事が出来ました。
「ショットガン効果」は3粒被弾すれば、「1粒の威力には概ね無関係に撃墜出来る」、ショットガンに取って非常に有難い特殊現象です。
この現象は1970年以降の400m/sのプラ薬莢7.5号弾をフルチョークで運用した時だけ、その恩恵を受けられます。それ以前の古い時代の7.5号装弾は構造的に、弾速は280m/sの低速であり、30mで無効弾となりました。
ケンさんと一般射手は4項の前表の様な違いがあり、その大きな効果は「新スナップショット」+リード自動調整「スイングショット」で命中率が1桁向上します。
それ故に狭い散弾散布の「フルチョーク」の運用が可能となり、「7.5号小粒弾」運用と併せると50mまで「3粒被弾無条件撃墜のショットガン効果」の利用が可能になった事で、また1桁撃墜率が向上しました。
「ショットガン効果」は「フルチョーク+7.5号装弾」時だけで得られ、1粒のパワーに概ね無関係な特殊効果です。
他の大粒装弾を使用時や7.5号弾運用時でも散弾散布範囲の広いチョークを運用した時は、散弾密度不足から「3粒被弾」定義を満たさず、効果抜群の「ショットガン効果」が利用出来なくなり、その時の撃墜は当たり所の良かった時だけに限られました。
 600羽捕獲の害鳥駆除。
600羽捕獲の害鳥駆除。
9.フルチョークの運用。
昔のフルチョークは32インチ以上の銃身に多く、長いから遠くまで届くのではなく、引止まり弊害減少の為、Maxでは40インチ等と言う、とんでもない長さの銃身もありました。
 40インチブロ-ニングスライド銃
40インチブロ-ニングスライド銃
1970~1990は30インチに多く、昨今のインナーチョークになってからは26インチ以下の銃身にもフルチョークが使われる様になりました。
射撃性能から言えば、長銃身側が優れていますが、長過ぎて取り廻しが悪く、ケンさんは特注24インチ銃身にバランサーを付け、又パッドエンドのピッチダウンを少し変え、30インチに劣らない感触となりました。
猟友会駆除従事者12名は射撃成績順に選抜するのですが、実戦能力の高いハンターは存在せず、その結果射撃技術比較表の複利効果で、12人害鳥捕獲数の過半を1人で捕獲すると言う、快挙が時々起こりました。
遡ればケンさんは1982年(32才)で猟友会役員になりましたが、それ以前の駆除は戦力外メンバーだけで行っており、駆除成果はピーク時からすれば2桁少い状態でした。
そこでケンさんはまず自らが実績を示しながら、実戦射撃の上手い若い猟友会員数人を役人に推薦しました。その結果、駆除成果は1桁上がり、ケンさん分を合計すると、更にそれが2倍になりました。
ケンさんのピーク能力は2006年(56才)前後の数年でした。2008年カルガモ駆除は28チャンス50発から、32羽を捕獲、ベスト記録である1.6発/羽を出しました。
またトラップ射撃も32g装弾ですが、国際式トラップ64枚連続をSKB1900-30インチで出しましたが、その頃はクレー射撃が今とはヒックにならんほどレベルが高くなっており、ケンさんはその好成績でも田舎親善大会成績は3位でした。
24インチ改では24g装弾フィールド式トラップ15mで54発連続、また5mダブルトラップ連続58枚ヒットとなり、この頃はクレー射撃のレエルが全体に下がり、時々優勝しました。
又2012年ニュージーランドのカナダガン猟では9発9中が成功、この時はレミントン1100レンタル銃のチークピースをガムテープで数㎜修正しました。
2017年にはニュージーランドでパラダイスダックと言うカルガモ2倍サイズのツクシガモ類を、85発で47羽を捕獲と言う、海外猟ならではの大記録を出せました。
ケンさんはこの様に67才頃まで、能力低下を奇跡的に免れる事が出来ました。
10.高齢者に依る害鳥駆除。
害鳥駆除のピーク成果から40年余が過ぎ、当時の駆除メンバーは過半が銃を卒業、ケンさんも68才で卒業、残ったメンバーも飛鳥撃墜能力は概ね全員が無くなりました。
昨今の我が地元猟友会の 害鳥駆除は、その結果としてピーク時の2桁ダウンに近い駆除成果に戻り、低迷して来ました。
これは恐らく、全国何処も類似現象であり、駆除に参加するのは戦力外老人ばかり、捕獲能力は殆ど無く、有害鳥獣駆除事業は税金泥棒と化して来ました。
下記の様に狩猟もバレーボールと同じで年齢的リミットは65才の様です。
ケンさんのバレーボールは30才前後で中断、55歳頃に誘われ再開、幾つかのサークルに所属しておりましたが、そのサークルはどれもそれ程長く持続せずでした。
60才前後から同年代メンバーはボールに反応が出来なくなり、全てのサークルはメンバー不足、流れ解散となりました。
趣味の狩猟は獲れなくても構いませんが、公的資金の駆除が税金泥棒なのです。
ケンさんスクールエリアでも戦力外駆除ハンターは一般ハンターの捕獲手助けをする名目で北海道から手当てを貰い、実際は駆除の利権を守ろうと、彼らの上げ足を取って葬り去ろうとしていました。
現状の駆除従事者は技能講習免除となっており、明らかに実戦能力の無いハンターが駆除を継続 してます。
駆除従事者は一般ハンターより高レベルな学科試験や実技試験(高度飛鳥撃墜能力&150mの実戦ライフル能力)で税金泥棒メンバーを排除、成果を出せるハンターが従事する様にしなければなりません。
現状の単なる日当稼ぎの税金泥棒では出動させる意味は全くありません。
ヒグマ駆除やエゾ鹿駆除ハンターに付いてはハンターの数も問題ですが、使える人材の育成が必要と言えます。
具体的には長い経験年数を要する必要性から、高齢者となりがちですが、安全で高命中率の新しい射撃技術をマスターしている事が重要項目だと言えます。
一方では能力低下が基準値内である事を毎年確認する為の一般ハンターの技能講習より高レベルの試験を毎年課すべきで、毎年入札を兼ね、学科や実技で予選会を催すのも良いかも知れません。
これで所定レベルに至らない人の駆除ライセンスをはく奪し、駆除従事者は成績の良い方から必要数を採用すれば良いと思われます。
1秒早く撃てる事は射程の短い散弾銃猟では発砲チャンスが大幅増、且つ濃い散弾に依り「撃墜率大幅向上」の効果がありました。
移動目標の場合は体全体で目標追尾しながら、指向スイング中の銃を肩に引き寄せながら、更にスイングを加速しながら、一定リズムで追い越した時点で、引き金を引きます。肩に銃が着くのを待つ必要は無く、この考え方はライフル射撃の200m以内にもそのまま使えます。
この時に引止まり射撃に陥らない事が最重要ですが、ショットガン射撃に通用する程度であれば、この追越して引き金を引く、イメージトレーニングと素振りのトレーニングで、確立出来ると思われます。
これが「スナップスイング射撃」と言う射撃方法になり、ショットガン猟で最も多用する、リード自動調整の高撃墜率の射撃方法となります。但しこの射撃方法を出来る人は巷には殆どいません。
6.スイングショット。
追い越す時に引き金を引く「スイング射撃」により、リードが何時も自動調整され、従来射法の「近距離&低速専用限定」は解除、本項単独で「撃墜率数倍向上」がありました。
一般射法ではリードは射撃距離や飛行速度により大きく変動しますが、これが自動調整される事は非常に有意義でした。
追い越した時に引き金を引く決断をしても、実際に弾の出るのは神経の反応遅れ等により、この間も加速したスイングは進行し、これがオーバースイングとなり、それがリードとなります。
一定リズムで追い越す様に心掛けますと、このオーバースイング量は目標の速度に正比例し、また 同時にそのスイング角度の開いた先は大きくなり、自動的に距離にも比例する事になります。
つまり弾速が一定とすれば、一定リズムで追い越す時に撃てば、リードの調整は完全に自動化され、高確率な自動命中が可能となります。
実質的に従来射法ではリード合わせが毎回違い、それを合わせる事は困難となり、「近距離&低速に限定」ですが、スイング射法であれば、その低い次元の限定から解放され、遠距離まで、そして高速まで、リードは広範囲で自動調整可となります。
しかし実際は小粒弾の弾速は途中低下が大きく、射撃距離により多少のリード追加側の調整を要しますが、その補正の難度は引止まり射撃のリード程の大規模高難度ではなく、容易です。
つまりスイング射撃をマスターすれば、散弾の命中率は最大1桁、格段に上がります。
これが散弾散布域の狭いフルチョーク運用を可能にし、濃い散弾密度を遠方までキープさせられます。そして7.5号の2.4㎜400粒の小粒弾運用と併せますと、50mまで4項の「3粒被弾撃墜」の「ショットガン効果」の運用を可能にし、劇的な撃墜率向上が可能となります。
7.高速3連射。
スイング射撃のマスターに依り、ショットガン射撃は従来の引止まり射撃より、遥か遠方の遥かに高速の獲物まで対応可能になりますが、追い風に乗った高速時の遠射までは及びません。
フルチョークの濃い弾幕を、秒速3発の高速連射で散弾パターンを横長弾幕で撃ち出せば、これに鳥を飛び込ませる事が可能となり、遠射高速時までカバー範囲が広がります。
またこの延長で群れに対しパターンを斜め袈裟掛け的に被せると、「複数瞬時撃墜」が可能になりました。
8.クレー射撃用7.5号小粒装弾。
7.5号装弾は狩猟用装弾の半額価格が魅力です。
小粒ですが弾粒数が多く、弾速途中低下分のリードを追加すれば50mまで無効化せず、フルチョーク時には、3粒被弾密度を50mまで送り込む事が可能となり、「ショットガン効果」の恩恵を十分に利用する事が出来ました。
「ショットガン効果」は3粒被弾すれば、「1粒の威力には概ね無関係に撃墜出来る」、ショットガンに取って非常に有難い特殊現象です。
この現象は1970年以降の400m/sのプラ薬莢7.5号弾をフルチョークで運用した時だけ、その恩恵を受けられます。それ以前の古い時代の7.5号装弾は構造的に、弾速は280m/sの低速であり、30mで無効弾となりました。
ケンさんと一般射手は4項の前表の様な違いがあり、その大きな効果は「新スナップショット」+リード自動調整「スイングショット」で命中率が1桁向上します。
それ故に狭い散弾散布の「フルチョーク」の運用が可能となり、「7.5号小粒弾」運用と併せると50mまで「3粒被弾無条件撃墜のショットガン効果」の利用が可能になった事で、また1桁撃墜率が向上しました。
「ショットガン効果」は「フルチョーク+7.5号装弾」時だけで得られ、1粒のパワーに概ね無関係な特殊効果です。
他の大粒装弾を使用時や7.5号弾運用時でも散弾散布範囲の広いチョークを運用した時は、散弾密度不足から「3粒被弾」定義を満たさず、効果抜群の「ショットガン効果」が利用出来なくなり、その時の撃墜は当たり所の良かった時だけに限られました。
 600羽捕獲の害鳥駆除。
600羽捕獲の害鳥駆除。9.フルチョークの運用。
昔のフルチョークは32インチ以上の銃身に多く、長いから遠くまで届くのではなく、引止まり弊害減少の為、Maxでは40インチ等と言う、とんでもない長さの銃身もありました。
 40インチブロ-ニングスライド銃
40インチブロ-ニングスライド銃1970~1990は30インチに多く、昨今のインナーチョークになってからは26インチ以下の銃身にもフルチョークが使われる様になりました。
射撃性能から言えば、長銃身側が優れていますが、長過ぎて取り廻しが悪く、ケンさんは特注24インチ銃身にバランサーを付け、又パッドエンドのピッチダウンを少し変え、30インチに劣らない感触となりました。
猟友会駆除従事者12名は射撃成績順に選抜するのですが、実戦能力の高いハンターは存在せず、その結果射撃技術比較表の複利効果で、12人害鳥捕獲数の過半を1人で捕獲すると言う、快挙が時々起こりました。
遡ればケンさんは1982年(32才)で猟友会役員になりましたが、それ以前の駆除は戦力外メンバーだけで行っており、駆除成果はピーク時からすれば2桁少い状態でした。
そこでケンさんはまず自らが実績を示しながら、実戦射撃の上手い若い猟友会員数人を役人に推薦しました。その結果、駆除成果は1桁上がり、ケンさん分を合計すると、更にそれが2倍になりました。
ケンさんのピーク能力は2006年(56才)前後の数年でした。2008年カルガモ駆除は28チャンス50発から、32羽を捕獲、ベスト記録である1.6発/羽を出しました。
またトラップ射撃も32g装弾ですが、国際式トラップ64枚連続をSKB1900-30インチで出しましたが、その頃はクレー射撃が今とはヒックにならんほどレベルが高くなっており、ケンさんはその好成績でも田舎親善大会成績は3位でした。
24インチ改では24g装弾フィールド式トラップ15mで54発連続、また5mダブルトラップ連続58枚ヒットとなり、この頃はクレー射撃のレエルが全体に下がり、時々優勝しました。
又2012年ニュージーランドのカナダガン猟では9発9中が成功、この時はレミントン1100レンタル銃のチークピースをガムテープで数㎜修正しました。
2017年にはニュージーランドでパラダイスダックと言うカルガモ2倍サイズのツクシガモ類を、85発で47羽を捕獲と言う、海外猟ならではの大記録を出せました。
ケンさんはこの様に67才頃まで、能力低下を奇跡的に免れる事が出来ました。
10.高齢者に依る害鳥駆除。
害鳥駆除のピーク成果から40年余が過ぎ、当時の駆除メンバーは過半が銃を卒業、ケンさんも68才で卒業、残ったメンバーも飛鳥撃墜能力は概ね全員が無くなりました。
昨今の我が地元猟友会の 害鳥駆除は、その結果としてピーク時の2桁ダウンに近い駆除成果に戻り、低迷して来ました。
これは恐らく、全国何処も類似現象であり、駆除に参加するのは戦力外老人ばかり、捕獲能力は殆ど無く、有害鳥獣駆除事業は税金泥棒と化して来ました。
下記の様に狩猟もバレーボールと同じで年齢的リミットは65才の様です。
ケンさんのバレーボールは30才前後で中断、55歳頃に誘われ再開、幾つかのサークルに所属しておりましたが、そのサークルはどれもそれ程長く持続せずでした。
60才前後から同年代メンバーはボールに反応が出来なくなり、全てのサークルはメンバー不足、流れ解散となりました。
趣味の狩猟は獲れなくても構いませんが、公的資金の駆除が税金泥棒なのです。
ケンさんスクールエリアでも戦力外駆除ハンターは一般ハンターの捕獲手助けをする名目で北海道から手当てを貰い、実際は駆除の利権を守ろうと、彼らの上げ足を取って葬り去ろうとしていました。
現状の駆除従事者は技能講習免除となっており、明らかに実戦能力の無いハンターが駆除を継続 してます。
駆除従事者は一般ハンターより高レベルな学科試験や実技試験(高度飛鳥撃墜能力&150mの実戦ライフル能力)で税金泥棒メンバーを排除、成果を出せるハンターが従事する様にしなければなりません。
現状の単なる日当稼ぎの税金泥棒では出動させる意味は全くありません。
ヒグマ駆除やエゾ鹿駆除ハンターに付いてはハンターの数も問題ですが、使える人材の育成が必要と言えます。
具体的には長い経験年数を要する必要性から、高齢者となりがちですが、安全で高命中率の新しい射撃技術をマスターしている事が重要項目だと言えます。
一方では能力低下が基準値内である事を毎年確認する為の一般ハンターの技能講習より高レベルの試験を毎年課すべきで、毎年入札を兼ね、学科や実技で予選会を催すのも良いかも知れません。
これで所定レベルに至らない人の駆除ライセンスをはく奪し、駆除従事者は成績の良い方から必要数を採用すれば良いと思われます。
2024年03月19日
全ての射撃のベースとなる正しい「スナップショット」
スナップショットは「西部劇並の早撃ち」ながら、確実に急所を撃ち抜く「新射法」です。
銃を素速く正確に撃てる事は、如何なる場面に於いても有利であり、全ての射撃の基本と言え、ケンさんは銃を扱う事が出来ると言う事は、「スナップショットが出来る」と言う言葉に置き換えられると思っています。
またボルト銃の「スナップショット」は「装填」と「安全装置解除」を入れても、殆ど時間は変わらずに操作出来、これをマスターすれば、銃は画期的に「安全」な物になり、且つ最強の狩猟道具となります。
1.スナップショットのやり方。



1.スナップショットは発砲決断と同時に体を前傾させ中写真の様な「発砲直前状態」に移行します。
2.同時に銃身或いはスコープの延長が、目の高さで、目標を正しく指で指す様に指向します。
この時の指向精度が照準精度になりますから、練習を繰り返します。
右写真の状態で構えてもスコープからは何も見えませんが、
すでに目標への志向は完了し、命中要件は概ね揃っています。
3.ホッペをかすめる様に銃を肩に引き寄せながら、至近距離で撃てば目標の急所に命中します。
50m以内であり、心に予めそのつもりがあれば、銃が肩に着くより少し手前から
スコープを通して、やや不完全ながら下写真の様な映像が目に飛び込んで来ます。

急所の直径は15㎝程度であり、そのド真ん中にヒットさせる必要はなく、要件を満たしていれば、そのまま撃ち、満たしていなければその時点から修正を加え、間もなく正照準になるタイミングで発砲します。射程50m以内であれば、そのタイミングは銃が肩に着く前になります。


4.次頁左写真は銃が肩に着いた直後ですが、上段左写真の発砲決断直後から
次頁左写真まで、上半身は全く動いておらず、2枚はピッタリ重なります。
これがスナップショットの秘訣です。通常はこの写真のタイミング以前にすでに発砲は
終わっています。銃が肩に着くと、その衝撃で照準がズレ、絶対的ではありませんが、
銃が肩に着く前に撃った方がやや有利と言えます。
発砲決断直後と、本当の発砲直前の2枚を重ねた写真は、上半身を動かさず、銃を下から滑り込ませた感じを受けますが、実際は前方に突き出して指向してから、ホッペをかすめて銃を肩に引き寄せながら、肩に銃が着く前に発砲する、これが本当のスナップショットであり、装填・安全解除まで入れても1秒弱程度で、必ず命中します。
これが出来れば獲物に逃げられる可能性は激減、もし走り出したら銃をその方向にスイングし、目標を追越すタイミングで撃てば「ムービングスタート射撃」となり、命中します。
それが「スナップスイング射撃」その物であり、その延長上に「ランニングショット」があります。
2.ランニングショットと連射。
発砲決断時、すでに目標が走っていた時は次の様に対処します。
体が発砲直前状態に移行しますが、体全体で移動目標を追尾します。
銃を指向しますが、移動目標を追尾しながらの指向となり、肩に銃を引寄せながらスイングを加速し、追越した時点で発砲します。勿論肩に銃が着くまで待つ必要はありません。
1発撃ったら、銃が肩に着く前に、銃を肩から降ろし、再装填しながら再肩付けするスナップスイング射撃を行います。
肩から銃が降りている間も体全体で目標を追尾しますので、スイング中の銃で目標を指向しながら、スイングを加速しながら肩に引き寄せ、目標を追越すタイミングで引き金を引きます。
以下、これを繰り返します。サコーはマガジン容量が5発、5連射が可能です。
薬室装填してから改めてマガジン満タンにすれば6連発となりますが、実用的には無意味です。
スイングの引止まりが無く、習熟すれば連射は1秒強毎となり、自動銃よりやや速い回転速度となります。有効射程は200m、150mを走る鹿の急所に70%が直撃し、鹿の胴体から失中する事は概ねありません。
3発被弾すれば、ショットガン効果で3発被弾直後に即倒しますから、ケンさんの連射から逃げられる可能性はかなり薄い物となります。
連射は獲物ばかり見ていると、何時しか危険領域に入った事に気が付かず、危険な発砲になってしまいます。
スナップスイング射撃であれば、危険領域の手前までに完了させられるかを読めますが、リード射撃は長時間追尾となり、危険領域判断が出来ませんから、実戦狩猟では禁止です。
3.前提条件。
全ての射撃は誰にでもやがて何時かは出来る物ですが、幾つかの前提条件があります。
スナップ射撃はストックのチークピースを調整したスコープ専用銃が前提であります。


スコープ後付け銃 スコープ専用銃
非専用銃で素速い照準は出来ません。スコープ後付け銃と専用銃の違いは僅かの様に見えますが、結果はまるで違う物になります。スコープ専用銃は偉大なる大発明です。
またスナップスイング射撃は引き止まりをしない事が前提ですから、ワンホール射撃或いはそれに準ずる、フリンチングを克服した射撃技術が前提です。
フリンチング克服の為には、射撃は反動を 伴わないと体を騙す必要があり、これには長期の実射を絶つ事と、イメージトレーニングが必要です。
4.全依託射撃。
遠射は全依託射撃をマスターすれば簡単です。
銃は全く手に持たず。写真はベンチレスト射撃です。
 ベンチレスト射撃
ベンチレスト射撃
照準はフロント委託台の微調整アジャスターで調整し、ストックエンドもサンドバッグに乗せ、左手は遊んでいますが、実戦時の全依託射撃は下記の様に多少違います。
照準微調整機能のないサンドバッグ等に全依託し、空いた左手はパッドエンドの下に置き、握りの強さや拳の角度で、銃の照準微調整を担当し、パッドは肩に当てず、触れる程度をキープします。
これで発射直前に体が硬くなるフリンチングをイメージトレーニングで無くし、且つ銃がブレない様に、ソッと且つ一気に引き金だけを引けば、遠射とワンホール射撃が可能となります。
引き金だけで銃は殆どブレず、ブレるのは引き金を引く為に右手に握る力が入り、その為に銃がブレます。銃だけに撃たせれば、銃にはワンホール射撃能力があり、射手がそれを阻止しているのです。
物事には全て重要なポイントがあり、その周辺の努力は有効ですが、それ以外の努力は無効になり事が多い様です。
そう言うステップを踏む事を必要な下積みと言い、それらを抜きに物事は出来ません。それらを抜きに上手くなろうとするのがシロートです。
やるべき事をしていないのですから、上手く行く筈がありません。
何処が重要か分からない時は、取敢えず理屈抜きですでに出来ている人の動作をフルコピーします。やっている内に何処が重要な事か、やがて分かって来ます。フルコピーが完成したら、次に自分流を完成させます。
フルコピーが出来る前に自分流を作ろうとすれば、それは次元の低い物になります。
ワンホール射撃、スナップショット、遠射、ランニングショット、誰もが憧れるこれらのライフル射撃は誰にでも出来る物であり、そのスタートラインの初期条件には何の前提も制限もありません。
ひ弱で過保護育ちのケンさんは音痴をたくさん持ち、世間知らずの「オボッチャマン」で、地道な努力が大嫌いでしたが、それでも大記録が達成出来ました。
誰でもやる気を出し、出来るまで続ければ、必ず出来る可能性を満たしており、殆どの人はマイナスハンデが多かったケンさんから見れば、羨ましい程の遥かに優位なスタート位置にすでにおられます。
銃を素速く正確に撃てる事は、如何なる場面に於いても有利であり、全ての射撃の基本と言え、ケンさんは銃を扱う事が出来ると言う事は、「スナップショットが出来る」と言う言葉に置き換えられると思っています。
またボルト銃の「スナップショット」は「装填」と「安全装置解除」を入れても、殆ど時間は変わらずに操作出来、これをマスターすれば、銃は画期的に「安全」な物になり、且つ最強の狩猟道具となります。
1.スナップショットのやり方。
1.スナップショットは発砲決断と同時に体を前傾させ中写真の様な「発砲直前状態」に移行します。
2.同時に銃身或いはスコープの延長が、目の高さで、目標を正しく指で指す様に指向します。
この時の指向精度が照準精度になりますから、練習を繰り返します。
右写真の状態で構えてもスコープからは何も見えませんが、
すでに目標への志向は完了し、命中要件は概ね揃っています。
3.ホッペをかすめる様に銃を肩に引き寄せながら、至近距離で撃てば目標の急所に命中します。
50m以内であり、心に予めそのつもりがあれば、銃が肩に着くより少し手前から
スコープを通して、やや不完全ながら下写真の様な映像が目に飛び込んで来ます。

急所の直径は15㎝程度であり、そのド真ん中にヒットさせる必要はなく、要件を満たしていれば、そのまま撃ち、満たしていなければその時点から修正を加え、間もなく正照準になるタイミングで発砲します。射程50m以内であれば、そのタイミングは銃が肩に着く前になります。

4.次頁左写真は銃が肩に着いた直後ですが、上段左写真の発砲決断直後から
次頁左写真まで、上半身は全く動いておらず、2枚はピッタリ重なります。
これがスナップショットの秘訣です。通常はこの写真のタイミング以前にすでに発砲は
終わっています。銃が肩に着くと、その衝撃で照準がズレ、絶対的ではありませんが、
銃が肩に着く前に撃った方がやや有利と言えます。
発砲決断直後と、本当の発砲直前の2枚を重ねた写真は、上半身を動かさず、銃を下から滑り込ませた感じを受けますが、実際は前方に突き出して指向してから、ホッペをかすめて銃を肩に引き寄せながら、肩に銃が着く前に発砲する、これが本当のスナップショットであり、装填・安全解除まで入れても1秒弱程度で、必ず命中します。
これが出来れば獲物に逃げられる可能性は激減、もし走り出したら銃をその方向にスイングし、目標を追越すタイミングで撃てば「ムービングスタート射撃」となり、命中します。
それが「スナップスイング射撃」その物であり、その延長上に「ランニングショット」があります。
2.ランニングショットと連射。
発砲決断時、すでに目標が走っていた時は次の様に対処します。
体が発砲直前状態に移行しますが、体全体で移動目標を追尾します。
銃を指向しますが、移動目標を追尾しながらの指向となり、肩に銃を引寄せながらスイングを加速し、追越した時点で発砲します。勿論肩に銃が着くまで待つ必要はありません。
1発撃ったら、銃が肩に着く前に、銃を肩から降ろし、再装填しながら再肩付けするスナップスイング射撃を行います。
肩から銃が降りている間も体全体で目標を追尾しますので、スイング中の銃で目標を指向しながら、スイングを加速しながら肩に引き寄せ、目標を追越すタイミングで引き金を引きます。
以下、これを繰り返します。サコーはマガジン容量が5発、5連射が可能です。
薬室装填してから改めてマガジン満タンにすれば6連発となりますが、実用的には無意味です。
スイングの引止まりが無く、習熟すれば連射は1秒強毎となり、自動銃よりやや速い回転速度となります。有効射程は200m、150mを走る鹿の急所に70%が直撃し、鹿の胴体から失中する事は概ねありません。
3発被弾すれば、ショットガン効果で3発被弾直後に即倒しますから、ケンさんの連射から逃げられる可能性はかなり薄い物となります。
連射は獲物ばかり見ていると、何時しか危険領域に入った事に気が付かず、危険な発砲になってしまいます。
スナップスイング射撃であれば、危険領域の手前までに完了させられるかを読めますが、リード射撃は長時間追尾となり、危険領域判断が出来ませんから、実戦狩猟では禁止です。
3.前提条件。
全ての射撃は誰にでもやがて何時かは出来る物ですが、幾つかの前提条件があります。
スナップ射撃はストックのチークピースを調整したスコープ専用銃が前提であります。


スコープ後付け銃 スコープ専用銃
非専用銃で素速い照準は出来ません。スコープ後付け銃と専用銃の違いは僅かの様に見えますが、結果はまるで違う物になります。スコープ専用銃は偉大なる大発明です。
またスナップスイング射撃は引き止まりをしない事が前提ですから、ワンホール射撃或いはそれに準ずる、フリンチングを克服した射撃技術が前提です。
フリンチング克服の為には、射撃は反動を 伴わないと体を騙す必要があり、これには長期の実射を絶つ事と、イメージトレーニングが必要です。
4.全依託射撃。
遠射は全依託射撃をマスターすれば簡単です。
銃は全く手に持たず。写真はベンチレスト射撃です。
 ベンチレスト射撃
ベンチレスト射撃照準はフロント委託台の微調整アジャスターで調整し、ストックエンドもサンドバッグに乗せ、左手は遊んでいますが、実戦時の全依託射撃は下記の様に多少違います。
照準微調整機能のないサンドバッグ等に全依託し、空いた左手はパッドエンドの下に置き、握りの強さや拳の角度で、銃の照準微調整を担当し、パッドは肩に当てず、触れる程度をキープします。
これで発射直前に体が硬くなるフリンチングをイメージトレーニングで無くし、且つ銃がブレない様に、ソッと且つ一気に引き金だけを引けば、遠射とワンホール射撃が可能となります。
引き金だけで銃は殆どブレず、ブレるのは引き金を引く為に右手に握る力が入り、その為に銃がブレます。銃だけに撃たせれば、銃にはワンホール射撃能力があり、射手がそれを阻止しているのです。
物事には全て重要なポイントがあり、その周辺の努力は有効ですが、それ以外の努力は無効になり事が多い様です。
そう言うステップを踏む事を必要な下積みと言い、それらを抜きに物事は出来ません。それらを抜きに上手くなろうとするのがシロートです。
やるべき事をしていないのですから、上手く行く筈がありません。
何処が重要か分からない時は、取敢えず理屈抜きですでに出来ている人の動作をフルコピーします。やっている内に何処が重要な事か、やがて分かって来ます。フルコピーが完成したら、次に自分流を完成させます。
フルコピーが出来る前に自分流を作ろうとすれば、それは次元の低い物になります。
ワンホール射撃、スナップショット、遠射、ランニングショット、誰もが憧れるこれらのライフル射撃は誰にでも出来る物であり、そのスタートラインの初期条件には何の前提も制限もありません。
ひ弱で過保護育ちのケンさんは音痴をたくさん持ち、世間知らずの「オボッチャマン」で、地道な努力が大嫌いでしたが、それでも大記録が達成出来ました。
誰でもやる気を出し、出来るまで続ければ、必ず出来る可能性を満たしており、殆どの人はマイナスハンデが多かったケンさんから見れば、羨ましい程の遥かに優位なスタート位置にすでにおられます。
2024年03月17日
ボウハンティング狩猟法。
4.狩猟方法。
ボウハンティングのみの特別な方法は無く、銃を使った狩猟時と同様の種類となります。
但し、射程距離が通常30m、50mが最大となり、その為の工夫が必要となります。
4-1.木の上の待ち場: 左写真の様に大きな木の中腹に足場を作り、鹿の通過を待ちます。
単純な通過待ちに加えて、人工的に水場やエサ場を作ってすぐ傍、またはそこへの途上を狙います。鹿の天敵はオオカミ等で、地上の周囲には相当警戒していますが、鹿に上空からの天敵はおらず、比較的注意が甘い盲点を突きます。


4-2.平たい土地の待ち屋:4-1と同様の考えですが、右イラストの様な待ち屋の小屋を作ります。イラストは銃猟用で、ボウの場合はもう少し天井を高くします。4-1も同様ですが、撃ち下ろしになる事で、50m以遠でも大丈夫です。肺を撃てば下記の理由で間もなく死亡します。
撃つ地点を予め決めておけば、射撃距離が事前に分かり、確実に命中させられます。
ボウの狙い目は主に心臓付近となります。ヒットによる出血と、胸腔に穴が空く事によって呼吸困難になります。肺自体に呼吸機能はなく、胸腔を外力により収縮させる事によって肺を収縮させて呼吸をしているのですが、胸腔に穴が空きますと肺が縮んだままとなり、著しく呼吸困難となります。
その為には追跡が容易になる様に、矢が刺さったままよりも、貫通する方が出血が多くなり望ましいと言えます。貫通していれば出血も多く、追跡は左程困難ではありません。
ボウでは銃の場合と違い、その場で即倒は殆ど無く、多少の追跡が不可欠となります。
アメリカの鹿猟に掛ける情熱は日本とは比較にならず、山奥に秘密のエサ場を作る為に、狩猟用のバギー用に農業用アタッチメントの用意もあり、銃砲店では牧草の種や肥料も売られています。
僅か1カ月の狩猟の為に事前努力を怠らない、この姿勢は見事と言えますが、そこまでしないと1頭の鹿が獲れないのも気の毒な話です。
狩猟解禁中の1カ月の休暇を取る人も少なくなく、アラスカやカナダの奥地のツンドラ平原まで片道1週間近くを掛け、キャンピングカーにバギー用トレーラーを付け、遠征をする人も少なくありません。
狩猟解禁の直前や直後には、狩猟遠征車による渋滞が起こる程なのです。
4-3.忍びのコール猟:鹿猟の解禁は何処の国でも鹿の繁殖期と重なり、鹿は良く響く独特の声を出し、鹿は自己の存在をアピールし、メスを呼び込みます。
そして自分の近くで他の鹿がアピールを始めれば、これを追い出しに掛かります。
ケンさんも以前森の中でエゾ鹿コール猟をやって見ましたが、本当に大物鹿が数十mまで来ました。短射程ボウでも対処出来る距離でしたが、20m先の木陰から姿を出さず、やがて去って行きました。
ただ出会い効率が低く、その後は牧草地で姿丸出しの自己アピールする、鹿に出会う作戦をメインにしましたが、この場合は100~150mの距離となりました。
山に入ったらコールを吹いてみます。反応が有ればその方向に進みます。そしてある程度まで近くに寄ったら最後のコールを吹き、射撃に備えます。
上手く行けば相手の鹿が確か声はこの辺と言う感じで探しに来ますが、多くは人間である事を見破られ、射手の視界外で引き上げてしまいます。従って最後までライバル鹿を装うか、動かない仏像の如くで過ごすか、どちらかに徹しなければなりません。
銃猟の場合はコールに反応の合った場所の近くで、山から降り易い場所に早朝もしくは夕方に出現 する可能性が高く、それに合わせたポイント猟出撃の方が良いと思います。
4-4.巻狩り:本州巻狩りと似た方法で、待ち場の射手と勢子に分かれて行う場合もあれば、全員が勢子と言うより忍び猟の場合もあり、その発砲が最大の鹿の移動促進する手段となります。
共通は鹿が多過ぎ放した猟犬が使えない事です。
ケンさんがアラスカ北部で体験した巻狩りは、渦巻き状に歩きながら輪を徐々に狭くして行く、眞に巻狩りと言える物でした。3人組がちょうど始め様としており、フォトOK?と申し入れた所、スペアの弓があるので、お前も参加しろと言う事になりました。
アラスカ北部の銃猟は全面的に禁止されていますが、ボウハンティイングだけが可能です。
銃で撃たれないカリブーは100m以上離れれば、人間の存在を全く気にしません。
遠巻きに囲い込み、当初は直径200m位から始まり、その輪を渦巻き状に徐々に縮じめて行きます。
やがてカリブーは人間側の企みに気が付き、囲みの薄い所を突破しようとしますが、そうはさせじと 両側の射手が走ってそこを狭くします。結局最後は何処かを突破し、その時が最大の射撃チャンスになりますが、射程限界のしかも動的で単射である事が難点です。
ケンさんの時は30m先を全速で突っ走って抜け様とし、照準は落差少々、リードベラボー、ライフルの10倍位の感触でスイングショットで矢を放ちました。
矢は当初前を通過してしまうかに見えましたが、突然矢が見えなくなり、同時にカリブーの走行速度が低下し、そして数十mで倒れました。
ボウは初期型のコンパウンドでしたが、矢は貫通していました。冒頭の写真がその時の物です。
尚、後刻リードを計算しました所、やはりライフル時の10倍の5.2mでした。


専用ロッジに自家用機、羨ましい限りの狩猟環境ですが、秘密の牧草地育成の話でもそうでしたが、そこまでしないと獲れないのも気の毒な話です。


その点ケンさんスクールは廃村の廃屋の貧弱な環境ですが、スクール看板の様に毎日2頭捕獲が平均実績、右写真は5日猟で19頭捕獲でした。
海外鹿猟は1カ月掛けて1頭獲れば成功、その差は余りにも大きく、著しいを遥かに超えています。
因みにアメリカでは人気NO.1のボウハンティングですが、日本の狩猟法では、音がしないから密猟に繋がるとして禁止されています。
世界中の鹿猟を調べれば調べる程、エゾ鹿猟は類稀な状況にありました。折角の世界ダントツなのですから、是非エゾ鹿の大物との勝負をタップリ楽しんで下さい。
海外で鹿1頭のガイド猟をすれば、1週間日程の実猟5日で1式が100万円前後、北海道のエゾ鹿猟であれば、それより遥かに安い金額で、毎日1頭も夢ではありません。
世界中のディアハンターを日本に呼び込んでと言う作戦もありかと思います。
5.エゾ鹿猟。
5-1.エゾ鹿民宿巻狩り:今も多くの人が参加する、この猟の話を少ししたいと思います。多くは民宿の主人が宿泊客を集める目的で巻狩りを行います。勢子は宿の主人が行い、鹿を追出す係と言うより単独忍び猟を行い、それに押された鹿を宿泊客の射手が待ち場で撃つと言う感じですが、後者は概ね絶望的な結果に終わります。
結果的には勢子の捕獲が90%以上となり、その10倍いる射手の射撃チャンスは、気配勝負に負け、甚だ僅かです。ケンさんも白糠と五葉山で合計78日ものドッグレス巻狩りを行いましたが、気配合戦に敗れ、捕獲はゼロでした。
「禅の心作戦」に開眼し、本州鹿を2日に1頭獲れるケンさんが78日も行ってゼロだったのです。従って民宿巻狩りではエゾ鹿は獲れないと断言出来ます。
民宿巻狩りとはチャーターガイド猟に比べガイド代が不要で安価に済む事から、多くの人が巻狩りに流れます。しかし捕獲率は概ねゼロ、参加価値はありません。

参加者はガイドの捕獲した鹿肉の分配を受け、ガイドが捕獲 した鹿で記念撮影、愛銃は撮影の小道具だけに留まります。この写真もその様な借り物の鹿ですが、中央下のバラ角はケンさん捕獲です。
5-2.ガイド猟:そんな事から獲れる可能性のあるのはガイド猟だけとなりますが、この手法はガイドの能力次第です。
昨今は駆除が1年中行われ、鹿は利口になり、地元ベテランハンターにも扱い難い存在となりました。エゾ鹿は今も昔も憧れの存在、かつては我と思う人がエゾ鹿ガイドになりましたが、昨今は獲れる地元はプロの駆除ハンター、獲れない地元ヒマ3流ベテランが小使い稼ぎにガイドをしています。
賢くなったエゾ鹿はハンターを避けた行動をするのは言うまでもなく、2流以下のベテランでも全くのお手上げ状態、もちろん地元のハンターは全員がそうなり、猟場で出会うハンターは激減しました。
エゾ鹿猟の出会いはガイドの技術次第であり、捕獲はそれに多少射撃技術等が絡みます。
そんなエゾ鹿ですが、天候サイクル概ね6日の悪天候明けには一斉に行動し、至る所に出没します。ケンさんはそんな日を「フィーバー」と名付けました。
そんなフィーバー日には、出会いは非常に簡単、地元3流ガイドでもその日だけは出会いが得られ、またガイドレス流し猟のアマチュアハンターでも、その日だけはエゾ鹿に出会えます。
そんな日は出会いが多く、大物が多く、射程距離は短く、照準時間は長くもらえると言った、初心者 ハンターに取っては甚だ良い事尽くめとなります。
そんな日に出猟したいのは山々ですが、それは当日の朝にならないと分かりません。
そう言う状態ですから、フィーバーが起こる確率は1/6、つまり17%、逆算すれば83%のガイドはエゾ鹿には出会える筈が無い詐欺ガイドである事になり、捕獲成功率はその1/3の「6%」、これが現状です。
ケンさんスクールは1日5回出会え、2頭獲れる、そして17年間でゼロは1度も無い、これが実績でした。
しかし結果的にはこの様なガイドは何処にもおらず、初心者エゾ鹿猟は手ブラを免れれば大成功と言えました。
本州巻狩りでは捕獲平均値は0.05頭/日人、つまり捕獲には20日通わなくてはならず、シーズンに2頭捕獲は難しいと言う事になりますが、エゾ鹿猟もそれよりは多少マシに留まります。
勿論詐欺ガイドが捕獲率や出会い率等を公表する筈もなく、公表しているのは西興部有料猟区のみとなります。それに依りますと訪れた参加者の80%はメス或いは小物の捕獲に成功すると言った数値になっております。
残念ながら初心者の捕獲成功は至らない可能性が高いと言う事になります。
未経験初心者がエゾ鹿を捕獲する為には、100mで5㎝の射撃精度と、狩猟慣れと迫力負けの慣れで10回程の失敗の体験が必要です。
ケンさんスクールでは4日遠征で実猟3日が可能、出会いが1日5回あり、2日目までに基礎10回の失敗を積上げる事が出来、3日目に中型以下の鹿と80m以下で出会えた時に初捕獲が記録されます。それで捕獲ゼロは皆無なのです。
現在の所、最高捕獲率の西興部の猟区では、4日遠征では実猟2日しかなく、且つ出会いはケンさんスクール比で半減、従って捕獲ゼロの可能性は高いと言う事になり、捕獲成功は多分2年目です。
ケンさんのスクールにも他所で民宿巻狩りを3年間で合計9日行った生徒が3名来ました。流石に捕獲はゼロではありませんでしたが、捕獲は小物数頭に留まり、3段角は見た事もないが共通でした。
ケンさんのスクールでは10月下旬からの1ヶ月であれば、大物に拘ったその出会い数は5回/日、捕獲は2頭/日、内容内訳は出会いの70%が3段角の成獣オス、20%が大物、5%が超大物でした。


流石に何時も写真の様にはなりませんが、朝飯前に1頭を捕獲する事は難しくなく、上手く行けば朝飯前の複数以上捕獲も全然夢ではありません。生徒に依る最大捕獲数は5日猟で19頭です。
大量捕獲には回収補助人が不可欠ですが、ケンさんの最大捕獲は5日50頭でした。ランニング射撃が可能であれば群れから平均数頭を戴く事も難しくはありません。
またケンさんのスクールで超大物との出会いは5%ですが、実は悪天候明けに集中、一生に1度だけでも対戦したい夢の超大物も、フィーバー日に迫力負けせず、150m射撃をミスしなければ、右写真の様に「束」にして帰還する事も難しくはありません。
エゾ鹿猟は行けば誰でも獲れる状態にはありませんが、100m5㎝の射撃技術を磨き、エゾ鹿猟実戦で基礎失敗10回を積み、中型以下と100mで出会え、全てが揃った時に初捕獲成功となります。
かつてのケンさんスクールではこれを初回遠征で全員が達成出来る様に事前指導して来ましたが、有料西興部猟区では多分2年目に、100m5㎝が達成すれば、概ね全員が成功する事でしょう。
ボウハンティングのみの特別な方法は無く、銃を使った狩猟時と同様の種類となります。
但し、射程距離が通常30m、50mが最大となり、その為の工夫が必要となります。
4-1.木の上の待ち場: 左写真の様に大きな木の中腹に足場を作り、鹿の通過を待ちます。
単純な通過待ちに加えて、人工的に水場やエサ場を作ってすぐ傍、またはそこへの途上を狙います。鹿の天敵はオオカミ等で、地上の周囲には相当警戒していますが、鹿に上空からの天敵はおらず、比較的注意が甘い盲点を突きます。

4-2.平たい土地の待ち屋:4-1と同様の考えですが、右イラストの様な待ち屋の小屋を作ります。イラストは銃猟用で、ボウの場合はもう少し天井を高くします。4-1も同様ですが、撃ち下ろしになる事で、50m以遠でも大丈夫です。肺を撃てば下記の理由で間もなく死亡します。
撃つ地点を予め決めておけば、射撃距離が事前に分かり、確実に命中させられます。
ボウの狙い目は主に心臓付近となります。ヒットによる出血と、胸腔に穴が空く事によって呼吸困難になります。肺自体に呼吸機能はなく、胸腔を外力により収縮させる事によって肺を収縮させて呼吸をしているのですが、胸腔に穴が空きますと肺が縮んだままとなり、著しく呼吸困難となります。
その為には追跡が容易になる様に、矢が刺さったままよりも、貫通する方が出血が多くなり望ましいと言えます。貫通していれば出血も多く、追跡は左程困難ではありません。
ボウでは銃の場合と違い、その場で即倒は殆ど無く、多少の追跡が不可欠となります。
アメリカの鹿猟に掛ける情熱は日本とは比較にならず、山奥に秘密のエサ場を作る為に、狩猟用のバギー用に農業用アタッチメントの用意もあり、銃砲店では牧草の種や肥料も売られています。
僅か1カ月の狩猟の為に事前努力を怠らない、この姿勢は見事と言えますが、そこまでしないと1頭の鹿が獲れないのも気の毒な話です。
狩猟解禁中の1カ月の休暇を取る人も少なくなく、アラスカやカナダの奥地のツンドラ平原まで片道1週間近くを掛け、キャンピングカーにバギー用トレーラーを付け、遠征をする人も少なくありません。
狩猟解禁の直前や直後には、狩猟遠征車による渋滞が起こる程なのです。
4-3.忍びのコール猟:鹿猟の解禁は何処の国でも鹿の繁殖期と重なり、鹿は良く響く独特の声を出し、鹿は自己の存在をアピールし、メスを呼び込みます。
そして自分の近くで他の鹿がアピールを始めれば、これを追い出しに掛かります。
ケンさんも以前森の中でエゾ鹿コール猟をやって見ましたが、本当に大物鹿が数十mまで来ました。短射程ボウでも対処出来る距離でしたが、20m先の木陰から姿を出さず、やがて去って行きました。
ただ出会い効率が低く、その後は牧草地で姿丸出しの自己アピールする、鹿に出会う作戦をメインにしましたが、この場合は100~150mの距離となりました。
山に入ったらコールを吹いてみます。反応が有ればその方向に進みます。そしてある程度まで近くに寄ったら最後のコールを吹き、射撃に備えます。
上手く行けば相手の鹿が確か声はこの辺と言う感じで探しに来ますが、多くは人間である事を見破られ、射手の視界外で引き上げてしまいます。従って最後までライバル鹿を装うか、動かない仏像の如くで過ごすか、どちらかに徹しなければなりません。
銃猟の場合はコールに反応の合った場所の近くで、山から降り易い場所に早朝もしくは夕方に出現 する可能性が高く、それに合わせたポイント猟出撃の方が良いと思います。
4-4.巻狩り:本州巻狩りと似た方法で、待ち場の射手と勢子に分かれて行う場合もあれば、全員が勢子と言うより忍び猟の場合もあり、その発砲が最大の鹿の移動促進する手段となります。
共通は鹿が多過ぎ放した猟犬が使えない事です。
ケンさんがアラスカ北部で体験した巻狩りは、渦巻き状に歩きながら輪を徐々に狭くして行く、眞に巻狩りと言える物でした。3人組がちょうど始め様としており、フォトOK?と申し入れた所、スペアの弓があるので、お前も参加しろと言う事になりました。
アラスカ北部の銃猟は全面的に禁止されていますが、ボウハンティイングだけが可能です。
銃で撃たれないカリブーは100m以上離れれば、人間の存在を全く気にしません。
遠巻きに囲い込み、当初は直径200m位から始まり、その輪を渦巻き状に徐々に縮じめて行きます。
やがてカリブーは人間側の企みに気が付き、囲みの薄い所を突破しようとしますが、そうはさせじと 両側の射手が走ってそこを狭くします。結局最後は何処かを突破し、その時が最大の射撃チャンスになりますが、射程限界のしかも動的で単射である事が難点です。
ケンさんの時は30m先を全速で突っ走って抜け様とし、照準は落差少々、リードベラボー、ライフルの10倍位の感触でスイングショットで矢を放ちました。
矢は当初前を通過してしまうかに見えましたが、突然矢が見えなくなり、同時にカリブーの走行速度が低下し、そして数十mで倒れました。
ボウは初期型のコンパウンドでしたが、矢は貫通していました。冒頭の写真がその時の物です。
尚、後刻リードを計算しました所、やはりライフル時の10倍の5.2mでした。


専用ロッジに自家用機、羨ましい限りの狩猟環境ですが、秘密の牧草地育成の話でもそうでしたが、そこまでしないと獲れないのも気の毒な話です。

その点ケンさんスクールは廃村の廃屋の貧弱な環境ですが、スクール看板の様に毎日2頭捕獲が平均実績、右写真は5日猟で19頭捕獲でした。
海外鹿猟は1カ月掛けて1頭獲れば成功、その差は余りにも大きく、著しいを遥かに超えています。
因みにアメリカでは人気NO.1のボウハンティングですが、日本の狩猟法では、音がしないから密猟に繋がるとして禁止されています。
世界中の鹿猟を調べれば調べる程、エゾ鹿猟は類稀な状況にありました。折角の世界ダントツなのですから、是非エゾ鹿の大物との勝負をタップリ楽しんで下さい。
海外で鹿1頭のガイド猟をすれば、1週間日程の実猟5日で1式が100万円前後、北海道のエゾ鹿猟であれば、それより遥かに安い金額で、毎日1頭も夢ではありません。
世界中のディアハンターを日本に呼び込んでと言う作戦もありかと思います。
5.エゾ鹿猟。
5-1.エゾ鹿民宿巻狩り:今も多くの人が参加する、この猟の話を少ししたいと思います。多くは民宿の主人が宿泊客を集める目的で巻狩りを行います。勢子は宿の主人が行い、鹿を追出す係と言うより単独忍び猟を行い、それに押された鹿を宿泊客の射手が待ち場で撃つと言う感じですが、後者は概ね絶望的な結果に終わります。
結果的には勢子の捕獲が90%以上となり、その10倍いる射手の射撃チャンスは、気配勝負に負け、甚だ僅かです。ケンさんも白糠と五葉山で合計78日ものドッグレス巻狩りを行いましたが、気配合戦に敗れ、捕獲はゼロでした。
「禅の心作戦」に開眼し、本州鹿を2日に1頭獲れるケンさんが78日も行ってゼロだったのです。従って民宿巻狩りではエゾ鹿は獲れないと断言出来ます。
民宿巻狩りとはチャーターガイド猟に比べガイド代が不要で安価に済む事から、多くの人が巻狩りに流れます。しかし捕獲率は概ねゼロ、参加価値はありません。

参加者はガイドの捕獲した鹿肉の分配を受け、ガイドが捕獲 した鹿で記念撮影、愛銃は撮影の小道具だけに留まります。この写真もその様な借り物の鹿ですが、中央下のバラ角はケンさん捕獲です。
5-2.ガイド猟:そんな事から獲れる可能性のあるのはガイド猟だけとなりますが、この手法はガイドの能力次第です。
昨今は駆除が1年中行われ、鹿は利口になり、地元ベテランハンターにも扱い難い存在となりました。エゾ鹿は今も昔も憧れの存在、かつては我と思う人がエゾ鹿ガイドになりましたが、昨今は獲れる地元はプロの駆除ハンター、獲れない地元ヒマ3流ベテランが小使い稼ぎにガイドをしています。
賢くなったエゾ鹿はハンターを避けた行動をするのは言うまでもなく、2流以下のベテランでも全くのお手上げ状態、もちろん地元のハンターは全員がそうなり、猟場で出会うハンターは激減しました。
エゾ鹿猟の出会いはガイドの技術次第であり、捕獲はそれに多少射撃技術等が絡みます。
そんなエゾ鹿ですが、天候サイクル概ね6日の悪天候明けには一斉に行動し、至る所に出没します。ケンさんはそんな日を「フィーバー」と名付けました。
そんなフィーバー日には、出会いは非常に簡単、地元3流ガイドでもその日だけは出会いが得られ、またガイドレス流し猟のアマチュアハンターでも、その日だけはエゾ鹿に出会えます。
そんな日は出会いが多く、大物が多く、射程距離は短く、照準時間は長くもらえると言った、初心者 ハンターに取っては甚だ良い事尽くめとなります。
そんな日に出猟したいのは山々ですが、それは当日の朝にならないと分かりません。
そう言う状態ですから、フィーバーが起こる確率は1/6、つまり17%、逆算すれば83%のガイドはエゾ鹿には出会える筈が無い詐欺ガイドである事になり、捕獲成功率はその1/3の「6%」、これが現状です。
ケンさんスクールは1日5回出会え、2頭獲れる、そして17年間でゼロは1度も無い、これが実績でした。
しかし結果的にはこの様なガイドは何処にもおらず、初心者エゾ鹿猟は手ブラを免れれば大成功と言えました。
本州巻狩りでは捕獲平均値は0.05頭/日人、つまり捕獲には20日通わなくてはならず、シーズンに2頭捕獲は難しいと言う事になりますが、エゾ鹿猟もそれよりは多少マシに留まります。
勿論詐欺ガイドが捕獲率や出会い率等を公表する筈もなく、公表しているのは西興部有料猟区のみとなります。それに依りますと訪れた参加者の80%はメス或いは小物の捕獲に成功すると言った数値になっております。
残念ながら初心者の捕獲成功は至らない可能性が高いと言う事になります。
未経験初心者がエゾ鹿を捕獲する為には、100mで5㎝の射撃精度と、狩猟慣れと迫力負けの慣れで10回程の失敗の体験が必要です。
ケンさんスクールでは4日遠征で実猟3日が可能、出会いが1日5回あり、2日目までに基礎10回の失敗を積上げる事が出来、3日目に中型以下の鹿と80m以下で出会えた時に初捕獲が記録されます。それで捕獲ゼロは皆無なのです。
現在の所、最高捕獲率の西興部の猟区では、4日遠征では実猟2日しかなく、且つ出会いはケンさんスクール比で半減、従って捕獲ゼロの可能性は高いと言う事になり、捕獲成功は多分2年目です。
ケンさんのスクールにも他所で民宿巻狩りを3年間で合計9日行った生徒が3名来ました。流石に捕獲はゼロではありませんでしたが、捕獲は小物数頭に留まり、3段角は見た事もないが共通でした。
ケンさんのスクールでは10月下旬からの1ヶ月であれば、大物に拘ったその出会い数は5回/日、捕獲は2頭/日、内容内訳は出会いの70%が3段角の成獣オス、20%が大物、5%が超大物でした。
流石に何時も写真の様にはなりませんが、朝飯前に1頭を捕獲する事は難しくなく、上手く行けば朝飯前の複数以上捕獲も全然夢ではありません。生徒に依る最大捕獲数は5日猟で19頭です。
大量捕獲には回収補助人が不可欠ですが、ケンさんの最大捕獲は5日50頭でした。ランニング射撃が可能であれば群れから平均数頭を戴く事も難しくはありません。
またケンさんのスクールで超大物との出会いは5%ですが、実は悪天候明けに集中、一生に1度だけでも対戦したい夢の超大物も、フィーバー日に迫力負けせず、150m射撃をミスしなければ、右写真の様に「束」にして帰還する事も難しくはありません。
エゾ鹿猟は行けば誰でも獲れる状態にはありませんが、100m5㎝の射撃技術を磨き、エゾ鹿猟実戦で基礎失敗10回を積み、中型以下と100mで出会え、全てが揃った時に初捕獲成功となります。
かつてのケンさんスクールではこれを初回遠征で全員が達成出来る様に事前指導して来ましたが、有料西興部猟区では多分2年目に、100m5㎝が達成すれば、概ね全員が成功する事でしょう。
2024年03月13日
アメリカでは大人気、日本では禁止されているボウハンティング。
太古から続く狩猟は西暦1500年頃の銃の普及以前の狩猟道具は槍や弓矢で行われていました。
弓矢は便利な飛び道具ですが、矢速が低く急所を狙える射程距離は、落差補正をしても30m程度でした。ならば初期のノーライフル丸弾の銃と同程度だったではないかと言えば、その通りです。
しかし絶対的な違いがありました。それは照準器です。銃には初期の頃から照準器が付いており、落ち付いて照準して撃てば、落差補正は不要で、必ず命中しました。
それに対し弓矢では最近まで照準器がなく、目の位置と矢の位置は上下と左右がズレており、これをカンで補正し、更に10mを超えると落差補正をカンで処理しなければ、命中しない高難度な狩猟道具でした。
銃のライフリング自体は1498年に発明されましたが、1546年以降のミニエー弾の普及まで、実用化が遅れたとは言え、すでに450年以上前から普及しています。しかし実はノーライフルと丸弾の歴史は1965年頃まで続きました。どうして1965年まで丸弾は続いたのか?
1.狩猟ブームの始まった頃の日本のハンター。
それは猪猟がメインで、大物猟時に散弾銃のノーライフルバレルから1粒弾を撃つ為にそうなりました。1970年代頃のハンターは殆どが雉撃ちで、そのイメージは猟犬を連れ、水平2連銃を担いでいました。
夢は猪や鹿の捕獲であり、服装は上からハンティング帽、厚手の赤チェックのシャツ、革のチョッキの、胸には丸弾スラグ弾2発、腰には25発弾帯、乗馬ズボン、靴は軽量地下足袋でした。



右写真は帽子がちょっと違いシャツが薄手ですが、概ねそんな感じでした。
下写真の少年は概ね当時のイメージです。弾帯は腰の位置が正しいです。
チョッキは革製以外や、サファリジャケットの様に長袖の場合もありましたが、偶発的大物戦に備えた、胸のスラグ弾2発は共通装備品でした。チョッキの背中部分はサブザックになっており、捕獲したキジを入れたり、雨具を入れていました。
水平2連銃は初矢がインプシリンダー、後矢フル チョークであり、丸弾スラグはフルチョークから安全に撃てる様に、やや小さ目に出来ており、その為に確実に急所が狙えるのは20~30mでした。
その後の時代では銃は単身のインプシリンダーチョークの自動銃となり、弾頭はフォスタースラグ弾となり、射程距離は50mまで延長されました。また射程80mのブリネッキ弾と言うのもありました。
現在の銃身ではリブがあり、その延長上は昔より容易に掴め、オープンサイトと大差ありません。
2.コンパウンドボウの進化。
弓矢も和弓の初速は60m/sですが、近年の洋弓では用具も進化し、コンパウンドボウで100m/sの初速が可能となり、また矢の進化から精度も大幅に向上しました。
和弓では距離28mから直径36cmの的を狙いますが、オリンピックのアーチェリー競技では2倍以上の距離の70mから10点圏が12㎝強の的を狙います。
2.5倍の距離で33%の大きさの的ですから、和弓よりアーチェリーの方が原理的に高精度です。洋弓ならば70mの射程が十分有るかの様にも見えますが、実戦での落差補正を考えますと、現在でも有効射程は30m前後となり、50m前後が限界となりますが、事前試射が出来れば80mも可能です。
矢の初速からすれば、20mまでは落差無視で狙え、30mは完全に落差補正を要し、絶対確実と言う事になると僅か10~20mに留まります。

尚、ボウガンと言う、一見すると機能の高そうな道具もありますが、矢が短く精度が出ません。
従ってこれを使ってボウハンティングをしようとする人は少ないと思います。
3.アラスカのカリブーのボウハンティング。
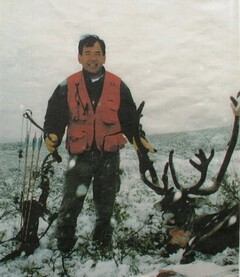
飛び道具研究科のケンさんは愛用のアーチェリーやパチンコで、30m先の空き缶を外さない程度の腕前は持っており、写真は2000年8月にアラスカ北部にて、飛び入り参加、捕獲させて頂きました。アラスカは8月20日、この日から冬が始まりました。
当時の弓矢もパワー的には馬鹿に出来ず、射程距離以外は少なく見ても308と同等以上でした。当時も今に比べれば不完全ですが、小さな照準器は付いていました。
ケンさんは愛用のアーチェリー感覚で照準器を使わずに矢を発射しました。30m先を走るカリブーに思い切りスイングし、前過ぎたかと思う位のリードを取って発射しました。
矢の行き先を見ていますと、前過ぎる様に見えましたが、最後の瞬間に矢は見えなくなりました。
その直後から、狙っていたカリブーは急に速度を落とし、やがて倒れました。ヒットは心臓のやや後方、矢は貫通しており、ヒットした周辺を見ても見当たりません。
見付かれば記念に貰って来ようと思ったのですが、残念に終わりました。鏃は3-1-4項左上のカミソリ3枚の3角鏃だったと思います。
エゾ鹿と同クラスのカリブーを貫通したのですから、少なくとも308と同じ程度のパワーです。
ボウハンティングではネット動画で見ても即倒する事はかなり稀ですが、ライフル銃のエゾ鹿心臓狙いで走られる距離よりも遥かに短距離で倒れました。現在のコンパウンドボウでは更に強力となり、マグナムライフル以上のパワーがあり、大型のブラウンベアでも貫通しています。
3-1.野性動物へのハンディ政策。
1990年頃からの狩猟用ライフル銃は300mの射程を持つ様になり、野生動物側にハンディを与える為にピストル・先込め銃・弓矢・ショットガンの4種が新しい狩猟方法が検討されました。そして最終的に弓矢とショットガンが生き残りました。


3-1-1.短銃による狩猟:454カスールでは300gr弾頭を1625fps、パワー1759ft-lbfと数字的には20番スラグ並の数値であり、最強のピストル弾500SWならば2500ft-lbfと30口径Stdライフルに肉薄して来ます。
しかし、命中しなければ、どんな強力な弾も無意味、強力過ぎる銃は命中させ難いのです。
ケンさんの感触ではまともに撃てるのは44レミントンマグの270gr、1450fps、1260ft-lbf程度までと思います。
銃身の前の部分はバランサーを兼ねたサイレンサーですが、弾は超音速弾であり衝撃波を発する事、及びシリンダーとバレルの隙間からの漏れ等々で消音効果は殆ど期待出来ません。
短い銃身に依り、射程距離を短くして野性動物にハンディを与え様とする物ですが、極めて短い銃身からは高精度を求める事が出来ず、獲物の急所に当てられず、またヒットしても半矢未回収が多く、ハイパワーマニアを刺激した新短銃のデビューだけに終わり、余り普及せずに終わりました。

3-1-2.マズルローダーハンティング:黒色火薬のマズルローダーならば野性動物に与える短射程は可能ですが、半矢未回収を押さえる為、マズルローダー定義が拡大され、ライフリングも無煙火薬もサボットも全てOKとした為、現用ボルトアクションライフルを改造したモダン型マズルローダーでサボットを使えば現用ライフルとの性能差は無くなり、動物保護意味が薄くなり普及していません。
3-1-3.ショットガンハンティング:初期にはノーライフルバレルから発射する射程50~80mスラグ弾で検討されていたのですが、半矢・未回収問題からサボットスラグ弾&フルライフルバレルもOKとなり、最大射程は150mとなりました。
それでもライフルの300mからすれば射程半分とハンディは確保されており、精度の実用性も十分にあり、その前の週はボウですから、よく普及していました。
しかし、エゾ鹿でもそうですが、通常のハンティングはアメリカでも100m前後が多く、実質ハンディが余り無い事が分かり、近年は減少気味となりました。

日本のエゾ鹿猟用サボットスラグ銃は国内法に合わせ、このライフリングを50%未満とした物が使われています。このサボットスラグ銃のお陰で経験年数がライフルに届かない新人ハンターでもエゾ鹿猟が可能になりました。
国内法ではライフリングのある銃身は全てライフル銃となり、ノーライフルでも ライフル弾の撃てる銃はライフル銃となります。その為、ライフリング長を50%未満としているのです。
長野の青木の陰で一気に悪者の銃と言う事になってしまいました。
3-1-4.ボウハンティング:その名の通り弓矢による狩猟です。
ボウ射程距離は30~50m程度であり、野性動物側に最も大きなハンディを与えた事にもなります。多くのエリアでは狩猟解禁は1か月間、期間中の1カ月全部を休暇にする人も少なくはありません。
最初の1週間はボウで解禁、次の1週間がショットガン(バックショット禁止)、最後がライフルになります。多くの州で定数は1シーズン1頭のみ、もう1頭獲りたい時は別の州に行かなくてはなりません。
それに対し、日本の定数は1日オス1頭+メス無制限、シーズンは3か月間以上、ケンさんのスクールでは生徒が5日で19頭が最高、ケンさんは5日で50頭を捕獲した事もあります。
鹿猟に付きましては世界中で超ダントツ、如何に日本が恵まれている事か分かると思います。
ボウは射程内まで引き寄せる難しさもありますが、注意事項を守れば狩猟経験の無い獲物は引き寄せる事が可能です。また音がしないので獲物が余り逃げず、結果的に出会い率も捕獲率も共に銃猟に比べて遥かに高く高人気です。またド至近距離までじっと引き寄せるスリルも格別です。
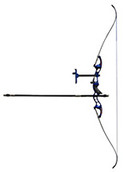



上写真は左から従来型の貫通しないリカーブボウ、初期型コンパウンドボウ、後期型コンパウンドボウ、そして使う矢はカーボン製、照準器も完璧となりました。弓を引くとピープサイトが目の前に来る様に調節します。次に照星を希望の距離で正しく命中する様に調整します。
照星は3~5種あり、希望の落差に合わせられます。言葉換えれば、3~5種の射程距離の設定が可能になります。
ボウハンティングは後述の様に太い木に足場を作ってそこから撃つか、水場か餌場近くの待ち屋に隠れて待ち受けます。獲物の位置と落差がある事も多く、出来れば照星の数だけ試射をして矢の位置を確認しておきます。
これだけ事前に確認しておけば、落着いて所定の場所まで引き寄せ、予定の照準器に載せ、トリガーを引けば、矢は必ず急所にヒットします。
急所はライフルの時と同じと言えますが、骨の無い所を狙うか骨のある所を狙うのかによって、矢尻の種類を変える必要があります。


左側8種類は主に骨の無い所の急所を撃つ鏃です。鏃には剃刀並の刃が付いています。
鏃はヒットすると開く物も多くあり、下段がそれになります。この場合切り裂き幅は約5㎝に及び、また緑の鏃は直径3㎝を丸く切り取り、308弾頭の直径1.5㎝ダメージを遥かに超えます。
しかしこれらの刃物は余り丈夫ではなく、骨にヒットすれば壊れます。それに対し右の8種は骨の急所を狙う鏃です。
昔からのライフル弾の鉛弾頭は骨の無い急所を専用の撃つ弾頭でした。
骨にヒットすると、鉛が全量飛散して威力を失うと言う、非常に大きな欠陥がありました。
それに対し銅弾頭は骨をも砕く改良された万能弾頭となりました。この銅弾頭と前足軸線上の背骨との交点である「ナミビアポイント」の組合せは即倒率100%で「最強」となりました。
従来型ボウでは矢の刺さる深さもそれ程深くなかったのですが、初期型コンパウンドボウでは貫通または深く刺さる様になり、後期型のコンパウンドボウでは大物エルクやブラウンベアでも貫通する様になりました。
照準器は落差補正用に3~5種類のセッティングが可能になっています。
ライフル弾でもそうですが、貫通すると出血が数倍多くなり、倒れるまでが早くなり、且つ追跡が容易になります。ケンさんの使う308のバーンズ銅弾頭の140grは大物エゾ鹿のショルダーを貫通しますが、超大物エゾ鹿のショルダーでは最後の皮の所で止まり、ヒグマでは全弾が停止していました。
こうして見ると威力と言う点で見れば、コンパウンドボウは308弾以上のパワーと言う事になります。即倒と言う点では現在の高速ライフル弾が1番良く倒れます。特に銅弾頭ならではの撃ち方ですが、前足軸線上の背骨との交点付近がベストポイント、100%即倒します。
弓矢は便利な飛び道具ですが、矢速が低く急所を狙える射程距離は、落差補正をしても30m程度でした。ならば初期のノーライフル丸弾の銃と同程度だったではないかと言えば、その通りです。
しかし絶対的な違いがありました。それは照準器です。銃には初期の頃から照準器が付いており、落ち付いて照準して撃てば、落差補正は不要で、必ず命中しました。
それに対し弓矢では最近まで照準器がなく、目の位置と矢の位置は上下と左右がズレており、これをカンで補正し、更に10mを超えると落差補正をカンで処理しなければ、命中しない高難度な狩猟道具でした。
銃のライフリング自体は1498年に発明されましたが、1546年以降のミニエー弾の普及まで、実用化が遅れたとは言え、すでに450年以上前から普及しています。しかし実はノーライフルと丸弾の歴史は1965年頃まで続きました。どうして1965年まで丸弾は続いたのか?
1.狩猟ブームの始まった頃の日本のハンター。
それは猪猟がメインで、大物猟時に散弾銃のノーライフルバレルから1粒弾を撃つ為にそうなりました。1970年代頃のハンターは殆どが雉撃ちで、そのイメージは猟犬を連れ、水平2連銃を担いでいました。
夢は猪や鹿の捕獲であり、服装は上からハンティング帽、厚手の赤チェックのシャツ、革のチョッキの、胸には丸弾スラグ弾2発、腰には25発弾帯、乗馬ズボン、靴は軽量地下足袋でした。
右写真は帽子がちょっと違いシャツが薄手ですが、概ねそんな感じでした。
下写真の少年は概ね当時のイメージです。弾帯は腰の位置が正しいです。
チョッキは革製以外や、サファリジャケットの様に長袖の場合もありましたが、偶発的大物戦に備えた、胸のスラグ弾2発は共通装備品でした。チョッキの背中部分はサブザックになっており、捕獲したキジを入れたり、雨具を入れていました。
水平2連銃は初矢がインプシリンダー、後矢フル チョークであり、丸弾スラグはフルチョークから安全に撃てる様に、やや小さ目に出来ており、その為に確実に急所が狙えるのは20~30mでした。
その後の時代では銃は単身のインプシリンダーチョークの自動銃となり、弾頭はフォスタースラグ弾となり、射程距離は50mまで延長されました。また射程80mのブリネッキ弾と言うのもありました。
現在の銃身ではリブがあり、その延長上は昔より容易に掴め、オープンサイトと大差ありません。
2.コンパウンドボウの進化。
弓矢も和弓の初速は60m/sですが、近年の洋弓では用具も進化し、コンパウンドボウで100m/sの初速が可能となり、また矢の進化から精度も大幅に向上しました。
和弓では距離28mから直径36cmの的を狙いますが、オリンピックのアーチェリー競技では2倍以上の距離の70mから10点圏が12㎝強の的を狙います。
2.5倍の距離で33%の大きさの的ですから、和弓よりアーチェリーの方が原理的に高精度です。洋弓ならば70mの射程が十分有るかの様にも見えますが、実戦での落差補正を考えますと、現在でも有効射程は30m前後となり、50m前後が限界となりますが、事前試射が出来れば80mも可能です。
矢の初速からすれば、20mまでは落差無視で狙え、30mは完全に落差補正を要し、絶対確実と言う事になると僅か10~20mに留まります。

尚、ボウガンと言う、一見すると機能の高そうな道具もありますが、矢が短く精度が出ません。
従ってこれを使ってボウハンティングをしようとする人は少ないと思います。
3.アラスカのカリブーのボウハンティング。
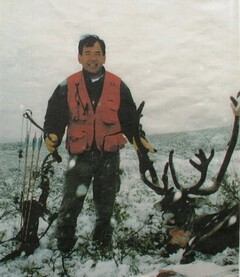
飛び道具研究科のケンさんは愛用のアーチェリーやパチンコで、30m先の空き缶を外さない程度の腕前は持っており、写真は2000年8月にアラスカ北部にて、飛び入り参加、捕獲させて頂きました。アラスカは8月20日、この日から冬が始まりました。
当時の弓矢もパワー的には馬鹿に出来ず、射程距離以外は少なく見ても308と同等以上でした。当時も今に比べれば不完全ですが、小さな照準器は付いていました。
ケンさんは愛用のアーチェリー感覚で照準器を使わずに矢を発射しました。30m先を走るカリブーに思い切りスイングし、前過ぎたかと思う位のリードを取って発射しました。
矢の行き先を見ていますと、前過ぎる様に見えましたが、最後の瞬間に矢は見えなくなりました。
その直後から、狙っていたカリブーは急に速度を落とし、やがて倒れました。ヒットは心臓のやや後方、矢は貫通しており、ヒットした周辺を見ても見当たりません。
見付かれば記念に貰って来ようと思ったのですが、残念に終わりました。鏃は3-1-4項左上のカミソリ3枚の3角鏃だったと思います。
エゾ鹿と同クラスのカリブーを貫通したのですから、少なくとも308と同じ程度のパワーです。
ボウハンティングではネット動画で見ても即倒する事はかなり稀ですが、ライフル銃のエゾ鹿心臓狙いで走られる距離よりも遥かに短距離で倒れました。現在のコンパウンドボウでは更に強力となり、マグナムライフル以上のパワーがあり、大型のブラウンベアでも貫通しています。
3-1.野性動物へのハンディ政策。
1990年頃からの狩猟用ライフル銃は300mの射程を持つ様になり、野生動物側にハンディを与える為にピストル・先込め銃・弓矢・ショットガンの4種が新しい狩猟方法が検討されました。そして最終的に弓矢とショットガンが生き残りました。


3-1-1.短銃による狩猟:454カスールでは300gr弾頭を1625fps、パワー1759ft-lbfと数字的には20番スラグ並の数値であり、最強のピストル弾500SWならば2500ft-lbfと30口径Stdライフルに肉薄して来ます。
しかし、命中しなければ、どんな強力な弾も無意味、強力過ぎる銃は命中させ難いのです。
ケンさんの感触ではまともに撃てるのは44レミントンマグの270gr、1450fps、1260ft-lbf程度までと思います。
銃身の前の部分はバランサーを兼ねたサイレンサーですが、弾は超音速弾であり衝撃波を発する事、及びシリンダーとバレルの隙間からの漏れ等々で消音効果は殆ど期待出来ません。
短い銃身に依り、射程距離を短くして野性動物にハンディを与え様とする物ですが、極めて短い銃身からは高精度を求める事が出来ず、獲物の急所に当てられず、またヒットしても半矢未回収が多く、ハイパワーマニアを刺激した新短銃のデビューだけに終わり、余り普及せずに終わりました。
3-1-2.マズルローダーハンティング:黒色火薬のマズルローダーならば野性動物に与える短射程は可能ですが、半矢未回収を押さえる為、マズルローダー定義が拡大され、ライフリングも無煙火薬もサボットも全てOKとした為、現用ボルトアクションライフルを改造したモダン型マズルローダーでサボットを使えば現用ライフルとの性能差は無くなり、動物保護意味が薄くなり普及していません。
3-1-3.ショットガンハンティング:初期にはノーライフルバレルから発射する射程50~80mスラグ弾で検討されていたのですが、半矢・未回収問題からサボットスラグ弾&フルライフルバレルもOKとなり、最大射程は150mとなりました。
それでもライフルの300mからすれば射程半分とハンディは確保されており、精度の実用性も十分にあり、その前の週はボウですから、よく普及していました。
しかし、エゾ鹿でもそうですが、通常のハンティングはアメリカでも100m前後が多く、実質ハンディが余り無い事が分かり、近年は減少気味となりました。

日本のエゾ鹿猟用サボットスラグ銃は国内法に合わせ、このライフリングを50%未満とした物が使われています。このサボットスラグ銃のお陰で経験年数がライフルに届かない新人ハンターでもエゾ鹿猟が可能になりました。
国内法ではライフリングのある銃身は全てライフル銃となり、ノーライフルでも ライフル弾の撃てる銃はライフル銃となります。その為、ライフリング長を50%未満としているのです。
長野の青木の陰で一気に悪者の銃と言う事になってしまいました。
3-1-4.ボウハンティング:その名の通り弓矢による狩猟です。
ボウ射程距離は30~50m程度であり、野性動物側に最も大きなハンディを与えた事にもなります。多くのエリアでは狩猟解禁は1か月間、期間中の1カ月全部を休暇にする人も少なくはありません。
最初の1週間はボウで解禁、次の1週間がショットガン(バックショット禁止)、最後がライフルになります。多くの州で定数は1シーズン1頭のみ、もう1頭獲りたい時は別の州に行かなくてはなりません。
それに対し、日本の定数は1日オス1頭+メス無制限、シーズンは3か月間以上、ケンさんのスクールでは生徒が5日で19頭が最高、ケンさんは5日で50頭を捕獲した事もあります。
鹿猟に付きましては世界中で超ダントツ、如何に日本が恵まれている事か分かると思います。
ボウは射程内まで引き寄せる難しさもありますが、注意事項を守れば狩猟経験の無い獲物は引き寄せる事が可能です。また音がしないので獲物が余り逃げず、結果的に出会い率も捕獲率も共に銃猟に比べて遥かに高く高人気です。またド至近距離までじっと引き寄せるスリルも格別です。
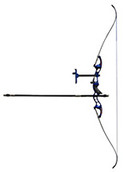


上写真は左から従来型の貫通しないリカーブボウ、初期型コンパウンドボウ、後期型コンパウンドボウ、そして使う矢はカーボン製、照準器も完璧となりました。弓を引くとピープサイトが目の前に来る様に調節します。次に照星を希望の距離で正しく命中する様に調整します。
照星は3~5種あり、希望の落差に合わせられます。言葉換えれば、3~5種の射程距離の設定が可能になります。
ボウハンティングは後述の様に太い木に足場を作ってそこから撃つか、水場か餌場近くの待ち屋に隠れて待ち受けます。獲物の位置と落差がある事も多く、出来れば照星の数だけ試射をして矢の位置を確認しておきます。
これだけ事前に確認しておけば、落着いて所定の場所まで引き寄せ、予定の照準器に載せ、トリガーを引けば、矢は必ず急所にヒットします。
急所はライフルの時と同じと言えますが、骨の無い所を狙うか骨のある所を狙うのかによって、矢尻の種類を変える必要があります。


左側8種類は主に骨の無い所の急所を撃つ鏃です。鏃には剃刀並の刃が付いています。
鏃はヒットすると開く物も多くあり、下段がそれになります。この場合切り裂き幅は約5㎝に及び、また緑の鏃は直径3㎝を丸く切り取り、308弾頭の直径1.5㎝ダメージを遥かに超えます。
しかしこれらの刃物は余り丈夫ではなく、骨にヒットすれば壊れます。それに対し右の8種は骨の急所を狙う鏃です。
昔からのライフル弾の鉛弾頭は骨の無い急所を専用の撃つ弾頭でした。
骨にヒットすると、鉛が全量飛散して威力を失うと言う、非常に大きな欠陥がありました。
それに対し銅弾頭は骨をも砕く改良された万能弾頭となりました。この銅弾頭と前足軸線上の背骨との交点である「ナミビアポイント」の組合せは即倒率100%で「最強」となりました。
従来型ボウでは矢の刺さる深さもそれ程深くなかったのですが、初期型コンパウンドボウでは貫通または深く刺さる様になり、後期型のコンパウンドボウでは大物エルクやブラウンベアでも貫通する様になりました。
照準器は落差補正用に3~5種類のセッティングが可能になっています。
ライフル弾でもそうですが、貫通すると出血が数倍多くなり、倒れるまでが早くなり、且つ追跡が容易になります。ケンさんの使う308のバーンズ銅弾頭の140grは大物エゾ鹿のショルダーを貫通しますが、超大物エゾ鹿のショルダーでは最後の皮の所で止まり、ヒグマでは全弾が停止していました。
こうして見ると威力と言う点で見れば、コンパウンドボウは308弾以上のパワーと言う事になります。即倒と言う点では現在の高速ライフル弾が1番良く倒れます。特に銅弾頭ならではの撃ち方ですが、前足軸線上の背骨との交点付近がベストポイント、100%即倒します。