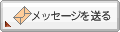2024年11月04日
皆さんに伝えたい事。その6と7:ワンホール射撃と300m遠射。
6.「ワンホール射撃」。
ライフルマンなら1度は達成したいのがワンホール射撃です。
ワンホール射撃は銃と弾の極限値に近く、フリンチングの完全排除が必要となります。

ケンさんの最高記録は150mテーブル撃ち5発が12㎜でした。
グルーピングだけで言えば5発8㎜と言う記録もありました。銃はH&K SL7オート 308です。

サコー75の頃は激安弾薬にした為、5発テーブル撃ち1ホールは1度も出せず、18㎜ワンホ-ル崩れが最高でした。3発は11㎜が最高でしたが、8㎜の記録が新たに見付かりました。
150m射撃で10㎝のシューターの3発が、8㎜に着弾する確率は、約1.9万発を撃つと3発が8㎜以内に入っていると言う物です。1.9万発はライフル銃の寿命を遥かに超えており、従ってこの記録がマグレと言うは絶対にありません。
ケンさんのフリンチング排除は、2000年末に交通事故に巻き込まれ、約2年間外出不能で射撃場に行く事が出来ずにいました。
家で出来る事は弾を入れない「ドライファイア」だけ、これを1年以上繰り返しました。そして2002年射撃再開のその日にワンホールが達成されました。
当初は縦長のワンホールの弾痕を横転弾1個、残りは弾着不明かと思いましたが、よく見直すと1ホール射撃でした。
結果的に1年強を続けたドライファイアが射撃には反動を伴わないと体を騙す事に成功しました。
前半は1日30分間のドライファイアでした。
後半は完璧に銃の揺れタイミングがセンターに合っている特に、微動もなく引き金が落ちる、完璧射撃の連続3回が続くまで連日行いました。
フリンチングは1発撃てばすぐにブリ返す為、撃つ前に毎回10~20回のドライファイアがお薦めです。
7.「遠射300m。」
スコープ照準は遠距離射撃や精密射撃には非常に有利で、更に上向き射撃のお陰で実用射程距離が約2倍となり、200mまで落差無視直撃射撃が出来ます。
弾は微少上向きで発射され、40m付近でゼロ点を通り、その後も上昇を続け、100m付近で3㎝上となり、その後は2乗的に下降、150mで再びゼロ点を通ります。
200mで5㎝下となり、0~200mまでの実用域では全て直撃照準でOKとなります。300mでは恐らく40㎝程度下だと思われます。
ケンさんは300mを実用化していますが、300mの落差を知らないのです。
その300mの手法は後述で説明します。
300mゼロインにしますと300mでは落差がありませんが、150m付近で上側15㎝強を飛行し、マイナス補正を要します。補正量は150mゼロイン時と比べ、半分以下となります。
こちらの方が有利だと言う人も多数います。300m射撃が主体或いはその確率が高ければそれで正解と言えますが、実際のエゾ鹿は150m前後に圧倒的に多く、300mは稀です。
憧れの300mを成功させたいはヨシとしても、常用時の殆どをマイナス補正しなければならないのは、大きな損失です。
落差補正の不安があれば命中しなくなるからです。
現実として通常射撃場通いで得られるのは100m射撃能力までした。
ケンさんスクール生徒約100名中概ね半数がライフルですが、200m射撃能力を持った生徒は皆無でした。同様にライフル銃1年生とサボットスラグ銃で、150m能力を持った生徒も皆無でした。
300m射撃能力を持つ射手は世間でも稀で1%未満です。
300m遠射は手順さえ踏めば誰でも出来ますが、現実は1%未満の誰も出来ない絶望的領域に近く、それを憧れても始まりません。
遠射がそもそも成功しない理由は2つです。1つは撃つ前から「遠いなあ、当たるかな」と言う不安、2つ目は落差補正がこれでイイのだろうかと言う不安です。
共に不安射撃は命中しないのです。
200m能力を持たない人が300mに挑戦しても命中する筈がありません。


これをヒットさせる方法は「全依託射撃」です。
ボンネット上にサンドバッグなり手荷物等を置台にして空いた左手はパッドエンドを持ち、握拳の強さや傾きで照準の微調整を担当します。
この手法ではブレは皆無となり、外れ様がありません。
ケンさんの置き台はハードスポンジですが、この置台の位置や材質に依り、発射時に銃が跳ね、弾着が150mで10㎝弱上がり、それが落差補正側に働いてくれる為、落差補正はチョイなのです。
ライフルマンなら1度は達成したいのがワンホール射撃です。
ワンホール射撃は銃と弾の極限値に近く、フリンチングの完全排除が必要となります。

ケンさんの最高記録は150mテーブル撃ち5発が12㎜でした。
グルーピングだけで言えば5発8㎜と言う記録もありました。銃はH&K SL7オート 308です。

サコー75の頃は激安弾薬にした為、5発テーブル撃ち1ホールは1度も出せず、18㎜ワンホ-ル崩れが最高でした。3発は11㎜が最高でしたが、8㎜の記録が新たに見付かりました。
150m射撃で10㎝のシューターの3発が、8㎜に着弾する確率は、約1.9万発を撃つと3発が8㎜以内に入っていると言う物です。1.9万発はライフル銃の寿命を遥かに超えており、従ってこの記録がマグレと言うは絶対にありません。
ケンさんのフリンチング排除は、2000年末に交通事故に巻き込まれ、約2年間外出不能で射撃場に行く事が出来ずにいました。
家で出来る事は弾を入れない「ドライファイア」だけ、これを1年以上繰り返しました。そして2002年射撃再開のその日にワンホールが達成されました。
当初は縦長のワンホールの弾痕を横転弾1個、残りは弾着不明かと思いましたが、よく見直すと1ホール射撃でした。
結果的に1年強を続けたドライファイアが射撃には反動を伴わないと体を騙す事に成功しました。
前半は1日30分間のドライファイアでした。
後半は完璧に銃の揺れタイミングがセンターに合っている特に、微動もなく引き金が落ちる、完璧射撃の連続3回が続くまで連日行いました。
フリンチングは1発撃てばすぐにブリ返す為、撃つ前に毎回10~20回のドライファイアがお薦めです。
7.「遠射300m。」
スコープ照準は遠距離射撃や精密射撃には非常に有利で、更に上向き射撃のお陰で実用射程距離が約2倍となり、200mまで落差無視直撃射撃が出来ます。
弾は微少上向きで発射され、40m付近でゼロ点を通り、その後も上昇を続け、100m付近で3㎝上となり、その後は2乗的に下降、150mで再びゼロ点を通ります。
200mで5㎝下となり、0~200mまでの実用域では全て直撃照準でOKとなります。300mでは恐らく40㎝程度下だと思われます。
ケンさんは300mを実用化していますが、300mの落差を知らないのです。
その300mの手法は後述で説明します。
300mゼロインにしますと300mでは落差がありませんが、150m付近で上側15㎝強を飛行し、マイナス補正を要します。補正量は150mゼロイン時と比べ、半分以下となります。
こちらの方が有利だと言う人も多数います。300m射撃が主体或いはその確率が高ければそれで正解と言えますが、実際のエゾ鹿は150m前後に圧倒的に多く、300mは稀です。
憧れの300mを成功させたいはヨシとしても、常用時の殆どをマイナス補正しなければならないのは、大きな損失です。
落差補正の不安があれば命中しなくなるからです。
現実として通常射撃場通いで得られるのは100m射撃能力までした。
ケンさんスクール生徒約100名中概ね半数がライフルですが、200m射撃能力を持った生徒は皆無でした。同様にライフル銃1年生とサボットスラグ銃で、150m能力を持った生徒も皆無でした。
300m射撃能力を持つ射手は世間でも稀で1%未満です。
300m遠射は手順さえ踏めば誰でも出来ますが、現実は1%未満の誰も出来ない絶望的領域に近く、それを憧れても始まりません。
遠射がそもそも成功しない理由は2つです。1つは撃つ前から「遠いなあ、当たるかな」と言う不安、2つ目は落差補正がこれでイイのだろうかと言う不安です。
共に不安射撃は命中しないのです。
200m能力を持たない人が300mに挑戦しても命中する筈がありません。


これをヒットさせる方法は「全依託射撃」です。
ボンネット上にサンドバッグなり手荷物等を置台にして空いた左手はパッドエンドを持ち、握拳の強さや傾きで照準の微調整を担当します。
この手法ではブレは皆無となり、外れ様がありません。
ケンさんの置き台はハードスポンジですが、この置台の位置や材質に依り、発射時に銃が跳ね、弾着が150mで10㎝弱上がり、それが落差補正側に働いてくれる為、落差補正はチョイなのです。
2024年10月07日
ヒグマに会って来ました。
狩猟解禁の10月1日を挟んで、北海道に1週間のレンタカードライブに行って来ました。
エゾ鹿猟ブームの頃とは時代が変わり、エゾ鹿ハンターらしき車は1台も見る事は無くなりました。

またもう1つ、北海道名物であった鮭釣りも、北海道の殆どが鮭の放流を辞めて10年が過ぎ、遡上数が激減、また漁港が鮭釣りを締め出した為、釣具店も多数が倒産しました。
そんな事から釣り餌を入手出来ず、渓流釣りも鮭釣りには行けませんでした。
ヒグマには会えましたが、エゾ鹿にはメスしか出会えずでした。
オス鹿は大物クラスに1度会えましたが、カメラを向ける時間が無く、森に入ってしまいました。

摩周湖の裏側になりますが、「神の子池」そして「サクラの滝」の2つに新たに行って見ました
「神の子池」は、今やすっかり有名となりました「美瑛の青い池」より遥かに素晴らしい物でした。

「サクラの滝」は6~7月がピークですが、「山女魚」の降海型に「サクラマス」が産卵の為に多数遡上します。それでも当日は30分の間に5匹の遡上が見られました。

エゾ鹿猟ブームの頃とは時代が変わり、エゾ鹿ハンターらしき車は1台も見る事は無くなりました。
またもう1つ、北海道名物であった鮭釣りも、北海道の殆どが鮭の放流を辞めて10年が過ぎ、遡上数が激減、また漁港が鮭釣りを締め出した為、釣具店も多数が倒産しました。
そんな事から釣り餌を入手出来ず、渓流釣りも鮭釣りには行けませんでした。
ヒグマには会えましたが、エゾ鹿にはメスしか出会えずでした。
オス鹿は大物クラスに1度会えましたが、カメラを向ける時間が無く、森に入ってしまいました。
摩周湖の裏側になりますが、「神の子池」そして「サクラの滝」の2つに新たに行って見ました
「神の子池」は、今やすっかり有名となりました「美瑛の青い池」より遥かに素晴らしい物でした。

「サクラの滝」は6~7月がピークですが、「山女魚」の降海型に「サクラマス」が産卵の為に多数遡上します。それでも当日は30分の間に5匹の遡上が見られました。

2024年06月09日
ツキノワグマ捕獲名人。その2.
大谷石之丞:明治38年(1905)、津軽で最も僻地と思われる赤石村奥地の百姓の次男として生れました。小学校卒業後、家業に従事の傍ら、マタギのシカリ大谷吉左エ門さんから、マタギや川漁の手解きを受けました。
赤石村は藩政時代からマタギの村として知られ、昭和62年(1987)82才で亡くなるまで、60年以上も獲物を追い続け捕獲数は78頭、命懸けの人生でした。

当時は単発の村田銃で足を止め、槍で止を刺すやり方でした。
山の詳しさに於いては、右に出る者がいなく、山の読みが鋭い。より安全により効率的に目的を果たす為には、何と言っても山を知る事が最も重要な条件となります。
持ち前のこの特技を生かして、クマのいそうな所へ迫るのに妙を得ていました。
クマがどこを通るか、どこで待てば良いか、事の成行きに付いて判断は誠に適切で事実、その通りになる事が十中八九であり、誠に戦略に長けた人だったそうです。
吉野秀市:群馬で一般的な猟は、2人1組で数匹の猟犬を連れて穴熊を探し当てる物と、6~7人で行う巻狩りですが、彼はマタギ等の集団による巻狩りとは違って、群馬の藤原郷で殆ど単独で猟をして来ました。
積雪期に穴に籠っている熊を穴から熊を追い出し、銃で仕留める方法でした。

その捕獲数が桁外れ、1シーズンに最大32頭の捕獲実績を持ち、生涯では300頭もの月の輪熊を捕りました。「最後の熊捕り名人」として紹介されています。
恐らく彼が最多数捕獲者だったと思われます。原則単独猟の吉野さんは生涯で300頭を捕り、大きな怪我をする事もなく、その銃の腕は一度も撃ち損じた事は無いと言う程の物でした。
しかしその多数捕獲の原因は彼が単に射撃の名手だったからではありません。如何なる射撃の名手であったとしても、射撃の腕だけでそれだけの数の熊を 射止める事は決して出来ません。
それにはまず何よりも熊の棲息する山域の自然を吉野さんが熟知していた事と、そこで生活する熊の生態を知り尽くしていた事にこそあると言えました。
それはマタギを初め猟をする人々誰もが目指していた事であるにも拘らず、彼程それを成し遂げた人はいませんでした。
毎年冬の3月頃まで単独で山に入り熊を追うと言う事は、名人と言えども数々の危機を体験する事無しに、成得る物ではありません。万が一の事態に備える周到さが何時もあったと思われます。
恐らく誰も無し得なかった手法で、熊の冬眠穴を次から次へと発見して行ったと思われますが、凄い人がいた物だと感心します。
赤石村は藩政時代からマタギの村として知られ、昭和62年(1987)82才で亡くなるまで、60年以上も獲物を追い続け捕獲数は78頭、命懸けの人生でした。

当時は単発の村田銃で足を止め、槍で止を刺すやり方でした。
山の詳しさに於いては、右に出る者がいなく、山の読みが鋭い。より安全により効率的に目的を果たす為には、何と言っても山を知る事が最も重要な条件となります。
持ち前のこの特技を生かして、クマのいそうな所へ迫るのに妙を得ていました。
クマがどこを通るか、どこで待てば良いか、事の成行きに付いて判断は誠に適切で事実、その通りになる事が十中八九であり、誠に戦略に長けた人だったそうです。
吉野秀市:群馬で一般的な猟は、2人1組で数匹の猟犬を連れて穴熊を探し当てる物と、6~7人で行う巻狩りですが、彼はマタギ等の集団による巻狩りとは違って、群馬の藤原郷で殆ど単独で猟をして来ました。
積雪期に穴に籠っている熊を穴から熊を追い出し、銃で仕留める方法でした。

その捕獲数が桁外れ、1シーズンに最大32頭の捕獲実績を持ち、生涯では300頭もの月の輪熊を捕りました。「最後の熊捕り名人」として紹介されています。
恐らく彼が最多数捕獲者だったと思われます。原則単独猟の吉野さんは生涯で300頭を捕り、大きな怪我をする事もなく、その銃の腕は一度も撃ち損じた事は無いと言う程の物でした。
しかしその多数捕獲の原因は彼が単に射撃の名手だったからではありません。如何なる射撃の名手であったとしても、射撃の腕だけでそれだけの数の熊を 射止める事は決して出来ません。
それにはまず何よりも熊の棲息する山域の自然を吉野さんが熟知していた事と、そこで生活する熊の生態を知り尽くしていた事にこそあると言えました。
それはマタギを初め猟をする人々誰もが目指していた事であるにも拘らず、彼程それを成し遂げた人はいませんでした。
毎年冬の3月頃まで単独で山に入り熊を追うと言う事は、名人と言えども数々の危機を体験する事無しに、成得る物ではありません。万が一の事態に備える周到さが何時もあったと思われます。
恐らく誰も無し得なかった手法で、熊の冬眠穴を次から次へと発見して行ったと思われますが、凄い人がいた物だと感心します。
2024年06月09日
ツキノワグマ捕獲名人。その1。
志田 忠儀 (シダ タダノリ):1917年、山形県西川町大井沢生まれ。8歳から山に入り15歳で熊を撃ち、生涯で50頭以上の熊を仕留めた伝説の猟師でえした。

戦前から 山に入り、3度の召集の後、戦後も3月ウサギ撃ち、4~5月は熊撃ち、6月ゼンマイ採り、夏は釣り、秋は茸や山菜取り、その後はイタチ狩りや再びクマ狩り、そして厳しい冬、1年を通じて山と共に生きた伝説の山人として知られています。
80歳過ぎまで現役のマタギとして活躍しました。1959年、磐梯朝日国立公園朝日地区管理人になり、朝日連峰遭難救助隊を務め、1982年同管理人を退くまで地元のブナ林を守る環境活動にも携わりました。
地元猟友会会長等を歴任。それらの功労で1989年、勲六等単光旭日章を受章しました。
100歳で天命を全うした伝説の猟師の知恵山に生きて来た男でした。
「ラスト・マタギ」「伝説の猟師の知恵」等の著書があります。2016年5月23日没。
舘香菜子(たて かなこ 2022年現在27才):青森県東通村役場の農林畜産課に勤務。ハンターではありませんが、庁内で「熊捕り名人」として知れ渡っています。

50歳以上も年上のベテラン猟師達から、親しみと尊敬の念を込めて「親方」と呼ばれています。
獣害対策を担う先輩達をサポートして来ましたが、経験を重ね前向きな姿勢と 農家の顔を覚えた事等から本格的に任される様になりました。
ツキノワグマはブルーベリーなど果実を好みます。一方で畜産農家が保管の為に地中に埋めているトウモロコシも掘返して食べてしまいます。
民家近くに出没するクマは、ドラム缶で作ったワナで捕獲するのですが、設置場所の僅かな違いでも全く入ってくれません。
きっかけはベテラン猟師のボヤキでした。「どうしたら入ってくれるのか」。餌を求めクマが通る「獣道」は決まっており、すぐそばにワナを仕掛けなければ捕獲する事は難しいのです。
現場に出向くと倒伏した雑草があり、かすかにクマの残り香が漂っていました。
「根拠がある訳では ないけれど、ここを通る」と直感した場所にワナを移設すると、その日の夜に掛かり、同じパターンが何度か続きました。
抜群のセンスと猟師達に評価され、設置場所への相談が舞込む様になったそうです。
高関辰五郎:1890年マタギで有名な阿仁町に生まれ、18歳で白神山地の岩崎村大間越に住み、阿仁町でも岩崎村でも仙人と呼ばれた伝説的なクマ撃ち名人でした。
1人で撃ち取ったクマが105頭、仲間と獲ったクマなら300頭は下らないと言います。彼は獲物の多い白神山地に目を付け、津梅川のそばに小さな小屋を建てて住む、伝説の名人マタギでした。
上原武知:長野県上高井郡仁礼村字米子に住み、かなり以前の記録と思われますが、本件記録時には未だ45歳である彼はクマ撃ちを始めてから未だ僅かに7年間に44頭の月の輪熊を斃したそうです。
この地方の山村には、信州側にも越後側にも幾人もの熊撃ちがいますが、彼を一躍名人としたのは、彼の豪胆にして射撃が正確、そして健脚でした。
この名人が縄張りとしている山は、上州と越後と信州の三国が境する白砂山から始まり、西へ大高山、赤石山、横手山、渋峠、万座山、猫岳、四阿山、六里ヶ原等の深い渓谷と密林と懸崖でした。
彼は1度熊の痕跡を見付けるとそれを追いますが、彼の歩く速さは熊よりも速いとされています。
専ら筒の短い単発銃を使うのは、藪や険しい崖を這ったりする時に筒が長いと邪魔になり、2連銃の薄い銃身では銃口が潰れてしまうからです。
熊を引付けるだけ引付け、1~2mの熊の手が届く直前で撃つ、この距離なら外れる事は無く、これが最も正確で安全な方法であると言っています。
今まで幾度か危険な場合に遭遇した事もありますが、一度も怪我した事がありません。

戦前から 山に入り、3度の召集の後、戦後も3月ウサギ撃ち、4~5月は熊撃ち、6月ゼンマイ採り、夏は釣り、秋は茸や山菜取り、その後はイタチ狩りや再びクマ狩り、そして厳しい冬、1年を通じて山と共に生きた伝説の山人として知られています。
80歳過ぎまで現役のマタギとして活躍しました。1959年、磐梯朝日国立公園朝日地区管理人になり、朝日連峰遭難救助隊を務め、1982年同管理人を退くまで地元のブナ林を守る環境活動にも携わりました。
地元猟友会会長等を歴任。それらの功労で1989年、勲六等単光旭日章を受章しました。
100歳で天命を全うした伝説の猟師の知恵山に生きて来た男でした。
「ラスト・マタギ」「伝説の猟師の知恵」等の著書があります。2016年5月23日没。
舘香菜子(たて かなこ 2022年現在27才):青森県東通村役場の農林畜産課に勤務。ハンターではありませんが、庁内で「熊捕り名人」として知れ渡っています。

50歳以上も年上のベテラン猟師達から、親しみと尊敬の念を込めて「親方」と呼ばれています。
獣害対策を担う先輩達をサポートして来ましたが、経験を重ね前向きな姿勢と 農家の顔を覚えた事等から本格的に任される様になりました。
ツキノワグマはブルーベリーなど果実を好みます。一方で畜産農家が保管の為に地中に埋めているトウモロコシも掘返して食べてしまいます。
民家近くに出没するクマは、ドラム缶で作ったワナで捕獲するのですが、設置場所の僅かな違いでも全く入ってくれません。
きっかけはベテラン猟師のボヤキでした。「どうしたら入ってくれるのか」。餌を求めクマが通る「獣道」は決まっており、すぐそばにワナを仕掛けなければ捕獲する事は難しいのです。
現場に出向くと倒伏した雑草があり、かすかにクマの残り香が漂っていました。
「根拠がある訳では ないけれど、ここを通る」と直感した場所にワナを移設すると、その日の夜に掛かり、同じパターンが何度か続きました。
抜群のセンスと猟師達に評価され、設置場所への相談が舞込む様になったそうです。
高関辰五郎:1890年マタギで有名な阿仁町に生まれ、18歳で白神山地の岩崎村大間越に住み、阿仁町でも岩崎村でも仙人と呼ばれた伝説的なクマ撃ち名人でした。
1人で撃ち取ったクマが105頭、仲間と獲ったクマなら300頭は下らないと言います。彼は獲物の多い白神山地に目を付け、津梅川のそばに小さな小屋を建てて住む、伝説の名人マタギでした。
上原武知:長野県上高井郡仁礼村字米子に住み、かなり以前の記録と思われますが、本件記録時には未だ45歳である彼はクマ撃ちを始めてから未だ僅かに7年間に44頭の月の輪熊を斃したそうです。
この地方の山村には、信州側にも越後側にも幾人もの熊撃ちがいますが、彼を一躍名人としたのは、彼の豪胆にして射撃が正確、そして健脚でした。
この名人が縄張りとしている山は、上州と越後と信州の三国が境する白砂山から始まり、西へ大高山、赤石山、横手山、渋峠、万座山、猫岳、四阿山、六里ヶ原等の深い渓谷と密林と懸崖でした。
彼は1度熊の痕跡を見付けるとそれを追いますが、彼の歩く速さは熊よりも速いとされています。
専ら筒の短い単発銃を使うのは、藪や険しい崖を這ったりする時に筒が長いと邪魔になり、2連銃の薄い銃身では銃口が潰れてしまうからです。
熊を引付けるだけ引付け、1~2mの熊の手が届く直前で撃つ、この距離なら外れる事は無く、これが最も正確で安全な方法であると言っています。
今まで幾度か危険な場合に遭遇した事もありますが、一度も怪我した事がありません。
2024年06月06日
ヒグマ捕獲名人、その3.


原子一男:北海道旭川市在住、1955年生れ「クマ撃ち」歴49年(2024年現在)、
原子(弟)(名前は失念):北海道旭川市在住、1961年生れ「クマ撃ち」歴43年、(2024年現在)兄弟でハンティングの腕前は一流、特に兄の狩猟技術は2007年の後述の事故まで超1流でした 。
捕獲数はネットからは不明ながら、同じ旭川猟友会の同年代の2名に聞きましたが、2007年時点ですでに70頭以上、弟は兄に比べれば半分以下と言われていますが、それでも2019年現在で30頭位だそうで、その後3年間に毎年少なくとも1頭の追加があると思われます。
弟さんは普段は林業に従事され、ハラコゾンメルと言う地元ハンター達に愛用されている登坂に強い雪山用のスキーも制作されています。
そのゾンメルスキーに貼るアザラシ皮(シール)は根室漁協定置網に迷込み溺死した物であり、彼はそれを購入、ケンさんもその皮剥ぎを手伝った事があります。
以下はその「クマ撃ち」ベテラン猟師原子(弟)さんに話を聞いた話です。
原子(兄)さんは、は2007年ヒグマに襲われながらも仕留め、瀕死の重傷で意識不明の重体、両腕が折られ顎も半分取られ、意識朦朧ながら銃を持って車に乗り、20㎞位先の交番で保護されました。
当日朝猟に行って小さいクマを2頭獲った後、昼からまたその近くで足跡を見付けました。でもその熊は見付からず、山の方に背中を向けて歩いていたら、背後の笹からクマが襲い掛かって来ました。
一応命中させましたが、襲撃を阻止する事は出来ませんでした。
翌年の春にその場所から50m位の所に骨になったクマの死体が見付かったそうです。
ヒグマに脳のギリギリまでを齧られ、アゴも半分失い死に掛けましたが、病院で頭蓋骨を外し中を消毒、また頭蓋骨を戻したそうです。
写真は2007年、北海道猟友会の原子兄氏が害獣駆除で450㎏を捕獲した時の物です。
この年の秋に事故に会われました。体力抜群で事故当時52歳、ヒグマ捕獲 経験数も十分あり過ぎヒグマと言う物をやや嘗めていたのかも知れません。本事故以後、このスーパー能力は失われました。
彼曰く、「エゾ鹿なんぞ蚊を叩く様な物」であると、言う話を聞いた事があります。
体力抜群の彼は積雪期にエゾ鹿の新しい足跡を見付けると、ゾンメルスキーで追跡、鹿を深雪に追い込み、動けなくなった群れを丸ごと捕獲するそうです。
「究極の狩猟」国内最大の猛獣「ヒグマ」とはどんな動物なのか? そして「知られざる「ヒグマ撃ち」の世界とは? 原子兄さんは現在も現役ハンタ―、先頃もクマが出て、猟友会として 出動駆除しています。兄さんがそれでも「クマ撃ち」辞めない理由、弟さん」に聞いてみました。
昔(1970年代以前)、親父がやっていた様な時代は、「ヒグマ撃ち」がお金になったからだと 思いますが、今はお金にはなりません。
兄の事は分かりませんが、僕が狩猟が好きなのは、ただ撃ちたいからではなく、山を歩き獲物を獲る事が好きなんです。獲ったら必ずその肉を食べていましたから、まあ楽しんで食べる事でしょうか。
自分が獲った物を食べられると言う事は嬉しい事だと思います。
家族も獲物を取って戻ると、「美味いね」食べますから、楽しみにもしていると思います。
店に並んでいる市販肉とは内容が違い、狩猟で獲る熊とか鹿とか鴨とか、店に出ていない物
ばかりです。獲物がそんなにない時代には、ウサギとかスズメも獲り、狩猟が生活の一部でした。
僕が狩猟を始めたきっかけは、親がハンターで兄もやっており、自分も好きだったので始めました。
「銃を撃ってみたい」という気持ちもありましたし、山を歩くのも好きだったです。初めて狩りの現場に行ったのは、中学生で13~14歳位、その頃から「やってみたいな」と思っていました。
猟銃の所有許可が出るのは20歳からなので、その年齢を待って狩猟免許を取り、その冬から狩りに出ました。最初は鴨を撃っていました。
初めてクマを獲ったのは22歳でしょうか。1人で獲りました。その年齢でクマを獲った人は、まずいないと思います。僕の場合、小さい頃から親父や兄が獲っているのも見ており、凄腕の兄に一緒に付いて行って手伝ったりもしていました。
それで自分で猟をやる様になってからも、極く自然に山を歩いて見付けたから獲ったと言う感じでした。そもそもクマを獲る猟師はおっかないから余りいないです。
普段は林業で、狩猟期間の3~4カ月も、「ヒグマ撃ち」だけをやっている訳ではなく、エゾ鹿撃ちをしていて、ヒグマの足跡を見付け、獲れそうなら獲ると言う感じです。
何でも撃つ一般的なハンターと言えますが、「ヒグマ撃ち」は仕留め損ねると襲い掛かって来る事があり、特別だと思います。
一般的にヒグマに対しての恐怖感は大きくベテラン猟師でも 「おっかないからヒグマだけはやらない」と言う人も多いです。「ヒグマ撃ち」で今の所は危険な目にあった事はありません。
こちら側から危ないなと思えば逆から行ったり、笹が生い茂って視界がない様な所では、特に気を付けながら歩いています。
何時もどうやったら上手い具合に獲れるか考えながら、「襲われても撃てる倒せる」を考え、ヒグマ場合は頭脳戦です。
ヒグマは音にも敏感ですが、臭いにはもっと敏感です。山の中で風が廻っている様な所に人が入ると、その臭いで気付いて逃げられてしまいます。
頭も、耳も、鼻も良く。何かがおかしいと思ったら、立上がり鼻を空に向けて臭いをかいだりしてすぐに逃げてしまいます。「ヒグマ撃ち」は凄く難しいです。
今(2019年)まで仕留めたのは30頭駆除で獲る事はなく、殆どが狩猟なので、それ程多くはありません。昭和時代は害獣駆除として、クマが繁殖する春に「春クマ駆除」と言うのをやっていたんですが、クマの頭数自体も減り、平成の1990年になって廃止になりました。
最近はかなり生息数が増え、家畜を含めた農産物や人的被害があった時には駆除が行われています。
愛用のライフル銃はボルトアクションのサコーM85フィンライト、30-06口径のフィンランドの銃です。自動式を使っていた事もありましたが、ボルト式に換えました。
弾自体が結構高いので全部自分で作っています。ヒグマ撃ちの装備に特別な物はありません。
山に入る時はリュックサックに、ロープと大きいビニール袋とペットシートの60㎝×90㎝を10枚位持って歩いています。鹿を獲った後、解体して肉にして持って帰る時にこれに包むのです。
クマの肉の味は何と表現すればいいんでしょうかね……熊の味がします。
いわゆる市販の牛や豚肉とは全く味が違います。やっぱりちょっと獣の香りはします。
肉は赤身なんですが、秋口になると脂が載って来て中々旨いです。臭いんじゃないかと思われがちですけれど、上手に解体すれば臭みはありません。解体が下手な人がやると、クマの体の外側の体臭が肉に付いてしまい、血抜き不十分であれば臭みが出てしまいます。
肉はちょっと硬目です。特に大きいクマだと筋肉質で、そのまま焼いて食べる事はしません。圧力鍋で煮て一度柔らかくして、それからすき焼きみたいにして食べます。
ヒグマを見付けた時は「止まれ!」って思います。止まらなかったら走っていても撃ちますが、殆ど止まってくれるので、照準を予め合わせておき、こっちを見た瞬間に撃ちます。
鹿もそうですが、熊も殆ど頭しか撃ちません。頭が見える所で止まった瞬間に撃つ。
頭しか撃たないのは1発で殺さないと暴れるからです。近い時は10m位で撃つ事もあります。
そうすると殆ど一発で倒れます。
今年獲ったのは30m位の距離の1頭と、20m位の距離の1頭です。
クマは動きが速いので、その距離で撃ち損じたら大変です。
熊は主食ではありませんが、エゾ鹿を追掛け捕まえて食べています。速くないと捕まえる事が出来ず、熊は鹿より速いのです。僕の様な猟師はやたらに撃ちません。
自分が獲るのは自分達が食べる分だけ。1~2頭獲ったら、それ以上は何頭いても撃ちません。それ以上獲っても処理が大変なだけです。
世の中には動物を保護する視点しか持たない人も多くいます。
街中に出て来たり、農作物を食べてしまうクマの駆除に付いても、「かわいそう」と言う人もいる様ですが、北海道札幌市の住宅街にヒグマが出没し、住民を恐怖に陥れました。
もし自分の家の近くにクマが出て来たら……と想像して欲しいと思います。
真昼間に家の前までクマが来るのです。「黙ってじっとしていたら襲っては来ない」と思ってるかも知れませんけれど、そんな事は有り得ません。
これまで仕留めたクマで一番大きいのは400㎏超えです。大きさで言えば、軽自動車位です。凄く大きいです。
冬で穴に入っていたんですが、穴の近くにおり、もう1人頼んで出て来るのをしばらく待って出て来た所を2人で頭をドンと撃って、それで終わりです。
獲ったクマは翌朝3人で行って解体して、雪の上を引っ張るプラスチックのソリ、3台に乗せて持って帰りました。一日掛かりで戻ったら夕方の6時、真っ暗になっていました。
北海道でも今は冬眠しないヒグマも増えました。ハンターが減りエゾ鹿が凄く増えているから、それを餌にするクマも増えているのだと思います。
1年中食べ物に困らないので山奥にいるクマは大きくなるし、増えてしまうんです。
2024年06月04日
ヒグマ捕獲名人、その2.


池上治男:1949年、北海道上砂川市生れ、砂川猟友会支部長を30年以上務め、地区一のベテランハンターです。
砂川市は札幌から北東へ80km。12月中旬でも腰の高さまで雪が積もる程の豪雪地帯で、辺り一面が白で埋め尽くされていました。
池上さんは高校時代は美術や剣道、トランペットに打ち込みました。卒業後は「太平洋の真ん中でトランペットを吹いてみたい」と言う夢を胸に北海道大の水産学部へ進み、相手の手を掴んだだけで簡単に投げ飛ばす技を見て「剣道とは違う変わった武道だな」と興味を持ち少林寺拳法同好会に所属。
「何時かは道場を開いて子供達に少林寺拳法を教えたい」と言う目標も持っていました。
大学卒業後は、国内トップクラス水産会社の一つ、株式会社極洋の捕鯨部漁労科に配属されました。その後3年間、捕鯨母船の指令室で捕鯨船を指揮し、「太平洋の真ん中でトランペットを吹く」夢も 叶えましたが、捕鯨は世界中で反発運動が高まり、衰退の一途を辿っておりました。
池上さんは1975年に25歳で退職、砂川市に帰りました。「何時かは」と思い描いて来た、「子供達に少林寺拳法を教えたい」と言う気持ちが湧き上がりました。
しかし少林寺拳法の指導はボランティアであり、生活するには本業を別に持たなければなりません。
ある時池上さんは、市内に住む医者から「塾をやってもらえませんか?」と相談を受けました。
その頃の砂川市は、大手財閥が炭鉱会社や化学会社を営む等、市全体に経済力がありました。
一方で子供の平均学力は低下しており、医者の頼みは「医学部に行く様な子を増やしたい。
その為に子供達に勉強を教えて欲しい」と言う物でした。本職を探していた池上さんは早速、妻の実家のクリーニング屋の2階を借りて、学習塾「池上塾」を発足しました。
車で数分の場所に少林寺拳法の道場も開講。学習塾は生徒が次々と地元の偏差値トップ校へ進学した事で、口コミですぐに評判になり、市内の小中学生100人以上が池上塾で学んでいたそうです。
1978年には知人数人で市議会にも挑戦、16時頃まで市議会議員として働き、夜は塾や少林寺拳法の先生として、真面目で面倒見のよい池上さんは、あらゆる場所から引く手数多でした。
「ハンターの人手が足りない」1981年41歳の時、仕事の合間によく通っていた喫茶店のオーナー、当時猟友会事務局長・藤井録郎氏は池上さんにこう漏らしました。
「農家のカラス被害が酷いが、ハンターの人手が足りなくて困っている」。池上さんは資格を取ればハンターとして銃を持てると聞き、「農家の為なら」とやって見る事にしました。
「資格」とは第一種銃猟免許の事です。狩猟に使う銃には主に「ショットガン」と「ライフル」の2種類があり、この免許があればどちらも所持する事が出来ます。
ライフルはショットガンを10年以上所持して初めて所持許可を受ける事が出来ます。
池上さんは的に向かって何度も撃ちながら、ベストな”構え方”を研究しました。
ショットガンとは小さな粒弾が同時に何発も飛ぶ銃で、最大射程距離は約50m程度、鹿や鳥類を撃つ事に適しています。
ライフルは日本で所持が許可される銃の中で最も威力が強く、最大射程は300mに及び、到達距離は何と3㎞に及びます。その威力は「鉄筋すら破壊する」程で、ヒグマは主にライフルで撃ちます。
ヒグマを撃つ際は、弾の威力がまっすぐに行く様に基本「立射」ですが、雪や茂みの中に伏せて撃つ事もありますが、池上さんが「怖い」と感じた事は今まで1度も無いそうです。
「動じない精神を(少林寺拳法で)鍛えていたからね」と池上さんは笑います。
「銃の持ち方は少林寺拳法の「左中段構え」に似ているんですよ。
銃を中央に持ちきちんと頬付けをする。そうしないと銃が跳ねてしまうから、しっかりとした構えが必要なんだ」と理解したそうです。
銃免許を取得した池上さんはまず、事務局長から聞いた通り、カラスの有害駆除を始める事にしました。有害駆除とは、自治体から依頼を受け、農作物の被害などを防ぐ為に行います。
池上さんがヒグマを撃ったのは、それから10年以上後のライフル銃取得後でした。
山の食糧が豊富だった1980年代当時、ヒグマは人里に降りて来なかったのです。
初めて撃ったヒグマの記憶は薄れて来ましたが、1990年代以降、ライフルを使える様になった池上さんは、徐々に「箱罠」に掛ったヒグマの止刺しを依頼される様になりました。
箱罠とは鉄製の檻にエゾ鹿の死骸等を仕掛け、ヒグマが餌を食べようと中に入り、踏み板を踏むと扉が閉まる物です。「檻の外からではなく、檻のすき間から銃を差し込んで、一発でドンッと撃ちます。
普通はおっかなくて、銃を中にも入れられないよ。ヒグマにこう(手で振り払う仕草をしながら)やられてしまえば、銃自体が飛んで行くからです。
ところがね、頭を下げて「まいった」って」ヒグマって言うのは覚悟するのです。「ヒグマは頭が良く」箱罠の中で銃を向けられ、状況を理解するのだと言います。
撃つ場所は、脳天。体を傷付けず1発で苦しまずに倒れる様にする為です。
「可哀想だ」と言う気持ちは池上さんの中に常にあります。
元々池上さんはヒグマの絵を頻繁に描く程、ヒグマの事が大好きでした。池上さんはヒグマを撃った後、必ずその場で手を合わせ、般若心経を唱えます。
「生き物を殺すと言う事は、生命を断ち切る事。
命を頂きますと言う事である」と、絵を眺めながら話します。
彼の教えは、実戦では「必ず一発で仕留めろ」。理由は2つです。
1つはヒグマが苦しまずに済む様にする為です。
もう1つは1発で死なない「半矢」状態にならない様にする為です。
猟場で半矢になった場合、反撃してくる恐れが極めて高く、人に攻撃心を抱いたヒグマは、その後も人を襲う様になります。
その為池上さんはこれまで必ず、1発でヒグマを射止めて来ました。1度も外した事はありません。それがどれだけ凄い事なのか。ある時、池上さんが箱罠のヒグマを撃とうとした際、「ヒグマを撃った事がないので、代わりにやらせて欲しい」と別のハンターに頼まれました。
それならと任せた物の銃を構えた腕がブルブル震え、何時までも撃つ事が出来なかったと言います。殆どのハンターは、例え鹿や鳥類のベテランハンターだったとしても、巨大なヒグマを目の前にすると恐怖に圧倒されてしまうのです。
ヒグマを1発で仕留める為に池上さんが意識している事。それは「歩いている状態のヒグマを決して撃たない事」と、「20m以内の近距離から撃つ事」の2つです。
下手に遠距離から撃ったり、動いているヒグマを狙ったりすれば、半矢になる危険があります。
「撃つ」と言うのは非常に大きな責任が伴ないます。
「半矢となればそのヒグマを山中で探し出し、止めを刺さなければいけないと言う事です。
そして3つ目は、茂みの中に沈んでいるヒグマに狙いを定め、ヒグマが立ち上がり、目が合った瞬間に撃つ事です。撃つのは箱罠と時とは異なり、ヒグマが立ち上がっている為、喉元のやや下です。
「立ち上がった熊はこちらを見ます。その瞬間に撃たないとダーッと走って襲って来る。」そうです。
砂川猟友会にもヒグマを撃った経験のあるハンターは、池上さんを含め3人しかいないのです。
ここで、箱罠の時は「麻酔銃を使えば?」と言う、素人的な疑問も湧きます。
麻酔で眠らせたヒグマを山の中へ運び、そのまま置いて来る事は出来ないのでしょうか?
まず麻酔銃を扱うには獣医師等の専門資格が必要です。
加えて麻酔銃も銃ですから銃を扱う資格を持ち、その中でもヒグマを目前にして僅か数十mから発砲する度胸がある人はまずいません。
そもそも池上さん達ハンターは何故ヒグマを撃つのでしょうか?
池上さんが「我々は“熊撃ち”ではない」と言う様に、商売や趣味、そしてヒグマを撃つ事を生き甲斐にしている人達と、池上さんの様に「有害駆除」のみ行うハンターでは、目的が大きく異なります。
池上さん達の場合、「自治体」「地域の振興局」「警察」の三者が「駆除した方が良い」と判断して初めて、猟友会に依頼が来ます。
この時、特定のハンターが指名される事はありませんが、元々適任者は池上さんを含め、3名しかおらず、支部長である池上さんは自ら担当する事が多いそうです。
自治体毎の「目標頭数」と言うのも存在します。各自治体で目指す、ヒグマの駆除数の事です。
何故そんな物が定められているのかと言うと、ヒグマによる農作物被害は深刻で2019年にはその被害額が北海道だけで2億円以上に及んでいるからです。
「農業は農家さんの一生で、収獲出来る回数が本当に少ないのです。
1年に1回の収穫と考えると、30歳から60代までやったとしても、30数回しか収穫はなく、多大な費用と半年以上の努力の全てが無駄になり、死活問題と言う程度を遥かに超える大問題と言えます。
そんな池上さんは2018年、要請に従ってヒグマを駆除しました。現場には十分な高さの土手がありましたが、それを当局は危険場所の発砲とし、ライフル銃の許可を取消しました。
裁判でその安全性が認められ、ライフル銃の資格を取戻す事が出来ましたが、市街地のヒグマの駆除の在り方を根本的に考えさせられる事件となりました。
2019年以降砂川猟友会では、その理由だけではありませんが、ヒグマ駆除の要請を先頃から辞退を続けています。報酬金目的でヒグマハンターになる人はいません。
国や自治体からの報酬は有りますが、生活の糧に出来る程ではありませんから、誰もが本業を持っています。
ヒグマ駆除その出動は本業停止しての出動となります。
出動すれば若干の手当はありますが、周辺地区に比べそれは高校生のバイト並と余りにも低く、ハンターの特殊技能やヒグマ駆除のリスクが全く考慮されておりません。
住民を守るのが警察の役目ですから、ヒグマ駆除は本来警察の「狙撃部隊」が出動すべきです。
ヒグマ駆除に使えるライフル銃と射撃技術を持っています。
しかし実際のヒグマ戦で正しく機能する事は低率です。
ケンさんスクール事例では体重130㎏の無害と言える大物エゾ鹿に冷静に対処出来たのは100名中僅か2名だけでした。
池上さんが遭遇した最も大きいヒグマは実測体重275kg。射手より遥かに大きな猛獣ヒグマに対し、冷静な射撃が出来る事が条件ですが、対応出来る人は極めて僅かです。
猛獣の目前で日頃の訓練ぶりを発揮出来る人は実は100人に推定1人もいないのです。
ヒグマ駆除のベテランでも捕獲数の多くは箱罠の止め刺しに留まり、実戦ヒグマ撃ちも90%のヒグマは逃げるだけです。
反撃して来るヒグマと対戦した経験を持つハンターは極めて少なく、肝心の時に正しく機能出来る人は甚だ僅かであり、過去にもハンター多数が返り討ちに合っているのが現状です。
そんな池上さんの元には今も自治体から「プロファイリング」依頼が頻繁に舞込みます。
プロファイリングとは、ヒグマの足跡や目撃者等のデータから、ヒグマの移動ルートを探る事です。
約30年ヒグマと向き合い、今も毎朝ヒグマパトロールをし、山を熟知した池上さんだからこそ成せる業です。DNA鑑定等でプロファイリングをする鑑識の専門家とは違い、我々ハンターは現場で「動物と植物の動き」見て判断するんです。
山の変化は毎日見ないとわからない。
早朝に行くのは、ヒグマ達は何時も、夜明けと共に麓へ水を飲みに来るからです。
そんな池上さんをヒグマ達は影から見ているのでしょうか。ある牧場から「ヒグマがよく出て困っている」と言われ池上さんが訪れた所、現場に着くや否や、目の前に突然ヒグマが現れました。
所がヒグマは、池上さんを見るなり物凄い勢いで逃げて行ったそうです。
「ヒグマは怖い人間とそうでない人間を見分けているんです。
猟友会ではヒグマだけでなくエゾ鹿も駆除しており、エゾ鹿の残滓は地中に埋める事になっています。我々が鹿を解体する現場もヒグマは遠くから見ており、解体中に1〜2分その場を離れて戻ったら、忽然と鹿がなくなっていた事もありました、ヒグマが持って行くんです。
また以前埋めた残滓(死がいの事)を掘り起こして食べられている事もありました。
ヒグマが市街地へ来る様になった理由に付いて、池上さんは確信を持っています。「色々な見解がありますが、ヒグマは単にエゾ鹿を追って町に来ているだけだと考えている」そうです。
北海道内で その数を増やし続けているエゾ鹿。天敵だったエゾ狼の絶滅や、ハンターの減少が原因だと言われており、そのせいで増殖し過ぎ、エゾ鹿は山の食糧が不足し、人里に降りてくるのです。
ハンターが駆除したエゾ鹿も、残滓も施設でバイオ処理されます。池上さんは、「本来エゾ鹿残滓は「山に置いてくるべき」だと考えます。
元々ヒグマの主食はエゾ鹿ではありませんが、自らエゾ鹿を捕獲しており、残滓を山に置いてくれば、ヒグマは山の中でエゾ鹿を食べる事が出来、自然の摂理でエゾ鹿は増えず、農作物被害も減り、ヒグマを殺さなくて済む、と思っているそうです。
「ヒグマに出会ったら、とにかく息を殺し、動かない事。万が一気付かれたら、ヒグマの目を見ながら両手を大きく広げ、「俺は人間だ! 来るな!」と大声で威嚇するのが有効」だそうです。
池上さんは今、ハンターとしてヒグマのプロファイリングをする傍ら、池上塾の教え子達はやがて東大や早稲田、一ツ橋大、東北大、等の有名大学を卒業し、彼らが世の中を良くしてくれる事でしょう。
過去には「池上さんの様なハンターになりたい」と訪ねて来る若者もいましたが、池上さんは簡単にOKを出しません。
と言うのも生き物を銃で撃つと言う事は、「反発を受ける」事になるからです。池上さんの元にも抗議の電話が掛かり、酷い時には恐喝まがいの言葉を吐かれる事もあるそうです。
「撃つ事でその人の人生が変わる。家族がいる人に、安易に「行ってくれ」とは頼めません。
池上さんの心の根底にあるのは何時も「半分は自己の為に、半分は人の為に」と言う少林寺拳法の理念です。
自己を確立出来たら、その力を社会や人の為に役立て様、そうした意味が込められていると言います。池上さんは今日も猟友会の支部長として、自身のやるべき事をまっとうしています。
2024年06月02日
ヒグマ捕獲名人。
 山本兵吉
山本兵吉 ベルダン1870
ベルダン1870山本 兵吉(やまもと へいきち)、1858~1950年、日本の猟師。
獣害史最悪と言われた三毛別羆事件のヒグマを退治する等、生涯で捕ったヒグマは300頭と言われます。北海道留萌郡鬼鹿村温根の沢(現・小平町鬼鹿田代)の住人で、鬼鹿山など当時の天塩国の山を主な猟場としました。
山本兵吉の愛銃はロシア製ベルダン1870、黒色火薬11㎜口径単発、村田13年式と同程度のライフル銃です。

大川 春義(おおかわ はるよし)、1909∼1985年、猟師(マタギ)、1915年獣害史上惨劇と言われた三毛別羆事件の舞台となった北海道苫前郡苫前村三毛別(後の苫前町三渓)出身。数少ない目撃者の1人。
当時6歳だったが、同事件の犠牲者の仇を討つ為に猟師となり、生涯にヒグマを100頭以上仕留めてヒグマ狩猟の名人と呼ばれると共に、北海道内のヒグマによる獣害防止に貢献した。

赤石正男(あかいし まさお) 1952年生れ、北海道標津町出身、標津町在住。赤石が初めてヒグマを獲ったのは、成人して散弾銃を持てる様になってすぐの事でした。ハンター歴は約50年、現在も確約中、「野性の熊が最も恐れる男」と呼ばれます。ヒグマの生態を知り尽くし、単独猟歴は120頭を超え、ライフル遠射、罠や捕獲檻を使用しての動物捕獲のエキスパートである。
彼の射程距離は300~400mで、「遠射」の命中率は図抜け、この距離でも、クマより的が小さいエゾ鹿の頭を確実に撃ち抜く事も出来、最長記録は810m先のヒグマだそうです。
赤石氏は「いまだに3ヵ月に2回ペースで、90㎞離れた網走の射撃訓練場に通っている様です。


久保俊治(としはる):1947年、北海道小樽市生まれ。日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育つ。
20歳の時に狩猟免許を取得し、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始する。
1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後は現地プロハンティングガイドにもなるも、翌1976年帰国。
知床半島の根元の標津町で牧場を経営しながら、ドッグレスの単独で山に入りヒグマ猟を行っていました。日本で唯一単独猟のヒグマ猟師。
捕獲頭数は70頭以上と言われていますが、本人は公共せず定かではありません。狩猟方法から推定すれば、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちですからもっと少ない気もします。
2018年~狩猟を目指す人、自然が大好きな人のライフスタイルがより豊かな物になる事を願ってアーブスクールジャパンを開講しました。
2024.4.10.心不全の為76才で死去されました。
ヒグマに気付かれない様に、山に入る自分が自然の中で異質ではいけないと、餌を探す鹿と同じ速さで歩き、自らを自然に溶け込ませ、自然の一部と化して歩を進め5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃し、獲物を苦しめない、獲った命を無駄にしない事を信条としていました。
全ては1頭の為に狩猟技術の高みを目指すと著書等では書かれ、ケンさんも彼の狩猟に憧れた時期もありました。しかしその後ケンさんも色々を経験し技量が上がりました。
現在の推定ではヒグマの周辺を何時も歩き廻り、ヒグマから見てあの人間は「無害」であると思い込ませ、至近距離まで接近し撃ったと思っています。
困難だった時代のアメリカ留学と、その後の独自の子育て方法がマスコミに注目され、「大草原のみゆきちゃん」一気に有名になりました。
著書「羆撃ち」も売れましたが、ドッグレスハンターのケンさんに言わせると前半の主役は偶然に出会えた「天才犬フチ」の大活躍物語であり、後半は「フチ」を無くしてオロオロする単なる「名犬ロリコン」物語と言えました。
2024年05月25日
「ヒグマエースと言う称号」
戦闘機の機銃は飛行機に固定されており、高度な機動をする相手飛行機に先を読み、高難度の飛行機操縦を瞬時且つ精密に行い、機銃を相手の飛行機に向け、撃墜します。
ここ1番に「肝が座っていなければ」出来る技ではありません。
長年やっていれば1~2機はマグレ撃墜もあり得ますが、5機はマグレではない事の証明となり、それを称えるのがエースと言う称号です。
第2次大戦のアメリカでは数万人の戦闘機パイロットがいましたが、エースは僅か30人余です。
大物猟でも同様の事が言えます。ここ1番に足が地に着いた射撃が出来なければ、勝負に勝てないのは戦闘機と同じです。
一般的に鹿撃ちと言えば、本州鹿巻狩りになりますが、ケンさんは最初の1頭捕獲までに9年間出撃70余日を要しました。最初の10年間ではこの1頭だけでした。
1.ヒグマエース。
その後まもなくしてケンさんは本州鹿猟に開眼、その後の4年間の40日で20頭を捕獲、ここでエゾ鹿猟に転向、2回目の10年間では約100頭を捕獲、続く3回目の10年間では約1000頭を捕獲、「不可能に挑戦」のライフワークを続けて来ました。
3回目の1000頭中には「猛獣のヒグマ6頭」も含まれ、「ヒグマエース」も達成となりました。
ハンターは2024年現在約10万人弱、ヒグマ捕獲総数はシーズンに100頭程度、本州ハンターによる捕獲は極めて僅か、ケンさんは15m出会い頭のヒグマ、450㎏のヒグマにも「臆せずに対処出来た事」を誇りに思います。
6頭中の3頭のヒグマは走っており、「ランニング射撃もマグレで無い事を立証出来」ました。

2.日本大物クラブのエースバッジ。
且つて2002年頃と思われますが、日本大物クラブに会費を払っていた事があります。
エゾ鹿5日猟で10頭を捕獲した記事を狩猟雑誌「狩猟界」に載せた処、この小さな金バッジ2個(ダブルエース)を送って来ました。

時代はケンさんが「禅の心作戦」で本州鹿猟開眼後、本州鹿猟捕獲率を1桁上げた頃の話です。
日本大物クラブは会員数が約150名、多くの会員が5頭捕獲のエースを目指す処か、何時かは1頭目捕獲を目指す状態でした。
ケンさんも1頭目捕獲には随分苦労しましたが、本州鹿猟に「禅の心作戦」で開眼後は4年で本州鹿20頭を捕獲、しかし本州鹿猟に限界を感じ、これを卒業しました。
巷の本州鹿巻狩りでは1日平均0.05頭/日人、1頭捕獲には20日を要します。
当時の鹿猟は12月1日~1月31日までの2カ月、毎週土日を皆勤しても17日、正月休み分をプラスして、やっとシーズンに1頭程度でした。
従って60%出撃と仮定では、エース達成まで8年以上を要し、エースは価値ある称号と言えました。
本州鹿捕獲は非常に大変ですが、北海道のエゾ鹿猟ケンさんスクールでは生徒が1日に5回勝負し2頭を捕獲、エース誕生は3日猟で可能でした。3段角のオス成獣に限っても70%がそれですから、エースまで4日猟で楽勝でした。
ケンさんスクール開講直後でもあり、エゾ鹿猟は桁違いに捕獲出来る事、捕獲内容の素晴らしさを多くの人に伝えたいと思っていました。
ケンさんがやれば70%以上捕獲出来、1日に3~4頭捕獲出来ます。
しかし生徒が来た時に出会いが少ない様ではいけないと思い、かなり控目捕獲するのですが、それでも1日2頭は楽勝なのです。
本州鹿も有能なガイドが付けば、ケンさんスクール並に出会え、そして捕獲が可能な事をU生徒が立証しました。しかしこれをガイドするガイドは今の所は存在せず、本州鹿は巻狩り主体、これは当面変わりなさそうです。
3.ケンさんスクールエゾ鹿エース。
写真D生徒は丹沢通い10年でエースになりましたが、スクールでは5日猟で公表5頭を捕獲、実際はケンさんの代理射撃を行い、オス10頭+メス3頭を捕獲しました。


丹沢10年分を2日間で超え、しかもケンさんがヒグマを捕獲すると言うオマケもあり、そのヒグマの毛皮は彼が保管しています。
この頃はまだスクールの前期時代、すでに数年前の阿寒で巷のガイドの80%以上が全くの詐欺ガイドであった事を経験しましたので、平均値より遥かに上の実力である事は分かっていました。
しかし北海道には、ケンさんより遥かに凄いガイドが必ずいると思っていました。
その様なガイドは存在しない事が判ったのはスクール中期時代以後でした。
ケンさんスクールでは平均捕獲が1日2頭を超え、従って5頭エース達成は上手く行けば初回遠征の2~3日で十分となり、エースは価値の無い物になりました。
上写真右は角長70㎝超える大物です。普段の出会い率は1桁下がりますが、フィーバーの日にはズラズラ出て来ます。現実に2011年ケンさんはフィーバー3度で大物31頭が獲れてしまいました。

フィーバ-1日だけで射撃ミスが少なければ、大物ダブルエース達成、これではエースの価値がありません。
巷では出会う事だけからしても大物勝負は大変な事ですが、ケンさんスクールではフィーバー日でなくてもある程度の大物捕獲があり、平均値は1日に0.5頭でした。それで行けば大物エースまでは実戦10日、シーズン5日出猟で2年で達成出来てしまいました。
4.超大物エゾ鹿のエース。
次のクラスは角長80㎝を超える超大物、これは生息数が超大幅に減少し、射撃距離が遠く、照準時間は短く、「迫力負け」する事なく、ナミビアポイントを速やかに撃ち抜かなくてはなりません。高難度の4乗となります。
スクールに於いても超大物成功者は僅か5名しかおらず、1頭捕獲まで平均22日、シーズン5日の出撃では1頭捕獲まで4.4年を要します。
そのペースで超大物エースまでは22年を要する事になりますが、超大物の獲達成者5名中3名はマグレ捕獲、2頭目の捕獲が続きません。


真の達成者は2名だけでした。ケンさん自身も「迫力負け」に随分泣かされました。
これをイメージトレーニングで乗り越えても、当時Stdの心臓狙いでは未回収に成り易く、狙い目をショルダーのナミビアポイントに変更後、やっと捕獲が可能となりました。
この急所変更により超大物捕獲率は5倍に跳ね上がりました。また生徒に依る超大物捕獲も、ナミビアポイントを指導する様になってからでした。
大物までは生息数も多く、「迫力負け」も自然に5回失敗で克服出来ますが、超大物クラスになりますと、生息数が極端に少なくなり、5回失敗を積み上げるには超大物エース誕生と同程度に大変な事でした。
従って積極的に「迫力負け対策」のイメージトレーニングをする必要があります。超大物は出会う事も、捕獲成功する事も一気に超高難度となります。
因みにケンさんは735日を出撃し、超大物33頭を捕獲しています。
つまり超大物1頭の捕獲に22.3日を要し、それで行けば111日出撃すれば超大物エースが誕生となります。
超大物エース達成までにはシーズン5日の出猟では22.2年を要し、狩猟人生の全てを掛けなくてはならない事になります。ケンさんに取っても狩猟5年中30年までは試行錯誤の繰り返し、超大物戦は高難度でした。
ケンさんスクールに於いて超大物出会いは5%弱、平均的に言えば5日猟をすれば1回の勝負が得られ、70%成功確率なら超大物エースまで36日となり、シーズン5日出撃なら7年を要する事になります。
しかし、後述の様に敵は実戦から多くを学び、その対策であの手この手を運用する様になり、計算通りには行きません。要は普通の射撃だけでは全く手が出させない様になりました。
5.超大物鹿は高難度です。
2017年、U生徒の捕獲した88㎝はその1週間前、K生徒の前にも50mで出ました。
しかしこの怪物は銃を向けると5秒で動く事により、これまで生き延びて来ました。
K生徒は慎重を期し過ぎ5秒で撃てず、1生に1度のチャンスを逃しましたが、U生徒はやや遠い80ⅿチャンスを3秒で撃ち捕獲に成功しました。
怪物クラスは多くがこうした行動を取ります。
ケンさんが捕獲した88㎝怪物は車と並行して走り、突然に車の後方を突っ切ろうとしましたが、ケンさんには通用せず、ランニング射撃に捕えられました。
87㎝怪物は発見時150mをすでに走っていました。しかしこの先の丘のトップで立ち止まり振り返ると予測、そこへ先行し「待ってたホイ射撃」に賭けました。
結果は予定通り、200mで立ち止まって振り返り、「待ってたホイ射撃」で即倒しました。
超大物クラス勝負は通常朝夕の自己アピール会場での出会いでは200m以遠ですが、この距離でも銃を向けると5秒で動く個体が多く、「アバウト早撃ち」が必要です。
何故5秒なのか? それは通常照準が10秒だからです。
その通勤途上の鉢合わせでは先のU生徒の様に「スナップショット」が必要になります。
また出会った時にすでに走っている事も多く、「ランニングショット」や「待ってたホイ射撃」が多くなります。超大物はすでに過去何度も射撃を受けており、その対策を学習済なのです。
超大物はその技で現在まで生き延びて来れたのです。
単なる射撃距離が遠く、照準時間が短い、迫力負けせず、速やかにナミビアポイント射撃、そんな簡単な物ではなく、超大物戦は高度な特殊射撃のオンパレードなのです。
あの大変だった「迫力負け対策」すらが、超大物戦ではほんの入門だったのです。
何れも場合も射撃技術的に簡単ではありません。
そしてそれ以上に超大物エゾ鹿のそれら行動に対し、心の動揺があってはなりません。
エースは更なる新しい逃げ口に対しても、積み上げた技術の応用で対処出来なくてはなりません。
積上げた技術とはどんな大物にも「迫力負け」しない、猛獣ヒグマにも「恐怖負け」せず怯まない、心側の積み上げ技術。更に技術的には鹿が逃げる前に撃てる下記の数々の特殊な技術です。
まずは西部劇の早撃ち並ながら必ず命中する「スナップショット」が必要です。
近くの委託物を素速く利用して撃つ「半委託射撃」、十分な照準時間があれば150m「ワンホール射撃」、精密射撃に裏打ちされた150~200mながら3秒で撃つ「アバウト早撃ち」等々があります。
鹿がすでに走っている事も多く、鹿の習性や地形から立止まり振り返る位置を予測する「待ってたホイ射撃」、動的の古い「虚像」に惑わされない「スイング射撃」、体全体で 追尾する再肩付「スナップスイング射撃」の連射技術等々があります。
これらの技術を駆使し、極めて稀な一瞬のチャンスにも速やか且つ冷静に対処、ここから絶望的困難だった超大物捕獲成功が生まれます。
そしてそれが5回以上繰り返され、マグレで無い事が立証され、これがエースなのです。故に、エースと言う称号には大きな価値があります。
ここ1番に「肝が座っていなければ」出来る技ではありません。
長年やっていれば1~2機はマグレ撃墜もあり得ますが、5機はマグレではない事の証明となり、それを称えるのがエースと言う称号です。
第2次大戦のアメリカでは数万人の戦闘機パイロットがいましたが、エースは僅か30人余です。
大物猟でも同様の事が言えます。ここ1番に足が地に着いた射撃が出来なければ、勝負に勝てないのは戦闘機と同じです。
一般的に鹿撃ちと言えば、本州鹿巻狩りになりますが、ケンさんは最初の1頭捕獲までに9年間出撃70余日を要しました。最初の10年間ではこの1頭だけでした。
1.ヒグマエース。
その後まもなくしてケンさんは本州鹿猟に開眼、その後の4年間の40日で20頭を捕獲、ここでエゾ鹿猟に転向、2回目の10年間では約100頭を捕獲、続く3回目の10年間では約1000頭を捕獲、「不可能に挑戦」のライフワークを続けて来ました。
3回目の1000頭中には「猛獣のヒグマ6頭」も含まれ、「ヒグマエース」も達成となりました。
ハンターは2024年現在約10万人弱、ヒグマ捕獲総数はシーズンに100頭程度、本州ハンターによる捕獲は極めて僅か、ケンさんは15m出会い頭のヒグマ、450㎏のヒグマにも「臆せずに対処出来た事」を誇りに思います。
6頭中の3頭のヒグマは走っており、「ランニング射撃もマグレで無い事を立証出来」ました。

2.日本大物クラブのエースバッジ。
且つて2002年頃と思われますが、日本大物クラブに会費を払っていた事があります。
エゾ鹿5日猟で10頭を捕獲した記事を狩猟雑誌「狩猟界」に載せた処、この小さな金バッジ2個(ダブルエース)を送って来ました。
時代はケンさんが「禅の心作戦」で本州鹿猟開眼後、本州鹿猟捕獲率を1桁上げた頃の話です。
日本大物クラブは会員数が約150名、多くの会員が5頭捕獲のエースを目指す処か、何時かは1頭目捕獲を目指す状態でした。
ケンさんも1頭目捕獲には随分苦労しましたが、本州鹿猟に「禅の心作戦」で開眼後は4年で本州鹿20頭を捕獲、しかし本州鹿猟に限界を感じ、これを卒業しました。
巷の本州鹿巻狩りでは1日平均0.05頭/日人、1頭捕獲には20日を要します。
当時の鹿猟は12月1日~1月31日までの2カ月、毎週土日を皆勤しても17日、正月休み分をプラスして、やっとシーズンに1頭程度でした。
従って60%出撃と仮定では、エース達成まで8年以上を要し、エースは価値ある称号と言えました。
本州鹿捕獲は非常に大変ですが、北海道のエゾ鹿猟ケンさんスクールでは生徒が1日に5回勝負し2頭を捕獲、エース誕生は3日猟で可能でした。3段角のオス成獣に限っても70%がそれですから、エースまで4日猟で楽勝でした。
ケンさんスクール開講直後でもあり、エゾ鹿猟は桁違いに捕獲出来る事、捕獲内容の素晴らしさを多くの人に伝えたいと思っていました。
ケンさんがやれば70%以上捕獲出来、1日に3~4頭捕獲出来ます。
しかし生徒が来た時に出会いが少ない様ではいけないと思い、かなり控目捕獲するのですが、それでも1日2頭は楽勝なのです。
本州鹿も有能なガイドが付けば、ケンさんスクール並に出会え、そして捕獲が可能な事をU生徒が立証しました。しかしこれをガイドするガイドは今の所は存在せず、本州鹿は巻狩り主体、これは当面変わりなさそうです。
3.ケンさんスクールエゾ鹿エース。
写真D生徒は丹沢通い10年でエースになりましたが、スクールでは5日猟で公表5頭を捕獲、実際はケンさんの代理射撃を行い、オス10頭+メス3頭を捕獲しました。

丹沢10年分を2日間で超え、しかもケンさんがヒグマを捕獲すると言うオマケもあり、そのヒグマの毛皮は彼が保管しています。
この頃はまだスクールの前期時代、すでに数年前の阿寒で巷のガイドの80%以上が全くの詐欺ガイドであった事を経験しましたので、平均値より遥かに上の実力である事は分かっていました。
しかし北海道には、ケンさんより遥かに凄いガイドが必ずいると思っていました。
その様なガイドは存在しない事が判ったのはスクール中期時代以後でした。
ケンさんスクールでは平均捕獲が1日2頭を超え、従って5頭エース達成は上手く行けば初回遠征の2~3日で十分となり、エースは価値の無い物になりました。
上写真右は角長70㎝超える大物です。普段の出会い率は1桁下がりますが、フィーバーの日にはズラズラ出て来ます。現実に2011年ケンさんはフィーバー3度で大物31頭が獲れてしまいました。

フィーバ-1日だけで射撃ミスが少なければ、大物ダブルエース達成、これではエースの価値がありません。
巷では出会う事だけからしても大物勝負は大変な事ですが、ケンさんスクールではフィーバー日でなくてもある程度の大物捕獲があり、平均値は1日に0.5頭でした。それで行けば大物エースまでは実戦10日、シーズン5日出猟で2年で達成出来てしまいました。
4.超大物エゾ鹿のエース。
次のクラスは角長80㎝を超える超大物、これは生息数が超大幅に減少し、射撃距離が遠く、照準時間は短く、「迫力負け」する事なく、ナミビアポイントを速やかに撃ち抜かなくてはなりません。高難度の4乗となります。
スクールに於いても超大物成功者は僅か5名しかおらず、1頭捕獲まで平均22日、シーズン5日の出撃では1頭捕獲まで4.4年を要します。
そのペースで超大物エースまでは22年を要する事になりますが、超大物の獲達成者5名中3名はマグレ捕獲、2頭目の捕獲が続きません。

真の達成者は2名だけでした。ケンさん自身も「迫力負け」に随分泣かされました。
これをイメージトレーニングで乗り越えても、当時Stdの心臓狙いでは未回収に成り易く、狙い目をショルダーのナミビアポイントに変更後、やっと捕獲が可能となりました。
この急所変更により超大物捕獲率は5倍に跳ね上がりました。また生徒に依る超大物捕獲も、ナミビアポイントを指導する様になってからでした。
大物までは生息数も多く、「迫力負け」も自然に5回失敗で克服出来ますが、超大物クラスになりますと、生息数が極端に少なくなり、5回失敗を積み上げるには超大物エース誕生と同程度に大変な事でした。
従って積極的に「迫力負け対策」のイメージトレーニングをする必要があります。超大物は出会う事も、捕獲成功する事も一気に超高難度となります。
因みにケンさんは735日を出撃し、超大物33頭を捕獲しています。
つまり超大物1頭の捕獲に22.3日を要し、それで行けば111日出撃すれば超大物エースが誕生となります。
超大物エース達成までにはシーズン5日の出猟では22.2年を要し、狩猟人生の全てを掛けなくてはならない事になります。ケンさんに取っても狩猟5年中30年までは試行錯誤の繰り返し、超大物戦は高難度でした。
ケンさんスクールに於いて超大物出会いは5%弱、平均的に言えば5日猟をすれば1回の勝負が得られ、70%成功確率なら超大物エースまで36日となり、シーズン5日出撃なら7年を要する事になります。
しかし、後述の様に敵は実戦から多くを学び、その対策であの手この手を運用する様になり、計算通りには行きません。要は普通の射撃だけでは全く手が出させない様になりました。
5.超大物鹿は高難度です。
2017年、U生徒の捕獲した88㎝はその1週間前、K生徒の前にも50mで出ました。
しかしこの怪物は銃を向けると5秒で動く事により、これまで生き延びて来ました。
K生徒は慎重を期し過ぎ5秒で撃てず、1生に1度のチャンスを逃しましたが、U生徒はやや遠い80ⅿチャンスを3秒で撃ち捕獲に成功しました。
怪物クラスは多くがこうした行動を取ります。
ケンさんが捕獲した88㎝怪物は車と並行して走り、突然に車の後方を突っ切ろうとしましたが、ケンさんには通用せず、ランニング射撃に捕えられました。
87㎝怪物は発見時150mをすでに走っていました。しかしこの先の丘のトップで立ち止まり振り返ると予測、そこへ先行し「待ってたホイ射撃」に賭けました。
結果は予定通り、200mで立ち止まって振り返り、「待ってたホイ射撃」で即倒しました。
超大物クラス勝負は通常朝夕の自己アピール会場での出会いでは200m以遠ですが、この距離でも銃を向けると5秒で動く個体が多く、「アバウト早撃ち」が必要です。
何故5秒なのか? それは通常照準が10秒だからです。
その通勤途上の鉢合わせでは先のU生徒の様に「スナップショット」が必要になります。
また出会った時にすでに走っている事も多く、「ランニングショット」や「待ってたホイ射撃」が多くなります。超大物はすでに過去何度も射撃を受けており、その対策を学習済なのです。
超大物はその技で現在まで生き延びて来れたのです。
単なる射撃距離が遠く、照準時間が短い、迫力負けせず、速やかにナミビアポイント射撃、そんな簡単な物ではなく、超大物戦は高度な特殊射撃のオンパレードなのです。
あの大変だった「迫力負け対策」すらが、超大物戦ではほんの入門だったのです。
何れも場合も射撃技術的に簡単ではありません。
そしてそれ以上に超大物エゾ鹿のそれら行動に対し、心の動揺があってはなりません。
エースは更なる新しい逃げ口に対しても、積み上げた技術の応用で対処出来なくてはなりません。
積上げた技術とはどんな大物にも「迫力負け」しない、猛獣ヒグマにも「恐怖負け」せず怯まない、心側の積み上げ技術。更に技術的には鹿が逃げる前に撃てる下記の数々の特殊な技術です。
まずは西部劇の早撃ち並ながら必ず命中する「スナップショット」が必要です。
近くの委託物を素速く利用して撃つ「半委託射撃」、十分な照準時間があれば150m「ワンホール射撃」、精密射撃に裏打ちされた150~200mながら3秒で撃つ「アバウト早撃ち」等々があります。
鹿がすでに走っている事も多く、鹿の習性や地形から立止まり振り返る位置を予測する「待ってたホイ射撃」、動的の古い「虚像」に惑わされない「スイング射撃」、体全体で 追尾する再肩付「スナップスイング射撃」の連射技術等々があります。
これらの技術を駆使し、極めて稀な一瞬のチャンスにも速やか且つ冷静に対処、ここから絶望的困難だった超大物捕獲成功が生まれます。
そしてそれが5回以上繰り返され、マグレで無い事が立証され、これがエースなのです。故に、エースと言う称号には大きな価値があります。
2024年02月21日
山田さんヒグマの腸を引き抜く。
(文春オンライン2024.01.31.要約)
それはやっぱり滝上町の山田さんの体験ですね。山田さんとは滝上町のハンター山田文夫さん(当時69)の体験談でした。自分でも「この原稿を載せてイイのかな」とちょっと不安になるほどの強烈なモノでした。
その一件は「格闘5分‣九死に一生」と題して「北海道新聞」2023年7月18日掲載していますが、以下、その内容の概要を紹介します。
ヒグマ駆除歴約20年、これまで100頭近くを駆除して来た山田さんが「牧草地にヒグマがいる」と 言う通報を受けたのは2022年7月の事でした。
若いハンターと2人で目撃現場へと向かうと、そこに体長1メートル程のヒグマ2頭がいました。
銃が撃てなくなる日没まではまだ1時間以上余裕があり、その場で駆除する事を決めました。
60mまで忍び寄り、それぞれが別のヒグマを狙って同時に撃ったが、相棒の弾は失中、ヒグマは山林へ逃げ、山田さんの弾はもう一頭の横腹に命中、更にもう一発を撃ち込んだ所で、牧草地の縁の崖から落下しました。
山田さんはヒグマの死骸を回収の為に崖下に降り、笹藪に入った所、手負いのヒグマが飛び出して来ました。体長1m体重70㎏のかなり小型のヒグマでした。

相棒はその直前に見て警告を発したのですが、山田さんは何も出来ないまま、ヒグマに押倒され、馬乗りになったヒグマに爪で頭を引っ掻掛かれ、顎や両腕を噛まれました。
叫び声を上げながら抵抗しましたが「力が強過ぎ全然離れない」。 ヒグマは急所の頭部や喉元を狙い執拗に攻撃して来ました。
相棒ハンターはタイミング悪く弾切れ、補充する為離れた所に止めた車へ走りました。
山田さんは死を覚悟しながらも、懸命にヒグマと格闘を続け、揉合い5分程が過ぎた頃、ヒグマ横腹の被弾口から腸が10㎝程出ているのが目に入り、咄嗟に右手で腸を握り、思い切り引き抜くと、ヒグマは途端に力が抜け、藪の中へと消えて行きました。
70針を縫う大怪我と後遺症。
筆者もそれなりにハンターの取材はして来ましたが、「クマの腸を引き抜いた」と言う話は初めて聞いたので、この記事を最初に読んだ時の衝撃は覚えています。
「仕留めた確証がないまま、笹藪に入るべきではなかった」「あの事故の原因は自分の油断だった」山田さん自身は記事の中でそう言っています。
結局、山田さんは頭と両腕、顎等を70針縫い、顎の感覚は今も鈍く、ロレツが廻り辛くなる等の後遺症が残りました。驚いたのはその後の山田さんの行動でした。「事故後2カ月には現場に復帰」 しているのですが、やっぱり現場に向かう時は「今でも恐怖心がある」と仰っていました。
「撃ちたくて撃っている訳ではない」
クマの生息数は激増しているのに、それを駆除出来るハンターは激減しています。1990年度には5200頭だったヒグマの推定生息数は、2020年度には11700頭と30年で倍増しています。
滝上地区では2000年頃にすでに激増、2007年からの箱罠駆除で1時期半減、その後再び激増しています。
一方北海道猟友会の会員数はピーク時1978年度に2万人いましたが、2022年度には5361人と 約4分の1にまで減少しています。
何故ハンターは激減してしまったのか。「猟友会等に取材すると、以前に比べてヒグマを獲る事の経済的なメリットが少なくなったと言う声をよく聞きます。」
ヒグマを獲れば行政からそれなりの報奨金が支払われますが、更に当時はヒグマの毛皮や漢方薬として珍重される熊の胆嚢も高く売れ、ハンターにすれば1頭ヒグマを獲れば非常に大きな利益となりました。
だからヒグマの反撃で命を落とすリスクを冒してでも、クマを獲る人達がいたのです。
1990年まで北海道はヒグマの生息数を抑える為に、春グマ駆除を奨励していました。
結果的にそれが乱獲へと繋がり、一時はヒグマが絶滅しかけた為、北海道は「春グマ駆除」を廃止、保護政策へと方針を180度転換したと言う経緯があります。
ヒグマ1頭を駆除しても1~5万円。
「ヒグマ有害駆除の奨励金は自治体によって異なり、概ね1頭当り1~5万円程度、「春グマ駆除」 時代と比べるとかなり低く抑えられており、更に毛皮等の需要も大きく低下しています。
ハンターは生活の為に本職の仕事が別にあり、有害駆除はその合間に行うボランティアであり、 有害駆除で自治体の要請を受けて出勤した場合、自治体によって異なりますが1~3万円位の日当が出ますが、その間の本業は休む事になります。
「何よりヒグマ駆除には、一歩間違うと自分が命を落とすリスクがあります。」
また「車の燃料費や1000円以上/発のライフル銃弾等々かなりの経費も必要です。」
そんな労力や危険性に見合った報酬が、ハンターに支払われているかと言えば、かなり疑問です。
比較的安全な春グマ駆除は、ヒグマの捕獲技術をベテランから若手へと継承する場でもありました。しかし春グマ駆除が廃止され30年以上、クマを獲る為に充分な技術や知識や経験を持つハンターは超高齢化しているのが実情です。
「こうした現状を踏まえ北海道も2016年から、若手が熟練者と捕獲する場合に限り、残雪期の捕獲を特別に許可する制度(春期管理捕獲)を始めました。
そして更に2024年から春グマ駆除は制限が大幅に緩和されるとの事です。
経験の浅い若手を連れてヒグマと対峙するのは、中々難しく、このままではヒグマ捕獲経験のあるハンターがいない地域も出て来ますが、ヒグマの方はお構いなしに何処にでも出没します。
何故こう言う事になってしまったのか。「一言でいえば、ヒグマと人間社会との軋轢問題を全て現場のハンターに丸投げして来た結果だと言えると思われます。
本来ヒグマ管理と言うのは北海道庁や警察の行政が主体となって行う物だと思うのですが、現状はその予算も人的資源も足りず、結果的にその“しわ寄せ”がハンターに行っている訳です。
前出の山田さんは次の様な言葉で結んでいます。「地域の安全を守る為、誰かがヒグマの駆除を しなければならないが、ハンターが危険と背中合わせの活動を続けている事を知って欲しい。」
(以上、文春オンライン要約)
(ケンさん加筆)
この手の記事としては、珍しく記載内容が概ね合っていると思いますが、山田さんへの評価はかなり過剰と思いました。ケンさんのヒグマ捕獲は僅か6頭ですが、それでも自らの能力だけで「捕獲への道を切り開いた」からこそ、言える内容があります。
1.ベテランは60mを外さない。
記事では山田さんを100頭捕獲のベテランとしていますが、ヒグマまでの距離僅か60m、ベテラン+ライフル銃ならばその60mで急所を外す様なブザマな射撃はしません。
彼の射撃はお粗末でケンさんは20年程前ですが、山田さんが50m先の鹿を半矢未回収にした時を見ています。駆除従事者は旧技能講習を免除され受講しておらず、もし受講したら不合格だったかも知れません。
また逃げるヒグマに1発を追加していますが、動的射撃技術を持たないライフル射撃は絶対に命中しません。これもケンさん自身が出来る様になってから分かった事ですが、目視した映像を狙って撃つ従来のライフル射撃では、目視映像が少し古い「虚像」であり、「実体」はもっと先にあり、見えないのです。
従ってそれを理解しない限り、ランニング射撃はマグレヒットも有り得ないのです。
新人の射撃はカスリもしなかったのですから、更に問題外の酷さです。更に新人は更に近くの木に登ったヒグマも失中しており、その技術では体験の為に連れて歩く価値が無いと言えます。
2.本当に必要なのは「恐怖負け」対策と正しい銃の取り扱い。
また2人とも、ヒグマに対して「恐怖負け」で何も出来なかった事が、最も重大だったと言えます。
本当に伝えるべき、ヒグマ駆除には不可欠である筈のヒグマ対戦時の最重要課題「迫力負け」と 「恐怖負け」の「心の伝承」が抜けている事にありました。
加えて従来からの銃の取扱いが、ケンさん考案の新取扱法が完成している昨今では、明らかに劣る「間違っている」手法と言えました。
銃の取扱教本を書く人はハンターではない為、教本には戯言が書いてあり、現場はそれとは違う 独自の手法で銃を取り扱っていました。
そして最も重要な「恐怖負け」しない心の伝承は、先輩の行動を見て学ぶ物でしたが、それを実際に体験出来る確率は後述理由から余りにも稀れでした。
今はそう言う社会構造ではなくなり、上手く見本を示して具体的に教え、そして誉める必要があります。現場独自の伝統の危ない銃の取扱いで、事故も起こらず、成果が上がれば、まだ良いのですが、実際は「返り討ち時」には残念ながら間に合わず、更に暴発等の事故も散見しています。
3.必要な対策は恐怖負け。
この対策は2つに分かれます。1つ目は「心の対策」です。
この対策をしなければ、ヒグマと安全に対戦する事は不可能と思われます。
人間でも何でもそうですが、自身より遥かに大きな体格の相手と対戦しますと戦う前から「迫力負け」をしてしまい、足が地に着かない射撃になってしまいます。
更に相手が猛獣となりますと、「恐怖負け」で体が動かなくなり、全く何も出来なくなってしまいます。
この問題で最も重要な問題は、ヒグマ捕獲名人と言われる山田さんも、「恐怖負け」の能力を「全く持っていなかった」点です。他のベテランヒグマハンターも概ね類似状態です。
4.ヒグマの反撃率は1%程度。
殆どのヒグマは反撃しません。そしてヒグマは非常に弾に弱く、「返り討ち」に会う確率は1%程度です。近年はヒグマ捕獲の90%が箱罠で対象外です。
箱罠の止刺し経験は「返り討ちの実戦」には殆ど役に立ちません。100頭捕獲の名人も本当のヒグマ捕獲は僅か10頭程度でケンさんと同クラス、前出の山田さんもこの例に漏れず、勿論経験が少ない相棒がこの経験を持っている筈がありません。
従って殆どのベテランヒグマハンターは「返り討ち」の経験が無いままなのです。
仮に遭遇時、「恐怖負け」に陥らず、体が速やかに行動出来たとしても、旧来の取り扱い法では銃の照準をする頃に、すでに被害を受けてしまう事になります。
実際は確率99%「恐怖負け」、何も出来ないままやられて しまうのです。この「恐怖負け」がハンターの「返り討ち」事件の「第1原因」です。
5.旧来の銃の取り扱いではイザと言う時に間に合わない。
旧取り扱いはイザと言う時に、少しでも可能性を残す為に、銃は何時も「実弾装填済み」、そして「安全装置解除済」の一触即発の非常に危険な状態で常時携帯しております。
時に「暴発」や「誤射」事件も起こっています。それでも「イザと言う時には間に合わない」のです。
この「間に合わない銃の取り扱い」が事件の「第2原因」です。
旧来の手法を説明します。銃には大きな反動があり、この反動を安全に受けられる場所は、銃のパッドプレートの大きさ程度しかありません。
従って旧来の銃の取り扱いは、まず肩の正しい位置に銃を着ける事から始まり、それから照準が始まりました。銃はそう言う物として取り扱われて来ました。
従って「恐怖負け」対策を十分に行い、更に後述の「新スナップショット」技術を身に付けなければ、残念ながら返り討ち時のヒグマに勝てる可能性はありません。
勝てる可能性の無い「駆除依頼」を出す事は、WW2日本軍の「特攻」と同様、人間として出来ない相談となります。
6.画期的な「新スナップショット」。
「新スナップショット」では装填せず・更に安全装置を掛けた状態で銃を携帯しています。
新取扱いでは「イザと言う時になってから」、装填・安全解除し撃っても、旧来法より圧倒的に速く、「返り討ち」に「間に合う可能性はかなり高い」と思います。
何時何処からヒグマが飛び出すのか分からない時は、装填して安全装置を掛けた状態で捜索、気休め程度の僅かな差ですが、もう少し早く撃てます。
銃を肩に着ける前に撃つ「新スナップショット」は、発砲の決断で、下記の2つを同時に行います。
「1つ目は体を発砲直前状態」に移行し、2つ目は「銃身を目標に向ける」事です。
銃は頬をかすめ肩に銃を引き寄せながら、肩に銃が着く前に発砲します。



銃を向けた中写真以後なら何時撃っても命中します。
上半身は発砲決断瞬間から発砲直後まで、全く動いていない点に注目して下さい。
一見照準をしていない様に見えますが、中写真の「銃を指向した時が概ね照準完了の時」、距離が近ければ急所を外す事は絶対にありません。
「返り討ち」はド至近距離ですから、日頃この練習を十分にしておけば、ヒグマパンチや噛付きより銃の有効リーチがMax.50mで長い分、必ず多少早く弾が急所に届きます。
しかし少しでも躊躇すれば、パンチの方が先に来るか、相打ちになります。
7.この手法で銃を肩の安全ポイントに付けられるのか?
銃を構えると、調度スコープが目の目前に来る様に、ストック寸法を事前調整してありますので、緊急時にホッペをかすめて肩付けすれば、ストックは完璧に必ず肩の安全な定位置に着きます。
実戦実習は事前の心の対策と、新スナップショットの手法を叩き込んでから、行うべきだと言えます。
心の対策は、色々な写真に対して行う「スナップショットのイメージトレーニング」です。
仮に足が地に着かない状態でも、透かさず銃を急所に向けて撃てる様に、条件反射で「行動が板に付くまで」繰り返しトレーニングを行います。
8.銃は心で撃ち、体全体で向ける物なのです。
「心で撃つ物」が銃であり、小手先で「狙って撃つ物ではなく」、「体全体で向けて撃つ」物なのです。
この手法は「ヒグマ戦」だけでなく、全ての実戦に甚だ有効です。
ケンさんの成功の原因は1番目がイメージトレーニングに依る「恐怖負け」の克服、2番目が西部劇並早撃ちの「新スナップショット」を考案した事、3番目が走るヒグマにも対応可能な「ランニングショット」を開拓出来た事の3つに依ります。



(ケンさん加筆終わり)
それはやっぱり滝上町の山田さんの体験ですね。山田さんとは滝上町のハンター山田文夫さん(当時69)の体験談でした。自分でも「この原稿を載せてイイのかな」とちょっと不安になるほどの強烈なモノでした。
その一件は「格闘5分‣九死に一生」と題して「北海道新聞」2023年7月18日掲載していますが、以下、その内容の概要を紹介します。
ヒグマ駆除歴約20年、これまで100頭近くを駆除して来た山田さんが「牧草地にヒグマがいる」と 言う通報を受けたのは2022年7月の事でした。
若いハンターと2人で目撃現場へと向かうと、そこに体長1メートル程のヒグマ2頭がいました。
銃が撃てなくなる日没まではまだ1時間以上余裕があり、その場で駆除する事を決めました。
60mまで忍び寄り、それぞれが別のヒグマを狙って同時に撃ったが、相棒の弾は失中、ヒグマは山林へ逃げ、山田さんの弾はもう一頭の横腹に命中、更にもう一発を撃ち込んだ所で、牧草地の縁の崖から落下しました。
山田さんはヒグマの死骸を回収の為に崖下に降り、笹藪に入った所、手負いのヒグマが飛び出して来ました。体長1m体重70㎏のかなり小型のヒグマでした。

相棒はその直前に見て警告を発したのですが、山田さんは何も出来ないまま、ヒグマに押倒され、馬乗りになったヒグマに爪で頭を引っ掻掛かれ、顎や両腕を噛まれました。
叫び声を上げながら抵抗しましたが「力が強過ぎ全然離れない」。 ヒグマは急所の頭部や喉元を狙い執拗に攻撃して来ました。
相棒ハンターはタイミング悪く弾切れ、補充する為離れた所に止めた車へ走りました。
山田さんは死を覚悟しながらも、懸命にヒグマと格闘を続け、揉合い5分程が過ぎた頃、ヒグマ横腹の被弾口から腸が10㎝程出ているのが目に入り、咄嗟に右手で腸を握り、思い切り引き抜くと、ヒグマは途端に力が抜け、藪の中へと消えて行きました。
70針を縫う大怪我と後遺症。
筆者もそれなりにハンターの取材はして来ましたが、「クマの腸を引き抜いた」と言う話は初めて聞いたので、この記事を最初に読んだ時の衝撃は覚えています。
「仕留めた確証がないまま、笹藪に入るべきではなかった」「あの事故の原因は自分の油断だった」山田さん自身は記事の中でそう言っています。
結局、山田さんは頭と両腕、顎等を70針縫い、顎の感覚は今も鈍く、ロレツが廻り辛くなる等の後遺症が残りました。驚いたのはその後の山田さんの行動でした。「事故後2カ月には現場に復帰」 しているのですが、やっぱり現場に向かう時は「今でも恐怖心がある」と仰っていました。
「撃ちたくて撃っている訳ではない」
クマの生息数は激増しているのに、それを駆除出来るハンターは激減しています。1990年度には5200頭だったヒグマの推定生息数は、2020年度には11700頭と30年で倍増しています。
滝上地区では2000年頃にすでに激増、2007年からの箱罠駆除で1時期半減、その後再び激増しています。
一方北海道猟友会の会員数はピーク時1978年度に2万人いましたが、2022年度には5361人と 約4分の1にまで減少しています。
何故ハンターは激減してしまったのか。「猟友会等に取材すると、以前に比べてヒグマを獲る事の経済的なメリットが少なくなったと言う声をよく聞きます。」
ヒグマを獲れば行政からそれなりの報奨金が支払われますが、更に当時はヒグマの毛皮や漢方薬として珍重される熊の胆嚢も高く売れ、ハンターにすれば1頭ヒグマを獲れば非常に大きな利益となりました。
だからヒグマの反撃で命を落とすリスクを冒してでも、クマを獲る人達がいたのです。
1990年まで北海道はヒグマの生息数を抑える為に、春グマ駆除を奨励していました。
結果的にそれが乱獲へと繋がり、一時はヒグマが絶滅しかけた為、北海道は「春グマ駆除」を廃止、保護政策へと方針を180度転換したと言う経緯があります。
ヒグマ1頭を駆除しても1~5万円。
「ヒグマ有害駆除の奨励金は自治体によって異なり、概ね1頭当り1~5万円程度、「春グマ駆除」 時代と比べるとかなり低く抑えられており、更に毛皮等の需要も大きく低下しています。
ハンターは生活の為に本職の仕事が別にあり、有害駆除はその合間に行うボランティアであり、 有害駆除で自治体の要請を受けて出勤した場合、自治体によって異なりますが1~3万円位の日当が出ますが、その間の本業は休む事になります。
「何よりヒグマ駆除には、一歩間違うと自分が命を落とすリスクがあります。」
また「車の燃料費や1000円以上/発のライフル銃弾等々かなりの経費も必要です。」
そんな労力や危険性に見合った報酬が、ハンターに支払われているかと言えば、かなり疑問です。
比較的安全な春グマ駆除は、ヒグマの捕獲技術をベテランから若手へと継承する場でもありました。しかし春グマ駆除が廃止され30年以上、クマを獲る為に充分な技術や知識や経験を持つハンターは超高齢化しているのが実情です。
「こうした現状を踏まえ北海道も2016年から、若手が熟練者と捕獲する場合に限り、残雪期の捕獲を特別に許可する制度(春期管理捕獲)を始めました。
そして更に2024年から春グマ駆除は制限が大幅に緩和されるとの事です。
経験の浅い若手を連れてヒグマと対峙するのは、中々難しく、このままではヒグマ捕獲経験のあるハンターがいない地域も出て来ますが、ヒグマの方はお構いなしに何処にでも出没します。
何故こう言う事になってしまったのか。「一言でいえば、ヒグマと人間社会との軋轢問題を全て現場のハンターに丸投げして来た結果だと言えると思われます。
本来ヒグマ管理と言うのは北海道庁や警察の行政が主体となって行う物だと思うのですが、現状はその予算も人的資源も足りず、結果的にその“しわ寄せ”がハンターに行っている訳です。
前出の山田さんは次の様な言葉で結んでいます。「地域の安全を守る為、誰かがヒグマの駆除を しなければならないが、ハンターが危険と背中合わせの活動を続けている事を知って欲しい。」
(以上、文春オンライン要約)
(ケンさん加筆)
この手の記事としては、珍しく記載内容が概ね合っていると思いますが、山田さんへの評価はかなり過剰と思いました。ケンさんのヒグマ捕獲は僅か6頭ですが、それでも自らの能力だけで「捕獲への道を切り開いた」からこそ、言える内容があります。
1.ベテランは60mを外さない。
記事では山田さんを100頭捕獲のベテランとしていますが、ヒグマまでの距離僅か60m、ベテラン+ライフル銃ならばその60mで急所を外す様なブザマな射撃はしません。
彼の射撃はお粗末でケンさんは20年程前ですが、山田さんが50m先の鹿を半矢未回収にした時を見ています。駆除従事者は旧技能講習を免除され受講しておらず、もし受講したら不合格だったかも知れません。
また逃げるヒグマに1発を追加していますが、動的射撃技術を持たないライフル射撃は絶対に命中しません。これもケンさん自身が出来る様になってから分かった事ですが、目視した映像を狙って撃つ従来のライフル射撃では、目視映像が少し古い「虚像」であり、「実体」はもっと先にあり、見えないのです。
従ってそれを理解しない限り、ランニング射撃はマグレヒットも有り得ないのです。
新人の射撃はカスリもしなかったのですから、更に問題外の酷さです。更に新人は更に近くの木に登ったヒグマも失中しており、その技術では体験の為に連れて歩く価値が無いと言えます。
2.本当に必要なのは「恐怖負け」対策と正しい銃の取り扱い。
また2人とも、ヒグマに対して「恐怖負け」で何も出来なかった事が、最も重大だったと言えます。
本当に伝えるべき、ヒグマ駆除には不可欠である筈のヒグマ対戦時の最重要課題「迫力負け」と 「恐怖負け」の「心の伝承」が抜けている事にありました。
加えて従来からの銃の取扱いが、ケンさん考案の新取扱法が完成している昨今では、明らかに劣る「間違っている」手法と言えました。
銃の取扱教本を書く人はハンターではない為、教本には戯言が書いてあり、現場はそれとは違う 独自の手法で銃を取り扱っていました。
そして最も重要な「恐怖負け」しない心の伝承は、先輩の行動を見て学ぶ物でしたが、それを実際に体験出来る確率は後述理由から余りにも稀れでした。
今はそう言う社会構造ではなくなり、上手く見本を示して具体的に教え、そして誉める必要があります。現場独自の伝統の危ない銃の取扱いで、事故も起こらず、成果が上がれば、まだ良いのですが、実際は「返り討ち時」には残念ながら間に合わず、更に暴発等の事故も散見しています。
3.必要な対策は恐怖負け。
この対策は2つに分かれます。1つ目は「心の対策」です。
この対策をしなければ、ヒグマと安全に対戦する事は不可能と思われます。
人間でも何でもそうですが、自身より遥かに大きな体格の相手と対戦しますと戦う前から「迫力負け」をしてしまい、足が地に着かない射撃になってしまいます。
更に相手が猛獣となりますと、「恐怖負け」で体が動かなくなり、全く何も出来なくなってしまいます。
この問題で最も重要な問題は、ヒグマ捕獲名人と言われる山田さんも、「恐怖負け」の能力を「全く持っていなかった」点です。他のベテランヒグマハンターも概ね類似状態です。
4.ヒグマの反撃率は1%程度。
殆どのヒグマは反撃しません。そしてヒグマは非常に弾に弱く、「返り討ち」に会う確率は1%程度です。近年はヒグマ捕獲の90%が箱罠で対象外です。
箱罠の止刺し経験は「返り討ちの実戦」には殆ど役に立ちません。100頭捕獲の名人も本当のヒグマ捕獲は僅か10頭程度でケンさんと同クラス、前出の山田さんもこの例に漏れず、勿論経験が少ない相棒がこの経験を持っている筈がありません。
従って殆どのベテランヒグマハンターは「返り討ち」の経験が無いままなのです。
仮に遭遇時、「恐怖負け」に陥らず、体が速やかに行動出来たとしても、旧来の取り扱い法では銃の照準をする頃に、すでに被害を受けてしまう事になります。
実際は確率99%「恐怖負け」、何も出来ないままやられて しまうのです。この「恐怖負け」がハンターの「返り討ち」事件の「第1原因」です。
5.旧来の銃の取り扱いではイザと言う時に間に合わない。
旧取り扱いはイザと言う時に、少しでも可能性を残す為に、銃は何時も「実弾装填済み」、そして「安全装置解除済」の一触即発の非常に危険な状態で常時携帯しております。
時に「暴発」や「誤射」事件も起こっています。それでも「イザと言う時には間に合わない」のです。
この「間に合わない銃の取り扱い」が事件の「第2原因」です。
旧来の手法を説明します。銃には大きな反動があり、この反動を安全に受けられる場所は、銃のパッドプレートの大きさ程度しかありません。
従って旧来の銃の取り扱いは、まず肩の正しい位置に銃を着ける事から始まり、それから照準が始まりました。銃はそう言う物として取り扱われて来ました。
従って「恐怖負け」対策を十分に行い、更に後述の「新スナップショット」技術を身に付けなければ、残念ながら返り討ち時のヒグマに勝てる可能性はありません。
勝てる可能性の無い「駆除依頼」を出す事は、WW2日本軍の「特攻」と同様、人間として出来ない相談となります。
6.画期的な「新スナップショット」。
「新スナップショット」では装填せず・更に安全装置を掛けた状態で銃を携帯しています。
新取扱いでは「イザと言う時になってから」、装填・安全解除し撃っても、旧来法より圧倒的に速く、「返り討ち」に「間に合う可能性はかなり高い」と思います。
何時何処からヒグマが飛び出すのか分からない時は、装填して安全装置を掛けた状態で捜索、気休め程度の僅かな差ですが、もう少し早く撃てます。
銃を肩に着ける前に撃つ「新スナップショット」は、発砲の決断で、下記の2つを同時に行います。
「1つ目は体を発砲直前状態」に移行し、2つ目は「銃身を目標に向ける」事です。
銃は頬をかすめ肩に銃を引き寄せながら、肩に銃が着く前に発砲します。



銃を向けた中写真以後なら何時撃っても命中します。
上半身は発砲決断瞬間から発砲直後まで、全く動いていない点に注目して下さい。
一見照準をしていない様に見えますが、中写真の「銃を指向した時が概ね照準完了の時」、距離が近ければ急所を外す事は絶対にありません。
「返り討ち」はド至近距離ですから、日頃この練習を十分にしておけば、ヒグマパンチや噛付きより銃の有効リーチがMax.50mで長い分、必ず多少早く弾が急所に届きます。
しかし少しでも躊躇すれば、パンチの方が先に来るか、相打ちになります。
7.この手法で銃を肩の安全ポイントに付けられるのか?
銃を構えると、調度スコープが目の目前に来る様に、ストック寸法を事前調整してありますので、緊急時にホッペをかすめて肩付けすれば、ストックは完璧に必ず肩の安全な定位置に着きます。
実戦実習は事前の心の対策と、新スナップショットの手法を叩き込んでから、行うべきだと言えます。
心の対策は、色々な写真に対して行う「スナップショットのイメージトレーニング」です。
仮に足が地に着かない状態でも、透かさず銃を急所に向けて撃てる様に、条件反射で「行動が板に付くまで」繰り返しトレーニングを行います。
8.銃は心で撃ち、体全体で向ける物なのです。
「心で撃つ物」が銃であり、小手先で「狙って撃つ物ではなく」、「体全体で向けて撃つ」物なのです。
この手法は「ヒグマ戦」だけでなく、全ての実戦に甚だ有効です。
ケンさんの成功の原因は1番目がイメージトレーニングに依る「恐怖負け」の克服、2番目が西部劇並早撃ちの「新スナップショット」を考案した事、3番目が走るヒグマにも対応可能な「ランニングショット」を開拓出来た事の3つに依ります。
(ケンさん加筆終わり)
2023年07月08日
ヒグマとクマゲラに会えました。
3.ヒグマとクマゲラに会えました。
さて北海道では渓流釣りに行きましたが、釣り場が荒らされ、レインボウが僅かに釣れたのみでした。とうとう北海道でも野性のイワナ釣りが難しくなりました。
野性動物でヒグマに会えました。場所はオシラネップ線の小学校跡地の少し上、山林の中からこちらを見ていましたが、カメラを向けた時はもう逃げ始めていました。カメラと銃は捉える速度は概ね同じですから、狩猟期間にライフル銃で出会えれば、捕獲の可能性はあったと思われます。


花畑で出会ったメス鹿はカメラでバッチリ捉えられ、これは撃墜確実です。
それで行きますとヒグマはカメラ連射2枚目でもう姿を消しており、ギリギリ1発目のスナップショットの境目であり、連射は不可能でした。以前の知床では駆除が行われず、エゾ鹿は道端にゴロゴロいましたが、昨今は駆除が行われる様になり、知床の保護区でも姿を見る事は稀となりました。
さて今回の知床林道はヒグマには会う事は出来ずでしたが、ヒグマより更に貴重なクマゲラに出会う事が出来ました。クマゲラはカラスより若干小型、キツツキの中ではダントツに大型な黒い鳥です。

写真はオスで頭が赤いのが特徴ですが、メスの頭の赤は非常に僅かです。今まで遠くに見た事は 数度ありますが、近くで見たのは初めてでした。


小清水原生花園も見に行きましたが、もう昔の様に野生の花が咲き乱れると言う事は無くなりました。
写真は人口の花畑です。小清水の近くにはサケが抜群に釣れる場所があったのですが、数年前からサケ釣り禁止になりました。
北海道で実に勿体ないと思うのは このサケ釣りとエゾ鹿猟で、この2つは有料化して北海道の観光資源として、日本人にも外国人にも開放する事が望ましいと思います。
4.衝撃的なエゾ鹿オスの写真。
もう一つ衝撃的な写真を発見しました。ニセコ方面に道の駅に展示されていた写真ですが、何と草を食べているオス鹿の頭には、角が絡んで外れなくなってしまったもう1頭のオスの頭蓋骨のミイラが、付いたままでした。

普通はこうなってしまうと2頭とも死んでしまうのが普通です。
どう言う経緯かは知りませんが、決闘の対戦相手が死に、更に相手の首が腐り、頭蓋骨が外れるまでには相当の期間を要すると思われます。その間をどうして生き延びたのか詳細は不明ですが、それを 生き延びたと言うのですから超驚きです。
春には角が落ち解放されますが、大変な受難でした。
角の形状がシンプルな日本鹿やエゾ鹿では絡まって動けなくなる事自体が珍しいですが、角形状が複雑な、ムースやカリブーやエルク では時々見受けられる様です。
5.ヒグマ事故の代表的原因である竹の子と、クマ笹ワラビを食べました。


熊笹の1種で千島笹の通称「根曲りタケノコ」、同じく熊笹等の中に生える「熊笹ワラビ」を食べました。北海道には竹が無く、タケノコと言えばこれを指します。意外と高価で写真の物が250円でした。
歯応えはシャキシャキ感が非常に強い独特の風味ですが、味は我地方の直径20㎝以上の巨大な 孟宗竹のタケノコが500円、孟宗の方が美味しいと思いました。
ワラビ自体はそこらに多数生えるのですが、熊笹ワラビは我が地方のワラビに比べ、長さも太さも2倍以上、濃い熊笹の中で育ったワラビほど、直射日光が当たらず、長く・太く・柔らかく・そして美味しいのだそうです。ワラビは当地方の物より遥かに美味しく、抜群と言えました。
但し両者共ヒグマの大好物、これらを採りに行く場所である熊笹籔は視界1mですから、ヒグマと1mで鉢合わせしたり、濃い笹藪の中で迷子になったり、毎年事故も多い山菜採りです。
2018年、秋田にてタケノコ採り4人が、ツキノワグマに殺されたのも、同じタケノコです。この事件では主犯と思われるスーパーKは駆除された物の、他の3頭の人喰い熊はまだ生き残っています。
6.立ち止まらないヒグマ。
ヒグマは我が国最大の野性獣であり、また狩猟対象獣でもあり、大物ヒグマの体重は400㎏を超えます。1度は勝負したい対戦相手と言えますが、鹿の様に立ち止まらず、普通射撃では超高難度です。肉食を好む少数のヒグマは昔からいました。
1960年代前半までは牧場の家畜が毎年数百頭に及びましたが、肉好ヒグマは徹底的に駆除され、1時期は家畜の被害も概ねゼロになりました。
1990年に春熊の駆除が廃止されて以降、ヒグマは増え続け、またその頃からエゾ鹿猟が盛んになり、その残滓を食べる事から、その後はまた肉食のヒグマが増えている傾向にあります。
オソ18と名が付けられたヒグマは最初に発見されたのがオソ地区であり、足跡の幅が18㎝であった為、そう言う名前が付きました。2019年以降すでに66頭の乳牛がやられているそうです。
ケンさんが捕獲したオサツ林道の推定450㎏の大ヒグマも足幅18㎝、オサツ18と言えました。ケンさんのヒグマはマグレではないと言える物の、僅か6頭の 捕獲しかなく、偉そうな事は言えませんが、立ち止まらないヒグマを捕獲する事は普通射撃ではかなり困難です。
エゾ鹿プロハンターでケンさんより圧倒的に多い実戦出撃をしているハンターでも、ヒグマ捕獲は数頭しかありません。ケンさんの6頭も普通射撃が可能だったのは2頭に留り、出会い頭のスナップショット、走っているヒグマのランニングショットが過半を占めています。
オサツ18の場合は斜め後方100mからのランニングショットでした。
7.ケンさんの射撃。
空気銃で30mのスズメの頭を外さなかったケンさんですが、1984年に始めたレミントン1100の20番スラグ射撃では 50mから撃って100mライフル用の40㎝の的紙から時に外れてしまう程でした。最初はノーライフルだからと思いましたが、フリンチングが主原因でした。


左:レミントン20番スラグ専用銃。 右:レミントン1187の散弾銃。
1989年、1番目の標的、やっと50mSB標的の黒点、11㎝を概ね外さない様になりました。翌1990年類似型式のレミントン742ライフルで撃ちましたが、結果はスラグガンと概ね同等と言えました。これでノーライフルだから当たらないと言う理由は使えなくなりました。
2番目の標的は普通のレミントン11-87のスラグ弾射撃です。
スラグ専用銃と普通の散弾バレルと言うのも、殆ど差が無しでした。

3番目は2002年H&Kオートで撃ちました。150mで5発が12㎜です。
これがケンさんの5発グルーピングではベストでした。
オートにしては抜群と言えるグルーピングでした。
308で急所を正しく撃てば必ず即倒即死しますが、迫力負け射撃では概ね全てが失中又は未回収となりマグレも起こりません。大物は狩猟慣れしているので銃を向けるとすぐに逃げ出します。
大物であればある程一般的に距離は遠くなり、照準時間が短く、それでいながらより確実に急所ヒットを必要とします。これを乗り超えなければ超大物捕獲は永遠にありません。

4番目は赤丸の直径は約15㎝、150mからサコー75で撃ちました。
これがケンさんのサコー75の普通時はこの程度でした。
実戦能力はこれで300m遠射を含み不自由する事は全くありませんでした。実戦に必用なのは超高精度射撃ではなく、相手が逃げる前に撃てる早撃ち能力でした。射撃は心に不安がればかすりもしない失中に終わります。
銃を向けて照準しても何時逃げ出すのかハラハラしていては、真面な射撃になる筈がありません。しかし逃げ出す前に必ず撃てる自信があれば、当然の様に命中します。更に大物ですと「迫力負け」問題が避けて通れません。
ランニング射撃は2000年頃にH&Kオートにより第1段階が完成しました。
3年の実戦90日と3000発をエゾ鹿に向けて射撃した結果、得られました。
それは有効射程50m、」1頭に5発強を要する物でしたが、走られれば何も出来なかった事に比べれば、大きな進歩と言え、当時はこれでランニング射撃を克服したつもりになっていました。2マガジン10発で3頭が最高記録、胴体に被弾させ、3発被弾のショットガン効果の捕獲でした。
2006年ランニング射撃はサコーボルトにより完全な完成を迎えました。
有効射程は何と4倍の200mとなり、それでいながら1頭捕獲に2.7発と命中率は約2倍向上、2ヶ月後には更に約2倍の1.4発と驚く程まで向上しました。ボルト銃がこんなの高能力とは夢にも思いませんでした。
同じ狩猟年度の2007年1月、シカ肉大量注文が入り、これにビッグフィーバーが重なり、5日間に捕獲50頭、この過程で念願だった5発5中もマグレとは言わせない3度記録、本物と言えました。
スナップスイング再肩付けのランニング射撃は動的射撃が可能不能と言うより、ボルト銃はランニング射撃が得意項目と言えました。
これは散弾銃の動的射撃と全く共通と言えました。
普通射撃でこれらに全く対応出来ないのは、反動によるフリンチングを克服していない為です。フリンチングにより発射直前に体が硬くなり、静的は照準がズレて高精度射撃が不可能となり、また動的は必要なスイングが引き止まりとなる為、目視では命中しないのです。
ランニング射撃その物は銃をスイングで、目標(虚像)を追い越す時に、引き金を引くだけで命中する簡単な作業です。
見えている映像は少し古い「虚像」である為、見て確認して撃つ従来射撃では絶対に命中はありません。目視確認で撃てるのは「虚像」と「実体」が同位置にある静止時の特例射撃だけなのです。
8.フリンチング対策の新アイデア。
肩に銃を着けるから、フリンチングで引き止まりになるのであり、フリンチングで照準がズレてしまうのですから、肩に銃を着けないで(軽く付ける)、銃は頬に付け撃つだけとすれば、恐らく引き止まりは起こらず、また照準ずれも起こらないだろうと思われます。
この考えはつい先程の思い付きですから、実証はされていませんが、恐らく正解だろうと思います。またこれが抜群に有効だったお呪い「そっと撃つ」の科学的根拠になる様な気がします。是非お試し下さい。そして成果が上がりましたらお知らせ下さい。
さて北海道では渓流釣りに行きましたが、釣り場が荒らされ、レインボウが僅かに釣れたのみでした。とうとう北海道でも野性のイワナ釣りが難しくなりました。
野性動物でヒグマに会えました。場所はオシラネップ線の小学校跡地の少し上、山林の中からこちらを見ていましたが、カメラを向けた時はもう逃げ始めていました。カメラと銃は捉える速度は概ね同じですから、狩猟期間にライフル銃で出会えれば、捕獲の可能性はあったと思われます。
花畑で出会ったメス鹿はカメラでバッチリ捉えられ、これは撃墜確実です。
それで行きますとヒグマはカメラ連射2枚目でもう姿を消しており、ギリギリ1発目のスナップショットの境目であり、連射は不可能でした。以前の知床では駆除が行われず、エゾ鹿は道端にゴロゴロいましたが、昨今は駆除が行われる様になり、知床の保護区でも姿を見る事は稀となりました。
さて今回の知床林道はヒグマには会う事は出来ずでしたが、ヒグマより更に貴重なクマゲラに出会う事が出来ました。クマゲラはカラスより若干小型、キツツキの中ではダントツに大型な黒い鳥です。
写真はオスで頭が赤いのが特徴ですが、メスの頭の赤は非常に僅かです。今まで遠くに見た事は 数度ありますが、近くで見たのは初めてでした。
小清水原生花園も見に行きましたが、もう昔の様に野生の花が咲き乱れると言う事は無くなりました。
写真は人口の花畑です。小清水の近くにはサケが抜群に釣れる場所があったのですが、数年前からサケ釣り禁止になりました。
北海道で実に勿体ないと思うのは このサケ釣りとエゾ鹿猟で、この2つは有料化して北海道の観光資源として、日本人にも外国人にも開放する事が望ましいと思います。
4.衝撃的なエゾ鹿オスの写真。
もう一つ衝撃的な写真を発見しました。ニセコ方面に道の駅に展示されていた写真ですが、何と草を食べているオス鹿の頭には、角が絡んで外れなくなってしまったもう1頭のオスの頭蓋骨のミイラが、付いたままでした。
普通はこうなってしまうと2頭とも死んでしまうのが普通です。
どう言う経緯かは知りませんが、決闘の対戦相手が死に、更に相手の首が腐り、頭蓋骨が外れるまでには相当の期間を要すると思われます。その間をどうして生き延びたのか詳細は不明ですが、それを 生き延びたと言うのですから超驚きです。
春には角が落ち解放されますが、大変な受難でした。
角の形状がシンプルな日本鹿やエゾ鹿では絡まって動けなくなる事自体が珍しいですが、角形状が複雑な、ムースやカリブーやエルク では時々見受けられる様です。
5.ヒグマ事故の代表的原因である竹の子と、クマ笹ワラビを食べました。


熊笹の1種で千島笹の通称「根曲りタケノコ」、同じく熊笹等の中に生える「熊笹ワラビ」を食べました。北海道には竹が無く、タケノコと言えばこれを指します。意外と高価で写真の物が250円でした。
歯応えはシャキシャキ感が非常に強い独特の風味ですが、味は我地方の直径20㎝以上の巨大な 孟宗竹のタケノコが500円、孟宗の方が美味しいと思いました。
ワラビ自体はそこらに多数生えるのですが、熊笹ワラビは我が地方のワラビに比べ、長さも太さも2倍以上、濃い熊笹の中で育ったワラビほど、直射日光が当たらず、長く・太く・柔らかく・そして美味しいのだそうです。ワラビは当地方の物より遥かに美味しく、抜群と言えました。
但し両者共ヒグマの大好物、これらを採りに行く場所である熊笹籔は視界1mですから、ヒグマと1mで鉢合わせしたり、濃い笹藪の中で迷子になったり、毎年事故も多い山菜採りです。
2018年、秋田にてタケノコ採り4人が、ツキノワグマに殺されたのも、同じタケノコです。この事件では主犯と思われるスーパーKは駆除された物の、他の3頭の人喰い熊はまだ生き残っています。
6.立ち止まらないヒグマ。
ヒグマは我が国最大の野性獣であり、また狩猟対象獣でもあり、大物ヒグマの体重は400㎏を超えます。1度は勝負したい対戦相手と言えますが、鹿の様に立ち止まらず、普通射撃では超高難度です。肉食を好む少数のヒグマは昔からいました。
1960年代前半までは牧場の家畜が毎年数百頭に及びましたが、肉好ヒグマは徹底的に駆除され、1時期は家畜の被害も概ねゼロになりました。
1990年に春熊の駆除が廃止されて以降、ヒグマは増え続け、またその頃からエゾ鹿猟が盛んになり、その残滓を食べる事から、その後はまた肉食のヒグマが増えている傾向にあります。
オソ18と名が付けられたヒグマは最初に発見されたのがオソ地区であり、足跡の幅が18㎝であった為、そう言う名前が付きました。2019年以降すでに66頭の乳牛がやられているそうです。
ケンさんが捕獲したオサツ林道の推定450㎏の大ヒグマも足幅18㎝、オサツ18と言えました。ケンさんのヒグマはマグレではないと言える物の、僅か6頭の 捕獲しかなく、偉そうな事は言えませんが、立ち止まらないヒグマを捕獲する事は普通射撃ではかなり困難です。
エゾ鹿プロハンターでケンさんより圧倒的に多い実戦出撃をしているハンターでも、ヒグマ捕獲は数頭しかありません。ケンさんの6頭も普通射撃が可能だったのは2頭に留り、出会い頭のスナップショット、走っているヒグマのランニングショットが過半を占めています。
オサツ18の場合は斜め後方100mからのランニングショットでした。
7.ケンさんの射撃。
空気銃で30mのスズメの頭を外さなかったケンさんですが、1984年に始めたレミントン1100の20番スラグ射撃では 50mから撃って100mライフル用の40㎝の的紙から時に外れてしまう程でした。最初はノーライフルだからと思いましたが、フリンチングが主原因でした。


左:レミントン20番スラグ専用銃。 右:レミントン1187の散弾銃。
1989年、1番目の標的、やっと50mSB標的の黒点、11㎝を概ね外さない様になりました。翌1990年類似型式のレミントン742ライフルで撃ちましたが、結果はスラグガンと概ね同等と言えました。これでノーライフルだから当たらないと言う理由は使えなくなりました。
2番目の標的は普通のレミントン11-87のスラグ弾射撃です。
スラグ専用銃と普通の散弾バレルと言うのも、殆ど差が無しでした。

3番目は2002年H&Kオートで撃ちました。150mで5発が12㎜です。
これがケンさんの5発グルーピングではベストでした。
オートにしては抜群と言えるグルーピングでした。
308で急所を正しく撃てば必ず即倒即死しますが、迫力負け射撃では概ね全てが失中又は未回収となりマグレも起こりません。大物は狩猟慣れしているので銃を向けるとすぐに逃げ出します。
大物であればある程一般的に距離は遠くなり、照準時間が短く、それでいながらより確実に急所ヒットを必要とします。これを乗り超えなければ超大物捕獲は永遠にありません。
4番目は赤丸の直径は約15㎝、150mからサコー75で撃ちました。
これがケンさんのサコー75の普通時はこの程度でした。
実戦能力はこれで300m遠射を含み不自由する事は全くありませんでした。実戦に必用なのは超高精度射撃ではなく、相手が逃げる前に撃てる早撃ち能力でした。射撃は心に不安がればかすりもしない失中に終わります。
銃を向けて照準しても何時逃げ出すのかハラハラしていては、真面な射撃になる筈がありません。しかし逃げ出す前に必ず撃てる自信があれば、当然の様に命中します。更に大物ですと「迫力負け」問題が避けて通れません。
ランニング射撃は2000年頃にH&Kオートにより第1段階が完成しました。
3年の実戦90日と3000発をエゾ鹿に向けて射撃した結果、得られました。
それは有効射程50m、」1頭に5発強を要する物でしたが、走られれば何も出来なかった事に比べれば、大きな進歩と言え、当時はこれでランニング射撃を克服したつもりになっていました。2マガジン10発で3頭が最高記録、胴体に被弾させ、3発被弾のショットガン効果の捕獲でした。
2006年ランニング射撃はサコーボルトにより完全な完成を迎えました。
有効射程は何と4倍の200mとなり、それでいながら1頭捕獲に2.7発と命中率は約2倍向上、2ヶ月後には更に約2倍の1.4発と驚く程まで向上しました。ボルト銃がこんなの高能力とは夢にも思いませんでした。
同じ狩猟年度の2007年1月、シカ肉大量注文が入り、これにビッグフィーバーが重なり、5日間に捕獲50頭、この過程で念願だった5発5中もマグレとは言わせない3度記録、本物と言えました。
スナップスイング再肩付けのランニング射撃は動的射撃が可能不能と言うより、ボルト銃はランニング射撃が得意項目と言えました。
これは散弾銃の動的射撃と全く共通と言えました。
普通射撃でこれらに全く対応出来ないのは、反動によるフリンチングを克服していない為です。フリンチングにより発射直前に体が硬くなり、静的は照準がズレて高精度射撃が不可能となり、また動的は必要なスイングが引き止まりとなる為、目視では命中しないのです。
ランニング射撃その物は銃をスイングで、目標(虚像)を追い越す時に、引き金を引くだけで命中する簡単な作業です。
見えている映像は少し古い「虚像」である為、見て確認して撃つ従来射撃では絶対に命中はありません。目視確認で撃てるのは「虚像」と「実体」が同位置にある静止時の特例射撃だけなのです。
8.フリンチング対策の新アイデア。
肩に銃を着けるから、フリンチングで引き止まりになるのであり、フリンチングで照準がズレてしまうのですから、肩に銃を着けないで(軽く付ける)、銃は頬に付け撃つだけとすれば、恐らく引き止まりは起こらず、また照準ずれも起こらないだろうと思われます。
この考えはつい先程の思い付きですから、実証はされていませんが、恐らく正解だろうと思います。またこれが抜群に有効だったお呪い「そっと撃つ」の科学的根拠になる様な気がします。是非お試し下さい。そして成果が上がりましたらお知らせ下さい。
2022年11月07日
北海道ツーリング&ビッグフィッシング再開。
2週間の北海道ツーリングに行って来ました。2500㎞も走ってしまいました。
今回の目的は紅葉見物、渓流釣り&サケ釣り、ラッコ&ヒグマウォッチング、花咲ガニ、黒カレー、アイナメ、ホタテ貝等々を喰べる、そんな処ですが、以下の詳細を参照下さい。
アラスカビッグフィッシング。
もう1つ目的がありました。3年前、悪性リンパ腫の為、アラスカビッグフィッシングが中止となりましたが、コロナもやや終息し、海外旅行が可能となって来ましたので、これの再開の為のリハーサルを兼ねています。
今回は2週間ノントラブルで過ごせましたので一応合格、アラスカビッグフィシングと、ツンドラ紅葉ドライブを再企画したいと思います。全行程は現地2週間の予定です。
紅葉ドライブは車中泊の予定、同行者はテント持参でお願いします。
ビッグフィッシングのみ部分参加も可能で、同行は釣全費用の40%の割り勘です。
ビッグフィッシングは3日間、行き先はコディアック島、カレイの親分1.5mのハリバット、アイナメの親分1mのリングコッド、婚姻色のドリーバーデンとレッドサーモンが予定されています。他にもキングやシルバーサーモンやアラスカメヌケも狙えそうです。
釣り予算は概算で、3日分のフィッシングがレンタル道具付で約6000ドル、この内の40%が同行者負担となります。こちらからはケンさんとワイフが参加します。
良い写真は1枚1万円で買い上げます。勿論それ以外にコディアック島までの航空券や現地ホテル代等は各自持ちです。詳しくはお問合せ下さい。
北海道ツーリング。
1.紅葉:低地が紅葉のピークでした。大沼公園と洞爺湖はベストチャンスでした。


2.渓流釣り:かつての猟場であった。滝上と根室で行いました。
本州では純野性物は絶望的に近くなりますが、北海道では都会から車で2時間離れれば釣れます。対象は山女魚、レインボウ、カラフト岩魚、エゾ岩魚、下流寄りではウグイがいます。山女魚は近年難しくなって来ました。


樺太岩魚は積雪の為に行けず、釣果は1匹のみ、レインボウのポイントでは大小10匹を釣り、5匹は塩焼き、樺太岩魚を含め、残りは押し寿司を作りました。
押し寿司はクマ笹の若葉で包むのが本来ですが、季節柄クマ笹の若葉が手に入らず、省略しましたが、過去最高の出来栄えとなりました。
根室ではエゾ岩魚と山女魚が予定されていましたが、ヤマメのポイントは水が枯れており、エゾ岩魚の大小8匹を釣り、大きいのは塩焼き、小さいのは唐揚げとなりました。
空揚げや天ぷらには小さい方が美味しいのです。
3.サケ釣り:かなりの場所で試しましたが、地元アングラーもかなりマバラ、ノーヒット&ノーバイトでした。鮭の捕獲所を見ると鮭は多少はいるのですが、良い群れに恵まれませんでした。
4.ラッコウォッチング:カメラも望遠鏡も揃えて臨んだのですが、見る事は出来ずに終わりました。また鮭釣りを含めて来シーズンに再チャレンジです。

5.ヒグマウォッチング:知床峠は積雪で通行不可、知床林道も工事中で通行不可で、ガッカリでしたが、国道近くでヒグマを見る事が出来ました。


6.エゾ鹿:知床地区では予想外にエゾ鹿に出会えずでしたが、根室地区では殆どがメスですが、1日に10回のエゾ鹿との出会いがありました。大物雄との出会いは12月中旬まで待たなくてはなりません。まだ繁殖シーズン前でオスの活発なアピールは見られません。見掛けたオスはまた夏毛のハンテンが残り、角も皮が剥けたばかりでした。


7.花咲ガニ:北海道のカニはタラバガニ、ケガニ、松葉ガニの3種が有名で、どれが美味しいかの議論が何時もされますが、ケンさんの感想では花咲ガニがNO.1だと思います。


食べたのは甲羅の幅が約15㎝の中型の2200円でした。抜群の実入りで味も抜群でした。白崎牧場で以前戴いたのはハサミ部分だけでも20.5㎝と超規格外、ハサミ部分は資料館に展示中です。花咲ガニは茹でると花が咲いた様に真っ赤になり、また根室半島の花咲港周辺でしか上らないカニで、余り出廻っておりません。
8.黒カレー:北海道にカレーも類は10種近くありますが、この黒カレーが安くて美味しいと思います。北海道で安いのはカレー、ホタテ、アイナメ、ホッケ、サメ、エイ、タコの頭と嘴、タラの頭、そんな所が、本州の半額程度以下で買えます。
9.アイナメ、:本州のアイナメは30㎝程度ですが、北海道では50cm前後が多いです。
今回は良いアイナメが無かったので、ホッケ(アイナメの仲間)で代用しましたが、ホッケとはこんなに美味い魚だったのかと思う様な、大きくて良い魚が400円で買えました。
10.ホタテ貝:貝柱の直径が4㎝もある様な大型ホタテが10個で1000円でした。
勿論味は抜群でした。流石に北海道でもこれは本来2000円をかなり超えますが、夕方の半額セールで1300円、それを値切って1000円で購入しました。
11.青ツブ貝:今回はそのシーズンでなくありませんでしたが、昨年中型が30~40個入って500円、美味しかったです。
12.タコのくちばし:水タコの足の長さは1m、くちばしは直径5㎝前後と巨大、これが8個入って250円位、抜群の美味しさに加え、抜群のボリュームです。
13.タラの頭:鍋に入れる魚は大型のマダラの頭が1番美味しいです。
1個100~200円、これで2人分に十分、且つ非常に美味しく頂けます。
14.子持ちのキューリウオ:アユもワカサギもキューリウオの仲間です。
北海道にもワカサギがいますが、本州より1.5倍のサイズです。汽水域にはその更に1.5倍のチカがおり、更にまた1.5倍のキューリウオがおり、30㎝前後になります。
子持ちでない時も並以上に美味しいのですが、子持ちは更に抜群です。
冬の氷穴釣りは楽しい釣りです。氷穴釣りは3種とも釣れます。また何時かやりたいと思います。

そうそうシシャモもキューリウオの仲間ですが、本物は北海道の太平洋側でした獲れません。こちらの子持ちは1匹が200円前後と別格、手を出し難い価格になります。オスはメスに比べると美味しくて、且つ半額以下になり、狙い目はオスと言えます。
15.ニシンのカズノコ入りのメスは焼いても美味しくなく、一方シラコ入りのオスは抜群に美味しい焼き魚となります。
その他、北海道でしか流通していない魚はかなりたくさんあります。
北海道の魚は概ね全てが美味しいのですが、沖縄の魚は余り美味しくありません。
今回の目的は紅葉見物、渓流釣り&サケ釣り、ラッコ&ヒグマウォッチング、花咲ガニ、黒カレー、アイナメ、ホタテ貝等々を喰べる、そんな処ですが、以下の詳細を参照下さい。
アラスカビッグフィッシング。
もう1つ目的がありました。3年前、悪性リンパ腫の為、アラスカビッグフィッシングが中止となりましたが、コロナもやや終息し、海外旅行が可能となって来ましたので、これの再開の為のリハーサルを兼ねています。
今回は2週間ノントラブルで過ごせましたので一応合格、アラスカビッグフィシングと、ツンドラ紅葉ドライブを再企画したいと思います。全行程は現地2週間の予定です。
紅葉ドライブは車中泊の予定、同行者はテント持参でお願いします。
ビッグフィッシングのみ部分参加も可能で、同行は釣全費用の40%の割り勘です。
ビッグフィッシングは3日間、行き先はコディアック島、カレイの親分1.5mのハリバット、アイナメの親分1mのリングコッド、婚姻色のドリーバーデンとレッドサーモンが予定されています。他にもキングやシルバーサーモンやアラスカメヌケも狙えそうです。
釣り予算は概算で、3日分のフィッシングがレンタル道具付で約6000ドル、この内の40%が同行者負担となります。こちらからはケンさんとワイフが参加します。
良い写真は1枚1万円で買い上げます。勿論それ以外にコディアック島までの航空券や現地ホテル代等は各自持ちです。詳しくはお問合せ下さい。
北海道ツーリング。
1.紅葉:低地が紅葉のピークでした。大沼公園と洞爺湖はベストチャンスでした。
2.渓流釣り:かつての猟場であった。滝上と根室で行いました。
本州では純野性物は絶望的に近くなりますが、北海道では都会から車で2時間離れれば釣れます。対象は山女魚、レインボウ、カラフト岩魚、エゾ岩魚、下流寄りではウグイがいます。山女魚は近年難しくなって来ました。
樺太岩魚は積雪の為に行けず、釣果は1匹のみ、レインボウのポイントでは大小10匹を釣り、5匹は塩焼き、樺太岩魚を含め、残りは押し寿司を作りました。
押し寿司はクマ笹の若葉で包むのが本来ですが、季節柄クマ笹の若葉が手に入らず、省略しましたが、過去最高の出来栄えとなりました。
根室ではエゾ岩魚と山女魚が予定されていましたが、ヤマメのポイントは水が枯れており、エゾ岩魚の大小8匹を釣り、大きいのは塩焼き、小さいのは唐揚げとなりました。
空揚げや天ぷらには小さい方が美味しいのです。
3.サケ釣り:かなりの場所で試しましたが、地元アングラーもかなりマバラ、ノーヒット&ノーバイトでした。鮭の捕獲所を見ると鮭は多少はいるのですが、良い群れに恵まれませんでした。
4.ラッコウォッチング:カメラも望遠鏡も揃えて臨んだのですが、見る事は出来ずに終わりました。また鮭釣りを含めて来シーズンに再チャレンジです。
5.ヒグマウォッチング:知床峠は積雪で通行不可、知床林道も工事中で通行不可で、ガッカリでしたが、国道近くでヒグマを見る事が出来ました。
6.エゾ鹿:知床地区では予想外にエゾ鹿に出会えずでしたが、根室地区では殆どがメスですが、1日に10回のエゾ鹿との出会いがありました。大物雄との出会いは12月中旬まで待たなくてはなりません。まだ繁殖シーズン前でオスの活発なアピールは見られません。見掛けたオスはまた夏毛のハンテンが残り、角も皮が剥けたばかりでした。

7.花咲ガニ:北海道のカニはタラバガニ、ケガニ、松葉ガニの3種が有名で、どれが美味しいかの議論が何時もされますが、ケンさんの感想では花咲ガニがNO.1だと思います。

食べたのは甲羅の幅が約15㎝の中型の2200円でした。抜群の実入りで味も抜群でした。白崎牧場で以前戴いたのはハサミ部分だけでも20.5㎝と超規格外、ハサミ部分は資料館に展示中です。花咲ガニは茹でると花が咲いた様に真っ赤になり、また根室半島の花咲港周辺でしか上らないカニで、余り出廻っておりません。
8.黒カレー:北海道にカレーも類は10種近くありますが、この黒カレーが安くて美味しいと思います。北海道で安いのはカレー、ホタテ、アイナメ、ホッケ、サメ、エイ、タコの頭と嘴、タラの頭、そんな所が、本州の半額程度以下で買えます。
9.アイナメ、:本州のアイナメは30㎝程度ですが、北海道では50cm前後が多いです。
今回は良いアイナメが無かったので、ホッケ(アイナメの仲間)で代用しましたが、ホッケとはこんなに美味い魚だったのかと思う様な、大きくて良い魚が400円で買えました。
10.ホタテ貝:貝柱の直径が4㎝もある様な大型ホタテが10個で1000円でした。
勿論味は抜群でした。流石に北海道でもこれは本来2000円をかなり超えますが、夕方の半額セールで1300円、それを値切って1000円で購入しました。
11.青ツブ貝:今回はそのシーズンでなくありませんでしたが、昨年中型が30~40個入って500円、美味しかったです。
12.タコのくちばし:水タコの足の長さは1m、くちばしは直径5㎝前後と巨大、これが8個入って250円位、抜群の美味しさに加え、抜群のボリュームです。
13.タラの頭:鍋に入れる魚は大型のマダラの頭が1番美味しいです。
1個100~200円、これで2人分に十分、且つ非常に美味しく頂けます。
14.子持ちのキューリウオ:アユもワカサギもキューリウオの仲間です。
北海道にもワカサギがいますが、本州より1.5倍のサイズです。汽水域にはその更に1.5倍のチカがおり、更にまた1.5倍のキューリウオがおり、30㎝前後になります。
子持ちでない時も並以上に美味しいのですが、子持ちは更に抜群です。
冬の氷穴釣りは楽しい釣りです。氷穴釣りは3種とも釣れます。また何時かやりたいと思います。

そうそうシシャモもキューリウオの仲間ですが、本物は北海道の太平洋側でした獲れません。こちらの子持ちは1匹が200円前後と別格、手を出し難い価格になります。オスはメスに比べると美味しくて、且つ半額以下になり、狙い目はオスと言えます。
15.ニシンのカズノコ入りのメスは焼いても美味しくなく、一方シラコ入りのオスは抜群に美味しい焼き魚となります。
その他、北海道でしか流通していない魚はかなりたくさんあります。
北海道の魚は概ね全てが美味しいのですが、沖縄の魚は余り美味しくありません。
2020年07月30日
エゾ鹿猟の射程距離の変化。
1.近距離50m時代。
太古の弓矢の時代から1990年頃まで、エゾ鹿は永らく50m前後にいました。
それはこれらの時代の50mは遠く命中率が低いので、高価な矢の紛失を恐れ、先込め銃や村田銃も命中率の低下から弾薬節約で撃たなかったのです。
そんな50m時代は初期のスクール(2002~)時代まで続き、稀には10m前後にいましたので普通のスラグ銃でも楽勝捕獲が可能でした。そう言う鹿はメデタイを超えていますのでデメキンと呼ぶ事にしました。初期に捕獲ゼロの生徒が皆無であったのはデメキン鹿のお陰でしたが、そう言う10mのデメキン鹿は2007年を最後に見なくなりました。
2.中距離100m時代。
2005年頃からエゾ鹿は毎年少しずつ距離が遠くなり、やがて2010年頃には100m戦後となり、サボットスラグ銃と100mの射撃技術が必要になりました。
この時代の捕獲ゼロの生徒が皆無だったのは、事前射撃教育と本人努力の相乗効果の賜物でした。
2013年には一気に遠く150m前後となり、サボットスラグ銃も届かない事がよくありました。
150mはライフル銃でも難度が増す距離であり、地元のアマチュアライフルハンターは出撃しても獲れない事が多くなり、出撃が大幅に減少しました。その結果2015年頃には再び鹿は80~150mに戻り、サボットスラグ銃でも何とかエゾ鹿猟が可能になり、現在に至ります。
しかし駆除慣れした1部のシカは150m以遠であり、また大物の習性上からデカくなる程、広い場所に出現しますので、大物や超大物と勝負するにはライフル銃が不可欠となります。
3.照準時間の変化。
駆除は今や年中行事となり、鹿は1年中狩猟圧力下にいます。
結果的に150mにいるのですが、そこにいればライフルでも余り撃たれない、また撃たれても余り当たらない事を学習済なのです。
もう一つの昨今の傾向は、銃を向けると3~5秒で動く個体が増えた事ですが、そうすれば照準が非常に難しくなります。これもシカが学習して得た行動です。しかしその対策は簡単です。まずは150m射撃の精度を上げれば良く、次に3秒程度で照準を終えて、発砲出来る早撃ちに対応出来る様にすれば良いのです。
4.対策方法その1:近距離用スナップショット。
銃を構える行為は以下の様になります。まず銃を肩に着け、頭がスコープを探しに行き、それからスコープで鹿を捜索し、その後に長~い照準に入ります。通常ですと発砲まで10~30秒を要します。
スナップショットはこの時間を1/10以下にする早撃ちテクニックです。手法は銃身で目標を指差す様に突き出し、まっすぐ肩に引き寄せます。体の方は銃身の突き出しと同時に最終姿勢に移行します。
すると頭はすでに最終位置にあるので、ショットガンなら銃が肩に着く遥か手前からリブを通した照準が可能となり、ライフル銃でも肩に銃が着く少し前から不完全ながらスコープから映像が得られます。
銃が肩に着く前でもすでに照準が出来ているのですから50m以内であれば撃てば命中します。
これがスナップショットです。これが出来なければ他の上級射撃にも効果は出ません。
5.対策方法その2:中距離用150mアバウトショット。
銃だけに撃たせる150mの10㎜代のワンホール射撃が出来る技術と、スナップショットが出来ると言う事が前提条件になります。ワンホールは銃だけに撃たせる、かなり高度な精密照準をしなければ達成出来ません。これ自体は実戦には不要なのですが、これが達成出来れば他の全ての射撃精度が向上します。
ワンホールからすれば獲物の急所は直径15cm程度と1桁大きく、スナップショットで構え、アバウト的な照準のままのヨイ加減で早撃ちしても急所の何処かには命中します。これが150mアバウト早撃ちの考え方です。銃は速く構えられるに越した事は無く、スナップショットは全ての射撃の基本となります。
6.対策方法その3:遠射300m。
昨今の市販ライフル銃は150mワンホールと300mの遠射能力を持っていますから、150mワンホールが達成されれば300m遠射達成も時間の問題となります。300mの最大の失中原因は落差補正の不安です。通常ですと300m射撃は落差補正が必要になり、補正に自信が持てないと命中しません。
しかし次の2つの手法で300m遠射は落差無視の直撃照準が可能になります。
因みにケンさんは150mゼロインですが300mの落差量は知りません。それでも失中する気がしないのです。
その1:全依託射撃による銃の跳ね上がり。
全依託射撃を行いますと、銃が発射の振動で跳ね上がり、弾着は上方にずれ自動的に落差補正が行われる方向になります、次項の上下方向に長い急所なら直撃射撃対応が十分に可能となります。
落差無視でも命中すると言う自信が湧けば、命中率は激増と言うか、最早失中は考えられなくなります。
その2:上下方向に広い急所に照準する。
銅弾頭は鉛弾頭と違い骨にヒットしても威力を失いません。この特性を利用し積極的に骨を狙います。骨にヒットすると脊髄にショックが伝わりやすく、高確率でその場にひっくり返ります。鹿が横向きの場合、最も良いのは背骨との交点ですが、前足の軸線に正しくヒットすれば何処に命中してもその場に倒れ、動けなくなります。
7.スナップショット50mと150mアバウト早撃ちと300m遠射。
この前者2つの射撃が出来る様になりますと、0~150mの鹿に対し最大3秒程度で発砲出来ます。
3秒であれば殆どの鹿が動き始める前に発砲出来、逃げられる不安が概ね無くなる為、精神的に大幅有利な射撃となり、命中率は格段に向上します。
そしてやがては300mの遠射も前足軸線ヒットの自信が付けば、失中する筈が無いと思える様になります。
合わせてケンさんは撃つ直前に行う「おまじない」を開発しました。それは「そっと撃つ」を心に3回念ずる事です。このおまじないを実行する様になってから、失中は完璧皆無となりました。
愛銃を信じ、不安を無くし、おまじないを実行する、これで全ての射撃は完璧となるのです。
これに走る鹿の「ランニングショット」や、動き始めの鹿にも命中させられる「ムービングスタート射撃」が加われば鬼に金棒となります。
8.永年の実戦経験から分かった事。

写真はケンさんの愛銃、サコー75改
銃やスコープ、そして弾薬は特別製である必要は全くなく、市販の普及品で大丈夫です。ケンさんの愛銃はサコー75バーミンターを短縮軽量化した25万円の市販銃、リューポルドの安物の3万円のスコープ、使用弾は酷評のロシア製超激安弾80円/発、弾頭は命中しないのと倒れない事で悪評の20円/発の初期型バーンズ140gr、しかもクリーニング無し、悪条件の塊と言えます。
しかしこの悪条件下でも数々の大記録を達成出来ました。

写真はケンさんの超激安使用弾。
市販弾薬の一覧表を見ますと、口径と弾頭の違い等で約150種類もあります。
少しでも捕獲率を上げ様とした結果だと思いますが、弾薬は小動物用に22LR、中型動物、鹿クラス、大物クラスの4種で十分なのですから、150種は最早傑作と言えるレベルの代表的な無用無益な行為でした。
良く倒れる事を売りにしているハイパワーマグナム銃、命中率の良さを売りにしているカスタム銃、高命中率の為の必需品を匂わせる高級スコープ、高精度の為には不可欠を匂わせる精密ハンドロード、銅や鉛を除去 する薬剤による完璧なクリーニング、これらは全て大嘘であり、全て不要でした。
講師が悪条件下で出した数々の大記録がこれを証明しています。
9.心を鍛える。
通常の経験の少ないハンターの場合、至近距離の出会いに対してはスコープに捉える事が出来ず、チャンスを逃がしてしまいます。急に動いた鹿に対しては旧位置に向けたアセリ発射に終わります。中距離射撃では 逃げられるかも知れないので、早く撃たなければと言うプレッシャーに耐えかね、そして遠射の場合は落差 補正の不安から、それらの結果は共にカスリもしない失中となりました。
超大物エゾ鹿との勝負はエゾ鹿ハンターの夢ですが、勝負出来る確率はケンさんのガイドの場合で約5%、5日に1回です。勝負の結果は超大物の迫力に負けた、足が地に着かないカスリもしないダメ射撃でした。
捕獲成功までには実績で20日を要しますが、迫力負けの経験を5回前後必要であり、3日出撃では7年前後を通う必要があります。


猛獣ヒグマとの勝負出来る確率もそれよりやや低い数%でした。その結果は迫力負けのエゾ鹿と同様な結果に陥る場合に加え、更に恐怖負けがありました。これに陥りますとフリーズになって動けなくなるか、気違いに刃物的にあらぬ方向に撃ちまくるかのどちらかになりました。
失中原因の概ね100%が銃や弾の精度不足ではなく、射手の心の訓練不足で、迫力負けや恐怖負け対策が至らなければ、貴重な実戦の良い出会いも全てカスリもしない無効射撃に終わってしまいます。その肝心の一瞬に上手くやる為には、足が地に着かない舞い上がった状態でも、手足が予定通りの行動をしてくれる様になるまでしぶとく訓練する事です。
反動を恐れる為に照準がズレてしまう様なフリンチング対策等の基礎練習は必要ですが、その後に本当にやるべき事は射撃場通いや机上理論ではなく、心を鍛えるイメージトレーニングです。
このトレーニングと実戦での場数経験、これが実戦で成果を上げられる唯一の手法です。
しかしランニング射撃だけは射撃理論が多少重要になります。
命中への必要条件は安定したスイングの継続と、見ないまま引き金を引く思い切りの良さです。
これに対し通常射撃では、銃を静止安定させて肉眼で照準しますので、ランニング射撃には理論の違いから対処不能となり、ダメ元射撃にもなりません。
ヒグマ勝負には迫力負けや恐怖負け対策が必要なのは言うまでもありませんが、ケンさんが倒したヒグマ6頭は2頭がスナップショット、4頭は動いていましたからムービング射撃が不可欠になります。
栃木O生徒は50日ほど通って、50mの歩いているヒグマに後方から2回射撃が出来ました。
2回ともイージーチャンスであったのですが、2回とも銃を止めて狙い込んでしまった為、かすりもしない失中となりました。勿体ない限りですね。
太古の弓矢の時代から1990年頃まで、エゾ鹿は永らく50m前後にいました。
それはこれらの時代の50mは遠く命中率が低いので、高価な矢の紛失を恐れ、先込め銃や村田銃も命中率の低下から弾薬節約で撃たなかったのです。
そんな50m時代は初期のスクール(2002~)時代まで続き、稀には10m前後にいましたので普通のスラグ銃でも楽勝捕獲が可能でした。そう言う鹿はメデタイを超えていますのでデメキンと呼ぶ事にしました。初期に捕獲ゼロの生徒が皆無であったのはデメキン鹿のお陰でしたが、そう言う10mのデメキン鹿は2007年を最後に見なくなりました。
2.中距離100m時代。
2005年頃からエゾ鹿は毎年少しずつ距離が遠くなり、やがて2010年頃には100m戦後となり、サボットスラグ銃と100mの射撃技術が必要になりました。
この時代の捕獲ゼロの生徒が皆無だったのは、事前射撃教育と本人努力の相乗効果の賜物でした。
2013年には一気に遠く150m前後となり、サボットスラグ銃も届かない事がよくありました。
150mはライフル銃でも難度が増す距離であり、地元のアマチュアライフルハンターは出撃しても獲れない事が多くなり、出撃が大幅に減少しました。その結果2015年頃には再び鹿は80~150mに戻り、サボットスラグ銃でも何とかエゾ鹿猟が可能になり、現在に至ります。
しかし駆除慣れした1部のシカは150m以遠であり、また大物の習性上からデカくなる程、広い場所に出現しますので、大物や超大物と勝負するにはライフル銃が不可欠となります。
3.照準時間の変化。
駆除は今や年中行事となり、鹿は1年中狩猟圧力下にいます。
結果的に150mにいるのですが、そこにいればライフルでも余り撃たれない、また撃たれても余り当たらない事を学習済なのです。
もう一つの昨今の傾向は、銃を向けると3~5秒で動く個体が増えた事ですが、そうすれば照準が非常に難しくなります。これもシカが学習して得た行動です。しかしその対策は簡単です。まずは150m射撃の精度を上げれば良く、次に3秒程度で照準を終えて、発砲出来る早撃ちに対応出来る様にすれば良いのです。
4.対策方法その1:近距離用スナップショット。
銃を構える行為は以下の様になります。まず銃を肩に着け、頭がスコープを探しに行き、それからスコープで鹿を捜索し、その後に長~い照準に入ります。通常ですと発砲まで10~30秒を要します。
スナップショットはこの時間を1/10以下にする早撃ちテクニックです。手法は銃身で目標を指差す様に突き出し、まっすぐ肩に引き寄せます。体の方は銃身の突き出しと同時に最終姿勢に移行します。
すると頭はすでに最終位置にあるので、ショットガンなら銃が肩に着く遥か手前からリブを通した照準が可能となり、ライフル銃でも肩に銃が着く少し前から不完全ながらスコープから映像が得られます。
銃が肩に着く前でもすでに照準が出来ているのですから50m以内であれば撃てば命中します。
これがスナップショットです。これが出来なければ他の上級射撃にも効果は出ません。
5.対策方法その2:中距離用150mアバウトショット。
銃だけに撃たせる150mの10㎜代のワンホール射撃が出来る技術と、スナップショットが出来ると言う事が前提条件になります。ワンホールは銃だけに撃たせる、かなり高度な精密照準をしなければ達成出来ません。これ自体は実戦には不要なのですが、これが達成出来れば他の全ての射撃精度が向上します。
ワンホールからすれば獲物の急所は直径15cm程度と1桁大きく、スナップショットで構え、アバウト的な照準のままのヨイ加減で早撃ちしても急所の何処かには命中します。これが150mアバウト早撃ちの考え方です。銃は速く構えられるに越した事は無く、スナップショットは全ての射撃の基本となります。
6.対策方法その3:遠射300m。
昨今の市販ライフル銃は150mワンホールと300mの遠射能力を持っていますから、150mワンホールが達成されれば300m遠射達成も時間の問題となります。300mの最大の失中原因は落差補正の不安です。通常ですと300m射撃は落差補正が必要になり、補正に自信が持てないと命中しません。
しかし次の2つの手法で300m遠射は落差無視の直撃照準が可能になります。
因みにケンさんは150mゼロインですが300mの落差量は知りません。それでも失中する気がしないのです。
その1:全依託射撃による銃の跳ね上がり。
全依託射撃を行いますと、銃が発射の振動で跳ね上がり、弾着は上方にずれ自動的に落差補正が行われる方向になります、次項の上下方向に長い急所なら直撃射撃対応が十分に可能となります。
落差無視でも命中すると言う自信が湧けば、命中率は激増と言うか、最早失中は考えられなくなります。
その2:上下方向に広い急所に照準する。
銅弾頭は鉛弾頭と違い骨にヒットしても威力を失いません。この特性を利用し積極的に骨を狙います。骨にヒットすると脊髄にショックが伝わりやすく、高確率でその場にひっくり返ります。鹿が横向きの場合、最も良いのは背骨との交点ですが、前足の軸線に正しくヒットすれば何処に命中してもその場に倒れ、動けなくなります。
7.スナップショット50mと150mアバウト早撃ちと300m遠射。
この前者2つの射撃が出来る様になりますと、0~150mの鹿に対し最大3秒程度で発砲出来ます。
3秒であれば殆どの鹿が動き始める前に発砲出来、逃げられる不安が概ね無くなる為、精神的に大幅有利な射撃となり、命中率は格段に向上します。
そしてやがては300mの遠射も前足軸線ヒットの自信が付けば、失中する筈が無いと思える様になります。
合わせてケンさんは撃つ直前に行う「おまじない」を開発しました。それは「そっと撃つ」を心に3回念ずる事です。このおまじないを実行する様になってから、失中は完璧皆無となりました。
愛銃を信じ、不安を無くし、おまじないを実行する、これで全ての射撃は完璧となるのです。
これに走る鹿の「ランニングショット」や、動き始めの鹿にも命中させられる「ムービングスタート射撃」が加われば鬼に金棒となります。
8.永年の実戦経験から分かった事。
写真はケンさんの愛銃、サコー75改
銃やスコープ、そして弾薬は特別製である必要は全くなく、市販の普及品で大丈夫です。ケンさんの愛銃はサコー75バーミンターを短縮軽量化した25万円の市販銃、リューポルドの安物の3万円のスコープ、使用弾は酷評のロシア製超激安弾80円/発、弾頭は命中しないのと倒れない事で悪評の20円/発の初期型バーンズ140gr、しかもクリーニング無し、悪条件の塊と言えます。
しかしこの悪条件下でも数々の大記録を達成出来ました。
写真はケンさんの超激安使用弾。
市販弾薬の一覧表を見ますと、口径と弾頭の違い等で約150種類もあります。
少しでも捕獲率を上げ様とした結果だと思いますが、弾薬は小動物用に22LR、中型動物、鹿クラス、大物クラスの4種で十分なのですから、150種は最早傑作と言えるレベルの代表的な無用無益な行為でした。
良く倒れる事を売りにしているハイパワーマグナム銃、命中率の良さを売りにしているカスタム銃、高命中率の為の必需品を匂わせる高級スコープ、高精度の為には不可欠を匂わせる精密ハンドロード、銅や鉛を除去 する薬剤による完璧なクリーニング、これらは全て大嘘であり、全て不要でした。
講師が悪条件下で出した数々の大記録がこれを証明しています。
9.心を鍛える。
通常の経験の少ないハンターの場合、至近距離の出会いに対してはスコープに捉える事が出来ず、チャンスを逃がしてしまいます。急に動いた鹿に対しては旧位置に向けたアセリ発射に終わります。中距離射撃では 逃げられるかも知れないので、早く撃たなければと言うプレッシャーに耐えかね、そして遠射の場合は落差 補正の不安から、それらの結果は共にカスリもしない失中となりました。
超大物エゾ鹿との勝負はエゾ鹿ハンターの夢ですが、勝負出来る確率はケンさんのガイドの場合で約5%、5日に1回です。勝負の結果は超大物の迫力に負けた、足が地に着かないカスリもしないダメ射撃でした。
捕獲成功までには実績で20日を要しますが、迫力負けの経験を5回前後必要であり、3日出撃では7年前後を通う必要があります。


猛獣ヒグマとの勝負出来る確率もそれよりやや低い数%でした。その結果は迫力負けのエゾ鹿と同様な結果に陥る場合に加え、更に恐怖負けがありました。これに陥りますとフリーズになって動けなくなるか、気違いに刃物的にあらぬ方向に撃ちまくるかのどちらかになりました。
失中原因の概ね100%が銃や弾の精度不足ではなく、射手の心の訓練不足で、迫力負けや恐怖負け対策が至らなければ、貴重な実戦の良い出会いも全てカスリもしない無効射撃に終わってしまいます。その肝心の一瞬に上手くやる為には、足が地に着かない舞い上がった状態でも、手足が予定通りの行動をしてくれる様になるまでしぶとく訓練する事です。
反動を恐れる為に照準がズレてしまう様なフリンチング対策等の基礎練習は必要ですが、その後に本当にやるべき事は射撃場通いや机上理論ではなく、心を鍛えるイメージトレーニングです。
このトレーニングと実戦での場数経験、これが実戦で成果を上げられる唯一の手法です。
しかしランニング射撃だけは射撃理論が多少重要になります。
命中への必要条件は安定したスイングの継続と、見ないまま引き金を引く思い切りの良さです。
これに対し通常射撃では、銃を静止安定させて肉眼で照準しますので、ランニング射撃には理論の違いから対処不能となり、ダメ元射撃にもなりません。
ヒグマ勝負には迫力負けや恐怖負け対策が必要なのは言うまでもありませんが、ケンさんが倒したヒグマ6頭は2頭がスナップショット、4頭は動いていましたからムービング射撃が不可欠になります。
栃木O生徒は50日ほど通って、50mの歩いているヒグマに後方から2回射撃が出来ました。
2回ともイージーチャンスであったのですが、2回とも銃を止めて狙い込んでしまった為、かすりもしない失中となりました。勿体ない限りですね。
2018年03月10日
エゾ鹿回収人募集中:エゾ鹿の超大物やヒグマをタダで撃てます。
スクールの生徒も高齢者又は都会育ちの若者が多くなり、体力が低下した講師とコンビの回収では120kgのエゾ鹿の回収に非常に困っているのが現状です。
そこでスクールはエゾ鹿の回収人を募集します。
期間は10月25日頃から約3週間です。
朝夕各1頭のエゾ鹿の回収が業務です。
エゾ鹿は100~150kg程度です。
見返りは1日1回エゾ鹿猟のチャンスを無償で与えます。
これは有料で参加するとしたら約30万円分の実習費に相当します。
回収人の捕獲したエゾ鹿肉は回収人所有となり、自由に使えます。
トップクラスのエゾ鹿猟ガイドの3週間見学はプライスレスとも言えます。
これで講師のエゾ鹿猟ガイドを3週間見学し、また実戦を勉強して腕を磨き、エゾ鹿の生態をよく研究し、将来プロを目指そうとするならば、またと無いチャンスかと思います。
回収人の負担は旭川空港までの交通費、飲食費、です。
空港送迎と宿泊費はこちら持ち、銃所持は申請中でもOKです。
銃の撃ち方やハンターとしての心構え等は教えます。
その他にもギブ&テイク体制が取れれば、更に援助出来る項目があるかも知れません。
またそれほど遠くない将来には講師もスクールを卒業する事になりますから、講師に換わってスクールの運営を引き受けて頂く事も可能です。
またエゾ鹿は今も自然増殖分を獲り切れておらず、エゾ鹿対策は必然的に長期戦に及び、地元駆除ハンターは現在でもかなり高齢者ですから、やがては移住ハンターが駆除の主体となる日はそれほど遠くなく、腕を磨いておけばエゾ鹿猟で生計を立てられる日が必ず来ると思います。現状でも腕の良い駆除ハンターは500~1000万円の年収です。
またヒグマの狩猟期間も2週間程度ダブっており、こちらは通常スクールの対象外、必要な技術があると認められれば、こちらのチャンスは上記とはまた別に与えられます。
但しこちらの場合は捕獲したヒグマは共有物となります。
ベストシーズン2週間でヒグマのチャンスが毎年1~2回以上必ずあります。
必要な射撃技術取得が出来ていれば、そして回収係を3年もやれば必然的にヒグマ捕獲となると思います。

写真のヒグマは全て講師の捕獲ですが、その捕獲にはNO.4以外は多くの生徒等が立会う事が出来ました。

エゾ鹿の超大物にも平均的で言えば3週間分の回収人の無償チャンスで1度はあると思いますが、見学中の出会いはその4~5倍あると思います。3週間の回収人チャンスは超大物捕獲も最短コースだと思います。
そこでスクールはエゾ鹿の回収人を募集します。
期間は10月25日頃から約3週間です。
朝夕各1頭のエゾ鹿の回収が業務です。
エゾ鹿は100~150kg程度です。
見返りは1日1回エゾ鹿猟のチャンスを無償で与えます。
これは有料で参加するとしたら約30万円分の実習費に相当します。
回収人の捕獲したエゾ鹿肉は回収人所有となり、自由に使えます。
トップクラスのエゾ鹿猟ガイドの3週間見学はプライスレスとも言えます。
これで講師のエゾ鹿猟ガイドを3週間見学し、また実戦を勉強して腕を磨き、エゾ鹿の生態をよく研究し、将来プロを目指そうとするならば、またと無いチャンスかと思います。
回収人の負担は旭川空港までの交通費、飲食費、です。
空港送迎と宿泊費はこちら持ち、銃所持は申請中でもOKです。
銃の撃ち方やハンターとしての心構え等は教えます。
その他にもギブ&テイク体制が取れれば、更に援助出来る項目があるかも知れません。
またそれほど遠くない将来には講師もスクールを卒業する事になりますから、講師に換わってスクールの運営を引き受けて頂く事も可能です。
またエゾ鹿は今も自然増殖分を獲り切れておらず、エゾ鹿対策は必然的に長期戦に及び、地元駆除ハンターは現在でもかなり高齢者ですから、やがては移住ハンターが駆除の主体となる日はそれほど遠くなく、腕を磨いておけばエゾ鹿猟で生計を立てられる日が必ず来ると思います。現状でも腕の良い駆除ハンターは500~1000万円の年収です。
またヒグマの狩猟期間も2週間程度ダブっており、こちらは通常スクールの対象外、必要な技術があると認められれば、こちらのチャンスは上記とはまた別に与えられます。
但しこちらの場合は捕獲したヒグマは共有物となります。
ベストシーズン2週間でヒグマのチャンスが毎年1~2回以上必ずあります。
必要な射撃技術取得が出来ていれば、そして回収係を3年もやれば必然的にヒグマ捕獲となると思います。
写真のヒグマは全て講師の捕獲ですが、その捕獲にはNO.4以外は多くの生徒等が立会う事が出来ました。

エゾ鹿の超大物にも平均的で言えば3週間分の回収人の無償チャンスで1度はあると思いますが、見学中の出会いはその4~5倍あると思います。3週間の回収人チャンスは超大物捕獲も最短コースだと思います。
2015年11月01日
6頭目のヒグマ捕獲。
11月1日:AM8時過ぎ、紋別郡山中の林道でヒグマ捕獲に成功しました。ヒグマとは鹿猟中の林道上で遭遇、しばらくは林道上でカーチェイス、やがて右手の上り坂の林の中に逃げ込みました。

体長170cm、体重220kg、脂の良く乗った美味しそうな若いメス。
全体にこげ茶色、頭に近くなるにつれて金毛の珍しい月の輪ヒグマです。
ヒグマは未熟な生徒に撃たす訳には行きません。筆者はすぐその場所に車を急行、車から降りてこれを追跡、物陰からの反撃に注意しながら100m程を急ぎの忍び足で進むと、150m先の木々の間を静かに歩くヒグマを発見、近くの立木を使ったウォーキングの依託固定待射撃を決断、結果は両ショルダーを撃ち抜き、ヒグマはその場でダウン、30秒程で大人しくなりました。
ヒグマは体長(鼻先から尻尾の付け根まで)170cm、推定体重は220kg、良く脂の乗った若いメスの月の輪ヒグマでした。月の輪付は初めてです。
筆者はこれで6頭目のヒグマとなりましたが、おかげ様で半矢未回収はゼロです。
翌日には早々にR生徒とヒグマのスペアリブと心臓のステーキパーティーです。ヒグマはどの様な味がするのか、鹿は牛に近いとか言えますが、熊は熊の味がするとしか言えません。では美味しいのか? 良い個体であれば保証付で抜群に美味しいのです。



こう言う写真を獲る事が出来たのはスクール生徒累計100人以上の中の3人だけです。
(2015年R生徒、2007年愛知H生徒、2006年神奈川D生徒) その写真はヒグマ捕獲
立会者だけが参加できるステーキパーティーと共に一生の思い出になる事でしょう。
ヒグマの狩猟期間は11月中旬には冬眠してしまいますから、実質2週間強しかありません。
近年の出会い実績からすればこの時期に1週間実戦を行なえば、チラ見的以上の出会いは可能です。本年もこの捕獲の前日に筆者は近くの林道で捕獲したのとは別のヒグマに出会いました。こちらも十分射撃可能でしたが、時間外でしたので見送りました。
射撃方法としては普通の鹿撃ち的な射撃では殆ど撃てません。ヒグマは鹿と違って立ち止まらないからです。出会いは殆どが50m以内、スナップショットやランニングショットを充分マスターした上でお越し下されば捕獲の可能性は十分あります。
ヒグマ狙いのハンターはそう言う特種射撃を充分練習した上でぜひお越し下さい。
体長170cm、体重220kg、脂の良く乗った美味しそうな若いメス。
全体にこげ茶色、頭に近くなるにつれて金毛の珍しい月の輪ヒグマです。
ヒグマは未熟な生徒に撃たす訳には行きません。筆者はすぐその場所に車を急行、車から降りてこれを追跡、物陰からの反撃に注意しながら100m程を急ぎの忍び足で進むと、150m先の木々の間を静かに歩くヒグマを発見、近くの立木を使ったウォーキングの依託固定待射撃を決断、結果は両ショルダーを撃ち抜き、ヒグマはその場でダウン、30秒程で大人しくなりました。
ヒグマは体長(鼻先から尻尾の付け根まで)170cm、推定体重は220kg、良く脂の乗った若いメスの月の輪ヒグマでした。月の輪付は初めてです。
筆者はこれで6頭目のヒグマとなりましたが、おかげ様で半矢未回収はゼロです。
翌日には早々にR生徒とヒグマのスペアリブと心臓のステーキパーティーです。ヒグマはどの様な味がするのか、鹿は牛に近いとか言えますが、熊は熊の味がするとしか言えません。では美味しいのか? 良い個体であれば保証付で抜群に美味しいのです。


こう言う写真を獲る事が出来たのはスクール生徒累計100人以上の中の3人だけです。
(2015年R生徒、2007年愛知H生徒、2006年神奈川D生徒) その写真はヒグマ捕獲
立会者だけが参加できるステーキパーティーと共に一生の思い出になる事でしょう。
ヒグマの狩猟期間は11月中旬には冬眠してしまいますから、実質2週間強しかありません。
近年の出会い実績からすればこの時期に1週間実戦を行なえば、チラ見的以上の出会いは可能です。本年もこの捕獲の前日に筆者は近くの林道で捕獲したのとは別のヒグマに出会いました。こちらも十分射撃可能でしたが、時間外でしたので見送りました。
射撃方法としては普通の鹿撃ち的な射撃では殆ど撃てません。ヒグマは鹿と違って立ち止まらないからです。出会いは殆どが50m以内、スナップショットやランニングショットを充分マスターした上でお越し下されば捕獲の可能性は十分あります。
ヒグマ狙いのハンターはそう言う特種射撃を充分練習した上でぜひお越し下さい。
2015年09月26日
オホーツクの鮭釣と知床のヒグマと大物エゾ鹿
先日の鮭釣は余り良い結果ではありませんでしたので、爆釣のメッカ、小清水止別川に行って来ました。駐車場には軽く200台、良いポイントには1mに1人以上です。その近くも2mに1人、これでは拙者の入れる余地はありません。
釣れる量も半端でなく、たくさん持っている人に聞いたところ、本日は18匹だったが数日前には38匹を記録したとの事でした。


1mに1人以上の超ラッシュ、少し離れた3人は誰かが釣れるとそこに入ろうと順番待ち。
そこでもう少しウトロ方面に適当な漁港を見付けました。ここは釣り新聞には出ていません。
駐車場には100台近くありましたが、ポイントが広く4mに1人程でした。
拙者の周辺には約20人、釣果は0~10匹ですが、過半はゼロ匹でした。拙者も金曜日のPMはゼロ匹組、土曜日は暗い内から良い場所を確保、おかげ様で3匹となりました。
隣のベテランは同じ時間に8匹を釣りましたのですからやはり腕の差が第1原因かもです。
釣れたのはギンピカメス1匹、チョイブナオス1匹、中ブナオス1匹でした。
チョイブナオスは浮きルアー、他は浮き餌で釣りました。餌はカツオとあかイカです。


73cm、ギンピカのメス。右は私の釣果ではありませんが、ここではかなり綺麗な鮭です。
久しぶりに知床に行って来ました。そしてヒグマ5頭に出会いました。メスや子供のエゾ鹿にもたくさん会いました。今は夏毛から冬毛に変わる頃、角はまだ皮膚が付いているのが普通ですが、知床で出会った大物オスはすでに冬毛に変わり、そして角も剥けていました。


角長70cm程度の大物蝦夷鹿と中型ヒグマ 共に距離50m、乱場なら1発で戴きです。


写真左:林道上100mで見たヒグマ、逃げ足が速かった。
写真右:森の中の100m先をゆっくり歩いて行ったヒグマ。
本年は紋別スクールでもヒグマ出会いの期待が持てそうです。
釣れる量も半端でなく、たくさん持っている人に聞いたところ、本日は18匹だったが数日前には38匹を記録したとの事でした。
1mに1人以上の超ラッシュ、少し離れた3人は誰かが釣れるとそこに入ろうと順番待ち。
そこでもう少しウトロ方面に適当な漁港を見付けました。ここは釣り新聞には出ていません。
駐車場には100台近くありましたが、ポイントが広く4mに1人程でした。
拙者の周辺には約20人、釣果は0~10匹ですが、過半はゼロ匹でした。拙者も金曜日のPMはゼロ匹組、土曜日は暗い内から良い場所を確保、おかげ様で3匹となりました。
隣のベテランは同じ時間に8匹を釣りましたのですからやはり腕の差が第1原因かもです。
釣れたのはギンピカメス1匹、チョイブナオス1匹、中ブナオス1匹でした。
チョイブナオスは浮きルアー、他は浮き餌で釣りました。餌はカツオとあかイカです。
73cm、ギンピカのメス。右は私の釣果ではありませんが、ここではかなり綺麗な鮭です。
久しぶりに知床に行って来ました。そしてヒグマ5頭に出会いました。メスや子供のエゾ鹿にもたくさん会いました。今は夏毛から冬毛に変わる頃、角はまだ皮膚が付いているのが普通ですが、知床で出会った大物オスはすでに冬毛に変わり、そして角も剥けていました。
角長70cm程度の大物蝦夷鹿と中型ヒグマ 共に距離50m、乱場なら1発で戴きです。
写真左:林道上100mで見たヒグマ、逃げ足が速かった。
写真右:森の中の100m先をゆっくり歩いて行ったヒグマ。
本年は紋別スクールでもヒグマ出会いの期待が持てそうです。
2015年04月21日
ヒグマトロフィー
ヒグマトロフィーが出来上がりました。2014年紋別解禁猟の在りし日を思い出します。

ヒグマNO.4、体長185cm、体重280kg、20m弱で立ち上がった所を射撃。
心臓狙いです。ヒグマは直ちに倒れ始め、5m先で動かなくなりました。
頭蓋骨を見ますとほぼ全域に癒着が進んでおり、かなりの高齢熊であった様です。

ヒグマNO.5、体長220cm、体重400kg以上、後方100mから走行中を射撃。
狙い目は骨盤です。僅かにずれ左大腿骨上部を粉砕し、内臓まで弾は達していました。
50m走り、そこから30m下の谷川で絶命していました。
鉛弾であれば大腿骨粉砕で鉛の全量飛び散り、内部まで弾が届かず、半矢未回収に
なったと思われます。銅弾のおかげで捕獲出来ました。
こちらはバカデカくてもその割に若いヒグマであり、外観だけでは分からない物ですね。
足跡の写真は実物サイズに調整してあります。
ヒグマ猟は如何ですか? ヒグマの猟期は最初の積雪(10月下旬)から2週間程度で冬眠に
入りますから、その2周間だけとなります。
捕獲はエゾ鹿に比べて数百倍難しくなりますが、ヒグマは近年増えており、出会うだけならば
この12年で12回出会ってますから2週間で会える計算になります。
ヒグマは普通の撃ち方では捕獲成功確率は相当低くなりますが、スナップショットとランニング
射撃が出来ればそれほど絶望的ではありません。
ヒグマNO.4、体長185cm、体重280kg、20m弱で立ち上がった所を射撃。
心臓狙いです。ヒグマは直ちに倒れ始め、5m先で動かなくなりました。
頭蓋骨を見ますとほぼ全域に癒着が進んでおり、かなりの高齢熊であった様です。
ヒグマNO.5、体長220cm、体重400kg以上、後方100mから走行中を射撃。
狙い目は骨盤です。僅かにずれ左大腿骨上部を粉砕し、内臓まで弾は達していました。
50m走り、そこから30m下の谷川で絶命していました。
鉛弾であれば大腿骨粉砕で鉛の全量飛び散り、内部まで弾が届かず、半矢未回収に
なったと思われます。銅弾のおかげで捕獲出来ました。
こちらはバカデカくてもその割に若いヒグマであり、外観だけでは分からない物ですね。
足跡の写真は実物サイズに調整してあります。
ヒグマ猟は如何ですか? ヒグマの猟期は最初の積雪(10月下旬)から2週間程度で冬眠に
入りますから、その2周間だけとなります。
捕獲はエゾ鹿に比べて数百倍難しくなりますが、ヒグマは近年増えており、出会うだけならば
この12年で12回出会ってますから2週間で会える計算になります。
ヒグマは普通の撃ち方では捕獲成功確率は相当低くなりますが、スナップショットとランニング
射撃が出来ればそれほど絶望的ではありません。
2014年12月25日
ヒグマのポイント猟
実はヒグマと言うのは普通のハンターに取って出会いが可能な時期はかなり短期間に限られ、捕獲(出会い)の難易度は想像以上にかなり高度な物となります。
筆者が捕獲したのも早い方から言って、10/27、10/29、10/31、11/2、11/9、の5頭ですから2週間弱で全てを捕獲しています。 1番遅い11/9を除外すると僅か1週間に集中していると言えます。
ヒグマ猟は10月1日から可能となりますが、それだけでは出会いが少な過ぎて成立が難しい状態です。この頃は主力のエゾ鹿の繁殖期も始まらずまだ鹿が活性化しておりません。
エゾ鹿猟が活気付くのは10月28日前後からです。その頃からエゾ鹿猟の傍らでヒグマ猟も始まりますが、残念ながら僅か2週間強の11月中旬からは長い冬眠に入ってしまいます。
こう言った状況下ですから狩猟で捕獲されるヒグマの数は僅か80頭程度、一方駆除を含めますと6倍程の年間で500頭前後が捕獲(過半は罠による)されています。
ヒグマは狩猟シーズン外の駆除による捕獲以外に数が稼げないと言っても過言ではありません。つまり一般的に言えば地元に住んでいなければ無理と言う事になります。
久保俊治と言うヒグマ撃ちの著書も出している1947年生まれのヒグマプロハンターが先頃テレビでも取り上げられ話題になりました。
彼は40年余を掛けて70頭余のヒグマを捕獲したそうですが、筆者はやっと5頭ですからエライ違いです。しかし地元に住んで駆除の捕獲で数倍に増えても、それでも1年に2頭に満たない、これもヒグマ猟の現実なのです。
伝説のヒグマプロ猟師には100頭超えの人も相当数いたそうですが、それでも年に3頭程度です。
そう言う状況下で筆者は過去2度も短い狩猟シーズン(実質1~2週間)に2頭の捕獲を記録出来ました。5回には程遠く、まだまだマグレの領域かと思いますが、これを発展させれば将来ヒグマのポイント猟が可能になるのかも知れません。
取りあえず、スクールでは有料ですが、来シーズンから筆者の支援状態が十分な時に限り、上級生徒にも撃ってもらう事にしました。
我と思わん人はスナップショットとウォーキングショットを練習の上、ぜひチャレンジして下さい。


左:久保氏ののヒグマ撃ち、前半はそれなりに迫力ありますが、
後半は亡くした猟犬のロリコン物語です。
右:筆者がその内に出そうと思っている書で、エゾ鹿猟の実戦ガイドです。
楽しみにしていて下さい。
筆者が捕獲したのも早い方から言って、10/27、10/29、10/31、11/2、11/9、の5頭ですから2週間弱で全てを捕獲しています。 1番遅い11/9を除外すると僅か1週間に集中していると言えます。
ヒグマ猟は10月1日から可能となりますが、それだけでは出会いが少な過ぎて成立が難しい状態です。この頃は主力のエゾ鹿の繁殖期も始まらずまだ鹿が活性化しておりません。
エゾ鹿猟が活気付くのは10月28日前後からです。その頃からエゾ鹿猟の傍らでヒグマ猟も始まりますが、残念ながら僅か2週間強の11月中旬からは長い冬眠に入ってしまいます。
こう言った状況下ですから狩猟で捕獲されるヒグマの数は僅か80頭程度、一方駆除を含めますと6倍程の年間で500頭前後が捕獲(過半は罠による)されています。
ヒグマは狩猟シーズン外の駆除による捕獲以外に数が稼げないと言っても過言ではありません。つまり一般的に言えば地元に住んでいなければ無理と言う事になります。
久保俊治と言うヒグマ撃ちの著書も出している1947年生まれのヒグマプロハンターが先頃テレビでも取り上げられ話題になりました。
彼は40年余を掛けて70頭余のヒグマを捕獲したそうですが、筆者はやっと5頭ですからエライ違いです。しかし地元に住んで駆除の捕獲で数倍に増えても、それでも1年に2頭に満たない、これもヒグマ猟の現実なのです。
伝説のヒグマプロ猟師には100頭超えの人も相当数いたそうですが、それでも年に3頭程度です。
そう言う状況下で筆者は過去2度も短い狩猟シーズン(実質1~2週間)に2頭の捕獲を記録出来ました。5回には程遠く、まだまだマグレの領域かと思いますが、これを発展させれば将来ヒグマのポイント猟が可能になるのかも知れません。
取りあえず、スクールでは有料ですが、来シーズンから筆者の支援状態が十分な時に限り、上級生徒にも撃ってもらう事にしました。
我と思わん人はスナップショットとウォーキングショットを練習の上、ぜひチャレンジして下さい。


左:久保氏ののヒグマ撃ち、前半はそれなりに迫力ありますが、
後半は亡くした猟犬のロリコン物語です。
右:筆者がその内に出そうと思っている書で、エゾ鹿猟の実戦ガイドです。
楽しみにしていて下さい。
2014年11月21日
エースと言う称号。
飛行機を5機撃墜するとエースと言う称号がもらえます。
永年やっていれば1~2機はまぐれやラッキーショットで撃墜できる事もありますが、5機はまぐれでなく実力だと認めてもらえる合格ラインの様な物でもあります。
狩猟の世界でもその様な難しさがあり、かつては5頭撃墜は高嶺の花でした。
しかし、鹿や猪が増え過ぎ、その称号的な価値も今では大幅に下がっていますが、ヒグマに関してはまだ価値がそんなに下がっていないと思っています。
そのヒグマ捕獲のエースが本年11月9日に達成されました。
20歳で狩猟を始めてから45年、大物猟を始めてからでも33年程掛かりました。
これを達成したからと言って、特に儲かる訳でも勲章をもらえる訳でも何でもありません。
何と言うか「男の拘り」程度のバカなアホらしい物ですが、拙者には大きな大きな目標達成です。
20mのド至近距離で対峙した時、そして本物サイズのビッグなヒグマに対しても、臆する事無く、速やかに射撃出来、そして命中した事は非常に嬉しく思っています。
誰か、若い人にこの技術の1部でも伝え残す事が出来れば幸いに思っております。
我と思わん方はスクールにぜひ参加して下さい。

おかげ様でヒグマ撃墜のエースになれました。
永年やっていれば1~2機はまぐれやラッキーショットで撃墜できる事もありますが、5機はまぐれでなく実力だと認めてもらえる合格ラインの様な物でもあります。
狩猟の世界でもその様な難しさがあり、かつては5頭撃墜は高嶺の花でした。
しかし、鹿や猪が増え過ぎ、その称号的な価値も今では大幅に下がっていますが、ヒグマに関してはまだ価値がそんなに下がっていないと思っています。
そのヒグマ捕獲のエースが本年11月9日に達成されました。
20歳で狩猟を始めてから45年、大物猟を始めてからでも33年程掛かりました。
これを達成したからと言って、特に儲かる訳でも勲章をもらえる訳でも何でもありません。
何と言うか「男の拘り」程度のバカなアホらしい物ですが、拙者には大きな大きな目標達成です。
20mのド至近距離で対峙した時、そして本物サイズのビッグなヒグマに対しても、臆する事無く、速やかに射撃出来、そして命中した事は非常に嬉しく思っています。
誰か、若い人にこの技術の1部でも伝え残す事が出来れば幸いに思っております。
我と思わん方はスクールにぜひ参加して下さい。

おかげ様でヒグマ撃墜のエースになれました。
2014年11月09日
2014年度解禁猟 第4期 講師 ビッグサイズ ヒグマ捕獲。
11月9日:生徒の居ない時には凄い事が起こる物です。特大のヒグマ捕獲。
本日もそんな日でした。鹿としましては朝と夕方にそれぞれエゾ鹿が1頭ずつ、特に大物でも無く、普通の鹿で特別な事はありません。
しかし、体長220cmと従来にない程のデカイヒグマを捕獲しました。
走るヒグマでしたが逃避方向は余りオフセットは無くスナップショット100mで撃ちました。
割と大きなヒグマで黒っぽい色でした。
1度倒れ、倒れている内に止め矢と思っていたのですが逃げ足の速い熊でした。
クマザサ方向に逃げ、且つデカかったので、単独追跡は控え、旭川から応援を呼びました。
2時間後、応援が到着、追跡しますと80mほど走って谷川に顔を突っ込んで倒れていました。

体長220cm、体重は推定で300kg以上でした。


体長220cm、体重は300kg以上と思われます。
煙草のサイズは約5.5cmと約9cmです。
他には特に特筆事項も無く、3日で73cmを1頭の他に6頭の小物に終わりました。
本日もそんな日でした。鹿としましては朝と夕方にそれぞれエゾ鹿が1頭ずつ、特に大物でも無く、普通の鹿で特別な事はありません。
しかし、体長220cmと従来にない程のデカイヒグマを捕獲しました。
走るヒグマでしたが逃避方向は余りオフセットは無くスナップショット100mで撃ちました。
割と大きなヒグマで黒っぽい色でした。
1度倒れ、倒れている内に止め矢と思っていたのですが逃げ足の速い熊でした。
クマザサ方向に逃げ、且つデカかったので、単独追跡は控え、旭川から応援を呼びました。
2時間後、応援が到着、追跡しますと80mほど走って谷川に顔を突っ込んで倒れていました。
体長220cm、体重は推定で300kg以上でした。
体長220cm、体重は300kg以上と思われます。
煙草のサイズは約5.5cmと約9cmです。
他には特に特筆事項も無く、3日で73cmを1頭の他に6頭の小物に終わりました。
2014年10月26日
2014年度解禁猟 第1期 講師 ラージサイズ ヒグマ捕獲
10月26日PM:猟場到着です。
超快晴& Tシャツ気温の25度弱、鹿撃ちの気温ではありません。
しかし大雪山は上半分が数日前の寒波で真っ白ですが、我々の必要とする近くの山の積雪はまだゼロ、今秋火曜日の寒波に期待と言った所です。
本年度の紅葉は2週間ほど早く、先日は旭川でも0度を観測、と思ったらとんでもない夏日、全く訳が分かりません。明らかに地球が狂い始めていると思います。
さてこんな日ですから夕方に鹿との好出会いは期待する方が無理と言う物です。
日没後10分設楽若オスが出て来ました。30分を過ぎたら70cm級も出て来ましたが、時間内の出会いはゼロでした。
明日の朝も様子を見て見ますが、基本的には火曜日の低気圧を待たなくてはなりません。
そうそうハンティングベースは近くの民宿に移りました。
従来と同じ雑魚寝ですが無料です。
10月27日:75cmとヒグマ獲れました。
朝1は75cm捕獲。幸先イイです。

ヒグマは体長185cm、今までで1番デカイです。黒っぽい年齢不詳のメス、丸々太って250kg以上?
14時頃、旧ベースより5kmくらい上の国道を横切るのを100mから発見しました。幸いにもそこは空き地があります。急いでそこに乗り付けました。ブッシュがあって射撃し難かったので少しでも高い所からが良いと判断、車のスッテプ上からの射撃にしました。
もうすでの50m以上逃げたと思い、その方向を見ますが逃げた方向のクマザサも動いていません。何とヒグマは20m地点に潜んでいたのです。こちらからも見えなかったのですが、ヒグマからもこちらが見えないらしく立ちあがってくれました。
まだ薄いブッシュがありましたが、ド迫力の20mからスナップ射撃、幸いにもブッシュに喰われる事なく弾は心臓付近に命中、背ロースを突き抜け皮の手前で停弾(解体して分かりました)、5m走ってダウンしてくれました。
夢の中ではド至近距離のヒグマに対する対戦は何度もしましたが、何時も成果は今一、「あ~、う~」で結果は定かでなく、目覚めてしまいました。
今回、パッタリではなくやや残念ですが、念願のド至近距離の立ちあがったヒグマに対して、概ね完ぺきな対応が出来て、満足しています。

10月28日:ブリザード、捕獲はゼロでした。
朝1、町外れで75cm級のNO.2に出会いましたが、バックストップの無い上向き射撃、見送りとなりました。
夕方、メス2頭が居ましたが、ブレーキランプが点灯した瞬間に全力ダッシュ、どちらも難しい対潜相手ですが、多分明日からはイージーチャンスも頂けるのではないかと思います。
10月29日:本日もまさかのブリザード、ピン角捕獲。
まさかのブリザードで上部林道は積雪50cm、しかし暖かいのでどんどん溶けています。
これで鹿があすから動くだろうと思います。
何時もの牧場にカニ角は居ましたが、R生徒にとっておく事にしました。
又上部林道からは80cm級が飛び出しましたが残念ががら射撃には結び付きませんでした。
明日PMからのR生徒の第2期5.5日は抜群になるかもです。
10月30日:予想に反して、何コレ的に出会いが少ない日となりました。
AMは筆者が自家用肉の為のメスを1頭捕獲、PMはR生徒が150mで70cm級に出会いましたが、十分な時間を頂けず発砲に至りませんでした。
超快晴& Tシャツ気温の25度弱、鹿撃ちの気温ではありません。
しかし大雪山は上半分が数日前の寒波で真っ白ですが、我々の必要とする近くの山の積雪はまだゼロ、今秋火曜日の寒波に期待と言った所です。
本年度の紅葉は2週間ほど早く、先日は旭川でも0度を観測、と思ったらとんでもない夏日、全く訳が分かりません。明らかに地球が狂い始めていると思います。
さてこんな日ですから夕方に鹿との好出会いは期待する方が無理と言う物です。
日没後10分設楽若オスが出て来ました。30分を過ぎたら70cm級も出て来ましたが、時間内の出会いはゼロでした。
明日の朝も様子を見て見ますが、基本的には火曜日の低気圧を待たなくてはなりません。
そうそうハンティングベースは近くの民宿に移りました。
従来と同じ雑魚寝ですが無料です。
10月27日:75cmとヒグマ獲れました。
朝1は75cm捕獲。幸先イイです。
ヒグマは体長185cm、今までで1番デカイです。黒っぽい年齢不詳のメス、丸々太って250kg以上?
14時頃、旧ベースより5kmくらい上の国道を横切るのを100mから発見しました。幸いにもそこは空き地があります。急いでそこに乗り付けました。ブッシュがあって射撃し難かったので少しでも高い所からが良いと判断、車のスッテプ上からの射撃にしました。
もうすでの50m以上逃げたと思い、その方向を見ますが逃げた方向のクマザサも動いていません。何とヒグマは20m地点に潜んでいたのです。こちらからも見えなかったのですが、ヒグマからもこちらが見えないらしく立ちあがってくれました。
まだ薄いブッシュがありましたが、ド迫力の20mからスナップ射撃、幸いにもブッシュに喰われる事なく弾は心臓付近に命中、背ロースを突き抜け皮の手前で停弾(解体して分かりました)、5m走ってダウンしてくれました。
夢の中ではド至近距離のヒグマに対する対戦は何度もしましたが、何時も成果は今一、「あ~、う~」で結果は定かでなく、目覚めてしまいました。
今回、パッタリではなくやや残念ですが、念願のド至近距離の立ちあがったヒグマに対して、概ね完ぺきな対応が出来て、満足しています。
10月28日:ブリザード、捕獲はゼロでした。
朝1、町外れで75cm級のNO.2に出会いましたが、バックストップの無い上向き射撃、見送りとなりました。
夕方、メス2頭が居ましたが、ブレーキランプが点灯した瞬間に全力ダッシュ、どちらも難しい対潜相手ですが、多分明日からはイージーチャンスも頂けるのではないかと思います。
10月29日:本日もまさかのブリザード、ピン角捕獲。
まさかのブリザードで上部林道は積雪50cm、しかし暖かいのでどんどん溶けています。
これで鹿があすから動くだろうと思います。
何時もの牧場にカニ角は居ましたが、R生徒にとっておく事にしました。
又上部林道からは80cm級が飛び出しましたが残念ががら射撃には結び付きませんでした。
明日PMからのR生徒の第2期5.5日は抜群になるかもです。
10月30日:予想に反して、何コレ的に出会いが少ない日となりました。
AMは筆者が自家用肉の為のメスを1頭捕獲、PMはR生徒が150mで70cm級に出会いましたが、十分な時間を頂けず発砲に至りませんでした。