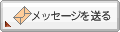2024年05月23日
久保俊治氏 死去。
久保俊治(としはる):1947年北海道小樽市生まれ。2024.4.10.心不全の為76才で死去されたそうです。
日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育ち、20歳の時に狩猟免許を取得、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始しました。
1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後現地プロ(アシスタント)ハンティングガイドになり、1976年帰国、標津町で牧場を経営しながら、単独で山に入りハンティングを行なっていました。
ヒグマに悟られない様に自然の一部と化して歩を進め、5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃す事を信条としていたハンターでした。

1.どの様にして五感能力が桁違いのヒグマに10mまで接近するのか?
永い間ケンさんにもその手法は分かりませんでした。
分からなかったからこそ、それを凄いと思い、また尊敬していました。
久保氏はプロハンターを目指し、若くして名犬フチと出会いました。フチは稀に見る天才犬と言えました。しかし以後は猟犬に頼り切った普通のダメハンターになってしまいました。
彼の著書「羆撃ち」は確かの素晴らしい物がありましたが、それは彼が主役ではなく、「名犬フチ」の物語でした。
しかし猟犬の寿命は短く、著書の後半は「愛犬ロリコン物語」でした。彼はヒグマ猟その物が分かっていた訳でもなく、猟犬の育て方が分かっていた訳でもありませんでした。
2代目以降の名犬を育て「名人芸」を持続させたなら、彼は名人と言えました。
フチの2代目誕生を試みましたが、全く上手く行かずそこで早々と完全に諦めてしまいました。
「フチは名犬」でしたが、「久保氏は名人では無かった」のです。

彼の愛銃は「サコ―フィンベア338ウインチェスターマグナム)でした。
このサコ―を入手した時期の久保氏は狩猟方法がまだ定まっていなかったと思われます。
彼の信条である10m射撃ではスコープ後付銃はスコープと眼の位置が定まらず、大幅不利になりました。スコープ専用銃ならスナップショットで急所を捉える事は可能ですが、そのスコープ専用銃は20年後の1990年頃にデビューしました。
ライフル銃は本来100m以遠を高精度で撃つ銃であり、彼もその目的でスコープ銃を選択したと思われます。ストックと銃の機関部や銃身のベディングと言う絶妙な取付け調整や、引金切れ味追及の為のシアチューニングをしていました。
これらは高精度射撃を目的でなければ、殆ど無意味と言える行為でした。
そもそも10mでヒグマを確実に仕留めるのであれば、スコープ付ライフル銃がベストではありません。
ヒグマ猟も意識し、それで338ウインマグと言う口径を選んだ様ですが、ライフルの鉛弾頭は近距離射撃やブッシュ越射撃が不得意と言うより、鉛弾頭には重大な欠陥がありました。
近距離射撃・僅かなブッシュ越・骨ヒットで鉛が飛散してしまい、以後威力を失う大欠陥がありました。鉛弾の欠陥を少なくするには下記の様に2つの方法がありました。
1つ目はA型セパレータ付の弾頭で先端部は全飛散しても後半部がそのまま残る弾頭であり、2つ目は重量弾頭で弾速を落とし、更にラウンドノーズで飛散率を低減させる方法です。
彼は近距離時の鉛弾の重大な欠陥には全く触れていませんから、それを知らなかったと思われます。10mのヒグマ対戦には無垢のブレネッキスラグ弾がベストであると思います。
弾速からこの弾頭は鉛の飛散が余り起こらず、確実にヒグマを倒してくれます。また薄いブッシュであれば通過可能です。また近距離ヒグマ勝負を行う場合は、咄嗟の場合に銃を速やかに構える能力が不可欠になる筈ですが、彼の銃はスコープ後付け銃であり、眼の位置がスコープに合わず、これには不向きでした。
これが1990年頃から普及したスコープ専用銃や、また2000年頃から法律で決められた銅弾頭であれば、話が全く変わります。
スコープ専用銃はケンさん考案の新しい銃で指向するスナップ射撃が可能となり、肩に着ける前に命中する発砲が可能となり、スナップショットは得意項目になりました。
また銅弾頭は鉛の飛散が全く怒らず、これを利用して積極的に「骨の急所を撃つ事が可能」となりました。
久保氏は猟犬を使った猟を諦め、ドッグレスで山を歩き廻る様になり、やがて至近距離からヒグマ 勝負を挑む様になりました。
銃の世界も1980年頃になりますと、スコープ専用銃が出始めていました。
銃のパフォーマンスを上げ様と日々の工夫があれば、新しい猟具や技術に興味が行く筈ですが、彼はそうなりませんでした。そう言う方面に関心が薄いのが猟犬を使うハンターの特徴と言えました。
彼より3歳若いケンさんはドッグレス猟であり、1985年頃にはショットガンもライフルも独自のスナップ ショットを完成し、スコープ専用銃「ルガー77ボルトライフル」もデビュー後の程なくして購入しました。
鹿猟犬を頼った猟をする久保氏は猟具に関心が薄く、狩猟の道具も1975年頃から、銃もナイフも全く進化せず、若い頃のスコープ後付銃のサコ―フィンベアをそのままの形でずっと使い続けました。
ナイフで申すなら炭素鋼のナイフから進化せずでした。ケンさんのナイフは炭素鋼→ステンレス鋼→ダマスカス鋼と進化し、画期的と言える程に進化しました。
炭素鋼では鹿1頭目の後半から切れ味が大幅低下しました。
ステンレス鋼になりますと、メス2頭目までは良いのですが、3頭目で切れ味が低下しました。
それがダマスカス鋼になりますと、メス20頭を研がずに解体出来ました。
久保氏が掴んだヒグマとの接触方法の極意は、多分結果オーライの形で得られたのではないかと思います。それは何時もヒグマのいる地域を歩き、ヒグマに無害の人間であると思わせたのです。
本州に住み、シーズン数十日のみの狩猟をしていたケンさんには真似の出来ない手法ですが、地元に住んでいて、特定エリア内の年間数頭以下のヒグマを捕獲するのであれば、可能な方法と言えました。50年狩猟をしていて新たに分かった事の追加です。
その延長で考えますと、ケンさんもヒグマ捕獲を目的に行動開始し、5年目の2006年に1頭目を捕獲、翌年に2頭目と3頭目を捕獲しました。そして箱罠に依るヒグマ駆除が始まりました。
それまで箱罠駆除は行われていなかったので、多くのヒグマがパタパタ掛かりまして、過半のヒグマが捕獲され、ケンさん猟場のヒグマ生息数は半分以下となりました。
そして7年目の2014年、ヒグマの生息数も回復し、4頭目と5頭目のヒグマを捕獲、エースとなりました。そして2015年6頭目のヒグマを捕獲しました。
これもヒグマ側からすれば、ケンさんの車を猟場でよく見掛ける様になり、逃げなくなったのではないかと思える部分もありました。唯ケンさんの場合は50m先を走るヒグマが多かったと言う違いはあります。
久保氏はテレビ取材時に、50mでノーマークのエゾ鹿を立ち木に半委託射撃で撃ちました。
流石に半矢で逃げ出す事は無かったのですが、驚いた事に即死ではない射撃でした。
獲物を苦しめない彼の信条からすれば、また5~10mでヒグマを確実に即死させている事からすれば、信じられない下手糞な射撃でした。
その時代ではアメリカ帰りが珍しかった事、更に独自の子育て「大草原のみゆきちゃん」の取材を通し、マスコミに有名になり、「羆撃ち}も売れました。
ヒグマ70頭を捕獲したと言う説もありますが、彼自身は捕獲数を公表しておらず、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちではそこまで行っていないと思われます。
ケンさんが若い頃には仙人の様な凄い人だと尊敬していましたが、唯の猟犬ロリコンダメハンターでした。
2.小山氏の銃のバランス。
別の話ですが、長い間ケンさんは小山氏が北海道でNO.1のガイドであると思って尊敬して来ました。それはケンさんが1頭も捕獲出来なかった90㎝以上を相当数捕獲していたからです。
その小山氏が昨今は動画を多数投稿される様になり、それで気が付いた点があります。300m遠射が多いとは言え殆どが即倒していないのです。どうしてなのかを考えてみました。
因みにケンさんの300mは殆どが即倒の即死です。

写真は小山氏の愛銃:レミントン700、カスタムバレル、口径レミントン7㎜マグナム、スコープ4~16倍ビデオ機能付、重装備です。
ハンティング動画撮影に拘りを持っておられ、ネットにも多数投稿されています。
射撃精度にもかなり拘っておられる様で、モア精度のハンドロードで7㎜レミントンマグをカスタムバレルから撃っておられ、300mなら過半が即倒だと思うのですが、即倒していないのです。
狙撃が心臓狙いもあってか、小山氏の投稿動画でも即倒が殆どありません。ケンさんが見た投稿動画10本余で、即倒は1回だけで、何時も半矢捜索で数十~数百mで死んでいました。
未回収動画を公開する事は無いと思われ、即倒率は更に低いと思われます。
そして角サイズに拘りを持っておられ、300m前後のビッグトロフィー級狙いの遠射が主体です。
小山氏とケンさんと何が違うかと言えば、口径と急所とスコープです。
ケンさんの愛銃はサコー75改バーミンターの308、スコープは安物の軽量型、使用弾は激安弾の140gr弾銅頭挿げ替え弾でした。
急所をナミビアポイントに変更してからのケンさんは、300m遠射を含む殆どを即倒に出来る様になりました。正しく急所ヒットすれば弾のパワーに関係なく、即倒します。
ケンさんのスコープに比べ小山氏のスコープシステムは重量が数倍あると思われます。全依託で手に持たないで撃つと銃が振動し、ケンさんの銃でも反動で跳ね多少弾着が上にズレます。
銃にはバランスがあり、これは静的でも動的でも大切な事だと思っています。
また後述説明の様に、スコープベースの取付け強度も心配です。
動画の安定性にも問題があり、小山氏の動画はこのスコープを通した物やヘッドカメラは良いのですが、歩いている時の映像は水平が定まっておらず、見ていると乗り物酔い症状になってしまいます。
また発射の反動で映像が消えてしまい、被弾の瞬間が写っていないのも非常に残念です。
海外の良い動画はスコープからの映像もありますが、歩いている時はジャイロ付ハンディーカメラ、捕獲時の映像は三脚に固定された別のカメラの撮影がメインです。
近年はカメラの性能が上がり、スロー再生ではライフル弾の飛行によって出来た、空間の歪が写っている事もある程になりました。
もう少し解像度とスロー再生能力が上がれば、ケンさんのスロー再生特殊能力で見えたヒットした部分の毛が立ち、それが水面の波の様に周りに向かって広がって行く過程が写ると思います。
あれは実際に見えた映像ですから、絶対に事実だと思っています。第2波や第3波が発生し、それが広がって直径30㎝で消えて行く、詳細な様子を確認したい物です。
小山氏のスコープを通した映像では、その瞬間が反動で消えてしまっており、見えません。
命中精度に関するケンさんの仮説ですが、このスコープ部分が重過ぎると全体の振動条件が大きく変わり、弾着が乱れると思います。
そのせいかどうかは分りませんが、小山氏の動画の射撃は殆ど即倒していません。狙う急所を即倒率の高いナミビアポイントに換えるべきだと思います。
肉を求めるミートハンターではなくビッグトロフィーを求めるハンターですから、前足軸線上の背骨を撃って背ロースが少しダメージを受けても関係なく、ナミビアポイントを撃つべきだと思います。
即倒は一種の芸術ですから、それが上手く獲れれば動画の価値も上がると思われます。
ケンさんもナミビアポイント実用化前は超大物多数を未回収にしてしましたが、ナミビアポイントを実用化後は殆どを即倒出来、捕獲率が5倍に急増しました。
ナミビアポイントは他の急所に比べ即倒エリアが広く、周辺ヒットでも即倒してくれます。
ケンさん自身もこのナミビアポイントで前記の様な大きな成果を上げましたが、ケンさんスクールでも急所をナミビアポイントに変更してから、生徒による超大物捕獲が可能になりました。
銃に色々を架装する事は銃の精度やスナップショットやスイング特製に変化を生じ、捕獲率の低下を招くと思っており、ケンさんはその方向になる架装をする気はありません。

 レミントンとサコー
レミントンとサコー
更にレミントンを始めとする世界中の多くの銃はスコープマウントベースが3㎜級ネジ2本で取付けられています。ケンさんも設計者の端クレですが、アレでは十分である筈が無いと思っています。

 ミロクとルガー
ミロクとルガー
サコーはレシーバーの作り付けマウントで、しかも緩みが来ない様に前が広いテーパとなっています。
ミロクでは中ネジ4本に強化されており、ルガーも絶対に緩まない様に嵌め込み式になっています。
従来版小ネジタイプの緩む率は不明ですが緩む可能性がある様です。それに対する対策が各メーカーで行われ、それが増えているのです。ケンさんは小ネジ部分タイプが緩んだ例は3件見ました。
レミントン、ウインチェスター、サベージサボットで各1件で、共に標準クラスのスコープでした。
標準負荷でも緩む可能性があるのに、その負荷を数倍にしたら緩まない筈がないと言う事になります。
小山氏が未だにマグナムに拘っている点も気になります。
彼の愛用は7㎜レミントンマグの様ですが、マグナム弾は即倒効果も遠射効果もゼロであり、アフリカの大型動物でもエゾ鹿仕様308のバーンズ140gr銅弾を遥々持参して試しましたが、500㎏クラスの大型動物でも十分と言えました。
3.銃はバーミンター、口径は308。
散弾銃では「ショットガン効果」と言うのがあり、「1粒のパワーには概ね無関係な3粒被弾で撃墜」出来ました。無関係とは言え皮下に達しなければ無効弾になります。
同様にライフルの場合も似た様な部分があり、「急所に正しくヒットすれば、パワーには概ね無関係に即倒」しました。勿論エゾ鹿でも概ね100%即倒ですから、パワーは十分と言えマグナムは不要です。
この場合も当然ですが、数十㎝深さの急所まで届く必要があります。
心臓ポイントは動脈出口付近の狭い範囲にヒットしない限り即倒しません。

ナミビアポイントは銅弾でしか適用出来ませんが、即倒エリアが広く、実用性は抜群です。
即倒に必要な最低必要パワーの幅は相当広く、十分獲れているのであれば、口径の選択をとやかく言うつもりはありませんが、精度的には7㎜マグより308の方が優れています。
7㎜レミントンマグでベンチレスト射撃大会にチャンレンジする人は皆無ですが、100mハンタークラスと300mハンタークラスに308はしばしば入賞しています。
ケンさん自身も300mは全依託射撃であれば、概ね殆どを即倒可能です。
ナミビアでは450㎏クドウを380mにて308銅弾の初弾で即倒させる事が出来ました。
弾速が速い事でマグナムは落差補正的にはやや有利で、同じ落差で308の300mが350mまで延長出来る事は事実です。
しかし遠射は基本的に弾道の安定性が決め手となり、高速弾の遠射が有利になる事も殆ど無いのです。ケンさん自身初弾命中ではありませんが、ボス決定戦の超大物を540mから2発連続で2頭とも即倒させられました。308の弾道の安定性はかなり良好と言えました。
アメリカの長距離スナイパーの300ウインマグも220grの重量弾頭を使用しており、50BMG弾(12.7×99㎜ NATO)でも650gr重量弾頭を使い、1㎞以遠の遠射で使っています。
軽量高速弾より重量弾頭の方が遠距離射撃時の弾道性能は良い様です。
また308同士でも高速な150gr弾よりも、180gr重量弾の方が300m以遠では弾速も精度も上廻ります。
またバーミンターモデルの方が射撃は安定しており、レミントン700やルガー77のハンターモデル時は弾のメーカーを変えると弾着が変わりました。
しかしサコーバーミンターは海外にも持ち出し、現地製の弾を何時も使用していますが、何処の弾も弾着は変わらず、スコープ調整は12年間1度もしていません。
願わくばですが、ケンさんの助言が届き、小山氏の射撃は何時も「即倒」となり、その瞬間が上手くビデオに記録される事を願っています。
また角長1m怪物級エゾ鹿と500㎏のヒグマが獲れるとイイなと思っています。
4.牛の様な巨大鹿&珍鹿。
余談ですが、2002年に滝上でムース級の怪物鹿に会いました。距離は800m、サイズは牛クラス、角はそれ程ではありませんが、太い2段角で角の開きが水平に近い真っ黒な個体でした。
化石の世界の大角鹿かユーラシアンムースの末裔だったかも知れません。

写真はヘラ角にならないユーラシアンムースの若鹿です。
当時は望遠カメラを持っておらず、ライフルスコープの観察で角の生えている方向はこんな感じでしたが、もっと遥かに凄い老練な個体でした。
残念ながら翌年にはいなくなりました。1998年根室別当賀地区の太平洋側でも、概ね同等の牛の様に見えるムースの様なデカい鹿を見ました。この鹿も翌年以降は寿命なのか見掛けなくなりました。


金色の鬣のキリンの様な頭の鹿を見たのは、苫小牧石油タンク基地の近く、2012年の事でした。あれから10数年が過ぎ、寿命を迎えた頃かもです。
次は2010の根室だったと思いますが、朝1番オスばかり6頭の群を300mで出会いました。
群れの1頭はかなりの大物、残りは中型に見えました。
そこで1番大きなのを撃とうとスコープに捉えましたが、片角でした。
それで隣の中型に見えるのを撃ち即倒、回収してビックリ81㎝130㎏でした。
ならばあの片角は軽く95㎝超、200㎏越だった?
片角でも撃つべきだったと思いましたが、時すでに遅しでした。
翌年その近くで、体格が群を抜いた直線計測88㎝を捕獲したと、風の便りに聞きました。直線88㎝は実角長105㎝前後となります。
紋別スクール2007年の事でした。
100%即倒急所であるナミビアポイントを2006年に開拓、生徒にも指導しました。
そして85㎝は絶対と言う大物に出会い、150m強からD生徒に撃たせましたが、ナミビアポイントの指導をコロリと忘れ心臓を撃って未回収、数日間周辺を探しましたが、見付けられずに終わりました。
D生徒はその前年も運に恵まれず(迫力負けで足が地に着かず)、90㎝近いのを未回収にしています。その数年前にもボス決定戦の4頭を全て心臓撃ちで未回収、実はそれがナミビアポイント開拓に発展しました。
彼のベスト記録は角先欠がなければ81㎝で超大物達成でしたが、欠けていた為79㎝に留まりました。D生徒は公式記録に依れば25日参加で50頭捕獲とスクールで第2位の記録ですが、残念ながら超大物は捕獲出来ずでした。
日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育ち、20歳の時に狩猟免許を取得、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始しました。
1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後現地プロ(アシスタント)ハンティングガイドになり、1976年帰国、標津町で牧場を経営しながら、単独で山に入りハンティングを行なっていました。
ヒグマに悟られない様に自然の一部と化して歩を進め、5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃す事を信条としていたハンターでした。

1.どの様にして五感能力が桁違いのヒグマに10mまで接近するのか?
永い間ケンさんにもその手法は分かりませんでした。
分からなかったからこそ、それを凄いと思い、また尊敬していました。
久保氏はプロハンターを目指し、若くして名犬フチと出会いました。フチは稀に見る天才犬と言えました。しかし以後は猟犬に頼り切った普通のダメハンターになってしまいました。
彼の著書「羆撃ち」は確かの素晴らしい物がありましたが、それは彼が主役ではなく、「名犬フチ」の物語でした。
しかし猟犬の寿命は短く、著書の後半は「愛犬ロリコン物語」でした。彼はヒグマ猟その物が分かっていた訳でもなく、猟犬の育て方が分かっていた訳でもありませんでした。
2代目以降の名犬を育て「名人芸」を持続させたなら、彼は名人と言えました。
フチの2代目誕生を試みましたが、全く上手く行かずそこで早々と完全に諦めてしまいました。
「フチは名犬」でしたが、「久保氏は名人では無かった」のです。

彼の愛銃は「サコ―フィンベア338ウインチェスターマグナム)でした。
このサコ―を入手した時期の久保氏は狩猟方法がまだ定まっていなかったと思われます。
彼の信条である10m射撃ではスコープ後付銃はスコープと眼の位置が定まらず、大幅不利になりました。スコープ専用銃ならスナップショットで急所を捉える事は可能ですが、そのスコープ専用銃は20年後の1990年頃にデビューしました。
ライフル銃は本来100m以遠を高精度で撃つ銃であり、彼もその目的でスコープ銃を選択したと思われます。ストックと銃の機関部や銃身のベディングと言う絶妙な取付け調整や、引金切れ味追及の為のシアチューニングをしていました。
これらは高精度射撃を目的でなければ、殆ど無意味と言える行為でした。
そもそも10mでヒグマを確実に仕留めるのであれば、スコープ付ライフル銃がベストではありません。
ヒグマ猟も意識し、それで338ウインマグと言う口径を選んだ様ですが、ライフルの鉛弾頭は近距離射撃やブッシュ越射撃が不得意と言うより、鉛弾頭には重大な欠陥がありました。
近距離射撃・僅かなブッシュ越・骨ヒットで鉛が飛散してしまい、以後威力を失う大欠陥がありました。鉛弾の欠陥を少なくするには下記の様に2つの方法がありました。
1つ目はA型セパレータ付の弾頭で先端部は全飛散しても後半部がそのまま残る弾頭であり、2つ目は重量弾頭で弾速を落とし、更にラウンドノーズで飛散率を低減させる方法です。
彼は近距離時の鉛弾の重大な欠陥には全く触れていませんから、それを知らなかったと思われます。10mのヒグマ対戦には無垢のブレネッキスラグ弾がベストであると思います。
弾速からこの弾頭は鉛の飛散が余り起こらず、確実にヒグマを倒してくれます。また薄いブッシュであれば通過可能です。また近距離ヒグマ勝負を行う場合は、咄嗟の場合に銃を速やかに構える能力が不可欠になる筈ですが、彼の銃はスコープ後付け銃であり、眼の位置がスコープに合わず、これには不向きでした。
これが1990年頃から普及したスコープ専用銃や、また2000年頃から法律で決められた銅弾頭であれば、話が全く変わります。
スコープ専用銃はケンさん考案の新しい銃で指向するスナップ射撃が可能となり、肩に着ける前に命中する発砲が可能となり、スナップショットは得意項目になりました。
また銅弾頭は鉛の飛散が全く怒らず、これを利用して積極的に「骨の急所を撃つ事が可能」となりました。
久保氏は猟犬を使った猟を諦め、ドッグレスで山を歩き廻る様になり、やがて至近距離からヒグマ 勝負を挑む様になりました。
銃の世界も1980年頃になりますと、スコープ専用銃が出始めていました。
銃のパフォーマンスを上げ様と日々の工夫があれば、新しい猟具や技術に興味が行く筈ですが、彼はそうなりませんでした。そう言う方面に関心が薄いのが猟犬を使うハンターの特徴と言えました。
彼より3歳若いケンさんはドッグレス猟であり、1985年頃にはショットガンもライフルも独自のスナップ ショットを完成し、スコープ専用銃「ルガー77ボルトライフル」もデビュー後の程なくして購入しました。
鹿猟犬を頼った猟をする久保氏は猟具に関心が薄く、狩猟の道具も1975年頃から、銃もナイフも全く進化せず、若い頃のスコープ後付銃のサコ―フィンベアをそのままの形でずっと使い続けました。
ナイフで申すなら炭素鋼のナイフから進化せずでした。ケンさんのナイフは炭素鋼→ステンレス鋼→ダマスカス鋼と進化し、画期的と言える程に進化しました。
炭素鋼では鹿1頭目の後半から切れ味が大幅低下しました。
ステンレス鋼になりますと、メス2頭目までは良いのですが、3頭目で切れ味が低下しました。
それがダマスカス鋼になりますと、メス20頭を研がずに解体出来ました。
久保氏が掴んだヒグマとの接触方法の極意は、多分結果オーライの形で得られたのではないかと思います。それは何時もヒグマのいる地域を歩き、ヒグマに無害の人間であると思わせたのです。
本州に住み、シーズン数十日のみの狩猟をしていたケンさんには真似の出来ない手法ですが、地元に住んでいて、特定エリア内の年間数頭以下のヒグマを捕獲するのであれば、可能な方法と言えました。50年狩猟をしていて新たに分かった事の追加です。
その延長で考えますと、ケンさんもヒグマ捕獲を目的に行動開始し、5年目の2006年に1頭目を捕獲、翌年に2頭目と3頭目を捕獲しました。そして箱罠に依るヒグマ駆除が始まりました。
それまで箱罠駆除は行われていなかったので、多くのヒグマがパタパタ掛かりまして、過半のヒグマが捕獲され、ケンさん猟場のヒグマ生息数は半分以下となりました。
そして7年目の2014年、ヒグマの生息数も回復し、4頭目と5頭目のヒグマを捕獲、エースとなりました。そして2015年6頭目のヒグマを捕獲しました。
これもヒグマ側からすれば、ケンさんの車を猟場でよく見掛ける様になり、逃げなくなったのではないかと思える部分もありました。唯ケンさんの場合は50m先を走るヒグマが多かったと言う違いはあります。
久保氏はテレビ取材時に、50mでノーマークのエゾ鹿を立ち木に半委託射撃で撃ちました。
流石に半矢で逃げ出す事は無かったのですが、驚いた事に即死ではない射撃でした。
獲物を苦しめない彼の信条からすれば、また5~10mでヒグマを確実に即死させている事からすれば、信じられない下手糞な射撃でした。
その時代ではアメリカ帰りが珍しかった事、更に独自の子育て「大草原のみゆきちゃん」の取材を通し、マスコミに有名になり、「羆撃ち}も売れました。
ヒグマ70頭を捕獲したと言う説もありますが、彼自身は捕獲数を公表しておらず、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちではそこまで行っていないと思われます。
ケンさんが若い頃には仙人の様な凄い人だと尊敬していましたが、唯の猟犬ロリコンダメハンターでした。
2.小山氏の銃のバランス。
別の話ですが、長い間ケンさんは小山氏が北海道でNO.1のガイドであると思って尊敬して来ました。それはケンさんが1頭も捕獲出来なかった90㎝以上を相当数捕獲していたからです。
その小山氏が昨今は動画を多数投稿される様になり、それで気が付いた点があります。300m遠射が多いとは言え殆どが即倒していないのです。どうしてなのかを考えてみました。
因みにケンさんの300mは殆どが即倒の即死です。

写真は小山氏の愛銃:レミントン700、カスタムバレル、口径レミントン7㎜マグナム、スコープ4~16倍ビデオ機能付、重装備です。
ハンティング動画撮影に拘りを持っておられ、ネットにも多数投稿されています。
射撃精度にもかなり拘っておられる様で、モア精度のハンドロードで7㎜レミントンマグをカスタムバレルから撃っておられ、300mなら過半が即倒だと思うのですが、即倒していないのです。
狙撃が心臓狙いもあってか、小山氏の投稿動画でも即倒が殆どありません。ケンさんが見た投稿動画10本余で、即倒は1回だけで、何時も半矢捜索で数十~数百mで死んでいました。
未回収動画を公開する事は無いと思われ、即倒率は更に低いと思われます。
そして角サイズに拘りを持っておられ、300m前後のビッグトロフィー級狙いの遠射が主体です。
小山氏とケンさんと何が違うかと言えば、口径と急所とスコープです。
ケンさんの愛銃はサコー75改バーミンターの308、スコープは安物の軽量型、使用弾は激安弾の140gr弾銅頭挿げ替え弾でした。
急所をナミビアポイントに変更してからのケンさんは、300m遠射を含む殆どを即倒に出来る様になりました。正しく急所ヒットすれば弾のパワーに関係なく、即倒します。
ケンさんのスコープに比べ小山氏のスコープシステムは重量が数倍あると思われます。全依託で手に持たないで撃つと銃が振動し、ケンさんの銃でも反動で跳ね多少弾着が上にズレます。
銃にはバランスがあり、これは静的でも動的でも大切な事だと思っています。
また後述説明の様に、スコープベースの取付け強度も心配です。
動画の安定性にも問題があり、小山氏の動画はこのスコープを通した物やヘッドカメラは良いのですが、歩いている時の映像は水平が定まっておらず、見ていると乗り物酔い症状になってしまいます。
また発射の反動で映像が消えてしまい、被弾の瞬間が写っていないのも非常に残念です。
海外の良い動画はスコープからの映像もありますが、歩いている時はジャイロ付ハンディーカメラ、捕獲時の映像は三脚に固定された別のカメラの撮影がメインです。
近年はカメラの性能が上がり、スロー再生ではライフル弾の飛行によって出来た、空間の歪が写っている事もある程になりました。
もう少し解像度とスロー再生能力が上がれば、ケンさんのスロー再生特殊能力で見えたヒットした部分の毛が立ち、それが水面の波の様に周りに向かって広がって行く過程が写ると思います。
あれは実際に見えた映像ですから、絶対に事実だと思っています。第2波や第3波が発生し、それが広がって直径30㎝で消えて行く、詳細な様子を確認したい物です。
小山氏のスコープを通した映像では、その瞬間が反動で消えてしまっており、見えません。
命中精度に関するケンさんの仮説ですが、このスコープ部分が重過ぎると全体の振動条件が大きく変わり、弾着が乱れると思います。
そのせいかどうかは分りませんが、小山氏の動画の射撃は殆ど即倒していません。狙う急所を即倒率の高いナミビアポイントに換えるべきだと思います。
肉を求めるミートハンターではなくビッグトロフィーを求めるハンターですから、前足軸線上の背骨を撃って背ロースが少しダメージを受けても関係なく、ナミビアポイントを撃つべきだと思います。
即倒は一種の芸術ですから、それが上手く獲れれば動画の価値も上がると思われます。
ケンさんもナミビアポイント実用化前は超大物多数を未回収にしてしましたが、ナミビアポイントを実用化後は殆どを即倒出来、捕獲率が5倍に急増しました。
ナミビアポイントは他の急所に比べ即倒エリアが広く、周辺ヒットでも即倒してくれます。
ケンさん自身もこのナミビアポイントで前記の様な大きな成果を上げましたが、ケンさんスクールでも急所をナミビアポイントに変更してから、生徒による超大物捕獲が可能になりました。
銃に色々を架装する事は銃の精度やスナップショットやスイング特製に変化を生じ、捕獲率の低下を招くと思っており、ケンさんはその方向になる架装をする気はありません。

 レミントンとサコー
レミントンとサコー更にレミントンを始めとする世界中の多くの銃はスコープマウントベースが3㎜級ネジ2本で取付けられています。ケンさんも設計者の端クレですが、アレでは十分である筈が無いと思っています。

 ミロクとルガー
ミロクとルガーサコーはレシーバーの作り付けマウントで、しかも緩みが来ない様に前が広いテーパとなっています。
ミロクでは中ネジ4本に強化されており、ルガーも絶対に緩まない様に嵌め込み式になっています。
従来版小ネジタイプの緩む率は不明ですが緩む可能性がある様です。それに対する対策が各メーカーで行われ、それが増えているのです。ケンさんは小ネジ部分タイプが緩んだ例は3件見ました。
レミントン、ウインチェスター、サベージサボットで各1件で、共に標準クラスのスコープでした。
標準負荷でも緩む可能性があるのに、その負荷を数倍にしたら緩まない筈がないと言う事になります。
小山氏が未だにマグナムに拘っている点も気になります。
彼の愛用は7㎜レミントンマグの様ですが、マグナム弾は即倒効果も遠射効果もゼロであり、アフリカの大型動物でもエゾ鹿仕様308のバーンズ140gr銅弾を遥々持参して試しましたが、500㎏クラスの大型動物でも十分と言えました。
3.銃はバーミンター、口径は308。
散弾銃では「ショットガン効果」と言うのがあり、「1粒のパワーには概ね無関係な3粒被弾で撃墜」出来ました。無関係とは言え皮下に達しなければ無効弾になります。
同様にライフルの場合も似た様な部分があり、「急所に正しくヒットすれば、パワーには概ね無関係に即倒」しました。勿論エゾ鹿でも概ね100%即倒ですから、パワーは十分と言えマグナムは不要です。
この場合も当然ですが、数十㎝深さの急所まで届く必要があります。
心臓ポイントは動脈出口付近の狭い範囲にヒットしない限り即倒しません。

ナミビアポイントは銅弾でしか適用出来ませんが、即倒エリアが広く、実用性は抜群です。
即倒に必要な最低必要パワーの幅は相当広く、十分獲れているのであれば、口径の選択をとやかく言うつもりはありませんが、精度的には7㎜マグより308の方が優れています。
7㎜レミントンマグでベンチレスト射撃大会にチャンレンジする人は皆無ですが、100mハンタークラスと300mハンタークラスに308はしばしば入賞しています。
ケンさん自身も300mは全依託射撃であれば、概ね殆どを即倒可能です。
ナミビアでは450㎏クドウを380mにて308銅弾の初弾で即倒させる事が出来ました。
弾速が速い事でマグナムは落差補正的にはやや有利で、同じ落差で308の300mが350mまで延長出来る事は事実です。
しかし遠射は基本的に弾道の安定性が決め手となり、高速弾の遠射が有利になる事も殆ど無いのです。ケンさん自身初弾命中ではありませんが、ボス決定戦の超大物を540mから2発連続で2頭とも即倒させられました。308の弾道の安定性はかなり良好と言えました。
アメリカの長距離スナイパーの300ウインマグも220grの重量弾頭を使用しており、50BMG弾(12.7×99㎜ NATO)でも650gr重量弾頭を使い、1㎞以遠の遠射で使っています。
軽量高速弾より重量弾頭の方が遠距離射撃時の弾道性能は良い様です。
また308同士でも高速な150gr弾よりも、180gr重量弾の方が300m以遠では弾速も精度も上廻ります。
またバーミンターモデルの方が射撃は安定しており、レミントン700やルガー77のハンターモデル時は弾のメーカーを変えると弾着が変わりました。
しかしサコーバーミンターは海外にも持ち出し、現地製の弾を何時も使用していますが、何処の弾も弾着は変わらず、スコープ調整は12年間1度もしていません。
願わくばですが、ケンさんの助言が届き、小山氏の射撃は何時も「即倒」となり、その瞬間が上手くビデオに記録される事を願っています。
また角長1m怪物級エゾ鹿と500㎏のヒグマが獲れるとイイなと思っています。
4.牛の様な巨大鹿&珍鹿。
余談ですが、2002年に滝上でムース級の怪物鹿に会いました。距離は800m、サイズは牛クラス、角はそれ程ではありませんが、太い2段角で角の開きが水平に近い真っ黒な個体でした。
化石の世界の大角鹿かユーラシアンムースの末裔だったかも知れません。

写真はヘラ角にならないユーラシアンムースの若鹿です。
当時は望遠カメラを持っておらず、ライフルスコープの観察で角の生えている方向はこんな感じでしたが、もっと遥かに凄い老練な個体でした。
残念ながら翌年にはいなくなりました。1998年根室別当賀地区の太平洋側でも、概ね同等の牛の様に見えるムースの様なデカい鹿を見ました。この鹿も翌年以降は寿命なのか見掛けなくなりました。
金色の鬣のキリンの様な頭の鹿を見たのは、苫小牧石油タンク基地の近く、2012年の事でした。あれから10数年が過ぎ、寿命を迎えた頃かもです。
次は2010の根室だったと思いますが、朝1番オスばかり6頭の群を300mで出会いました。
群れの1頭はかなりの大物、残りは中型に見えました。
そこで1番大きなのを撃とうとスコープに捉えましたが、片角でした。
それで隣の中型に見えるのを撃ち即倒、回収してビックリ81㎝130㎏でした。
ならばあの片角は軽く95㎝超、200㎏越だった?
片角でも撃つべきだったと思いましたが、時すでに遅しでした。
翌年その近くで、体格が群を抜いた直線計測88㎝を捕獲したと、風の便りに聞きました。直線88㎝は実角長105㎝前後となります。
紋別スクール2007年の事でした。
100%即倒急所であるナミビアポイントを2006年に開拓、生徒にも指導しました。
そして85㎝は絶対と言う大物に出会い、150m強からD生徒に撃たせましたが、ナミビアポイントの指導をコロリと忘れ心臓を撃って未回収、数日間周辺を探しましたが、見付けられずに終わりました。
D生徒はその前年も運に恵まれず(迫力負けで足が地に着かず)、90㎝近いのを未回収にしています。その数年前にもボス決定戦の4頭を全て心臓撃ちで未回収、実はそれがナミビアポイント開拓に発展しました。
彼のベスト記録は角先欠がなければ81㎝で超大物達成でしたが、欠けていた為79㎝に留まりました。D生徒は公式記録に依れば25日参加で50頭捕獲とスクールで第2位の記録ですが、残念ながら超大物は捕獲出来ずでした。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その3:ボウハンティングは高効率。
エゾ鹿のボウハンティング。その2:アメリカの現状と射程距離の変化。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その1:ハーフライフル。
皆さんに伝えたい事。その14と15:ライフルと散弾の特殊効果。
皆さんに伝えたい事。その12と13:エゾ鹿の習性、ナンバーランキングのオス。
皆さんに伝えたい事。その11,難しいエゾ鹿猟。
エゾ鹿のボウハンティング。その2:アメリカの現状と射程距離の変化。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その1:ハーフライフル。
皆さんに伝えたい事。その14と15:ライフルと散弾の特殊効果。
皆さんに伝えたい事。その12と13:エゾ鹿の習性、ナンバーランキングのオス。
皆さんに伝えたい事。その11,難しいエゾ鹿猟。