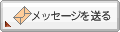2015年01月08日
近距離から遠距離までの全てに通用する射撃方法はありません。
近い鹿も遠い鹿も全てを獲りたい気持ちはよく分かりますが、一般的には近も遠も共にかなり難易度が高く、当面は最も良く出会う中距離以下を外さない様に徹する事が無難な方法です。
如何なる距離でも銃は狙って撃つ事に変わりはありませんが、運用方法は射撃距離によって大きく異なります。
銃は肉眼で照準器を通して狙うのではなく、体全体で銃を獲物に向け、心の目で狙います。
照準は確認して撃ちたい所ではありますが、中距離までの要求精度はそれほど高くありませんから最終確認はせずに撃ちます。つまり見ないで撃つ事になり、この思い込みの変更が成功へのカギになります。
100m以内の近距離ではどうしても早目に逃げられる傾向にありますから、とにかく必要なのは早撃ちになります。精度的には直径15cmの急所に当てれば良いのですから早撃ちでも充分当てられます。この射撃も一般的な射法では発砲前にかなり逃げられたり、焦って撃ってかなり外したりですから、全部当てようとしてする思いを変え、半分当たればヨシとすれば心がグンと楽になります。
200m級になりますときっちり狙わないと当たりません。今度は依託度の高い半依託射撃をしないと当たりませんから、近距離射撃とは全く違う撃ち方になります。
300mになりますと精度的に全依託射撃が必要になって中距離射撃とは全く違う射撃になります。そしてこれは後述の説明にもあります様に難しい落差補正が絡み、当てられませんから当面は除外する方が得策です。
1.正しい近距離実戦射撃=スナップショット。
本来近距離射撃は非常にイージー射撃になる筈ですが、モタ付けばすぐに射撃チャンスを逸しますから実際は射手が焦ってしまい、非常に命中率の悪い射撃になります
そうなる理由は照準が遅いからであり、その原因は正しい照準動作をしないからです。
照準と言う動作だけに付きましても、一般的に「肩に銃を付けて」「頭がスコープを探し」「その結果として肩を付け直し」「それから照準が始まり」「確認して撃つ」この5行程があるのが普通ですが、それは正しい照準方法ではなく直列思考のダメな照準方法です。
正しい照準方法を説明します。
ある目標に向かって最終的な発砲直前状態の形を体に覚え込ませます。
そしてその形の復元を直列では無く並列並行的にさせる、これが正しい照準方法です。
つまり体は目標に対して特定の位置関係と銃の反動に備えたあのスタイルに向かい、同時に頭は頬がチークピースに当り目がスコープの正面に来るその位置に向かい、そして銃もこれらと並行的動作で、装填と安全装置の解除をしながら、銃身で目標の急所を指差す様に向けて、まっすぐ肩に引き寄せます。
こうすると全ての動作が一瞬の1行程で完了しますから一般的な5行程照準に比べて著しく時間短縮が可能になります。更に、正しい照準方法は銃が肩に付く以前から照準がすでに始まっているのが特徴ですから、実際にはもっと大きな時間の短縮が起こります。
目はすでにスコープに正対する位置を完了しており獲物の急所を見ております。
銃身も指向させた時点ですでに目標の急所に正対していますから、肩にストックが付く少し前にはスコープを通して急所付近が目に入り始めます。
その結果として軸線がずれていれば、肩に銃が付くまでに照準補正を始める事が出来、その正しい軸線を横切るのを見越して引き金を引きますが、それは肩に銃が付く付かないを問いません。ずれが微少以内であれば、肩にストックが付くかなり前にそのまま発砲しても弾は急所付近に当ります。
銃が肩に付くまでの1工程はどちらの照準もほぼ同じ時間になります。
しかし一般的な手法では全5行程であり、更に4工程も必要になりますが、正しい照準方法では1行程目の半ば過ぎの時点(つまり0.5行程)でもう全てが完了しますから、5行程対0.5工程つまり1/10が達成された事になります。
そしてその射撃はちゃんと当たる射撃になっており、圧倒的短時間ですから獲物に逃げられる可能性は甚だ僅かになります。

ストックが肩に付く前のスコープの黒丸の中にこんな感じの急所付近が拡大された映像
が目に入って来ます。この時点で微修正なり発砲を決断するのがスナップショットなのです。
スコープの中の黒丸はなるべく中心に見える様な位置に目を持って行くのが正論ですが、
少し位ずれていても気にする必要はありません。
これが正しい近距離照準の手法です。スナップショットと呼ばれる撃ち方ですが、これは特別な撃ち方ではなく、これが近距離射撃の標準的な手法になり、実戦射撃全ての基本になります。通常の皆さんはこの正しい射撃をしませんから、その結果として「確実に戴けるチャンス」もを撃てずに或いは焦り射撃で逃がしてしまうのです。
筆者のヒグマ5頭も全てこのスナップショット、またNZで大物エルクを捕獲したのもこの射法です。
筆者はこの正しい射法をマスターしていましたからこれらの捕獲に成功しましたが、この射法抜きであれば結果は一般の皆さんと同じ事になったと思います。
スナップショットをマスターすると言う言葉は銃を扱えると言う言葉と同意語なのです。
このスナップショットをマスターする事と、見ている映像が古い虚像である事を理解すれば、全ての場面の獲物に対処出来る様になるのは時間の問題です。
初期には多くの人が50mでも的紙から外れてしまう射撃を経験された事と思います。あれは主原因がフリンチングです。スナップショットでは高精度を出す事は不可能ですが、肩に銃が付く前に撃ちますから、フリンチングは起こり難い構造にあり、瞬時に撃っても実用レベルに耐えられる精度が出せるのです。
従いまして、100m未満なら気合を入れて銃を安定させ、照準を確認しなくても十分に実用的な精度は出せるのです。この狙い込まなければ当てられないと言う射手側の従来の思い込みを変えなくてはなりません。
精度が原因である失中は一切なく、失中は何か1桁以上大きなミスが原因で起こります。
2.正しい中距離射撃=半依託射撃。
次に正しい中距離実戦射撃のお話をします。これにはまず銃の安定保持が不可欠です。
その結果、何か固定物に寄り掛かる、ここまでは容易に想像が付きますが、実は射手の体側も何かに寄り掛かって安定化を図ると射撃精度は著しく向上します。
銃と体の安定化を優先した結果、毎回著しく変形した本来の正しいとされる射撃フォームからは程遠い形になりますが、これが実戦用の正しい半託射撃の考え方になります。
どんなスタイルになるかは各々の場面によって色々あり過ぎて代表的な例を示せない程になり、中距離射撃は言葉を変えれば射撃場で撃つあの標準的なスタイルとは全く違うと言う事になります。これも従来の思い込みを変えなくてはなりません。
また委託を優先しますとスコープの映像も黒い部分が出て来ますが、ある程度の中心寄りに目標の急所を捉えられるのであれば、全く問題はありません。
3.遠射は当面考えない。
300m級になりますと一段と要求精密度が増し150mで5cm程度以下を要求されます。
これには銃を完全に委託しないと命中しませんから、また今までとは違う撃ち方になり、
これを満たす射撃方法はボンネット射撃とプローン(伏せ撃ち)だけとなります。
更に250m以遠は落差補正が不可欠となり、それには正確な射撃距離データが必要です。しかし距離の実測をする時間はありませんから目視測定になりますが、目測であると2倍以上のかなり大きな誤差が出る事も何ら珍しくありません。
大幅に間違った補正であればしない方が当然ですが良く当ります。従いまして当面は近距離&中距離に焦点を置き、遠射は取りあえず対象外とした方が得策です。
遠射はその猟場の地形に精通し、あそこまでは何mを全て覚えてからチャレンジすれば、自然に当る様になります。そしてそう言う日はそれ程遠い事ではありません。
なお、この落差補正量は300mや400mの遠距離ゼロインにしておき、中近距離でマイナス補正すればその補正量は半減すると言うマジックが起こります。
この落差補正をすると言う考え方その物は間違ってはいませんが、実際には正確な距離データの入手が非常に難しい物になります。
通常は目視によってかなり大きく間違った距離をベースに補正が行われますから、すでにお話した間違い補正が行われる可能性の方が高く、結果的に自信を持てない射撃になってしまいます。
射撃と言うのは本当に不思議な物で心に不安要素が少しでもあると命中しません。
自信を持って撃った射撃だけが命中するのです。
そう言う事ですから当面の間は落差補正の射撃はしないと言う考えがベストで、具体的には150mゼロインにしておき200m強までを直撃する事だけを考えて練習を積み重ねます。
まずは最も確実に戴ける近距離射撃から自分のモノにしなければなりません。
スナップショットは全ての実戦の基本、そして従来からの古い思い込みの幾つかを排除する、これが上達へのステップになります。
如何なる距離でも銃は狙って撃つ事に変わりはありませんが、運用方法は射撃距離によって大きく異なります。
銃は肉眼で照準器を通して狙うのではなく、体全体で銃を獲物に向け、心の目で狙います。
照準は確認して撃ちたい所ではありますが、中距離までの要求精度はそれほど高くありませんから最終確認はせずに撃ちます。つまり見ないで撃つ事になり、この思い込みの変更が成功へのカギになります。
100m以内の近距離ではどうしても早目に逃げられる傾向にありますから、とにかく必要なのは早撃ちになります。精度的には直径15cmの急所に当てれば良いのですから早撃ちでも充分当てられます。この射撃も一般的な射法では発砲前にかなり逃げられたり、焦って撃ってかなり外したりですから、全部当てようとしてする思いを変え、半分当たればヨシとすれば心がグンと楽になります。
200m級になりますときっちり狙わないと当たりません。今度は依託度の高い半依託射撃をしないと当たりませんから、近距離射撃とは全く違う撃ち方になります。
300mになりますと精度的に全依託射撃が必要になって中距離射撃とは全く違う射撃になります。そしてこれは後述の説明にもあります様に難しい落差補正が絡み、当てられませんから当面は除外する方が得策です。
1.正しい近距離実戦射撃=スナップショット。
本来近距離射撃は非常にイージー射撃になる筈ですが、モタ付けばすぐに射撃チャンスを逸しますから実際は射手が焦ってしまい、非常に命中率の悪い射撃になります
そうなる理由は照準が遅いからであり、その原因は正しい照準動作をしないからです。
照準と言う動作だけに付きましても、一般的に「肩に銃を付けて」「頭がスコープを探し」「その結果として肩を付け直し」「それから照準が始まり」「確認して撃つ」この5行程があるのが普通ですが、それは正しい照準方法ではなく直列思考のダメな照準方法です。
正しい照準方法を説明します。
ある目標に向かって最終的な発砲直前状態の形を体に覚え込ませます。
そしてその形の復元を直列では無く並列並行的にさせる、これが正しい照準方法です。
つまり体は目標に対して特定の位置関係と銃の反動に備えたあのスタイルに向かい、同時に頭は頬がチークピースに当り目がスコープの正面に来るその位置に向かい、そして銃もこれらと並行的動作で、装填と安全装置の解除をしながら、銃身で目標の急所を指差す様に向けて、まっすぐ肩に引き寄せます。
こうすると全ての動作が一瞬の1行程で完了しますから一般的な5行程照準に比べて著しく時間短縮が可能になります。更に、正しい照準方法は銃が肩に付く以前から照準がすでに始まっているのが特徴ですから、実際にはもっと大きな時間の短縮が起こります。
目はすでにスコープに正対する位置を完了しており獲物の急所を見ております。
銃身も指向させた時点ですでに目標の急所に正対していますから、肩にストックが付く少し前にはスコープを通して急所付近が目に入り始めます。
その結果として軸線がずれていれば、肩に銃が付くまでに照準補正を始める事が出来、その正しい軸線を横切るのを見越して引き金を引きますが、それは肩に銃が付く付かないを問いません。ずれが微少以内であれば、肩にストックが付くかなり前にそのまま発砲しても弾は急所付近に当ります。
銃が肩に付くまでの1工程はどちらの照準もほぼ同じ時間になります。
しかし一般的な手法では全5行程であり、更に4工程も必要になりますが、正しい照準方法では1行程目の半ば過ぎの時点(つまり0.5行程)でもう全てが完了しますから、5行程対0.5工程つまり1/10が達成された事になります。
そしてその射撃はちゃんと当たる射撃になっており、圧倒的短時間ですから獲物に逃げられる可能性は甚だ僅かになります。

ストックが肩に付く前のスコープの黒丸の中にこんな感じの急所付近が拡大された映像
が目に入って来ます。この時点で微修正なり発砲を決断するのがスナップショットなのです。
スコープの中の黒丸はなるべく中心に見える様な位置に目を持って行くのが正論ですが、
少し位ずれていても気にする必要はありません。
これが正しい近距離照準の手法です。スナップショットと呼ばれる撃ち方ですが、これは特別な撃ち方ではなく、これが近距離射撃の標準的な手法になり、実戦射撃全ての基本になります。通常の皆さんはこの正しい射撃をしませんから、その結果として「確実に戴けるチャンス」もを撃てずに或いは焦り射撃で逃がしてしまうのです。
筆者のヒグマ5頭も全てこのスナップショット、またNZで大物エルクを捕獲したのもこの射法です。
筆者はこの正しい射法をマスターしていましたからこれらの捕獲に成功しましたが、この射法抜きであれば結果は一般の皆さんと同じ事になったと思います。
スナップショットをマスターすると言う言葉は銃を扱えると言う言葉と同意語なのです。
このスナップショットをマスターする事と、見ている映像が古い虚像である事を理解すれば、全ての場面の獲物に対処出来る様になるのは時間の問題です。
初期には多くの人が50mでも的紙から外れてしまう射撃を経験された事と思います。あれは主原因がフリンチングです。スナップショットでは高精度を出す事は不可能ですが、肩に銃が付く前に撃ちますから、フリンチングは起こり難い構造にあり、瞬時に撃っても実用レベルに耐えられる精度が出せるのです。
従いまして、100m未満なら気合を入れて銃を安定させ、照準を確認しなくても十分に実用的な精度は出せるのです。この狙い込まなければ当てられないと言う射手側の従来の思い込みを変えなくてはなりません。
精度が原因である失中は一切なく、失中は何か1桁以上大きなミスが原因で起こります。
2.正しい中距離射撃=半依託射撃。
次に正しい中距離実戦射撃のお話をします。これにはまず銃の安定保持が不可欠です。
その結果、何か固定物に寄り掛かる、ここまでは容易に想像が付きますが、実は射手の体側も何かに寄り掛かって安定化を図ると射撃精度は著しく向上します。
銃と体の安定化を優先した結果、毎回著しく変形した本来の正しいとされる射撃フォームからは程遠い形になりますが、これが実戦用の正しい半託射撃の考え方になります。
どんなスタイルになるかは各々の場面によって色々あり過ぎて代表的な例を示せない程になり、中距離射撃は言葉を変えれば射撃場で撃つあの標準的なスタイルとは全く違うと言う事になります。これも従来の思い込みを変えなくてはなりません。
また委託を優先しますとスコープの映像も黒い部分が出て来ますが、ある程度の中心寄りに目標の急所を捉えられるのであれば、全く問題はありません。
3.遠射は当面考えない。
300m級になりますと一段と要求精密度が増し150mで5cm程度以下を要求されます。
これには銃を完全に委託しないと命中しませんから、また今までとは違う撃ち方になり、
これを満たす射撃方法はボンネット射撃とプローン(伏せ撃ち)だけとなります。
更に250m以遠は落差補正が不可欠となり、それには正確な射撃距離データが必要です。しかし距離の実測をする時間はありませんから目視測定になりますが、目測であると2倍以上のかなり大きな誤差が出る事も何ら珍しくありません。
大幅に間違った補正であればしない方が当然ですが良く当ります。従いまして当面は近距離&中距離に焦点を置き、遠射は取りあえず対象外とした方が得策です。
遠射はその猟場の地形に精通し、あそこまでは何mを全て覚えてからチャレンジすれば、自然に当る様になります。そしてそう言う日はそれ程遠い事ではありません。
なお、この落差補正量は300mや400mの遠距離ゼロインにしておき、中近距離でマイナス補正すればその補正量は半減すると言うマジックが起こります。
この落差補正をすると言う考え方その物は間違ってはいませんが、実際には正確な距離データの入手が非常に難しい物になります。
通常は目視によってかなり大きく間違った距離をベースに補正が行われますから、すでにお話した間違い補正が行われる可能性の方が高く、結果的に自信を持てない射撃になってしまいます。
射撃と言うのは本当に不思議な物で心に不安要素が少しでもあると命中しません。
自信を持って撃った射撃だけが命中するのです。
そう言う事ですから当面の間は落差補正の射撃はしないと言う考えがベストで、具体的には150mゼロインにしておき200m強までを直撃する事だけを考えて練習を積み重ねます。
まずは最も確実に戴ける近距離射撃から自分のモノにしなければなりません。
スナップショットは全ての実戦の基本、そして従来からの古い思い込みの幾つかを排除する、これが上達へのステップになります。
沖縄の鹿。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その3:ボウハンティングは高効率。
エゾ鹿のボウハンティング。その2:アメリカの現状と射程距離の変化。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その1:ハーフライフル。
皆さんに伝えたい事。その14と15:ライフルと散弾の特殊効果。
皆さんに伝えたい事。その12と13:エゾ鹿の習性、ナンバーランキングのオス。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その3:ボウハンティングは高効率。
エゾ鹿のボウハンティング。その2:アメリカの現状と射程距離の変化。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その1:ハーフライフル。
皆さんに伝えたい事。その14と15:ライフルと散弾の特殊効果。
皆さんに伝えたい事。その12と13:エゾ鹿の習性、ナンバーランキングのオス。
この記事へのコメント
本州鹿、イノシシ猟のため150m以内の射撃です50mでセンター上2,5㎝着弾調整100mで5㎝上を着弾ブローニング30-06ですが近距離の30~50のスイング遅れ難しいです発見の遅れもありますね、全力で走る本州鹿の鼻先を狙い引き金引くのですが確実なヒットが難しいですね。
Posted by 猟師です at 2016年07月26日 17:02