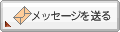2024年06月26日
銃に関する偉大な発明。
4.銃に関する偉大な発明。
フリントロック(燧石)銃:最初の銃は火縄式、1500年頃に実用化され、1550年頃からヨーロッパの戦いにフリントロック銃が用いられました。
日本には1543年に火縄銃が種子島に伝えられ、数年の内に日本全国に拡散し、当時日本は世界で1番大量に銃を持っている国でした。
火縄銃は種火を何時も持ち歩き、火縄に着火していなければ発砲出来ず、さりとて火縄に常時火を燈すには消耗度(30㎝/h)が多過ぎました。
1550年頃に発明されたフリントロック(燧石銃)は種火の携帯が不要となり、「何時でも即発砲が可能となった偉大な発明」と言え、300年間も運用されました。
ライフリングの発明:これ自体の発明は1498年まで遡りますが、実用化は次項パーカッション式と同時期の1850年代でした。
従来は丸弾ですが、ドングリ型弾頭(ミニエー弾)とライフリングの組合せでは射程距離は数倍に延長されました。更にこの傾向は小口径化により初速の向上と弾頭空気抵抗の減少で更に延長され、急所狙いは従来の20mから150m(現サボットスラグ銃並)に向上しました。
一方で15~18㎜の丸弾銃の場合は散弾運用も兼ねられましたが、小口径化(11㎜)ライフル銃ではそれが困難となり、先込め銃ながら散弾専用の薄い銃身の軽量な2連式散弾銃が誕生しました。
パーカッション(管打ち)銃:フリントロックは何時でも何処でも撃てる偉大な発明でしたが、火縄銃を含め、雨天には使用不能でした。
1850年頃発明されたパーカッション銃は、フリント式と同じ黒色火薬の先込め式ですが、100%の確実な発火と長年の夢の全天候性が可能となった「偉大な発明」となりました。
また着火パワーの大幅向上により、特殊な紙に包まれたままの弾薬に着火が可能となり、弾薬と言える様になりました。フリント式はその多くがパーカッション式に改造されました。
また火縄式も燧石式も薬室に火種を伝える小穴から大量の火薬ガスを噴き出しましたが、これが甚だ微少となり、火薬圧力の全てを弾頭の加速に利用出来る様になりました。
又シリンダーに多数の弾を予め装填したリボルバー型では早撃ちや連射も可能となりました。
パーカッションリボルバーは後述のカートリッジが実用化されると、カートリッジ式に改造されました。
カートリッジ:1864年、弾丸・主火薬・発火薬を薬莢に収めたカートリッジは「最も偉大な大発明」の1つでした。
装填時間を1/10に短縮出来、これによりレバーアクション式等の連発銃も完成、これで何時でも何処でも、遠くまで正確に命中し、雨天でも100%発火、更に連発も可能となり、銃は古くからの夢の全てを達成、完成の域に達したかに見えました。
 民間用ウインチェスター1873
民間用ウインチェスター1873
民間でベストセラーとなった10数連発(銃身下のマガジン長に依る)ウインチェンスター1873は拳銃のピースメーカーと共通弾薬は便利で良いのですが、拳銃弾44-40は低威力で短射程でした。
 軍用スプリングフィールド1873
軍用スプリングフィールド1873
その為米陸軍は同年ですが、45-70ライフル弾を使用するスプリングフィールド1973を採用しました。
本銃はパーカッション銃を改造出来るメリットもありました。
しかし隣国と国境を接するヨーロッパでは ボルトアクション式が新規採用され、やがて現在のボルト銃その物となったモーゼル98に発展しました。
 シャスポー1866フランス
シャスポー1866フランス
 モーゼル1898ドイツ
モーゼル1898ドイツ
無煙火薬:1884年発明の無煙火薬は従来の黒色火薬比で弾速2倍、4倍パワーが可能となった「最も偉大な発明」の1つとなり、全ての黒色火薬銃を一気に旧式にしてしまいました。
黒色火薬は湿気易い欠点と、銃の腐植と言う大きな欠点がありましたが、これも画期的に改善され、1900年前後には現在も使われている弾薬(代表は30-06)が制定され、銃の型式も概ね現在と同じ物になりました。
以後の銃はWW2後に合金鋼が実用化され、1960年代にNC(数値)加工が可能となり、それらを前提に再設計され、精度や耐久性が大きく向上され、多種の自動銃がデビューしました。
散弾銃の自動銃は非常に大きな成果を上げました。連発数は当初5発でしたが、野性鳥獣保護と 残弾による暴発事故防止の為、日本では1970年代の後半に4発となり、数年後に3発となりました。
ライフル銃にも多種の自動銃がデビューしましたが、多くは余り高精度ではなく、回転性能も低く、余り使えるとは言い難い銃でした。
特筆は1967年デビューのBAR、比較的命中精度も回転性能も良く、当時流行のマグナムもよく売れましたが、元々自動銃の存在意味は無かった事が後刻判明しました。
また1990年頃になりますとコンピューター制御のNC加工が可能となり、これを前提とした再設計が再度行われ、精度が一段と向上しました。
ケンさんが運用したH&Kオートもこの年代ですが、150mで12㎜のワンホールを達成しました。
精度と回転性能が良ければ自動銃有利と思われ、本銃は究極のライフル銃かと思われましたが、3項の説明の様に、自動銃は究極の銃ではありませんでした。
ライフルスコープ:ライフルスコープのアイデアその物は黒色火薬カートリッジ銃の時代からありましたが、普及はWW2の狙撃銃から始まりました。
スコープ取付高差を利用した微少上向き発射のお陰で「有効射程2倍の大発明」となり、遠距離射撃や精密射撃には非常に便利な物でした。
 スコープ後付け銃
スコープ後付け銃
多くのライフル銃にスコープが後付けされましたが、後付けスコープは狂易かった事もあり、オープンサイトを予備に残しました。
 頭の位置が安定していないスコープ後付け銃
頭の位置が安定していないスコープ後付け銃
その為、銃を構えてもスコープは目前には無く、まず頭がスコープを探し、それから目標を捜索する事になり、スコープは視野が極端に狭い事もあって、目標を捉え難い欠点がありました。
その為に「スナップショット」や「ランニングショット」は不得意と言えました。
スコープ専用銃:スコープ専用銃普及は1990年頃からとなりました。
チークピース調整済スコープ専用銃は構えればスコープが目の正面に来る為、スコープの視野は狭いままながら目標を素速く捉え易く、スナップショットやランニングショットが可能となり、射撃時の頭の安定性が大幅に向上しました。
 スコープ専用銃
スコープ専用銃
 頭の位置が非常に安定しているスコープ専用銃
頭の位置が非常に安定しているスコープ専用銃
結果から言えばスコープは射程2倍となり、更にスコープ専用銃となった事から、後述の新スナップ ショット等々の新しい射撃技術に発展し、「スコープ専用銃は無煙火薬級の画期的な大発明」の1つと言えました。
新スナップショット:スコープ専用銃は肩付けより先に銃を指向する「スナップショット」や体全体で目標を追尾する「スナップスイングショット」をマスターすれば、更に新しい可能性が広がりました。
近距離の「出会い頭の射撃や動的連射も得意項目」と言える様になりました。
「新射法とスコープ専用銃の組合せ」は50~300m以遠まで「あらゆる場面で最強の狩猟銃」となりました。その範囲は動的も含まれます。(50m未満はショットガン効果のバックショットが最強。)
更にスナップショットは全射撃の基本に組入れる事が可能であり、全射撃の照準時間を大幅短縮、「スナップショット」も「再肩付けスナップスイングショット」も「画期的な大発明に匹敵」と言えました。
フリントロック(燧石)銃:最初の銃は火縄式、1500年頃に実用化され、1550年頃からヨーロッパの戦いにフリントロック銃が用いられました。
日本には1543年に火縄銃が種子島に伝えられ、数年の内に日本全国に拡散し、当時日本は世界で1番大量に銃を持っている国でした。
火縄銃は種火を何時も持ち歩き、火縄に着火していなければ発砲出来ず、さりとて火縄に常時火を燈すには消耗度(30㎝/h)が多過ぎました。
1550年頃に発明されたフリントロック(燧石銃)は種火の携帯が不要となり、「何時でも即発砲が可能となった偉大な発明」と言え、300年間も運用されました。
ライフリングの発明:これ自体の発明は1498年まで遡りますが、実用化は次項パーカッション式と同時期の1850年代でした。
従来は丸弾ですが、ドングリ型弾頭(ミニエー弾)とライフリングの組合せでは射程距離は数倍に延長されました。更にこの傾向は小口径化により初速の向上と弾頭空気抵抗の減少で更に延長され、急所狙いは従来の20mから150m(現サボットスラグ銃並)に向上しました。
一方で15~18㎜の丸弾銃の場合は散弾運用も兼ねられましたが、小口径化(11㎜)ライフル銃ではそれが困難となり、先込め銃ながら散弾専用の薄い銃身の軽量な2連式散弾銃が誕生しました。
パーカッション(管打ち)銃:フリントロックは何時でも何処でも撃てる偉大な発明でしたが、火縄銃を含め、雨天には使用不能でした。
1850年頃発明されたパーカッション銃は、フリント式と同じ黒色火薬の先込め式ですが、100%の確実な発火と長年の夢の全天候性が可能となった「偉大な発明」となりました。
また着火パワーの大幅向上により、特殊な紙に包まれたままの弾薬に着火が可能となり、弾薬と言える様になりました。フリント式はその多くがパーカッション式に改造されました。
また火縄式も燧石式も薬室に火種を伝える小穴から大量の火薬ガスを噴き出しましたが、これが甚だ微少となり、火薬圧力の全てを弾頭の加速に利用出来る様になりました。
又シリンダーに多数の弾を予め装填したリボルバー型では早撃ちや連射も可能となりました。
パーカッションリボルバーは後述のカートリッジが実用化されると、カートリッジ式に改造されました。
カートリッジ:1864年、弾丸・主火薬・発火薬を薬莢に収めたカートリッジは「最も偉大な大発明」の1つでした。
装填時間を1/10に短縮出来、これによりレバーアクション式等の連発銃も完成、これで何時でも何処でも、遠くまで正確に命中し、雨天でも100%発火、更に連発も可能となり、銃は古くからの夢の全てを達成、完成の域に達したかに見えました。
 民間用ウインチェスター1873
民間用ウインチェスター1873民間でベストセラーとなった10数連発(銃身下のマガジン長に依る)ウインチェンスター1873は拳銃のピースメーカーと共通弾薬は便利で良いのですが、拳銃弾44-40は低威力で短射程でした。
 軍用スプリングフィールド1873
軍用スプリングフィールド1873その為米陸軍は同年ですが、45-70ライフル弾を使用するスプリングフィールド1973を採用しました。
本銃はパーカッション銃を改造出来るメリットもありました。
しかし隣国と国境を接するヨーロッパでは ボルトアクション式が新規採用され、やがて現在のボルト銃その物となったモーゼル98に発展しました。
 シャスポー1866フランス
シャスポー1866フランス モーゼル1898ドイツ
モーゼル1898ドイツ無煙火薬:1884年発明の無煙火薬は従来の黒色火薬比で弾速2倍、4倍パワーが可能となった「最も偉大な発明」の1つとなり、全ての黒色火薬銃を一気に旧式にしてしまいました。
黒色火薬は湿気易い欠点と、銃の腐植と言う大きな欠点がありましたが、これも画期的に改善され、1900年前後には現在も使われている弾薬(代表は30-06)が制定され、銃の型式も概ね現在と同じ物になりました。
以後の銃はWW2後に合金鋼が実用化され、1960年代にNC(数値)加工が可能となり、それらを前提に再設計され、精度や耐久性が大きく向上され、多種の自動銃がデビューしました。
散弾銃の自動銃は非常に大きな成果を上げました。連発数は当初5発でしたが、野性鳥獣保護と 残弾による暴発事故防止の為、日本では1970年代の後半に4発となり、数年後に3発となりました。
ライフル銃にも多種の自動銃がデビューしましたが、多くは余り高精度ではなく、回転性能も低く、余り使えるとは言い難い銃でした。
特筆は1967年デビューのBAR、比較的命中精度も回転性能も良く、当時流行のマグナムもよく売れましたが、元々自動銃の存在意味は無かった事が後刻判明しました。
また1990年頃になりますとコンピューター制御のNC加工が可能となり、これを前提とした再設計が再度行われ、精度が一段と向上しました。
ケンさんが運用したH&Kオートもこの年代ですが、150mで12㎜のワンホールを達成しました。
精度と回転性能が良ければ自動銃有利と思われ、本銃は究極のライフル銃かと思われましたが、3項の説明の様に、自動銃は究極の銃ではありませんでした。
ライフルスコープ:ライフルスコープのアイデアその物は黒色火薬カートリッジ銃の時代からありましたが、普及はWW2の狙撃銃から始まりました。
スコープ取付高差を利用した微少上向き発射のお陰で「有効射程2倍の大発明」となり、遠距離射撃や精密射撃には非常に便利な物でした。
 スコープ後付け銃
スコープ後付け銃多くのライフル銃にスコープが後付けされましたが、後付けスコープは狂易かった事もあり、オープンサイトを予備に残しました。
 頭の位置が安定していないスコープ後付け銃
頭の位置が安定していないスコープ後付け銃その為、銃を構えてもスコープは目前には無く、まず頭がスコープを探し、それから目標を捜索する事になり、スコープは視野が極端に狭い事もあって、目標を捉え難い欠点がありました。
その為に「スナップショット」や「ランニングショット」は不得意と言えました。
スコープ専用銃:スコープ専用銃普及は1990年頃からとなりました。
チークピース調整済スコープ専用銃は構えればスコープが目の正面に来る為、スコープの視野は狭いままながら目標を素速く捉え易く、スナップショットやランニングショットが可能となり、射撃時の頭の安定性が大幅に向上しました。
 頭の位置が非常に安定しているスコープ専用銃
頭の位置が非常に安定しているスコープ専用銃結果から言えばスコープは射程2倍となり、更にスコープ専用銃となった事から、後述の新スナップ ショット等々の新しい射撃技術に発展し、「スコープ専用銃は無煙火薬級の画期的な大発明」の1つと言えました。
新スナップショット:スコープ専用銃は肩付けより先に銃を指向する「スナップショット」や体全体で目標を追尾する「スナップスイングショット」をマスターすれば、更に新しい可能性が広がりました。
近距離の「出会い頭の射撃や動的連射も得意項目」と言える様になりました。
「新射法とスコープ専用銃の組合せ」は50~300m以遠まで「あらゆる場面で最強の狩猟銃」となりました。その範囲は動的も含まれます。(50m未満はショットガン効果のバックショットが最強。)
更にスナップショットは全射撃の基本に組入れる事が可能であり、全射撃の照準時間を大幅短縮、「スナップショット」も「再肩付けスナップスイングショット」も「画期的な大発明に匹敵」と言えました。
Posted by little-ken
at 16:45
│銃と弾