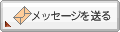2023年12月01日
織田信長の3段射法。火縄銃、燧石銃、管打銃。
銃の歴史は速く撃てる連射と、次いで遠距離狙撃に挑戦、もう1つは何時でも何処でもすぐに撃てる全天候性チャンレンジの歴史でもありました。
銃が実用化されたのは1500年頃、黒色火薬で鉛の丸弾、勿論先込め、巻張銃身の火縄銃でした。
当時の先込め銃はノーライフルで丸弾、上半身ヒットの射程距離は僅か50mと短く、マグレ期待も 200mまででした。1発撃つと再装填に20秒程を要し、騎馬の走行速度からすると、必殺距離からの2発目は到底間に合わず、マグレ期待発砲でも2発目は限界付近、絶望的な大問題でした。
それでも銃は時代の最先端技術、戦争に利用され、この運用次第で勝敗の行方が変わりました。
1.信長の3段撃ち。
1543年、南蛮船が鹿児島県の種子島に漂着した事から、日本に火縄銃伝来する事となりました。そんな火縄銃を用いた著名な合戦の一つが、1575年の「織田信長」「徳川家康」連合軍と、「武田勝頼」軍の「長篠の戦い」でした。
結果は、織田信長が考案したとされる、火縄銃の戦術「三段撃ち」が決め手となり、織田・徳川連合軍の圧勝に終わりました。これを検証して見たいと思います。


上:国友筒 下:堺筒、
織田・徳川連合軍が準備した銃の数は3000丁だった事が通説になっています。
どうして大量の銃を揃える事が出来たかに付きましては、信長の眼力に加え、滋賀県長浜の国友や大阪の堺と言った銃の生産地を領地にした事が上げられます。
三段撃ちの基本的手順は、鉄砲隊を3列に分け、撃ち終わった1列目は後方に廻り、弾込め等の準備を行っている間に、2列目が発射、2列目も後方に下がり再装填、その間に3列目が発射、3列目が下がったその頃、再装填を終えた1列目が再び前に出て発射、これを繰り返しました。
当時の火縄銃の再装填には、再装填はまず銃口から火薬、次にパッチに包まれた丸弾を入れ、朔杖で奥まで押し込み、火鋏みを上げ、発火薬を火口に入れ、火蓋を閉じます。
そして火縄に息を吹き掛け、燃えカスを飛ばした火縄をセットします。
これで銃を構えて火蓋を開放し、引き金を引けば発火となり、所要時間は約20秒でした。
一方射程距離はノーライフルの丸弾ですから急所狙いは20m以内、人間の胴体に70%命中させられる距離は、50m程度でした。弾自体の飛行距離はMax.500m程度ですが、100mでは胴体に 10%しか命中せず、それ以遠で命中するのはマグレ弾だけとなりました。
一方武田の騎馬隊の走る速度は40~50㎞/h、秒速では10~15m/sでした。接近する武田軍の群にマグレ期待の200mから射撃しても、騎馬は装填完了前に来てしまい、間に合いません。
それで考え出されたのが。馬防柵後方からの三段撃ちと言えますが、火縄銃研究会の10名射撃でこれを試した所、10名が一斉射撃しようとすると、最も遅い射手の装填完了まで数秒 待たなくてはならず、10発一斉射の間隔は平均24秒となりました。
一方10丁個々が装填次第前に出て射撃すれば、平均20秒で10発射撃が可能でした。
どちらも時間当たりの発射数にベラボーな差はありませんが、3000丁で撃てば1秒間に150発が絶え間なく発射される事になります。
豪快な連続射撃に聞こえ、実戦では装填済み次第、200mの射撃で群れに向けて撃つ方法が採用された様子です。この射撃方法であれば、腕は関係無くなります。
稀にはそれをスリ抜け、至近距離まで来る場合もあります。概ね真直ぐ向かって来るにしても、動的を迎え撃つ事は通常の射撃術では困難と言え、しかもそれを確実に倒さなくてはならなくなります。
そうなりますと、この射撃には名人の腕が必要になります。当時は銃も弾も非常に貴重品ですから、十分な射撃訓練は出来る筈もなく、この場合の効率の良い射撃方法は、腕の良くない射手は弾込係に徹し、名人に装填済の銃を供給する方が、最も効率的と言えました。
今も昔も名人が生まれる確率は、100~1000人に1人程度です。
1-1.火縄銃兵の装備弾数。
ケンさんがカモ猟に行く時は何時も120発を身に付け、エゾ鹿猟に出掛ける時は身に付けているのは30発ですが、更に40発を荷物に入れていました。WW2の日本兵の装備は120発、WW2のアメリカのM1ガーランド兵は80発、M1カービン兵は135発、ベトナム戦M16兵は210発でした。




当時の火縄銃兵の装備弾数は調べる事が出来ませんでしたが、4つの画像が見付かりました。
左上の銃兵の場合ですと口径によっては、10~20発程度の早号ポーチを身に付けており、右上の場合は15発程度、左下の銃兵の場合は僅か8発しか身に付けていません。右下は現在の射撃用火縄銃の50発早号ケース、寸法は長さ19㎝・幅9㎝・高さ10㎝です。
つまりどう見ても50発を大きく下廻る数量しか身に付けていない様でした。
長篠の戦で銃は3000丁と言われた多数の銃が最短20秒毎に火を吐いたのは事実ですが、装備していた弾数が、20発では僅か400秒(約7分)程度で弾切れです。
戦いは8時間続き、1時間に2.5発しか撃たない(それでも3000丁なら1秒間に約2発)、予想イメージより遥かに静かな射撃戦だったと言えます。
ベトナム戦M16装備兵の210発でも、セミオートで1秒1発で撃ちまくれば、300秒程度で弾切れです。勿論何時の時代でも完全弾切れになる様な撃ち方はしません。
また武田側参加は15000名とされており、死者数は武田側1万名とされていますが、死傷者1万ならまだしもですが、死者に対し負傷者は少なく見て数倍、多く見て10倍程ある筈です。
通常は20%も戦死すれば完全な壊滅状態と言え、徹底的な追撃戦をしなければ、戦いはそれで 終わります。どうも「長篠の戦」は近代戦のイメージで歪曲されている様に感じました。
2.銃の発火方式の歴史。
2-1.火縄銃。
火の付いた火縄を発火薬に直接押し付ける方式の銃で、ヨーロッパの物は肩当ストックが付き、口径は18㎜前後が多く、火縄は引き金に連動してゆっくり降下しました。
日本に伝わったのはマラッカ製と言われていますが、肩当の無いストックと、火縄が引き金によってバネ仕掛けで落ちる物で、口径は撃ち易さと資材節約を重要視した12㎜前後が主流でした。
火縄銃の発火は確実ですが、点火は爆発ではなく着火ですから、遅発の可能性があり、また火縄に着火した状態でなければ撃つ事も出来ず、常時種火の携帯を必要とし、長時間待機は不可能であり、非常に不便な物でした。
勿論雨天は使用出来ない銃でした。また着火炎が伝わる小穴からガスの吹き戻し量も多く、燃焼効率も良いとは言えない構造でした。
2-2.燧石銃。
燧石をハンマーに咥え、金属の当て板をかすめて火花を得て、その火花が発火薬の中に飛び込むと言う物で、発火薬の燃焼効率が上がり、火縄式よりも遅発が少なく、何時でも何処でも撃てる優れ物でした。
初期には発火成功率問題がありましたが、改良によって克服され、ヨーロッパでは火縄銃の時代はすぐに終わり、燧石銃は完成の域に達し、200年以上の運用が続きました。
もう一つ大きな出来事は銃身が巻張りではなく、丸棒から穴を開けた銃身に換わり、銃その物が規格品となりました。
またバヨネット(銃剣)が装備された事も特徴の1つでした。これに対し、日本の銃は1品製造、銃兵は小刀のみの携帯、混戦時の戦力は大幅減となりました。
勿論先込め単発式は変わりませんが、18㎜と言うのは概ね現在のショットガンの12ゲージであり、散弾の運用も可能でした。
この近距離時に有効な散弾の運用も、日本は12㎜の小口径火縄銃が主力であり、散弾運用は出来ずでした。

燧石銃の射撃、発射煙と同量近いガスが漏れている。

ケンタッキーライフル
アメリカ西部開拓者と言えば、ピースメーカーと、ウインチェスターレバーアクション銃が想像されますが、それは西部開拓史末期の15年間だけ、西部開拓者は散弾も使えるマスケット銃、又は散弾には使えないが長射程のケンタッキーライフルでした。
アメリカの独立戦争はイギリス側ブラウンベスマスケット銃、対するアメリカ側はケンタッキーライフルでした。丸弾ながらライフリングを生かした、長射程の狙撃で応戦していました。

圧倒的銃不足の中、やがてフランスからシャルルビルマスケット銃が大量に供給され、勝利を掴む事が出来ました。

アメリカ軍は独立戦争に勝利し、勝った勢いでそのままフランス軍の植民地に雪崩れ込み、フランス軍も追い払ってしまいました。カナダ東部にフランス語圏がありますが、アメリカにないのはこの為です。
この時以来アメリカとフランスが犬猿の仲となりました。その後に制定されたアメリカ軍の制式はスプリングフィールド銃、それはシャルルビルをそのまま国産化した銃でした。
2-3.管打ち銃。
1807年、衝撃を与えると発火する雷汞が発明されました。色々な発火方法が試行錯誤され、1550年頃発火薬を塗込んだ銅のキャップをニップルに被せ、これを叩く方法に落ち着きました。
燧石銃を小改造で管打ち銃に改造出来る点もメリットでした。管打ち式の発火は100%確実になり、更に本銃からは全天候性となりました。
また強力な発火炎は後期には特殊な紙に包まれたままの火薬にも直接点火出来る様になり、不完全ながらカートリッジとなりました。

6連発のシリンダーを備えた物は現在の銃と同様の連発が可能となり、勿論ピストル型もありました。管打ち銃後半の新技術として、ライフリングの加工が普及し、口径15㎜のライフル銃となり、弾頭はドングリ型のミニエー弾となり、落差補正をすれば、射程距離が従来比で数倍に延長されました。

但し使用火薬が黒色火薬ですから、弾速は300m/sの程度、現在のサボットスラグ銃に少々至らない程度であり、急所狙いは落差補正をし、150m程度が限度と思われます。
パーカッション式はこうして多くの夢が叶い、何時でも何処でも撃て、且つ天候を問わない、絶対に確実な発火が可能となり、更に従来よりもライフリングとミニエー弾で圧倒的な高精度と長射程を得る事が出来ました。しかし小口径化した事とライフリングにより、散弾の共用が難しくなりました。

後述管打ち銃の射撃、発射ガスが殆ど漏れていない。
それで生まれたのが、専用の散弾銃でした。散弾に専用設計された銃は、銃身の肉厚も薄く、銃身長も短くなり、またチョークも1854年に発明 され、先込めではありましたが、概ね現在の散弾銃の近い性能の2連銃が生まれました。

銃が実用化されたのは1500年頃、黒色火薬で鉛の丸弾、勿論先込め、巻張銃身の火縄銃でした。
当時の先込め銃はノーライフルで丸弾、上半身ヒットの射程距離は僅か50mと短く、マグレ期待も 200mまででした。1発撃つと再装填に20秒程を要し、騎馬の走行速度からすると、必殺距離からの2発目は到底間に合わず、マグレ期待発砲でも2発目は限界付近、絶望的な大問題でした。
それでも銃は時代の最先端技術、戦争に利用され、この運用次第で勝敗の行方が変わりました。
1.信長の3段撃ち。
1543年、南蛮船が鹿児島県の種子島に漂着した事から、日本に火縄銃伝来する事となりました。そんな火縄銃を用いた著名な合戦の一つが、1575年の「織田信長」「徳川家康」連合軍と、「武田勝頼」軍の「長篠の戦い」でした。
結果は、織田信長が考案したとされる、火縄銃の戦術「三段撃ち」が決め手となり、織田・徳川連合軍の圧勝に終わりました。これを検証して見たいと思います。


上:国友筒 下:堺筒、
織田・徳川連合軍が準備した銃の数は3000丁だった事が通説になっています。
どうして大量の銃を揃える事が出来たかに付きましては、信長の眼力に加え、滋賀県長浜の国友や大阪の堺と言った銃の生産地を領地にした事が上げられます。
三段撃ちの基本的手順は、鉄砲隊を3列に分け、撃ち終わった1列目は後方に廻り、弾込め等の準備を行っている間に、2列目が発射、2列目も後方に下がり再装填、その間に3列目が発射、3列目が下がったその頃、再装填を終えた1列目が再び前に出て発射、これを繰り返しました。
当時の火縄銃の再装填には、再装填はまず銃口から火薬、次にパッチに包まれた丸弾を入れ、朔杖で奥まで押し込み、火鋏みを上げ、発火薬を火口に入れ、火蓋を閉じます。
そして火縄に息を吹き掛け、燃えカスを飛ばした火縄をセットします。
これで銃を構えて火蓋を開放し、引き金を引けば発火となり、所要時間は約20秒でした。
一方射程距離はノーライフルの丸弾ですから急所狙いは20m以内、人間の胴体に70%命中させられる距離は、50m程度でした。弾自体の飛行距離はMax.500m程度ですが、100mでは胴体に 10%しか命中せず、それ以遠で命中するのはマグレ弾だけとなりました。
一方武田の騎馬隊の走る速度は40~50㎞/h、秒速では10~15m/sでした。接近する武田軍の群にマグレ期待の200mから射撃しても、騎馬は装填完了前に来てしまい、間に合いません。
それで考え出されたのが。馬防柵後方からの三段撃ちと言えますが、火縄銃研究会の10名射撃でこれを試した所、10名が一斉射撃しようとすると、最も遅い射手の装填完了まで数秒 待たなくてはならず、10発一斉射の間隔は平均24秒となりました。
一方10丁個々が装填次第前に出て射撃すれば、平均20秒で10発射撃が可能でした。
どちらも時間当たりの発射数にベラボーな差はありませんが、3000丁で撃てば1秒間に150発が絶え間なく発射される事になります。
豪快な連続射撃に聞こえ、実戦では装填済み次第、200mの射撃で群れに向けて撃つ方法が採用された様子です。この射撃方法であれば、腕は関係無くなります。
稀にはそれをスリ抜け、至近距離まで来る場合もあります。概ね真直ぐ向かって来るにしても、動的を迎え撃つ事は通常の射撃術では困難と言え、しかもそれを確実に倒さなくてはならなくなります。
そうなりますと、この射撃には名人の腕が必要になります。当時は銃も弾も非常に貴重品ですから、十分な射撃訓練は出来る筈もなく、この場合の効率の良い射撃方法は、腕の良くない射手は弾込係に徹し、名人に装填済の銃を供給する方が、最も効率的と言えました。
今も昔も名人が生まれる確率は、100~1000人に1人程度です。
1-1.火縄銃兵の装備弾数。
ケンさんがカモ猟に行く時は何時も120発を身に付け、エゾ鹿猟に出掛ける時は身に付けているのは30発ですが、更に40発を荷物に入れていました。WW2の日本兵の装備は120発、WW2のアメリカのM1ガーランド兵は80発、M1カービン兵は135発、ベトナム戦M16兵は210発でした。




当時の火縄銃兵の装備弾数は調べる事が出来ませんでしたが、4つの画像が見付かりました。
左上の銃兵の場合ですと口径によっては、10~20発程度の早号ポーチを身に付けており、右上の場合は15発程度、左下の銃兵の場合は僅か8発しか身に付けていません。右下は現在の射撃用火縄銃の50発早号ケース、寸法は長さ19㎝・幅9㎝・高さ10㎝です。
つまりどう見ても50発を大きく下廻る数量しか身に付けていない様でした。
長篠の戦で銃は3000丁と言われた多数の銃が最短20秒毎に火を吐いたのは事実ですが、装備していた弾数が、20発では僅か400秒(約7分)程度で弾切れです。
戦いは8時間続き、1時間に2.5発しか撃たない(それでも3000丁なら1秒間に約2発)、予想イメージより遥かに静かな射撃戦だったと言えます。
ベトナム戦M16装備兵の210発でも、セミオートで1秒1発で撃ちまくれば、300秒程度で弾切れです。勿論何時の時代でも完全弾切れになる様な撃ち方はしません。
また武田側参加は15000名とされており、死者数は武田側1万名とされていますが、死傷者1万ならまだしもですが、死者に対し負傷者は少なく見て数倍、多く見て10倍程ある筈です。
通常は20%も戦死すれば完全な壊滅状態と言え、徹底的な追撃戦をしなければ、戦いはそれで 終わります。どうも「長篠の戦」は近代戦のイメージで歪曲されている様に感じました。
2.銃の発火方式の歴史。
2-1.火縄銃。
火の付いた火縄を発火薬に直接押し付ける方式の銃で、ヨーロッパの物は肩当ストックが付き、口径は18㎜前後が多く、火縄は引き金に連動してゆっくり降下しました。
日本に伝わったのはマラッカ製と言われていますが、肩当の無いストックと、火縄が引き金によってバネ仕掛けで落ちる物で、口径は撃ち易さと資材節約を重要視した12㎜前後が主流でした。
火縄銃の発火は確実ですが、点火は爆発ではなく着火ですから、遅発の可能性があり、また火縄に着火した状態でなければ撃つ事も出来ず、常時種火の携帯を必要とし、長時間待機は不可能であり、非常に不便な物でした。
勿論雨天は使用出来ない銃でした。また着火炎が伝わる小穴からガスの吹き戻し量も多く、燃焼効率も良いとは言えない構造でした。
2-2.燧石銃。
燧石をハンマーに咥え、金属の当て板をかすめて火花を得て、その火花が発火薬の中に飛び込むと言う物で、発火薬の燃焼効率が上がり、火縄式よりも遅発が少なく、何時でも何処でも撃てる優れ物でした。
初期には発火成功率問題がありましたが、改良によって克服され、ヨーロッパでは火縄銃の時代はすぐに終わり、燧石銃は完成の域に達し、200年以上の運用が続きました。
もう一つ大きな出来事は銃身が巻張りではなく、丸棒から穴を開けた銃身に換わり、銃その物が規格品となりました。
またバヨネット(銃剣)が装備された事も特徴の1つでした。これに対し、日本の銃は1品製造、銃兵は小刀のみの携帯、混戦時の戦力は大幅減となりました。
勿論先込め単発式は変わりませんが、18㎜と言うのは概ね現在のショットガンの12ゲージであり、散弾の運用も可能でした。
この近距離時に有効な散弾の運用も、日本は12㎜の小口径火縄銃が主力であり、散弾運用は出来ずでした。
燧石銃の射撃、発射煙と同量近いガスが漏れている。

ケンタッキーライフル
アメリカ西部開拓者と言えば、ピースメーカーと、ウインチェスターレバーアクション銃が想像されますが、それは西部開拓史末期の15年間だけ、西部開拓者は散弾も使えるマスケット銃、又は散弾には使えないが長射程のケンタッキーライフルでした。
アメリカの独立戦争はイギリス側ブラウンベスマスケット銃、対するアメリカ側はケンタッキーライフルでした。丸弾ながらライフリングを生かした、長射程の狙撃で応戦していました。

圧倒的銃不足の中、やがてフランスからシャルルビルマスケット銃が大量に供給され、勝利を掴む事が出来ました。

アメリカ軍は独立戦争に勝利し、勝った勢いでそのままフランス軍の植民地に雪崩れ込み、フランス軍も追い払ってしまいました。カナダ東部にフランス語圏がありますが、アメリカにないのはこの為です。
この時以来アメリカとフランスが犬猿の仲となりました。その後に制定されたアメリカ軍の制式はスプリングフィールド銃、それはシャルルビルをそのまま国産化した銃でした。
2-3.管打ち銃。
1807年、衝撃を与えると発火する雷汞が発明されました。色々な発火方法が試行錯誤され、1550年頃発火薬を塗込んだ銅のキャップをニップルに被せ、これを叩く方法に落ち着きました。
燧石銃を小改造で管打ち銃に改造出来る点もメリットでした。管打ち式の発火は100%確実になり、更に本銃からは全天候性となりました。
また強力な発火炎は後期には特殊な紙に包まれたままの火薬にも直接点火出来る様になり、不完全ながらカートリッジとなりました。

6連発のシリンダーを備えた物は現在の銃と同様の連発が可能となり、勿論ピストル型もありました。管打ち銃後半の新技術として、ライフリングの加工が普及し、口径15㎜のライフル銃となり、弾頭はドングリ型のミニエー弾となり、落差補正をすれば、射程距離が従来比で数倍に延長されました。

但し使用火薬が黒色火薬ですから、弾速は300m/sの程度、現在のサボットスラグ銃に少々至らない程度であり、急所狙いは落差補正をし、150m程度が限度と思われます。
パーカッション式はこうして多くの夢が叶い、何時でも何処でも撃て、且つ天候を問わない、絶対に確実な発火が可能となり、更に従来よりもライフリングとミニエー弾で圧倒的な高精度と長射程を得る事が出来ました。しかし小口径化した事とライフリングにより、散弾の共用が難しくなりました。

後述管打ち銃の射撃、発射ガスが殆ど漏れていない。
それで生まれたのが、専用の散弾銃でした。散弾に専用設計された銃は、銃身の肉厚も薄く、銃身長も短くなり、またチョークも1854年に発明 され、先込めではありましたが、概ね現在の散弾銃の近い性能の2連銃が生まれました。

Posted by little-ken
at 11:00
│銃と弾