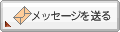2023年06月09日
虚像問題とスイングショット。
3.虚像と実体の位置ずれ。
動的を撃とうとすると、どうしてもこの虚像問題を避けて通れません。ヨチヨチ歩きの赤ちゃんにボールを投げると、通り過ぎてから捕ろうとしますが、あれが未学習の場合の本来の姿です。
やがて経験を積み、コースとタイミングを読んで、ボールを上手く手で捕れる様になります。
この学習は自然に行われますが、稀にこの学習が上手く進まない場合があり、これがスポーツ音痴になります。音痴は死んでも治らないと言われて来ましたが、ケンさんは高校時代の特訓により1年強で運動音痴を克服出来ました。その他の各種の音痴も必ず治せます。
虚像問題を発見したのは、ライフル銃によるエゾ鹿のウォーキング射撃の時でした。
ライフル銃をやるつもりのない人にも、役に立つ話ですから、聞いて下さい。
100m先を、ゆっくり歩く鹿の速度を3.6㎞/hと仮定します。何で半端な数字になるのか?
この速度が丁度秒速で1mになり、説明が付け易いからです。
ライフル弾の飛行速度は散弾より遥かに速く、キリの良い所で1000m/sとします。(本当はもう少し 遅い)、すると弾の100mの飛行時間は0.1秒、その間に鹿が移動する距離は10㎝となります。
10㎝ズレならば、間違っても鹿の胴体から外れる事は無い筈ですが、結果は誰が撃っても下図の様にケツの僅か後方に着弾、狙った所から誤差は1m強、逆算すると約1秒分と言う事になりました。
つまり光の速さは30万㎞/sですから無視出来ますが、網膜の映像を脳が理解するには時間を要し、更に脳が撃つと決断して指令を出しても、実際に弾が出るまでには時間を要します。そして弾の飛行時間が0.1秒、これらの合計が1秒強と言う事になりました。
そんなに時間を要しているとはとても思えませんが、誰が撃っても類似結果ですから、これは事実です。結局見えていたのは0.4~0.5秒古い虚像だった事になり、この時の虚像と実体の位置ズレは1秒分の1mだった事になります。
これで詳しい位置関係が分かりましたので、1m前、つまり顎よりもう少し前を撃てば命中します。
一方36㎞/hで走る鹿に対しては、銃を止めたまま狙うと10mも前を撃たないと命中しない事になり、事実上普通射撃では不可能と言う事になります。
ウォーキングエゾ鹿では、もう一つ方法があります。
ボール捕球はその手法と思われますが、照準が合ったと言う結果からではなく、間もなく合うと言う予測タイミングで引き金を引けば、これも命中します。後者の方が実用的です。
4.静止時は虚像と実体の位置は同じですが・・・・・
ライフル射撃は精密なじっくり狙いで撃つ事から、静止時専用の例外射撃と言えます。
一方止まっている目標を散弾銃のスナップショットで撃つ場合も、2つの位置関係は同じですから、見て撃てば命中します。しかし散弾銃は鳥猟がメインであり、静止射撃がメインではありません。
真直ぐ遠去かる飛び立ちの鳥もリードは僅かですから、鹿のウォーキングと同様に見て撃っても当たりそうなのですが、見ているのは古い虚像で在り、実体との差は約1秒分の1mであります。
パターンでカバー出来るのは±30㎝までですから、1mズレを無視すれば、ショットガンと言えども失中します。クレーの正面コースも同じで、簡単そうですが、難しいのです。
但し移動目標をリードゼロで正しく追尾をキープしたままで撃てば、虚像と実体の位置関係の差は存在しなくなります。実際の鹿のウォーキング射撃では弾の飛行時間が0.1秒あり、10㎝のリードが必要になります。
正面を低く飛ぶクレーもこの範疇になりますが、10㎝ならショットガンのパターンでカバー出来る範囲となり、結果的に命中します。この様に銃を追尾したまま撃てば命中しますが、銃を止めて撃てば失中となるのです。
5.リード射撃。
銃には反動があり、これを体が上手く処理しようとして、発射直前に体が勝手に硬くなり、身構えてしまいます。その結果、散弾銃では移動目標の命中に不可欠な追尾スイングが止まってしまう、引き止まり射撃に陥ります。
銃の反動は絶対に無くならず、身構えも生命的防衛反応ですから、この弊害を無くす事は特別な訓練をしない限り不可能です。従って残念ながら99%以上がこの反動トラブルに陥ります。
ショットガンの弾速は鳥の飛行速度に対して、余り速くなく、弾速を360m/sとし、鳥の飛行速度を36㎞/hとし、目標までの距離を36mと仮定しますとします。
弾の飛行時間は丁度0.1秒、鳥はその間に調度1m移動します。従って1m前を狙って追尾を継続していれば命中し、これがリード射撃になります。1m前ならそれほど難しくはありませんが、リードは鳥の飛行速度や射撃距離によって毎回大きく変わる欠点があります。
所が現実には99%が反動を予測して追尾スイングが止まってしまいますから、その分のリードを増さないと命中しません。その量は人間の反応遅れが0.4秒と仮定、スイングが一気に止まる訳ではなく、弊害分を半分の0.2秒としますと、引き止まり射撃は本来の3倍の3m前を狙わないと命中しない事になり、散弾でカバー出来るのは±0.2mですから、3m前はかなり高難度と言えます。
更に鳥が追い風に乗った高速遠射になりますと、飛行速度は先の仮定条件の約3倍になり、更に遠射の射程50mでは、リードは1.5倍強となります。合計しますと試算の4.5倍となり、引き止まり射撃ではリードが13.5m、その大きなリードを±0.3mに合わせる事は絶望的不可能になります。
高速遠射時は追尾スイングを継続するリード射撃でも、リードが4.5mとなり、リードを合わせる事は余りにも高難度となり、事実上リード射撃では高速遠射には対応出来ないと言う事になります。
つまり巷の引き止まり射撃のショットガンは、近距離時&低速時に限られますが、リード射撃なら飛躍的に命中率を向上させ、且つ中距離&中速まで、守備範囲の拡大が可能となります。
6.リード射撃の限界。
リード射撃は目標を見ながら射撃出来る点は有利なのですが、肝心のリードが飛行速度や距離により、甚だ大きく変化する欠点があります。更に鳥の飛行速度や射程距離の計測は目測ですから、少なく見ても±20%の誤差が含まれ、高速遠射の多いカモ猟では、リードを正確に合わせる事は絶望的となります。
高速遠射時の飛行速度と射程距離の計測が各々±20%の誤差で行われ、そのデータでリードの設定が±20%で行われると仮定、それぞれが均等分布と仮定、その結果±30㎝以内に入った時が命中と言う事にします。試算結果は、命中するのは300発に1発となりました。
実戦のカモデコイ猟に初心者3人を案内した事がありますが、初撃墜までに共に約300発を要しました。彼らは引き止まり射撃ですから必ずしも、上記のリード射撃の300発に1発とは条件設定が異なりますが、高速遠射では飛行速度や射程距離、そして必要リード等々の概ね全てが分かっていても、正味リード4.5m前後を命中させる事は想像より遥かに難しいのが現状なのです。
動的を撃とうとすると、どうしてもこの虚像問題を避けて通れません。ヨチヨチ歩きの赤ちゃんにボールを投げると、通り過ぎてから捕ろうとしますが、あれが未学習の場合の本来の姿です。
やがて経験を積み、コースとタイミングを読んで、ボールを上手く手で捕れる様になります。
この学習は自然に行われますが、稀にこの学習が上手く進まない場合があり、これがスポーツ音痴になります。音痴は死んでも治らないと言われて来ましたが、ケンさんは高校時代の特訓により1年強で運動音痴を克服出来ました。その他の各種の音痴も必ず治せます。
虚像問題を発見したのは、ライフル銃によるエゾ鹿のウォーキング射撃の時でした。
ライフル銃をやるつもりのない人にも、役に立つ話ですから、聞いて下さい。
100m先を、ゆっくり歩く鹿の速度を3.6㎞/hと仮定します。何で半端な数字になるのか?
この速度が丁度秒速で1mになり、説明が付け易いからです。
ライフル弾の飛行速度は散弾より遥かに速く、キリの良い所で1000m/sとします。(本当はもう少し 遅い)、すると弾の100mの飛行時間は0.1秒、その間に鹿が移動する距離は10㎝となります。
10㎝ズレならば、間違っても鹿の胴体から外れる事は無い筈ですが、結果は誰が撃っても下図の様にケツの僅か後方に着弾、狙った所から誤差は1m強、逆算すると約1秒分と言う事になりました。
つまり光の速さは30万㎞/sですから無視出来ますが、網膜の映像を脳が理解するには時間を要し、更に脳が撃つと決断して指令を出しても、実際に弾が出るまでには時間を要します。そして弾の飛行時間が0.1秒、これらの合計が1秒強と言う事になりました。
そんなに時間を要しているとはとても思えませんが、誰が撃っても類似結果ですから、これは事実です。結局見えていたのは0.4~0.5秒古い虚像だった事になり、この時の虚像と実体の位置ズレは1秒分の1mだった事になります。
これで詳しい位置関係が分かりましたので、1m前、つまり顎よりもう少し前を撃てば命中します。
一方36㎞/hで走る鹿に対しては、銃を止めたまま狙うと10mも前を撃たないと命中しない事になり、事実上普通射撃では不可能と言う事になります。
ウォーキングエゾ鹿では、もう一つ方法があります。
ボール捕球はその手法と思われますが、照準が合ったと言う結果からではなく、間もなく合うと言う予測タイミングで引き金を引けば、これも命中します。後者の方が実用的です。
4.静止時は虚像と実体の位置は同じですが・・・・・
ライフル射撃は精密なじっくり狙いで撃つ事から、静止時専用の例外射撃と言えます。
一方止まっている目標を散弾銃のスナップショットで撃つ場合も、2つの位置関係は同じですから、見て撃てば命中します。しかし散弾銃は鳥猟がメインであり、静止射撃がメインではありません。
真直ぐ遠去かる飛び立ちの鳥もリードは僅かですから、鹿のウォーキングと同様に見て撃っても当たりそうなのですが、見ているのは古い虚像で在り、実体との差は約1秒分の1mであります。
パターンでカバー出来るのは±30㎝までですから、1mズレを無視すれば、ショットガンと言えども失中します。クレーの正面コースも同じで、簡単そうですが、難しいのです。
但し移動目標をリードゼロで正しく追尾をキープしたままで撃てば、虚像と実体の位置関係の差は存在しなくなります。実際の鹿のウォーキング射撃では弾の飛行時間が0.1秒あり、10㎝のリードが必要になります。
正面を低く飛ぶクレーもこの範疇になりますが、10㎝ならショットガンのパターンでカバー出来る範囲となり、結果的に命中します。この様に銃を追尾したまま撃てば命中しますが、銃を止めて撃てば失中となるのです。
5.リード射撃。
銃には反動があり、これを体が上手く処理しようとして、発射直前に体が勝手に硬くなり、身構えてしまいます。その結果、散弾銃では移動目標の命中に不可欠な追尾スイングが止まってしまう、引き止まり射撃に陥ります。
銃の反動は絶対に無くならず、身構えも生命的防衛反応ですから、この弊害を無くす事は特別な訓練をしない限り不可能です。従って残念ながら99%以上がこの反動トラブルに陥ります。
ショットガンの弾速は鳥の飛行速度に対して、余り速くなく、弾速を360m/sとし、鳥の飛行速度を36㎞/hとし、目標までの距離を36mと仮定しますとします。
弾の飛行時間は丁度0.1秒、鳥はその間に調度1m移動します。従って1m前を狙って追尾を継続していれば命中し、これがリード射撃になります。1m前ならそれほど難しくはありませんが、リードは鳥の飛行速度や射撃距離によって毎回大きく変わる欠点があります。
所が現実には99%が反動を予測して追尾スイングが止まってしまいますから、その分のリードを増さないと命中しません。その量は人間の反応遅れが0.4秒と仮定、スイングが一気に止まる訳ではなく、弊害分を半分の0.2秒としますと、引き止まり射撃は本来の3倍の3m前を狙わないと命中しない事になり、散弾でカバー出来るのは±0.2mですから、3m前はかなり高難度と言えます。
更に鳥が追い風に乗った高速遠射になりますと、飛行速度は先の仮定条件の約3倍になり、更に遠射の射程50mでは、リードは1.5倍強となります。合計しますと試算の4.5倍となり、引き止まり射撃ではリードが13.5m、その大きなリードを±0.3mに合わせる事は絶望的不可能になります。
高速遠射時は追尾スイングを継続するリード射撃でも、リードが4.5mとなり、リードを合わせる事は余りにも高難度となり、事実上リード射撃では高速遠射には対応出来ないと言う事になります。
つまり巷の引き止まり射撃のショットガンは、近距離時&低速時に限られますが、リード射撃なら飛躍的に命中率を向上させ、且つ中距離&中速まで、守備範囲の拡大が可能となります。
6.リード射撃の限界。
リード射撃は目標を見ながら射撃出来る点は有利なのですが、肝心のリードが飛行速度や距離により、甚だ大きく変化する欠点があります。更に鳥の飛行速度や射程距離の計測は目測ですから、少なく見ても±20%の誤差が含まれ、高速遠射の多いカモ猟では、リードを正確に合わせる事は絶望的となります。
高速遠射時の飛行速度と射程距離の計測が各々±20%の誤差で行われ、そのデータでリードの設定が±20%で行われると仮定、それぞれが均等分布と仮定、その結果±30㎝以内に入った時が命中と言う事にします。試算結果は、命中するのは300発に1発となりました。
実戦のカモデコイ猟に初心者3人を案内した事がありますが、初撃墜までに共に約300発を要しました。彼らは引き止まり射撃ですから必ずしも、上記のリード射撃の300発に1発とは条件設定が異なりますが、高速遠射では飛行速度や射程距離、そして必要リード等々の概ね全てが分かっていても、正味リード4.5m前後を命中させる事は想像より遥かに難しいのが現状なのです。
Posted by little-ken
at 11:48
│銃と弾