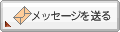2023年05月31日
最強の銃とスチール装弾と銅弾の真実。
14.最強の狩猟銃。
結論としてオートのライフルは、連射が得意と言う思い込みの塊であり、連射能力は想像より遥かに低いモノでした。写真のストレートボルトのブレーザーR93は肩付けのままの速い装填速度が自慢ですが、所詮オートの回転速度に敵う筈もなく、見失った目標の再補足が無くなる訳でもなく、オートよりも劣る連射が避けられません。

再肩付け射撃は反動により目標を見失なう事がなく、速い連射が可能だった様に思います。連射は目標を見失わない事が、最も重要でした。散弾の連射は目標を見失しなう事はなく、高速連射が可能で、散弾をバラ撒く50m以内のオートの連射には、ボルトライフルの再肩付連射は足元にも及びません。

写真のレミントンバックショット専用銃では本州鹿の巻狩り実質4年間、90回の出撃で、18チャンスから20頭(ダブル2回)を捕獲、出撃4.5回で1頭、射程内を通った鹿は全て捕獲、失中&未回収ゼロと言う快挙を達成しました。この様に散弾銃のバックショット運用は50m以内なら最強無敵ですが、50m以遠は不可能領域であり、その条件ならスコープ専用ボルト銃の天下となります。

ボルトアクション銃は1800年代末期に登場した旧式銃です。多くは指向性の全くないオープンサイトを装備し、体格無視の統一量産ストックを付け、頑丈さだけが取り柄の銃でした。オープンサイトの銃は、不適切なストック形状と、指向性の欠落から、不得意項目の多い銃でした。スナップショット、ランニングショット、連射、精密射撃、遠射、不得意項目は全項目に及びました。
しかし、ボルトアクション銃は、1960年代に奇跡の高性能銃として、生まれ変わりました。高精度バレルを付け、ストックを調整したスコープ専用銃は、150mワンホール射撃が可能となり、微少上向き発射により実用射程距離が2倍の300mとなり、不得意と思われていたスナップショットやランニングショットが得意となる、比類無き最強の狩猟銃となりました。
しかし動的射撃対応者は0.1%程度しかおらず、事実上ライフル銃に連射機能は不要と言えました。スクールの初期は連射を認めておりましたが、有効に機能した事は只の1度もなく、しばしば暴発を起こし危ないだけでした。それで強制的に単発運用に切り替えました。
結果、暴発事故は皆無となり、肝心の捕獲率では予想に反して向上しました。
暴発の原因はランニング射撃技術が無いのに、次に備えて無条件次弾装填をしてしまう事でした。一方単発運用の欠点は止矢が1~2秒遅れるだけですが、それによって回収不能となった例は皆無でした。と言う事で、通常射撃のライフル銃には連射機能が不要である事を証明出来ました。

散弾オートの狩猟銃はガス式のレミントン1100は1963年デビュー時から見ても、60年も銃自体の進化はありませんが、弾は1970年前後から、プラスチック薬莢を使った高速装弾(初速400m/s)に進化し、新装弾とフルチョークの組み合わせは絶大な効果を発揮しました。
1965年頃までの旧装弾は初速が300m/s、30~40mで弾速が低下し無効弾となりましたが、プラ薬莢弾で鴨なら射撃用7.5号弾、鹿なら4号バック27粒弾は50mまで無効化する事なく弾速を 維持、フルチョークの運用により、50m弱まで3粒被弾の散弾密度をキープ、圧倒的撃墜効率のショットガン効果により、鴨や鹿をバッタバッタと連続撃墜出来る、飛躍的に高性能な狩猟銃となりました。尚、本州鹿は20m前後の射程が多い為、それに合わせたチョークが最強となります。
15.スチール装弾。
スチール装弾は規制の前年の2000年にモニターユーザーとなり、1000発を試験運用しました。他のモニター者の意見は、全て鉛散弾に比べて大幅に墜ちないと言う評価でした。また、装弾メーカーの見解では、鉛時より1~2号大粒側を使えば、同等効果が期待出来ると言う見解でした。
1000発を試したケンさんの見解はまるで違いました。
スチール装弾は、30%多い弾粒により、撃墜の可能性を30%増す、これが本当の答えになります。但し、軽い弾粒は空気の抵抗による弾速低下が大きく、その分のリードを追加しないとパターンが後落し、パターンの端しかヒットしませんが、リードが合えば、弾粒に比例して良く墜ちます。
しかし最強弾は鉛の7.5号の430粒は、50mまで3粒被弾撃墜密度をキープ出来ましたが、この効果が期待出来るスチール弾は7号スチール(437粒)となりますが、残念ながらスチール弾は5号(248粒)より小粒はありません。
鉛の7.5号の様な、50mまで3粒被弾撃墜のショットガン効果は、スチール弾ではパターン中央部の散弾密度が特に濃い僅かな部分以外では望めない、これがもう1つの正しい答えとなります。
同時期に始まったライフル銃の非鉛弾の命中率&即倒率の大幅低下報告共々、巷のモニター ハンターの技術レベルは甚だお粗末でした。因みに、ケンさんの得意な学科は実験計測でしたが、これは物事の原理が良く分かっていないと、誤差を計測してしまいますが、これと同じでした。
16.ライフルの銅弾頭。
同様の事はライフルの銅弾頭のモニターにも言えました。
彼らの言葉をまとめれば、鉛弾に比べ命中率はかなり低下、貫通するだけで倒れないと言う評価でした。その為クマ猟に限り鉛弾の使用が許可されていた時期もありました。
ケンさんはこのモニターに参加しておりませんが、得られた結論は全く違う物でした。まず銅弾頭が生まれた経緯は、鉛弾頭には大きな欠陥があり、これを対策するのが目的でした。
その鉛弾頭の欠陥その1とは、近距離射撃でマッシュルーム効果が過剰に働き、表面爆発で鉛が全飛散し、威力を失う事でした。
欠陥その2としては骨にヒットすると同様に鉛が全飛散してしまう事でした。
その為、A型フレーム等のセパレート構造になった弾を使うか、重量低速弾のラウンドノーズを使う事によってこの欠陥を防いでおり、これを使わない鹿猟では骨の急所を避け、その結果半矢未回収が増えました。
実際に銅弾に切換り後、心臓狙いをすると、逃げられる確率はやや高い様にも見えました。しかし 肩甲骨と背骨の交点を撃つと、即倒率が抜群に高い事を突き止めました。
この場所を従来の鹿用鉛高速弾で撃てば、肩甲骨の表面で鉛の全飛散が起こり、間違いなく未回収となりますが、銅弾は飛散が起こらず、奥の脊髄にショックを与える為、概ね100%が即倒します。
そこで表面爆発しない銅弾の特徴を生かし、一段と高速軽量弾頭にする事により、150mで3発が11㎜の精度まで向上、銅弾だから精度が悪いと言う事は無くなり、積極的に骨の急所を狙う事により、即倒率は概ね100%と言える、銅弾様々になりました。
銅弾頭は当初180gr、続いて165gr、150grとなり、最終的に140grになりました。
命中精度は140grが150mで11㎜、即倒率は100%、ヒグマ450㎏も50m走られましたが、1発で死に至りました。
もはや銅弾頭が鉛弾頭に劣る項目は皆無となり、欠陥のある鉛弾頭は使う気が起こりません。
モニターユーザーの選定も、一般猟友会で多少捕獲数の多い程度では、シーズン10頭程度、そのクラスの一般人ハンターを何人揃え様が、正確な比較は難しいと思います。
ケンさんのエゾ鹿猟は年間500発以上を使用し、150頭以上を捕獲していました。
スチール装弾の頃は年間2000~3000発を主にカモ猟に使っており、1000羽前後を捕獲しており、誰もが否定したカモ猟には小粒の7.5号弾がベストである事を導き出しました。
7.5号弾はフルチョークと組合せれば、50mでもショットガン効果に必用な3粒被弾をキープする事が出来ました。多くの人が使用するインプシリンダーでは3粒被弾がキープ出来ず撃墜困難となり、7.5号弾は非力で使えないとする一般的結論からすれば、誰も信じない画期的な出来事でした。
カルガモやカラスの駆除でもケンさんのフルチョーク+7.5号弾+スイング射撃はインプシリンダー+6~3号+引止まり射撃の一般駆除者より1桁以上高い成果を上げ、一般駆除者もどの道、命中しない&撃墜出来ないならばで、弾代が半額以下で済む7.5号弾をやがて使う様になりました。
そしてこれにより流れ弾事故も減少し、撃墜率も弾粒数比例で多少増えました。
結論としてオートのライフルは、連射が得意と言う思い込みの塊であり、連射能力は想像より遥かに低いモノでした。写真のストレートボルトのブレーザーR93は肩付けのままの速い装填速度が自慢ですが、所詮オートの回転速度に敵う筈もなく、見失った目標の再補足が無くなる訳でもなく、オートよりも劣る連射が避けられません。

再肩付け射撃は反動により目標を見失なう事がなく、速い連射が可能だった様に思います。連射は目標を見失わない事が、最も重要でした。散弾の連射は目標を見失しなう事はなく、高速連射が可能で、散弾をバラ撒く50m以内のオートの連射には、ボルトライフルの再肩付連射は足元にも及びません。

写真のレミントンバックショット専用銃では本州鹿の巻狩り実質4年間、90回の出撃で、18チャンスから20頭(ダブル2回)を捕獲、出撃4.5回で1頭、射程内を通った鹿は全て捕獲、失中&未回収ゼロと言う快挙を達成しました。この様に散弾銃のバックショット運用は50m以内なら最強無敵ですが、50m以遠は不可能領域であり、その条件ならスコープ専用ボルト銃の天下となります。

ボルトアクション銃は1800年代末期に登場した旧式銃です。多くは指向性の全くないオープンサイトを装備し、体格無視の統一量産ストックを付け、頑丈さだけが取り柄の銃でした。オープンサイトの銃は、不適切なストック形状と、指向性の欠落から、不得意項目の多い銃でした。スナップショット、ランニングショット、連射、精密射撃、遠射、不得意項目は全項目に及びました。
しかし、ボルトアクション銃は、1960年代に奇跡の高性能銃として、生まれ変わりました。高精度バレルを付け、ストックを調整したスコープ専用銃は、150mワンホール射撃が可能となり、微少上向き発射により実用射程距離が2倍の300mとなり、不得意と思われていたスナップショットやランニングショットが得意となる、比類無き最強の狩猟銃となりました。
しかし動的射撃対応者は0.1%程度しかおらず、事実上ライフル銃に連射機能は不要と言えました。スクールの初期は連射を認めておりましたが、有効に機能した事は只の1度もなく、しばしば暴発を起こし危ないだけでした。それで強制的に単発運用に切り替えました。
結果、暴発事故は皆無となり、肝心の捕獲率では予想に反して向上しました。
暴発の原因はランニング射撃技術が無いのに、次に備えて無条件次弾装填をしてしまう事でした。一方単発運用の欠点は止矢が1~2秒遅れるだけですが、それによって回収不能となった例は皆無でした。と言う事で、通常射撃のライフル銃には連射機能が不要である事を証明出来ました。

散弾オートの狩猟銃はガス式のレミントン1100は1963年デビュー時から見ても、60年も銃自体の進化はありませんが、弾は1970年前後から、プラスチック薬莢を使った高速装弾(初速400m/s)に進化し、新装弾とフルチョークの組み合わせは絶大な効果を発揮しました。
1965年頃までの旧装弾は初速が300m/s、30~40mで弾速が低下し無効弾となりましたが、プラ薬莢弾で鴨なら射撃用7.5号弾、鹿なら4号バック27粒弾は50mまで無効化する事なく弾速を 維持、フルチョークの運用により、50m弱まで3粒被弾の散弾密度をキープ、圧倒的撃墜効率のショットガン効果により、鴨や鹿をバッタバッタと連続撃墜出来る、飛躍的に高性能な狩猟銃となりました。尚、本州鹿は20m前後の射程が多い為、それに合わせたチョークが最強となります。
15.スチール装弾。
スチール装弾は規制の前年の2000年にモニターユーザーとなり、1000発を試験運用しました。他のモニター者の意見は、全て鉛散弾に比べて大幅に墜ちないと言う評価でした。また、装弾メーカーの見解では、鉛時より1~2号大粒側を使えば、同等効果が期待出来ると言う見解でした。
1000発を試したケンさんの見解はまるで違いました。
スチール装弾は、30%多い弾粒により、撃墜の可能性を30%増す、これが本当の答えになります。但し、軽い弾粒は空気の抵抗による弾速低下が大きく、その分のリードを追加しないとパターンが後落し、パターンの端しかヒットしませんが、リードが合えば、弾粒に比例して良く墜ちます。
しかし最強弾は鉛の7.5号の430粒は、50mまで3粒被弾撃墜密度をキープ出来ましたが、この効果が期待出来るスチール弾は7号スチール(437粒)となりますが、残念ながらスチール弾は5号(248粒)より小粒はありません。
鉛の7.5号の様な、50mまで3粒被弾撃墜のショットガン効果は、スチール弾ではパターン中央部の散弾密度が特に濃い僅かな部分以外では望めない、これがもう1つの正しい答えとなります。
同時期に始まったライフル銃の非鉛弾の命中率&即倒率の大幅低下報告共々、巷のモニター ハンターの技術レベルは甚だお粗末でした。因みに、ケンさんの得意な学科は実験計測でしたが、これは物事の原理が良く分かっていないと、誤差を計測してしまいますが、これと同じでした。
16.ライフルの銅弾頭。
同様の事はライフルの銅弾頭のモニターにも言えました。
彼らの言葉をまとめれば、鉛弾に比べ命中率はかなり低下、貫通するだけで倒れないと言う評価でした。その為クマ猟に限り鉛弾の使用が許可されていた時期もありました。
ケンさんはこのモニターに参加しておりませんが、得られた結論は全く違う物でした。まず銅弾頭が生まれた経緯は、鉛弾頭には大きな欠陥があり、これを対策するのが目的でした。
その鉛弾頭の欠陥その1とは、近距離射撃でマッシュルーム効果が過剰に働き、表面爆発で鉛が全飛散し、威力を失う事でした。
欠陥その2としては骨にヒットすると同様に鉛が全飛散してしまう事でした。
その為、A型フレーム等のセパレート構造になった弾を使うか、重量低速弾のラウンドノーズを使う事によってこの欠陥を防いでおり、これを使わない鹿猟では骨の急所を避け、その結果半矢未回収が増えました。
実際に銅弾に切換り後、心臓狙いをすると、逃げられる確率はやや高い様にも見えました。しかし 肩甲骨と背骨の交点を撃つと、即倒率が抜群に高い事を突き止めました。
この場所を従来の鹿用鉛高速弾で撃てば、肩甲骨の表面で鉛の全飛散が起こり、間違いなく未回収となりますが、銅弾は飛散が起こらず、奥の脊髄にショックを与える為、概ね100%が即倒します。
そこで表面爆発しない銅弾の特徴を生かし、一段と高速軽量弾頭にする事により、150mで3発が11㎜の精度まで向上、銅弾だから精度が悪いと言う事は無くなり、積極的に骨の急所を狙う事により、即倒率は概ね100%と言える、銅弾様々になりました。
銅弾頭は当初180gr、続いて165gr、150grとなり、最終的に140grになりました。
命中精度は140grが150mで11㎜、即倒率は100%、ヒグマ450㎏も50m走られましたが、1発で死に至りました。
もはや銅弾頭が鉛弾頭に劣る項目は皆無となり、欠陥のある鉛弾頭は使う気が起こりません。
モニターユーザーの選定も、一般猟友会で多少捕獲数の多い程度では、シーズン10頭程度、そのクラスの一般人ハンターを何人揃え様が、正確な比較は難しいと思います。
ケンさんのエゾ鹿猟は年間500発以上を使用し、150頭以上を捕獲していました。
スチール装弾の頃は年間2000~3000発を主にカモ猟に使っており、1000羽前後を捕獲しており、誰もが否定したカモ猟には小粒の7.5号弾がベストである事を導き出しました。
7.5号弾はフルチョークと組合せれば、50mでもショットガン効果に必用な3粒被弾をキープする事が出来ました。多くの人が使用するインプシリンダーでは3粒被弾がキープ出来ず撃墜困難となり、7.5号弾は非力で使えないとする一般的結論からすれば、誰も信じない画期的な出来事でした。
カルガモやカラスの駆除でもケンさんのフルチョーク+7.5号弾+スイング射撃はインプシリンダー+6~3号+引止まり射撃の一般駆除者より1桁以上高い成果を上げ、一般駆除者もどの道、命中しない&撃墜出来ないならばで、弾代が半額以下で済む7.5号弾をやがて使う様になりました。
そしてこれにより流れ弾事故も減少し、撃墜率も弾粒数比例で多少増えました。
Posted by little-ken
at 17:57
│銃と弾