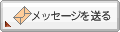2020年12月23日
種子島銃
2020年2月の予想ではもう治療方法はなく、そろそろ低空飛行も終わっている頃だったのですが、おかげ様で最後のダメ元治療には初めて効果があり、もう少し低空飛行が続けられる事になりました。
今回は鉄砲伝来の地として有名な種子島に行って来ました。琵琶湖畔の国友鉄砲の里資料館は銃専門の詳しい学芸員がいますが、種子島銃博物館は地元民俗資料館を兼ねており、普通の民族資料館と同様にパートのおばさんがいるだけ、残念ながら詳しい話を聞く事は出来ませんでした。
鉄砲伝来の時代背景ですが、1400年代の中頃から大航海時代が始まり、アフリカの多くはすでにヨーロッパ諸国の植民地になり、次のターゲットはアジア、そんな植民地開拓競争真っ只中と言える時代でした。
1.火縄銃の伝来。
通説では南蛮船(ポルトガル船)となっていますが、実は民国の貿易船団でした。
船団は明国(中国)の最南端の町の広東を出発した数日後、海賊に襲われバラバラになってしまい、その後に更に台風で大きなダメージを受け、10日程漂流の後、種子島の南側の一角に漂着しました。そしてその船には3人のポルトガル人が便乗しており、彼らは火縄銃を持っていました。
島の家老は乗船していた中国人と筆談し、事情を理解、近くの港まで手漕ぎ船12艘で曳航し、修理する事にしました。乗船していた百数十人は近くの寺に分散して滞在、結果としてその期間は修理が完了するまでの約半年間になりました。
領主の種子島時堯公はポルトガル人の銃に興味を持ち、試射に立会い驚愕、3匁半の弾(13g、直径約13.2㎜)は50m先の的にした大きな貝殻を粉々にしました。そしてその日以来、試射銃はずっと領主の種子島時堯公の手元に置かれ、ポルトガル人から聞いた射撃のコツを練習していました。
そして12日後、種子島時堯公自身による試射が行われ、弓の腕が余り良くなかった時堯公でも初弾で命中させられると言う、予想以上の成果を確認しました。

種子島時堯公はこの銃を譲って欲しいと申し出た所、お礼に差し上げると言う事になりましたが、そんな高額な物をタダで貰う訳にも行かず、家臣と相談して永楽銭2000疋を送りました。

疋(びき)は銭25枚が紐に通してある物で、2000疋は小判2.5両、1980年現在のお金にして25万円です。その結果、もう1丁の銃が種子島時堯公の手に届けられました。通説では2000両、1丁が1980年価格の約1億円だった事になります
こうして火縄銃の原型銃2丁は日本の所属となり、種子島時堯公は時の将軍足利義晴に伝来銃の1丁を献上しました。もう1丁は種子島筒の見本となり、以後は種子島家で大切に保存されて来ましたが、明治初期の1877年の戦火で焼失してしまいました。
写真は半年後の2度目の南蛮船で伝来した銃であり、口径は伝来1号銃と違い約18㎜です。この時にも複数の銃が持ち込まれたモノと思われます。
2.国産銃の始まり。
種子島時堯氏はすぐに刀鍛冶の八板金兵衛に同じ物を作る様に命じました。種子島は砂鉄を多く産出し、昔から鍛冶の仕事が盛んでした。金兵衛は苦労の末、銃身は何とか作り上げましたが、尾栓のネジを作る方法が分からず、結局は数か月後に尾栓を焼嵌めした物を作り上げました。

1544年早々、この完成直後の八板金兵衛作の銃は実戦に使われ、屋久島の奪回に成功しましたが、焼嵌めした尾栓が緩んで吹っ飛ぶ等々の欠陥銃でした。しかしこの戦果は尾ヒレが付き、種子島筒と共にあっと言う間に後に火縄銃の生産地となる大阪の堺や紀州の根来寺まで広がりました。
翌年再度訪れた南蛮船にはポルトガル人の鉄砲鍛冶が乗っており、彼から尾栓の作り方のみならず銃身の作り方を改めて学ぶ事が出来、ようやく種子島銃は完成の域となりました。
写真の銃は八板金兵衛作には間違いないのですが、国産第1号銃は伝来第1号銃と共に消失しており、その後に作った数十丁の中の1丁と思われます。
鉄砲の主要生産地は和泉の堺、紀州の根来、近江の国友と日野が有名です。
堺と根来には金兵衛の種子島筒がモデルとして持ち込まれ、国友には種子島時堯公が将軍に献上した銃が見本銃として示され、国友でも火縄銃の製造が1544年から始まりました。
3.火縄銃の種類。火縄銃は下記の種類がありました。
小筒:口径12㎜程度(30番村田)の物を指します。威力は低いが安価で反動が少ない為、猟銃や動員兵への支給銃として用いられました。また鉄砲による戦闘に不慣れな明・朝鮮の兵の防具は鉄砲に対する防御力が弱く、小筒でも十分な威力を持っていた為、朝鮮の役では大量に用いられました。
中筒:口径15.5㎜程度(20番)の物を指し、小筒に比べて威力が増大しますが、扱いが難しい上に高価なので、臨時雇いでなく、継続して主人に仕える足軽が用いる銃とされました。当世具足や竹束等の火縄銃に対応した防御装備が広まった結果、小筒に替わり主に用いられる様になりました。
士筒(さむらいづつ):口径18㎜程度(12番)の物を指します。威力は絶大ですが非常に高価、更に銃身が長く重量も重く、発射時は大きな反動があるなど扱いが難しい為、十分な鍛錬と財力を持つ侍のみが用いる事が出来ました。彼らはこの侍筒を武家奉公人に持たせ、必要に応じて用いました。
馬上筒:騎兵銃として用いられました。後世の騎兵銃と比べ銃身がより短く、拳銃に近い(ヨーロッパの胸甲騎兵の拳銃と同程度)でした。両手で扱います。
短筒:火縄銃版の拳銃。片手で扱う為に馬上筒よりも更に銃身を短くしていますが、馬上筒と同じく、騎兵銃として用いられました。火縄に常に火を点す必要上から懐に隠すのは困難であり、後世の拳銃の様な護身用、携帯用としての使用は困難であったと考えられます。
大鉄砲:口径23~40㎜クラスの銃であり、人力で撃てる限界でした。
差火点火式の地上設置型の大筒と異なり、抱え大筒とも言われ、銃床とカラクリを用いた火縄銃の体裁を持つ物を指す事が多い様です。こうした火器は通常の弾丸の他に棒火矢(ロケット弾)等を射出し、攻城戦・海戦で構造物を破壊・炎上する為に用いられました。
射撃する際の反動は強烈であり、射手は射撃時に自ら転がる事で反動を吸収する程でした。
その為命中の確実を期す場合は地面に据えて擲弾筒の様に撃ったり、射台に据えて用いました。
狭間筒:通常の筒に比べ、弾丸重量の割に銃身が長い物を指します。
城や船舶の鉄砲狭間(銃眼)に依託して射撃する用途の筒でした。有効射程は2~300mに及ぶとされます。
4.国産火縄銃の特徴。
1.日本は12㎜口径が主体、威力は海外の18㎜比で1/3の威力ですが、反動が小さく
撃ち易い銃でした。
2.長篠の戦(1575)の以降、銃が明らかに戦いの主力になったにも拘らず、
槍や刀をも持ち、余り戦い方を変えませんでした。
3.装填には竹筒に弾と1発分の火薬を入れた早号と言う物を使いました。
4.発射薬には別の小粒火薬を使用していました。
5.長い曲った小穴を通して自然引火を待つ発火方式の為、遅発を生じ易い構造にありました。
6.撃てば毎回吹っ飛ぶ火縄の再取り付けが必要でした。
7.銃兵を含み、役に立たない鎧を着用していました。
8.その為に銃を肩に当てる事が出来ずにストックの無い銃になりました。
9.日本では銃兵と他の兵科が完全に分かれており、銃兵は銃以外の武器を持たず、
また銃剣術と言う考えもありませんでした。
10.我が国には良い燧石が算出しなかった事もありますが、ずっと点火方式は火縄式の
ままでした。しかしこれは火薬の主材料の硝石は殆んどを輸入、弾丸の鉛もかなり
輸入していましたから、燧石だけを輸入しなかった点はおかしいと思います。
11.日本は砂鉄から木炭を使った「たたら製鉄」、低い生産量でした。
12.日本の銃身はずっと巻張り、銃身製造に3~10倍の手間暇を掛け、量産には不向きでした。
13.日本ではずっと規格品製造ではなく1品製造でした。
14.日本の火縄銃は発火方式も生産方式も約300年間改められる事はなく運用され続けました。
5.ヨーロッパの銃。


1.発火装置が何時でも何処でもすぐに撃てる銃燧石式のフリントロックに移行し、火縄銃は
ごく初期に使われたのみでした。雨に弱いのは火縄式と同様でした。
2.燧石は数発以上の連続使用に耐えられ、毎回を調整する火縄に比べれば有利と言えました。
3.口径は18㎜主体でした。従って遠くまで威力が期待出来ました。
4.銃には肩当のストックが必ず付いており、照準にも射撃にも大幅に有利でした。
5.兵は騎兵を除く全員が銃兵であり、装填が間に合わない時は銃剣で戦いました。
6.鎧は殆ど意味が無く、銃兵は着用していませんでした。
7.コークスを使った製鉄で大量の鉄を作っていました。
8.丸棒に穴を開けて銃身を作りました。7項と合わせて日本よりかなり量産が可能でした。
9.すでに1600年頃から規格品を製造し、互換性を目指していました。
10.産業革命後の1700年代の中場からは動力に蒸気機関を利用し、完全な互換性のある
銃の大量生産が可能でした。
11.すでに1600年頃から丸弾のライフル銃がありました。
12.弾丸型のミニエー弾とライフリングで1849年以降は命中率や射程が数倍に伸びました。
13.紙で包んだカートリッジを用いていました。紙は牛脂で防水され、紙を歯で噛み切り、
発射薬用に火皿に 少し入れ、残りを装填、紙はパッチの代わりとし、そのまま丸弾と
共にロッドで押し込みました。
14.点火が強力なパーカッション式の雷管となった1850年代以降には、酸化剤で処理した
紙に包んだままで発砲出来ました。また雨の日でも発射出来る様になりました。
6.火縄銃の射程と精度。
使うのは黒色火薬ですから必然的に低速弾となり、250m/s前後であったと思われます。
つまり黒色火薬の燃焼特性上から1900年代の村田銃や1960年代の水平2連銃で撃つ丸弾スラグ弾と同程度と考えて良さそうです。
古い時代だから銃身精度も低いと思われがちですが、少なくとも国友銃身では銃身内はまっすぐの真円でピカピカ、現在の散弾銃身に遜色のない仕上がりでした。
50mで特に出来の良い銃と弾であれば10㎝程度、通常の物では30㎝程度でした。
火縄銃の文献にも30mなら鎧の同を5発5中、50mでは5発4中との記載がありました。
従って1960年代までの散弾銃身から撃つ丸弾スラグ時代と余り変わらない精度でした。
照準は肩当ストックが無い火縄銃側が多少不利になり、反動によるフリンチングは今も昔も特に変わらず、精度を発揮させるにはそれなりの射撃技術を要しました。
弾丸は800m程飛びますが、確実に狙って撃てるのは30~50m、命中が期待出来るのは100~200m程度まででした。再装填には20秒程を要しますから、150mで第1弾を発射すると、歩兵でも第2弾発射は目前に迫って来る事になり、騎馬では2発目は間に合わない事になります。
その欠点を補う為に3つのグループに分けて行う3段撃ちが有名ですが、ケンさんは攻めて来る敵は動的であり、命中させるには特殊技能が必要ですから、助手2名が弾込めに徹し、専門の射手が撃ちまくるべきであると思います。
7.火縄銃の威力。
火縄銃は大きく分けて18㎜クラス、15㎜クラス、12㎜クラスの3つに分かれますが、これはちょうど12番、20番、30番村田と概ね同口径クラスになります。
現在の12番スラグは450m/s、2500ft-lbfの程度ですが、当時の18㎜は弾速250m/s、770ft-lbfの程度だったと思われます。1900年代の30番村田に至っては450ft-lbfの程度でしたから12㎜火縄は350ft-lbfの程度と思われます。
数字だけからしますと情けない程の非力さを感じますが、国内の多くの火縄銃が12㎜であった事を考えますと、結構使えるパワーを持っていたと思われます。
またクラスの弾速の丸弾は意外と貫通力が大きく、ケンさんは20番の7.5号弾を15㎜の丸弾に詰め替えて撃った処、推定弾速300m/sの丸弾は直径15㎝の杉の生丸太を貫通し、その貫通力にビックリしました。
当然鎧を貫通しますから、火縄銃が普及した後の鎧は余り意味を持たない物になりました。
8.火縄銃と燧石銃。
火縄銃は1500年前後から使い始められましたが、火縄に火が付いていなければ全く役に立たず、種火の保持が大変であり、ヨーロッパでは何時でも何処でもすぐに使える発火方法を模索しました。
そしてヤスリ車に燧石を擦り付けて発火させるホイールロックや、当て金に燧石を掠める様に当てるフリントロックは初期の試行錯誤時代を超えて1600年頃に概ね完成、1850年代までずっと長らく使われ続けました。
少し絶妙な話になりますが、2つの銃はどちらが確実に発火出来、よく当たったのか?
確実な発火に付きましては火縄の方がやや上と言えますが、着火から弾が出るまでの時間遅れは燧石式の方が速く且つ安定していました。
銃の照準はブレていますからその弾が出るまでの時間が速く且つ安定している事は高命中率の必要条件でした。実際に火縄銃の発砲を見た事がありますが、着火から弾が出るまでには少し時間遅れがありました。

火縄銃は引き金を引く事により、火挟みが火皿の発火専用の小粒火薬に向かってバネ仕掛けで落下、そして着火となりますが、主火薬引火までは1㎜程度の長さ20㎜弱の子穴を通して自然引火待ちでした。その為に遅発が起こりがちで発砲までの時間もやや不安定でした。


フリントロック式ではフリントがフリッツェンに当たりながら、フリッツェンを1度開けて主火薬と同じ粒の発火薬に火花を投入、発火薬の燃焼が始まり、動画にはありませんが、その頃1度開いたフリッツェンが跳ね返ってパンの蓋をして主火薬室への小穴を通して燃焼中の火流を吹き込みます。
小穴の長さが10mm以下と短い点も有利に働きます。この為に主火薬の燃焼は速く始まり、その時間遅れも僅かとなり、且つ安定するのです。
一方でフリントロック式は強力なハンマーが不可欠であり、これをロックする引金も重くなり、またハンマーが落ちる時の衝撃も命中率を低下させる方向にありますが、これらは何時も一定ですから、燃焼が不安定な火縄式より高精度な射撃が可能になるのです。
フリント式の安全装置はハンマーのハーフコックです。その位置では引金を引けませんが、ハンマーをフルコックすれば何時でも撃てます。これに対し火縄式では火蓋があります。
この火蓋が不用意に開かない様に普段は紙縒り等で縛ってあり、この紐を切る事を戦いの火蓋を切ると言います。火蓋が不用意に開いてしまう事も、紙縒りが切れてしまう事も余り変わりない様に思えます。この辺から安全装置を信用してはならないと言う、間違った教えが出来たのかも知れません。
9.パーカッション式。

何時でも何処でもどんな天候でも本当に撃てる様になったのは1850年頃から実用化されたパーカッション式です。モデルがン用のプラキャップの様な構造で銅キャップの中に発射薬が塗り込んであり、これをニップルに被せてハンマーで叩けば、確実な発火が起こり、火炎は主火薬室に強く吹き込みます。


ライフリングと弾丸型の弾で命中精度も大幅に向上しました。更に従来は火門口から大量のガスが噴き出し、擦れは無視できない程の量でしたが、雷管キャップのお陰でガス漏れは非常に僅かとなりました。
また雷管キャップと新アイデアの防水紙に包まれたカートリッジのお陰で雨中でも発火出来る様になりました。発火炎は一段と強力に燃焼室に吹き込み、紙に包まれたままの火薬に火を付ける事が出来たのです。
パーカッション式のもう1つの利点は従来のフリント式から容易に改造出来た事です。
写真もフリント式からの改造銃です。日本の火縄銃も末期には多数がパーカッション式に改造されました。
また1850年頃からは新技術ラッシュ、弾丸型のミニエー弾とライフリングで射程2倍1849、リムファイアー弾連発銃1849、センターファイアー弾1864、ウインチェスターレバーアクション銃とコルトピースメーカーコンビ1873、無煙火薬により弾速2倍以上1884、そして1900年前後に今の銃と弾薬が出揃いました。

モーゼルは1898年、アメリカの30-06は1906年です。100mの急所が狙える様になりました。
写真はモーゼル1898です。
その後の銃の改良は1950年頃から丈夫な合金鋼がデビュー、1970年頃からはNC加工が進み、基本原理は変わりませんが、両者を前提とした新設計の銃に置き換わりました。銃身はコールドハンマー式に換わり、ライフルスコープ付が一般化し、精度の良い銃であれば300mの遠射も夢ではなくなりました。
連射連発は1500年頃からの憧れでした。故に1970年前後には狩猟用のオートが各種デビューしました。しかしライフル銃は100m超えを狙うには銃を安定させ、きっちり狙う必要があり、アバウト照準連射のショットガンと違い、かなり難度の高い物でした。
(要はショットガン的な射法ではライフル銃は当たらないのです。)
一方で動的には銃のスイングを止めないで狙わなければならず、銃を止めた通常射撃の精密照準とは全く異質の物でした。早い話がライフルの自動銃は使いこなせない役に立たない銃の代表格と言えました。
どの道で行っても連射の意味が無ければ、精度の良いボルト銃が1番候補です。現在の銃は長い間の夢であった100mで1ホール射撃や、300mの遠射が可能ですが、これを出せる人は現状では非常に僅かです。
原因はフリンチング処理が不完全である事、そして射撃時に心の平静度が不足している事の2つだけです。たった2つだけですから、しぶとく諦めなければ誰でも必ず達成できると信じます。
ぜひチャレンジをして下さい。
今回は鉄砲伝来の地として有名な種子島に行って来ました。琵琶湖畔の国友鉄砲の里資料館は銃専門の詳しい学芸員がいますが、種子島銃博物館は地元民俗資料館を兼ねており、普通の民族資料館と同様にパートのおばさんがいるだけ、残念ながら詳しい話を聞く事は出来ませんでした。
鉄砲伝来の時代背景ですが、1400年代の中頃から大航海時代が始まり、アフリカの多くはすでにヨーロッパ諸国の植民地になり、次のターゲットはアジア、そんな植民地開拓競争真っ只中と言える時代でした。
1.火縄銃の伝来。
通説では南蛮船(ポルトガル船)となっていますが、実は民国の貿易船団でした。
船団は明国(中国)の最南端の町の広東を出発した数日後、海賊に襲われバラバラになってしまい、その後に更に台風で大きなダメージを受け、10日程漂流の後、種子島の南側の一角に漂着しました。そしてその船には3人のポルトガル人が便乗しており、彼らは火縄銃を持っていました。
島の家老は乗船していた中国人と筆談し、事情を理解、近くの港まで手漕ぎ船12艘で曳航し、修理する事にしました。乗船していた百数十人は近くの寺に分散して滞在、結果としてその期間は修理が完了するまでの約半年間になりました。
領主の種子島時堯公はポルトガル人の銃に興味を持ち、試射に立会い驚愕、3匁半の弾(13g、直径約13.2㎜)は50m先の的にした大きな貝殻を粉々にしました。そしてその日以来、試射銃はずっと領主の種子島時堯公の手元に置かれ、ポルトガル人から聞いた射撃のコツを練習していました。
そして12日後、種子島時堯公自身による試射が行われ、弓の腕が余り良くなかった時堯公でも初弾で命中させられると言う、予想以上の成果を確認しました。

種子島時堯公はこの銃を譲って欲しいと申し出た所、お礼に差し上げると言う事になりましたが、そんな高額な物をタダで貰う訳にも行かず、家臣と相談して永楽銭2000疋を送りました。

疋(びき)は銭25枚が紐に通してある物で、2000疋は小判2.5両、1980年現在のお金にして25万円です。その結果、もう1丁の銃が種子島時堯公の手に届けられました。通説では2000両、1丁が1980年価格の約1億円だった事になります
こうして火縄銃の原型銃2丁は日本の所属となり、種子島時堯公は時の将軍足利義晴に伝来銃の1丁を献上しました。もう1丁は種子島筒の見本となり、以後は種子島家で大切に保存されて来ましたが、明治初期の1877年の戦火で焼失してしまいました。
写真は半年後の2度目の南蛮船で伝来した銃であり、口径は伝来1号銃と違い約18㎜です。この時にも複数の銃が持ち込まれたモノと思われます。
2.国産銃の始まり。
種子島時堯氏はすぐに刀鍛冶の八板金兵衛に同じ物を作る様に命じました。種子島は砂鉄を多く産出し、昔から鍛冶の仕事が盛んでした。金兵衛は苦労の末、銃身は何とか作り上げましたが、尾栓のネジを作る方法が分からず、結局は数か月後に尾栓を焼嵌めした物を作り上げました。

1544年早々、この完成直後の八板金兵衛作の銃は実戦に使われ、屋久島の奪回に成功しましたが、焼嵌めした尾栓が緩んで吹っ飛ぶ等々の欠陥銃でした。しかしこの戦果は尾ヒレが付き、種子島筒と共にあっと言う間に後に火縄銃の生産地となる大阪の堺や紀州の根来寺まで広がりました。
翌年再度訪れた南蛮船にはポルトガル人の鉄砲鍛冶が乗っており、彼から尾栓の作り方のみならず銃身の作り方を改めて学ぶ事が出来、ようやく種子島銃は完成の域となりました。
写真の銃は八板金兵衛作には間違いないのですが、国産第1号銃は伝来第1号銃と共に消失しており、その後に作った数十丁の中の1丁と思われます。
鉄砲の主要生産地は和泉の堺、紀州の根来、近江の国友と日野が有名です。
堺と根来には金兵衛の種子島筒がモデルとして持ち込まれ、国友には種子島時堯公が将軍に献上した銃が見本銃として示され、国友でも火縄銃の製造が1544年から始まりました。
3.火縄銃の種類。火縄銃は下記の種類がありました。
小筒:口径12㎜程度(30番村田)の物を指します。威力は低いが安価で反動が少ない為、猟銃や動員兵への支給銃として用いられました。また鉄砲による戦闘に不慣れな明・朝鮮の兵の防具は鉄砲に対する防御力が弱く、小筒でも十分な威力を持っていた為、朝鮮の役では大量に用いられました。
中筒:口径15.5㎜程度(20番)の物を指し、小筒に比べて威力が増大しますが、扱いが難しい上に高価なので、臨時雇いでなく、継続して主人に仕える足軽が用いる銃とされました。当世具足や竹束等の火縄銃に対応した防御装備が広まった結果、小筒に替わり主に用いられる様になりました。
士筒(さむらいづつ):口径18㎜程度(12番)の物を指します。威力は絶大ですが非常に高価、更に銃身が長く重量も重く、発射時は大きな反動があるなど扱いが難しい為、十分な鍛錬と財力を持つ侍のみが用いる事が出来ました。彼らはこの侍筒を武家奉公人に持たせ、必要に応じて用いました。
馬上筒:騎兵銃として用いられました。後世の騎兵銃と比べ銃身がより短く、拳銃に近い(ヨーロッパの胸甲騎兵の拳銃と同程度)でした。両手で扱います。
短筒:火縄銃版の拳銃。片手で扱う為に馬上筒よりも更に銃身を短くしていますが、馬上筒と同じく、騎兵銃として用いられました。火縄に常に火を点す必要上から懐に隠すのは困難であり、後世の拳銃の様な護身用、携帯用としての使用は困難であったと考えられます。
大鉄砲:口径23~40㎜クラスの銃であり、人力で撃てる限界でした。
差火点火式の地上設置型の大筒と異なり、抱え大筒とも言われ、銃床とカラクリを用いた火縄銃の体裁を持つ物を指す事が多い様です。こうした火器は通常の弾丸の他に棒火矢(ロケット弾)等を射出し、攻城戦・海戦で構造物を破壊・炎上する為に用いられました。
射撃する際の反動は強烈であり、射手は射撃時に自ら転がる事で反動を吸収する程でした。
その為命中の確実を期す場合は地面に据えて擲弾筒の様に撃ったり、射台に据えて用いました。
狭間筒:通常の筒に比べ、弾丸重量の割に銃身が長い物を指します。
城や船舶の鉄砲狭間(銃眼)に依託して射撃する用途の筒でした。有効射程は2~300mに及ぶとされます。
4.国産火縄銃の特徴。
1.日本は12㎜口径が主体、威力は海外の18㎜比で1/3の威力ですが、反動が小さく
撃ち易い銃でした。
2.長篠の戦(1575)の以降、銃が明らかに戦いの主力になったにも拘らず、
槍や刀をも持ち、余り戦い方を変えませんでした。
3.装填には竹筒に弾と1発分の火薬を入れた早号と言う物を使いました。
4.発射薬には別の小粒火薬を使用していました。
5.長い曲った小穴を通して自然引火を待つ発火方式の為、遅発を生じ易い構造にありました。
6.撃てば毎回吹っ飛ぶ火縄の再取り付けが必要でした。
7.銃兵を含み、役に立たない鎧を着用していました。
8.その為に銃を肩に当てる事が出来ずにストックの無い銃になりました。
9.日本では銃兵と他の兵科が完全に分かれており、銃兵は銃以外の武器を持たず、
また銃剣術と言う考えもありませんでした。
10.我が国には良い燧石が算出しなかった事もありますが、ずっと点火方式は火縄式の
ままでした。しかしこれは火薬の主材料の硝石は殆んどを輸入、弾丸の鉛もかなり
輸入していましたから、燧石だけを輸入しなかった点はおかしいと思います。
11.日本は砂鉄から木炭を使った「たたら製鉄」、低い生産量でした。
12.日本の銃身はずっと巻張り、銃身製造に3~10倍の手間暇を掛け、量産には不向きでした。
13.日本ではずっと規格品製造ではなく1品製造でした。
14.日本の火縄銃は発火方式も生産方式も約300年間改められる事はなく運用され続けました。
5.ヨーロッパの銃。


1.発火装置が何時でも何処でもすぐに撃てる銃燧石式のフリントロックに移行し、火縄銃は
ごく初期に使われたのみでした。雨に弱いのは火縄式と同様でした。
2.燧石は数発以上の連続使用に耐えられ、毎回を調整する火縄に比べれば有利と言えました。
3.口径は18㎜主体でした。従って遠くまで威力が期待出来ました。
4.銃には肩当のストックが必ず付いており、照準にも射撃にも大幅に有利でした。
5.兵は騎兵を除く全員が銃兵であり、装填が間に合わない時は銃剣で戦いました。
6.鎧は殆ど意味が無く、銃兵は着用していませんでした。
7.コークスを使った製鉄で大量の鉄を作っていました。
8.丸棒に穴を開けて銃身を作りました。7項と合わせて日本よりかなり量産が可能でした。
9.すでに1600年頃から規格品を製造し、互換性を目指していました。
10.産業革命後の1700年代の中場からは動力に蒸気機関を利用し、完全な互換性のある
銃の大量生産が可能でした。
11.すでに1600年頃から丸弾のライフル銃がありました。
12.弾丸型のミニエー弾とライフリングで1849年以降は命中率や射程が数倍に伸びました。
13.紙で包んだカートリッジを用いていました。紙は牛脂で防水され、紙を歯で噛み切り、
発射薬用に火皿に 少し入れ、残りを装填、紙はパッチの代わりとし、そのまま丸弾と
共にロッドで押し込みました。
14.点火が強力なパーカッション式の雷管となった1850年代以降には、酸化剤で処理した
紙に包んだままで発砲出来ました。また雨の日でも発射出来る様になりました。
6.火縄銃の射程と精度。
使うのは黒色火薬ですから必然的に低速弾となり、250m/s前後であったと思われます。
つまり黒色火薬の燃焼特性上から1900年代の村田銃や1960年代の水平2連銃で撃つ丸弾スラグ弾と同程度と考えて良さそうです。
古い時代だから銃身精度も低いと思われがちですが、少なくとも国友銃身では銃身内はまっすぐの真円でピカピカ、現在の散弾銃身に遜色のない仕上がりでした。
50mで特に出来の良い銃と弾であれば10㎝程度、通常の物では30㎝程度でした。
火縄銃の文献にも30mなら鎧の同を5発5中、50mでは5発4中との記載がありました。
従って1960年代までの散弾銃身から撃つ丸弾スラグ時代と余り変わらない精度でした。
照準は肩当ストックが無い火縄銃側が多少不利になり、反動によるフリンチングは今も昔も特に変わらず、精度を発揮させるにはそれなりの射撃技術を要しました。
弾丸は800m程飛びますが、確実に狙って撃てるのは30~50m、命中が期待出来るのは100~200m程度まででした。再装填には20秒程を要しますから、150mで第1弾を発射すると、歩兵でも第2弾発射は目前に迫って来る事になり、騎馬では2発目は間に合わない事になります。
その欠点を補う為に3つのグループに分けて行う3段撃ちが有名ですが、ケンさんは攻めて来る敵は動的であり、命中させるには特殊技能が必要ですから、助手2名が弾込めに徹し、専門の射手が撃ちまくるべきであると思います。
7.火縄銃の威力。
火縄銃は大きく分けて18㎜クラス、15㎜クラス、12㎜クラスの3つに分かれますが、これはちょうど12番、20番、30番村田と概ね同口径クラスになります。
現在の12番スラグは450m/s、2500ft-lbfの程度ですが、当時の18㎜は弾速250m/s、770ft-lbfの程度だったと思われます。1900年代の30番村田に至っては450ft-lbfの程度でしたから12㎜火縄は350ft-lbfの程度と思われます。
数字だけからしますと情けない程の非力さを感じますが、国内の多くの火縄銃が12㎜であった事を考えますと、結構使えるパワーを持っていたと思われます。
またクラスの弾速の丸弾は意外と貫通力が大きく、ケンさんは20番の7.5号弾を15㎜の丸弾に詰め替えて撃った処、推定弾速300m/sの丸弾は直径15㎝の杉の生丸太を貫通し、その貫通力にビックリしました。
当然鎧を貫通しますから、火縄銃が普及した後の鎧は余り意味を持たない物になりました。
8.火縄銃と燧石銃。
火縄銃は1500年前後から使い始められましたが、火縄に火が付いていなければ全く役に立たず、種火の保持が大変であり、ヨーロッパでは何時でも何処でもすぐに使える発火方法を模索しました。
そしてヤスリ車に燧石を擦り付けて発火させるホイールロックや、当て金に燧石を掠める様に当てるフリントロックは初期の試行錯誤時代を超えて1600年頃に概ね完成、1850年代までずっと長らく使われ続けました。
少し絶妙な話になりますが、2つの銃はどちらが確実に発火出来、よく当たったのか?
確実な発火に付きましては火縄の方がやや上と言えますが、着火から弾が出るまでの時間遅れは燧石式の方が速く且つ安定していました。
銃の照準はブレていますからその弾が出るまでの時間が速く且つ安定している事は高命中率の必要条件でした。実際に火縄銃の発砲を見た事がありますが、着火から弾が出るまでには少し時間遅れがありました。

火縄銃は引き金を引く事により、火挟みが火皿の発火専用の小粒火薬に向かってバネ仕掛けで落下、そして着火となりますが、主火薬引火までは1㎜程度の長さ20㎜弱の子穴を通して自然引火待ちでした。その為に遅発が起こりがちで発砲までの時間もやや不安定でした。


フリントロック式ではフリントがフリッツェンに当たりながら、フリッツェンを1度開けて主火薬と同じ粒の発火薬に火花を投入、発火薬の燃焼が始まり、動画にはありませんが、その頃1度開いたフリッツェンが跳ね返ってパンの蓋をして主火薬室への小穴を通して燃焼中の火流を吹き込みます。
小穴の長さが10mm以下と短い点も有利に働きます。この為に主火薬の燃焼は速く始まり、その時間遅れも僅かとなり、且つ安定するのです。
一方でフリントロック式は強力なハンマーが不可欠であり、これをロックする引金も重くなり、またハンマーが落ちる時の衝撃も命中率を低下させる方向にありますが、これらは何時も一定ですから、燃焼が不安定な火縄式より高精度な射撃が可能になるのです。
フリント式の安全装置はハンマーのハーフコックです。その位置では引金を引けませんが、ハンマーをフルコックすれば何時でも撃てます。これに対し火縄式では火蓋があります。
この火蓋が不用意に開かない様に普段は紙縒り等で縛ってあり、この紐を切る事を戦いの火蓋を切ると言います。火蓋が不用意に開いてしまう事も、紙縒りが切れてしまう事も余り変わりない様に思えます。この辺から安全装置を信用してはならないと言う、間違った教えが出来たのかも知れません。
9.パーカッション式。

何時でも何処でもどんな天候でも本当に撃てる様になったのは1850年頃から実用化されたパーカッション式です。モデルがン用のプラキャップの様な構造で銅キャップの中に発射薬が塗り込んであり、これをニップルに被せてハンマーで叩けば、確実な発火が起こり、火炎は主火薬室に強く吹き込みます。

ライフリングと弾丸型の弾で命中精度も大幅に向上しました。更に従来は火門口から大量のガスが噴き出し、擦れは無視できない程の量でしたが、雷管キャップのお陰でガス漏れは非常に僅かとなりました。
また雷管キャップと新アイデアの防水紙に包まれたカートリッジのお陰で雨中でも発火出来る様になりました。発火炎は一段と強力に燃焼室に吹き込み、紙に包まれたままの火薬に火を付ける事が出来たのです。
パーカッション式のもう1つの利点は従来のフリント式から容易に改造出来た事です。
写真もフリント式からの改造銃です。日本の火縄銃も末期には多数がパーカッション式に改造されました。
また1850年頃からは新技術ラッシュ、弾丸型のミニエー弾とライフリングで射程2倍1849、リムファイアー弾連発銃1849、センターファイアー弾1864、ウインチェスターレバーアクション銃とコルトピースメーカーコンビ1873、無煙火薬により弾速2倍以上1884、そして1900年前後に今の銃と弾薬が出揃いました。

モーゼルは1898年、アメリカの30-06は1906年です。100mの急所が狙える様になりました。
写真はモーゼル1898です。
その後の銃の改良は1950年頃から丈夫な合金鋼がデビュー、1970年頃からはNC加工が進み、基本原理は変わりませんが、両者を前提とした新設計の銃に置き換わりました。銃身はコールドハンマー式に換わり、ライフルスコープ付が一般化し、精度の良い銃であれば300mの遠射も夢ではなくなりました。
連射連発は1500年頃からの憧れでした。故に1970年前後には狩猟用のオートが各種デビューしました。しかしライフル銃は100m超えを狙うには銃を安定させ、きっちり狙う必要があり、アバウト照準連射のショットガンと違い、かなり難度の高い物でした。
(要はショットガン的な射法ではライフル銃は当たらないのです。)
一方で動的には銃のスイングを止めないで狙わなければならず、銃を止めた通常射撃の精密照準とは全く異質の物でした。早い話がライフルの自動銃は使いこなせない役に立たない銃の代表格と言えました。
どの道で行っても連射の意味が無ければ、精度の良いボルト銃が1番候補です。現在の銃は長い間の夢であった100mで1ホール射撃や、300mの遠射が可能ですが、これを出せる人は現状では非常に僅かです。
原因はフリンチング処理が不完全である事、そして射撃時に心の平静度が不足している事の2つだけです。たった2つだけですから、しぶとく諦めなければ誰でも必ず達成できると信じます。
ぜひチャレンジをして下さい。
Posted by little-ken
at 10:03
│銃と弾