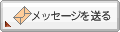2020年12月12日
ランドクルーザー
アメリカがWW2を勝ち取った理由は下記の様に幾つかが挙げられます。
レーダー、VTヒューズ、護衛空母、FM2戦闘機、P51戦闘機、B17&B29戦略爆撃機、M4シャーマン戦車、自動小銃ガーランド、バズーカ砲、そしてジープです。日本は全体的な工業生産量を始めとして、残念ながら1つとして勝てませんでした。
この方面の個別のお話も面白いのですが、それぞれが長くなりますので、また別の機会にしたいと思います。
米軍のターボチャージャーはWW2の初期からB-17等ですでに実用化していましたが、日本では研究室から出られませんでした。
同様にメッサーシュミットのダイムラーエンジンはアンダーライセンスで日本に持ち込まれましたが、飛燕も彗星もまともに稼働出来ず、スピットファイアのロールスロイスのエンジンがアンダーライセンスでアメリカのP51マスタングのエンジンとして大活躍したのとは対照的です。
良質な鉄製品には良い合金と熱処理が不可欠なのですが、1970年以前の日本製品はベースとなる鉄の純度が低く、良い合金が出来ませんでした。その為、まともなエンジンや自動車が出来なかったのです。
1970年頃以降は鉄が良くなり、やがて日本製品は高品質の代表格になりました。そんな中で日本車、特にジープ型のランドクルーザーが世界に誇れる製品に育った事はトヨタの車両エンジニアだった1人として嬉しく思います。
JEEP:ウイリスMB型とフォードGPW型があり、基本設計はバンタムでしたが、量産はウイリスとフォードが行いました。1940年にはバンタム増加試作車を試験配備、1941年にはバンタムのBRC-40型やウイリスMA型とフォードGP型が実戦投入されました。
1942年からは共通仕様に改良されたウイリスMB型とフォードGPW型を大量配備、米軍の行く所には全てジープがあり、米軍の勝利に大きな貢献をしました。
世界中に4WDの有用性を見せ付け、4輪駆動車のバイブルとなり、世界中で類似の車が急遽製造されましたが、WW2の内に十分な実用化が出来たのはアメリカ軍だけでした。
ドイツ軍が多用したキューベルワーゲンはリヤエンジンリヤドライブの2WDでした。
後述の様に捕獲したバンタムを手本にトヨタも戦時型AK10型を試作しましたが、普及には至りませんでした。
WW2後自衛隊向けにトヨタジープBJ10型、日産ジープ4W60型が提出されましたが、採用されたのはウィリス MB型のアンダーライセンスの三菱CJ3A型であり、量産はエンジン変更でボンネットが10cmほど高くなった CJ3B型となりました。


数年後トヨタの試作車はランドクルーザーとなり、日産の試作車はパトロールに発展しました。
ウイリス社は戦後カイザー社に買収され、更にアメリカンモータースに買収され、更に幾多の社名変更や系列傘下の変更があり、現在はクライスラーがジープラングラー等々を生産しています。
1.世界中の追従を許さない工業製品:万能車ランドクルーザー。
1942年、ウイリスジープの原型であるバンタムBRC60を捕獲し、これを基にトヨタで試作が進みました。それが四式小型貨物車こと「AK10型」、これがランドクルーザーの原型と言えなくはありませんが、直接の原型はもう少し後の下記の自衛隊向けの入札で始まりました。
1951年にトヨタはジープBJ-10型、日産も4W60型ジープを自衛隊向けに試作、結果は三菱のアンダ―ライセンスのウイリスジープCJ3A型に敗れ、ランクル等のその後は主に輸出に向けられました。
FJ20型:1954年には軍用イメージを少なくしたボデーとし、FJ20型となりました。更に三菱からジープの名称を使うなとクレームが入り、ランドクルーザーと名乗る様になり、同時に輸出を開始しました。当時の日本製品はまだ安かろう悪かろうの時代でしたが、ありとあらゆる物が輸出されました。
その中で最初に海外で認められた日本製品がこのランドクルーザーでした。

国内の警察等にも多少が納入されましたが、過半が2WDモデルと言う何とも皮肉な内容でした。
FJ40型:1960年にモデルチェンジ、外観的には前モデルと余り変更は無かったのですが、トランスファーを装備した本格的な4WD車に生まれ変わり、世界のランドクルーザーの出発点となりました。

本家ジープは全ての4WD車の原本であったのですが、シリーズ展開にアメリカ独自色が強くなり過ぎ、海外での評価は低く、追い打ちを掛けたのが1960年から運用されたM151通称ケネディージープの横転し易いと言う 欠陥問題、その結果として海外でのライバルはイギリスのランドローバーだけとなりました。
BJ40型:1973年、ディーゼルエンジンモデルが追加されました。B型エンジンの40型ジープモデルと言う事でBJ40型になり、3000㏄ダイハツ系B型85hpのエンジンでした。これが後述の様にその後の明暗を分けたと言っても過言ではありません。このディーゼルエンジンの粘りと高燃費が高耐久性や高走破性と共に世界的にも評価され、世界のランドクルーザーに飛躍した原因となりました。
ディーゼルエンジンは低馬力ですが、その低速トルクの粘りには昔から定評があり、これが4WD車には抜群の相性となりました。この粘りと低燃費こそが4WD車の求めていたエンジンだったのです。
海外では日本の様に国策で軽油(1970年当時はガソリンの半額)は安くないのですが、それでもエンジンの粘りと低燃費は十分な価値があったのです。

ライバルの初期型ランドローバー1948年型ですが、ディーゼルエンジンモデル追加はトヨタより10年も遅い1983年から、しかも2500㏄68hpとかなり劣った物でした。
4WD車の未舗装軟弱路の燃料消費は高負荷運転となる為に、5㎞/㍑でしたが、これがディーゼルエンジンのお陰で2倍の10㎞/㍑になったのです。
国内は1980年頃からクロカンブームを迎え、ランクルが維持費最安値の4ナンバー登録となった事も普及を後押し、多くのオフローダーは当時人気のパジェロを選びましたが、本格的マニアはランクル40を選びました。
最大の理由は走破性と高耐久性です。パジェロ如きは比較の対象にもならない程の大差でした。
このランクルの高評価の理由に粘りのディーゼルエンジンが含まれているのは確実です。
実はランクルはつい先頃までトヨタ製では無く、荒川車体製(初期には荒川板金)だったと言う経緯がありますが、その荒川は豊田自動織機からトヨタ自動車が分離して間もなくの事、1部のメンバーが自己資本で1946年に自前独立したのが始まりです。
その後に社名をアラコに変更、2004年からはトヨタ車体に1工場になりました。
トヨタ車体はトヨタ車のミニバン、商用車、SUV等の企画、開発から生産までを手掛ける完成車メーカーです。
BJ70型とHZJ70型:1984年ランクルはモデルチェンジし、亜鉛鋼板の採用や下塗り塗料の改良により長い間の難題であったボデーのサビ問題から決別、ボデーの出来具合も良くなり、居住性や乗り心地が大幅改善され、走破性も耐久性も一段と良くなりました。
エンジンも13B-Tの3400㏄120hpを経由し、130hpの1HZの4200㏄にパワーアップ、最早ディーゼルが走らないとは言わせない時代となりました。


HZJ76型:70型になり、すでに乗り心地は大幅に改善されましたが、1999年の76型はフロントにコイルスプリングの採用で更に大幅に改善され、接地製の向上で走破性も向上し、後述の経緯により強度も向上しました。
ランクルは輸出用にはターボディーゼルの4200㏄190hpや4500㏄205hpも用意され、世界の追従を許さない車となりました。2019年には累計1000万台を達成、ランクル40型は2017年に歴史遺産車に指定されました。

これに対しランドロ-バーのディーゼルエンジンは格下2500㏄しか用意出来ず、出力も1986年に85hp、2002年になっても122hpに留まり、ついに2015年ランドローバーはキブアップして生産中止となりました。
もう1つのライバルであった日産パトロールもトヨタと同サイズ4200㏄ながら大幅に劣る160hpのエンジンに留まり、2007年にギブアップしてしまいました。
クロカン4WD車の評価は、走破性や高耐久性や乗り心地の差もありますが、
結局は大排気量ビッグパワーのディーゼルエンジンの戦いであったと言えました。
ディーゼルはその後大幅に進化、トヨタでも200hpの出力は1998年レベルでは4200㏄が必要でしたが、2020年では2800㏄でも出せる様になりました。
現在のヨーロッパのディーゼルエンジンなら2000㏄でも楽勝で出せるパワーとなりましたが、僻地における過酷な運転環境を考慮すると、まだ当面はランクルの大排気量の神話は継続されそうです。
ランクル76の裏話:ライバルが全て消滅し、ベストセラーの名を欲しいままにしているランクル70シリーズ (全幅1695㎜)ですが、実は1999年のモデルチェンジは当初より変更された縮小案で実行されました。
ライバルのランドローバーは1983年に1791㎜にボデー拡大とコイルサスの採用を進め、ランクルをリードしていました。高耐久性や走破性、高性能ディーゼルエンジンでは全く負けていなかったランクル70シリーズですが、これを追い掛ける形でボデー拡大を含むモデルチェンジが計画されました。
世界の主流となったボデーのワイド化でしたが、トヨタの長期販売戦略からするとランクル70の優先順位は低く、トラックモデルはすでにワイド化し十分なパワーと強度を得た好評のハイラックスに置き換わるだろうと判断され、ランクル70のワイド化は試作を完了していましたが、見送られました。
そこでモデルチェンジは外観的には全く無変更となり、フロントコイルサス採用と12V化をメインに行なわれましたが、シャーシは完全なフルモデルチェンジでした。



左から4輪コイルのランクルプラド78型1990~1995、FRリーフのランクル77型1990~1998、
Fのみコイルとなったランクル76型1999~2004(輸出用は今も生産中)
その結果、ロングになってからの1990年以来、全く同じボデーが30年以上の3代に渡って使われると言う世界の珍事となり、外観上で76を見分けられる点はホイールボルトが6本から5本になった事だけです。尚ワイド用に用意した部品を短縮化した為に強度は一段と向上、壊れない名声は一段と上がり、ライバルのギブアップを早めました。
実用車ランクル70型:ランクルがジープやランドローバーを凌駕して行く姿は誠に痛快な物語と言えます。また真面目な物造りが評価されて行く姿は、日本人として心に爽快感を感じます。
ランクルの話は3つに大きく分かれ、その1つ目が今回の話で、初期型ジープの延長から発展した過酷な運用に耐えられる世界の実用車のランクル70の物語でした。2番目は軽量化したとは言え実用性充分なランクルプラドの物語になります。そして3番目は本来の車を追求したラグジュアリーなツーリングカーランクル100型の物語になります。
パリダカと言う完走率が低い事で有名なハードなラリーがあります。
後述のパジェロが名を上げたラリーであり、これは通常のラリーと違って走るルートの設定はなく、何処をどう走っても良いのですが、大きな穴凹もたくさんあり、そこに突っ込むかそうでないかで勝負が大きく変わります。
ワークスはチームで走りますから先頭が突っ込んでも皆で引き上げ、引きずってでも次のサービスポイントに辿り着けばメカニックが翌朝までに再生してくれますが、プライベーターは自分で直さなくてはなりません。
すると睡眠時間を削る事になり、翌日は意識朦朧、増々飛び込み易くなる悪循環に陥り、完走は難しい物になります。その為に「完走したかったらランクル70にしなさい」と言われておりました。
実際ワークスの多くが度々穴凹に飛び込んだ為、ラッキーなプライベーターのランクル70がベスト10入りした事もありました。そんな事もあってプライベーターの殆んどがランクル70だった事が長らくありました。
実際にケンさんも鹿を追い掛けて牧草地内で穴凹に飛び込んだ事も数多くありましたが、何時もランクル76のお陰でノントラブルでした。ケンさんも後述の様にハンティングカーとして2007~2014年はこのランクルの76型を運用しましたが、ハンティングカーとしては最高の車でした。過酷な条件下で運用するには絶対に76が最高だと思います。
エゾ鹿ハンティングの根室同好会は当初パジェロが主流でしたが、後述の様にケンさんのランクルに影響されて、結局はランクルが殆どになってしまいました。
2.ランクル3本柱の1つプラド:1時期のパジェロの独走に待ったを掛けるべく、ランクル70ベースで急造されたプラドですが、何時しかパジェロとは比較にならない世界に通用する立派な4WD車に育ちました。

三菱のパジェロ作戦は1982年、パッとしない三菱の起死回生作戦でした。しかしこれが過剰に成功し、これに慢心した三菱は本来の努力をしなくなり、やがて2019年にはパジェロが製造中止となり、三菱自動車自体が崩壊の危機に陥りました。
WW2の日本軍もパールハーバーの予想外の大戦果やゼロ戦(三菱製)の大活躍で連戦連勝しました。日本軍は何時しかこれに慢心し、敵を侮る様になり、その結果ミッドウェーの大敗となり、以後は負け戦の連続、当時ゼロ戦と言う画期的な戦闘機を作りながら、次期モデルや改良が遅れ、苦戦に陥って行く様は今の三菱と重なる部分があります。
デビュー時のパジェロは確かに画期的な車でした。パリダカで優勝した事も見事でした。そしてクロカンブームを起こし、パジェロは売れに売れ、三菱はパジェロ専門工場を新設しました。しかし世界の自動車メーカーが何時までも只々それを眺めていた訳ではありません。
間もなく市販車パジェロではパリダカに勝てる見込みが立たず、プロトタイプ出場で優勝をキープしました。しかしこれにもパジェロと名を付けた所に嘘がありました。
ユーザーを騙す作戦もその後数年は有効で、パリダカ効果のパジェロは好調に売れ続けましたが、・・・・・・
これに対し完成度は余り高くありませんが、トヨタはランクル70にハイラックスのエンジンや駆動系部品と組み合わせた急改造版でパジェロに挑みました。しかしトヨタのプラドは徐々に改良され続けた結果、実力を増し性能は部分的には逆転するまでになりました。


1996年にプラドはフルチェンジしましたが、何故か2代目パジェロに外観がよく似ており、2代目プラドの実力をまだ知らない、パリダカ信者のパジェロユーザーからボロクソに批判されました。
しかし本当の実力はプラドの1KDエンジンの130hpに対し、パジェロ4M40エンジンは125hp,カタログ上は微差ですが、プラドの130hpの出来は素晴らしく、パジェロは125hpを2基積まないと勝てないとまで言われていました。それ以外にも旋回半径や走破性や強度や燃費に至るまで全てプラドの圧勝なのでした。
それを知らぬはパリダカ信者のパジェロユーザーのみでしたが、やがて随所でその性能差を見聞きし、また自らもパジェロの劣度を体験し、パリダカ信者は1人減り2人減り、やがて殆んどいなくなりました。そんな噓の広告の三菱はやがて崩壊を迎えますが、これには日本軍の大本営の嘘の発表が重なって見える気がします。
クロカンブームは2000数年まで続いており、2代目プラドやランクル80は売れまくっていたのですが、2代目パジェロの末期頃には売り上げ台数は激減してしまいました。
その1例ですが、根室エゾ鹿同好会も当初はパジェロが主流、多分パジェロが1番優れていると信じていたと思います。ケンさんも当時はパジェロでしたが、予算の関係でした。しかしケンさんのパジェロは2000年末に交通事故で失われ、賠償金+αで以前から欲しかったプラド78型に変更しました。
予想通りプラド78型は高走破性を発揮、パジェロ組の多くはケンさんの78型プラドにレスキューされ、プラドとの走破性や耐久性の差を強く感じ、10年待たずして殆どがランクルになっていました。
その頃にはパジェロの販売台数は激減、3代目、4代目とモデルチェンジをしても、買うのは三菱関係者のみ、情けない位しか売れず、パジェロは2019年には製造中止となり、三菱自動車自体が崩壊の危機に陥りました。
一方プラドはハイラックスの部品を流用したランクル70より強度を低下させた設計ですが、パジェロより遥かに強度はあり、世界的に十分な強度の車となり、トヨタ車全般に言える高品質が加わり、やがてランクル3本柱の1本に育ちました。この物語も長くなりますので、ここでは軽くに留め、また別の機会にしたいと思います。
ハンティングカーランクル78プラド:全く同じボデーを使ったランクル2台をハンティングカーとして使った結果を申し上げますと、ボデーは全く同一、従って居住性も同一でしたが、全く別の性格の車でした。

78型のサスペンションはコイルスプリングで、普通路面では悪くありませんが、ボトムラバーがリーフ時のままでしたので大きなギャップでは激しい突き上げがあり、収まるまでに更に中ジャンプと小ジャンプがありました。ケンさんは対策として硬めの長いコイルスプリングと減衰力の強いショックアブソーバを組合せて運用しました。
またデフに対して反トルク方向を支える力が不足し、重負荷運転をするとジャダー(激しい振動)を起し、駆動力の低下と共に駆動系のダメージが起こり易い構造にありましたが、これは対策出来ずでした。
また重積載時にケツダレが大きく使い難い物でしたが、これに対しコイルスプリングの中にエアースプリングを補助に入れると言う手法を取りました。この様にオリジナルにはまだ未完成の部分がありましたが、ケツダレやジャダーの問題も次期モデルには対策され、プラドはどんどん良い車に育って行きました。
ハンティングカーランクル76:サスはフロントがコイル、リヤはリーフスプリングと言う仕様で、永年の改良の成果が十分感じられる良い仕上がりで概ね完成版と言え、走破性や乗り心地には問題はなく初めてノーマル サスペンションのままで運用しました。
リヤキャリアにエゾ鹿2頭を積んでも不安はなく、FR共デフロックを使えばスタック知らず、過酷な条件下で運用するハンティングカーには絶対にランクル76が最高だと思います。

しかしエンジンはHZ型ノンターボ、78プラドと同じ130hpですが、少々パンチに欠け、そこで燃料の噴射量の調整とギヤ比を5%落とす改造を加えて所、生まれ変わった程のパワフルになりました。燃費も78型プラドに比べてやや良くなり、7~8㎞/㍑になりました。
運転席のシートも腰の負担が少なくなる様に少し取り付け位置と角度を変更し、これで高速郊外ドライブ以外は文句なしの最高と言える車になりました。
3.本来の車はこうあるべきを目指したランクル100型:詳しく語るとこれも長くなりますので今回は軽くに留めます。
40型の1部シリーズが発展したステーションワゴンですが、最初からステーションワゴンとして設計された50型、60型、80型、100型、200型と発展したツーリング型ランクルシリ-ズの話です。
ランクルも60型までは旧型の延長上のシャーシに新しいボデーを載せただけの物でしたが、車はどんな気象条件下にも、どんな路面状況下にあっても、より快適に、より楽しく走れる物でありたい、これが目標でした。
そんな夢が実現し始めた車が、1989年にデビューしたランクル80型でした。コイルスプリングと新しいアイデアのサブスプリングを取り入れたバンプストッパーは素晴らしい乗り心地を生み出し、従来のリーフスプリング車の60型に比べると2倍走っても疲労は同等に収まり、これぞ技術革新の見本と思わせました。


1998年にデビューのランクル100型は更にフロント独立懸架の採用とショックアブソーバをコンピューター制御とした事で、60型の3倍走っても疲労は同程度以下で収まると言う、夢の様な車になりました。
ケンさん自身の運用から、過酷な道を走破するハンティングカーとしてはランクル76型の前後デフロック付の電動ウインチ装着車は最高の車でした。しかし高速道路等を多用したツーリングには最高の車ではありません。

ケンさんの狩猟も2012年頃からは過酷な道を走破しなければならない猟場は無くなり、一方で空港送迎比率が高くなり、ツーリングで疲れない車として、2015年にハンティングカーをランクル100型に換えました。完成度は非常に高く、初めてドノーマルのまま運用出来る車となり、空港送迎業務の負担も半減以下になりました。
車は何時でも何処でも快適に楽しく走れる、そんな本来の車のあるべきスタイルを追求した車、ランクル100型では技術はこの様に使うのだと言う事を魅せてくれました。更に200型は電子装置の充実が図られ、例えばTRC(トラクションコントロール)は最早相当のベテランでも勝てない程の出来栄えとなりました。
しかし200型は国内ではディーゼルモデルが無かった為、ケンさんは100型を22年間愛用しました。
ランクル100型の唯一の欠点は天井が低く、車中泊に向かない事でした。
セルシオ(レクサスLS)との比較:セルシオはトヨタの最高級乗用車でレクサスの最高級車LSでもありました。ケンさんはセダンには興味も運用経験も無く、これは友人の話です。友人は永らく主力用のクラウンとハンティング専用車のランクルを併用していました。ランクルは40型であり、その後は60型でした。
1989年セルシオがデビュー、そしてあの圧倒的な乗り心地となったランクル80も同じ1989年にデビューしました。友人はクラウンを新型のセルシオに換え、ランクル60を新型の80に換えました。
そしてこの時から主役は入れ替わり、普段にもランクル80を乗る様になりました。
1998年、更に圧倒的乗り心地になったランクル100型がデビュー、ランクル80は新しい100に更新されました。しかしセルシオは更新されず運用が終わり、ランクル100型のみの運用となりました。
もう普段使いにもランクルの方が完全に良くなり、ランクルが目指していた時代が始まったのです。
そもそも良い乗り心地の為には下記の条件をクリアしなければなりません。
タイヤ径は大きい程乗り心地は良くなります。ランクルの方がデカいタイヤです。
車重は重い方が乗り心地は良くなります。ランクルの方が重いです。
サスペンションストロークは長い方が乗り心地は良くなります。ランクルの方が圧倒的に長いです。エンジンはパワフルな方が乗り心地は良くなります。ランクルディーゼルの方が実用トルクは遥かにデカいです。
セルシオはランクルの乗り心地を超えられない可能性は元々原理的に十分あるのです。その後友人のランクル100はランクル200に更新されましたが、セルシオはレクサスLSと名を変えましたが、更新は無く消えました。
ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの性能差:ランクル200型の輸出向け同士の比較です。
ガソリン「G」エンジン :3UR型5.6リットル、386hp/5600rpm、55.5kg・m/3600rpm。
ディーゼル「D」エンジン:1VZ型4.5リットル、265hp/3400rpm、65.8kg・m/1600rpm。
馬力では1.5倍程「G」の方が大ですが、問題はその最高出力が5600rpmと常用外の回転域である事です。普段使いは1000~2500rpm、ブン廻しても4000rpm程度です。
更に車を走らせる力は馬力ではなく回転力の「トルク」であり、最大トルクは「D」の方が20%程大ですが、更に「D」の方は実用回転域内、「G」は実用回転域外ですからその差はもっと大きくなります。恐らく実用トルクの比率は1.4倍程の差になると思われます。
5段変速ですと1.4倍と言うのは1段シフトダウンをした程度と同じになります。つまり登坂車線のある道路で、「D」はシフトダウンをしなくても十分な加速を得られますが、「G」はシフトダウンしなければ十分な加速が得られないと言う事になります。どちらが快適で速いのかと言うと、勿論「D」の方が速いと言うのが答えです。
燃費は「D」の方が数割良く、しかも燃料代は15%程安いと言う事になり、コスト比は更に大きく開きます。「D」は常用的には速く、使い易く、静か、安いと言う事になり、「ディーゼルエンジンの圧勝」と言う事になります。
静粛性に付きましても実用回転数が低い「D」の方が騒音計レベルでは静かと言う評価になりますが、音質的に「D」の方が不慣れが故にやや煩いと言う評価に落ち着きますが、大きな差はありません。
この評価は小型乗用車に付きましては近年プリウスシステムに逆転されましたが、ヘビー級用のハイブリッドや電気車が普及するまでの、当面の間は変わりません。ケンさんは2030~2040年に「D」の新車販売が終れば、中古車「D」のランドクルーザーには大きなプレミアムが付くだろうと思っています。
レーダー、VTヒューズ、護衛空母、FM2戦闘機、P51戦闘機、B17&B29戦略爆撃機、M4シャーマン戦車、自動小銃ガーランド、バズーカ砲、そしてジープです。日本は全体的な工業生産量を始めとして、残念ながら1つとして勝てませんでした。
この方面の個別のお話も面白いのですが、それぞれが長くなりますので、また別の機会にしたいと思います。
米軍のターボチャージャーはWW2の初期からB-17等ですでに実用化していましたが、日本では研究室から出られませんでした。
同様にメッサーシュミットのダイムラーエンジンはアンダーライセンスで日本に持ち込まれましたが、飛燕も彗星もまともに稼働出来ず、スピットファイアのロールスロイスのエンジンがアンダーライセンスでアメリカのP51マスタングのエンジンとして大活躍したのとは対照的です。
良質な鉄製品には良い合金と熱処理が不可欠なのですが、1970年以前の日本製品はベースとなる鉄の純度が低く、良い合金が出来ませんでした。その為、まともなエンジンや自動車が出来なかったのです。
1970年頃以降は鉄が良くなり、やがて日本製品は高品質の代表格になりました。そんな中で日本車、特にジープ型のランドクルーザーが世界に誇れる製品に育った事はトヨタの車両エンジニアだった1人として嬉しく思います。
JEEP:ウイリスMB型とフォードGPW型があり、基本設計はバンタムでしたが、量産はウイリスとフォードが行いました。1940年にはバンタム増加試作車を試験配備、1941年にはバンタムのBRC-40型やウイリスMA型とフォードGP型が実戦投入されました。
1942年からは共通仕様に改良されたウイリスMB型とフォードGPW型を大量配備、米軍の行く所には全てジープがあり、米軍の勝利に大きな貢献をしました。
世界中に4WDの有用性を見せ付け、4輪駆動車のバイブルとなり、世界中で類似の車が急遽製造されましたが、WW2の内に十分な実用化が出来たのはアメリカ軍だけでした。
ドイツ軍が多用したキューベルワーゲンはリヤエンジンリヤドライブの2WDでした。
後述の様に捕獲したバンタムを手本にトヨタも戦時型AK10型を試作しましたが、普及には至りませんでした。
WW2後自衛隊向けにトヨタジープBJ10型、日産ジープ4W60型が提出されましたが、採用されたのはウィリス MB型のアンダーライセンスの三菱CJ3A型であり、量産はエンジン変更でボンネットが10cmほど高くなった CJ3B型となりました。


数年後トヨタの試作車はランドクルーザーとなり、日産の試作車はパトロールに発展しました。
ウイリス社は戦後カイザー社に買収され、更にアメリカンモータースに買収され、更に幾多の社名変更や系列傘下の変更があり、現在はクライスラーがジープラングラー等々を生産しています。
1.世界中の追従を許さない工業製品:万能車ランドクルーザー。
1942年、ウイリスジープの原型であるバンタムBRC60を捕獲し、これを基にトヨタで試作が進みました。それが四式小型貨物車こと「AK10型」、これがランドクルーザーの原型と言えなくはありませんが、直接の原型はもう少し後の下記の自衛隊向けの入札で始まりました。
1951年にトヨタはジープBJ-10型、日産も4W60型ジープを自衛隊向けに試作、結果は三菱のアンダ―ライセンスのウイリスジープCJ3A型に敗れ、ランクル等のその後は主に輸出に向けられました。
FJ20型:1954年には軍用イメージを少なくしたボデーとし、FJ20型となりました。更に三菱からジープの名称を使うなとクレームが入り、ランドクルーザーと名乗る様になり、同時に輸出を開始しました。当時の日本製品はまだ安かろう悪かろうの時代でしたが、ありとあらゆる物が輸出されました。
その中で最初に海外で認められた日本製品がこのランドクルーザーでした。

国内の警察等にも多少が納入されましたが、過半が2WDモデルと言う何とも皮肉な内容でした。
FJ40型:1960年にモデルチェンジ、外観的には前モデルと余り変更は無かったのですが、トランスファーを装備した本格的な4WD車に生まれ変わり、世界のランドクルーザーの出発点となりました。

本家ジープは全ての4WD車の原本であったのですが、シリーズ展開にアメリカ独自色が強くなり過ぎ、海外での評価は低く、追い打ちを掛けたのが1960年から運用されたM151通称ケネディージープの横転し易いと言う 欠陥問題、その結果として海外でのライバルはイギリスのランドローバーだけとなりました。
BJ40型:1973年、ディーゼルエンジンモデルが追加されました。B型エンジンの40型ジープモデルと言う事でBJ40型になり、3000㏄ダイハツ系B型85hpのエンジンでした。これが後述の様にその後の明暗を分けたと言っても過言ではありません。このディーゼルエンジンの粘りと高燃費が高耐久性や高走破性と共に世界的にも評価され、世界のランドクルーザーに飛躍した原因となりました。
ディーゼルエンジンは低馬力ですが、その低速トルクの粘りには昔から定評があり、これが4WD車には抜群の相性となりました。この粘りと低燃費こそが4WD車の求めていたエンジンだったのです。
海外では日本の様に国策で軽油(1970年当時はガソリンの半額)は安くないのですが、それでもエンジンの粘りと低燃費は十分な価値があったのです。

ライバルの初期型ランドローバー1948年型ですが、ディーゼルエンジンモデル追加はトヨタより10年も遅い1983年から、しかも2500㏄68hpとかなり劣った物でした。
4WD車の未舗装軟弱路の燃料消費は高負荷運転となる為に、5㎞/㍑でしたが、これがディーゼルエンジンのお陰で2倍の10㎞/㍑になったのです。
国内は1980年頃からクロカンブームを迎え、ランクルが維持費最安値の4ナンバー登録となった事も普及を後押し、多くのオフローダーは当時人気のパジェロを選びましたが、本格的マニアはランクル40を選びました。
最大の理由は走破性と高耐久性です。パジェロ如きは比較の対象にもならない程の大差でした。
このランクルの高評価の理由に粘りのディーゼルエンジンが含まれているのは確実です。
実はランクルはつい先頃までトヨタ製では無く、荒川車体製(初期には荒川板金)だったと言う経緯がありますが、その荒川は豊田自動織機からトヨタ自動車が分離して間もなくの事、1部のメンバーが自己資本で1946年に自前独立したのが始まりです。
その後に社名をアラコに変更、2004年からはトヨタ車体に1工場になりました。
トヨタ車体はトヨタ車のミニバン、商用車、SUV等の企画、開発から生産までを手掛ける完成車メーカーです。
BJ70型とHZJ70型:1984年ランクルはモデルチェンジし、亜鉛鋼板の採用や下塗り塗料の改良により長い間の難題であったボデーのサビ問題から決別、ボデーの出来具合も良くなり、居住性や乗り心地が大幅改善され、走破性も耐久性も一段と良くなりました。
エンジンも13B-Tの3400㏄120hpを経由し、130hpの1HZの4200㏄にパワーアップ、最早ディーゼルが走らないとは言わせない時代となりました。


HZJ76型:70型になり、すでに乗り心地は大幅に改善されましたが、1999年の76型はフロントにコイルスプリングの採用で更に大幅に改善され、接地製の向上で走破性も向上し、後述の経緯により強度も向上しました。
ランクルは輸出用にはターボディーゼルの4200㏄190hpや4500㏄205hpも用意され、世界の追従を許さない車となりました。2019年には累計1000万台を達成、ランクル40型は2017年に歴史遺産車に指定されました。

これに対しランドロ-バーのディーゼルエンジンは格下2500㏄しか用意出来ず、出力も1986年に85hp、2002年になっても122hpに留まり、ついに2015年ランドローバーはキブアップして生産中止となりました。
もう1つのライバルであった日産パトロールもトヨタと同サイズ4200㏄ながら大幅に劣る160hpのエンジンに留まり、2007年にギブアップしてしまいました。
クロカン4WD車の評価は、走破性や高耐久性や乗り心地の差もありますが、
結局は大排気量ビッグパワーのディーゼルエンジンの戦いであったと言えました。
ディーゼルはその後大幅に進化、トヨタでも200hpの出力は1998年レベルでは4200㏄が必要でしたが、2020年では2800㏄でも出せる様になりました。
現在のヨーロッパのディーゼルエンジンなら2000㏄でも楽勝で出せるパワーとなりましたが、僻地における過酷な運転環境を考慮すると、まだ当面はランクルの大排気量の神話は継続されそうです。
ランクル76の裏話:ライバルが全て消滅し、ベストセラーの名を欲しいままにしているランクル70シリーズ (全幅1695㎜)ですが、実は1999年のモデルチェンジは当初より変更された縮小案で実行されました。
ライバルのランドローバーは1983年に1791㎜にボデー拡大とコイルサスの採用を進め、ランクルをリードしていました。高耐久性や走破性、高性能ディーゼルエンジンでは全く負けていなかったランクル70シリーズですが、これを追い掛ける形でボデー拡大を含むモデルチェンジが計画されました。
世界の主流となったボデーのワイド化でしたが、トヨタの長期販売戦略からするとランクル70の優先順位は低く、トラックモデルはすでにワイド化し十分なパワーと強度を得た好評のハイラックスに置き換わるだろうと判断され、ランクル70のワイド化は試作を完了していましたが、見送られました。
そこでモデルチェンジは外観的には全く無変更となり、フロントコイルサス採用と12V化をメインに行なわれましたが、シャーシは完全なフルモデルチェンジでした。


左から4輪コイルのランクルプラド78型1990~1995、FRリーフのランクル77型1990~1998、
Fのみコイルとなったランクル76型1999~2004(輸出用は今も生産中)
その結果、ロングになってからの1990年以来、全く同じボデーが30年以上の3代に渡って使われると言う世界の珍事となり、外観上で76を見分けられる点はホイールボルトが6本から5本になった事だけです。尚ワイド用に用意した部品を短縮化した為に強度は一段と向上、壊れない名声は一段と上がり、ライバルのギブアップを早めました。
実用車ランクル70型:ランクルがジープやランドローバーを凌駕して行く姿は誠に痛快な物語と言えます。また真面目な物造りが評価されて行く姿は、日本人として心に爽快感を感じます。
ランクルの話は3つに大きく分かれ、その1つ目が今回の話で、初期型ジープの延長から発展した過酷な運用に耐えられる世界の実用車のランクル70の物語でした。2番目は軽量化したとは言え実用性充分なランクルプラドの物語になります。そして3番目は本来の車を追求したラグジュアリーなツーリングカーランクル100型の物語になります。
パリダカと言う完走率が低い事で有名なハードなラリーがあります。
後述のパジェロが名を上げたラリーであり、これは通常のラリーと違って走るルートの設定はなく、何処をどう走っても良いのですが、大きな穴凹もたくさんあり、そこに突っ込むかそうでないかで勝負が大きく変わります。
ワークスはチームで走りますから先頭が突っ込んでも皆で引き上げ、引きずってでも次のサービスポイントに辿り着けばメカニックが翌朝までに再生してくれますが、プライベーターは自分で直さなくてはなりません。
すると睡眠時間を削る事になり、翌日は意識朦朧、増々飛び込み易くなる悪循環に陥り、完走は難しい物になります。その為に「完走したかったらランクル70にしなさい」と言われておりました。
実際ワークスの多くが度々穴凹に飛び込んだ為、ラッキーなプライベーターのランクル70がベスト10入りした事もありました。そんな事もあってプライベーターの殆んどがランクル70だった事が長らくありました。
実際にケンさんも鹿を追い掛けて牧草地内で穴凹に飛び込んだ事も数多くありましたが、何時もランクル76のお陰でノントラブルでした。ケンさんも後述の様にハンティングカーとして2007~2014年はこのランクルの76型を運用しましたが、ハンティングカーとしては最高の車でした。過酷な条件下で運用するには絶対に76が最高だと思います。
エゾ鹿ハンティングの根室同好会は当初パジェロが主流でしたが、後述の様にケンさんのランクルに影響されて、結局はランクルが殆どになってしまいました。
2.ランクル3本柱の1つプラド:1時期のパジェロの独走に待ったを掛けるべく、ランクル70ベースで急造されたプラドですが、何時しかパジェロとは比較にならない世界に通用する立派な4WD車に育ちました。

三菱のパジェロ作戦は1982年、パッとしない三菱の起死回生作戦でした。しかしこれが過剰に成功し、これに慢心した三菱は本来の努力をしなくなり、やがて2019年にはパジェロが製造中止となり、三菱自動車自体が崩壊の危機に陥りました。
WW2の日本軍もパールハーバーの予想外の大戦果やゼロ戦(三菱製)の大活躍で連戦連勝しました。日本軍は何時しかこれに慢心し、敵を侮る様になり、その結果ミッドウェーの大敗となり、以後は負け戦の連続、当時ゼロ戦と言う画期的な戦闘機を作りながら、次期モデルや改良が遅れ、苦戦に陥って行く様は今の三菱と重なる部分があります。
デビュー時のパジェロは確かに画期的な車でした。パリダカで優勝した事も見事でした。そしてクロカンブームを起こし、パジェロは売れに売れ、三菱はパジェロ専門工場を新設しました。しかし世界の自動車メーカーが何時までも只々それを眺めていた訳ではありません。
間もなく市販車パジェロではパリダカに勝てる見込みが立たず、プロトタイプ出場で優勝をキープしました。しかしこれにもパジェロと名を付けた所に嘘がありました。
ユーザーを騙す作戦もその後数年は有効で、パリダカ効果のパジェロは好調に売れ続けましたが、・・・・・・
これに対し完成度は余り高くありませんが、トヨタはランクル70にハイラックスのエンジンや駆動系部品と組み合わせた急改造版でパジェロに挑みました。しかしトヨタのプラドは徐々に改良され続けた結果、実力を増し性能は部分的には逆転するまでになりました。


1996年にプラドはフルチェンジしましたが、何故か2代目パジェロに外観がよく似ており、2代目プラドの実力をまだ知らない、パリダカ信者のパジェロユーザーからボロクソに批判されました。
しかし本当の実力はプラドの1KDエンジンの130hpに対し、パジェロ4M40エンジンは125hp,カタログ上は微差ですが、プラドの130hpの出来は素晴らしく、パジェロは125hpを2基積まないと勝てないとまで言われていました。それ以外にも旋回半径や走破性や強度や燃費に至るまで全てプラドの圧勝なのでした。
それを知らぬはパリダカ信者のパジェロユーザーのみでしたが、やがて随所でその性能差を見聞きし、また自らもパジェロの劣度を体験し、パリダカ信者は1人減り2人減り、やがて殆んどいなくなりました。そんな噓の広告の三菱はやがて崩壊を迎えますが、これには日本軍の大本営の嘘の発表が重なって見える気がします。
クロカンブームは2000数年まで続いており、2代目プラドやランクル80は売れまくっていたのですが、2代目パジェロの末期頃には売り上げ台数は激減してしまいました。
その1例ですが、根室エゾ鹿同好会も当初はパジェロが主流、多分パジェロが1番優れていると信じていたと思います。ケンさんも当時はパジェロでしたが、予算の関係でした。しかしケンさんのパジェロは2000年末に交通事故で失われ、賠償金+αで以前から欲しかったプラド78型に変更しました。
予想通りプラド78型は高走破性を発揮、パジェロ組の多くはケンさんの78型プラドにレスキューされ、プラドとの走破性や耐久性の差を強く感じ、10年待たずして殆どがランクルになっていました。
その頃にはパジェロの販売台数は激減、3代目、4代目とモデルチェンジをしても、買うのは三菱関係者のみ、情けない位しか売れず、パジェロは2019年には製造中止となり、三菱自動車自体が崩壊の危機に陥りました。
一方プラドはハイラックスの部品を流用したランクル70より強度を低下させた設計ですが、パジェロより遥かに強度はあり、世界的に十分な強度の車となり、トヨタ車全般に言える高品質が加わり、やがてランクル3本柱の1本に育ちました。この物語も長くなりますので、ここでは軽くに留め、また別の機会にしたいと思います。
ハンティングカーランクル78プラド:全く同じボデーを使ったランクル2台をハンティングカーとして使った結果を申し上げますと、ボデーは全く同一、従って居住性も同一でしたが、全く別の性格の車でした。

78型のサスペンションはコイルスプリングで、普通路面では悪くありませんが、ボトムラバーがリーフ時のままでしたので大きなギャップでは激しい突き上げがあり、収まるまでに更に中ジャンプと小ジャンプがありました。ケンさんは対策として硬めの長いコイルスプリングと減衰力の強いショックアブソーバを組合せて運用しました。
またデフに対して反トルク方向を支える力が不足し、重負荷運転をするとジャダー(激しい振動)を起し、駆動力の低下と共に駆動系のダメージが起こり易い構造にありましたが、これは対策出来ずでした。
また重積載時にケツダレが大きく使い難い物でしたが、これに対しコイルスプリングの中にエアースプリングを補助に入れると言う手法を取りました。この様にオリジナルにはまだ未完成の部分がありましたが、ケツダレやジャダーの問題も次期モデルには対策され、プラドはどんどん良い車に育って行きました。
ハンティングカーランクル76:サスはフロントがコイル、リヤはリーフスプリングと言う仕様で、永年の改良の成果が十分感じられる良い仕上がりで概ね完成版と言え、走破性や乗り心地には問題はなく初めてノーマル サスペンションのままで運用しました。
リヤキャリアにエゾ鹿2頭を積んでも不安はなく、FR共デフロックを使えばスタック知らず、過酷な条件下で運用するハンティングカーには絶対にランクル76が最高だと思います。
しかしエンジンはHZ型ノンターボ、78プラドと同じ130hpですが、少々パンチに欠け、そこで燃料の噴射量の調整とギヤ比を5%落とす改造を加えて所、生まれ変わった程のパワフルになりました。燃費も78型プラドに比べてやや良くなり、7~8㎞/㍑になりました。
運転席のシートも腰の負担が少なくなる様に少し取り付け位置と角度を変更し、これで高速郊外ドライブ以外は文句なしの最高と言える車になりました。
3.本来の車はこうあるべきを目指したランクル100型:詳しく語るとこれも長くなりますので今回は軽くに留めます。
40型の1部シリーズが発展したステーションワゴンですが、最初からステーションワゴンとして設計された50型、60型、80型、100型、200型と発展したツーリング型ランクルシリ-ズの話です。
ランクルも60型までは旧型の延長上のシャーシに新しいボデーを載せただけの物でしたが、車はどんな気象条件下にも、どんな路面状況下にあっても、より快適に、より楽しく走れる物でありたい、これが目標でした。
そんな夢が実現し始めた車が、1989年にデビューしたランクル80型でした。コイルスプリングと新しいアイデアのサブスプリングを取り入れたバンプストッパーは素晴らしい乗り心地を生み出し、従来のリーフスプリング車の60型に比べると2倍走っても疲労は同等に収まり、これぞ技術革新の見本と思わせました。


1998年にデビューのランクル100型は更にフロント独立懸架の採用とショックアブソーバをコンピューター制御とした事で、60型の3倍走っても疲労は同程度以下で収まると言う、夢の様な車になりました。
ケンさん自身の運用から、過酷な道を走破するハンティングカーとしてはランクル76型の前後デフロック付の電動ウインチ装着車は最高の車でした。しかし高速道路等を多用したツーリングには最高の車ではありません。
ケンさんの狩猟も2012年頃からは過酷な道を走破しなければならない猟場は無くなり、一方で空港送迎比率が高くなり、ツーリングで疲れない車として、2015年にハンティングカーをランクル100型に換えました。完成度は非常に高く、初めてドノーマルのまま運用出来る車となり、空港送迎業務の負担も半減以下になりました。
車は何時でも何処でも快適に楽しく走れる、そんな本来の車のあるべきスタイルを追求した車、ランクル100型では技術はこの様に使うのだと言う事を魅せてくれました。更に200型は電子装置の充実が図られ、例えばTRC(トラクションコントロール)は最早相当のベテランでも勝てない程の出来栄えとなりました。
しかし200型は国内ではディーゼルモデルが無かった為、ケンさんは100型を22年間愛用しました。
ランクル100型の唯一の欠点は天井が低く、車中泊に向かない事でした。
セルシオ(レクサスLS)との比較:セルシオはトヨタの最高級乗用車でレクサスの最高級車LSでもありました。ケンさんはセダンには興味も運用経験も無く、これは友人の話です。友人は永らく主力用のクラウンとハンティング専用車のランクルを併用していました。ランクルは40型であり、その後は60型でした。
1989年セルシオがデビュー、そしてあの圧倒的な乗り心地となったランクル80も同じ1989年にデビューしました。友人はクラウンを新型のセルシオに換え、ランクル60を新型の80に換えました。
そしてこの時から主役は入れ替わり、普段にもランクル80を乗る様になりました。
1998年、更に圧倒的乗り心地になったランクル100型がデビュー、ランクル80は新しい100に更新されました。しかしセルシオは更新されず運用が終わり、ランクル100型のみの運用となりました。
もう普段使いにもランクルの方が完全に良くなり、ランクルが目指していた時代が始まったのです。
そもそも良い乗り心地の為には下記の条件をクリアしなければなりません。
タイヤ径は大きい程乗り心地は良くなります。ランクルの方がデカいタイヤです。
車重は重い方が乗り心地は良くなります。ランクルの方が重いです。
サスペンションストロークは長い方が乗り心地は良くなります。ランクルの方が圧倒的に長いです。エンジンはパワフルな方が乗り心地は良くなります。ランクルディーゼルの方が実用トルクは遥かにデカいです。
セルシオはランクルの乗り心地を超えられない可能性は元々原理的に十分あるのです。その後友人のランクル100はランクル200に更新されましたが、セルシオはレクサスLSと名を変えましたが、更新は無く消えました。
ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの性能差:ランクル200型の輸出向け同士の比較です。
ガソリン「G」エンジン :3UR型5.6リットル、386hp/5600rpm、55.5kg・m/3600rpm。
ディーゼル「D」エンジン:1VZ型4.5リットル、265hp/3400rpm、65.8kg・m/1600rpm。
馬力では1.5倍程「G」の方が大ですが、問題はその最高出力が5600rpmと常用外の回転域である事です。普段使いは1000~2500rpm、ブン廻しても4000rpm程度です。
更に車を走らせる力は馬力ではなく回転力の「トルク」であり、最大トルクは「D」の方が20%程大ですが、更に「D」の方は実用回転域内、「G」は実用回転域外ですからその差はもっと大きくなります。恐らく実用トルクの比率は1.4倍程の差になると思われます。
5段変速ですと1.4倍と言うのは1段シフトダウンをした程度と同じになります。つまり登坂車線のある道路で、「D」はシフトダウンをしなくても十分な加速を得られますが、「G」はシフトダウンしなければ十分な加速が得られないと言う事になります。どちらが快適で速いのかと言うと、勿論「D」の方が速いと言うのが答えです。
燃費は「D」の方が数割良く、しかも燃料代は15%程安いと言う事になり、コスト比は更に大きく開きます。「D」は常用的には速く、使い易く、静か、安いと言う事になり、「ディーゼルエンジンの圧勝」と言う事になります。
静粛性に付きましても実用回転数が低い「D」の方が騒音計レベルでは静かと言う評価になりますが、音質的に「D」の方が不慣れが故にやや煩いと言う評価に落ち着きますが、大きな差はありません。
この評価は小型乗用車に付きましては近年プリウスシステムに逆転されましたが、ヘビー級用のハイブリッドや電気車が普及するまでの、当面の間は変わりません。ケンさんは2030~2040年に「D」の新車販売が終れば、中古車「D」のランドクルーザーには大きなプレミアムが付くだろうと思っています。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その6:トヨタプリウス&ディーゼルの発展
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その5:ジムニー最新型
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その4:ジムニーライバル登場そして自滅。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その3:唯一の改良コイルサス。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。
嘘もイイ加減にしなさい。その12:ランクルの強度と耐久性。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その5:ジムニー最新型
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その4:ジムニーライバル登場そして自滅。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その3:唯一の改良コイルサス。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。
嘘もイイ加減にしなさい。その12:ランクルの強度と耐久性。
Posted by little-ken
at 10:54
│ハンティングカー