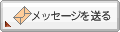2020年12月07日
スズキ ジムニー・
1.世界中の追従を許さない工業製品。
デビュー以来他社の追従を許さない世界に誇れる日本製品として挙げられるのは、トヨタのランドクルーザー、ホンダのスーパーカブ、そしてスズキのジムニーがあります。ランクル40型は2017年、スーパーカブC100型は2009年、初代ジムニーLJ10型は2020年に歴史遺産車に指定されました。
ホンダ―スーパーカブ:1番凄いのはこれです。
1958年に「C100型」がデビュー以来、2017年には累計1億台を超え、今も変わらない原設計のままで世界の多くの国で継続生産中、その後幾多の後発メーカーの製品も出ましたが、何れもスーパーカブを凌駕出来ず、世界№.1の座を今も更新中です。ホンダの創立者である本田宗一郎さんの世界に誇るべき作品です。

ランドクルーザー:1951年にトヨタジープBJ-10型を自衛隊向けに試作、日産も4W60型ジープを提出、三菱のウイリスのアンダ―ライセンスジープに敗れ、ランクルは当初から輸出に向けられました。1954年には三菱からジープと言う名称を使うなとクレーム、以来ランドクルーザーとなりました。

当時の日本製品は安かろう悪かろうの時代ですが、海外で最初に認められた日本の工業製品はこのランドクルーザーです。2019年には累計1000万台を達成、高品質と耐久性と乗り心地が評価され、世界の追従を許さない車となりました。
日本には日産、三菱、マツダ、日野、いすゞ、スズキ、ダイハツ等のたくさんの自動車メーカーがありますが、その中でも最も技術レベルの低かったトヨタが世界の№.1になったのですから痛快です。
当時トヨタフォークリフトの設計に在籍していましたが、1970年までのトヨタは壊れない所が無いと言える位に良く壊れました。
実はケンさんがランドクルーザーに乗り始めたのは1980年のBJ60型からですが、もしトヨタエンジンだったら見送りましたが、ダイハツエンジンだったので購入、その時から切っても切れないランクル人生となりました。
時代は変わり1990年以降のランクルを含むトヨタ車は世界で最高の品質の車となりました。
1例としてケンさんは1998年型ランクル100型を22年間で15万km乗りましたが、ずっと無整備で時期が来たら公的車検場で検査を受けるだけを繰り返し、概ねアンタッチャブル&無故障で22年間を過ごす事が出来ました。我ながらここまで無整備で乗り切れるとは思っておらずこれには驚きました。
高耐久性以外にも最高の乗り心地も得られ、ランクルより10年以上新しいニッサンキャラバンで400㎞走るとしっかり疲れますが、ランクルで1000㎞走った方が疲れないのですから恐れ入ります。
オーストラリアやアフリカに行きますと僻地に行けば行くほどランクルオンリーになります。
ランクル神話に「生き残りたかったらランクルにしなさい」と言う伝説がある程です。
ランクルはWW2後の自衛隊向けの入札に敗れた為に輸出に廻され、海外で評価が得られたのも荒川社員の頑張りがあったからなのです。同時期にスタートした日産のパトロール(サファリ)や三菱のジープやパジェロがその後は売れずに、とうとう製造中止になった事と比べますと、天と地の差があります。ランクルのストーリーは長くなりますので別の機会にさせて頂きます。
2.スズキジムニー。
ジムニーはスズキ自動車が生産する本格的な軽4輪駆動車であり、これまた世界の追従を許さない走破性の高さとタフさを持っています。実はランクルが先頃までトヨタ製では無く荒川車体(初期には荒川板金)だったと言う経緯がありますが、その荒川は豊田自動織機からトヨタ自動車が分離して間もなく、1部のメンバーが自己資本で自前独立したのが始まりです。
ジムニーも実は原型はスズキ製では無かったのです。
スズキが作ったら多分パジェロミニの様な駄作になったと思います。
ジムニーの原型:東京のホープ自動車のON型がベースになっています。

ホープON型は三菱系のエンジンや駆動系部品が使われておりましたが売れず、1967年から100台程を売った処で製造権の譲渡先を探しました。最初の行ったのは従来のエンジン等の購入先の三菱、次いで国内の全ての軽自動車メーカーを一巡しましたが全て門前払いでした。
最後の残ったのはスズキだけ、どうせ買ってもらえないだろうと、本社ではなく東京営業所に話を持ち込みました。これが運命の分かれ道となりました。当時スズキ東京の社長が後のスズキの大社長であり大会長となった鈴木修氏、2つ返事で購入したそうです。
酷い欠陥車だった初代ジムニーLJ10型:多くが三菱系の部品で出来ていたホープON型を当時のベストセラーであった軽トラのスズキキャリーの部品を流用して再設計したのがジムニーであり、1970年のデビューでした。原型のホープON形にもかなりの欠陥があった様ですが、ジムニーLJ10型も欠陥が多数ありました。

そうとは知らないケンさんは近隣の農家でも多数の軽トラキャリーがノントラブルで動いているので、その延長の稼働率が得られるだろうとして購入したのですが・・・・・結果はしっかり裏切られました。
次から次へと重要部品が壊れるので、数千㎞の僅か1年でクビにしました。壊れたのは次の通りです。まずはエンジンを廻し過ぎない様に注意していたのですが、それでもピストンに穴が空いてしまいました。次にデフのギヤが欠けてしまい、ドライブシャフトも折れてしまいました。更にステリングのジョイントがガタガタになってしまいました。
何れもキャリーの中古部品を利用して自分で直しましたので費用的には知れていましたが、信じられないトラブルの連続には驚きました。この時にスズキの車は金輪際もう買わないと決めました。
それ以外に走らないのには驚きました。当時の軽自動車は僅か360㏄の25hp、今の軽自動車の半分程度のエンジンで、豪快な走りは期待出来る物ではありませんでしたが、登坂車線を4速ミッションの3速ならまだ我慢出来るのですが、2速の20㎞/hでしか走れませんでした。
加えて致命的な欠陥の数々、それは圧倒的に問題の多かったトヨタ車よりも遥かに多いトラブルでした。よくぞこんな欠陥車を販売した物だと思いました。出来の悪い車でしたが、その後の大記録の出発点となった初代ジムニーは2020年に歴史遺産車に指定されました。
使える車に育った2代目ジムニーLJ20型:1972年エンジンが換わったLJ20型になり、排気量は同じ360㏄ながら水冷2気筒28hp、馬力もトルクも12%程上がり、当時の並の非力車になりました。
そしてあれ程あった欠陥は概ねが対策されたらしく、当時の並の軽自動車になりました。

壊そうとしても壊れなかった SJ10:1976年からは初代ジープ系最後のSJ10型となりました。
車体は長さ200㎜、幅100㎜大きくなり、エンジンは550㏄の28hpになりました。
最大馬力は同じですが、圧倒的なトルクアップの1.4倍、パワー不足感は無くなりました。

1981年からは新しい箱型ボデーに変わり、SJ30型になりましたが、このSJ30型までが2サイクルエンジン、重量が軽く、素晴らしいトルクを発生してくれ、また水没してもウォーターハンマーを起こさず、水を抜けば直ちに甦るのも大きなメリットと言えました。

SJ10型やSJ30型は車重も700kg前後と軽く、スタックしても人力で何とか出来る車でした。
更にジープ型最終ボデーの車は壊そうとしても壊れない程の完成度に仕上がり、オフロード走破性の高さは最強、ジムニーの黄金期と言える作品でした。
当時毎週水曜日の夜がケンさんの所属するオフロードクラブの悪路走行会、近くの河川敷でスタックや水没を楽しむ会でした。
ヒルクライムの主役はランクル40でしたが、川渡りの主役は2サイクルジムニーでした。
ケンさんの接地センサーや駆動センサーはこの時に身に付けました。
4サイクルエンジンとなったJA71型:1984年には同じボデーですが、エンジンが4サイクルターボエンジンになりました。静かでよく走る様になり、ボデーの出来具合も良くなり実用性は大きく上がりましたが、この頃から改良される度に、モデルが変わる度に車重が重くなって行き、走破性はピーク時に比べると少しずつ低下して行きました。1990年にはJA11型となり全長のみ100㎜長くなりましたが、特に大きな変更はありません。

コイルサスとなったJA12型:1995年にはJA11型と同じボデーですが、サスがコイルになったJA12型がデビュー、永年のテーマであった乗り心地は著しく改善されました。
同じ1995年にはワゴン登録のJA22型がデビュー、こちらにはアルトワークスやワゴンRと同じ新しいパワフルなエンジンを得まして、生まれ変わりましたと言うより、乗り心地、走り共に満足の行く物となり、普通的にも不満無く使える車になりました。

余りの評判にワイフの買い物用に購入してみました。走りと乗り心地に大きな不満はなかったのですが、スズキと言うメーカ―は大いに疑問のある会社でした。
デーラーオプションのメッキグリルにした処、ウインカーの配線がしてありませんでした。新車納入であるにも拘らず信じ難いミスでした。更にサスから異音がし、調べてみますと右前輪ショックアブソーバの上部マウントの締め忘れでした。これまた信じ難いミスです。
更に僅か2年でウインカーレンズを止めているビスとスペアホイールの裏側は錆びて来ました。これ等は本来無償修理の筈なのですが、クレーム対象期間を過ぎていたので門前払いでした。前者はホームセンターのステンレスビスに取り換え、後者は自分で塗装をやり直しました。
更にもう1件門前払いだったクレームがありました。それはジムニー好評でスズキは心を入れ替えたかなと思い購入した娘の通学用のワゴン車でした。10年近い中古車でしたが、ATの変速が不能になり、調べますとプリント版の湿気による誤動作でした。
プリント版は消耗部品ではなく、エンジンや車体と同程度の長期対応部品ですからクレームを申請したのですがこれも門前払い、ジムニーのトラブルと合わせまして再びスズキの車はもう死ぬまで絶対に買わないと言う事になりました。
解体屋で同系車を見るとそのプリント版は全て抜かれていました。
つまりその故障はよくある事だったのです。
対策はプリント版をシリカゲル乾燥材で包むだけで完治、スズキと言う会社の次元の低さを強く感しました。これ以外にも現在のスズキの車は完璧にまっすぐ走れません。
この様な会社のスズキでは将来的に生き残りは難しいと思われます。
クレームとは:ガス湯沸かし器等がガス中毒の恐れがあるとし、20年近く前の商品の回収をテレビで呼び掛けていた事を覚えておられますでしょうか?
つまり重要な案件に付きましては期間の設定は無いのです。
クレームは起こる筈のないトラブルが起こった時の無償修理制度です。そもそもクレームはなぜ起こるのか? それは「設計不良」「材質不良」「組立不良」「等々」が重なり本来の性能が出せなかった場合に起こりますが、実は重要なのはその原因は何処にあり、その原因の時期が何時だったのかの方が重要になります。
更に物品の購入にしても「暗黙の了解」と言う項目があります。昨今の新車を購入すれば、10年10万㎞は殆ど壊れずに運用出来ると言う物です。そう言う了解の上に契約が成り立っており、長期部品は保証期間に関係なくクレームは成立するのです。
トヨタにはこの権利を主張する機会が近年は殆ど無くなりました。
ニッサンは対応可、三菱は割引に応じ、スズキは非対応、マツダとホンダは分かりません。
ホンダは1964~1970年にS600やS800と言う高性能なカッコイイスポーツカーがあり、また1969~1972年まで1300クーペ9と言う画期的な性能のモデルがありましたが、共にたくさん売れたのにあっと言う間に姿を消してしまいました。耐久性が著しく不足していたのです。


今のホンダはアメリカでは50万㎞走れる車ですが、その記憶が何時までも抜けず、ホンダはケンさんの選択から何時も除外されていました。
その後ジムニーは1998年には大きく丸くなった新しいボデーのJB23型になり、2018年には現用の電子装備の多くなった角形のボデーのJB64型となりました。
しかしエンジンパワーは向上せず、車重のみ重くなり、今や1tを超えました。


結果的に旧角形ボディー最終モデルのJA22型は最高の走れる車と言う事になりました。高速道路を120㎞/h以上の速度で余裕の巡航、トレーラーを牽引しても登坂車線不要には驚きました。
初期のLJ10型では登坂車線を20㎞/hでしか走れなかったのですから、夢の様な走りが可能になりました。
ジムニーJB23型に対し、類似のパジェロミニがありました。ユーザーはパリダカ連続優勝系列の自称1流メーカーのパジェロミニが2流メーカーのジムニー如きに負ける筈が無いと思っていました。

同様に本家パジェロもトヨタの凡作プラド如きに負ける筈が無いと信じて購入しましたが、実際にはプラドは全項目大差で圧勝、パジェロ系は全て3~4流だったのです。その三菱はどうなったのか? パジェロは製造中止になり、三菱自動車自体が存続の危機を迎えています。
ジムニーのライバルは現在皆無、しかしこの34年間に進化したのはコイルサスだけ、他は軽自動車枠拡大だけで殆ど進化しておらず、最新型JB64型も電子装置の追加装備だけ、将来的に言えばかなり心配です。
国内の軽№.1は永らくスズキの指定席でしたが、昨今はトヨタ品質のダイハツが定着、スズキは全ての面で真面目に取り組んで欲しいと思います。
クレーム対応はユーザーの為もありますが、本当は自社の為なのです。
トヨタの高品質はここからがスタートでした。
デビュー以来他社の追従を許さない世界に誇れる日本製品として挙げられるのは、トヨタのランドクルーザー、ホンダのスーパーカブ、そしてスズキのジムニーがあります。ランクル40型は2017年、スーパーカブC100型は2009年、初代ジムニーLJ10型は2020年に歴史遺産車に指定されました。
ホンダ―スーパーカブ:1番凄いのはこれです。
1958年に「C100型」がデビュー以来、2017年には累計1億台を超え、今も変わらない原設計のままで世界の多くの国で継続生産中、その後幾多の後発メーカーの製品も出ましたが、何れもスーパーカブを凌駕出来ず、世界№.1の座を今も更新中です。ホンダの創立者である本田宗一郎さんの世界に誇るべき作品です。

ランドクルーザー:1951年にトヨタジープBJ-10型を自衛隊向けに試作、日産も4W60型ジープを提出、三菱のウイリスのアンダ―ライセンスジープに敗れ、ランクルは当初から輸出に向けられました。1954年には三菱からジープと言う名称を使うなとクレーム、以来ランドクルーザーとなりました。

当時の日本製品は安かろう悪かろうの時代ですが、海外で最初に認められた日本の工業製品はこのランドクルーザーです。2019年には累計1000万台を達成、高品質と耐久性と乗り心地が評価され、世界の追従を許さない車となりました。
日本には日産、三菱、マツダ、日野、いすゞ、スズキ、ダイハツ等のたくさんの自動車メーカーがありますが、その中でも最も技術レベルの低かったトヨタが世界の№.1になったのですから痛快です。
当時トヨタフォークリフトの設計に在籍していましたが、1970年までのトヨタは壊れない所が無いと言える位に良く壊れました。
実はケンさんがランドクルーザーに乗り始めたのは1980年のBJ60型からですが、もしトヨタエンジンだったら見送りましたが、ダイハツエンジンだったので購入、その時から切っても切れないランクル人生となりました。
時代は変わり1990年以降のランクルを含むトヨタ車は世界で最高の品質の車となりました。
1例としてケンさんは1998年型ランクル100型を22年間で15万km乗りましたが、ずっと無整備で時期が来たら公的車検場で検査を受けるだけを繰り返し、概ねアンタッチャブル&無故障で22年間を過ごす事が出来ました。我ながらここまで無整備で乗り切れるとは思っておらずこれには驚きました。
高耐久性以外にも最高の乗り心地も得られ、ランクルより10年以上新しいニッサンキャラバンで400㎞走るとしっかり疲れますが、ランクルで1000㎞走った方が疲れないのですから恐れ入ります。
オーストラリアやアフリカに行きますと僻地に行けば行くほどランクルオンリーになります。
ランクル神話に「生き残りたかったらランクルにしなさい」と言う伝説がある程です。
ランクルはWW2後の自衛隊向けの入札に敗れた為に輸出に廻され、海外で評価が得られたのも荒川社員の頑張りがあったからなのです。同時期にスタートした日産のパトロール(サファリ)や三菱のジープやパジェロがその後は売れずに、とうとう製造中止になった事と比べますと、天と地の差があります。ランクルのストーリーは長くなりますので別の機会にさせて頂きます。
2.スズキジムニー。
ジムニーはスズキ自動車が生産する本格的な軽4輪駆動車であり、これまた世界の追従を許さない走破性の高さとタフさを持っています。実はランクルが先頃までトヨタ製では無く荒川車体(初期には荒川板金)だったと言う経緯がありますが、その荒川は豊田自動織機からトヨタ自動車が分離して間もなく、1部のメンバーが自己資本で自前独立したのが始まりです。
ジムニーも実は原型はスズキ製では無かったのです。
スズキが作ったら多分パジェロミニの様な駄作になったと思います。
ジムニーの原型:東京のホープ自動車のON型がベースになっています。

ホープON型は三菱系のエンジンや駆動系部品が使われておりましたが売れず、1967年から100台程を売った処で製造権の譲渡先を探しました。最初の行ったのは従来のエンジン等の購入先の三菱、次いで国内の全ての軽自動車メーカーを一巡しましたが全て門前払いでした。
最後の残ったのはスズキだけ、どうせ買ってもらえないだろうと、本社ではなく東京営業所に話を持ち込みました。これが運命の分かれ道となりました。当時スズキ東京の社長が後のスズキの大社長であり大会長となった鈴木修氏、2つ返事で購入したそうです。
酷い欠陥車だった初代ジムニーLJ10型:多くが三菱系の部品で出来ていたホープON型を当時のベストセラーであった軽トラのスズキキャリーの部品を流用して再設計したのがジムニーであり、1970年のデビューでした。原型のホープON形にもかなりの欠陥があった様ですが、ジムニーLJ10型も欠陥が多数ありました。

そうとは知らないケンさんは近隣の農家でも多数の軽トラキャリーがノントラブルで動いているので、その延長の稼働率が得られるだろうとして購入したのですが・・・・・結果はしっかり裏切られました。
次から次へと重要部品が壊れるので、数千㎞の僅か1年でクビにしました。壊れたのは次の通りです。まずはエンジンを廻し過ぎない様に注意していたのですが、それでもピストンに穴が空いてしまいました。次にデフのギヤが欠けてしまい、ドライブシャフトも折れてしまいました。更にステリングのジョイントがガタガタになってしまいました。
何れもキャリーの中古部品を利用して自分で直しましたので費用的には知れていましたが、信じられないトラブルの連続には驚きました。この時にスズキの車は金輪際もう買わないと決めました。
それ以外に走らないのには驚きました。当時の軽自動車は僅か360㏄の25hp、今の軽自動車の半分程度のエンジンで、豪快な走りは期待出来る物ではありませんでしたが、登坂車線を4速ミッションの3速ならまだ我慢出来るのですが、2速の20㎞/hでしか走れませんでした。
加えて致命的な欠陥の数々、それは圧倒的に問題の多かったトヨタ車よりも遥かに多いトラブルでした。よくぞこんな欠陥車を販売した物だと思いました。出来の悪い車でしたが、その後の大記録の出発点となった初代ジムニーは2020年に歴史遺産車に指定されました。
使える車に育った2代目ジムニーLJ20型:1972年エンジンが換わったLJ20型になり、排気量は同じ360㏄ながら水冷2気筒28hp、馬力もトルクも12%程上がり、当時の並の非力車になりました。
そしてあれ程あった欠陥は概ねが対策されたらしく、当時の並の軽自動車になりました。

壊そうとしても壊れなかった SJ10:1976年からは初代ジープ系最後のSJ10型となりました。
車体は長さ200㎜、幅100㎜大きくなり、エンジンは550㏄の28hpになりました。
最大馬力は同じですが、圧倒的なトルクアップの1.4倍、パワー不足感は無くなりました。

1981年からは新しい箱型ボデーに変わり、SJ30型になりましたが、このSJ30型までが2サイクルエンジン、重量が軽く、素晴らしいトルクを発生してくれ、また水没してもウォーターハンマーを起こさず、水を抜けば直ちに甦るのも大きなメリットと言えました。

SJ10型やSJ30型は車重も700kg前後と軽く、スタックしても人力で何とか出来る車でした。
更にジープ型最終ボデーの車は壊そうとしても壊れない程の完成度に仕上がり、オフロード走破性の高さは最強、ジムニーの黄金期と言える作品でした。
当時毎週水曜日の夜がケンさんの所属するオフロードクラブの悪路走行会、近くの河川敷でスタックや水没を楽しむ会でした。
ヒルクライムの主役はランクル40でしたが、川渡りの主役は2サイクルジムニーでした。
ケンさんの接地センサーや駆動センサーはこの時に身に付けました。
4サイクルエンジンとなったJA71型:1984年には同じボデーですが、エンジンが4サイクルターボエンジンになりました。静かでよく走る様になり、ボデーの出来具合も良くなり実用性は大きく上がりましたが、この頃から改良される度に、モデルが変わる度に車重が重くなって行き、走破性はピーク時に比べると少しずつ低下して行きました。1990年にはJA11型となり全長のみ100㎜長くなりましたが、特に大きな変更はありません。

コイルサスとなったJA12型:1995年にはJA11型と同じボデーですが、サスがコイルになったJA12型がデビュー、永年のテーマであった乗り心地は著しく改善されました。
同じ1995年にはワゴン登録のJA22型がデビュー、こちらにはアルトワークスやワゴンRと同じ新しいパワフルなエンジンを得まして、生まれ変わりましたと言うより、乗り心地、走り共に満足の行く物となり、普通的にも不満無く使える車になりました。

余りの評判にワイフの買い物用に購入してみました。走りと乗り心地に大きな不満はなかったのですが、スズキと言うメーカ―は大いに疑問のある会社でした。
デーラーオプションのメッキグリルにした処、ウインカーの配線がしてありませんでした。新車納入であるにも拘らず信じ難いミスでした。更にサスから異音がし、調べてみますと右前輪ショックアブソーバの上部マウントの締め忘れでした。これまた信じ難いミスです。
更に僅か2年でウインカーレンズを止めているビスとスペアホイールの裏側は錆びて来ました。これ等は本来無償修理の筈なのですが、クレーム対象期間を過ぎていたので門前払いでした。前者はホームセンターのステンレスビスに取り換え、後者は自分で塗装をやり直しました。
更にもう1件門前払いだったクレームがありました。それはジムニー好評でスズキは心を入れ替えたかなと思い購入した娘の通学用のワゴン車でした。10年近い中古車でしたが、ATの変速が不能になり、調べますとプリント版の湿気による誤動作でした。
プリント版は消耗部品ではなく、エンジンや車体と同程度の長期対応部品ですからクレームを申請したのですがこれも門前払い、ジムニーのトラブルと合わせまして再びスズキの車はもう死ぬまで絶対に買わないと言う事になりました。
解体屋で同系車を見るとそのプリント版は全て抜かれていました。
つまりその故障はよくある事だったのです。
対策はプリント版をシリカゲル乾燥材で包むだけで完治、スズキと言う会社の次元の低さを強く感しました。これ以外にも現在のスズキの車は完璧にまっすぐ走れません。
この様な会社のスズキでは将来的に生き残りは難しいと思われます。
クレームとは:ガス湯沸かし器等がガス中毒の恐れがあるとし、20年近く前の商品の回収をテレビで呼び掛けていた事を覚えておられますでしょうか?
つまり重要な案件に付きましては期間の設定は無いのです。
クレームは起こる筈のないトラブルが起こった時の無償修理制度です。そもそもクレームはなぜ起こるのか? それは「設計不良」「材質不良」「組立不良」「等々」が重なり本来の性能が出せなかった場合に起こりますが、実は重要なのはその原因は何処にあり、その原因の時期が何時だったのかの方が重要になります。
更に物品の購入にしても「暗黙の了解」と言う項目があります。昨今の新車を購入すれば、10年10万㎞は殆ど壊れずに運用出来ると言う物です。そう言う了解の上に契約が成り立っており、長期部品は保証期間に関係なくクレームは成立するのです。
トヨタにはこの権利を主張する機会が近年は殆ど無くなりました。
ニッサンは対応可、三菱は割引に応じ、スズキは非対応、マツダとホンダは分かりません。
ホンダは1964~1970年にS600やS800と言う高性能なカッコイイスポーツカーがあり、また1969~1972年まで1300クーペ9と言う画期的な性能のモデルがありましたが、共にたくさん売れたのにあっと言う間に姿を消してしまいました。耐久性が著しく不足していたのです。


今のホンダはアメリカでは50万㎞走れる車ですが、その記憶が何時までも抜けず、ホンダはケンさんの選択から何時も除外されていました。
その後ジムニーは1998年には大きく丸くなった新しいボデーのJB23型になり、2018年には現用の電子装備の多くなった角形のボデーのJB64型となりました。
しかしエンジンパワーは向上せず、車重のみ重くなり、今や1tを超えました。


結果的に旧角形ボディー最終モデルのJA22型は最高の走れる車と言う事になりました。高速道路を120㎞/h以上の速度で余裕の巡航、トレーラーを牽引しても登坂車線不要には驚きました。
初期のLJ10型では登坂車線を20㎞/hでしか走れなかったのですから、夢の様な走りが可能になりました。
ジムニーJB23型に対し、類似のパジェロミニがありました。ユーザーはパリダカ連続優勝系列の自称1流メーカーのパジェロミニが2流メーカーのジムニー如きに負ける筈が無いと思っていました。

同様に本家パジェロもトヨタの凡作プラド如きに負ける筈が無いと信じて購入しましたが、実際にはプラドは全項目大差で圧勝、パジェロ系は全て3~4流だったのです。その三菱はどうなったのか? パジェロは製造中止になり、三菱自動車自体が存続の危機を迎えています。
ジムニーのライバルは現在皆無、しかしこの34年間に進化したのはコイルサスだけ、他は軽自動車枠拡大だけで殆ど進化しておらず、最新型JB64型も電子装置の追加装備だけ、将来的に言えばかなり心配です。
国内の軽№.1は永らくスズキの指定席でしたが、昨今はトヨタ品質のダイハツが定着、スズキは全ての面で真面目に取り組んで欲しいと思います。
クレーム対応はユーザーの為もありますが、本当は自社の為なのです。
トヨタの高品質はここからがスタートでした。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その6:トヨタプリウス&ディーゼルの発展
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その5:ジムニー最新型
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その4:ジムニーライバル登場そして自滅。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その3:唯一の改良コイルサス。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。
嘘もイイ加減にしなさい。その12:ランクルの強度と耐久性。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その5:ジムニー最新型
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その4:ジムニーライバル登場そして自滅。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その3:唯一の改良コイルサス。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。
嘘もイイ加減にしなさい。その12:ランクルの強度と耐久性。
Posted by little-ken
at 11:16
│ハンティングカー