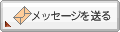2020年11月28日
セドリック ディーゼル
ウイリスジープ:ケンさんの車人生は写真のウイリスジープ1954年型のCJ3B型から始まりました。 ジープはそれなりに良い車でしたが、最大の悩みは燃費でした。

1リットル50円で5~8㎞しか走らなかったのです。それ以前はバイクで25㎞/㍑でした。このバイク時代でも燃料代は最大の悩みの種でした。当時のガソリンは50円で10㎞強/㍑でした。と言う事はツーリングを 半分以下にしなければならないと言う事になります。
ベレット ディーゼル:それで色々調べました所、ディーゼル車なら燃費も良くガソリン車の1.5倍、更に燃料単価はガソリンの半分以下、走りは期待出来ませんが、これならツーリング回数は減らさなくても済みます。

それで購入したのはいすゞの1964年型ベレットPRD10型を1969年に購入しました。
取説によれば1800㏄、50hp、110㎞/hとありましたが、最大巡航は80㎞/h程度、これを超えるとオイル消費が著しく増しました。実用燃費は15㎞/㍑、ガソリン換算30㎞/㍑と十分目的を達成出来ました。
平坦路の実用加速はそれ程悪くないのですが、MT3速車はちょっとした登りでも2速にダウン、45㎞/hしか出せません。登坂45㎞と巡航80㎞/hはかなり不満でした。不可能に挑戦はこの時SWが入ったと思います。
しかし実行に移す前にベレットは友人に貸したら居眠り運転で崖下にダイビング、運よく立ち木に掛かり人間は小破でしたが車は大破、使用不能になってしまいました。
その後まもなくいすゞはディーゼル乗用車から撤退、ベレットの改造は未着工のままで終わりました。
ベレットは12V車ですが、始動系と充電系は24Vでした。24Vスターターの始動性は良かったのですが、直列バッテリーの中間から12Vを取り出すだけなので、片方のバッテリーだけがすぐに上がってしまう曲者でした。
この点ランクルの昔は全て24V、1988年以降はスターターだけ24V、常用はバッテリー2個並列運転した12V、始動時は直列に切り替え24Vで始動しますから、後述スキー場の下り坂始動をせずに済む様になりました。
セドリックディーゼル:その後しばらくはディーゼル車が途絶え、カローラ1100とブルーバード1600のガソリン車に乗っていました。まもなく臨市の自動車学校がセドリックディーゼルを使用し、4年毎に払い下げると言う情報を仕入れました。早速申し込みに行きました。検定車は走行3万km程度で10万円、教習車は10万km程度で 3万円との事でした。弟も欲しいと言う事で検定車2台と部品取用に教習者1台を申し込みました。

セドリックディーゼルは払下げより、2年程早い1973年、12万円で売りに出ているのを見付けそれを購入しました。出所は同じ自動車学校、Q-130後期型でした。そして1976年には待望の直接払下げ車のQ-230型右写真を入手しました。2つは性能的には大差なく、2000㏄の55馬力、常用性能もそれに対する不満もベレットと同様でしたが、ディーゼルエンジンに強い、いすゞと違って冬季の始動性にかなり問題がありました。
始動性の改善:セドリックディーゼルの構成はタクシーや自動車学校用のガソリン4気筒2000㏄のエンジンをそのままディーゼルエンジンに置き換えただけと言う構成で,電装関係もギヤ比も信じられない事にそのままでした。冬季には当然の様に始動困難でした。始動性の問題点は12V運用が最大のネックでした。
パワーハーネスの容量不足に加え、配線の取り廻し不良、そしてアース不良でした。
ケンさんは電気式のフォークリフトの設計をしておりましたので1目で分かりました。
対策は電線を2倍に太くし、最短距離に変更し、アースも同クラスの電線で直接取りました。結果、外気0℃で 従来2~3分を要していた始動時間は20~30秒で済む様になりました.
直ちに弟の車や友人達の車にも同様の対策が施され、全車の始動性が著しく向上したのは言うまでもありませんが、メーカー新車のパワーハーネスやアースが改善されたのは驚いた事にケンさんの成功から7年後となりました。つまり日産には誰も真面目にこの始動性対策に向き合った技術者がいなかったのですから恐れ入ります。
セドリックディーゼルは外気マイナス15度以下になるとエンジンその物が始動不能でした。
対策は相当な高回転を与えるしかありませんが、エンジンその物の始動性に問題がありましたので、モーターの強化程度では追い付きません。
スキーでは近くの山道の下り途中に駐車、翌朝はグローを十分予熱後に スターターを廻しながら下り坂を走り続けました。1分程下り坂クランキングアシストを続けると初爆があり回転が上がり始め、更に10~20秒で連爆となり、間もなく始動すると言う状況でした。毎朝これが日課でした。
ギヤ比の再設定:セドリックディーゼルはガソリエンジンをそのままディーゼルエンジンに置き換えただけ、エンジンの許容回転数が2/3であるにも拘らず、ギヤ比はそのままでした。
3速MTで最大巡航速度は90㎞弱/h、登坂車線は2速で45㎞/hと大きな不満がありましたが、車両設計者でもあるケンさんは巡航速度&登坂速度の問題もギヤ比の変更でかなり大幅に改善出来ると読みました。
当時日産にはセドリックに使えるデフのギヤ比は3.9と4.3と4.6の3種がありました。同様にトランスミッションは タクシーや自動車学校用の3速、ライトバン用の4速、高級車用のOD付3速がありました。標準仕様では3速MTと4.3のデフでした。
3種類のMTと3種類のギヤ比のデフの全てを解体屋で調達し、全ての組合せで試験走行してみる事にしました。期待出来そうなのは4速MTと小さ目ギヤ比のデフ組合せ時、又はOD付3速MTに大き目ギヤ比のデフを組合せた時の2種です。
2か月後、結果が出ました。後者のOD付3速MTにギヤ比の4.6のデフを組合せが最良でした。
巡航速度はOD比0.7のお陰で従来90㎞/hから120㎞強/hにまで向上、加速も巡航燃費も10%程向上しました。
最大の効果は登坂車線問題でした。デフのギヤ比10%違いが駆動力向上となり、ベタ踏みで登坂車線を3速でかろうじて粘る事が可能になり、少し助走しておけば登坂車線の終りまで90㎞/hを維持出来ました。一旦速度を落とすと回復は不能ですが、ツーリングのストレスが大幅に少なくなった事は言うまでもありません。
ところがこの組合せが商品化されたのは始動性の改善と同じ7年目、繰り返しますが日産にはギヤ比も始動性も真面目に考える技術者が誰もいなかったのです。これが技術の日産だそうですから笑ってしまいます。
技術が無いのかやる気が無いのかは分かりませんが、ダメな会社でした。
そう言った良くない伝統が根本的に対策されないので、日産はやがて存続のピンチになり、ルノーからゴーン氏を迎えましたが、それも上手く行かず、今また存続のピンチに陥っています。
ランクル80のギヤ比:ランクル80型は良く出来た車両であり、このモデルから画期的に良くなった項目がたくさんありました。まずサスがコイルスプリングになり、乗り心地と走破性が圧倒的に向上しました。
更にストロークエンドのラバークッションシステムが大幅に改善され、適正なショックアブソーバとの組合せにより、他に類を見ない程の大衝撃吸収性が改善されました。また錆び対策や塗装も大幅に進化しました。更にディーゼルエンジンが高性能となり、これらの結果から世界ダントツの位置に駆け上がりました。
しかしこの時点でトヨタも国内では出来なかった事があります。それは排ガス絡みで低速時の燃料噴射量を増す事が出来なかった事と、同じく排ガス絡みでベストギヤ比に設定出来なかった事です。
結果としてHD型4200㏄エンジンで165hpのランクル80がプラド78のKZ型の3000㏄の130hpにスペック上は全く負けていないのですが、実走行では格下のプラドに大きく負けてしまいました。


プラドのKZエンジンは稀に見る傑作エンジンと言われていましたが、ライバル他車対決でパジェロは4M40 エンジンを2個積まなければ勝てない、テラノはTD27を3個積まなければ勝てないと言われていました。
そこでケンさんはランクル80に車検に受かるレベルの改造を施しました。低速時の燃料噴射量を増し、デフのギヤ比を5%大きい輸出用に変更したのです。この改造で格下プラドに負ける事も無くなり、トレーラー牽引もストレスなく出来、加速も燃費もかなり改善しました。ケンさんのハンティングカーの赤いランクル76型も燃料噴射量のチューニングとギヤ比の変更を行っています。
ランクルのノーマルHDエンジンを余り良くない様に書きましたが、マイクロバスのコースターでは排ガス規制が甘くなりランクル80より10~20%パワフルでした。またコースターは日産のシビリアンや三菱のローザに圧倒的な動力性能で勝っていました。またこのHDエンジンをマリン用にした場合、2倍近い350HPとパワフルです。
またランクルは同排気量のサファリのTD42エンジンには超圧勝でした。そんなダメなサファリは2007年に製造中止されてしまい、マイクロバスのシビリアンはガソリン車だけとなりました。非常に情けない日産です。
その次に運用した白のランクル100型には最初からこれらの対策が行われ、初めて無改造のまま気持ちよく運用出来ました。乗り心地もショックアブソーバの制御がコンピューター式となり、走破性共々更に大幅に改善されました。
トラクションコントロール(TRC)にしましてもランクル200型になりますと僅かにスリップを始めた時点で効き始め、他社の大きくスリップしてから慌ててブレーキを掛けているTRCとは出来が違います。
トヨタの評価が世界中でまた大きく上がったのは言うまでもありません。
さて問題点の多かったセドリックディーゼルですが、唯一好評と言われた車体の耐久性も左程ではなく、走行が20万kmとなった4年目には部品取り用の教習車の部品は概ね消費し尽くされてしまいました。
結果から言えば、もうその頃には耐久性に大幅劣ると思われていたトヨタに逆転を許してしまっていたのです。しかしセドリックで日本数周のツーリングに楽しく行けたのは事実、出来が良くない日産のSD20ディーゼルエンジンのお陰でした。その頃には車体の出来は良くなったトヨタですが、ディーゼルエンジンはまだ悲惨でした。
ディーゼル車の発展:古いイメージのディーゼル車は、燃費は良いが加速は悪く、巡航速度は不十分、上り坂では悲惨、そして排気ガスは汚く、車全体も臭く、エンジンは脂の滲みが多く真っ黒でした。
1985年頃まではその良くない伝説の通りでしたが、その頃でも低速トルクの粘りには群を抜く物がありました。同年ランクル60はターボ付12H‐Tになり、巡航速度の不足と上り坂問題だけは一気に解決しました。
1989年ランクル80がデビュー、新エンジンはHD-Tになり、燃費はやや低下しましたが、圧倒的なビッグトルクとなり、ガソリンエンジンを大きく凌駕しました。
ガソリンエンジンに負けない動力性能は長い間の夢でしたが、ここに達成されたのです。
良いエンジンに恵まれランクルは優れた走破性や車体強度の下地もあり、一気に世界のベストセラーに上り詰めました。この時代の排気ガスはまだ綺麗とは言えませんが、エンジンはオイルの滲みがなくなり綺麗なままになりました。
1993年、名エンジンと言われたKZがデビュー、ランクルプラドやハイエースに搭載されました。
カタログパワーは驚く程ではないのですが、実用的な走りは圧巻の一言、最早ガソリン車との比較の時代は終り、幾つかのシリーズでは低性能のガソリンエンジンがバリエーションから消え去りました。
ディーゼルはその後も徐々にクリーン化が進み、2017年にはクリーンディーゼルがデビュー、最早全ての欠点は過去の伝説となり、それを知らないのは地球上で日本人とアメリカ人だけとなりました。
ルマン24Hで勝つ為には:1923~2005年までの長い間はずっとガソリンエンジンの時代、それが当たり前でした。流れが変わり、アウディのターボディーゼルが2006~2014年の上位を独占しました。以後は勝つ為に絶対に必要なのは燃費と耐久性面からディーゼルエンジンとなりました。
しかし更に時代は変わり、今はハイブリッドでなければ勝てない時代となり、2015~2017年はベンツのガソリンハイブリッド車が上位を独占し、2018~2020年はトヨタが上位独占3連勝しています。我がトヨタも勿論ハイブリッドです。
プリウス:故障の1番多かったトヨタが今では1番故障の少ないメーカーになり、プリウスシステムもケンさんを含む世界中から使えないと言われていましたが、トヨタの看板商品に育ちました。この2つにはトヨタの執念を感じます。ディーゼル乗用車の実燃費が20㎞弱/㍑に留まっておりますが、ここでもレースの世界同様にすでに逆転が起こりプリウスは25㎞/㍑となりました。
しかし重いボデーの場合はまだディーゼル車の圧勝、ランクルやトラックに使えるヘビー級プリウスシステムの出現を期待する所です。
1997年に初代プリウスはデビューし、10・15モードで28㎞/㍑でした。
高速道路や郊外が多ければプリウスシステムは有効に働かず、28㎞/㍑はどんなに超ケチケチ運転をしても達成出来る数値ではなく、絵に描いた餅であり、世界中が使い物にならない車だと思っていました。
2002年にデビューした2代目は10・15モードで35㎞/㍑とかなり向上しました。走行フィーリングもかなり向上し、良く売れました。2代目は空走を多用した運転をすればかなり高燃費が出せました。
個人的な燃費チャレンジをする人が多く、車の流れを乱す車が多かったのが印象に残っています。
2009年には3代目がデビュー、エンジンもモーターも強化され、最早省エネ運転に挑戦しなくても20㎞/㍑をクリア出来る様になり、実用性に不足のない車となり、爆発的に売れまくりました。
エンジンは膨張行程の方が圧縮行程よりかなり長いアトキンソンサイクルの高効率の新エンジンとなり、抜群の燃費と走行フィーリングが可能となりました。
2015年には4代目がデビュー、3代目と類似スペックながら、リチウム電池採用でバッテリーの耐久性問題から決別、走行フィーリングも一段と向上、今やスポーツドライブを楽しめる車となり、それでいながら燃費も向上、JC8モードで40㎞弱/㍑と言う素晴らしい燃費を達成、普通に乗っても25㎞/㍑は難しくなくなりました。
プリウス単体は今やベストセラー車ではなくなりましたが、その理由はトヨタの新車の60%超がプリウスシステムを載せているからです。しかし今の日本の運用状況である10年又は10万kmと、現在の燃料単価では省燃費メリットは得られません。現状では40万円高額な車を売ったメーカーとそのシステムの部品メーカーが儲かっただけ、全体的から見ればCO₂が多少減少し、ガソリンスタンドの経営を多少圧迫したに過ぎません。
車は何年まで使えるのか?:日本では今だに10年又は10万kmが近くなっただけで、そろそろ交換されてはと言われます。それは車を売る方の都合であって、車の寿命はまだ70%残っております。10年で手放した車はどうなるのか? 何処かの国に輸出され少なくもそこで更に30年間の運用をされます。
日本車の寿命はそれだけあると言えばそうなりますが、大きな修理なしに乗れる期間は概ね現在の思いの2倍以上、少なくともトヨタ車なら概ね20年又は30万kmだと思います。
オーストラリアで20万km未満の中古車には走行距離が少ないと言う表現が付けられます。日本的に言ったら、完全に末期状態にある事になりますが、そうではなく、軽く50万km走れるのでそう言う表現になるのです。
国内のタクシー用の中古車市場に於いても、50万km以上走った車にも相応の価格が付いており、それはまだ今後もそれなりに多少は使える事を意味しています。因みにトヨタコンフォートの寿命は100万km以上です。
ケンさんランクル100型は新車時500万円でしたが、22年間で15.5万kmまで殆ど無整備で乗り切れました。2020年、叩き売っても200万円以上、買えば300万円の価値があります。つまりまだ半分程度は十分使える 価値がある事を示します。
ただ同じ日本製であっても日産や三菱の場合はトヨタの数倍のトラブルがあります。
ワーゲンやボルボを自慢している友人もいますが、トヨタ車の優秀さを知らない人が多く、気の毒に思います。
車検整備:そう言う法定用語はありませんが、12カ月または24カ月点検は法律で受ける事を決められて おり、それに対して定期交換部品と言う物は自動車の場合はありません。
勿論10年を超えたから点検項目が増え、交換部品が増える事もありません。
車検自体はメカは分からなくても良いので、自分の車に関心を持ち、責任を持って、自分で法定点検を行い、受検するのが本筋です。やりたくない人や手を汚したくない人は、資格を持った業者に、代行をお願い出来るのが現在の法制度です。
点検は分からないながら車の下に潜って自分で各部を見て触って見ます。漏れも緩みもなく、ちゃんと走ればまず問題はありません。点検記録用紙は愛車手帳にあり、試験ではありませんから、この名称は多分これ、良いと思えばチェックマーク、未記入の部分を無くします。未記入の部分があると、点検をしていないと解釈され法定違反となります。これで法定点検は終りです。悪くなければ整備をする必要はありません。
法定点検の次は検査を受けなければなりませんが、これが車検です。近くの公的車検場に予約して持ち込めば、2000円程度で検査をしてくれます。車のナンバープレートと違う車検場でもOKです。
もし不合格ならば、車検場の検査用紙には不具合内容が掛かれており、それを持ってデーラーに駆け込みます。トヨタ車なら午前中に駆け込めば、3時頃に部品が到着し、付けてもらったらそれで車検場で再検査、無料です。その日に間に合わない時は日を改めますが、予約は不要、検査代2000円が再度必要です。
オイル等の定期交換サイクルはマニュアルにありますが、従来思っているより遥かにロングインターバルです。ガソリンスタンドや車の用品店の交換サイクルやオイルのグレード等の奨めに従う必要は全くありません。
指定グレードのオイルはドラム缶で買うと150円/㍑とガソリンと同程度の価格ですが、これで十分なのです。マニュアルはそれで絶対に大丈夫と言う指定サイクルですからそれで数十万kmの耐久性があります。2倍サボッても多分壊れません。それより大幅に手やお金を掛けても勿体ないだけです。
減るのはタイヤ、そしてブレーキパッドだけです。タイヤを交換する時にパッドも見てもらいましょう。
目視で簡単に見えます。半分以上あれば次回タイヤ交換時でOKです。
10万kmになったらベルトやホース類のゴム部品を換えると良いと思いますが、近年は泡良くば20年又は20万kmの寿命がある様です。これで新車は今まで思っていたよりも2倍は使えますし、車関係の無駄な出費は激減となりました。
トヨタの車は何時から使える車になったのか?:1960年代までのトヨタはよく壊れました。1963年に名神高速道路が開通しますと高速道路には故障車が溢れました。
当時のシェアはトヨタも日産も概ね30%ずつでしたが、故障車全体の60%がトヨタ車、それ位トヨタの車は良く壊れました。
しかし1970年型のパブリカ1000は壊れませんでした。多分この頃が境目だと思います。
ケンさんの最初の愛車はいすゞのべレットディーゼル、次はディーゼルが無くなり、やむなく初代1968年型のカローラ1100、ところが僅か1万kmでショックアブソーバもステアリングもガタガタ、トヨタはダメな車でした。それで次はブルーバード1600、5万kmくらいしか使いませんでしたが、リヤのケツ下がり以外は良い車でした。


当時はトヨタに務めていたのにどうしてケンさんの愛車は非トヨタ車だったのか?
トヨタはすぐに壊れるので使う気が起こらなかったのです。1980年に購入したランクル60もトヨタエンジンなら買わなかった、1966~1970年の初代カローラ対サニーの戦いは販売上カローラの圧勝でしたが、技術内容的にはサニーの圧勝、初代カローラはすぐ壊れる、これが当時のトヨタ車でした。
さてセドリックディーゼルで全国をツーリングしていた時代の中盤、1977年にケンさんは結婚、ワイフの練習用の車を購入しました。1970年型のパブリカ1000で7年落ちでした。
車検が1年残っていたので、運転練習に1年間使えればと思い、解体屋で3万円の車でした。

そして1年後まだ好調なのでユーザー車検を受けました。2年後も好調なので再度ユーザー車検を受けました。こうして5年間約5万kmをノントラブルの無故障で走り切りました。
交換したのはバッテリー3000円、中古マフラー1000円、中古タイヤ4000円、これが全てでした。
結論として1970年型パブリカはエンジンオイルすら交換なしに5万kmを快調に走り切りました。予定では数年を持たずして壊れると思っていたのですが、見事に裏切られました。この時にトヨタ車が頻繁に壊れる時代は終わたのを感じました。カローラも2代目からは壊れない車になり、世界で1番売れた車種となりました。
1970年代までのタクシーは耐久性が理由で、市街地はトヨタ、山間部はニッサンでしたが、本当はもう逆転が起こり、日産の時代もすでに終わっていました。
次のモデルからは山間部のタクシーもトヨタになり、遂に1995年以降は100万kmの耐久性を持つトヨタコンフォートの概ね1人舞台となりました。最近まで知らなかったのですが、そのコンフォートのベース車はクラウンではなく、X80系マークⅡであり、更に長さ100㎜違いの小型車用と長い中型車用の2種がありました。


更に2018年からはLPGハイブリッドのトヨタJPNタクシーに変わりました。
ロンドンタクシーに似ていますが、かなり小ぶりでJPNは4.40x1.695、ロンドンは4.86x1.87と大差があります。国内でタクシーを作る会社はすでになく、トヨタJPNの1人舞台、例外的にニューヨークでニッサンNV200型が走っていますが、耐久性と燃費でトヨタJPNがタクシーの世界でも完全制覇をする日も近いかも知れません。
思えば1935年、トヨタの第1号車G1型トラックは刈谷の工場で完成し、名古屋のお披露目会場まで20数kmを自走しましたが、故障の続出で到着まで3日を要しましたが、35年後の1970年、遂に使える車となりました。
あれ程ダメだったカローラも1974年には世界1の生産台数となりました。更に1990年、トヨタは世界トップ品質を達成し、2009年、GMの失速もあって遂に販売台数世界1を達成しました。
故障の塊りだったトヨタ車が世界中で1番故障の少ない車になったのです。この様にトヨタの執念は本物でした。世界中から使えないと言われたプリウスシステムも、世界中から認められた使える車になりました。レースやラリーの世界でも永らく勝てなかったトヨタが連勝、この世界でも高品質&高耐久性を実証しました。こちらでもトヨタの執念を感じます。
ダメトヨタでもやれたのですから、やる気があればそして諦めなければ三菱や日産にも出来ない筈はありません。内燃機関の新車を売る事が出来るのは2030~2040年まで、それからは電気自動車の時代であり、自動運転の時代となり、車の構造もプレス鉄板のスポット溶接と言う構造ではなくなります。きっとこれからはピンチもチャンスも従来より遥かにたくさんある事と思われます。
電気自動車の燃費:日産リーフの資料によれば、7.4km/kwhの走行とあり、それで行けば15円/kwhの 深夜電力ならば2.0円/kmとなります。150円/㍑のガソリンで20㎞/㍑では7.5円/km、15㎞/㍑ならば10円/kmとなりますから、かなり安い事になります。ソーラーで充電すれば上手く行けば出費はゼロです。
欠点は高額な充電設備代等が必要ですが、補助金が有ったり、他に安い充電方法も在りますからそれ程の心配は無用です。また2000円/月で日産デーラーの充電設備が使え、必ずしも充電設備は不要です。
リーフはすでに世界では30万台ほど売れている車で、日本人の思っているより遥かに良い車です。
そして何よりもリーフは摩耗する部分が構造的にタイヤ以外に殆んど無く、古い車でも心配はありません。初期型の8年落ちのリーフは2000年現在、30~50万円で購入出来、非常にお得です。
ケンさん家では家全体の電力をリーフのバッテリーで動かしています。前のボロ家ではエアコンを目一杯節約して2.5万円/月であったのが、今はケチらなくても深夜電力とリーフのお陰で1.5万円/月になりました。
100㎞/㍑ :現在の車は10~20km/リットル、全ての車がプリウスシステムなら20km/㍑になるかも知れま せんが、今の延長ではここまでです。ケンさんの直感的フィーリングではなるベく自然エネルギーにして、車は100km/㍑を達成すれば、そして建物のエアコン等も同程度に高断熱&高効率化すれば、石油消費は1/100~1/1000まで低下し、取敢えずの環境諸問題は50~100年位なら先送り出来そうに思えます。
且つて本田のスーパーカブは1983年型で180km/㍑の定地燃費性能があり、少し上手くやれば本当に100km走れた時がありました。又1865年型のトヨタスポーツ800と言う小さなスポーツカーの実用燃費は35km/㍑でした。

やリスのハイブリッドでは40㎞/㍑も達成も手が届きそうな雰囲気です。
これからすれば100㎞/㍑はもうすでに時間の問題とすら思えます。
またエコレースでは3000km以上/㍑をすでに達成しており、ソーラーパワーのみで走るレースも行われています。これらを組合せたの総合技術でソーラータンデムカー+予備エンジンで1000km/㍑も夢ではなくなると思います。
今後は自然エネルギーが主役になりますが、自然エネルギーは気象任せの甚だ気紛れです。
例えば太陽光発電のコストは2020年で最早深夜電力料金を下廻っておりますが、昼間で太陽が出ていなければ発電しません。
従って石油系の発電を予備にして、大規模な蓄電システムと送電やりくりシステムの開発によって、自然エネルギーで車を充電して走らせ、家や工場の電力を賄うのが1番良さそうです。
そんな日が早く来るとイイですね。

1リットル50円で5~8㎞しか走らなかったのです。それ以前はバイクで25㎞/㍑でした。このバイク時代でも燃料代は最大の悩みの種でした。当時のガソリンは50円で10㎞強/㍑でした。と言う事はツーリングを 半分以下にしなければならないと言う事になります。
ベレット ディーゼル:それで色々調べました所、ディーゼル車なら燃費も良くガソリン車の1.5倍、更に燃料単価はガソリンの半分以下、走りは期待出来ませんが、これならツーリング回数は減らさなくても済みます。

それで購入したのはいすゞの1964年型ベレットPRD10型を1969年に購入しました。
取説によれば1800㏄、50hp、110㎞/hとありましたが、最大巡航は80㎞/h程度、これを超えるとオイル消費が著しく増しました。実用燃費は15㎞/㍑、ガソリン換算30㎞/㍑と十分目的を達成出来ました。
平坦路の実用加速はそれ程悪くないのですが、MT3速車はちょっとした登りでも2速にダウン、45㎞/hしか出せません。登坂45㎞と巡航80㎞/hはかなり不満でした。不可能に挑戦はこの時SWが入ったと思います。
しかし実行に移す前にベレットは友人に貸したら居眠り運転で崖下にダイビング、運よく立ち木に掛かり人間は小破でしたが車は大破、使用不能になってしまいました。
その後まもなくいすゞはディーゼル乗用車から撤退、ベレットの改造は未着工のままで終わりました。
ベレットは12V車ですが、始動系と充電系は24Vでした。24Vスターターの始動性は良かったのですが、直列バッテリーの中間から12Vを取り出すだけなので、片方のバッテリーだけがすぐに上がってしまう曲者でした。
この点ランクルの昔は全て24V、1988年以降はスターターだけ24V、常用はバッテリー2個並列運転した12V、始動時は直列に切り替え24Vで始動しますから、後述スキー場の下り坂始動をせずに済む様になりました。
セドリックディーゼル:その後しばらくはディーゼル車が途絶え、カローラ1100とブルーバード1600のガソリン車に乗っていました。まもなく臨市の自動車学校がセドリックディーゼルを使用し、4年毎に払い下げると言う情報を仕入れました。早速申し込みに行きました。検定車は走行3万km程度で10万円、教習車は10万km程度で 3万円との事でした。弟も欲しいと言う事で検定車2台と部品取用に教習者1台を申し込みました。

セドリックディーゼルは払下げより、2年程早い1973年、12万円で売りに出ているのを見付けそれを購入しました。出所は同じ自動車学校、Q-130後期型でした。そして1976年には待望の直接払下げ車のQ-230型右写真を入手しました。2つは性能的には大差なく、2000㏄の55馬力、常用性能もそれに対する不満もベレットと同様でしたが、ディーゼルエンジンに強い、いすゞと違って冬季の始動性にかなり問題がありました。
始動性の改善:セドリックディーゼルの構成はタクシーや自動車学校用のガソリン4気筒2000㏄のエンジンをそのままディーゼルエンジンに置き換えただけと言う構成で,電装関係もギヤ比も信じられない事にそのままでした。冬季には当然の様に始動困難でした。始動性の問題点は12V運用が最大のネックでした。
パワーハーネスの容量不足に加え、配線の取り廻し不良、そしてアース不良でした。
ケンさんは電気式のフォークリフトの設計をしておりましたので1目で分かりました。
対策は電線を2倍に太くし、最短距離に変更し、アースも同クラスの電線で直接取りました。結果、外気0℃で 従来2~3分を要していた始動時間は20~30秒で済む様になりました.
直ちに弟の車や友人達の車にも同様の対策が施され、全車の始動性が著しく向上したのは言うまでもありませんが、メーカー新車のパワーハーネスやアースが改善されたのは驚いた事にケンさんの成功から7年後となりました。つまり日産には誰も真面目にこの始動性対策に向き合った技術者がいなかったのですから恐れ入ります。
セドリックディーゼルは外気マイナス15度以下になるとエンジンその物が始動不能でした。
対策は相当な高回転を与えるしかありませんが、エンジンその物の始動性に問題がありましたので、モーターの強化程度では追い付きません。
スキーでは近くの山道の下り途中に駐車、翌朝はグローを十分予熱後に スターターを廻しながら下り坂を走り続けました。1分程下り坂クランキングアシストを続けると初爆があり回転が上がり始め、更に10~20秒で連爆となり、間もなく始動すると言う状況でした。毎朝これが日課でした。
ギヤ比の再設定:セドリックディーゼルはガソリエンジンをそのままディーゼルエンジンに置き換えただけ、エンジンの許容回転数が2/3であるにも拘らず、ギヤ比はそのままでした。
3速MTで最大巡航速度は90㎞弱/h、登坂車線は2速で45㎞/hと大きな不満がありましたが、車両設計者でもあるケンさんは巡航速度&登坂速度の問題もギヤ比の変更でかなり大幅に改善出来ると読みました。
当時日産にはセドリックに使えるデフのギヤ比は3.9と4.3と4.6の3種がありました。同様にトランスミッションは タクシーや自動車学校用の3速、ライトバン用の4速、高級車用のOD付3速がありました。標準仕様では3速MTと4.3のデフでした。
3種類のMTと3種類のギヤ比のデフの全てを解体屋で調達し、全ての組合せで試験走行してみる事にしました。期待出来そうなのは4速MTと小さ目ギヤ比のデフ組合せ時、又はOD付3速MTに大き目ギヤ比のデフを組合せた時の2種です。
2か月後、結果が出ました。後者のOD付3速MTにギヤ比の4.6のデフを組合せが最良でした。
巡航速度はOD比0.7のお陰で従来90㎞/hから120㎞強/hにまで向上、加速も巡航燃費も10%程向上しました。
最大の効果は登坂車線問題でした。デフのギヤ比10%違いが駆動力向上となり、ベタ踏みで登坂車線を3速でかろうじて粘る事が可能になり、少し助走しておけば登坂車線の終りまで90㎞/hを維持出来ました。一旦速度を落とすと回復は不能ですが、ツーリングのストレスが大幅に少なくなった事は言うまでもありません。
ところがこの組合せが商品化されたのは始動性の改善と同じ7年目、繰り返しますが日産にはギヤ比も始動性も真面目に考える技術者が誰もいなかったのです。これが技術の日産だそうですから笑ってしまいます。
技術が無いのかやる気が無いのかは分かりませんが、ダメな会社でした。
そう言った良くない伝統が根本的に対策されないので、日産はやがて存続のピンチになり、ルノーからゴーン氏を迎えましたが、それも上手く行かず、今また存続のピンチに陥っています。
ランクル80のギヤ比:ランクル80型は良く出来た車両であり、このモデルから画期的に良くなった項目がたくさんありました。まずサスがコイルスプリングになり、乗り心地と走破性が圧倒的に向上しました。
更にストロークエンドのラバークッションシステムが大幅に改善され、適正なショックアブソーバとの組合せにより、他に類を見ない程の大衝撃吸収性が改善されました。また錆び対策や塗装も大幅に進化しました。更にディーゼルエンジンが高性能となり、これらの結果から世界ダントツの位置に駆け上がりました。
しかしこの時点でトヨタも国内では出来なかった事があります。それは排ガス絡みで低速時の燃料噴射量を増す事が出来なかった事と、同じく排ガス絡みでベストギヤ比に設定出来なかった事です。
結果としてHD型4200㏄エンジンで165hpのランクル80がプラド78のKZ型の3000㏄の130hpにスペック上は全く負けていないのですが、実走行では格下のプラドに大きく負けてしまいました。


プラドのKZエンジンは稀に見る傑作エンジンと言われていましたが、ライバル他車対決でパジェロは4M40 エンジンを2個積まなければ勝てない、テラノはTD27を3個積まなければ勝てないと言われていました。
そこでケンさんはランクル80に車検に受かるレベルの改造を施しました。低速時の燃料噴射量を増し、デフのギヤ比を5%大きい輸出用に変更したのです。この改造で格下プラドに負ける事も無くなり、トレーラー牽引もストレスなく出来、加速も燃費もかなり改善しました。ケンさんのハンティングカーの赤いランクル76型も燃料噴射量のチューニングとギヤ比の変更を行っています。
ランクルのノーマルHDエンジンを余り良くない様に書きましたが、マイクロバスのコースターでは排ガス規制が甘くなりランクル80より10~20%パワフルでした。またコースターは日産のシビリアンや三菱のローザに圧倒的な動力性能で勝っていました。またこのHDエンジンをマリン用にした場合、2倍近い350HPとパワフルです。
またランクルは同排気量のサファリのTD42エンジンには超圧勝でした。そんなダメなサファリは2007年に製造中止されてしまい、マイクロバスのシビリアンはガソリン車だけとなりました。非常に情けない日産です。
その次に運用した白のランクル100型には最初からこれらの対策が行われ、初めて無改造のまま気持ちよく運用出来ました。乗り心地もショックアブソーバの制御がコンピューター式となり、走破性共々更に大幅に改善されました。
トラクションコントロール(TRC)にしましてもランクル200型になりますと僅かにスリップを始めた時点で効き始め、他社の大きくスリップしてから慌ててブレーキを掛けているTRCとは出来が違います。
トヨタの評価が世界中でまた大きく上がったのは言うまでもありません。
さて問題点の多かったセドリックディーゼルですが、唯一好評と言われた車体の耐久性も左程ではなく、走行が20万kmとなった4年目には部品取り用の教習車の部品は概ね消費し尽くされてしまいました。
結果から言えば、もうその頃には耐久性に大幅劣ると思われていたトヨタに逆転を許してしまっていたのです。しかしセドリックで日本数周のツーリングに楽しく行けたのは事実、出来が良くない日産のSD20ディーゼルエンジンのお陰でした。その頃には車体の出来は良くなったトヨタですが、ディーゼルエンジンはまだ悲惨でした。
ディーゼル車の発展:古いイメージのディーゼル車は、燃費は良いが加速は悪く、巡航速度は不十分、上り坂では悲惨、そして排気ガスは汚く、車全体も臭く、エンジンは脂の滲みが多く真っ黒でした。
1985年頃まではその良くない伝説の通りでしたが、その頃でも低速トルクの粘りには群を抜く物がありました。同年ランクル60はターボ付12H‐Tになり、巡航速度の不足と上り坂問題だけは一気に解決しました。
1989年ランクル80がデビュー、新エンジンはHD-Tになり、燃費はやや低下しましたが、圧倒的なビッグトルクとなり、ガソリンエンジンを大きく凌駕しました。
ガソリンエンジンに負けない動力性能は長い間の夢でしたが、ここに達成されたのです。
良いエンジンに恵まれランクルは優れた走破性や車体強度の下地もあり、一気に世界のベストセラーに上り詰めました。この時代の排気ガスはまだ綺麗とは言えませんが、エンジンはオイルの滲みがなくなり綺麗なままになりました。
1993年、名エンジンと言われたKZがデビュー、ランクルプラドやハイエースに搭載されました。
カタログパワーは驚く程ではないのですが、実用的な走りは圧巻の一言、最早ガソリン車との比較の時代は終り、幾つかのシリーズでは低性能のガソリンエンジンがバリエーションから消え去りました。
ディーゼルはその後も徐々にクリーン化が進み、2017年にはクリーンディーゼルがデビュー、最早全ての欠点は過去の伝説となり、それを知らないのは地球上で日本人とアメリカ人だけとなりました。
ルマン24Hで勝つ為には:1923~2005年までの長い間はずっとガソリンエンジンの時代、それが当たり前でした。流れが変わり、アウディのターボディーゼルが2006~2014年の上位を独占しました。以後は勝つ為に絶対に必要なのは燃費と耐久性面からディーゼルエンジンとなりました。
しかし更に時代は変わり、今はハイブリッドでなければ勝てない時代となり、2015~2017年はベンツのガソリンハイブリッド車が上位を独占し、2018~2020年はトヨタが上位独占3連勝しています。我がトヨタも勿論ハイブリッドです。
プリウス:故障の1番多かったトヨタが今では1番故障の少ないメーカーになり、プリウスシステムもケンさんを含む世界中から使えないと言われていましたが、トヨタの看板商品に育ちました。この2つにはトヨタの執念を感じます。ディーゼル乗用車の実燃費が20㎞弱/㍑に留まっておりますが、ここでもレースの世界同様にすでに逆転が起こりプリウスは25㎞/㍑となりました。
しかし重いボデーの場合はまだディーゼル車の圧勝、ランクルやトラックに使えるヘビー級プリウスシステムの出現を期待する所です。
1997年に初代プリウスはデビューし、10・15モードで28㎞/㍑でした。
高速道路や郊外が多ければプリウスシステムは有効に働かず、28㎞/㍑はどんなに超ケチケチ運転をしても達成出来る数値ではなく、絵に描いた餅であり、世界中が使い物にならない車だと思っていました。
2002年にデビューした2代目は10・15モードで35㎞/㍑とかなり向上しました。走行フィーリングもかなり向上し、良く売れました。2代目は空走を多用した運転をすればかなり高燃費が出せました。
個人的な燃費チャレンジをする人が多く、車の流れを乱す車が多かったのが印象に残っています。
2009年には3代目がデビュー、エンジンもモーターも強化され、最早省エネ運転に挑戦しなくても20㎞/㍑をクリア出来る様になり、実用性に不足のない車となり、爆発的に売れまくりました。
エンジンは膨張行程の方が圧縮行程よりかなり長いアトキンソンサイクルの高効率の新エンジンとなり、抜群の燃費と走行フィーリングが可能となりました。
2015年には4代目がデビュー、3代目と類似スペックながら、リチウム電池採用でバッテリーの耐久性問題から決別、走行フィーリングも一段と向上、今やスポーツドライブを楽しめる車となり、それでいながら燃費も向上、JC8モードで40㎞弱/㍑と言う素晴らしい燃費を達成、普通に乗っても25㎞/㍑は難しくなくなりました。
プリウス単体は今やベストセラー車ではなくなりましたが、その理由はトヨタの新車の60%超がプリウスシステムを載せているからです。しかし今の日本の運用状況である10年又は10万kmと、現在の燃料単価では省燃費メリットは得られません。現状では40万円高額な車を売ったメーカーとそのシステムの部品メーカーが儲かっただけ、全体的から見ればCO₂が多少減少し、ガソリンスタンドの経営を多少圧迫したに過ぎません。
車は何年まで使えるのか?:日本では今だに10年又は10万kmが近くなっただけで、そろそろ交換されてはと言われます。それは車を売る方の都合であって、車の寿命はまだ70%残っております。10年で手放した車はどうなるのか? 何処かの国に輸出され少なくもそこで更に30年間の運用をされます。
日本車の寿命はそれだけあると言えばそうなりますが、大きな修理なしに乗れる期間は概ね現在の思いの2倍以上、少なくともトヨタ車なら概ね20年又は30万kmだと思います。
オーストラリアで20万km未満の中古車には走行距離が少ないと言う表現が付けられます。日本的に言ったら、完全に末期状態にある事になりますが、そうではなく、軽く50万km走れるのでそう言う表現になるのです。
国内のタクシー用の中古車市場に於いても、50万km以上走った車にも相応の価格が付いており、それはまだ今後もそれなりに多少は使える事を意味しています。因みにトヨタコンフォートの寿命は100万km以上です。
ケンさんランクル100型は新車時500万円でしたが、22年間で15.5万kmまで殆ど無整備で乗り切れました。2020年、叩き売っても200万円以上、買えば300万円の価値があります。つまりまだ半分程度は十分使える 価値がある事を示します。
ただ同じ日本製であっても日産や三菱の場合はトヨタの数倍のトラブルがあります。
ワーゲンやボルボを自慢している友人もいますが、トヨタ車の優秀さを知らない人が多く、気の毒に思います。
車検整備:そう言う法定用語はありませんが、12カ月または24カ月点検は法律で受ける事を決められて おり、それに対して定期交換部品と言う物は自動車の場合はありません。
勿論10年を超えたから点検項目が増え、交換部品が増える事もありません。
車検自体はメカは分からなくても良いので、自分の車に関心を持ち、責任を持って、自分で法定点検を行い、受検するのが本筋です。やりたくない人や手を汚したくない人は、資格を持った業者に、代行をお願い出来るのが現在の法制度です。
点検は分からないながら車の下に潜って自分で各部を見て触って見ます。漏れも緩みもなく、ちゃんと走ればまず問題はありません。点検記録用紙は愛車手帳にあり、試験ではありませんから、この名称は多分これ、良いと思えばチェックマーク、未記入の部分を無くします。未記入の部分があると、点検をしていないと解釈され法定違反となります。これで法定点検は終りです。悪くなければ整備をする必要はありません。
法定点検の次は検査を受けなければなりませんが、これが車検です。近くの公的車検場に予約して持ち込めば、2000円程度で検査をしてくれます。車のナンバープレートと違う車検場でもOKです。
もし不合格ならば、車検場の検査用紙には不具合内容が掛かれており、それを持ってデーラーに駆け込みます。トヨタ車なら午前中に駆け込めば、3時頃に部品が到着し、付けてもらったらそれで車検場で再検査、無料です。その日に間に合わない時は日を改めますが、予約は不要、検査代2000円が再度必要です。
オイル等の定期交換サイクルはマニュアルにありますが、従来思っているより遥かにロングインターバルです。ガソリンスタンドや車の用品店の交換サイクルやオイルのグレード等の奨めに従う必要は全くありません。
指定グレードのオイルはドラム缶で買うと150円/㍑とガソリンと同程度の価格ですが、これで十分なのです。マニュアルはそれで絶対に大丈夫と言う指定サイクルですからそれで数十万kmの耐久性があります。2倍サボッても多分壊れません。それより大幅に手やお金を掛けても勿体ないだけです。
減るのはタイヤ、そしてブレーキパッドだけです。タイヤを交換する時にパッドも見てもらいましょう。
目視で簡単に見えます。半分以上あれば次回タイヤ交換時でOKです。
10万kmになったらベルトやホース類のゴム部品を換えると良いと思いますが、近年は泡良くば20年又は20万kmの寿命がある様です。これで新車は今まで思っていたよりも2倍は使えますし、車関係の無駄な出費は激減となりました。
トヨタの車は何時から使える車になったのか?:1960年代までのトヨタはよく壊れました。1963年に名神高速道路が開通しますと高速道路には故障車が溢れました。
当時のシェアはトヨタも日産も概ね30%ずつでしたが、故障車全体の60%がトヨタ車、それ位トヨタの車は良く壊れました。
しかし1970年型のパブリカ1000は壊れませんでした。多分この頃が境目だと思います。
ケンさんの最初の愛車はいすゞのべレットディーゼル、次はディーゼルが無くなり、やむなく初代1968年型のカローラ1100、ところが僅か1万kmでショックアブソーバもステアリングもガタガタ、トヨタはダメな車でした。それで次はブルーバード1600、5万kmくらいしか使いませんでしたが、リヤのケツ下がり以外は良い車でした。


当時はトヨタに務めていたのにどうしてケンさんの愛車は非トヨタ車だったのか?
トヨタはすぐに壊れるので使う気が起こらなかったのです。1980年に購入したランクル60もトヨタエンジンなら買わなかった、1966~1970年の初代カローラ対サニーの戦いは販売上カローラの圧勝でしたが、技術内容的にはサニーの圧勝、初代カローラはすぐ壊れる、これが当時のトヨタ車でした。
さてセドリックディーゼルで全国をツーリングしていた時代の中盤、1977年にケンさんは結婚、ワイフの練習用の車を購入しました。1970年型のパブリカ1000で7年落ちでした。
車検が1年残っていたので、運転練習に1年間使えればと思い、解体屋で3万円の車でした。

そして1年後まだ好調なのでユーザー車検を受けました。2年後も好調なので再度ユーザー車検を受けました。こうして5年間約5万kmをノントラブルの無故障で走り切りました。
交換したのはバッテリー3000円、中古マフラー1000円、中古タイヤ4000円、これが全てでした。
結論として1970年型パブリカはエンジンオイルすら交換なしに5万kmを快調に走り切りました。予定では数年を持たずして壊れると思っていたのですが、見事に裏切られました。この時にトヨタ車が頻繁に壊れる時代は終わたのを感じました。カローラも2代目からは壊れない車になり、世界で1番売れた車種となりました。
1970年代までのタクシーは耐久性が理由で、市街地はトヨタ、山間部はニッサンでしたが、本当はもう逆転が起こり、日産の時代もすでに終わっていました。
次のモデルからは山間部のタクシーもトヨタになり、遂に1995年以降は100万kmの耐久性を持つトヨタコンフォートの概ね1人舞台となりました。最近まで知らなかったのですが、そのコンフォートのベース車はクラウンではなく、X80系マークⅡであり、更に長さ100㎜違いの小型車用と長い中型車用の2種がありました。


更に2018年からはLPGハイブリッドのトヨタJPNタクシーに変わりました。
ロンドンタクシーに似ていますが、かなり小ぶりでJPNは4.40x1.695、ロンドンは4.86x1.87と大差があります。国内でタクシーを作る会社はすでになく、トヨタJPNの1人舞台、例外的にニューヨークでニッサンNV200型が走っていますが、耐久性と燃費でトヨタJPNがタクシーの世界でも完全制覇をする日も近いかも知れません。
思えば1935年、トヨタの第1号車G1型トラックは刈谷の工場で完成し、名古屋のお披露目会場まで20数kmを自走しましたが、故障の続出で到着まで3日を要しましたが、35年後の1970年、遂に使える車となりました。
あれ程ダメだったカローラも1974年には世界1の生産台数となりました。更に1990年、トヨタは世界トップ品質を達成し、2009年、GMの失速もあって遂に販売台数世界1を達成しました。
故障の塊りだったトヨタ車が世界中で1番故障の少ない車になったのです。この様にトヨタの執念は本物でした。世界中から使えないと言われたプリウスシステムも、世界中から認められた使える車になりました。レースやラリーの世界でも永らく勝てなかったトヨタが連勝、この世界でも高品質&高耐久性を実証しました。こちらでもトヨタの執念を感じます。
ダメトヨタでもやれたのですから、やる気があればそして諦めなければ三菱や日産にも出来ない筈はありません。内燃機関の新車を売る事が出来るのは2030~2040年まで、それからは電気自動車の時代であり、自動運転の時代となり、車の構造もプレス鉄板のスポット溶接と言う構造ではなくなります。きっとこれからはピンチもチャンスも従来より遥かにたくさんある事と思われます。
電気自動車の燃費:日産リーフの資料によれば、7.4km/kwhの走行とあり、それで行けば15円/kwhの 深夜電力ならば2.0円/kmとなります。150円/㍑のガソリンで20㎞/㍑では7.5円/km、15㎞/㍑ならば10円/kmとなりますから、かなり安い事になります。ソーラーで充電すれば上手く行けば出費はゼロです。
欠点は高額な充電設備代等が必要ですが、補助金が有ったり、他に安い充電方法も在りますからそれ程の心配は無用です。また2000円/月で日産デーラーの充電設備が使え、必ずしも充電設備は不要です。
リーフはすでに世界では30万台ほど売れている車で、日本人の思っているより遥かに良い車です。
そして何よりもリーフは摩耗する部分が構造的にタイヤ以外に殆んど無く、古い車でも心配はありません。初期型の8年落ちのリーフは2000年現在、30~50万円で購入出来、非常にお得です。
ケンさん家では家全体の電力をリーフのバッテリーで動かしています。前のボロ家ではエアコンを目一杯節約して2.5万円/月であったのが、今はケチらなくても深夜電力とリーフのお陰で1.5万円/月になりました。
100㎞/㍑ :現在の車は10~20km/リットル、全ての車がプリウスシステムなら20km/㍑になるかも知れま せんが、今の延長ではここまでです。ケンさんの直感的フィーリングではなるベく自然エネルギーにして、車は100km/㍑を達成すれば、そして建物のエアコン等も同程度に高断熱&高効率化すれば、石油消費は1/100~1/1000まで低下し、取敢えずの環境諸問題は50~100年位なら先送り出来そうに思えます。
且つて本田のスーパーカブは1983年型で180km/㍑の定地燃費性能があり、少し上手くやれば本当に100km走れた時がありました。又1865年型のトヨタスポーツ800と言う小さなスポーツカーの実用燃費は35km/㍑でした。

やリスのハイブリッドでは40㎞/㍑も達成も手が届きそうな雰囲気です。
これからすれば100㎞/㍑はもうすでに時間の問題とすら思えます。
またエコレースでは3000km以上/㍑をすでに達成しており、ソーラーパワーのみで走るレースも行われています。これらを組合せたの総合技術でソーラータンデムカー+予備エンジンで1000km/㍑も夢ではなくなると思います。
今後は自然エネルギーが主役になりますが、自然エネルギーは気象任せの甚だ気紛れです。
例えば太陽光発電のコストは2020年で最早深夜電力料金を下廻っておりますが、昼間で太陽が出ていなければ発電しません。
従って石油系の発電を予備にして、大規模な蓄電システムと送電やりくりシステムの開発によって、自然エネルギーで車を充電して走らせ、家や工場の電力を賄うのが1番良さそうです。
そんな日が早く来るとイイですね。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その6:トヨタプリウス&ディーゼルの発展
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その5:ジムニー最新型
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その4:ジムニーライバル登場そして自滅。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その3:唯一の改良コイルサス。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。
嘘もイイ加減にしなさい。その12:ランクルの強度と耐久性。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その5:ジムニー最新型
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その4:ジムニーライバル登場そして自滅。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。その3:唯一の改良コイルサス。
スズキ ジムニーと世界に誇れる工業製品。
嘘もイイ加減にしなさい。その12:ランクルの強度と耐久性。
Posted by little-ken
at 10:14
│ハンティングカー