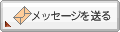2020年10月16日
ハンターのバイブル、その2 : ライフルハンター。
3.ライフル-ハンター。

1992年、第三書館より出版、本書は1952~1991年までの39年間の氏の狩猟ドギュメント?です。本州共猟の勉強時代、エゾ鹿&ヒグマの単独猟 時代?、アフリカのライオンや象、USAのピューマ、カナダ北部の北極熊等々との勝負?がリアルに描かれています。
海外猟には要大金ですが、彼はスポンサーからではなく、自前費用で遠征、後刻に撮影フィルム等をマスコミに売ると言う手法で調達しました。柳田氏のビジネスの1つとして海外映画等の配信業務があった様です。
柳田氏は1932年生まれ。熊類62頭、エゾ鹿92頭、猪&本州鹿等69頭となっていますが、本文記載内容や更に後述の理由から信憑性はかなり低そうです。表紙の動物は体重僅か55kgの貧弱なピューマ、どうしてこれが選ばれたのか、一方で構えている銃は象撃ち用の水平2連ダブルライフル、そのつもりで見ますとこの辺からもケチが付きそうです。
4.柳田佳久氏の射撃。
4-1.スナップショット。

柳田氏の最初の銃は20歳を待って入手したレミントン740、初期の自動銃のオープンサイト、口径は30-06です。ケンさんも同系の742を愛用しましたが、狩猟用の空気銃で立ち撃ち168点/200点満点、30mの雀の頭と外さなかったその腕を以ってしても、使えるのは精々100mであり、当たらないと言える銃でした。

柳田氏が長らく愛用したのはウェザビーの30-06、アイアンサイトを残した物です。スコープ専用銃が普及する前ですから矢無を得ない部分はありますが、チークピースの合わないスコープ銃ではスナップショットは不可能であると言えます。またケンさんの友人が本銃を使っていましたが、余り出来の良い銃ではないと思いました。
スナップショットやランニングショットをバンバン決めた事になっていますが、これもそう有れたらと言う願望、又はそう言う名人がかつていたのを聞いた事があるのレベルだと思います。本文中にも対ヒグマ戦で発砲直前の銃を叩かれた、ポーラーベア戦では銃を構えても照準が定まらなかったとありますが、ケンさん式のスナップショットでは照準時間はゼロですから、照準が定まらない事も銃を叩かれると言う事もあり得ません。つまり氏はスナップショットが全く出来なかったのです。
柳田氏の射撃を見た事があります。銃を30度位上に向けて肩にツンツンと5~10回ほど行い、やっと肩の位置が決まると頬を強く乗せながら、「ガバッ」と銃を目標に向け、それからスコープで目標を探します。だから照準に長い時間が必要です。アイアンサイトを残した銃ではスナップショットは不可能である事はすでに申しました通りですが、柳田氏の射法ではスナップショット処の話ではなく、一般的な射法の中でも遅い方になります。
4-2.ランニングショット。
ライフル銃1年生の氏の銃はレミントン740のオート,本文記載にある様な200mの走るツキノワグマを撃った事になっていますが、静止の200m射撃にも本銃では無理がありますが、ランニング射撃は出来る筈が無いと思います。ケンさんも愛用しましたが、オープンサイトは実に使い難い銃でした。
ランニング射撃技術はチークピースを調整したスコープ専用銃のH&Kオートと、ガイド猟実戦90日と2000~3000発の試行錯誤の実戦 射撃から得られました。見ていると簡単そうですが、そう簡単には得られる筈が無い技術なのです。
その後のウェザビーボルトでは本文中に、森の中を走るエゾ鹿の200mのランニングで、本来補正不要である筈の落差に付いては触れていますが、最も重要なリードに付きましては単にポストに載せて撃つとありました。
実際に150mゼロインならば200mは落差補正不要です。リードは真横に走る鹿とするなら約2.5m、熊ならもう少し小さくなりますが、リードは動的射撃には絶対に避けて通れない項目となり、ポストに載せて撃ったら絶対に命中しません。つまりランニング射撃は全く理解していない事を自ら証明しているのです。
4-3.迫力負け&恐怖負け。
スナップショット等の問題もありますが、もっとも重要な「迫力負け&恐怖負け対策」はどうしたのでしょう。本州鹿猟では獲物が小さいので起らないのですが、射手より明らかに対戦相手の方がデカいエゾ鹿猟では起ります。
対戦前からすでにその大きさに負けてしまい、足が地に着かない射撃となるのが「迫力負け」です。実例では大藪氏のコーナーでも紹介しましたが、それに陥る確率は残念ながら90%以上です。
約100名のスクールの生徒中、角長80cmのエゾ鹿の超大物を捕獲したのは僅か5名のみ、捕獲成功までの出猟日は平均21日、しかしこれでそのクラスの「迫力負け」を超えられたのではなく、捕獲は全てマグレでした。例外的な1名を除き、その後も「迫力負け」は続き、2頭目の捕獲に成功していない、これが「迫力負け」の対策の難度の高さを物語っています。
ケンさんはこれを乗り越えなければ、アフリカのビッグゲームでも足が地に 着かない射撃となり、本当の成功はあり得ないと思っています。
柳田氏はこれに対して、「迫力負け」も「恐怖負け」も全てが「根性」だと本書で結論付けています。根性であればケンさんも類い稀なハイレベルを持ち合わせているつもりでいましたが、「迫力負け」には何年も悩まされ続けました。
別例ですが、エゾ鹿捕獲数百頭、ヒグマ複数捕獲のベテランハンターと半矢ヒグマの捜索をしましたが、彼らを以ってしても「恐怖負け」状態で捜索は全く役に立たず、発見は全て護衛係のケンさんでした。
反動に身構えて照準がずれ、大幅に精度ダウンのフリンチング、獲物の体格に負けてしまう「迫力負け」、獲物の恐怖に負けてしまう「恐怖負け」等々は、猛獣ハンターの超えなければならない大きなハードルとなりますが、これら3件は共に絶望的に近い難度になります。
それではアフリカ猟の猛獣ハンターは全員がそれをクリアしているのか? そう様な事は全く無く、それを未クリアでもお金さえ出せば、支援射撃や代理射撃等により、安全に獲らせてもらえるシステムになっている、これがアフリカ猟なのです。
4-4.遠射。
ライフル銃が他の銃と比べて最も優れているのが射撃精度です。しかし氏がライフルを取得した1952年時点も現在も弾の弾速やパワーに付きましては特に変わりませんが、しかしその時点のオートでは100mが限界でした。
氏の次の愛銃ウェザビーの30-06なら年代もかなり新しくなり、200mの難度は無く、300mもそれ程の難度ではないと思います。しかしこれを実際に出せる腕前のハンターは100人に1人以下、ケンさんの教えたスクールの100人近い生徒でも300m遠射の成功例はゼロ、これが現実です。
柳田氏は銃の200mや300mの精度に付きましてはかなり詳しく書いておられ、それは概ね正しいと思いますが、仮に射撃場でそれが出せたとしても、これが実戦で出せるかどうかは別問題です。
スクールの生徒でもLB射撃選手がおり、300mで10cmを外さないと豪語していましたが、実戦ではマグレで2頭を捕獲したに過ぎませんでしたが、共に100mで1m前後の誤差がありました。
氏は本文中に銃をしっかり構えないと、撃った時の衝撃で弾が出る前に照準がずれると書いていますが、これも完全な間違い、銃は出来るだけ人間が関与せず、銃だけに撃たせる様にするのが本当の射撃術になります。
4-5.ビッグ5の捕獲。
アフリカ猟の代表格は象、犀、ケープバッファロー、ライオン、豹の5種類でビッグ5と呼ばれます。
氏は象、犀、ケープバッファロー、ライオンを倒し、豹に換えて類似のアメリカのピューマが加わっています。多くの勝負に対する記載はライオンとポーラベアーを除き、詳細に書いて無いのは残念です。
ケンさんもそうですが、多くの読者はビッグ5との死闘?の話を聞きたかったと思います。言い訳的な説明としてこれらのガイド付アフリカ猟は、お金さえ出せば誰にでも出来、本当の醍醐味は単独猟にあるとしています。
しかしライオンの記載は今までの推定技量からすると、信じ難い表記です。
ライオンの20mは決まらず、走って向かって来る状況下で更に2発、それも決まらず、最終的には8mで撃って6mで倒れたとあります。人間のダッシュで50mは7秒程度ですから、ライオンのダッシュで12mは2秒以下しかない筈です。
この状況下は2発目不可の1発勝負の世界です。アイアンサイトのスコープ銃が2秒で3発を撃てるとは絶対に思えません。ガイドの支援射撃3発が絶対に入っている筈です。
4-6.安全装置の取扱い等。
柳田氏は直前装填等や安全装置運用の記載は一切なく、一触即発の銃で猟をしていたと思われ、残念です。捕獲のみが狩猟ではなく、捕獲に拘らない狩猟を楽しみに来たと言う表現は、余りにも言い訳が強過ぎて好みませんが、安全は何よりも大切なのは言うまでもありません。
ボルトアクション銃の安全装置は使い難く、1度完全装填してボルトハンドルをハーフロックの位置まで上げて運用する方法を指示するプロガイドもいました。
国内でも多数見掛けたのは、完全装填後ボルトハンドルを上げた状態で引き金を引きながら、ボルトハンドルをロック位置まで戻すハンターです。これはボルトアクション銃の構造を知らないドシロート、左写真はボルトヘッドですが、撃針を落とした状態では撃針が飛び出たままなのです。ファーイーストの築地氏によれば銃によっては雷管が強く押され100%暴発するそうです。
自動銃の撃針は普段引っ込んでいてハンマーで叩かれた時だけ前進して雷管を付き、また引っ込んだ位置に戻りますが、ボルトアクションの撃針は出たまま固定なのです。築地氏の申す通り、その状態で雷管はかなり強く押され、それだけでも暴発する可能性がかなりあり、そこまで行かなくてもこの状態では完全に一触即発です。この様な運用をしない様にお願い致します。
一般的に安全装置解除や装填には各々それなりの時間が必要であり、目標をスコープに捉えて照準するにはもっと長い時間が必要と考えられています。しかしケンさんのスナップショットでは安全装置解除に要する時間はゼロ、装填する時間は甚だ僅か、スコープに捉え照準するには近距離の場合に限りですが、これも甚だ僅かの時間で済ませられます。正しいスナップショットと安全装置の操作を身に付ける事をお薦めします。
4-7.その他の問題記載。
30-08?:30-06は1906年制定、これに対抗する308は約50年後の1954年制定、30-06の改良版が308であり、パワーこそ5~10%減少しておりますが、命中精度は308の方が明らかに有利です。どちらが優れているかはここに及んで言うまでもありません。わざわざ100年前の旧型を選択する方がおかしいと思います。
308の欠点らしい物と言えば、30-06の様に200grの重量弾頭が使えない事位ですが、時代は軽量高速弾が有利とハッキリ方向性を示していますから、欠点とは言い難い項目になります。
柳田氏の初ライフルのレミントン740の取得は308デビュー以前ですから必然的に30-06になります。次のウェザビーボルト取得時は308があった筈ですから、308の選択が正しかったのですが、再び30-06を選択しました。
それ自体は前例が少なく矢無を得ない感はありますが、だからと言って308を30-08と記載するのは、少なくとも1992年の本誌の編集校正時には必ず修正されなくてはなりません。最もStd的なカートリッジである308を知らない様では銃を語るライターの資格は無いと思います。
当時、巷のドシロート達は30-06に対し308を30-08と呼んでいましたが、柳田氏もそのレベルだったのかも知れません。また1970年代よりエゾ鹿猟がブームになり、30-06か308の選択と、マグナムの必要性に付いてが話題になっていましたが、これに付いての記載は全くありません。口径選択はエゾ鹿猟を目指そうとする当時の多数の読者の最重要テーマであり、ライタ―として書かなければならなかったテーマだった筈です。
1952年のレミントン740で200m射撃とランニング射撃:本項でも触れていますが、この時代の30-06のオートは精度的にも200mの能力はなく、オープンサイトでは200mの鹿は静止でも小さ過ぎて照準出来ません。ましてライフル1年生が200m先のランニングを当てられる筈がありません。
レミントン740は100mが限界でしたが、同時期のオートでもスコープを使えばブローニングには150mの能力があり、45年後の1990年代後半のH&Kには250mの能力がありました。
写真の2重使用:同じヒグマの写真が説明文の体重200kgと300kgを変えて複数回使用されています。ケンさんは6頭しか捕獲しておりませんから偉そうな事は言えませんが、周囲の枝葉まで同じ状態で別ヒグマはあり得ません。読者を騙すのもイイ加減にしなさいと言えます。またヒグマの野性生態写真として紹介されているのは、黒1色で鼻ツラが白い事からアメリカクロクマの可能性がかなり高いと思います。
もちろん黒いヒグマはいます。ケンさんの捕獲した6頭中2頭がそれでした。また鼻ツラが白っぽいヒグマも居るかも知れませんが、ケンさんは各地の資料館の剥製や資料を含めて見た事がありません。
ヒットポイントの説明がない:倒したと言う表記の中にヒットポイントの説明がなく、またヒットした時のショック 症状に付いても記載がなく、この面からも怪しい気がします。
200m超えはソリッド弾?:ソリッド弾は無垢の弾です。鉛弾は骨や硬い皮膚にヒットすると鉛が四散し、至近距離の高速弾ではヒットすると表面爆発をして機能を失う欠点があります。ソリッド弾はそうならない様にした弾頭で、昨今のエゾ鹿猟ではお馴染みのバーンズ弾頭もそう言う対策を目的としたカッパーソリッド弾です。この当時のソリッド弾は現在のバーンズ弾の様に先が開かず、そのままの形で突き抜けます。
そのまま突き抜ける事で言えば軍用のFMJ弾があります。安い練習弾は多くがこれであり、ケンさんは初期の頃ですがある時に弾切れになり、このFMJでエゾ鹿を撃った事があります。その結果は良い所にヒットした時の即倒率は変わりませんが、着弾位置が少しずれると情けない程に逃げられてしまう事もありました。
そんな事から多少命中率が良いからと言って、どうして柳田氏が200mのエゾ鹿撃ちやヒグマ撃ちに未回収の出易いソリッド弾を使うのか、多分分かっていないだけと思いますが、その真意は全く分かりません。
2種類の弾を準備:弾と銃の相性は重要な問題です。それによる誤差は無視出来ない程の量になります。リロードで市販弾より高精度を目指す手法は当時まだある程度有効でしたが、しかし弾種が複数では各々に対しそれ様の照準をしなければなりません。
スクールにも近射用と遠射用の複数弾を用意し、何人もが理想を追求しようとしましたが、通常の人間はここ1番の時に冷静にそれに対応出来ず、遠近用の2種の弾の使い分やヒグマ用だけの重量弾頭が有効に機能した事は唯の1度もありません。
実戦時は異常心理状態にあり、頭は殆ど回転せず、どの様な能書きも注意書きも全て無効になってしまいます。遠射はライフルハンターの夢ですが、実戦ではその機会は非常に少なく、運用機会の多い100~150mを何時も直撃射撃で安心出来る、150mゼロインがベストです。100m前後では約2cm程上を飛び、200mでも落差は5cm以内、射撃ミスの原因のトップが落差補正の不安である事を考えますと、昨今のバーンズ銅弾頭1種で何時も直撃射撃のメリットは計り知れない程の物になります。
遠射をバッチリ決めたい想いから、300mゼロインにする人が多くいます。300mを直撃出来るメリットはあり、400m時の落差補正も大幅に少なく出来ますが、その運用機会は極めて稀であり、また元々300mは余り当てられるモノではありません。一方300mゼロインでは多用する100~150mで15cmマイナス側に補正しなければなりません。このマイナス補正を忘れて撃ち頃の距離のチャンスを棒に振るのを多数見て来ました。
パーティション:これに付きましても酷い間違いが書かれていました。鉛弾は骨等にヒットすると鉛が四散し、至近距離では高速弾の場合は表面爆発で機能を失う欠点がある事は先にも書いた通りです。通常のフィールドゲームではソリッド弾までの必要性はありません。
鉛が四散し易い様なシーンになっても、弾頭の後半が残る様にジャケット中央部を強化した物がパーティションであり、更にそれを完全独立にした物がAフレームです。柳田氏曰く、パーティションはヒットにより2つに千切れ、威力を増すとしておられますが、勿論大間違いです。
200kgのエゾ鹿?:エゾ鹿は繁殖期になりますとその方面が忙しく、絶食状態になりますのでかなり大きく 見える個体でも実測してみると130kg前後でした。ケンさんは特に大き目の個体を10回ほど実測してみましたが、通常の大物は150kgにかなり満たないのが普通です。西興部猟区では繁殖期前の10月に170kgの個体が捕獲されたそうですが、これが通常の最大であると思います。
超大物をメインターゲットとして大物が多い平野部で1050頭を捕獲したケンさんが150kg越えは1度も無いのに、山岳猟の小柄な92頭捕獲の柳田氏が200kgのエゾ鹿を捕獲出来る可能性は限りなく低いと思われます。
20mのライオンにあり得ない追加3発: ライオンは12mを2秒以下でダッシュします。
ケンさんのスナップスイング連射は自動銃より速いのですが、それでも3発は絶望的不可能、2発目が撃てるかどうかの瀬戸際です。この場合は客がヤバいと見てガイドとアシスタントが相次いで発砲したと思われます。柳田氏の射撃技術なら追加1発が出来るかどうかになり、出来たとしてもダメ元射撃に留まると思います。
元々デンジャラスゲームは1発勝負の世界であり、客がヤバいと見た時は、ガイドとアシスタントの2人が相前後して水平2連のダブルライフルで支援するシステムになっています。全てのデンジャラスゲームはそう言う、アシスト体制の下で安全に勝負するのがデンジャラスゲームの普通のやり方です。これを1人でやり遂げたと書くのは、心臓に強力な毛が生えているか、余程のドシロートライターかになります。
白糠の湯井ガイド:湯井さんは道東の白糠でエゾ鹿の巻狩り民宿を経営し、自らが勢子とガイドをしていました。ケンさんも1993年から3シーズンお世話になり、当時のエゾ鹿猟に於いて最初の目標とする人でした。その湯井さんが1992年頃、3日連続で林道を1人で歩いている男がいたので、話し掛けてみたそうです。
結果から言えば、それが柳田氏であったのですが、氏曰く「ここは鹿が多いと聞いて来たのですが、1週間が 過ぎても1度も鹿に会えない」と言う事でした。湯井氏は柳田氏に良かったらガイドしましょうか? と申し入れたそうです。鹿に出会えなかったらガイド料は不要ですと言う条件で、3日ガイド猟を行い、数頭を捕獲させたそうですが、湯井氏が言うには柳田氏はハンターとしては3流であり、単独で獲れる筈が無いと言う事でした。
柳田氏と湯井氏の出会いは著書「ライフルハンター」を1冊置いて行ったそうですから、ライフルハンター出版の1992年と思われます。柳田氏は道東白糠の狩猟小屋の取得が1989年、本当の単独猟はそこから始まった様ですが、ケンさんも1993年から湯井さんの所にお世話になりましたが、柳田氏には会えておらず、湯井氏も以後は1度も見掛けなかったそうです。
小屋の取得年度と湯井氏に出会ったのは多少ずれがありますが、言える事は道東白糠の単独猟の期間は非常に僅かだった様であり、且つ成果は上がらず早期撤退に終わった様です。
大物猟は只々歩き廻っても出会えず、出会えなければ勉強にならず、その為にはグループ猟またはガイド猟で勉強しなければなりません。ケンさんも13年間本州鹿の巻狩りで勉強し、10頭弱を獲らせて戴き、エゾ鹿猟でも3シーズンのガイド猟を行い、多数を獲らせて戴き、生態の勉強が出来ました。
柳田氏も39年中の10数年はグループ猟で教わったと書いており、その後はずっと単独猟と書いておられます。しかし末期の白糠の狩猟小屋でも成果を上げられず、早期に撤退した様ですから、書物全体に?が付きます。
柳田氏の想い:「ライフルハンター」の後書きで氏はこう語っています。
アフリカ猟やアラスカ猟はお金(サラリーマンの年収の比ではないかなりの高額)と暇(1~2カ月とかなり長期)と体力(並の上クラス以上)があれば、誰にでも出来、本当の狩猟の醍醐味は単独猟にあると述べていますが、本当はその単独猟が彼自身の本当の憧れだったのではないでしょうか。そんな気がします。
もう一方の誰でも出来るアフリカ猟にはケンさんも同感で、アフリカ猟が夢である人はとにかく行くべきです。お手軽1週間1式が100万円程度、且つイージー射撃コースもあり、行けば何とかなります。しかしビッグトロフィー勝負の難度は高く、ケンさんのクドゥ猟は通常の遠射の限界を超えた380mの遠射の速射を要しました。
ケンさんのアフリカ猟は予算の関係でデンジャラスゲームの対戦は無く、アンテロープ類のみで終わりました。氏の部屋には各種剥製がありますが、数種類のデンジャラスゲームを除けば、何れもケンさんのトロフィーとは比較にならない様な貧弱な物ばかりでした。ケンさんのデンジャラスゲームは北海道のヒグマ450kg、氏のポーラーベアとは概ね同サイズ、こちらは完全な単独猟であり、別のヒグマでは出会い頭の15m、幸いにも両者に対し、臆する事なく速やかに対処出来ました。
ノンフィクション?:湯井氏の話と上記各項と合わせますと「ライフルハンター」はノンフィクションではなさそうだと言うのが自信を 持った結論ですが、ケンさんのバイブルと言うか、憧れだった時代もある程の立派な小説であったと言えます。
著者本人が大活躍したドギュメンタリ―ではなく、架空の主人公が大活躍する、小説にすれば良かったのでは ないかと思われます。世の中の名人ハンターは稀にいてもそれを上手く表現する能力が無く、一方で表現能力を持ったハンターにはその狩猟力が大幅に不足するのが常ですが、ケンさんはその中間辺りかと思われます。
何はともあれ、エゾ鹿猟は本当に魅力ある狩猟でチャレンジする価値は十分にあり、男ならヒグマ猟も一生に1度は勝負したい物です。日本の狩猟環境は抜群ですが、ガイドレス単独猟は誰でも出来る訳ではありません。
昨今は腕の良いハンターは駆除で生計を立て、ガイドをしなくなりました。その結果ガイドは3流ばかりとなり、他所で3連続計9日間捕獲ゼロだった生徒や、同じく小物数頭のみの生徒が多数スクールに来ましたが、全員が下写真の様な持ち帰りが出来ました。獲らせる能力のない3流ガイドが多くなった事は嘆きです。




左写真:一生に1度は勝負したい超大物エゾ鹿ですが、これこそ体重記録更新かと
思われた超大物も実測は140kgでした。
右写真:スクール生徒の平均的持ち帰り状況です。スクールの後半の名称は5205、1日平均
5回の出会いがあり、平均2頭の捕獲があり、内0.5頭が大物、これが平均実績、別の
データでは出会いの70%が3段角の成獣オス、20%が大物、5%が超大物でした。
左下写真:フィーバーの日に会えれば、そして迫力負けしなければ、超大物を束にして帰れます。
右下写真:11月初旬の2週間を出撃すればヒグマ勝負も可能です。
1992年、第三書館より出版、本書は1952~1991年までの39年間の氏の狩猟ドギュメント?です。本州共猟の勉強時代、エゾ鹿&ヒグマの単独猟 時代?、アフリカのライオンや象、USAのピューマ、カナダ北部の北極熊等々との勝負?がリアルに描かれています。
海外猟には要大金ですが、彼はスポンサーからではなく、自前費用で遠征、後刻に撮影フィルム等をマスコミに売ると言う手法で調達しました。柳田氏のビジネスの1つとして海外映画等の配信業務があった様です。
柳田氏は1932年生まれ。熊類62頭、エゾ鹿92頭、猪&本州鹿等69頭となっていますが、本文記載内容や更に後述の理由から信憑性はかなり低そうです。表紙の動物は体重僅か55kgの貧弱なピューマ、どうしてこれが選ばれたのか、一方で構えている銃は象撃ち用の水平2連ダブルライフル、そのつもりで見ますとこの辺からもケチが付きそうです。
4.柳田佳久氏の射撃。
4-1.スナップショット。

柳田氏の最初の銃は20歳を待って入手したレミントン740、初期の自動銃のオープンサイト、口径は30-06です。ケンさんも同系の742を愛用しましたが、狩猟用の空気銃で立ち撃ち168点/200点満点、30mの雀の頭と外さなかったその腕を以ってしても、使えるのは精々100mであり、当たらないと言える銃でした。
柳田氏が長らく愛用したのはウェザビーの30-06、アイアンサイトを残した物です。スコープ専用銃が普及する前ですから矢無を得ない部分はありますが、チークピースの合わないスコープ銃ではスナップショットは不可能であると言えます。またケンさんの友人が本銃を使っていましたが、余り出来の良い銃ではないと思いました。
スナップショットやランニングショットをバンバン決めた事になっていますが、これもそう有れたらと言う願望、又はそう言う名人がかつていたのを聞いた事があるのレベルだと思います。本文中にも対ヒグマ戦で発砲直前の銃を叩かれた、ポーラーベア戦では銃を構えても照準が定まらなかったとありますが、ケンさん式のスナップショットでは照準時間はゼロですから、照準が定まらない事も銃を叩かれると言う事もあり得ません。つまり氏はスナップショットが全く出来なかったのです。
柳田氏の射撃を見た事があります。銃を30度位上に向けて肩にツンツンと5~10回ほど行い、やっと肩の位置が決まると頬を強く乗せながら、「ガバッ」と銃を目標に向け、それからスコープで目標を探します。だから照準に長い時間が必要です。アイアンサイトを残した銃ではスナップショットは不可能である事はすでに申しました通りですが、柳田氏の射法ではスナップショット処の話ではなく、一般的な射法の中でも遅い方になります。
4-2.ランニングショット。
ライフル銃1年生の氏の銃はレミントン740のオート,本文記載にある様な200mの走るツキノワグマを撃った事になっていますが、静止の200m射撃にも本銃では無理がありますが、ランニング射撃は出来る筈が無いと思います。ケンさんも愛用しましたが、オープンサイトは実に使い難い銃でした。
ランニング射撃技術はチークピースを調整したスコープ専用銃のH&Kオートと、ガイド猟実戦90日と2000~3000発の試行錯誤の実戦 射撃から得られました。見ていると簡単そうですが、そう簡単には得られる筈が無い技術なのです。
その後のウェザビーボルトでは本文中に、森の中を走るエゾ鹿の200mのランニングで、本来補正不要である筈の落差に付いては触れていますが、最も重要なリードに付きましては単にポストに載せて撃つとありました。
実際に150mゼロインならば200mは落差補正不要です。リードは真横に走る鹿とするなら約2.5m、熊ならもう少し小さくなりますが、リードは動的射撃には絶対に避けて通れない項目となり、ポストに載せて撃ったら絶対に命中しません。つまりランニング射撃は全く理解していない事を自ら証明しているのです。
4-3.迫力負け&恐怖負け。
スナップショット等の問題もありますが、もっとも重要な「迫力負け&恐怖負け対策」はどうしたのでしょう。本州鹿猟では獲物が小さいので起らないのですが、射手より明らかに対戦相手の方がデカいエゾ鹿猟では起ります。
対戦前からすでにその大きさに負けてしまい、足が地に着かない射撃となるのが「迫力負け」です。実例では大藪氏のコーナーでも紹介しましたが、それに陥る確率は残念ながら90%以上です。
約100名のスクールの生徒中、角長80cmのエゾ鹿の超大物を捕獲したのは僅か5名のみ、捕獲成功までの出猟日は平均21日、しかしこれでそのクラスの「迫力負け」を超えられたのではなく、捕獲は全てマグレでした。例外的な1名を除き、その後も「迫力負け」は続き、2頭目の捕獲に成功していない、これが「迫力負け」の対策の難度の高さを物語っています。
ケンさんはこれを乗り越えなければ、アフリカのビッグゲームでも足が地に 着かない射撃となり、本当の成功はあり得ないと思っています。
柳田氏はこれに対して、「迫力負け」も「恐怖負け」も全てが「根性」だと本書で結論付けています。根性であればケンさんも類い稀なハイレベルを持ち合わせているつもりでいましたが、「迫力負け」には何年も悩まされ続けました。
別例ですが、エゾ鹿捕獲数百頭、ヒグマ複数捕獲のベテランハンターと半矢ヒグマの捜索をしましたが、彼らを以ってしても「恐怖負け」状態で捜索は全く役に立たず、発見は全て護衛係のケンさんでした。
反動に身構えて照準がずれ、大幅に精度ダウンのフリンチング、獲物の体格に負けてしまう「迫力負け」、獲物の恐怖に負けてしまう「恐怖負け」等々は、猛獣ハンターの超えなければならない大きなハードルとなりますが、これら3件は共に絶望的に近い難度になります。
それではアフリカ猟の猛獣ハンターは全員がそれをクリアしているのか? そう様な事は全く無く、それを未クリアでもお金さえ出せば、支援射撃や代理射撃等により、安全に獲らせてもらえるシステムになっている、これがアフリカ猟なのです。
4-4.遠射。
ライフル銃が他の銃と比べて最も優れているのが射撃精度です。しかし氏がライフルを取得した1952年時点も現在も弾の弾速やパワーに付きましては特に変わりませんが、しかしその時点のオートでは100mが限界でした。
氏の次の愛銃ウェザビーの30-06なら年代もかなり新しくなり、200mの難度は無く、300mもそれ程の難度ではないと思います。しかしこれを実際に出せる腕前のハンターは100人に1人以下、ケンさんの教えたスクールの100人近い生徒でも300m遠射の成功例はゼロ、これが現実です。
柳田氏は銃の200mや300mの精度に付きましてはかなり詳しく書いておられ、それは概ね正しいと思いますが、仮に射撃場でそれが出せたとしても、これが実戦で出せるかどうかは別問題です。
スクールの生徒でもLB射撃選手がおり、300mで10cmを外さないと豪語していましたが、実戦ではマグレで2頭を捕獲したに過ぎませんでしたが、共に100mで1m前後の誤差がありました。
氏は本文中に銃をしっかり構えないと、撃った時の衝撃で弾が出る前に照準がずれると書いていますが、これも完全な間違い、銃は出来るだけ人間が関与せず、銃だけに撃たせる様にするのが本当の射撃術になります。
4-5.ビッグ5の捕獲。
アフリカ猟の代表格は象、犀、ケープバッファロー、ライオン、豹の5種類でビッグ5と呼ばれます。
氏は象、犀、ケープバッファロー、ライオンを倒し、豹に換えて類似のアメリカのピューマが加わっています。多くの勝負に対する記載はライオンとポーラベアーを除き、詳細に書いて無いのは残念です。
ケンさんもそうですが、多くの読者はビッグ5との死闘?の話を聞きたかったと思います。言い訳的な説明としてこれらのガイド付アフリカ猟は、お金さえ出せば誰にでも出来、本当の醍醐味は単独猟にあるとしています。
しかしライオンの記載は今までの推定技量からすると、信じ難い表記です。
ライオンの20mは決まらず、走って向かって来る状況下で更に2発、それも決まらず、最終的には8mで撃って6mで倒れたとあります。人間のダッシュで50mは7秒程度ですから、ライオンのダッシュで12mは2秒以下しかない筈です。
この状況下は2発目不可の1発勝負の世界です。アイアンサイトのスコープ銃が2秒で3発を撃てるとは絶対に思えません。ガイドの支援射撃3発が絶対に入っている筈です。
4-6.安全装置の取扱い等。
柳田氏は直前装填等や安全装置運用の記載は一切なく、一触即発の銃で猟をしていたと思われ、残念です。捕獲のみが狩猟ではなく、捕獲に拘らない狩猟を楽しみに来たと言う表現は、余りにも言い訳が強過ぎて好みませんが、安全は何よりも大切なのは言うまでもありません。
ボルトアクション銃の安全装置は使い難く、1度完全装填してボルトハンドルをハーフロックの位置まで上げて運用する方法を指示するプロガイドもいました。
国内でも多数見掛けたのは、完全装填後ボルトハンドルを上げた状態で引き金を引きながら、ボルトハンドルをロック位置まで戻すハンターです。これはボルトアクション銃の構造を知らないドシロート、左写真はボルトヘッドですが、撃針を落とした状態では撃針が飛び出たままなのです。ファーイーストの築地氏によれば銃によっては雷管が強く押され100%暴発するそうです。
自動銃の撃針は普段引っ込んでいてハンマーで叩かれた時だけ前進して雷管を付き、また引っ込んだ位置に戻りますが、ボルトアクションの撃針は出たまま固定なのです。築地氏の申す通り、その状態で雷管はかなり強く押され、それだけでも暴発する可能性がかなりあり、そこまで行かなくてもこの状態では完全に一触即発です。この様な運用をしない様にお願い致します。
一般的に安全装置解除や装填には各々それなりの時間が必要であり、目標をスコープに捉えて照準するにはもっと長い時間が必要と考えられています。しかしケンさんのスナップショットでは安全装置解除に要する時間はゼロ、装填する時間は甚だ僅か、スコープに捉え照準するには近距離の場合に限りですが、これも甚だ僅かの時間で済ませられます。正しいスナップショットと安全装置の操作を身に付ける事をお薦めします。
4-7.その他の問題記載。
30-08?:30-06は1906年制定、これに対抗する308は約50年後の1954年制定、30-06の改良版が308であり、パワーこそ5~10%減少しておりますが、命中精度は308の方が明らかに有利です。どちらが優れているかはここに及んで言うまでもありません。わざわざ100年前の旧型を選択する方がおかしいと思います。
308の欠点らしい物と言えば、30-06の様に200grの重量弾頭が使えない事位ですが、時代は軽量高速弾が有利とハッキリ方向性を示していますから、欠点とは言い難い項目になります。
柳田氏の初ライフルのレミントン740の取得は308デビュー以前ですから必然的に30-06になります。次のウェザビーボルト取得時は308があった筈ですから、308の選択が正しかったのですが、再び30-06を選択しました。
それ自体は前例が少なく矢無を得ない感はありますが、だからと言って308を30-08と記載するのは、少なくとも1992年の本誌の編集校正時には必ず修正されなくてはなりません。最もStd的なカートリッジである308を知らない様では銃を語るライターの資格は無いと思います。
当時、巷のドシロート達は30-06に対し308を30-08と呼んでいましたが、柳田氏もそのレベルだったのかも知れません。また1970年代よりエゾ鹿猟がブームになり、30-06か308の選択と、マグナムの必要性に付いてが話題になっていましたが、これに付いての記載は全くありません。口径選択はエゾ鹿猟を目指そうとする当時の多数の読者の最重要テーマであり、ライタ―として書かなければならなかったテーマだった筈です。
1952年のレミントン740で200m射撃とランニング射撃:本項でも触れていますが、この時代の30-06のオートは精度的にも200mの能力はなく、オープンサイトでは200mの鹿は静止でも小さ過ぎて照準出来ません。ましてライフル1年生が200m先のランニングを当てられる筈がありません。
レミントン740は100mが限界でしたが、同時期のオートでもスコープを使えばブローニングには150mの能力があり、45年後の1990年代後半のH&Kには250mの能力がありました。
写真の2重使用:同じヒグマの写真が説明文の体重200kgと300kgを変えて複数回使用されています。ケンさんは6頭しか捕獲しておりませんから偉そうな事は言えませんが、周囲の枝葉まで同じ状態で別ヒグマはあり得ません。読者を騙すのもイイ加減にしなさいと言えます。またヒグマの野性生態写真として紹介されているのは、黒1色で鼻ツラが白い事からアメリカクロクマの可能性がかなり高いと思います。
もちろん黒いヒグマはいます。ケンさんの捕獲した6頭中2頭がそれでした。また鼻ツラが白っぽいヒグマも居るかも知れませんが、ケンさんは各地の資料館の剥製や資料を含めて見た事がありません。
ヒットポイントの説明がない:倒したと言う表記の中にヒットポイントの説明がなく、またヒットした時のショック 症状に付いても記載がなく、この面からも怪しい気がします。
200m超えはソリッド弾?:ソリッド弾は無垢の弾です。鉛弾は骨や硬い皮膚にヒットすると鉛が四散し、至近距離の高速弾ではヒットすると表面爆発をして機能を失う欠点があります。ソリッド弾はそうならない様にした弾頭で、昨今のエゾ鹿猟ではお馴染みのバーンズ弾頭もそう言う対策を目的としたカッパーソリッド弾です。この当時のソリッド弾は現在のバーンズ弾の様に先が開かず、そのままの形で突き抜けます。
そのまま突き抜ける事で言えば軍用のFMJ弾があります。安い練習弾は多くがこれであり、ケンさんは初期の頃ですがある時に弾切れになり、このFMJでエゾ鹿を撃った事があります。その結果は良い所にヒットした時の即倒率は変わりませんが、着弾位置が少しずれると情けない程に逃げられてしまう事もありました。
そんな事から多少命中率が良いからと言って、どうして柳田氏が200mのエゾ鹿撃ちやヒグマ撃ちに未回収の出易いソリッド弾を使うのか、多分分かっていないだけと思いますが、その真意は全く分かりません。
2種類の弾を準備:弾と銃の相性は重要な問題です。それによる誤差は無視出来ない程の量になります。リロードで市販弾より高精度を目指す手法は当時まだある程度有効でしたが、しかし弾種が複数では各々に対しそれ様の照準をしなければなりません。
スクールにも近射用と遠射用の複数弾を用意し、何人もが理想を追求しようとしましたが、通常の人間はここ1番の時に冷静にそれに対応出来ず、遠近用の2種の弾の使い分やヒグマ用だけの重量弾頭が有効に機能した事は唯の1度もありません。
実戦時は異常心理状態にあり、頭は殆ど回転せず、どの様な能書きも注意書きも全て無効になってしまいます。遠射はライフルハンターの夢ですが、実戦ではその機会は非常に少なく、運用機会の多い100~150mを何時も直撃射撃で安心出来る、150mゼロインがベストです。100m前後では約2cm程上を飛び、200mでも落差は5cm以内、射撃ミスの原因のトップが落差補正の不安である事を考えますと、昨今のバーンズ銅弾頭1種で何時も直撃射撃のメリットは計り知れない程の物になります。
遠射をバッチリ決めたい想いから、300mゼロインにする人が多くいます。300mを直撃出来るメリットはあり、400m時の落差補正も大幅に少なく出来ますが、その運用機会は極めて稀であり、また元々300mは余り当てられるモノではありません。一方300mゼロインでは多用する100~150mで15cmマイナス側に補正しなければなりません。このマイナス補正を忘れて撃ち頃の距離のチャンスを棒に振るのを多数見て来ました。
パーティション:これに付きましても酷い間違いが書かれていました。鉛弾は骨等にヒットすると鉛が四散し、至近距離では高速弾の場合は表面爆発で機能を失う欠点がある事は先にも書いた通りです。通常のフィールドゲームではソリッド弾までの必要性はありません。
鉛が四散し易い様なシーンになっても、弾頭の後半が残る様にジャケット中央部を強化した物がパーティションであり、更にそれを完全独立にした物がAフレームです。柳田氏曰く、パーティションはヒットにより2つに千切れ、威力を増すとしておられますが、勿論大間違いです。
200kgのエゾ鹿?:エゾ鹿は繁殖期になりますとその方面が忙しく、絶食状態になりますのでかなり大きく 見える個体でも実測してみると130kg前後でした。ケンさんは特に大き目の個体を10回ほど実測してみましたが、通常の大物は150kgにかなり満たないのが普通です。西興部猟区では繁殖期前の10月に170kgの個体が捕獲されたそうですが、これが通常の最大であると思います。
超大物をメインターゲットとして大物が多い平野部で1050頭を捕獲したケンさんが150kg越えは1度も無いのに、山岳猟の小柄な92頭捕獲の柳田氏が200kgのエゾ鹿を捕獲出来る可能性は限りなく低いと思われます。
20mのライオンにあり得ない追加3発: ライオンは12mを2秒以下でダッシュします。
ケンさんのスナップスイング連射は自動銃より速いのですが、それでも3発は絶望的不可能、2発目が撃てるかどうかの瀬戸際です。この場合は客がヤバいと見てガイドとアシスタントが相次いで発砲したと思われます。柳田氏の射撃技術なら追加1発が出来るかどうかになり、出来たとしてもダメ元射撃に留まると思います。
元々デンジャラスゲームは1発勝負の世界であり、客がヤバいと見た時は、ガイドとアシスタントの2人が相前後して水平2連のダブルライフルで支援するシステムになっています。全てのデンジャラスゲームはそう言う、アシスト体制の下で安全に勝負するのがデンジャラスゲームの普通のやり方です。これを1人でやり遂げたと書くのは、心臓に強力な毛が生えているか、余程のドシロートライターかになります。
白糠の湯井ガイド:湯井さんは道東の白糠でエゾ鹿の巻狩り民宿を経営し、自らが勢子とガイドをしていました。ケンさんも1993年から3シーズンお世話になり、当時のエゾ鹿猟に於いて最初の目標とする人でした。その湯井さんが1992年頃、3日連続で林道を1人で歩いている男がいたので、話し掛けてみたそうです。
結果から言えば、それが柳田氏であったのですが、氏曰く「ここは鹿が多いと聞いて来たのですが、1週間が 過ぎても1度も鹿に会えない」と言う事でした。湯井氏は柳田氏に良かったらガイドしましょうか? と申し入れたそうです。鹿に出会えなかったらガイド料は不要ですと言う条件で、3日ガイド猟を行い、数頭を捕獲させたそうですが、湯井氏が言うには柳田氏はハンターとしては3流であり、単独で獲れる筈が無いと言う事でした。
柳田氏と湯井氏の出会いは著書「ライフルハンター」を1冊置いて行ったそうですから、ライフルハンター出版の1992年と思われます。柳田氏は道東白糠の狩猟小屋の取得が1989年、本当の単独猟はそこから始まった様ですが、ケンさんも1993年から湯井さんの所にお世話になりましたが、柳田氏には会えておらず、湯井氏も以後は1度も見掛けなかったそうです。
小屋の取得年度と湯井氏に出会ったのは多少ずれがありますが、言える事は道東白糠の単独猟の期間は非常に僅かだった様であり、且つ成果は上がらず早期撤退に終わった様です。
大物猟は只々歩き廻っても出会えず、出会えなければ勉強にならず、その為にはグループ猟またはガイド猟で勉強しなければなりません。ケンさんも13年間本州鹿の巻狩りで勉強し、10頭弱を獲らせて戴き、エゾ鹿猟でも3シーズンのガイド猟を行い、多数を獲らせて戴き、生態の勉強が出来ました。
柳田氏も39年中の10数年はグループ猟で教わったと書いており、その後はずっと単独猟と書いておられます。しかし末期の白糠の狩猟小屋でも成果を上げられず、早期に撤退した様ですから、書物全体に?が付きます。
柳田氏の想い:「ライフルハンター」の後書きで氏はこう語っています。
アフリカ猟やアラスカ猟はお金(サラリーマンの年収の比ではないかなりの高額)と暇(1~2カ月とかなり長期)と体力(並の上クラス以上)があれば、誰にでも出来、本当の狩猟の醍醐味は単独猟にあると述べていますが、本当はその単独猟が彼自身の本当の憧れだったのではないでしょうか。そんな気がします。
もう一方の誰でも出来るアフリカ猟にはケンさんも同感で、アフリカ猟が夢である人はとにかく行くべきです。お手軽1週間1式が100万円程度、且つイージー射撃コースもあり、行けば何とかなります。しかしビッグトロフィー勝負の難度は高く、ケンさんのクドゥ猟は通常の遠射の限界を超えた380mの遠射の速射を要しました。
ケンさんのアフリカ猟は予算の関係でデンジャラスゲームの対戦は無く、アンテロープ類のみで終わりました。氏の部屋には各種剥製がありますが、数種類のデンジャラスゲームを除けば、何れもケンさんのトロフィーとは比較にならない様な貧弱な物ばかりでした。ケンさんのデンジャラスゲームは北海道のヒグマ450kg、氏のポーラーベアとは概ね同サイズ、こちらは完全な単独猟であり、別のヒグマでは出会い頭の15m、幸いにも両者に対し、臆する事なく速やかに対処出来ました。
ノンフィクション?:湯井氏の話と上記各項と合わせますと「ライフルハンター」はノンフィクションではなさそうだと言うのが自信を 持った結論ですが、ケンさんのバイブルと言うか、憧れだった時代もある程の立派な小説であったと言えます。
著者本人が大活躍したドギュメンタリ―ではなく、架空の主人公が大活躍する、小説にすれば良かったのでは ないかと思われます。世の中の名人ハンターは稀にいてもそれを上手く表現する能力が無く、一方で表現能力を持ったハンターにはその狩猟力が大幅に不足するのが常ですが、ケンさんはその中間辺りかと思われます。
何はともあれ、エゾ鹿猟は本当に魅力ある狩猟でチャレンジする価値は十分にあり、男ならヒグマ猟も一生に1度は勝負したい物です。日本の狩猟環境は抜群ですが、ガイドレス単独猟は誰でも出来る訳ではありません。
昨今は腕の良いハンターは駆除で生計を立て、ガイドをしなくなりました。その結果ガイドは3流ばかりとなり、他所で3連続計9日間捕獲ゼロだった生徒や、同じく小物数頭のみの生徒が多数スクールに来ましたが、全員が下写真の様な持ち帰りが出来ました。獲らせる能力のない3流ガイドが多くなった事は嘆きです。

左写真:一生に1度は勝負したい超大物エゾ鹿ですが、これこそ体重記録更新かと
思われた超大物も実測は140kgでした。
右写真:スクール生徒の平均的持ち帰り状況です。スクールの後半の名称は5205、1日平均
5回の出会いがあり、平均2頭の捕獲があり、内0.5頭が大物、これが平均実績、別の
データでは出会いの70%が3段角の成獣オス、20%が大物、5%が超大物でした。
左下写真:フィーバーの日に会えれば、そして迫力負けしなければ、超大物を束にして帰れます。
右下写真:11月初旬の2週間を出撃すればヒグマ勝負も可能です。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その3:ボウハンティングは高効率。
エゾ鹿のボウハンティング。その2:アメリカの現状と射程距離の変化。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その1:ハーフライフル。
皆さんに伝えたい事。その14と15:ライフルと散弾の特殊効果。
皆さんに伝えたい事。その12と13:エゾ鹿の習性、ナンバーランキングのオス。
皆さんに伝えたい事。その11,難しいエゾ鹿猟。
エゾ鹿のボウハンティング。その2:アメリカの現状と射程距離の変化。
エゾ鹿ボウハンティングの可能性。その1:ハーフライフル。
皆さんに伝えたい事。その14と15:ライフルと散弾の特殊効果。
皆さんに伝えたい事。その12と13:エゾ鹿の習性、ナンバーランキングのオス。
皆さんに伝えたい事。その11,難しいエゾ鹿猟。