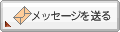2020年03月28日
日本軍の弾薬系統
WW2は何処の国も独自の弾薬で戦いました。
全て口径は7.7mmクラス、アメリカは30-06と30カービン、イギリスは303ブリティッシュ、ドイツは7.92モーゼル、ロシアは7.62x54R、当然ですが陸海空軍の口径は同一でした。
それに対する日本軍には5種類がありました。そしてこれらが全体数量としても著しく不足し、更にせっかく補充があっても使えない弾薬では話にもなりません。
6.5mmの38式(6.5 x 51SR)
7.7mmの92式(7.7 x 58SR)
7.7mmの99式(7.7 x 58)
7.9mm(7.92 x 57)モーゼル
7.7mm(7.7 x 56R)の303ブリティッシュ
陸軍は6.5mmの38式(6.5 x 51SR)を主力でWW2が始まりましたが、途中で威力不足を感じ7.7mmの99式(7.7 x 58)を追加、それに鹵獲したチェコ兵器と航空機の後席対空機銃に使う7.9mm(7.92 x 57)モーゼルの3系統でした。
主力小銃や機関銃だけでも2系統ですから話にならず、アメリカのサブ口径30カービン体制とはまるで違います。
更に日本軍の混乱を広げたのは7.7mm弾はリム以外同寸のリムレスの99式とセミリムド(機関銃用)の92式があり、更に機関銃用には特別製の減装弾がありましたから話は非常に厄介になります。フィリピンで永らく戦いを続けた小野田少尉は99式小銃でしたが、弾薬が切れ機関銃用の92式のリムを削って運用していたそうです。
海軍の陸戦隊は概ね陸軍と同装備ですが、機関銃の弾は陸軍と同じ92式7.7mmではなく、何とイギリス軍と同じ7.7mmの303ブリティッシュでした。
これでは補充の混乱は必須、仮に勝てる戦いであっても勝てません。
何故機関銃用の減装弾が特別に必要なのか?
それは日本の鉄が貧弱だったからです。銃には鉄ではなく鋼が使われます。
鋼は鉄の合金に熱処理をした物ですが、ベースの鉄の純度が99.99%以上でないと希望の硬さと強度の合金が出来ないのですが、日本はこれが出来ず、出来上がった鋼の品質はバラバラでした。
機関銃自体は外国で実績のあるタイプなのですが、日本の鋼材はオリジナル強度が出せず、標準弾ではすぐに強度不足で銃が壊れてしまいました。減装し過ぎると機関銃は回転せず、専用減装弾でゴマかしていたのですが、弾薬の種類が多過ぎて希望通りの補充が受けられず、戦地での日本の機関銃は何時も弾薬不足と弾薬が合わない不調の中にありました。
同様に典型的な例に陸軍の戦闘機である飛燕のエンジンがあります。
ドイツのメッサーシュミットと同じダイムラーのエンジンなのですが、ドイツでは快調に飛んでいるのに、日本製エンジンの飛燕はまともに飛べませんでした。これも同じ理由によります。
この点ではイギリスの戦闘機であるスピットファイアーのロールスロイスのマーリンエンジンをライセンス生産したアメリカのパッカードマーリンエンジンのP‐51マスタング戦闘機は立派に飛びました。またアメリカのB17フォトレス爆撃機はWW2開戦時からすでにターボチャージャーを実用化していましたが、日本ではずっと研究室レベルから出られませんでした。
これも同様のベース鉄の精度が原因です。
陸軍と海軍の共通性の欠落や、弾薬の統一等、勝利の為には当り前の事が実行されませんでしたが、結論として日本人は「全体効率を考える能力が欠落している」様です。
尚、WW2後、西側諸国は全てNATO弾の308に統一しました。
しかし主力弾はベトナム戦から223が追加となり、308の2本立となりましたのは御存知の通りです。
全て口径は7.7mmクラス、アメリカは30-06と30カービン、イギリスは303ブリティッシュ、ドイツは7.92モーゼル、ロシアは7.62x54R、当然ですが陸海空軍の口径は同一でした。
それに対する日本軍には5種類がありました。そしてこれらが全体数量としても著しく不足し、更にせっかく補充があっても使えない弾薬では話にもなりません。
6.5mmの38式(6.5 x 51SR)
7.7mmの92式(7.7 x 58SR)
7.7mmの99式(7.7 x 58)
7.9mm(7.92 x 57)モーゼル
7.7mm(7.7 x 56R)の303ブリティッシュ
陸軍は6.5mmの38式(6.5 x 51SR)を主力でWW2が始まりましたが、途中で威力不足を感じ7.7mmの99式(7.7 x 58)を追加、それに鹵獲したチェコ兵器と航空機の後席対空機銃に使う7.9mm(7.92 x 57)モーゼルの3系統でした。
主力小銃や機関銃だけでも2系統ですから話にならず、アメリカのサブ口径30カービン体制とはまるで違います。
更に日本軍の混乱を広げたのは7.7mm弾はリム以外同寸のリムレスの99式とセミリムド(機関銃用)の92式があり、更に機関銃用には特別製の減装弾がありましたから話は非常に厄介になります。フィリピンで永らく戦いを続けた小野田少尉は99式小銃でしたが、弾薬が切れ機関銃用の92式のリムを削って運用していたそうです。
海軍の陸戦隊は概ね陸軍と同装備ですが、機関銃の弾は陸軍と同じ92式7.7mmではなく、何とイギリス軍と同じ7.7mmの303ブリティッシュでした。
これでは補充の混乱は必須、仮に勝てる戦いであっても勝てません。
何故機関銃用の減装弾が特別に必要なのか?
それは日本の鉄が貧弱だったからです。銃には鉄ではなく鋼が使われます。
鋼は鉄の合金に熱処理をした物ですが、ベースの鉄の純度が99.99%以上でないと希望の硬さと強度の合金が出来ないのですが、日本はこれが出来ず、出来上がった鋼の品質はバラバラでした。
機関銃自体は外国で実績のあるタイプなのですが、日本の鋼材はオリジナル強度が出せず、標準弾ではすぐに強度不足で銃が壊れてしまいました。減装し過ぎると機関銃は回転せず、専用減装弾でゴマかしていたのですが、弾薬の種類が多過ぎて希望通りの補充が受けられず、戦地での日本の機関銃は何時も弾薬不足と弾薬が合わない不調の中にありました。
同様に典型的な例に陸軍の戦闘機である飛燕のエンジンがあります。
ドイツのメッサーシュミットと同じダイムラーのエンジンなのですが、ドイツでは快調に飛んでいるのに、日本製エンジンの飛燕はまともに飛べませんでした。これも同じ理由によります。
この点ではイギリスの戦闘機であるスピットファイアーのロールスロイスのマーリンエンジンをライセンス生産したアメリカのパッカードマーリンエンジンのP‐51マスタング戦闘機は立派に飛びました。またアメリカのB17フォトレス爆撃機はWW2開戦時からすでにターボチャージャーを実用化していましたが、日本ではずっと研究室レベルから出られませんでした。
これも同様のベース鉄の精度が原因です。
陸軍と海軍の共通性の欠落や、弾薬の統一等、勝利の為には当り前の事が実行されませんでしたが、結論として日本人は「全体効率を考える能力が欠落している」様です。
尚、WW2後、西側諸国は全てNATO弾の308に統一しました。
しかし主力弾はベトナム戦から223が追加となり、308の2本立となりましたのは御存知の通りです。
Posted by little-ken
at 21:59
│銃と弾