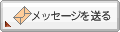2024年12月05日
6.超高難度な戦闘機の射撃。
飛行機がまっすぐ飛ぶ前提ならその射撃は普通の動的射撃の難度に留まります。
しかし実際の単発プロペラ戦闘機は巡航速度以外では真っすぐ飛べないのです。
飛行機のプロペラ後流と言うのは激しくネジれており、これが方向舵を横に押す為、プロペラ飛行機は真っすぐ飛べないのです。
飛行機は巡航速度時に真っすぐ飛ぶ様に、エンジン取付けの軸線も方向舵の軸線も真っすぐではなく、また大きなプロペラ反力と釣合う様に、全てが少しですが非対称に作られています。
従って長距離移動する時は必ず巡航速度で飛びます。そうでないとコンパスで目的地に向かえないのです。
エンジンを強く吹かしていれば、プロペラ反力やプロペラ後流の横に押す力の方が勝り、離陸時浮揚直後の飛行機は15度位斜めに進みます。
速度が上がるに連れて多少真直ぐ寄りになり、巡航高度に達し、スロットルを巡行に緩めると真っすぐ飛ぶ様になります。
反対にエンジンを絞って降下する時は機体側が勝り、反対方向を向いてしまいます。
ケンさんも戦闘機型練習機を操縦して来ましたが、離陸浮揚直後の機体は補正しなければ30度程滑走路からズレて飛行してしまいます。
また反力に逆らって旋回する時と、反対側の旋回は2倍以上の特性差がありました。
急降下時は測定していませんが、その反対側に概ね同程度向くと思われます。
一方戦闘機の機銃は飛行機の正しく前方に向けて取り付けられています。
上下方向は機体の軸線ではありませんが、飛行速度によって飛行機の姿勢は変わります。
練習機で模擬空戦をした事がありますが、照準を合わせるには1発修正で安定させても約2秒、微修正を加えれば更に数秒を要し、飛行機はその間に150m/秒も進みます。
同方向なら多少時間はありますが、対向時は1秒で目前になり、多くは照準合わせし切れない内に、衝突しない様に離脱操作をしなければならなくなります。

また多くは急降下で速度を増しながら接敵照準射撃しますが、巡航速度より相当速く、飛行機は斜め飛行し、その度合いは刻一刻と変化します。
飛行機を敵機に真直ぐ向けても、斜め飛行では命中しません。しかもその度合いは速度と共にドンドン変わるのです。
弾は照準点に向かわず、照準は真直ぐでも100m先では相当ズレ、失中となります。
また激しく動き廻る飛行機同士が接触しない為には、数百mのクリアランスが必要で、100m射撃は同方向時以外に照準は有り得ず、射撃開始は要落差補正の500m以遠となり、200mで射撃を終り離脱します。
その1~2秒間に照準&修正が出来る、或いは予め敵機の飛行コースを読み、事前に照準コースに前以って自機を持って行ける天才だけが墜とせるパイロットと言えました。
狩猟で言えば、スナップショット能力を持たない人が、出会い頭の鹿や走る鹿に発砲する様な物でした。戦闘機の空戦中は実質的に照準は不可能レベルでした。

また補正項目が多過ぎ対処不能であり、訓練場の動かない静止標的でも命中させる事は至難でした。以後照準機は見易い光像式となりましたが、補正が容易になった訳ではありません。
結局戦闘機の墜とせる射撃は例外的少数の天才パイロットはに限られます。
その少数の国宝級の人が国運を握っているのです。
新人パイロットの養成に5年を要し、1人前のパイロットになるには10年を要しますが、墜とせるパイロットはその中の例外的少数に限られるのです。
撃たれた側から言えば、ミシンで縫った様な一直線等間隔の被弾にはならず、まばらな被弾或いは穴だらけになります。ジェット機は丈夫で、数百発の被弾でも帰投出来た機もあったそうです。
戦闘機の射撃は高難度過ぎ当たらないので、操縦桿を上下左右絶妙にシャクっていたパイロットもいたそうです。勿論ラッキーショット以外撃墜出来ませんが、それでもエースになった人もいた様です。
WW2時代でも5項末の記載の様に好条件で撃っても、弾間隔は広がり過ぎ、撃墜に至りません。
その為にジェット時代の米軍は20㎜炸裂弾100発/秒のバルカン砲x1に発展、多くは1000発(F16は500発)、EUでは数発で撃墜出来る、30㎜炸裂弾当初15発/秒、現在は30発/秒のアデン砲x2に発展、2丁計で300発です。
現在の戦闘機は正味射撃可能時間5~10秒です。
尚ジェット機はケンさんも操縦を体験しましたが、プロペラ機の様な非対称の空力特性は無く、操縦し易い=照準し易く、弾は飛行に対し真直ぐに飛んでくれる様です。
狙い越しは自機のGと相手機の予想コースからコンピューターが決めてくれ、照準器のリングが緑色に変わっている間に相手機を捉え、撃てば命中しますが、その直後に新たな機動が加われば失中します。
ケンさんも実戦狩猟では類稀なランニング射撃の名手になりましたが、初めての20mを走る本州鹿に向けたスラグ弾射撃は、リードが合わず全弾失中でした。
しかし実際の単発プロペラ戦闘機は巡航速度以外では真っすぐ飛べないのです。
飛行機のプロペラ後流と言うのは激しくネジれており、これが方向舵を横に押す為、プロペラ飛行機は真っすぐ飛べないのです。
飛行機は巡航速度時に真っすぐ飛ぶ様に、エンジン取付けの軸線も方向舵の軸線も真っすぐではなく、また大きなプロペラ反力と釣合う様に、全てが少しですが非対称に作られています。
従って長距離移動する時は必ず巡航速度で飛びます。そうでないとコンパスで目的地に向かえないのです。
エンジンを強く吹かしていれば、プロペラ反力やプロペラ後流の横に押す力の方が勝り、離陸時浮揚直後の飛行機は15度位斜めに進みます。
速度が上がるに連れて多少真直ぐ寄りになり、巡航高度に達し、スロットルを巡行に緩めると真っすぐ飛ぶ様になります。
反対にエンジンを絞って降下する時は機体側が勝り、反対方向を向いてしまいます。
ケンさんも戦闘機型練習機を操縦して来ましたが、離陸浮揚直後の機体は補正しなければ30度程滑走路からズレて飛行してしまいます。
また反力に逆らって旋回する時と、反対側の旋回は2倍以上の特性差がありました。
急降下時は測定していませんが、その反対側に概ね同程度向くと思われます。
一方戦闘機の機銃は飛行機の正しく前方に向けて取り付けられています。
上下方向は機体の軸線ではありませんが、飛行速度によって飛行機の姿勢は変わります。
練習機で模擬空戦をした事がありますが、照準を合わせるには1発修正で安定させても約2秒、微修正を加えれば更に数秒を要し、飛行機はその間に150m/秒も進みます。
同方向なら多少時間はありますが、対向時は1秒で目前になり、多くは照準合わせし切れない内に、衝突しない様に離脱操作をしなければならなくなります。
また多くは急降下で速度を増しながら接敵照準射撃しますが、巡航速度より相当速く、飛行機は斜め飛行し、その度合いは刻一刻と変化します。
飛行機を敵機に真直ぐ向けても、斜め飛行では命中しません。しかもその度合いは速度と共にドンドン変わるのです。
弾は照準点に向かわず、照準は真直ぐでも100m先では相当ズレ、失中となります。
また激しく動き廻る飛行機同士が接触しない為には、数百mのクリアランスが必要で、100m射撃は同方向時以外に照準は有り得ず、射撃開始は要落差補正の500m以遠となり、200mで射撃を終り離脱します。
その1~2秒間に照準&修正が出来る、或いは予め敵機の飛行コースを読み、事前に照準コースに前以って自機を持って行ける天才だけが墜とせるパイロットと言えました。
狩猟で言えば、スナップショット能力を持たない人が、出会い頭の鹿や走る鹿に発砲する様な物でした。戦闘機の空戦中は実質的に照準は不可能レベルでした。
また補正項目が多過ぎ対処不能であり、訓練場の動かない静止標的でも命中させる事は至難でした。以後照準機は見易い光像式となりましたが、補正が容易になった訳ではありません。
結局戦闘機の墜とせる射撃は例外的少数の天才パイロットはに限られます。
その少数の国宝級の人が国運を握っているのです。
新人パイロットの養成に5年を要し、1人前のパイロットになるには10年を要しますが、墜とせるパイロットはその中の例外的少数に限られるのです。
撃たれた側から言えば、ミシンで縫った様な一直線等間隔の被弾にはならず、まばらな被弾或いは穴だらけになります。ジェット機は丈夫で、数百発の被弾でも帰投出来た機もあったそうです。
戦闘機の射撃は高難度過ぎ当たらないので、操縦桿を上下左右絶妙にシャクっていたパイロットもいたそうです。勿論ラッキーショット以外撃墜出来ませんが、それでもエースになった人もいた様です。
WW2時代でも5項末の記載の様に好条件で撃っても、弾間隔は広がり過ぎ、撃墜に至りません。
その為にジェット時代の米軍は20㎜炸裂弾100発/秒のバルカン砲x1に発展、多くは1000発(F16は500発)、EUでは数発で撃墜出来る、30㎜炸裂弾当初15発/秒、現在は30発/秒のアデン砲x2に発展、2丁計で300発です。
現在の戦闘機は正味射撃可能時間5~10秒です。
尚ジェット機はケンさんも操縦を体験しましたが、プロペラ機の様な非対称の空力特性は無く、操縦し易い=照準し易く、弾は飛行に対し真直ぐに飛んでくれる様です。
狙い越しは自機のGと相手機の予想コースからコンピューターが決めてくれ、照準器のリングが緑色に変わっている間に相手機を捉え、撃てば命中しますが、その直後に新たな機動が加われば失中します。
ケンさんも実戦狩猟では類稀なランニング射撃の名手になりましたが、初めての20mを走る本州鹿に向けたスラグ弾射撃は、リードが合わず全弾失中でした。
Posted by little-ken
at 08:50