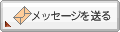2022年07月30日
マタギ資料館。
かねて念願だった阿仁のマタギ資料館に行って来ました。建物外観からかなり期待が 持てそうだったのですが、展示部分は全体の僅か1/4程度でした。入り口にはクマの親子連れとの剝製と村田銃モドキが出迎えてくれます。銃を手に写真撮影が可能です。


1.マタギ時代の定義。
マタギは東北地方を中心に各地に集団がありました。マタギの時代の定義は、古くは江戸時代以前に遡り、先込め火縄銃を使いました。
その前は槍や弓を使っており、その歴史は400年に及ぶそうです。
1880年(明治13年)射程20mの村田銃がデビューするや、銃は急速にこれに置き換わりました。そして1950年頃から銃は元折れ単発銃が部分的に入り、1960年頃までには水平2連銃に置き換わり、集団マタギの時代は概ね終わりました。
この1880~1960年までの村田銃が主役の頃が、真のマタギ時代と言えました。
その後は1965年頃から50m射撃を可能とする自動銃や新しいスラグ弾が入り始め、1970年頃にはこれに換わりました。ライフル銃も同時に入り始め、高性能な銃器の出現はマタギ組織の崩壊を早めました。
2.展示銃。
マタギ資料館の銃の展示は、6丁の火縄銃に加え20番村田猟銃が1丁、12番元折れの 単発銃が2丁展示されているのみでした。3番目の元折れ銃は先台を紛失しています。 村田銃の前は火縄銃であったのは事実ですが、末期にはパーカッション式や村田式に 改造された火縄銃も活躍した筈ですが、その展示は皆無でした。

展示火縄銃6丁は全て純火縄銃ばかりですが、火縄銃も村田銃も右側にアクションが付いていますから、展示方向が反対なのも気になる所です。
12番の元折れ単発銃はマタギ時代の末期ですから、現在の展示では火縄銃の時代から、末期の元込め単発銃の時代に飛んでおり、主流だった村田銃の時代が僅か1丁で、殆ど抜けた状態であり、3つに分けたそれぞれに十分な展示があると良いと思いました。
3.弾薬類の展示。

弾薬資材もクマ用の20番丸弾スラグ3個と、クマ猟には使わない散弾だけ、しかもそれが沖鴨用のBB散弾より3クラス大粒の散弾(AAの5㎜クラス)の展示があるのみでした。大根おろし金の様な物は散弾の鋳型と言う事です。右側の3個は弾頭の鋳型です。
3個は口径違いと思われます。中央下の物は薬莢に雷管を取り付ける道具で、その右は ワッズとなるボール紙を打ち抜くポンチですが、12番用の様です。
また写真では僅かに写っている程度ですが、先込め銃用の火薬入れが左端にあり、火縄が 右端にありますが、特に何の説明もないまま、同じケース内に展示されていました。
火縄銃の時代と黒色火薬の時代と無煙火薬の時代の3つに分けると良いと思いました。
4.マタギの装備品。

何時も思うのですが、マタギは末期以外は黒色火薬を使っており、腐食が大の火薬です。後述の映画「イタズ」では家で洗い矢を使っていましたが、マタギは銃の手入れ用品を携帯していなかった様です。
5.散弾の運用。
本来散弾としては1~12号の設定があり、その上に昔は沖鴨を撃つBシリーズ3種(B,BB,BBB)があり、更にその上が雁(ガン)を撃つÅシリーズ3種があります。
更に鹿用には1~4号(16~27粒)のバックショットがあり、その上にはOシリーズの12粒・9粒・6粒があり、そして最後が1粒弾のスラグとなり、12番なら18㎜となり、30番村田では13㎜となります。散弾粒は銃砲店で購入するのが普通でした。
現在では鳥猟用には1~9号まで、その上にBBがありますが、無煙火薬プラスチック薬莢装弾になってからは、弾速がかなり高速化し、射程延長となり、現在の最大狩猟鳥であるカルガモやマガモ用にも2.4㎜粒が400個入った7.5号射撃装弾が最も有効である事が分かり、大粒鳥撃ち装弾を使う人は少なくなりました。
シカ猟用にはバックショット4種がありますが、4号バックショットと言う27粒弾が 最も有効である事も分かり、使う人が増えました。
その上はスラグ弾になりますが丸弾ではなく、風切り羽で自転する構造であり、実用射程はフォスター型で50m、ブレネッキ型では80mとマタギ時代の数倍となりました。


マタギ資料館の弾薬方面の展示では20番真鍮が薬莢1発、12番金属薬莢の25発弾帯だけ、使っていたのは共に黒色火薬とみられますが、マタギの主流と思われていた30番村田の銃や弾薬の展示は皆無でした。
マタギの狩猟対象はクマ、カモシカ、サル、キツネ、タヌキ、アナグマ、野ウサギ、ムササビ、テン、と大から小まで多岐に渡り、そして狩猟方法もその動物の種類毎に数種以上があるのですが、それらの説明は皆無でした。
散弾は中小型動物用と思われますが、それなら直径5㎜の40粒のAA弾より、3㎜の200粒入りの5号弾クラスがベストと言えます。
そもそも幾ら黒色火薬の時代と言え、あのクソ長い銃身は不要と思われます。
この時代にショットガン効果を利用した、小粒弾3粒思想はないと思われますが、それを使う事が出切れば、クマには15~30粒前後の1~4号のバックショットを30インチ前後のフルチョークから撃てば、射程は50mまで有効になります。
中小型動物用にはフルチョークで粒入った5号装弾が50mまで有効となり、やはり散弾銃の最大メリットは散弾を撃てる事にあり、どちらの場合も射程距離&命中率から見ても、小粒散弾を撃つ方が得策と思われます。
6.射撃フォーム。

写真は火縄銃射撃の勇ましい写真ですが、当時の精度から言える射程距離20m程度であり、巻狩りと言う形態を考えると、更に問題ありです。
長射程をライフル銃で撃つ場合なら類似のスタイルもあり、ケンさんもアフリカでは150ⅿの立ち撃ちで多用しました。
しかし当時の火縄銃の射程や精度等からすると射程は20ⅿ、その距離で動的になるかも知れないクマを撃つには手持ちのフリー射撃しか考えられません。
これは多分実猟を知らないライター指示のヤラセ写真だと思われます。
当時の巻狩りでは物陰から、けもの道に銃を向けじっと待機、10~20ⅿまで引き寄せて肝で撃つ時代と思われ、1頭捕獲は当時の年収に匹敵する為、ライターやカメラマンは クマに感付かれない様に射手の遥か後方から見学していた筈で、本当の狩猟の臨場感を体験する事も、射撃シーンを見る事も無かったと思われます。
従ってマタギの風習や装備に関しては、狩猟後の演歌で聞く事が出来、詳細に書けても、マタギの狩猟に付いては誰も書けていません。書かれている狩猟シーンは酒の席で、何度も出る伝説の名人マタギの又聞き、或いは尾ひれの付いた誰かの自慢話に過ぎません。
7.マタギの銃。


左写真は銃床の付いた銃を装備していますが、当時平均の身長155㎝と仮定しますと、 銃の全長は119㎝であり、村田銃より10㎝ほど短い様です。
また右写真からはやや分かり難いですが、拡大しますと銃身が8角形であり、先端まで 全域に先台があり、それで行けば口径18㎜クラスの火縄銃ですが、12番クラスの弾帯をしており、銃種は不明です。

左のマタギグループ写真は大正時代とあり、1912~1926年の間です。1番左の軍服調の男だけは30番前後ですが元折れ単発銃、隣の着物の男は銃を持って おらず、2人はマタギではないと思われます。
多分村の顔役の仲介で、クマの巻狩りに臨時特別参加したものと思われます。
クマは親子と見られますが、3頭連れは珍しいと思います。
他は全員が口径30番かどうか詳細は不明ですが、村田銃を使用しています。
中央の3人以外は余り伝統式な服装ではありません。



写真は1917年(大正6年)とあり、全員マタギ猟装で、4名は村田銃の30番と思われる銃を使用しています。1番右の人だけが民間型の村田猟銃ですが、他の3人は驚いた事に ハーフライフルかどうかは不明ですが、村田軍用銃型を使用しています。
更に中央の人が構えているのは、元折れハンマー式の銃で、説明文にイギリスのグリナー銃とありますが、驚く事に薬莢が著しく細長い事からライフル銃の様です。
1917年のマタギが軍用型村田銃と、ライフル銃を使用していた事には、ケンさんも思いを新たにしました。まだまだ知らない事だらけです。
当時の実際は知る由もありませんが、村田猟銃その物が、村田軍用銃から派生し、軍用と並行生産された事、そして軍用村田銃は30年式や38年式歩兵銃が普及後は散弾銃に改造され、民間に払い下げ販売が行われた事、等々の理由から、軍用と同じ薬莢を使う特別口径の30番村田口径が主流だったと思われます。
元々村田銃に30番が多い理由は、村田軍用弾と同じ薬莢を使う為でしたが、結果的に強力な12番に比べ、火薬消費が半分以下で済む、小口径が好まれた時代背景もありました。その為、経済的ではありますが、30番村田銃はクマ用の猟銃としては非力でした。
8.マタギ映画。




上写真左2枚は1982年に制作されたマタギと言う映画のシーンです。
また右の2枚は1987年に作られたイタズ(熊)と言う映画のシーンです。
前者はもうマタギ文化が殆ど消えた1982年に老マタギが大熊とマタギ式の勝負する映画です。
共に主人公の銃は30番と思われる村田銃、服装等の時代考証も阿仁マタギ保存会が指導しているのでかなり正確と言えます。
2つは共に老マタギが大熊と戦う設定であり、クマの実猟シーンがありました。
但し本来のクマは当然、月の輪熊なのですが、北海道の登別ヒグマ牧場のクマを8頭購入したそうであり、このヒグマによって2本の映画が作られました。
出てくる銃器やその使い方も、クマとヒグマ以上に酷いデタラメでした。
レミントン700風のスコープ付ボルトアクションライフルが、何と秒速3発の連射を行い、空飛ぶヤマドリを撃墜、更に短射程20mである筈の村田銃のハンターが、クマに十字砲火を浴びせており、開いた口が塞がらない状態でした。
巻狩りは何でもそうですが、大きな山を10人程度で囲む訳ですから、隣の射手が見える事は極めて稀です。またライフル銃で鳥を撃つ事もあり得ません。
実際に命中すればヤマドリはバラバラになってしまい、またライフル銃で飛鳥撃墜は不可能です。
ヒグマ射撃シーンも縛られた鎖が見えるシーンがあり、その状態でヒグマが射殺されました。もう少し上手く設定出来ないのかと思いました。阿仁マタギ熊牧場はその時の映画撮影時に購入したヒグマの生き残りを飼育展示したのが発端でした。
マタギの狩猟は火縄銃時代を別にして、1880年(明治13年)頃の村田銃30番から始まり、1960年頃には強力な12番水平2連銃に換わり、村田銃は姿を消しました。
強力な12番への置換わりの始まりは、その村田時代の後盤の中場から、元折れ単発銃として仲間入りして来ました。
9.銃の展示方法。
マタギ資料館の展示銃は、使われなくなって永らく蔵に入っていた火縄銃と、末期に使用された元折れ単発の12番銃が主体となっていました。
この村田銃に始まり、村田銃の消滅までの約80年間が、本格的なマタギの時代と言えました。従って本来資料館では全ての展示物には、年号表示が必要だと思います。
日本刀も火縄銃も、300年以上に渡り大きな進歩無しであった為、年号省略が多い日本の資料館ですが、残念に思います。
高性能な銃器の出現はマタギ組織の崩壊を促し、特に200m以遠の射撃を可能とする、スコープ付ライフル銃を使うマタギは、完全に古い時代のマタギではなくなりました。
10.マタギの槍。
古いマタギの時代には単発銃で動きを止め、槍で止めを刺したと言われています。
この言葉には非常に大きなロマンを感じ、ケンさんもフクロナガサを購入しました。
しかし、実際のクマは即倒し難い動物ですが、弾には意外と弱く、被弾すると即倒しますが、直ちに起き上がり、ケンさんが捕獲したヒグマ6頭中の5頭が被弾後トンズラ、その逃げ足はかなり速く、槍ではとても追い掛けられなかったと思います。
しかし6頭中の4頭は僅か5m以内で死に、走り去った直後の時間で言えば被弾後2秒後には4頭はすでに息絶えて倒れ、槍の使う機会は少なかったと思われます。
11.マタギライターの限界。
マタギを描いた長期取材のドギュメンタリー調の本は多くありますが、取材が可能なのは巻狩りのみでした。忍び猟はシロートが同行した状態では敵に感付かれてしまい、狩猟の成立は難しくなります。マタギの猟には生活が懸かっていますから、そんな取材は受けられず、従って本当のマタギ猟の取材は誰もした事がなく、本当のマタギを描いた本は皆無です。
マタギ資料館の展示物の大クマもヒグマでガッカリしました。
しかしそれは今に始まった事ではなかったのです。
12.東北の動物。
マタギ時代には本州鹿も日本猪も未生息でしたが、現在は青森県に至るまで生息は広がりました。しかしそれは2000年以降であり、まだ生息が少ないのか、本州他地域や北海道でよく見られる様な耕作地のフェンスもなく、動物注意の看板も第1位はクマ、2位タヌキ、3位本州鹿、4位は小差でカモシカでした。




クマ注意の看板も高速道路では普通のクマのシルエットですが、一般道では親子連れのクマでした。そして本州鹿の看板は例によってホワイトテール鹿の看板ですが、クマより遥かに少なく、それと同数程度のカモシカの看板がありました。
クマ猟をする人の減少から、生息数は近年相当増えており、クマの出会いを期待しました。白神山地や男鹿半島、八甲田山や八幡平周辺、奥入瀬渓谷や十和田湖を走りましたが、 野性動物との出会いは残念ながら皆無でした。
知床では観光船に乗るか、観光シーズン以外の知床林道を早朝に走れば、簡単にヒグマやエゾ鹿の野性動物に会えますが、そう言うコースは東北にはないのが残念です。
1.マタギ時代の定義。
マタギは東北地方を中心に各地に集団がありました。マタギの時代の定義は、古くは江戸時代以前に遡り、先込め火縄銃を使いました。
その前は槍や弓を使っており、その歴史は400年に及ぶそうです。
1880年(明治13年)射程20mの村田銃がデビューするや、銃は急速にこれに置き換わりました。そして1950年頃から銃は元折れ単発銃が部分的に入り、1960年頃までには水平2連銃に置き換わり、集団マタギの時代は概ね終わりました。
この1880~1960年までの村田銃が主役の頃が、真のマタギ時代と言えました。
その後は1965年頃から50m射撃を可能とする自動銃や新しいスラグ弾が入り始め、1970年頃にはこれに換わりました。ライフル銃も同時に入り始め、高性能な銃器の出現はマタギ組織の崩壊を早めました。
2.展示銃。
マタギ資料館の銃の展示は、6丁の火縄銃に加え20番村田猟銃が1丁、12番元折れの 単発銃が2丁展示されているのみでした。3番目の元折れ銃は先台を紛失しています。 村田銃の前は火縄銃であったのは事実ですが、末期にはパーカッション式や村田式に 改造された火縄銃も活躍した筈ですが、その展示は皆無でした。
展示火縄銃6丁は全て純火縄銃ばかりですが、火縄銃も村田銃も右側にアクションが付いていますから、展示方向が反対なのも気になる所です。
12番の元折れ単発銃はマタギ時代の末期ですから、現在の展示では火縄銃の時代から、末期の元込め単発銃の時代に飛んでおり、主流だった村田銃の時代が僅か1丁で、殆ど抜けた状態であり、3つに分けたそれぞれに十分な展示があると良いと思いました。
3.弾薬類の展示。
弾薬資材もクマ用の20番丸弾スラグ3個と、クマ猟には使わない散弾だけ、しかもそれが沖鴨用のBB散弾より3クラス大粒の散弾(AAの5㎜クラス)の展示があるのみでした。大根おろし金の様な物は散弾の鋳型と言う事です。右側の3個は弾頭の鋳型です。
3個は口径違いと思われます。中央下の物は薬莢に雷管を取り付ける道具で、その右は ワッズとなるボール紙を打ち抜くポンチですが、12番用の様です。
また写真では僅かに写っている程度ですが、先込め銃用の火薬入れが左端にあり、火縄が 右端にありますが、特に何の説明もないまま、同じケース内に展示されていました。
火縄銃の時代と黒色火薬の時代と無煙火薬の時代の3つに分けると良いと思いました。
4.マタギの装備品。

何時も思うのですが、マタギは末期以外は黒色火薬を使っており、腐食が大の火薬です。後述の映画「イタズ」では家で洗い矢を使っていましたが、マタギは銃の手入れ用品を携帯していなかった様です。
5.散弾の運用。
本来散弾としては1~12号の設定があり、その上に昔は沖鴨を撃つBシリーズ3種(B,BB,BBB)があり、更にその上が雁(ガン)を撃つÅシリーズ3種があります。
更に鹿用には1~4号(16~27粒)のバックショットがあり、その上にはOシリーズの12粒・9粒・6粒があり、そして最後が1粒弾のスラグとなり、12番なら18㎜となり、30番村田では13㎜となります。散弾粒は銃砲店で購入するのが普通でした。
現在では鳥猟用には1~9号まで、その上にBBがありますが、無煙火薬プラスチック薬莢装弾になってからは、弾速がかなり高速化し、射程延長となり、現在の最大狩猟鳥であるカルガモやマガモ用にも2.4㎜粒が400個入った7.5号射撃装弾が最も有効である事が分かり、大粒鳥撃ち装弾を使う人は少なくなりました。
シカ猟用にはバックショット4種がありますが、4号バックショットと言う27粒弾が 最も有効である事も分かり、使う人が増えました。
その上はスラグ弾になりますが丸弾ではなく、風切り羽で自転する構造であり、実用射程はフォスター型で50m、ブレネッキ型では80mとマタギ時代の数倍となりました。
マタギ資料館の弾薬方面の展示では20番真鍮が薬莢1発、12番金属薬莢の25発弾帯だけ、使っていたのは共に黒色火薬とみられますが、マタギの主流と思われていた30番村田の銃や弾薬の展示は皆無でした。
マタギの狩猟対象はクマ、カモシカ、サル、キツネ、タヌキ、アナグマ、野ウサギ、ムササビ、テン、と大から小まで多岐に渡り、そして狩猟方法もその動物の種類毎に数種以上があるのですが、それらの説明は皆無でした。
散弾は中小型動物用と思われますが、それなら直径5㎜の40粒のAA弾より、3㎜の200粒入りの5号弾クラスがベストと言えます。
そもそも幾ら黒色火薬の時代と言え、あのクソ長い銃身は不要と思われます。
この時代にショットガン効果を利用した、小粒弾3粒思想はないと思われますが、それを使う事が出切れば、クマには15~30粒前後の1~4号のバックショットを30インチ前後のフルチョークから撃てば、射程は50mまで有効になります。
中小型動物用にはフルチョークで粒入った5号装弾が50mまで有効となり、やはり散弾銃の最大メリットは散弾を撃てる事にあり、どちらの場合も射程距離&命中率から見ても、小粒散弾を撃つ方が得策と思われます。
6.射撃フォーム。
写真は火縄銃射撃の勇ましい写真ですが、当時の精度から言える射程距離20m程度であり、巻狩りと言う形態を考えると、更に問題ありです。
長射程をライフル銃で撃つ場合なら類似のスタイルもあり、ケンさんもアフリカでは150ⅿの立ち撃ちで多用しました。
しかし当時の火縄銃の射程や精度等からすると射程は20ⅿ、その距離で動的になるかも知れないクマを撃つには手持ちのフリー射撃しか考えられません。
これは多分実猟を知らないライター指示のヤラセ写真だと思われます。
当時の巻狩りでは物陰から、けもの道に銃を向けじっと待機、10~20ⅿまで引き寄せて肝で撃つ時代と思われ、1頭捕獲は当時の年収に匹敵する為、ライターやカメラマンは クマに感付かれない様に射手の遥か後方から見学していた筈で、本当の狩猟の臨場感を体験する事も、射撃シーンを見る事も無かったと思われます。
従ってマタギの風習や装備に関しては、狩猟後の演歌で聞く事が出来、詳細に書けても、マタギの狩猟に付いては誰も書けていません。書かれている狩猟シーンは酒の席で、何度も出る伝説の名人マタギの又聞き、或いは尾ひれの付いた誰かの自慢話に過ぎません。
7.マタギの銃。
左写真は銃床の付いた銃を装備していますが、当時平均の身長155㎝と仮定しますと、 銃の全長は119㎝であり、村田銃より10㎝ほど短い様です。
また右写真からはやや分かり難いですが、拡大しますと銃身が8角形であり、先端まで 全域に先台があり、それで行けば口径18㎜クラスの火縄銃ですが、12番クラスの弾帯をしており、銃種は不明です。

左のマタギグループ写真は大正時代とあり、1912~1926年の間です。1番左の軍服調の男だけは30番前後ですが元折れ単発銃、隣の着物の男は銃を持って おらず、2人はマタギではないと思われます。
多分村の顔役の仲介で、クマの巻狩りに臨時特別参加したものと思われます。
クマは親子と見られますが、3頭連れは珍しいと思います。
他は全員が口径30番かどうか詳細は不明ですが、村田銃を使用しています。
中央の3人以外は余り伝統式な服装ではありません。
写真は1917年(大正6年)とあり、全員マタギ猟装で、4名は村田銃の30番と思われる銃を使用しています。1番右の人だけが民間型の村田猟銃ですが、他の3人は驚いた事に ハーフライフルかどうかは不明ですが、村田軍用銃型を使用しています。
更に中央の人が構えているのは、元折れハンマー式の銃で、説明文にイギリスのグリナー銃とありますが、驚く事に薬莢が著しく細長い事からライフル銃の様です。
1917年のマタギが軍用型村田銃と、ライフル銃を使用していた事には、ケンさんも思いを新たにしました。まだまだ知らない事だらけです。
当時の実際は知る由もありませんが、村田猟銃その物が、村田軍用銃から派生し、軍用と並行生産された事、そして軍用村田銃は30年式や38年式歩兵銃が普及後は散弾銃に改造され、民間に払い下げ販売が行われた事、等々の理由から、軍用と同じ薬莢を使う特別口径の30番村田口径が主流だったと思われます。
元々村田銃に30番が多い理由は、村田軍用弾と同じ薬莢を使う為でしたが、結果的に強力な12番に比べ、火薬消費が半分以下で済む、小口径が好まれた時代背景もありました。その為、経済的ではありますが、30番村田銃はクマ用の猟銃としては非力でした。
8.マタギ映画。



上写真左2枚は1982年に制作されたマタギと言う映画のシーンです。
また右の2枚は1987年に作られたイタズ(熊)と言う映画のシーンです。
前者はもうマタギ文化が殆ど消えた1982年に老マタギが大熊とマタギ式の勝負する映画です。
共に主人公の銃は30番と思われる村田銃、服装等の時代考証も阿仁マタギ保存会が指導しているのでかなり正確と言えます。
2つは共に老マタギが大熊と戦う設定であり、クマの実猟シーンがありました。
但し本来のクマは当然、月の輪熊なのですが、北海道の登別ヒグマ牧場のクマを8頭購入したそうであり、このヒグマによって2本の映画が作られました。
出てくる銃器やその使い方も、クマとヒグマ以上に酷いデタラメでした。
レミントン700風のスコープ付ボルトアクションライフルが、何と秒速3発の連射を行い、空飛ぶヤマドリを撃墜、更に短射程20mである筈の村田銃のハンターが、クマに十字砲火を浴びせており、開いた口が塞がらない状態でした。
巻狩りは何でもそうですが、大きな山を10人程度で囲む訳ですから、隣の射手が見える事は極めて稀です。またライフル銃で鳥を撃つ事もあり得ません。
実際に命中すればヤマドリはバラバラになってしまい、またライフル銃で飛鳥撃墜は不可能です。
ヒグマ射撃シーンも縛られた鎖が見えるシーンがあり、その状態でヒグマが射殺されました。もう少し上手く設定出来ないのかと思いました。阿仁マタギ熊牧場はその時の映画撮影時に購入したヒグマの生き残りを飼育展示したのが発端でした。
マタギの狩猟は火縄銃時代を別にして、1880年(明治13年)頃の村田銃30番から始まり、1960年頃には強力な12番水平2連銃に換わり、村田銃は姿を消しました。
強力な12番への置換わりの始まりは、その村田時代の後盤の中場から、元折れ単発銃として仲間入りして来ました。
9.銃の展示方法。
マタギ資料館の展示銃は、使われなくなって永らく蔵に入っていた火縄銃と、末期に使用された元折れ単発の12番銃が主体となっていました。
この村田銃に始まり、村田銃の消滅までの約80年間が、本格的なマタギの時代と言えました。従って本来資料館では全ての展示物には、年号表示が必要だと思います。
日本刀も火縄銃も、300年以上に渡り大きな進歩無しであった為、年号省略が多い日本の資料館ですが、残念に思います。
高性能な銃器の出現はマタギ組織の崩壊を促し、特に200m以遠の射撃を可能とする、スコープ付ライフル銃を使うマタギは、完全に古い時代のマタギではなくなりました。
10.マタギの槍。
古いマタギの時代には単発銃で動きを止め、槍で止めを刺したと言われています。
この言葉には非常に大きなロマンを感じ、ケンさんもフクロナガサを購入しました。
しかし、実際のクマは即倒し難い動物ですが、弾には意外と弱く、被弾すると即倒しますが、直ちに起き上がり、ケンさんが捕獲したヒグマ6頭中の5頭が被弾後トンズラ、その逃げ足はかなり速く、槍ではとても追い掛けられなかったと思います。
しかし6頭中の4頭は僅か5m以内で死に、走り去った直後の時間で言えば被弾後2秒後には4頭はすでに息絶えて倒れ、槍の使う機会は少なかったと思われます。
11.マタギライターの限界。
マタギを描いた長期取材のドギュメンタリー調の本は多くありますが、取材が可能なのは巻狩りのみでした。忍び猟はシロートが同行した状態では敵に感付かれてしまい、狩猟の成立は難しくなります。マタギの猟には生活が懸かっていますから、そんな取材は受けられず、従って本当のマタギ猟の取材は誰もした事がなく、本当のマタギを描いた本は皆無です。
マタギ資料館の展示物の大クマもヒグマでガッカリしました。
しかしそれは今に始まった事ではなかったのです。
12.東北の動物。
マタギ時代には本州鹿も日本猪も未生息でしたが、現在は青森県に至るまで生息は広がりました。しかしそれは2000年以降であり、まだ生息が少ないのか、本州他地域や北海道でよく見られる様な耕作地のフェンスもなく、動物注意の看板も第1位はクマ、2位タヌキ、3位本州鹿、4位は小差でカモシカでした。
クマ注意の看板も高速道路では普通のクマのシルエットですが、一般道では親子連れのクマでした。そして本州鹿の看板は例によってホワイトテール鹿の看板ですが、クマより遥かに少なく、それと同数程度のカモシカの看板がありました。
クマ猟をする人の減少から、生息数は近年相当増えており、クマの出会いを期待しました。白神山地や男鹿半島、八甲田山や八幡平周辺、奥入瀬渓谷や十和田湖を走りましたが、 野性動物との出会いは残念ながら皆無でした。
知床では観光船に乗るか、観光シーズン以外の知床林道を早朝に走れば、簡単にヒグマやエゾ鹿の野性動物に会えますが、そう言うコースは東北にはないのが残念です。
Posted by little-ken
at 16:25